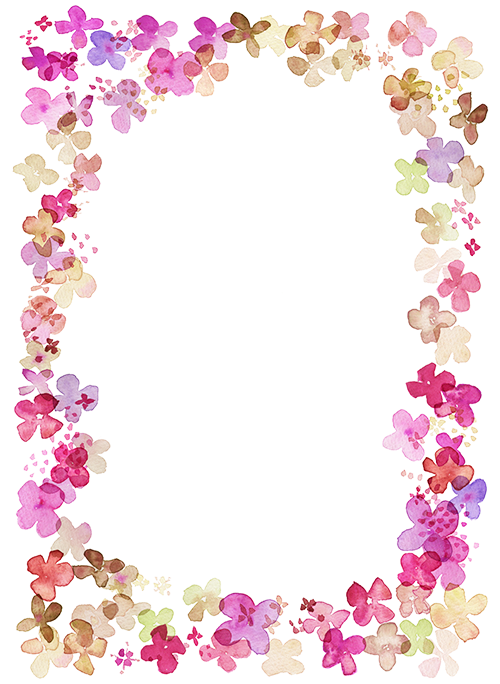「あれっ。珍しい〜。辰野が弁当持ってきてる」
その日の昼休み。朋空が弁当を机に置くと、赤城が笑顔で寄ってきた。
「久しぶりだから、変な奴が邪魔しに来ないよう俺が見張っててやるよ」
「……サンキュー」
ふざけた話だが、本当に昼休みほど声を掛けられる。落ち着いて食べられない状況だったから、食べることも諦めた。
売店に行こうと行くまいと、誰かしらに捕まる。それなら眠って、少しでも体力回復した方がマシだと思った。
腹も鳴らなかったしな。
ついていた割り箸を割り、手を合わせる。
雅月といると腹が鳴るし、何でも新鮮に見える。
可愛くて、明るくて、隣にいるだけで癒される。高校生になっても全く変わらない。
俺の世界そのものだ。
「おお、美味そう〜。辰野の母さん料理上手いんだな」
赤城は顔を覗かせ、蓋を開けた弁当箱を見て目を輝かせた。
彼の言う通り、とても美味しそうな弁当だった。
雅月のやつ、これをひとりで作ったのか。すごいな……。
卵焼きを頬張ると、俺が好きな甘めの味付けだった。
美味い。美味いし、言葉じゃ言い表せないほど幸せだった。
大好きな恋人が、自分の為に作ってくれた。ただそれだけで、天に昇りそうなほど舞い上がっている。
( やばい…… )
食べるのが勿体ない。でも早く放課後が来てほしい。
矛盾した想いを抱え、朋空は額を押さえた。
◇
部活に向かう生徒、家に帰る生徒。
そのどちらでもなく、睡眠をとるために移動する俺。
青春できてるかどうか未だによく分からないけど、とりあえず充実はしている。大好きな恋人と毎日顔を合わせられるから。
「朋空先輩、お疲れ様」
睡眠研究室に入り、雅月は鞄を置いた。笑いかけたものの、やはり今日一日は睡魔との戦いだった。
「俺、横になったら一瞬で眠れそうです」
「そうか。じゃあ早速寝よう。……って言いたいところだけど」
朋空先輩はベッドに座ると、俺の方に向かって手を伸ばした。
多分、「来て」という意味なので目の前まで歩く。すると引き寄せられ、彼と一緒にベッドに倒れた。
「先に言わせてくれ。弁当、やばい美味かった」
「あ! 大丈夫でした? 食べられました?」
「美味すぎて記憶少し飛んだ」
「あははっ。でも、良かった。先輩の好きなもの全然知らないから、完全に俺のチョイスになっちゃったけど」
家族以外にご飯を作ったのは初めて。しかもそれが大好きな先輩の為だから、尋常じゃなく緊張した。
でも、喜んでもらえて良かった。
「もう毎日作ってほしいよ。……大変だから、それは冗談だけど」
そのうち昼で帰るようになるしな、と言って先輩は腰に手を当てた。
そうか。先輩は三年生だから、これからはほとんど午前授業になるんだ。
寂しくなって俯いたが、それも全部仕方のないこと。そして先輩の大事な未来の為だと言い聞かせて、顔を上げた。
「先輩。いつもは無理かもしれないけど、また弁当作ります。次は好きなおかずも作るから。……無理しないでくださいね」
「……ありがと。嬉しい」
彼は弁当が入っていた紙袋を取り出し、子どもみたいに笑った。
「洗って返すんでいいか?」
「大丈夫ですよっ! このまま持って帰ります」
空になった弁当箱。それを見たらまた嬉しくなって、先輩の肩に体重を軽く預けた。
このままずっとこうしていたい。
一年持て余してしまったけど……本当は先輩ともっと色々なことをして、学校の行事を楽しんで、同じ時間を過ごしたかった。
密かな願いを胸に秘めて息をつくと、不意に名前を呼ばれた。
「雅月」
「あ、はい」
「昨日はないって言ったけど。……悩み……っていうか、不安なら少しある」
朋空先輩は俺を抱いたまま、掠れた声で話し出した。
「俺の母親、再婚するつもりなんだ」
「あっ」
「何? 知ってた?」
「いえ! 全く存じ上げません!」
一瞬固まったけど、慌ててかぶりを振る。先輩には申し訳ないけど、初めて聞いたようなふりをした。
先輩は少し怪しげにこちらを見ていたけど、それ以上は触れずに話を続けた。
「高校入る前から、かな。もう知り合ってから三年ぐらいになる」
「そうだったんですか……い、良い人ですか?」
語彙力ない俺はそれ以外に訊き方が分からなかった。朋空先輩は案の定吹き出し、腕を組んだ。
「そうだなぁ。多分、良い人だよ。優しいし、俺の進路についても相談乗ってくれるし」
「多分」と付けてしまうのは、結婚してから豹変する人がいるから、と笑った。
「俺の前の父親が、モロそういうタイプだった。母さんには幸せになってほしいけど、もうそういう目には遭ってほしくない。……と思ってる」
「……」