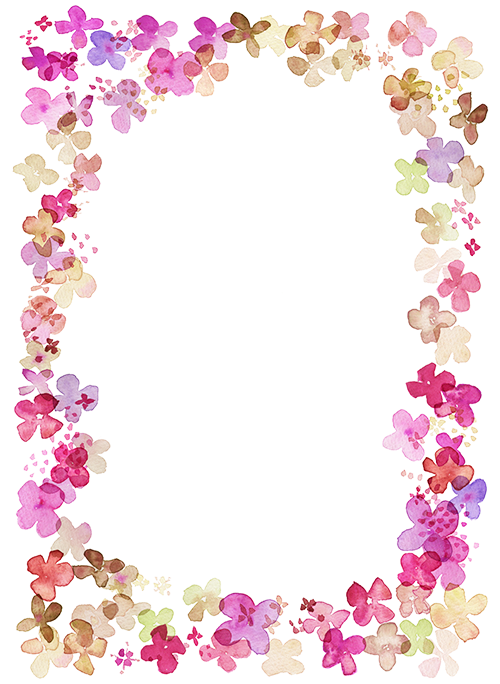「入ちゃん? どしたん、グレたの?」
「赤城先輩」
鞄を持って教室から出ると、ちょうど赤城先輩に出会した。彼は以前と違う恰好の俺を見て、露骨に驚いた。
「全然感じ違うじゃ〜ん。噂通りだ」
「噂? って何です?」
「入ちゃんが午前中の間にグレた、って学校中で噂になってるよ」
何それカッコ悪っ。どうせなら登校時から始めれば良かった。
「あ、でもちょうど良かった。辰野は今日先生から呼び出されてて、研究室に行くの遅れるって。入ちゃんに伝えといてって言われてたんだ」
「そうなんですね。わざわざすみません、ありがとうございます」
丁寧にお辞儀し、笑顔を浮かべると、赤城先輩はますます怪訝そうに身体を屈めた。
「入ちゃんはどんなに見た目を変えても、笑うと良い子オーラが滲み出るな」
「えぇ。じゃ、笑うのやめます」
「いやいや、ガラスのハートの俺にはスマイル必須だよ。それよか何でそんなイメチェン果たしたの? あんまり襟緩めない方がいいよ。変態が寄ってきちゃう」
赤城先輩は腕を組み、俺の襟元に手をかけた。
確かに彼の言う通り、逆に変な人を寄せ付けてしまうこともあるか。
「その……俺のファンクラブみたいなのができたらしいんです。危ないから、友達がパッと見近寄りがたい風にしなってコーディネートしてくれたんですよね」
「あぁ、それは聞いた。だから前に言ったろ? 入ちゃんはウチの獣達を誑かしちゃうビジュアルなんだって」
「誑かすって……」
いくらなんでも過大評価だ。
「本当にそうなら、もっと告られてもいいと思うんですよね」
「何! 告られたいの?」
「いえっそういうわけじゃないです」
俺には朋空先輩がいるから、告白されても断るしかない。
でももし本当にモテ始めてるなら、中々悪くないと思ってしまうのだ。しようもない矛盾である。
ファンクラブも、俺の知らない水面下で事態が進んでるのも怖いし。はぁ……。
「でも、先輩……。真面目な話、今の俺ってかっこいいです?」
「確実に調子に乗り始めちゃってるな」
最終的に、知らないひとについていかないよう釘をさされた。
でも、そこは本当に心配ないと思う。朋空先輩と会う前から俺は結構警戒心が強い方だったし。
「ねぇ、二年の入川君だよね? ちょっと話があるんだけど……」
「はいっ。何でしょう?」
研究室に向かおうとすると、また知らない男子生徒に声を掛けられた。上履きの色からして三年生だ。しかも背が高くて、すごくかっこいい。
赤城先輩と同じ系統っぽいな。いつもクラスの中心にいて、女の子からもモテそうな……。
ちなみにこの間わずか三秒。三秒で色々思考したあたり、俺の洞察力は著しいスピードで高まっている。
先輩は、俺の笑顔を見るとホッとしたように顔を綻ばせた。
そういえばスマイルをやめようと思ってたのに、声を掛けられると条件反射で笑顔を浮かべてしまう。尖った恰好をしてる意味がなくなってしまうが、館原のキャラ付けは俺には無理だ。諦めよう。
「俺、三年の進堂一真。実は、君のファンなんだよね」
「ファッ!?」
「うん。ファン」
聞き間違いかと思い見返したが、彼はにっこり微笑んだ。
ファンって……本当にいるのか。面と向かって言われたのが初めての為、どうしても信じられない。
あんぐり状態で見つめていると、進堂さんは焦った様子で続けた。
「あー……! 知らないかな? 先週から入川君のファンクラブもできたんだけど」
「な、何かそのようなものができたとは聞きましたけど……冗談だと思ってました。辰野先輩ぐらい綺麗な人なら分かりますけど」
俺みたいな平凡野郎にファンなんているわけない。
後ずさってそう答えると、彼はまた笑いながら首を横に振った。
「ちゃんとできてるよ。それに君はすごく綺麗」
「……っ」
“綺麗”なんて、生まれて初めて言われた。
朋空先輩からも可愛いとしか言われたことないよな、とぐるぐる考える。
お世辞だと思うけど……この進堂という先輩が尋常じゃないイケメンなので、妙に意識してしまう。
だけど、褒められる以上にあり得ない言葉が彼の口から飛び出した。
「っていうか俺が、君のファンクラブの会長なんだよね」
「うそっ」
「ほんと」
いやいや。……嘘だろ?
びっくりし過ぎて首を捻りそうになった。今も、嫌な汗が滝のように流れている。
「つかぬ事をお聞きしますが……ファンクラブって何やるんですか?」
「何でもやるよ。とりあえずは応援だけどね。君が困ってることがあったら、メンバー総出で力になる。辰野のファン達もそうしてると思うけど」
どうやら、それなりに団結力があるらしい。あと横の繋がりもすごいのか、もうグループチャットができていた。
ううん……でも、やっぱり手放しでは喜べない。
「あの……そんな好いてもらえるのは有り難いんですけど、俺はマジでただのゴミ虫野郎です。応援してもらっても、皆さんに何も返せません。だからあまり、推す必要はないかと」
第一に、推すような対象じゃない。
あと何を応援してもらうのかも全っ然分からん。俺が本当に困ってることなんて、数学の成績が絶望的に悪いことぐらいだ。
けど進堂先輩は、そんなことないよ! と大声で否定した。
「君がしなきゃいけないことなんてない。これは俺達が好きでやってることだ。辰野の影に隠れてるけど、君はすごく可愛い。もっと堂々とすべきだよ」