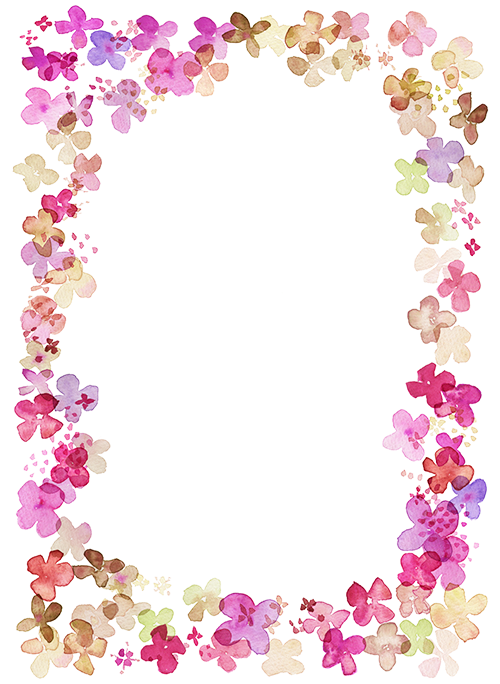それ全然大丈夫じゃない。青くなりながら傍に寄ると、先輩は倒れてしまうんじゃないか、ってほど顔が真っ赤だった。
「お前が可愛過ぎて、寿命がだいぶ縮んだ」
「うえっ」
伸びるんじゃなくて縮むのか。色々衝撃で慌てたが、先輩は深呼吸して、俺のことを抱き寄せた。
「はー……そうかそうか。俺がいなくて怖かったのか」
「だ、だって……一緒に寝てたのに」
「そうだよな。よしよし、ごめんな」
先輩はうんうん頷き、俺の頭を撫でられる。何かちょっと屈辱感があるけど、現状大号泣してるから仕方ない。
でも、起きたら独りで怖かったって……マジで情けない理由で泣いてる。
もう駄目だ……。先輩の胸に顔をうずめると、髪の毛を持ち上げられた。
「雅月、耳まで真っ赤だぞ」
「言わないでください……」
羞恥心のパラメーターが天井を突き破った。地面に倒れてのたうち回りたい衝動に駆られたけど、余裕たっぷりの朋空先輩は苦笑している。
「いや、俺もさっき起きたんだよ。やば、アラームかけ忘れたって思ってさ。でもお前が横でぐーぐー寝てて可愛かったから、しばらく眺めてた」
「ちょ! そこは起こしてください!」
「いいだろ。寝顔を見るのは恋人の特権だ」
朋空先輩はあっけらかんと言い放ち、足を組んだ。
「それで、喉渇いたから自販機で飲み物買ってたんだ。戻ってきたらお前が泣いてるから焦ったよ」
はい、と言って先輩は俺に烏龍茶をくれた。
「ありがとうございます……」
「どういたしまして。それより、何の夢見てたの?」
囁くように……いや、語りかけるように先輩は耳打ちした。
それはまるで子守唄のようで、思わず瞼を閉じそうになった。
「こーら。寝ちゃ駄目」
「う」
このまま眠れたら幸せだったけど、当然ながら顔を上げさせられ、阻止される。諦めて、胸の中に燻る想いをひとつひとつ取り出した。
「父親、のこと」
「父親? お前のお父さんって確か……」
「うん。俺が物心つく前に、病気で死んだ」
母親同士の会話から、先輩は既に知っていそうだ。でも誰かに話す機会なんて今までなかったから、俺が知る限りのことを彼に話した。
「父さんが死んだのは、俺のせいなんじゃないかと思って……」
表に出さないようにしていた、本当の気持ち。それを吐き出せたことに少しだけホッとしている。
友達には言えなかったこと……なのに、朋空先輩は聞いてほしいぐらいだ。この差は何だろう。
やはりこれが恋人パワーなのか。密かに戦いてると、先輩は険しい顔で前に屈んだ。
「ないな」
「え?」
「絶対ない。仮に過労だったとしても……それを子どものせいだなんて、絶対に思わないよ」
だって、こんなに可愛い息子だぞ? と言って、先輩は笑った。
「子どもの成長を見られなかったことは悔やんでるだろうけど。お前に苦しんでほしいなんて、親父さんは思ってないよ。だから大丈夫だ」
お前は愛されてるよ。
先輩は俺の頬に短いキスをした。
「先輩……ありがとうございます」
もしかしたら、一番聴きたい言葉だった。
心に根を張る罪悪感。それを誰かに伝えたくて。
「ほんとは謝りたかったんだ。父さんと……母さんに」
でもそれすらも彼らを傷つけてしまいそうで、怖かった。
俯いて泣く俺を、先輩は静かに抱いてくれた。
許されたわけじゃない。どんなに会いたいと願っても、父はもういないから。
だけど、温かい光に包まれている。