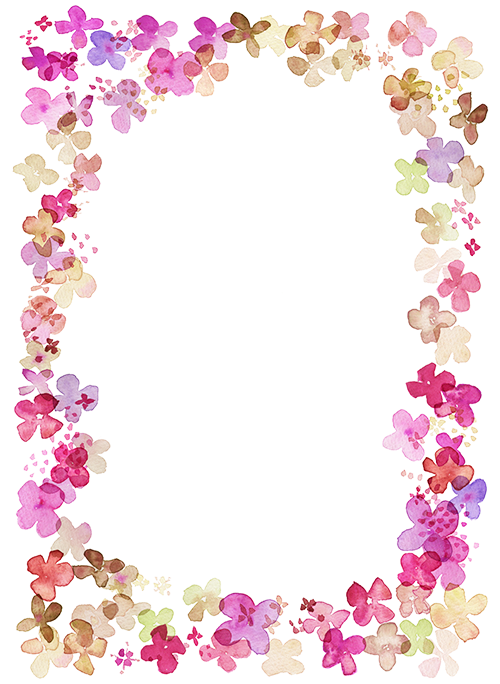……。
いや、一旦落ち着こう。正直まだボーッとして、状況を理解できてない。
体育座りをして、膝を抱えた。よく考えるとこんな時間まで学校にいたのは初めてだ。暗いのもあるが、静けさも相まってすごく不気味だった。
お化けとか出たらやだな。早く帰らなきゃ。
そう思うのに、中々腰が上がらない。ため息ばかりもれて、顔を膝にうずめた。
何かしんどい夢も見ていた気がする。何だっけ……。
必死に思い出そうとする傍ら、思い出すな、という警告も聞こえた。
辛いだけだから考えない方がいいと、ずっと封じていた記憶。
────父のことだ。
病気で亡くなってしまったけど、……それも全部俺のせいだったんじゃないか、と無意識に自分を責めていた。
俺が生まれなければ、父は無理して仕事したりしないで、母とずっと暮らしていられたんじゃないか。そんなことを考えたら、もう止まれなかった。
父への罪悪感。そして母に恨まれてるんじゃないか、という不安。
何で今思い出すんだよ……。
痛いぐらい奥歯を噛み締めた。大丈夫だって。……母さんが優しいことも分かってる。けど、それでも悔やまずにいられない。
怖くてたまらないんだ。
何だかとても、ひとりで帰れる気がしない。
子どもじゃないんだから早く立ち上がらないといけないのに。
「……朋空先輩……っ」
気付いたらスマホに額をあて、涙をこぼしていた。
一体どこにいるんだろう。呼んだら来てくれるだろうか。
そもそもわざと置いていかれたとしたら……ちょっと、本気で立ち直れないかもしれない。
今だけは、先輩に優しく頭を撫でてほしい。ボロボロと溢れて止まらない涙をぬぐい、嗚咽していたが。
「雅月……、どうした?」
ガラッと開かれたドア。顔を上げると、そこには驚いた顔の朋空先輩が立っていた。
「うっ……先輩……っ」
正直、俺も驚いた。てっきり帰ったと思っていたから、またまた酷い泣き顔を見られてしまい、顔から火が出そうになる。
朋空先輩は早足でこちらに駆け寄り、床に屈んで視線を合わせてきた。
「何、何で泣いてんの」
先輩は困ったように俺の頬に手を当てる。それからハンカチを取り出し、そっと涙を拭いてくれた。
「腫れるから、強く擦るなよ」
「ふぁい……」
ハンカチを受け取り、こくこくと頷く。少しずつ落ち着いてきて、何とか説明することができた。
「げ……幻滅しないで聞いてほしいんですけど」
「うん」
「怖い夢を見て……それで起きたら真っ暗で、朋空先輩がいないから……こ、怖くなっちゃって……」
話していて、とんでもなく情けなかった。それぐらいで弱音を吐いてる自分に嫌気が差す。
朋空先輩に会うまでこんなに泣き上戸だなんて知らなかった。肩を震わせながらしゃくり上げると、何故か朋空先輩は彼に手をつき、左胸を押さえていた。
「先輩? 大丈夫ですか?」
「大丈夫。……だけど、軽く心臓痛い……」