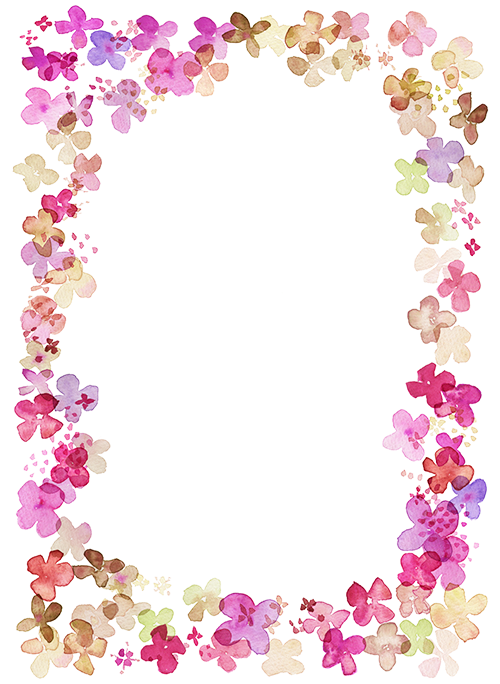日中は昨日までと同じく、研究会の詳細や朋空先輩の所在についてよく訊かれた。
元はと言えば赤城先輩が発端なんだけど、それはもう仕方ない。ある意味では先輩の関心が一旦俺に向くことで、ちょっとしたワンクッションになる。危なそうな人を予め知ることもできるし、悪くない気がしてきた。
この時の俺はとても呑気に。密かに、知名度が先輩の次ぐらい高まってることも知らず、放課後まで過ごした。
「あ。朋空先輩、お疲れ様です!」
「お疲れ」
帰りのホームルームを終え、研究室に向かう途中でちょうど先輩と会えた。
今朝会ったばかりなのに、何だか懐かしく思えた。
「さ。どうぞどうぞ」
部屋に入り、ドアを閉める。朋空先輩にベッドを指し示し、俺はドア付近の椅子に腰掛けた。
「それは……」
「はい?」
「どういうこと?」
部屋の端と端に留まり、見つめ合う。怪訝そうに尋ねる先輩に、俺も意味が分からず。顎に手を添え、考える人みたいなポーズをとった。
「どういうこと、とは」
「何でそんなところに座ってんの」
「……あぁ! 俺はここで適当にスマホ見て、休んでますよ。ベッドは先輩が伸び伸び使ってくださいね」
先輩の為を想って微笑んだのだが、彼はさっきよりも腑に落ちない表情で腕を組んだ。
「お前もいつも寝てるんだろ? 何で俺がいたら寝ないんだ」
「俺は大丈夫ですよ。そもそも先輩がここにひとりじゃ来づらいって言うから、付き添いで来てるだけなので」
「雅月」
「はい」
「来て」
朋空先輩はベッドに座ると、隣の面を叩いた。
…………。
何だ、その有無を言わさない感じは。
全力でツッコみたかったけど、言われるまま隣に行き、失礼しますと言って座った。
とりあえず何もない正面を見ながら、隣の先輩の声に耳を傾ける。
「お前が傍で起きてるのに、俺だけ寝るわけにいかないだろ」
「そんなことないから、気を遣わないでください。それに俺は、先輩が寝てる間に変なことしないし!」
冗談混じりに笑うと、先輩は少し考え、含みのある笑みを浮かべた。
「してもいいけど?」
「え?」
それは、どういう……。
不思議に思って横を向いたとき、身体を引き寄せられた。
「わあっ!」
視界が反転し、柔らかい腕の中に抱き込まれる。
「ちょ、先輩っ」
「はは。……あったかい。お前、赤ん坊みたいだな」
先輩の強行のせいで、向かい合わせで寝ることになった。
逃げようとしたけど腰に手を回され、地味に押さえられてる。絶対逃がさないという意志がひしひし感じられた。
それにしても、男二人でこの距離はやばい。
俺は男に興味ない。そのはずだ。
けど今の状況は、意識せざるを得ない。服越しとはいえ、胸も太腿もあたっているんだから。
「基礎体温高……。冬は湯たんぽになって気持ちよさそう」
「夏は暑いでしょ。ちょっと離れましょうよ」
「良いだろ、このままで。寝るぞ」
うー……。
寝たくても寝られない。先輩は落ち着き払って瞼を伏せたけど、俺は今にも心臓が爆発しそうだった。
互いの息づかいが感じられて、少し動いただけで伝わってしまう。こんな体勢でリラックスできるわけない。
「…………」
でも、やっぱし綺麗だ。
先輩の顔を見ながら、思わずため息が出そうになった。
何で男なのにこんな睫毛長いんだ……。
肌も白くて、透き通ってる。俺はもちろん、母さんも羨みそうだ。
触ってみたいな。ちょっとでいいから。
思わず手を伸ばしかけた時、朋空先輩は突然瞼を開けた。
「何」
「ひあっ!」
まずい。びっくりし過ぎて変な声を上げてしまった。
案の定、先輩は不審そうにこちらを見返す。
「ふっ。冗談て言ったんだけど、ほんとに何かする気だった?」
「な!」
やばい。誤解されてる。
断じてそんな気はないと、勢いよく首を横に振った。
「違います!」
「そう? 何かしようとしてなかった?」
「そ、その……あまりに綺麗だから」
至近距離で問い詰められ、たじろぐ。もはや半泣きで彼の袖を掴み、身を縮めた。
「ほ……本当にちょっとだけ、触ってみたいと思っちゃって。なにかする気はマジでないです!! ごめんなさい……」
目を瞑り、震えながら謝る。
嫌われたらどうしよう。びくびくしながら俯くと、無理やり顔を上げさせられた。
「何泣きそうな顔してんだ。俺がお前に怒るわけないだろ」
涙でぬれた瞳で、恐る恐る瞼を開ける。朋空先輩は少し困ったように、だけど優しく笑った。
「そんな怯えられると結構傷つくよ。全然信頼されてないんだな、って」
「し、信頼してますよ! 先輩が優しいことは知ってます!」
「なら、もっと甘えろよ。俺はお前にならいくら触られてもいい」
顎を支えていた長い指が、俺の唇をそっとなぞった。
今までで一番長い時間。どっちの熱かも分からないほど密着して、見つめ合う。
「触っ。……ってもいいんですか?」
「あぁ」
朋空先輩は俺の手を掴むと、そのまま自分の頬に持っていった。
「わあ」
思ったとおりだ。先輩の頬はもちもちして柔らかい。
「満足した?」
「はい。すごく」
小学生のようなノリでふにふにしていたが、今度は俺も頬を触られた。
「ちょ、せんぱ……っ」
「じゃあ次は俺の番だ」
先輩は不敵な笑みを浮かべ、俺を自分の胸に押しつけた。
「はぁ。……最高」
「……っ!!」
何が最高なのかさっぱり分からない。先輩は意外に力があるから、窒息しそうで必死にもがいた。
彼の肩を全力で押し、ようやく抜け出す。
「……っはぁ! 先輩、苦しい」
「悪い悪い。手に入る位置にいると、手に入れたくなっちゃうんだよな」
先輩は目を細め、恍惚とした表情を浮かべた。
「ずう……っと、こうして力いっぱいお前を抱き締めてみたかったんだ。抱き締めたら満足できるかもって思ったけど。……他のもん全部手放してでも、お前が欲しくなった」
「ふえ……」
待て待て。それってまるで。
……告白じゃないか。
見返すことしかできない俺のつむじを指で押し、先輩は天井を見上げた。
「俺が怖いよな。逃げていいぞ。どうせマンションで捕まえるし」
「逃がす気ないじゃないですか……!!」
真顔で言う先輩に底知れない恐怖を覚える。
でも、多分先輩は酷いことはしない。それを確信してるから、自ら彼の胸に顔をうずめた。
「どうせ捕まるなら……もうちょっと、このままでもいい。……です」
顔を見られたくないから潜ったのに、また簡単に顔を見られてしまった。
「やっぱりお前、可愛すぎだな」