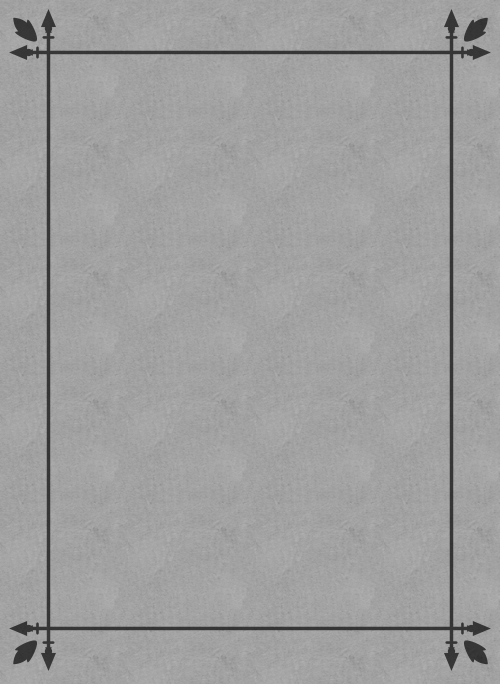春の風が、冷たくて少し甘かった。
入学式の朝。新しい制服の襟が、やけに固く感じる。
駅のホームを降りたとたん、視界がふっと霞んだ。
頭の奥がぼんやりして、足元がぐらりと揺れる。
体調がよくなかったのか、緊張しすぎていたのか、自分でもよくわからなかった。
とりあえず、近くのベンチに腰を下ろす。
手のひらで額を押さえ、息を整える。
(……情けない。初日からこれかよ。よりによって入学式の日に)
シャツの中を通る風が、思ったより冷たかった。
体の奥から力が抜けていくようで、しばらく動けない。
そのとき――
「大丈夫ですか?顔、真っ青ですよ」
突然の声に、思わず顔を上げた。
そこに立っていたのは、一人の男子生徒だった。
朝の光を背にして、少し眩しいくらいだった。
制服は同じ。つまり、同じ高校。
少し長めの前髪の下で、穏やかな目が俺を覗き込んでいる。
柔らかくて、どこか人懐っこい声だった。
「……ちょっと、寝不足で」
やっとの思いで言葉を返すと、その人はほっとしたように微笑んだ。
笑うと目尻が少し下がる。
その仕草だけで、息が詰まりそうになる。
「無理しないでね。はい、これ」
差し出されたのは、白地に青い刺繍が入ったハンカチ。
角の部分に、小さくS.Sの文字。
けれど、縫い目は少し歪で、ところどころ糸が不揃いだった。
それなのに、不思議と温かい。
誰かの手で、ちゃんと縫われた跡だった。
「いいんですか、これ借りて」
「うん。それに……」
彼は俺の胸元をちらりと見て、目を細めた。
「その制服。同じ高校ですよね?」
「……はい」
「そっか。じゃあ、よかったら一緒に行きましょうか?まだ時間ありますし」
その言葉に、心臓が小さく跳ねた。
知らない人なのに、なぜか懐かしいような声だった。
けれど、俺は思わず首を横に振っていた。
「……大丈夫です。一人で行けるんで」
「そう?」
少しだけ寂しそうに笑って、彼は鞄を肩にかけ直した。
「じゃあ、気をつけてね」
そう言って歩き出す後ろ姿を、俺はただ見送った。
桜並木の中、朝の光に包まれた背中が少しずつ遠ざかっていく。
(……名前、聞けばよかった)
手の中のハンカチを握りしめる。
指先に刺繍の糸の感触が伝わるたび、心の奥がじんと熱くなった。
なぜだろう。たった数分の出来事なのに、ずっと頭から離れなかった。
数日後。
新しい学校の廊下を歩いていたとき、図書室の窓際で本を読んでいる姿が目に入った。
(……いた)
陽の光を受けた横顔。あの日と同じ穏やかな表情。
ページをめくる指先まで、あのときの声と重なった。
「……」
声をかけようとしたのに、言葉が喉で止まった。
心臓の音ばかりが響いて、足が動かない。
ただ立ち尽くすことしかできなかった。
(どうして声が出ないんだ。返すだけなのに)
その日から、彼の姿を何度も目にするようになった。
図書室。放課後の静けさの中、窓際の席で本を読む姿。
外の風がカーテンを揺らしても、彼は微動だにせず文字を追っている。
(返さなきゃ。……でも、なんて言えばいい?)
勇気が出ないまま、時間だけが過ぎた。
名前も知らない。クラスも違う。
けれど、気づけば目で追ってしまっていた。
だから、図書委員の募集が出たとき、迷うことはなかった。
気づけば手が上がっていた。
(この仕事なら、自然に話せる。きっと……)
そう思ったのに、現実は思ったよりも残酷だった。
カウンター越しに、彼が本を抱えて現れる。
そのたびに、喉が乾いて声が出ない。
貸出カードを受け取る指先が、ほんの一瞬触れただけで息が止まる。
(やばい。心臓うるさい)
本を返す彼は、いつも同じ柔らかい笑顔だった。
誰にでもそうなんだろうけど――それでも、自分にだけ特別な気がしてしまう。
目が合えば、反射的に逸らす。
それでも、また見たくなる。
(返したいだけだったのに。いつのまにか……)
あの日からずっと、ハンカチを返すためのきっかけを探していたはずなのに――
いつのまにか、ただ彼の姿を探していた。
(……でも、いいこともあった)
返却された本の間から、ふと小さな紙が覗いていた。
図書カード――その右上に書かれた名前が、視界の中で静かに光って見えた。
思わず指が止まる。
そこには、丁寧な文字で書かれたフルネームと学年、クラス。
――白川柊(しらかわ しゅう)。
(……S.S。そうか)
指先に残っていたあの刺繍の感触。
白地に青い糸で、少しだけ不器用に縫われた文字。
(白川柊……)
名前を心の中で繰り返した瞬間、世界の色がほんの少し変わった気がした。
見慣れた校舎の窓も、白いカーテンも、どこか新しく見える。
名前を知っただけで、どうしてこんなに胸が高鳴るんだろう。
呼んだこともないのに、呼び慣れたように口の中で転がしてしまう。
(そっか……二年生、だったんだ)
先輩という響きが、思ったよりもしっくりきた。
年上なんだ、と知った瞬間、少し納得した。
あの柔らかい空気。
静かな声。
人の懐にすっと入り込むような優しさ。
全部、俺にはないものだった。
(白川先輩、か……)
気づいたら、少しだけ背伸びしたくなっていた。
この距離を縮めるには、少しでも大人にならなきゃ、って。
無意味な意地だってわかってるのに、そんなことを考えてしまう。
白川先輩は本が好きらしい。
放課後、図書室の窓際でいつも本を読んでいる姿を見かける。
でも、読む本は決まっていない。
小説の日もあれば、エッセイ、写真集、科学書。
まるで世界を少しずつ味わうみたいに、あらゆるページをめくっていた。
(なんか……全部を受け入れてる人、みたいだ)
そんなふうに思った。
どんな本にも偏見がなく、好奇心でページを開くその姿が、好きだった。
そして、羨ましかった。
自分の中にまだ知らない、広さを持っているようで。
カウンター越しに、彼が差し出す本のタイトルを見るのが楽しみになっていた。
貸出カードを受け取るとき、指先が少し触れる。
その一瞬に心臓が跳ねて、落ち着いたふりをするのに精一杯だった。
(今度はどんな本読むんだろ)
小さな興味のふりをして、実は目が離せなかった。
タイトルを覚えて、あとで自分も借りてみる。
そして、同じページを見つめながら考える。
――白川先輩も、ここを読んで、どんなことを思ったんだろう。
(好きな人の好きを知りたくなるって、こういうことなんだな)
思った瞬間、顔が熱くなった。
その感情に名前をつけるのが怖くて、俯いた。
憧れとか尊敬とか、いくらでも言い訳できるのに、どれも違った。
(返さなきゃ、ハンカチ……)
そう何度も思うのに、目の前に立つと、喉が乾いて声が出ない。
白川先輩という名前を覚えたのに、口に出す勇気がない。
心の中では何度も呼んでいるのに。
放課後の図書室。
静かな空気の中で、本を読む横顔を眺めながら、心の奥で小さくつぶやく。
(――白川先輩)
声にならない呼びかけは、風に溶けて消えていく。
でも、そのたびに胸の奥があたたかくなる。
まるで、その名前を呼ぶたびに、自分の中に小さな灯りが灯っていくみたいだった。
名前を知って、距離を感じて、でもその分惹かれていく。
その繰り返しが、いつの間にか日常になっていた。
そして気づけば、
夕陽を浴びるその人の姿が――俺にとって、春そのものになっていた。
放課後の図書室で、ふと笑う彼の横顔を見て思う。
(この人の笑顔を、もっと近くで見たい)
それだけで、息が詰まるほど苦しくなった。
ポケットの奥。
あの日のハンカチは、今も大切にしまってある。
白い布に残る淡い香りが、時間を止めたように残っていた。
(……いつか、ちゃんと返そう。そのときは、お礼じゃなくて、ちゃんと想いを込めて)
入学式の朝。新しい制服の襟が、やけに固く感じる。
駅のホームを降りたとたん、視界がふっと霞んだ。
頭の奥がぼんやりして、足元がぐらりと揺れる。
体調がよくなかったのか、緊張しすぎていたのか、自分でもよくわからなかった。
とりあえず、近くのベンチに腰を下ろす。
手のひらで額を押さえ、息を整える。
(……情けない。初日からこれかよ。よりによって入学式の日に)
シャツの中を通る風が、思ったより冷たかった。
体の奥から力が抜けていくようで、しばらく動けない。
そのとき――
「大丈夫ですか?顔、真っ青ですよ」
突然の声に、思わず顔を上げた。
そこに立っていたのは、一人の男子生徒だった。
朝の光を背にして、少し眩しいくらいだった。
制服は同じ。つまり、同じ高校。
少し長めの前髪の下で、穏やかな目が俺を覗き込んでいる。
柔らかくて、どこか人懐っこい声だった。
「……ちょっと、寝不足で」
やっとの思いで言葉を返すと、その人はほっとしたように微笑んだ。
笑うと目尻が少し下がる。
その仕草だけで、息が詰まりそうになる。
「無理しないでね。はい、これ」
差し出されたのは、白地に青い刺繍が入ったハンカチ。
角の部分に、小さくS.Sの文字。
けれど、縫い目は少し歪で、ところどころ糸が不揃いだった。
それなのに、不思議と温かい。
誰かの手で、ちゃんと縫われた跡だった。
「いいんですか、これ借りて」
「うん。それに……」
彼は俺の胸元をちらりと見て、目を細めた。
「その制服。同じ高校ですよね?」
「……はい」
「そっか。じゃあ、よかったら一緒に行きましょうか?まだ時間ありますし」
その言葉に、心臓が小さく跳ねた。
知らない人なのに、なぜか懐かしいような声だった。
けれど、俺は思わず首を横に振っていた。
「……大丈夫です。一人で行けるんで」
「そう?」
少しだけ寂しそうに笑って、彼は鞄を肩にかけ直した。
「じゃあ、気をつけてね」
そう言って歩き出す後ろ姿を、俺はただ見送った。
桜並木の中、朝の光に包まれた背中が少しずつ遠ざかっていく。
(……名前、聞けばよかった)
手の中のハンカチを握りしめる。
指先に刺繍の糸の感触が伝わるたび、心の奥がじんと熱くなった。
なぜだろう。たった数分の出来事なのに、ずっと頭から離れなかった。
数日後。
新しい学校の廊下を歩いていたとき、図書室の窓際で本を読んでいる姿が目に入った。
(……いた)
陽の光を受けた横顔。あの日と同じ穏やかな表情。
ページをめくる指先まで、あのときの声と重なった。
「……」
声をかけようとしたのに、言葉が喉で止まった。
心臓の音ばかりが響いて、足が動かない。
ただ立ち尽くすことしかできなかった。
(どうして声が出ないんだ。返すだけなのに)
その日から、彼の姿を何度も目にするようになった。
図書室。放課後の静けさの中、窓際の席で本を読む姿。
外の風がカーテンを揺らしても、彼は微動だにせず文字を追っている。
(返さなきゃ。……でも、なんて言えばいい?)
勇気が出ないまま、時間だけが過ぎた。
名前も知らない。クラスも違う。
けれど、気づけば目で追ってしまっていた。
だから、図書委員の募集が出たとき、迷うことはなかった。
気づけば手が上がっていた。
(この仕事なら、自然に話せる。きっと……)
そう思ったのに、現実は思ったよりも残酷だった。
カウンター越しに、彼が本を抱えて現れる。
そのたびに、喉が乾いて声が出ない。
貸出カードを受け取る指先が、ほんの一瞬触れただけで息が止まる。
(やばい。心臓うるさい)
本を返す彼は、いつも同じ柔らかい笑顔だった。
誰にでもそうなんだろうけど――それでも、自分にだけ特別な気がしてしまう。
目が合えば、反射的に逸らす。
それでも、また見たくなる。
(返したいだけだったのに。いつのまにか……)
あの日からずっと、ハンカチを返すためのきっかけを探していたはずなのに――
いつのまにか、ただ彼の姿を探していた。
(……でも、いいこともあった)
返却された本の間から、ふと小さな紙が覗いていた。
図書カード――その右上に書かれた名前が、視界の中で静かに光って見えた。
思わず指が止まる。
そこには、丁寧な文字で書かれたフルネームと学年、クラス。
――白川柊(しらかわ しゅう)。
(……S.S。そうか)
指先に残っていたあの刺繍の感触。
白地に青い糸で、少しだけ不器用に縫われた文字。
(白川柊……)
名前を心の中で繰り返した瞬間、世界の色がほんの少し変わった気がした。
見慣れた校舎の窓も、白いカーテンも、どこか新しく見える。
名前を知っただけで、どうしてこんなに胸が高鳴るんだろう。
呼んだこともないのに、呼び慣れたように口の中で転がしてしまう。
(そっか……二年生、だったんだ)
先輩という響きが、思ったよりもしっくりきた。
年上なんだ、と知った瞬間、少し納得した。
あの柔らかい空気。
静かな声。
人の懐にすっと入り込むような優しさ。
全部、俺にはないものだった。
(白川先輩、か……)
気づいたら、少しだけ背伸びしたくなっていた。
この距離を縮めるには、少しでも大人にならなきゃ、って。
無意味な意地だってわかってるのに、そんなことを考えてしまう。
白川先輩は本が好きらしい。
放課後、図書室の窓際でいつも本を読んでいる姿を見かける。
でも、読む本は決まっていない。
小説の日もあれば、エッセイ、写真集、科学書。
まるで世界を少しずつ味わうみたいに、あらゆるページをめくっていた。
(なんか……全部を受け入れてる人、みたいだ)
そんなふうに思った。
どんな本にも偏見がなく、好奇心でページを開くその姿が、好きだった。
そして、羨ましかった。
自分の中にまだ知らない、広さを持っているようで。
カウンター越しに、彼が差し出す本のタイトルを見るのが楽しみになっていた。
貸出カードを受け取るとき、指先が少し触れる。
その一瞬に心臓が跳ねて、落ち着いたふりをするのに精一杯だった。
(今度はどんな本読むんだろ)
小さな興味のふりをして、実は目が離せなかった。
タイトルを覚えて、あとで自分も借りてみる。
そして、同じページを見つめながら考える。
――白川先輩も、ここを読んで、どんなことを思ったんだろう。
(好きな人の好きを知りたくなるって、こういうことなんだな)
思った瞬間、顔が熱くなった。
その感情に名前をつけるのが怖くて、俯いた。
憧れとか尊敬とか、いくらでも言い訳できるのに、どれも違った。
(返さなきゃ、ハンカチ……)
そう何度も思うのに、目の前に立つと、喉が乾いて声が出ない。
白川先輩という名前を覚えたのに、口に出す勇気がない。
心の中では何度も呼んでいるのに。
放課後の図書室。
静かな空気の中で、本を読む横顔を眺めながら、心の奥で小さくつぶやく。
(――白川先輩)
声にならない呼びかけは、風に溶けて消えていく。
でも、そのたびに胸の奥があたたかくなる。
まるで、その名前を呼ぶたびに、自分の中に小さな灯りが灯っていくみたいだった。
名前を知って、距離を感じて、でもその分惹かれていく。
その繰り返しが、いつの間にか日常になっていた。
そして気づけば、
夕陽を浴びるその人の姿が――俺にとって、春そのものになっていた。
放課後の図書室で、ふと笑う彼の横顔を見て思う。
(この人の笑顔を、もっと近くで見たい)
それだけで、息が詰まるほど苦しくなった。
ポケットの奥。
あの日のハンカチは、今も大切にしまってある。
白い布に残る淡い香りが、時間を止めたように残っていた。
(……いつか、ちゃんと返そう。そのときは、お礼じゃなくて、ちゃんと想いを込めて)