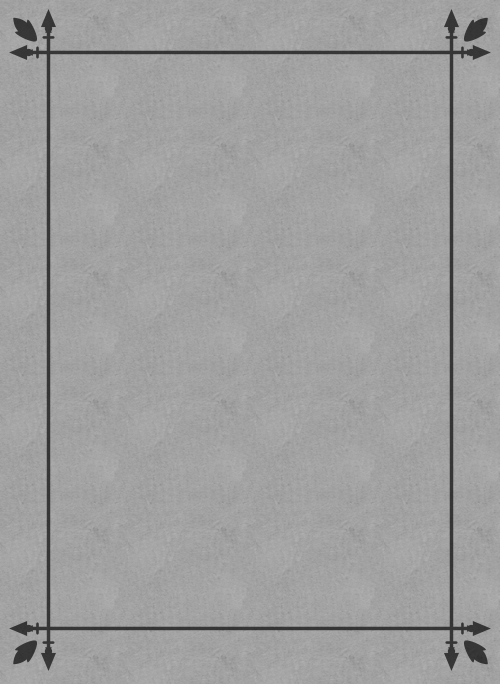放課後の教室。
夕陽が西の窓から差し込んで、埃の粒が光の中をゆっくり舞っていた。
机の上には、昨夜読み終えたばかりの文庫本が置かれていた。
ページを閉じた瞬間に感じたあの熱が、まだ胸の奥に残っている気がする。
(……いい話だったな。最後、ずるいよ……あんな言葉)
柊は指先でそっと表紙を撫でた。
ページの角に触れるたび、昨日の夜の静けさが思い出される。
枕元の灯りの下で、ひとり涙した時間。
本を閉じたあと、しばらく呼吸もできなかった。
(……あれを読んだ後で、すぐに眠れる人いるのかな)
小さく笑って、息を吐く。
心の奥に残った余韻を振りほどくように、本を抱えて立ち上がった。
(返さなきゃ。律、今日もカウンターにいるかな)
そんなことを考えた自分に、思わず苦笑する。
別に、わざわざ意識するほどのことでもないのに。
でも――あの静かな声を思い出すと、不思議と図書室への足取りが軽くなる。
図書室のカウンターで、律が本の整理をしていた。
制服の袖から伸びる指が、滑らかにページを撫でていく。
整った横顔に、窓からの光が淡く落ちる。
夕陽の色が、彼の睫毛に金を落としていた。
(……ほんと、絵になるな)
そんなことを思ってしまって、慌てて視線を逸らした。
でも、その瞬間、律が顔を上げる。
目が合って――心臓が、どくりと跳ねた。
「……あ、それ、返却ですか?」
低くて穏やかな声。
静かな空気に溶けて、胸の奥にまで響いた。
「うん。昨日、読み終わったんだ」
柊は明るく言いながらも、心の中はざわついていた。
律は「そうですか」と小さく呟き、手を止めた。
カウンターの上に積まれていた整理中の本を、そっと脇に寄せる。
その仕草がどこまでも丁寧で、静かな動作のひとつひとつに、彼らしい落ち着きが滲んでいた。
それから、律はゆっくりと柊の方へ視線を戻す。
その穏やかな眼差しに、柊の胸の鼓動がまた一拍、強く鳴った。
「どうでした?」
ただそれだけの問いなのに、心を覗かれたような気がして、柊は少し言葉に詰まる。
迷いながらも、正直に口にした。
「……最後の一行で、泣いた」
律の指が止まった。
ページを撫でていた動作も止まり、静寂が落ちる。
柊が顔を上げると、律がゆっくりとこちらを見ていた。
その瞳が、どこか嬉しそうに揺れている。
「柊先輩の……泣き顔、見たかったです」
心臓が一瞬で跳ね上がる。
空気が変わった。
図書室の時計の音が、やけに大きく響く。
「な、何言ってるの……」
声が震える。
頬が熱くなって、目を合わせられない。
律は少しだけ笑って、まっすぐに言った。
「だって、想像できないんです。柊先輩が泣くところ」
その穏やかな声の奥に、ほんの少しだけ親しさが混じっている。
柊は思わず小さく息を呑む。
「そりゃ……人前では泣かないから」
「じゃあ、俺だけに見せてください」
――息が止まった。
(……今、なんて?)
柊の手から文庫本が滑りかけた瞬間、律の手が伸びた。
二人の指先が触れる。
ほんの一瞬。
それだけで、胸の奥がじんわりと熱くなった。
律の指が柊の手を支える。
その手の温もりが伝わってくる。
「……ごめんなさい。落ちそうだったので」
律がそう言って手を離す。
でも、その一瞬がやけに長く感じた。
「……律って、意外とそういうこと言うんだな」
照れ隠しのように笑うと、律は首を傾げた。
「意外、ですか?」
「うん。もっとクールで、他人に興味なさそうだと思ってた」
「それ、よく言われます。でも――」
律は少しだけ前に出る。
その距離が縮まって、息の音が近くなった。
胸が苦しいほど高鳴る。
「柊先輩が相手だと、自然に話せるんです」
その言葉が落ちた瞬間、時間が止まったように感じた。
心のどこかが、やさしく揺れる。
(……ずるい。そんな顔、そんな声)
窓の外の風がカーテンを揺らし、夕陽が二人を包む。
光が柔らかく混ざり合って、世界が少し霞んで見えた。
柊は笑うように、でも少しだけ震える声で言った。
「……そんなこと言われたら、また泣きそうになるじゃないか」
律は目を細めて、優しく笑う。
「じゃあ、今度こそ見せてくださいね。柊先輩の涙」
少し悪戯っぽいその言葉が、まっすぐ胸に届いた。
柊は思わず息を呑み、そして小さく笑う。
「……じゃあ、今度、この本、借りてみてよ。結構いい話だからさ、おすすめするよ。……泣いた仲間、欲しいし」
律は目を細めて、小さく息をこぼした。
「泣かせるんですか?俺を?」
「うん。思いっきり、泣かせてやる」
「それなら、覚悟しておきます」
そう言って笑う律の声は、驚くほど優しくて。
柊の胸の奥が、少しだけ温かくなる。
律は、ふっと笑った。
「じゃあ、次は俺のおすすめですね」
唐突な言葉に、柊は瞬きをした。
「おすすめ?」
「はい。泣いた本の後には、笑えるやつを読まなきゃ。バランス取らないと」
その言い方が、やけに真面目で。
でも、どこか優しくて。
柊は思わず吹き出してしまった。
「何それ」
呆れたように言いながらも、頬が少し熱くなる。
律のその言葉が冗談なのか本気なのか、わからなかった。
けれど、どちらにしても――嫌じゃなかった。
「次は、先輩のこと、泣かせませんから」
その声が、どこまでも優しくて。
柊の胸の奥で、また静かに何かが鳴った。
思わず変な声が出た。
恥ずかしくて、でもおかしくて、笑いを堪えきれない。
律はそんな柊を見て、静かに笑った。
いつもの冷静さより、ほんの少しだけ楽しそうな表情で。
「冗談じゃないですよ。本気です」
「……そういうセリフ、さらっと言えるのずるい」
「ずるいですか?」
「……ずるいよ、年下のくせに。泣き顔見たいとか、泣かせないとか……どっちなのさ」
「年下だから、素直なんです」
(……何それ)
そんなこと言われたら、もう反応できない。
柊は視線を逸らして、返却カードを渡そうとした。
けれど、その瞬間――指先が、触れた。
ほんの一瞬なのに、鼓動が跳ねる。
離そうとしたのに、律が少しだけそのままにしていた。
「……律」
名前を呼ぶと、律の指がわずかに動いた。
その目が、まっすぐに柊を見つめている。
「俺、先輩のそういう顔……好きです」
「……っ、律、そういうこと言うなって……!」
「だって、本当のことですよ」
律は静かに笑った。
まるでからかうようで、でもどこか優しい。
柊は頬を赤くしたまま、ぷいと顔を背ける。
「……もう知らない」
「じゃあ、次の本の感想も楽しみにしてますね」
「な、なんで当然みたいに……!」
「返却日って、案外いい日だなって思って」
その言葉に、柊は一瞬だけ目を見開く。
そして、小さく笑ってしまった。
「……ほんと、ずるいな」
窓の外では、夕陽が静かに沈んでいく。
二人の影が重なって、ひとつに溶けた。
夕陽が西の窓から差し込んで、埃の粒が光の中をゆっくり舞っていた。
机の上には、昨夜読み終えたばかりの文庫本が置かれていた。
ページを閉じた瞬間に感じたあの熱が、まだ胸の奥に残っている気がする。
(……いい話だったな。最後、ずるいよ……あんな言葉)
柊は指先でそっと表紙を撫でた。
ページの角に触れるたび、昨日の夜の静けさが思い出される。
枕元の灯りの下で、ひとり涙した時間。
本を閉じたあと、しばらく呼吸もできなかった。
(……あれを読んだ後で、すぐに眠れる人いるのかな)
小さく笑って、息を吐く。
心の奥に残った余韻を振りほどくように、本を抱えて立ち上がった。
(返さなきゃ。律、今日もカウンターにいるかな)
そんなことを考えた自分に、思わず苦笑する。
別に、わざわざ意識するほどのことでもないのに。
でも――あの静かな声を思い出すと、不思議と図書室への足取りが軽くなる。
図書室のカウンターで、律が本の整理をしていた。
制服の袖から伸びる指が、滑らかにページを撫でていく。
整った横顔に、窓からの光が淡く落ちる。
夕陽の色が、彼の睫毛に金を落としていた。
(……ほんと、絵になるな)
そんなことを思ってしまって、慌てて視線を逸らした。
でも、その瞬間、律が顔を上げる。
目が合って――心臓が、どくりと跳ねた。
「……あ、それ、返却ですか?」
低くて穏やかな声。
静かな空気に溶けて、胸の奥にまで響いた。
「うん。昨日、読み終わったんだ」
柊は明るく言いながらも、心の中はざわついていた。
律は「そうですか」と小さく呟き、手を止めた。
カウンターの上に積まれていた整理中の本を、そっと脇に寄せる。
その仕草がどこまでも丁寧で、静かな動作のひとつひとつに、彼らしい落ち着きが滲んでいた。
それから、律はゆっくりと柊の方へ視線を戻す。
その穏やかな眼差しに、柊の胸の鼓動がまた一拍、強く鳴った。
「どうでした?」
ただそれだけの問いなのに、心を覗かれたような気がして、柊は少し言葉に詰まる。
迷いながらも、正直に口にした。
「……最後の一行で、泣いた」
律の指が止まった。
ページを撫でていた動作も止まり、静寂が落ちる。
柊が顔を上げると、律がゆっくりとこちらを見ていた。
その瞳が、どこか嬉しそうに揺れている。
「柊先輩の……泣き顔、見たかったです」
心臓が一瞬で跳ね上がる。
空気が変わった。
図書室の時計の音が、やけに大きく響く。
「な、何言ってるの……」
声が震える。
頬が熱くなって、目を合わせられない。
律は少しだけ笑って、まっすぐに言った。
「だって、想像できないんです。柊先輩が泣くところ」
その穏やかな声の奥に、ほんの少しだけ親しさが混じっている。
柊は思わず小さく息を呑む。
「そりゃ……人前では泣かないから」
「じゃあ、俺だけに見せてください」
――息が止まった。
(……今、なんて?)
柊の手から文庫本が滑りかけた瞬間、律の手が伸びた。
二人の指先が触れる。
ほんの一瞬。
それだけで、胸の奥がじんわりと熱くなった。
律の指が柊の手を支える。
その手の温もりが伝わってくる。
「……ごめんなさい。落ちそうだったので」
律がそう言って手を離す。
でも、その一瞬がやけに長く感じた。
「……律って、意外とそういうこと言うんだな」
照れ隠しのように笑うと、律は首を傾げた。
「意外、ですか?」
「うん。もっとクールで、他人に興味なさそうだと思ってた」
「それ、よく言われます。でも――」
律は少しだけ前に出る。
その距離が縮まって、息の音が近くなった。
胸が苦しいほど高鳴る。
「柊先輩が相手だと、自然に話せるんです」
その言葉が落ちた瞬間、時間が止まったように感じた。
心のどこかが、やさしく揺れる。
(……ずるい。そんな顔、そんな声)
窓の外の風がカーテンを揺らし、夕陽が二人を包む。
光が柔らかく混ざり合って、世界が少し霞んで見えた。
柊は笑うように、でも少しだけ震える声で言った。
「……そんなこと言われたら、また泣きそうになるじゃないか」
律は目を細めて、優しく笑う。
「じゃあ、今度こそ見せてくださいね。柊先輩の涙」
少し悪戯っぽいその言葉が、まっすぐ胸に届いた。
柊は思わず息を呑み、そして小さく笑う。
「……じゃあ、今度、この本、借りてみてよ。結構いい話だからさ、おすすめするよ。……泣いた仲間、欲しいし」
律は目を細めて、小さく息をこぼした。
「泣かせるんですか?俺を?」
「うん。思いっきり、泣かせてやる」
「それなら、覚悟しておきます」
そう言って笑う律の声は、驚くほど優しくて。
柊の胸の奥が、少しだけ温かくなる。
律は、ふっと笑った。
「じゃあ、次は俺のおすすめですね」
唐突な言葉に、柊は瞬きをした。
「おすすめ?」
「はい。泣いた本の後には、笑えるやつを読まなきゃ。バランス取らないと」
その言い方が、やけに真面目で。
でも、どこか優しくて。
柊は思わず吹き出してしまった。
「何それ」
呆れたように言いながらも、頬が少し熱くなる。
律のその言葉が冗談なのか本気なのか、わからなかった。
けれど、どちらにしても――嫌じゃなかった。
「次は、先輩のこと、泣かせませんから」
その声が、どこまでも優しくて。
柊の胸の奥で、また静かに何かが鳴った。
思わず変な声が出た。
恥ずかしくて、でもおかしくて、笑いを堪えきれない。
律はそんな柊を見て、静かに笑った。
いつもの冷静さより、ほんの少しだけ楽しそうな表情で。
「冗談じゃないですよ。本気です」
「……そういうセリフ、さらっと言えるのずるい」
「ずるいですか?」
「……ずるいよ、年下のくせに。泣き顔見たいとか、泣かせないとか……どっちなのさ」
「年下だから、素直なんです」
(……何それ)
そんなこと言われたら、もう反応できない。
柊は視線を逸らして、返却カードを渡そうとした。
けれど、その瞬間――指先が、触れた。
ほんの一瞬なのに、鼓動が跳ねる。
離そうとしたのに、律が少しだけそのままにしていた。
「……律」
名前を呼ぶと、律の指がわずかに動いた。
その目が、まっすぐに柊を見つめている。
「俺、先輩のそういう顔……好きです」
「……っ、律、そういうこと言うなって……!」
「だって、本当のことですよ」
律は静かに笑った。
まるでからかうようで、でもどこか優しい。
柊は頬を赤くしたまま、ぷいと顔を背ける。
「……もう知らない」
「じゃあ、次の本の感想も楽しみにしてますね」
「な、なんで当然みたいに……!」
「返却日って、案外いい日だなって思って」
その言葉に、柊は一瞬だけ目を見開く。
そして、小さく笑ってしまった。
「……ほんと、ずるいな」
窓の外では、夕陽が静かに沈んでいく。
二人の影が重なって、ひとつに溶けた。