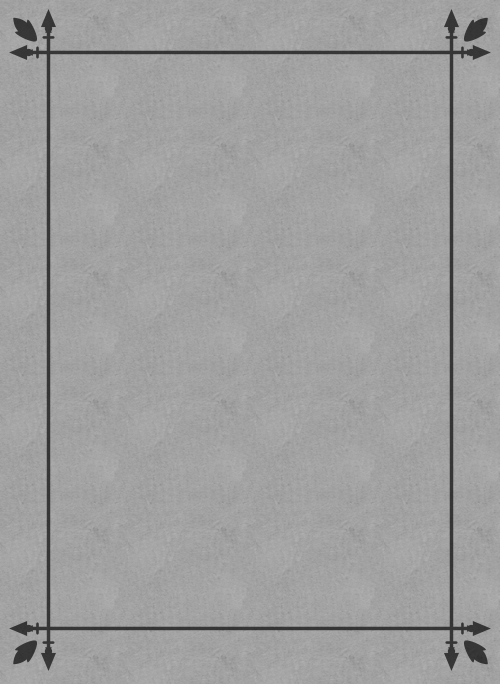放課後の図書室。
窓の外には西日が傾き、淡い橙色の光が棚の隙間を縫うように差し込んでいた。
本の紙の香りと、微かに揺れるカーテン。
ページをめくる音と、時計の針の音。
世界の中で、ふたりの呼吸だけが静かに重なっている。
柊は返却カウンターに文庫本をそっと置いた。
「……この前の続き、読みました?」
律が、少し低めの声で問いかける。
周囲に人がいないのを確認して、ほんの少しだけ声を落とす。
その距離感が、なんだか特別に感じられた。
柊は口元に柔らかな笑みを浮かべた。
「うん、読んだ。やっぱり主人公報われなかった」
「だから俺、あの作家苦手なんですよ」
「へぇ、そういうとこ、ちゃんと気にするんだ」
「ちゃんとって何ですか」
「だって、律ってもっと淡々としてるのかと思ってたから」
「……そんなに冷たい人間じゃないですよ」
律の頬が、照明の光を受けてほんのり朱に染まる。
柊は、その変化が少しおかしくて、小さく笑った。
彼の笑い声は、静かな空気の中でやわらかく弾ける。
「律のそういう反応、好きだな」
「……反応って、何の話ですか」
「なんか、見てると気分が良くなる」
「それ、からかってます?」
「からかってないよ。素直に言っただけ」
「……そういう言葉、簡単に言わないほうがいいですよ」
律は目線を逸らしているのに、声だけが妙に低い。
その響きに、柊の心臓が跳ねた。
「先輩、この本も好きそうです」
律が差し出したのは、海辺の風景が描かれた表紙の小説。
「少し切ないけど、最後が穏やかで、読むと救われます」
「自分からおすすめしてくれるなんて、珍しいね」
「……まあ、今日は気分がいいんで」
「気分がいい?」
「はい。今日も先輩に会えたから」
柊のまつげが、わずかに揺れた。
目を伏せたとき、胸の奥に小さな灯りがともる。
(……そんなこと、何の気なしに言うんだ)
「たまには俺のセンスも信じてくださいよ」
「信じてるよ。律、ほんと本の選び方うまいし」
「ほんとってつけるの、ダメですよ」
「どうして?」
「それ言われると、何か勘違いしそうになるんで」
(勘違い、か……)
柊は心の中で呟いた。
もし、それが本当の気持ちだったら――なんて、考えかけて首を振る。
そんなこと、思うわけがない。
後輩にそんな目で見られても、困るだけだ。
……なのに、どうして頬がこんなに熱いんだろう。
律はふいに、小さく息を吸った。
「先輩」
「ん?」
「俺、金曜日って結構好きなんです」
「どうして?」
「……先輩が必ず来るから」
その言葉は、図書室の静けさの中で、妙に鮮やかに響いた。
柊の胸の奥で、何かがゆっくりと動き出す。
「そんなの、たまたまだよ」
「たまたまでも、俺には特別です」
言ってから、律は照れたように目を逸らす。
本を並べる手元が、ほんの少し震えていた。
「図書室、金曜だけ空気が違うんですよ。……先輩がいると落ち着くんです」
「僕がいるから?」
「そうです。先輩って、静かだけど空気を柔らかくする人なんで」
「そんな風に言われたの初めて」
「俺が最初でいいです」
その言葉の端に、少しだけ照れと誇らしさが混ざっていた。
柊はそっと目を細める。
(この人、ほんとに真っ直ぐだな)
けれどその真っ直ぐさが、どうしようもなく心を揺らす。
自分の心が少しずつ色を帯びていくのが、怖くもあり、嬉しくもあった。
「ねえ、律」
「はい?」
「報われない話って、嫌い?」
「苦手です。でも、先輩が読むなら……隣で一緒に読んでもいいです」
「それって、慰めてくれるってこと?」
「違います。ただ、先輩がページをめくる音、好きなんで」
(……そんなこと、真顔で言わないでよ)
柊の頬に、ゆっくりと赤みが広がっていく。
図書室の光が、その色をやわらかく包み込む。
柊は慌てて、ポケットからハンカチを取り出した。
「……ちょっと、暑いな」
そう言って、頬を拭うふりをする。
律が首をかしげた。
「どうしたんですか、先輩」
「ん、なんでもない。ただ……ちょっと暑くなって」
視線を逸らしながら、柊は曖昧に笑う。
律は小さく笑って、少しだけ身を乗り出した。
「先輩、いつもハンカチ持ち歩いてるんですか?」
「うん、まあ……クセみたいなもんかな」
「へえ。やっぱり、そうなんですね……」
律の声はどこか柔らかくて、
柊はその響きに、ますます顔を上げられなくなった。
金曜日の図書室は、今日も静かだった。
けれど、ふたりの距離だけは確かに、先週よりも近づいていた。
窓の外には西日が傾き、淡い橙色の光が棚の隙間を縫うように差し込んでいた。
本の紙の香りと、微かに揺れるカーテン。
ページをめくる音と、時計の針の音。
世界の中で、ふたりの呼吸だけが静かに重なっている。
柊は返却カウンターに文庫本をそっと置いた。
「……この前の続き、読みました?」
律が、少し低めの声で問いかける。
周囲に人がいないのを確認して、ほんの少しだけ声を落とす。
その距離感が、なんだか特別に感じられた。
柊は口元に柔らかな笑みを浮かべた。
「うん、読んだ。やっぱり主人公報われなかった」
「だから俺、あの作家苦手なんですよ」
「へぇ、そういうとこ、ちゃんと気にするんだ」
「ちゃんとって何ですか」
「だって、律ってもっと淡々としてるのかと思ってたから」
「……そんなに冷たい人間じゃないですよ」
律の頬が、照明の光を受けてほんのり朱に染まる。
柊は、その変化が少しおかしくて、小さく笑った。
彼の笑い声は、静かな空気の中でやわらかく弾ける。
「律のそういう反応、好きだな」
「……反応って、何の話ですか」
「なんか、見てると気分が良くなる」
「それ、からかってます?」
「からかってないよ。素直に言っただけ」
「……そういう言葉、簡単に言わないほうがいいですよ」
律は目線を逸らしているのに、声だけが妙に低い。
その響きに、柊の心臓が跳ねた。
「先輩、この本も好きそうです」
律が差し出したのは、海辺の風景が描かれた表紙の小説。
「少し切ないけど、最後が穏やかで、読むと救われます」
「自分からおすすめしてくれるなんて、珍しいね」
「……まあ、今日は気分がいいんで」
「気分がいい?」
「はい。今日も先輩に会えたから」
柊のまつげが、わずかに揺れた。
目を伏せたとき、胸の奥に小さな灯りがともる。
(……そんなこと、何の気なしに言うんだ)
「たまには俺のセンスも信じてくださいよ」
「信じてるよ。律、ほんと本の選び方うまいし」
「ほんとってつけるの、ダメですよ」
「どうして?」
「それ言われると、何か勘違いしそうになるんで」
(勘違い、か……)
柊は心の中で呟いた。
もし、それが本当の気持ちだったら――なんて、考えかけて首を振る。
そんなこと、思うわけがない。
後輩にそんな目で見られても、困るだけだ。
……なのに、どうして頬がこんなに熱いんだろう。
律はふいに、小さく息を吸った。
「先輩」
「ん?」
「俺、金曜日って結構好きなんです」
「どうして?」
「……先輩が必ず来るから」
その言葉は、図書室の静けさの中で、妙に鮮やかに響いた。
柊の胸の奥で、何かがゆっくりと動き出す。
「そんなの、たまたまだよ」
「たまたまでも、俺には特別です」
言ってから、律は照れたように目を逸らす。
本を並べる手元が、ほんの少し震えていた。
「図書室、金曜だけ空気が違うんですよ。……先輩がいると落ち着くんです」
「僕がいるから?」
「そうです。先輩って、静かだけど空気を柔らかくする人なんで」
「そんな風に言われたの初めて」
「俺が最初でいいです」
その言葉の端に、少しだけ照れと誇らしさが混ざっていた。
柊はそっと目を細める。
(この人、ほんとに真っ直ぐだな)
けれどその真っ直ぐさが、どうしようもなく心を揺らす。
自分の心が少しずつ色を帯びていくのが、怖くもあり、嬉しくもあった。
「ねえ、律」
「はい?」
「報われない話って、嫌い?」
「苦手です。でも、先輩が読むなら……隣で一緒に読んでもいいです」
「それって、慰めてくれるってこと?」
「違います。ただ、先輩がページをめくる音、好きなんで」
(……そんなこと、真顔で言わないでよ)
柊の頬に、ゆっくりと赤みが広がっていく。
図書室の光が、その色をやわらかく包み込む。
柊は慌てて、ポケットからハンカチを取り出した。
「……ちょっと、暑いな」
そう言って、頬を拭うふりをする。
律が首をかしげた。
「どうしたんですか、先輩」
「ん、なんでもない。ただ……ちょっと暑くなって」
視線を逸らしながら、柊は曖昧に笑う。
律は小さく笑って、少しだけ身を乗り出した。
「先輩、いつもハンカチ持ち歩いてるんですか?」
「うん、まあ……クセみたいなもんかな」
「へえ。やっぱり、そうなんですね……」
律の声はどこか柔らかくて、
柊はその響きに、ますます顔を上げられなくなった。
金曜日の図書室は、今日も静かだった。
けれど、ふたりの距離だけは確かに、先週よりも近づいていた。