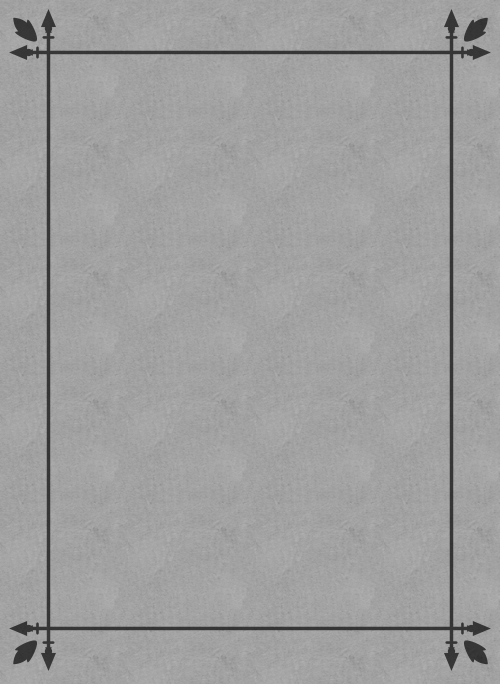放課後の図書室。
ページをめくる音と、遠くの時計の針の音だけが響いていた。
柊は、窓際の定位置で本を閉じた。
指先に残る紙の感触が、まだ物語の余韻を離してくれない。
ふと顔を上げると、カウンターの向こうで律くんが黙々と作業をしていた。
返却された本を一冊ずつ確認し、仕分けして、整える。
その一連の動きに、無駄がない。
姿勢も視線もまっすぐで、まるで教科書の挿絵みたいに整っていた。
(……集中してる顔、結構いいな)
静かな空気の中、そんなことを思った瞬間、目が離せなくなった。
本の背表紙の影に紛れて、視線を送る。
でも――その視線に気づかれるのは、案外早かった。
「……あの、柊先輩」
低い声に呼ばれ、心臓が跳ねた。
律は本を抱えたまま、少しだけ首を傾げている。
いつもの落ち着いた顔のままなのに、目だけがわずかに困っていた。
「え、なに?」
「さっきから、ずっと見られてる気がするんですけど」
「……っ」
(やっぱりバレてた!?)
柊は慌てて笑い、頬をかく。
「ごめん。集中してる姿、ちょっとかっこいいなって思って」
律の手が止まった。
まるで時間まで一緒に止まったみたいに、空気が静まり返る。
その沈黙が、妙に長く感じられた。
(やば……言い方、素直すぎた?いや、でも本当のことだし……)
ようやく律が息をつく。
「……そういうの、図書室では禁止です」
「え?」
「褒め言葉とか、そういうの。集中できなくなるんで」
口ではそう言いながらも、律くんの耳の先がほんのり赤い。
その色が、夕陽のせいじゃないのがわかる。
柊先輩はつい、くすっと笑ってしまった。
「じゃあ、心のメモに書いとく」
「……メモ、破棄してください」
「無理。たぶん永久保存版」
律は返却された本を抱え直し、背を向けた。
けれど、その横顔の端――唇の端がほんの少し、上がっている。
(あ、笑ってる)
そんなことに気づいて、胸の奥がふわりと温かくなった。
外では夕陽が傾き、オレンジ色の光が本棚の影を長く伸ばしていく。
二人の間を通り抜けるその光が、どこかやさしくて。
柊は、本を抱えたまま、そっと息を吐いた。
(……なんか、こういうのが青春ってやつなんだろうな)
静かな図書室で、ページをめくる音がまた戻る。
けれどその音の向こう、確かに何かが生まれた気がした。
ページをめくる音と、遠くの時計の針の音だけが響いていた。
柊は、窓際の定位置で本を閉じた。
指先に残る紙の感触が、まだ物語の余韻を離してくれない。
ふと顔を上げると、カウンターの向こうで律くんが黙々と作業をしていた。
返却された本を一冊ずつ確認し、仕分けして、整える。
その一連の動きに、無駄がない。
姿勢も視線もまっすぐで、まるで教科書の挿絵みたいに整っていた。
(……集中してる顔、結構いいな)
静かな空気の中、そんなことを思った瞬間、目が離せなくなった。
本の背表紙の影に紛れて、視線を送る。
でも――その視線に気づかれるのは、案外早かった。
「……あの、柊先輩」
低い声に呼ばれ、心臓が跳ねた。
律は本を抱えたまま、少しだけ首を傾げている。
いつもの落ち着いた顔のままなのに、目だけがわずかに困っていた。
「え、なに?」
「さっきから、ずっと見られてる気がするんですけど」
「……っ」
(やっぱりバレてた!?)
柊は慌てて笑い、頬をかく。
「ごめん。集中してる姿、ちょっとかっこいいなって思って」
律の手が止まった。
まるで時間まで一緒に止まったみたいに、空気が静まり返る。
その沈黙が、妙に長く感じられた。
(やば……言い方、素直すぎた?いや、でも本当のことだし……)
ようやく律が息をつく。
「……そういうの、図書室では禁止です」
「え?」
「褒め言葉とか、そういうの。集中できなくなるんで」
口ではそう言いながらも、律くんの耳の先がほんのり赤い。
その色が、夕陽のせいじゃないのがわかる。
柊先輩はつい、くすっと笑ってしまった。
「じゃあ、心のメモに書いとく」
「……メモ、破棄してください」
「無理。たぶん永久保存版」
律は返却された本を抱え直し、背を向けた。
けれど、その横顔の端――唇の端がほんの少し、上がっている。
(あ、笑ってる)
そんなことに気づいて、胸の奥がふわりと温かくなった。
外では夕陽が傾き、オレンジ色の光が本棚の影を長く伸ばしていく。
二人の間を通り抜けるその光が、どこかやさしくて。
柊は、本を抱えたまま、そっと息を吐いた。
(……なんか、こういうのが青春ってやつなんだろうな)
静かな図書室で、ページをめくる音がまた戻る。
けれどその音の向こう、確かに何かが生まれた気がした。