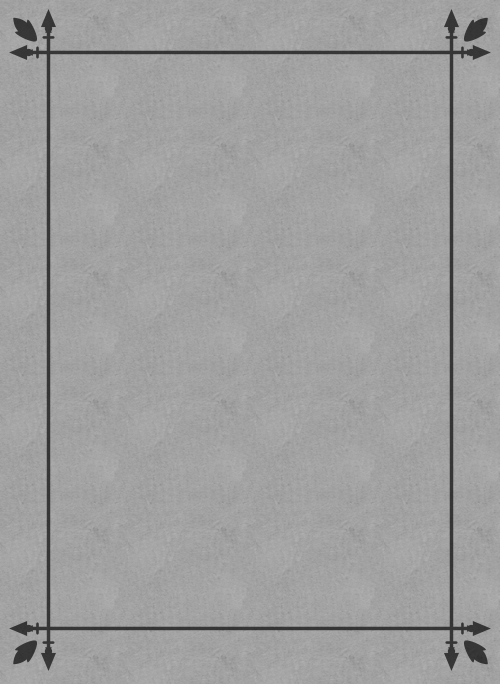柊は一瞬、言葉を失った。
胸の奥が熱くなって、鼓動が早くなる。
夕陽の光がカウンター越しに差し込み、埃の粒が金色に揺れていた。
(あの日――)
記憶の奥が、ふっと光に照らされる。
駅のホーム。春の冷たい風。
人混みの中、制服の袖を握りしめてしゃがみ込んでいた少年の姿。
顔色が悪く、額にうっすら汗を浮かべていた。
「大丈夫ですか?顔、真っ青ですよ」
差し出したハンカチ。
白地に青い刺繍。
少年は驚いたように顔を上げ、かすかに首を振った。
でも、その手は確かに震えていて、柊は迷わずその手にハンカチを手渡した。
(まさか、あれが――)
目の前の律と重なっていく。
「……もしかして。あの日、駅でハンカチを貸したのは――律だったのか?」
律は少しだけ驚いたように目を瞬かせ、それから小さく頷いた。
「そうです。ずっと返しそびれていて……すみませんでした」
柊は思わず、笑みをこぼした。
「いや、いいんだよ。それより――体調、大丈夫だった?あのとき、かなり辛そうだったから」
律は少しだけ口元を緩めて、頬を掻いた。
「大丈夫でしたよ。入学式も、ちゃんと間に合いましたし」
その瞬間、柊の胸の奥がじんわりと温かくなった。
(……そっか。よかった)
一瞬の静寂。
窓の外のカーテンが揺れ、空気がゆっくり流れる。
時計の針の音だけが、二人の間に響いていた。
律がふと目を伏せ、唇を結ぶ。
「……あの、ハンカチ、ありがとうございました」
その言葉に、柊は少し戸惑ったように瞬きをした。
「そんな、大げさな……。ただのハンカチだよ」
「いえ」
律が顔を上げる。まっすぐな瞳。
「それから――」
息を呑む。
律のまつ毛がわずかに震え、夕陽の光を反射してきらめいた。
「好きです」
一瞬、世界が止まったようだった。
その声は小さくて、震えていて、でも――真っすぐだった。
「ハンカチを渡してくださった時から、ずっと」
柊は息を飲んだ。
心臓の音が急に大きくなって、喉の奥まで響く。
(……律が、僕を?そんなはず――いや、でも)
思い返す。
何度も視線が合った瞬間。
借りた本を返すたびに、少しだけ見せた笑顔。
名前を呼んだとき、律がわずかに顔を赤くしたこと。
全部、今になって繋がっていく。
(そういえば……律と図書室で話すようになってから、僕、前よりもずっとこの場所が好きになった)
静かなページの音。
窓辺に落ちる光。
本を開くたびに感じる紙の匂い。
同じ空間に流れる、穏やかな時間。
その全部が――律といるからこそ、心地よかった。
「……うん」
柊は、少し笑って言った。
声がかすかに震えていたけれど、言葉は確かだった。
「僕も好きだよ。律と図書室で過ごす時間が――すごく、大切だと思ってる」
律の目がわずかに見開かれ、そしてふっと笑った。
その笑顔は、これまで見たどの表情よりも柔らかくて、優しかった。
「……ありがとうございます」
律の声が、少し掠れた。
その瞬間、柊の胸の奥で何かが静かにほどけていく。
柊は、律の微笑みに胸が熱くなったまま、ふと目を逸らした。
頬の奥がくすぐったいように熱い。
夕陽の光が窓を染め、二人の影を長く伸ばしている。
「……でも」
少し間を置いて、柊は苦笑を浮かべた。
「僕は、律みたいにイケメンじゃないし。ただの、本好きな地味な奴だよ」
律が瞬きをした。
「え?」
「ほら、律って、顔も整ってるし、女子にも人気あるでしょ?なんで、そんな僕なんかに――」
柊の言葉を遮るように、律が一歩近づいた。
その距離が、急に近い。
ほんの少し前まで、本棚の向こうにいたはずの彼が、今はすぐ目の前にいる。
「僕なんかじゃないです」
律の声は静かだった。
けれど、その低い声には不思議な熱が宿っていた。
「俺は――柊先輩だから、好きになったんです」
「……律」
「本が好きなとこも、丁寧に話を聞いてくれるとこも、時々おっとりしてるのに、真剣な時は誰よりもまっすぐで。そういうところ、全部、俺の好きな柊先輩です」
柊は視線を落とした。
耳まで熱くなっているのが、自分でもわかる。
(そんな真っすぐに言われたら……どうすればいいんだよ)
「……そんなこと言われたら、困る」
「困ります?」
律が小さく笑う。
その笑みは、いつもの無表情の奥から零れたように柔らかかった。
「う、うん……」
律の瞳がまっすぐ射抜くように柊を見た。
「先輩だから、惹かれたんです。俺、最初は近づけないって思ってた。でも話してるうちに、どんどん引き寄せられて。……もう止められなくなりました」
その言葉の一つ一つが、柊の胸に静かに沈んでいく。
喉の奥がきゅっと詰まって、何も言えなかった。
(……律の声、こんなに穏やかだったっけ)
心臓の音が、やけに大きく響く。
「律……そういうの、ずるいよ」
「ずるくても、言いたかったんです」
律は少し俯いて、照れ隠しのように息を吐いた。
けれど次の瞬間、また目を上げ、真っ直ぐに柊を見つめる。
「……俺、先輩のことになると、意地悪になります」
「意地悪?」
柊が顔を上げると、律がほんの少しだけ、いたずらっぽく口の端を上げた。
「だって、先輩が他の人と話してると、面白くないんですよ。あの笑顔、俺だけに見せてほしいって思ってしまう」
「そ、そんな……」
柊はあわてて目を逸らした。
「そ、それは……独占欲強すぎるでしょ……」
「はい。自覚してます」
律はあっさり言って、ほんの一歩、さらに近づいた。
距離が、息に触れるほど近い。
柊の背中がカウンターに軽くぶつかった。
(ちょ、ちょっと……近い……!近すぎるって……!)
「……律、ここ、図書室……」
「わかってます」
律の声は低く、けれど穏やかで。
その瞳は、まるで何かを確かめるように柊を見つめていた。
「でも、今は他に誰もいませんよ」
柊は思わず息を呑んだ。
視線を逸らしたいのに、逸らせない。
心臓の音が、耳の奥で鳴り響く。
律の顔が、ほんの少し近づいて――
ふと、その距離を保ったまま、小さく笑った。
「……先輩、そうやって顔赤くなるの、反則です」
「な、何それ……律のほうがずるい……」
「ずるいって言われても、嬉しいです」
「……もう」
柊は思わず唇を尖らせた。
「からかわないでよ……ほんとに」
「からかってません」
律は真顔で言った。
「本気です。……先輩のことになると、たぶん俺、手加減できなくなる」
「手加減って……図書室でそんなセリフ言わないでよ……」
「じゃあ、場所を変えたら言ってもいいですか?」
「り、律っ!」
柊の声が裏返った。
その反応に、律は少しだけ笑いを漏らす。
「冗談ですよ」
そう言いながらも、その目には本気の色が残っている。
柊は頬を押さえて、深呼吸をした。
「……ほんとに、意地悪」
「はい。先輩限定です」
「限定しなくていいから……」
小さく呟いた声は、ほとんど風に溶けてしまう。
けれど律には、ちゃんと届いていた。
ほんの少しだけ照れたように、彼の目元が緩んだ。
「……じゃあ、その意地悪、受け止めてくれるのは先輩だけ、ってことで」
「なにそれ、そういう言い方ずるい」
「おあいこです」
律がにやりと笑ったその瞬間、空気の緊張がほんの少しだけ、柔らかくほどけた。
窓の外では、沈みかけた夕陽が本棚の隙間から差し込み、二人の影を淡く重ねていく。
(……何、その顔。絶対、何か言う気だ)
柊は胸の奥で小さく息をついた。
律のああいう顔は、絶対に何か仕掛けてくる前触れだ。
そんな中、律がふと思い出したように、わざとらしく首を傾げた。
「そういえば、さっき」
「……え?」
「俺のこと、イケメンって言ってましたよね?」
その瞬間、柊の思考が止まった。
心臓が「ドクン」と音を立てて、空気が一瞬で熱を帯びる。
「は?……な、何言ってるの」
律はにっこり笑った。
その余裕たっぷりな笑顔が、逆に腹が立つくらいだ。
「ほら、律みたいにイケメンじゃないしって。あれ、ちゃんと聞きましたから」
「え、いや、それは――」
柊は思わず両手を振った。
「そ、そらみみじゃない?多分、空気の反響とかで……!」
律は唇の端を上げて、わざとらしく目を細めた。
「へぇ~、空気の反響でイケメンって聞こえるんですか?」
「だ、だから違うってば……!」
「違わないですよ。確かに言いました」
わざと低い声で、少しだけ近づく。
そのトーンが妙に艶っぽくて、柊の耳が一気に熱くなる。
「へ~……先輩、僕のこと、そんな目で見てたんですね~」
「なっ……そ、そんな目ってどんな目だよ!」
声が裏返った。最悪だ。
この状況、どう見ても律のペースだ。
「さぁ?」
律がわざとらしく肩をすくめる。
その仕草が妙に余裕たっぷりで、逆に焦りを誘う。
「優しくて、少し照れてて、でもちゃんと見てる――そんな目です」
「なっ……もう、やめてよ、そういう言い方!」
柊は顔を覆って俯いた。
耳まで真っ赤なのが、自分でもわかる。
(うわぁ……絶対、楽しんでる……)
「……本当に、意地悪すぎる」
律はその様子を見て、肩を揺らして小さく笑った。
「だから言ったじゃないですか。先輩限定で、俺、意地悪になるって」
「知らないよ、そんなの……」
柊の声は小さく震えていた。
「でも、先輩が照れるの、見てて飽きないんですよ」
「……っ!」
柊は思わず顔を上げて、律を睨むように見た。
けれど、そのまま視線がぶつかって――動けなくなった。
律の瞳が、静かに細められる。
その奥にある光が、あたたかくて、まっすぐで、
見つめられているだけで息が苦しくなる。
(……やばい。目、そらせない)
「……やっぱり、そういう目、してますよ。先輩」
「~~っ!知らない!本当に知らないから!」
柊は思わず声を上げて、くるりと背を向けた。
耳まで真っ赤。心臓は暴れるように鳴っている。
律はそんな背中を見て、小さく笑った。
その笑い声は、意地悪というよりもどこか嬉しそうだった。
「……図書室、閉館までまだ十分ありますけど?」
「……今日はもう帰る!」
柊は勢いよく言って、鞄を掴んだ。
顔を上げるのも恥ずかしくて、早足でドアへ向かう。
「先輩」
背中に、律の声が落ちてくる。
「また来週も来ますよね」
柊は立ち止まりかけて――小さく息を吐いた。
「……来る」
それだけ言って、ドアを押し開ける。
廊下に出た瞬間、頬の熱が一気に広がった。
(……もう、本当にずるい。あんな顔、反則だよ)
図書室の扉が静かに閉まり、中にはまだ、律の笑い声が余韻のように残っていた。
夕陽は完全に沈み、図書室には、二人が交わした言葉だけが、静かに、あたたかく、残り続けていた。
胸の奥が熱くなって、鼓動が早くなる。
夕陽の光がカウンター越しに差し込み、埃の粒が金色に揺れていた。
(あの日――)
記憶の奥が、ふっと光に照らされる。
駅のホーム。春の冷たい風。
人混みの中、制服の袖を握りしめてしゃがみ込んでいた少年の姿。
顔色が悪く、額にうっすら汗を浮かべていた。
「大丈夫ですか?顔、真っ青ですよ」
差し出したハンカチ。
白地に青い刺繍。
少年は驚いたように顔を上げ、かすかに首を振った。
でも、その手は確かに震えていて、柊は迷わずその手にハンカチを手渡した。
(まさか、あれが――)
目の前の律と重なっていく。
「……もしかして。あの日、駅でハンカチを貸したのは――律だったのか?」
律は少しだけ驚いたように目を瞬かせ、それから小さく頷いた。
「そうです。ずっと返しそびれていて……すみませんでした」
柊は思わず、笑みをこぼした。
「いや、いいんだよ。それより――体調、大丈夫だった?あのとき、かなり辛そうだったから」
律は少しだけ口元を緩めて、頬を掻いた。
「大丈夫でしたよ。入学式も、ちゃんと間に合いましたし」
その瞬間、柊の胸の奥がじんわりと温かくなった。
(……そっか。よかった)
一瞬の静寂。
窓の外のカーテンが揺れ、空気がゆっくり流れる。
時計の針の音だけが、二人の間に響いていた。
律がふと目を伏せ、唇を結ぶ。
「……あの、ハンカチ、ありがとうございました」
その言葉に、柊は少し戸惑ったように瞬きをした。
「そんな、大げさな……。ただのハンカチだよ」
「いえ」
律が顔を上げる。まっすぐな瞳。
「それから――」
息を呑む。
律のまつ毛がわずかに震え、夕陽の光を反射してきらめいた。
「好きです」
一瞬、世界が止まったようだった。
その声は小さくて、震えていて、でも――真っすぐだった。
「ハンカチを渡してくださった時から、ずっと」
柊は息を飲んだ。
心臓の音が急に大きくなって、喉の奥まで響く。
(……律が、僕を?そんなはず――いや、でも)
思い返す。
何度も視線が合った瞬間。
借りた本を返すたびに、少しだけ見せた笑顔。
名前を呼んだとき、律がわずかに顔を赤くしたこと。
全部、今になって繋がっていく。
(そういえば……律と図書室で話すようになってから、僕、前よりもずっとこの場所が好きになった)
静かなページの音。
窓辺に落ちる光。
本を開くたびに感じる紙の匂い。
同じ空間に流れる、穏やかな時間。
その全部が――律といるからこそ、心地よかった。
「……うん」
柊は、少し笑って言った。
声がかすかに震えていたけれど、言葉は確かだった。
「僕も好きだよ。律と図書室で過ごす時間が――すごく、大切だと思ってる」
律の目がわずかに見開かれ、そしてふっと笑った。
その笑顔は、これまで見たどの表情よりも柔らかくて、優しかった。
「……ありがとうございます」
律の声が、少し掠れた。
その瞬間、柊の胸の奥で何かが静かにほどけていく。
柊は、律の微笑みに胸が熱くなったまま、ふと目を逸らした。
頬の奥がくすぐったいように熱い。
夕陽の光が窓を染め、二人の影を長く伸ばしている。
「……でも」
少し間を置いて、柊は苦笑を浮かべた。
「僕は、律みたいにイケメンじゃないし。ただの、本好きな地味な奴だよ」
律が瞬きをした。
「え?」
「ほら、律って、顔も整ってるし、女子にも人気あるでしょ?なんで、そんな僕なんかに――」
柊の言葉を遮るように、律が一歩近づいた。
その距離が、急に近い。
ほんの少し前まで、本棚の向こうにいたはずの彼が、今はすぐ目の前にいる。
「僕なんかじゃないです」
律の声は静かだった。
けれど、その低い声には不思議な熱が宿っていた。
「俺は――柊先輩だから、好きになったんです」
「……律」
「本が好きなとこも、丁寧に話を聞いてくれるとこも、時々おっとりしてるのに、真剣な時は誰よりもまっすぐで。そういうところ、全部、俺の好きな柊先輩です」
柊は視線を落とした。
耳まで熱くなっているのが、自分でもわかる。
(そんな真っすぐに言われたら……どうすればいいんだよ)
「……そんなこと言われたら、困る」
「困ります?」
律が小さく笑う。
その笑みは、いつもの無表情の奥から零れたように柔らかかった。
「う、うん……」
律の瞳がまっすぐ射抜くように柊を見た。
「先輩だから、惹かれたんです。俺、最初は近づけないって思ってた。でも話してるうちに、どんどん引き寄せられて。……もう止められなくなりました」
その言葉の一つ一つが、柊の胸に静かに沈んでいく。
喉の奥がきゅっと詰まって、何も言えなかった。
(……律の声、こんなに穏やかだったっけ)
心臓の音が、やけに大きく響く。
「律……そういうの、ずるいよ」
「ずるくても、言いたかったんです」
律は少し俯いて、照れ隠しのように息を吐いた。
けれど次の瞬間、また目を上げ、真っ直ぐに柊を見つめる。
「……俺、先輩のことになると、意地悪になります」
「意地悪?」
柊が顔を上げると、律がほんの少しだけ、いたずらっぽく口の端を上げた。
「だって、先輩が他の人と話してると、面白くないんですよ。あの笑顔、俺だけに見せてほしいって思ってしまう」
「そ、そんな……」
柊はあわてて目を逸らした。
「そ、それは……独占欲強すぎるでしょ……」
「はい。自覚してます」
律はあっさり言って、ほんの一歩、さらに近づいた。
距離が、息に触れるほど近い。
柊の背中がカウンターに軽くぶつかった。
(ちょ、ちょっと……近い……!近すぎるって……!)
「……律、ここ、図書室……」
「わかってます」
律の声は低く、けれど穏やかで。
その瞳は、まるで何かを確かめるように柊を見つめていた。
「でも、今は他に誰もいませんよ」
柊は思わず息を呑んだ。
視線を逸らしたいのに、逸らせない。
心臓の音が、耳の奥で鳴り響く。
律の顔が、ほんの少し近づいて――
ふと、その距離を保ったまま、小さく笑った。
「……先輩、そうやって顔赤くなるの、反則です」
「な、何それ……律のほうがずるい……」
「ずるいって言われても、嬉しいです」
「……もう」
柊は思わず唇を尖らせた。
「からかわないでよ……ほんとに」
「からかってません」
律は真顔で言った。
「本気です。……先輩のことになると、たぶん俺、手加減できなくなる」
「手加減って……図書室でそんなセリフ言わないでよ……」
「じゃあ、場所を変えたら言ってもいいですか?」
「り、律っ!」
柊の声が裏返った。
その反応に、律は少しだけ笑いを漏らす。
「冗談ですよ」
そう言いながらも、その目には本気の色が残っている。
柊は頬を押さえて、深呼吸をした。
「……ほんとに、意地悪」
「はい。先輩限定です」
「限定しなくていいから……」
小さく呟いた声は、ほとんど風に溶けてしまう。
けれど律には、ちゃんと届いていた。
ほんの少しだけ照れたように、彼の目元が緩んだ。
「……じゃあ、その意地悪、受け止めてくれるのは先輩だけ、ってことで」
「なにそれ、そういう言い方ずるい」
「おあいこです」
律がにやりと笑ったその瞬間、空気の緊張がほんの少しだけ、柔らかくほどけた。
窓の外では、沈みかけた夕陽が本棚の隙間から差し込み、二人の影を淡く重ねていく。
(……何、その顔。絶対、何か言う気だ)
柊は胸の奥で小さく息をついた。
律のああいう顔は、絶対に何か仕掛けてくる前触れだ。
そんな中、律がふと思い出したように、わざとらしく首を傾げた。
「そういえば、さっき」
「……え?」
「俺のこと、イケメンって言ってましたよね?」
その瞬間、柊の思考が止まった。
心臓が「ドクン」と音を立てて、空気が一瞬で熱を帯びる。
「は?……な、何言ってるの」
律はにっこり笑った。
その余裕たっぷりな笑顔が、逆に腹が立つくらいだ。
「ほら、律みたいにイケメンじゃないしって。あれ、ちゃんと聞きましたから」
「え、いや、それは――」
柊は思わず両手を振った。
「そ、そらみみじゃない?多分、空気の反響とかで……!」
律は唇の端を上げて、わざとらしく目を細めた。
「へぇ~、空気の反響でイケメンって聞こえるんですか?」
「だ、だから違うってば……!」
「違わないですよ。確かに言いました」
わざと低い声で、少しだけ近づく。
そのトーンが妙に艶っぽくて、柊の耳が一気に熱くなる。
「へ~……先輩、僕のこと、そんな目で見てたんですね~」
「なっ……そ、そんな目ってどんな目だよ!」
声が裏返った。最悪だ。
この状況、どう見ても律のペースだ。
「さぁ?」
律がわざとらしく肩をすくめる。
その仕草が妙に余裕たっぷりで、逆に焦りを誘う。
「優しくて、少し照れてて、でもちゃんと見てる――そんな目です」
「なっ……もう、やめてよ、そういう言い方!」
柊は顔を覆って俯いた。
耳まで真っ赤なのが、自分でもわかる。
(うわぁ……絶対、楽しんでる……)
「……本当に、意地悪すぎる」
律はその様子を見て、肩を揺らして小さく笑った。
「だから言ったじゃないですか。先輩限定で、俺、意地悪になるって」
「知らないよ、そんなの……」
柊の声は小さく震えていた。
「でも、先輩が照れるの、見てて飽きないんですよ」
「……っ!」
柊は思わず顔を上げて、律を睨むように見た。
けれど、そのまま視線がぶつかって――動けなくなった。
律の瞳が、静かに細められる。
その奥にある光が、あたたかくて、まっすぐで、
見つめられているだけで息が苦しくなる。
(……やばい。目、そらせない)
「……やっぱり、そういう目、してますよ。先輩」
「~~っ!知らない!本当に知らないから!」
柊は思わず声を上げて、くるりと背を向けた。
耳まで真っ赤。心臓は暴れるように鳴っている。
律はそんな背中を見て、小さく笑った。
その笑い声は、意地悪というよりもどこか嬉しそうだった。
「……図書室、閉館までまだ十分ありますけど?」
「……今日はもう帰る!」
柊は勢いよく言って、鞄を掴んだ。
顔を上げるのも恥ずかしくて、早足でドアへ向かう。
「先輩」
背中に、律の声が落ちてくる。
「また来週も来ますよね」
柊は立ち止まりかけて――小さく息を吐いた。
「……来る」
それだけ言って、ドアを押し開ける。
廊下に出た瞬間、頬の熱が一気に広がった。
(……もう、本当にずるい。あんな顔、反則だよ)
図書室の扉が静かに閉まり、中にはまだ、律の笑い声が余韻のように残っていた。
夕陽は完全に沈み、図書室には、二人が交わした言葉だけが、静かに、あたたかく、残り続けていた。