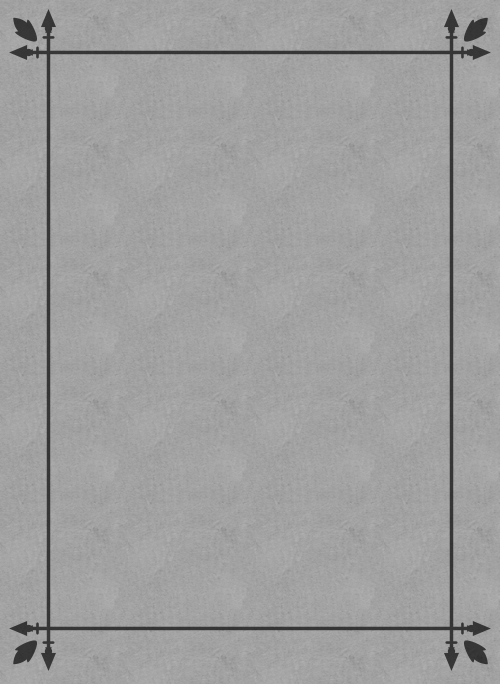放課後の図書室は、今日も静かだった。
ページをめくる音と、外の風が窓を揺らす音だけが、世界を形作っている。
木製の本棚の並ぶ空間は、午後の光に満たされていた。
薄くオレンジがかった光が、整然と並ぶ背表紙の上にやわらかく落ちている。
古い紙の匂いと、インクの残り香。
時計の針の音が、まるで呼吸のように一定のリズムで響く。
白川柊は、窓際の定位置に腰を下ろした。
鞄をそっと足元に置き、机の上で本を開く。
光の粒がページの上にこぼれ落ちる。
白い指先が、文字の流れを追うように静かに動いた。
指で文字をなぞる癖は、もう無意識だ。
幼い頃からの習慣。落ち着くための、ひとりだけの儀式。
(……静かだな)
その一言が、胸の中にゆっくりと広がっていく。
そう思うたびに、少しだけ安心する。
ここにいるときだけは、誰も自分に話しかけてこない。
笑顔を作る必要も、無理に輪に入る必要もない。
何かを求められることも、見られることもない。
(この時間が、一番好きだ)
窓の外では、グラウンドの向こうに夕陽が落ちかけている。
放課後の喧騒が遠くで薄まっていくのを感じながら、柊はページをめくった。
紙の擦れる音が、呼吸と重なって心地いい。
――そして、いつものように。
読み終えた本を胸に抱え、カウンターへと歩く。
木の床がきしむたび、図書室の空気が微かに揺れる。
「……お願いします」
淡々とした声で、貸出カウンターに本を差し出した。
声は小さいが、静まり返った空間ではそれだけで鮮明に響いた。
その瞬間。
バーコードを読み取る手が、わずかに止まった。
顔を上げた相手と、視線がかち合う。
整った顔立ち。
切れ長の目。
無造作な黒髪が、窓の光を受けて青みを帯びている。
静かなのに、どこか冷たさを含んだ雰囲気。
姿勢が良く、動作に無駄がない。
そして、低く落ち着いた声が耳に届く。
「返却期限、二週間後です」
「……はい」
それだけの会話。
たった一往復のやり取りなのに、なぜか心臓が一拍だけ跳ねた。
(……整ってるな、この人)
胸の中で、自然とそう思っていた。
制服の着こなしはきっちりしているのに、ネクタイの結び目だけがわずかに緩んでいる。
その無造作さが、彼を大人びて見せていた。
近くで見ると、睫毛が驚くほど長い。
息をするたびに、光がその輪郭を描くように揺れる。
整っているのに、どこか近寄りがたい。
まるで、触れたら壊れてしまうガラス細工のようだ。
――名前は、わからない。
柊の中には、ただ「図書委員の彼」という輪郭だけが残った。
その日以来、柊は彼の存在を頭の片隅に置くようになった。
次の週も、その次の週も。
金曜日の放課後になると、図書室のカウンターには必ず彼がいた。
(あの人、いつも金曜日にいるんだな……)
柊は小さく息を吐き、窓際の席に腰を下ろした。
開いた本のページを見つめながらも、意識のどこかはカウンターに向かっている。
彼――図書委員は、淡々とした手つきで本を整理していた。
姿勢を崩すこともなく、静かに、丁寧に。
表情は変わらず、まるで感情を閉じ込めたように無表情だった。
(いつも、あんな顔してる。……機嫌、悪いのかな)
目が合うと、すぐにそらされる。
それが一度や二度ではなく、毎回そうだった。
(別に、話したいとかじゃないけど。なんか……感じ悪い人だな)
そう思いながらも、なぜか視線はまた彼の方に向かってしまう。
気づけば、同じページを何度も読み返していた。
文字が目に入ってこない。
頭の中では、彼の手の動きばかりが鮮明に映っていた。
(なんで、気になるんだろ……)
自分でも理由がわからなかった。
ページをめくる手を止めて、窓の外を見る。
夕陽が沈みかけ、ガラス窓が橙色に染まっている。
外から吹く風がカーテンを揺らし、柊の髪を撫でた。
視線の先では、図書委員が静かに椅子から立ち上がっていた。
背筋を伸ばし、書架の間を歩いていく。
その歩き方は驚くほど静かで、靴の音ひとつ響かない。
(……やっぱり、大人っぽいな)
柊の胸の奥が、わずかに締めつけられた。
同じ制服のはずなのに、纏う空気がどこか違う。
時計の針が午後五時を過ぎたころ、図書室はすっかり人が少なくなっていた。
他の生徒たちは帰宅し、空気はさらに静まり返る。
まるで、時間そのものがゆっくりと溶けていくようだった。
「……」
柊は読みかけの本を閉じた。
椅子を引く音が、図書室に小さく響く。
その音に反応したように、カウンターの奥で彼が顔を上げた。
目が合う。
その瞬間、柊は息を呑んだ。
彼の目が、いつもよりわずかに柔らかく見えたからだ。
無表情の中に、ほんの一瞬だけ影が揺れた気がした。
(今……少し、笑った?)
けれど確信を持つ前に、彼はすぐに視線を戻した。
まるで何事もなかったように。
柊は胸の奥で小さく息を整え、カウンターへ向かった。
「これ、お願いします」
受け取る手が、かすかに触れそうになる。
その瞬間、互いの指先がわずかにかすめた。
一瞬だけ、時間が止まった気がした。
冷たいはずの空気が、妙に熱い。
ほんの一秒にも満たない接触なのに、指先が離れてからもしばらく痺れていた。
図書委員は黙ったまま、バーコードを通した。
その手元が、微かに震えているのを柊は見逃さなかった。
(……今、震えた?)
何かを言おうとして、言葉が出なかった。
胸の鼓動が速くなっている。
理由も、意味も、わからないまま。
「……ありがとうございます」
ようやくそれだけを口にして、本を受け取る。
廊下へ続く扉の前で、柊はふと立ち止まった。
振り返ると、カウンターの向こうで彼がこちらを見ていた。
無表情なのに、どこか寂しげな目。
(……なんで、見てるんだろ)
視線が絡んだ瞬間、心の奥で何かが小さく鳴った。
それが何の音なのか、柊にはわからなかった。
けれど、痛みではない。
ページの綴じ糸が、そっと結ばれるときの音に似ている――そんな気がした。
ドアの取っ手に触れる。
金属の冷たさが、現実へ引き戻す。
扉を開けると、廊下から夕暮れの光が流れ込んだ。
その光の中で、柊はもう一度だけ振り返った。
彼はまだ、そこにいた。
静かに、ただ見送るように。
(……また、来週も来よう)
そう思った自分に気づいた瞬間、胸の奥が少し熱くなった。
ドアが閉まる音が響く。
そして、心のどこかで何かが――静かに始まった気がした。
ページをめくる音と、外の風が窓を揺らす音だけが、世界を形作っている。
木製の本棚の並ぶ空間は、午後の光に満たされていた。
薄くオレンジがかった光が、整然と並ぶ背表紙の上にやわらかく落ちている。
古い紙の匂いと、インクの残り香。
時計の針の音が、まるで呼吸のように一定のリズムで響く。
白川柊は、窓際の定位置に腰を下ろした。
鞄をそっと足元に置き、机の上で本を開く。
光の粒がページの上にこぼれ落ちる。
白い指先が、文字の流れを追うように静かに動いた。
指で文字をなぞる癖は、もう無意識だ。
幼い頃からの習慣。落ち着くための、ひとりだけの儀式。
(……静かだな)
その一言が、胸の中にゆっくりと広がっていく。
そう思うたびに、少しだけ安心する。
ここにいるときだけは、誰も自分に話しかけてこない。
笑顔を作る必要も、無理に輪に入る必要もない。
何かを求められることも、見られることもない。
(この時間が、一番好きだ)
窓の外では、グラウンドの向こうに夕陽が落ちかけている。
放課後の喧騒が遠くで薄まっていくのを感じながら、柊はページをめくった。
紙の擦れる音が、呼吸と重なって心地いい。
――そして、いつものように。
読み終えた本を胸に抱え、カウンターへと歩く。
木の床がきしむたび、図書室の空気が微かに揺れる。
「……お願いします」
淡々とした声で、貸出カウンターに本を差し出した。
声は小さいが、静まり返った空間ではそれだけで鮮明に響いた。
その瞬間。
バーコードを読み取る手が、わずかに止まった。
顔を上げた相手と、視線がかち合う。
整った顔立ち。
切れ長の目。
無造作な黒髪が、窓の光を受けて青みを帯びている。
静かなのに、どこか冷たさを含んだ雰囲気。
姿勢が良く、動作に無駄がない。
そして、低く落ち着いた声が耳に届く。
「返却期限、二週間後です」
「……はい」
それだけの会話。
たった一往復のやり取りなのに、なぜか心臓が一拍だけ跳ねた。
(……整ってるな、この人)
胸の中で、自然とそう思っていた。
制服の着こなしはきっちりしているのに、ネクタイの結び目だけがわずかに緩んでいる。
その無造作さが、彼を大人びて見せていた。
近くで見ると、睫毛が驚くほど長い。
息をするたびに、光がその輪郭を描くように揺れる。
整っているのに、どこか近寄りがたい。
まるで、触れたら壊れてしまうガラス細工のようだ。
――名前は、わからない。
柊の中には、ただ「図書委員の彼」という輪郭だけが残った。
その日以来、柊は彼の存在を頭の片隅に置くようになった。
次の週も、その次の週も。
金曜日の放課後になると、図書室のカウンターには必ず彼がいた。
(あの人、いつも金曜日にいるんだな……)
柊は小さく息を吐き、窓際の席に腰を下ろした。
開いた本のページを見つめながらも、意識のどこかはカウンターに向かっている。
彼――図書委員は、淡々とした手つきで本を整理していた。
姿勢を崩すこともなく、静かに、丁寧に。
表情は変わらず、まるで感情を閉じ込めたように無表情だった。
(いつも、あんな顔してる。……機嫌、悪いのかな)
目が合うと、すぐにそらされる。
それが一度や二度ではなく、毎回そうだった。
(別に、話したいとかじゃないけど。なんか……感じ悪い人だな)
そう思いながらも、なぜか視線はまた彼の方に向かってしまう。
気づけば、同じページを何度も読み返していた。
文字が目に入ってこない。
頭の中では、彼の手の動きばかりが鮮明に映っていた。
(なんで、気になるんだろ……)
自分でも理由がわからなかった。
ページをめくる手を止めて、窓の外を見る。
夕陽が沈みかけ、ガラス窓が橙色に染まっている。
外から吹く風がカーテンを揺らし、柊の髪を撫でた。
視線の先では、図書委員が静かに椅子から立ち上がっていた。
背筋を伸ばし、書架の間を歩いていく。
その歩き方は驚くほど静かで、靴の音ひとつ響かない。
(……やっぱり、大人っぽいな)
柊の胸の奥が、わずかに締めつけられた。
同じ制服のはずなのに、纏う空気がどこか違う。
時計の針が午後五時を過ぎたころ、図書室はすっかり人が少なくなっていた。
他の生徒たちは帰宅し、空気はさらに静まり返る。
まるで、時間そのものがゆっくりと溶けていくようだった。
「……」
柊は読みかけの本を閉じた。
椅子を引く音が、図書室に小さく響く。
その音に反応したように、カウンターの奥で彼が顔を上げた。
目が合う。
その瞬間、柊は息を呑んだ。
彼の目が、いつもよりわずかに柔らかく見えたからだ。
無表情の中に、ほんの一瞬だけ影が揺れた気がした。
(今……少し、笑った?)
けれど確信を持つ前に、彼はすぐに視線を戻した。
まるで何事もなかったように。
柊は胸の奥で小さく息を整え、カウンターへ向かった。
「これ、お願いします」
受け取る手が、かすかに触れそうになる。
その瞬間、互いの指先がわずかにかすめた。
一瞬だけ、時間が止まった気がした。
冷たいはずの空気が、妙に熱い。
ほんの一秒にも満たない接触なのに、指先が離れてからもしばらく痺れていた。
図書委員は黙ったまま、バーコードを通した。
その手元が、微かに震えているのを柊は見逃さなかった。
(……今、震えた?)
何かを言おうとして、言葉が出なかった。
胸の鼓動が速くなっている。
理由も、意味も、わからないまま。
「……ありがとうございます」
ようやくそれだけを口にして、本を受け取る。
廊下へ続く扉の前で、柊はふと立ち止まった。
振り返ると、カウンターの向こうで彼がこちらを見ていた。
無表情なのに、どこか寂しげな目。
(……なんで、見てるんだろ)
視線が絡んだ瞬間、心の奥で何かが小さく鳴った。
それが何の音なのか、柊にはわからなかった。
けれど、痛みではない。
ページの綴じ糸が、そっと結ばれるときの音に似ている――そんな気がした。
ドアの取っ手に触れる。
金属の冷たさが、現実へ引き戻す。
扉を開けると、廊下から夕暮れの光が流れ込んだ。
その光の中で、柊はもう一度だけ振り返った。
彼はまだ、そこにいた。
静かに、ただ見送るように。
(……また、来週も来よう)
そう思った自分に気づいた瞬間、胸の奥が少し熱くなった。
ドアが閉まる音が響く。
そして、心のどこかで何かが――静かに始まった気がした。