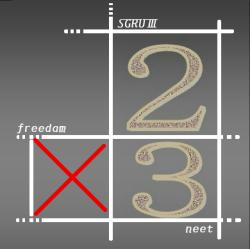朝を迎える。今日も照り付ける日差しに目を細め、私はゆっくりと体を起こす。私の背中に繋がれていた鎖は幾つかほどけ、以前ほどの起き難さはもうない。
ただ、それでも全てが全て変わる訳ではない。こころに染みついた汚れ、黒い斑点模様のそれらは未だに取りきれず、隙あらば元の状態に私を引き戻そうと蠢いている。
無垢で無力な少女に心を開けたところで、私は所詮その程度。或いは、もはやそれほど酷いものなのだと、またしても否定的な思想を捻り出している。
─何も知らないあの子に何がわかる。
私の思いは行き場のない風と同じ、吹き溜まりでしばらくホコリに塗れて後には影さえも残さず、何も伝えていないのにわかってもらえる訳もない。
自分が何者なのか、それが必要だったのかもしれない。
例えば少女の親戚なら、或いは少女が自分を知っている者の連れ子だったらと、そう言うわかりやすい繋がりの様なものが。
─そうではない
自問自答を繰り返す。私はあの子に何を求めていると言うのだろうか?ただ、何もせず庭に来ては無邪気に遊び、何もせずに帰ってしまう。私と話す事も一言二言で、それら全ては子供が放つ何の裏も綾もない無修飾の言葉だけ。
─誰とも関わりたくないんだ
徐々に熱を含み、そろそろあの少女も来るだろう頃、私はそんな退廃的な答えに辿り着いていた。それが答えとして一番納得できるものだった。
毎日何もせずに三食得られ、朝は涼風に慰められ、昼は蝉に激励されて、夜は満点の星空に抱かれて寝ている。それでも私は出来の悪い案山子の如く振舞って、あの老夫婦とさえ関わろうとしない。
そして、敵意など私に抱くはずもない普通の少女に対してすら私はそうなのだ。何がそうさせているのかは何となくわかっている。ただ、不都合なんだ。自分にとって、どう説明すれば良いのかはわからないが、例えるなら心の輪の内に誰も入ってきて欲しくない。
自己嫌悪がそうさせるのか、それまで人と接して来なかったからか…。
わかっている。私は単に、純粋な優しさに怯えているのだ。そんなものが存在すらしない世界が日常で、むしろ未知なそれは、今私が対峙しているそれこそが。
─こわい
気のない振りを装って、私は柄にもなく洗面台へと向かっていた。縁側にあのまま居れば、少女が来ることを心待ちにしている事を肯定してしまう。そんな自分を肯定できずに居るので、どうやら顔のひとつでも水に当てれば落ち着くだろうかと、直接そう思ったわけでもなかったのに、足は知らず内に洗面台に向かい、目はそこにある鏡に映ったふぬけをまざまざと映している。
この気持ちはあの老夫婦が毎日出すご飯に対してと大変似ている。きっと私はその優しさ自体がこわいのではない。理由もなく、意味もなく、明確な意図さえ見いだせないこれらの「単に純粋な優しさ。」と、言うものが突如途絶えたら・・・。
ありたいに言えば、店であればお金を支払う事で相殺されるはずで、世の中にあるほとんどがそうであるのに、それしか知らない自分には何もかもが不可解でしかない。
顔を何度も洗う。手も、肌着も水浸しにしてまで私はそれを続けている。それでも、手が濡れた感覚さえもう掴めない。耳の奥でドッドッドッと、行き場のない不安から必死で逃げ回っている心音だけしている。それを止めたくて、何度も水を顔に打ちつけているのに、顔の熱が下がる事さえなく、息はいつの間にか喘鳴音に近しい程荒れ狂ってしまった。
─少女は来るだろうか・・・・・また俺は同じ事を!どうして!?
もう、考えたくない。そして、関わりたくもない。だから、拒絶して何が悪いと言うのだろうか…?拒絶?もう、来なくなる?私は、それで良い。もう、こんなに悩まなくて済むのだから。何を悩んでいるんだ?何も知らない子供が、勝手に遊んで帰るだけ、そんな事に、私は何を悩んでいるんだ?
─来てほしいのに、来なくなる事
黙れ。そんな事思っていない。思っているかもしれない。どうすれば良いのか、どうしたら良いのか…。
─あの笑顔をまた見たい
違う。そうじゃない。私はきっと、あの少女と笑い合いたいだけだ。何度も何度も頭の中を照らす光の正体が、そうなのはわかりきっている。
─関わるのがこわい
どんなに振り切ろうとしても、心の片隅にある固く乾いた部分がジリジリと焼け、私を再びあの輝くオアシスへと手招く、水瓶を持って待っているのはあの少女に違いない。
ガサガサと小刻みに草を払う音、それだけでも耳は過敏に反応して、風のせいだと言い聞かせても耳は次に声を拾おうか、それとも足音を探ろうかと勝手に草野を駆け抜ける。
心はもはや、自分の理性ではどうしようもない。焦りを超えた怒りに近い感情が胸を縄で縛って、強引に外へと引きずっていく。
今は、洗面台の鏡の中でせめぎあっている自分同志を見ているしかないのだから。
─居た
目はその時、明らかに自分の支配から乖離していた。壁にある小さな格子窓の向こう側に見え隠れする白。その白の断片を勝手につなげ合わせて彼女の実像を見事に形成する。
途端にこころは違った音を狂奏的に全身へと放つ。ドクンドクンドクンと、足の先までそれが感じる事ができそうな程、恐れが現実になった事への衝撃と、あの少女がまた来ていると言う事を確認した事への歓喜。拒絶と渇望の絶頂にあるこの心音は、もはや表現できる言葉すらない。その時私の中にはその音だけしかなかった。
顔は既に硬直していただろう。その後の事は意識すら希薄だった様な、まるで自分が自分でない様な感覚しかない。芯のない足は勝手に庭へと向かい、いつもの縁側に私はいつの間にか立っていた。
─まぶしい
ひたすらに輝く夏の庭先。私が私を取り戻した時には、私を包む光は夏の頂点にあるそれだった。そして、目はあの子だけを捉えている。光が幻惑する夏の庭で、無邪気に遊び回るあの子の姿を。
─いつもと変わらない
自分が来た事を特段取り上げるでもなく、ましてやどうしていたのか等と言う問いかけすらもなく、少女は昨日と同じように、或いは私と初めて会ったあの日と変わらず、何も意味せず、意図せず、夏草の合間を駆け回っていた。
私はその少女の無関心さにどこかで傷ついたのかもしれない。それでも、逆に質問攻めにされたなら、余計にこの心は違う闇を生み出したかもしれないとさえ思った。
“いつも通り”が心地よかった。
一瞬走った痛みは、草で手を切った程度のもの。だからだろう、私はいつしか縁側に腰掛け、彼女をまた見ているだけの私になれたのだ。
ある意味、これが・・・
─今ある、小さな幸せ
私にとって確実に、そうだった。この、ただ暑く眩しい世界で、もぬけの殻になった自分が幸せになれる訳などない。
そう思っていたからこそ、この無垢で自由で無意味な・・・
─いつまでも、明日も
一方的な願いに私は身を委ねている。少女の事など何一つ考えてはいない願い。当然こころで留めて、喉にすら通すことはないだろう。どんなに願おうとも、時の流れがそれを赦しはしないと知っていても、これこそ「夢」なのだとわかっていても。
「明日、お散歩に連れてって。」
「え?」
ただ見ていた私に少女は突然そう切り出した。今まで「一緒に何かしよう。」と誘う事は絶対になかった彼女が、何を思ったのか…私は驚きをそのまま口に出し、硬直した。
「あ・・・・ああ。」
あまり何も考えずに返答していた。少女はそれを聞くと嬉しそうに去って行った。何が起きたのかわからず、答えの結果がどうなるのかもわからず、私はどんどん焦り出す自分が居るのだけ把握していた。
そこから先、どうにもならなかった。
恐らく、少女が誘ってきた瞬間にスイッチと言うスイッチは切れたのだろう。考えるよりも先に口は「ああ」と開いていたし、視線はずっと彼女を追ったまま動かせなかった。
気が付くと私は座敷に居て、暮れ頃に訪れる鈴虫の爽響に包まれ、更には知らぬ内に足は夕食を囲む老夫婦の元へと向かい、パクパクと口だけを再び動かせている。
味のない無感触な砂粒をゴロゴロとかきこんでいるかの様だ。
─明日・・・か
あの少女の何気ない言葉。それけを噛みしめている。
まずい訳ではない。手はどうして良いかわからないから目の前の白米を掬い、目は彩豊かな料理だけを捉えて、口は無造作に上下していく。
私は、私の意識はそこにはない。もはや、傍らでそれをただ見守っているだけの木偶。自分を呆然と見ているこの自分こそ、私から抜け出て行った理性と意識の正体だろう。
反芻しているのは、紛れもなくあの少女の声そのものでしかない。
─明日がこわい
今日を振り返る事はためらわないのに、どうして明日の事を思うと、こんなにも胸が苦しむのだろう。
少女と会うのが嫌なのだろうか?何がそうさせると言うのだろうか?酷く煩わしいとさえ思うのに、どこか待ち遠しく恐ろしい。
こわいものの正体だけは、どれだけ考えても探してもわからない。
寝る事などできずに布団の中で懊悩を何度も転がした。頭の向きと同じく、右にふってみては容量の良い答えで誤魔化し、左にふっては都合の良い応えで鎮静化を促す。
私は眠れない事などそう何度もなかった。それこそ仕事で悩んでどうのとか、学園生活を送っていた時代でさえだ。
─生きる事に、無関心だったから
放っておいても時間が何とかしてくれる。どうあがいても、興味がない事を悩みはしないだろう。明日に何があると言うのだ?
─少女に嫌われたらと思うとこわいのか?
わかっている。例えそんな事態に陥っても、別段問題はない。今更何かで傷ついたところで私は既に屍、痛みは無に帰すだろう。
─もし、少女が来なくなったら
私はその後も自問自答を何度も繰り返し、恐らくは明け方までそうしていただろう。結局首を捻るだけでは答えなど出はしないのだ。
体調不良を偽って誘いを無難に断ろうと言う容量の良い考えや、雨が降って中止になるなんて都合の良い考えだけでは、胸騒ぎも心の狂乱も鎮まりはしない。
やがて、懊悩の繰り返しが鬱積し、ちょうど心の穴と言う穴を埋め尽くした頃、精根尽き果てたのだろう、私は指を折って数えられる程度の瞬間眠りに堕ちていたのだった。
その浅い眠りがわずかにあった後。心の中で再び「あの子が来る」と、実に無感情で不愛想なナレーションに似たそれが頭の課で響いた。
慌てて飛び起きた私は足先を激しく柱の角にぶちつける。ガツンと、いやに鈍い音がしていたにも関わらず、意識はもはやそんなところにさえ行かなかった。
慌てて回転させた目には、まだ夜明けを待っている薄暗くどこか湿りがちの空があった。
「・・・・なんだ、まだ夜か。」
そう落胆に入り混じるほのかな安堵を感じたのも束の間、足先に火がついたかの様ひりつく痛みが走る。あまりの痛さに私は立っている事さえできず、その場でひたすら身もだえしていた。
「いたたたっ!」
足の親指、その内側の爪はわずかに変形し肉が切れている。当然赤い血が滲み出し、目立った汚れ等なかった畳に点々と赤いシミを作っていた。
「たっ・・・・・。」
正直に言えば、畳を汚してしまった罪悪感がその時はとても希薄だった。足の痛みはその次ぐらいにどうでも良く感じていた。むしろ、その痛みで一瞬でも少女の事を考えずにすんだと言う事が一番自分の中で大きな事として残っていた。
それから、私は少女が来るまでずっと縁側に居た。血の滲む足先を庭に抛り出すように向けて、割と気楽に、或いは無関心にも似た心境で待つことができた。
時が流れ、夜明けが連れてきたのは、朝の光だけでなく、得た事のない幸せに対しての不安に入り混じる希望。
「行こうか。」
私にも、言葉をこうやって口にする事が奇跡とかではなく、何の苦労も作為もなくできる。その言葉を、少女は無条件に受け入れる。
「うん!」
足の爪先に火の灯るような痛みがまだあったが、そこに蓋をするように靴を履く。思えば、ここに来て以来私は靴すら履く事もない日々だった。
いつもと変わらず、真っ白なワンピースを振り乱しながら少女はあちらこちらを行き来している。その中心点に、今日は私と言う存在がある。これまで規律を持たず、意味や意図などと言う概念から縛られる事のなかった少女が、今日だけは私を中心に動くのだ。
「どこに行きたい?」
私は少し高い位置から少女に話しかけていた。いや、冷静な自分と、大人としての自分を演じたいだけだと最初からわかっている。
今まで散々コケにされ、どんな場所に居ても誰かの足元で転がり続けていた自分のプライド。それが、こんな少女が相手ならばと、全く醜くて情けない。
目線を合わせたくて、ためらわず腰を落として頭まで下げるのだから。
「うーん、行きたいところ?」
あの少女と話している。幻影のように自分の目の前で揺れていたそれが、自分の言葉に反応し、その受け答えを目の前でしている。
彼女の連れて行きたい場所に一緒に行きたい。いや、行かせてあげたい。どんな場所にでも、この笑顔と一緒なら、もう何もいらないくらいに思える。
「んっと、じゃぁね!お山!」
少女はニコっと笑うと自分を先導するように駆けだす、人けのない山道をずんずん突き進んでいく。
─あぁ、せっかく格好良いところを見せようと思ったのに。
「お山って、このまま道を登っていくのか?」
林道に入っていくらか時間が経った。不思議なぐらいに静かな道に、小さな足音と自分のものだけが残響を繰り返す。あれだけ強烈に日が射しているにも関わらず、溢れかえる夏の音と一緒に熱さも段々と薄らいでいく。
「はぁ・・・はぁ・・・、しかし、元気だな。」
私と少女の距離は少しずつ離れている様な気がしていた。足で道を歩く事をすっかり放棄していた私と、そうではないだろう少女との差がこの距離に現れているのだろうか。
まして、山登りなど学生時代に嫌々していた私にとってこの峻嶮な隘路は、人の濁流を遡行する事より困難だと思った。それでも、嫌さは微塵も感じない。
「こっちだよ。」
そう言って少女は、青々とした葉をクスクスと揺らす桜の木々を横切って行く。一足先に高台の頂上に立ち、私に向けて大きく手まねきをして見せた。
「はいはい。」
ひどく疲れていたのに、じわじわと心地が良い。ひよって固くなった足をポンっと一叩きして、一歩一歩に力を込める。一歩体を前に出す度に、頭の方から視界が開けて行くのがわかる。
自分の目の前を覆うようにあった坂道の終点が一段一段、ゆっくりだが着実に下がって行く。
「着いた。」
私は少女のいる場所より少し手前の地点でそう言った。少女は私の声を聞いて、一瞬だけ振り向いた。
「見て!」
少女に言われるまま頭を上げると、押圧されていく青に、溶けだした茜が入り混じる光の水平線が空一面に続いていた。延々と広がる蒼く赤い空、眼下に広がる小さな影絵は色鮮やかな光彩をぽつりぽつりと放っている。
「あ・・・・。」
ただ息を飲んで、立ちすくんだ。死ねば見る事すらなかっただろう絶景は、どこまでも幻想的で、とてもそこにあるとは思えない。
「なんて、きれいなんだ。」
心からきれいだと思ったものなど、ここ数年なかった。
どんなに賛美された作品や光景でも、心からそれをきれいだとは思っていなかった。世に溢れる俗物なんて、どこまでも金や欲がつきまといながら、きれいごとだけの上辺だけだと思っていた。
彼女が見せたかったものだったからこそ、それこそがそう思えた根拠だと言う事も。
「ありがとう・・・。」
空の茜が刻々と深淵に消えて、紫がかっている。少女に向けて精いっぱいの感謝に返事はなく、さきまであった少女の姿もない。
「・・・・え?」
こんな高台から落ちたのか?そう思った瞬間心は再び氷に閉ざされた心地だった。
今の今まで自分の袖に触れそうな程近くに居た少女が、音も立てずに忽然と姿を消していた。
「おい!?どこだ!どこに行ったんだ!」
少女の姿だけを探す。草の中、木の間、岩壁の陰、行ったり来たりを繰り返すうちに日は完全に沈み、前も後ろも自分が何をしているのかさえわからなくなった。
あんなに小さな女の子だ。
自分がちゃんと家まで帰さないといけない。
ここは山の中だぞ?
何かあったらどうするんだ?
どうしてちゃんと手をつないでおかなかったんだ
崖から落ちたんじゃ・・・
どこに行ったんだ。
俺のせいだろ!
頼むから出て来てくれよ!
あの子の・・・笑ってなくても良いから。
どこだ
どこに行ったんだ!?