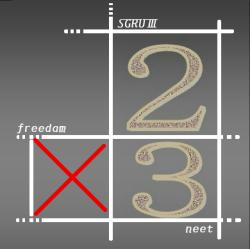遥か天辺に青く滲んだ筋雲が何も無い空に吸い込まれていく。あらゆる喧騒を抱いた全ての時間まで吸い込まれ、後に残ったのは光で白く溶けた青藍だけ。
林鐘の入り混じる風に蝉の鳴き声がふんわりと漂っているその庭先で、私は心音さえ盲失し、こちらを見続けているその少女以外何もない。そんな状態に滑落していた。
心の音が消え、その世界を夏の青が包んで、対峙した二人は理由もなく、いつまでもそうしている。とりとめもなく、少女がふと口を開き、こう話しかけた。
「からだがわるいの?」
心衰で彫深く黒ずんだ私の顔を見て、少女は病気だと思ったのだろうか。間違いとも言えない、私は自覚がある。心の難病を病んでいると言う事に。
少女は心配そうな顔をしている。小さく結んだ後ろ髪をふわふわと揺らしながら、言葉で語りかけず、純真な瞳で私に語りかけてくる。
─何を?
違う。少女は無垢だが、多くは知らない。世間を知らない。穢れを知らない。そんな彼女が放つ言葉に裏や作為などないのだ。少女の態度は心配が半分、好奇心のようなものが半分と言った感じで、我々が当たり前として使う建前のような、心配している風を装って相手に近づこうとか言う不純なものが一切感じられない。
だからこそ、この目の前にただある潔白が、今の私には感じた事のない痛烈な痛さすら伴うものとなっていて、言うなればこの少女の瞳は神の審判にすら思えた。その触れた事すらない白さに、私はすっかりすくみあがって、こころの震えが止まらない。
私は黙りこくっていた。こんなもの、今になくなる。子供の興味など移ろいやすく、しばらくすれば退屈して彼女は帰るだろう。
─こんなに汚く、ドブ川のヘドロより醜悪な俺と関わるべきではない。
だが、私がどんなに暗い表情をしようが、どんな否定的な感情を向けようが、或いは目線の先を彼女から遠ざけようが、彼女はまるで空を漂うカモメ雲の様に、あるがまま。
私との距離を心の境界線間際で保ったまま、空を仰いだり、庭の虫をちょこちょこ追いかけたり、時折駆け抜ける夏風にただ身を委ねたり、まるで掴みどころがない。
一見すれば無邪気そのものだが、私を無視しているわけではなく、捕まえた虫を私に見せて笑ったり、こっちに顔をくるりと向けたり、空を指さして、胸を突き通すような笑顔を見せる。物理的な距離はまるで縮まらず、むしろ広がる事さえあるのに、黒一色しかない私のこころのキャンパス上に彼女が居て、無邪気に遊んでいるかのよう。彼女の周囲だけは眩しく白く輝き、太陽には到底出せないそれに、黒い部分が黒でなくなっていく。
こんなに何もない自分が、未知の感情で溢れている。人と触れ合うのが、ただ恐いだけなのだと気付いてる。こんな何も知らない子供でさえ、いつ自分に敵意を向けてくるだろうか?と。ありもしない脅迫染みた誤解や思い込み、それを客観視できても、私には抗う事ができなくて、時間をいくら頭の頂から注いでも、足元には冷や汗の溜まった水溜りができるだけでしかない。
「またね、おだいじに!」
少女はふいにそう言うと、後腐れなくまっすぐ帰った。
私はとうとう彼女と一言も交わすことがなく、昼時を迎えた。いつもなら、どんなに愚堕っていても腹の片隅から聴き慣れた催促がある。今日に限っては、そんな気配すらない。
少女が居なくなった雑草だらけの夏の庭。私はそこに目を向けたまま、未だ心で続く想いの流動に身を任せていた。違う、溺れているんだ。
─あの子の笑顔から、抜け出せない。
この家の関係の子供だろうか?近所に住んでいるのだろうか?明日はまたここに来るだろうか?いくつだろうか?名前は──名前はなんて言うのだろうか・・・?
時は知らずうちに経ち、いつもの様に日々を終えようとしている。
あの老父も何も変わらず、一人分余計に作って食卓に置く。私がそれを食べようが食べまいが関係なく、朝も昼も夜も必ず、食事を終えると決まってどこかに消え、また食事時には姿を現す。それだけが私と老夫婦の接点で、それが今ある事実の全て。
私は、それをあの日は残して、今日は食べている。
何一つ、変化はない。
それでも、私の日常に一つ変化があった。あの少女が毎朝、日が昇ってしばらくしてから、体が昼時を告げる頃まで来る様になったと言う事だ。
小さな少女が来るだけの変化は、私にとって無視できないものだった。
─明日もあの子は来るだろうか?
私は何度彼女が訪れても、口を閉じたまま彼女をただ見ていた。それでも彼女は相変わらず楽しそうに庭を遊び回り、私を誘うように草花を摘んで来たり、目を合わせばニコリと微笑んで、私に言葉ではなく、それらでお話しをしているかの様だ。
いや、実際そこまで奥深くはないのかもしれない。ただ、私が何も言わなくても彼女はいつもの様に、私の目の前で自由気ままに遊んで見せて、何が楽しいのだろうか─私の心も少しずつそれが・・・たのしい。
「ほら!これ、あげるね!」
庭で摘み取ったのだろうか、名も知らない花を少女は私の膝元に置いた。彼女はにこりと笑い、もっと取って来るよと言って走り出す。
と、次の瞬間だった。
「きゃぁ!」
背丈ほどある草に絡まったのか、彼女はころんだ。私はつい身を乗り出していた。けがはしなかっただろうか?と、咄嗟にそう思ったのだろう。
「ころんじゃった。」
すぐに草の間から起き上がった少女の頭には雑草やら何やら色々とついていて、それが特に模様のようでなかったにも関わらず、何ともおかしくて、私は安堵したせいもあったのか、口元を自然と緩めてしまっていた。
それを見てか、少女も笑った。いつもの様に特に意味がなく、ただ面白がっているだけの無邪気で無垢なあの笑顔だ。
─あぁ、夏だな。
自分に対しての嫌悪感が嘘のように晴れて行く、全てなくしたクセに未だに社会と鎖で繋がれていたのだとようやく気付いた。
生きる意味がなくたって良い。ドス黒く汚れていたって構わない。そんな事と無関係に空はこんなにも青く、風は思うままに流れ、蝉は夏の音色を奏でるのだから。
生きる理由もないくせに生きて来れたのに、それが途端にできなくなる訳ではない。現に私は今生きているじゃないか、どんな状態にあろうと、私の心もまた同じように─
「また、明日もおいでよ。」
それが、私が初めて少女にかけた言葉だった。少女が突然ここを訪れる様になってから何日経ったかさえわからないが、この取るに足らない一言が私の初めての言葉になった。
「うん、また明日も遊ぼうね!」
いつもと同じ様に彼女は山林の脇道を潜り抜けて去って行く、私はしばらく目で余韻を味わっていた。私自身が発した言葉─いつからそれが社交辞令の様な、表身だけのものになっていたのかさえ思い出せない。
それぐらい長い間、私は言葉を失っていたのだろう。少女はずっと語りかけて来ていたのに、私が何も言えなかっただけなのだ。
そう、少女はずっと話しかけていたのだ。いつの間にか言葉を失い、音だけの情報を呟く無機物と化していたこの私の中に眠っていた私に対して・・・ずっと。
誰に言われるでもなく夜が訪れる。草原には秋を告げる虫達も集まり出して、夏の残り香とともに音を風に乗せる。色鮮やかで賑やかな夏のざわめきも、徐々に安らいでいく。
私は何事もなかったかの様に食卓に座り、ひたすら箸を進めた。
「おかわり、頂けますか?」
なぜ、そんな事を切り出したのか自分でもわからずにいた。だが、何も考えずに私はそう言っていたのだ。今までに感じた事のない空腹感が背中を押していたし、今こうして得られている満腹感・・・言い方が変かもしれないが、ようやく私の胃は食欲が満たされる感じを得られている。そして、それを貪欲に私は欲しているようだ。
「はい。」
老婆はその一言だけ、嫌な顔も不思議がる事さえもせず、私から椀を受け取って炊き立てのご飯を目一杯よそぐ、そして私にそれを無言で渡した。
「ありがとう。」
私はためらいなくそう言った。
その一言で、私はようやく満腹を得られた。
恐らくそれは数十年ぶりに得ただろう、至高の、本当の満腹感だったに違いない。