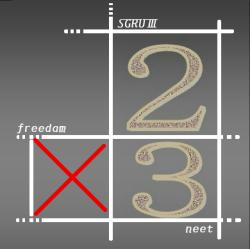屋灯りが消え、月明かりも途絶え、頬を沿う様に流れる藺草の薫がゆっくりと漂い、夏の日の出に煽られて立ち昇っているのは何か、知らぬ者の何か、鮮少な何か。
彼がそれを感じる頃には朝はとうに支度の時間を過ぎ、誰かのせわしく働きまわる音さえもう無い。
男は戻りつつある意識の中で、昨晩の事を整理しようとした。やはり、これと言う答えがなくて、瞼を開けるのさえ何か恐ろしい気がしていた。
─目を開けても昨日と同じ場所だったら・・・
恐る恐る目を開けていく。薄開きにした隙間からは、狙い打ったかの如く光が散入してきて、一瞬にして全てが真っ白になった。その眩しさで更に目は閉じこもり、男は顔を日光から背け、しばらく逃げた。
光から逃げて、彼は何に恐れているのかさえわからない自分がいる事に気づいた。あれだけ社会の闇夜に抱かれても平気だった自分が、何でもない平穏な目覚めに恐怖している。
─いつまでもこのままでいるのはバカらしい
客観視すれば露骨に不格好でしかない。彼は目を開け、全てを確かめた。思った通りに昨日の続きであり、昨晩の不可思議は幻でも何でもなかったのだと。
男はのそのそと起き上がり、右によろめきながら軒先の庭を眺めた。土手辺りにクワやカマに堆肥を詰め込んだビニール袋が幾つも見える。中には三又に先が別れた物や彼が見た事もない農機具もあった。
だが、男が探していたものは当然それらではない。
─あの、老夫婦は?
男は力の向きが不安定な感じの歩き方で部屋を出て、廊下を進みだした。夜宴の暗下では桑染に近かった廊下も、日の元では照り返しで白にさえ近い黄支子色を織りなしている。
部屋の全てには襖があり、わざわざ開けて見て回る事はしなかった。倫理的にどうとか気にしてではなく、男の頭には「昨晩の、あの食卓」に行こうと言う事以外にはなかったのだ。彼が老夫婦と時間を共有したのはそこだけだったから。
「すみません・・・。」
控え目がちに彼は身をせせらせながら、食卓に向かってそう言った。言葉は彼の吐息よりも手前で無に散り、どこにも届かない。大きな仕事で失敗して謝った時のそれより弱い。
彼はもう少し声を絞ろうかとも考えたが、その必要がない事にすぐに気付いた。
なぜなら、食卓にはまた食事が用意されており、作られて間もない事さえ見た目でわかる程だった。
そして、老夫婦はもう食べ終えたのだろう事と、自分の分だけが食卓に並べてあるのも彼には直感できた。食卓の上にある食事は、何ひとつ語らないが、その有り様全てが答えだった。
牡丹柄の座布団に座り、男は椀を手に取る。まだ、しっかりと温かい。彼はあまり考えもせずに食事を始めた。腹が減っていたのもそうだが、彼にはそうするしかない様な無力感があった。納得できよう答えなどないのだから、どうでもよかったのだ。
それでも、食べ終わりには「ごちそう様」と感謝の意を込めて呟き、自分の手で炊事場に汚れた食器を持って行った。
この料理はあの祖父母が用意したのは確かだし、何もできない自分にはこれを片付けるぐらいの事しかなかった。それで老夫婦に媚びようとしたわけではないし、昨晩は何もせずに残していった皿をその後誰がどうしたか考えると、今朝のこれも残したままにしておくのはさすがに胸が痛んだのだ。
悪く言えば、勝手に上がり込んで了解もなく、ひと部屋を寝床にし、朝は朝でこうして何食わぬ顔で食卓の上に置かれていた料理に手を付けている。自分の為に用意された訳でも無い誰かの為の食事を─
彼の無骨な手では椀の底に残っている味噌の粕を落とすのも至難なのか、手慣れぬ手つきで何度となく食器を手から滑らせ、ようやく全てを片付ける頃にはクタクタになっていた。それこそ炊事場にへたり込むぐらいに。
男は一息つきながら、当然の様な事を思った。これをあの老夫婦・・・仮にどちらか一方だけがしているとしても、毎日こなしているのだと。日々の労務はそれだけに尽きないはず、当然料理を作ったり、部屋を掃除したり色々とある。
汚れた椀を一つ洗うのさえこの手間だと思えば、自分がしている行いはどうなのだろうかと言う気がしてくる。いくら倫理観が大破してしまったとは言え、非礼千万の極みだ。
─だったら、何が俺にできると言うのだ?
乾天にそよぐ巻層雲に尋ねても返事はない。あるは全てを青に変えてしまう夏の空。そこに宛もなく漂う。彼が見ている景色は、今まで見た事もない程“無”だった。
居間へと戻り、鳴き連ねている蝉の声だけが静かに入り乱れている時間の中で、言葉も思いも閉ざし、日の暮れを迎えた。
あれほど忙しく、叱責に背中を蹴りまわされ、鈍いこの脚は否が応にも隘路を突き進むよう強いられていただけなのに、それらがなければこの自分は何もできないのだ。
自分にとっての生きる原動力、すなわち自らが自らを動かす原動力そのものがなかったのだ。
奇妙な怠無の沼底へと滑落して、彼が何もできなくなって数日の刻が流れた。彼を取り巻いている日常には相変わらず変化がなく、あの老夫婦と会えたのはあの日一日限りでしかなかった。彼が朝起きる頃には既に家にはおらず、できたばかりの朝食だけが待っていて、呆然と軒先を眺めて夕方を迎えた彼を今度は夕飯だけが彼を迎える。
ただ一つ変わった事と言えば、彼が無断で寝床にしていた部屋にはいつしか布団がきれいに敷かれ、彼の眠りを迎えるようになった事だ。
あの老夫婦は彼に一瞬会っても何も言わない。彼も何も話しかけない。言葉を交わせばこの奇妙な日常は音を立てて崩れる様な気さえしてくる。お互いに存在しない予防線を張り巡らせて、珍奇な均衡を保っているかの様な日常が続いた。
一陣の風が山林の合間をくすぐり、にわかに暗んできた空には積乱雲の類か、強く降り出した雨は一瞬にして庭を駆け抜け、水たまりを幾つも残して去って行った。
家に居た男は暮れ合いに訪れた通り雨の行く末を呆然と眺め、庭にある無数の小さな水鏡が金雀色に輝いている光景に心の端まで焼かれた心地がしてならなかった。
今夜の夕食はいつもよりも遅く、きっとあの時雨に濡れたであろう老夫婦を思うと、何となく辛い気持ちになった。自分に何ができると言う訳ではないが、それでも待っているだけしかできないのだろうかと、或いはこのままで良いのかと─
会わせる顔もないので、彼はもう寝ることにした。死よりも辛い事はこの世にないなどと何度か訊かされたが、何にも比べようがない程、男は今まさに辛い。枕に頭を沈めて眼を強く閉じても、どうしてだろうか─浮かぶのは食卓にいつもの様に並べられている皿に盛られた料理の数々。それもきっちり三人分、老父と老婆と・・・そして。思い浮かべたくもないのに、きっとそうだろうと思うだけで辛い。
心の存在を訪ねても、明確な答えなど誰も出せはしないだろう。たった今、強く締め付けられて苦しい部分。ここに、今まで捨てられていた自分の心があったのか─。
翌朝、目が腫れぼったい。まるで目ヤニで糊付けした様に瞼は貼り付き、ヒリヒリとした痛みを伴う。
枕を覆う白布が皺だらけになって、未だに湿り気を含んでいる。恐らく目は赤い色をしているだろう。辛さから逃げる一心で布団に潜り込み、全てを遮断しようとした。何度も自分を貶しながら、早く眠りに堕ちないかと祈りながら。それでも、時間が流れているのかさえ疑う程に眠りは訪れず、去来する辛さで満身創痍になり、精根尽きて今に至るのだから、目の赤さは鏡に映さずとも容易に想像できる。
目覚めても尚、心の辛さは酷く、剥き出しの地面をカタカタと這いずりまわるクマ蝉と似た痛々しさで、晴れやかな晴天とは相容れぬものだった。
より一層けだるく、彼は悪霊に憑りつかれてしまった人の顔をしている。男はその顔のまま突き動かされた様に寝床を這い出て、庭に裸足のまま出た。足元をくすぐる砂利の一つ一つが気を僅かだが紛らわせ、体の全てを射抜く日差しは赤目にしみいる。
束の間の笹凪、アカザの袂で青月の雫を溶かした菖蒲色のヒルガオは微笑みながら少し首を傾げ、さわさわとゆかしく揺れている。
「ねぇ、どうしたの?」
男は突然聞こえた人の声に動揺し、腰から抜けそうになった。
咄嗟に全神経をヒリつかせながら首を捻った。声のした先には、淡桜色の服に身を包んだ小さな女の子がいた。
─誰だ・・・?
彼は目線を下げ、まじまじと彼女の顔を見た。彼女は屈託のない笑顔で、目を見つめ返している。淀みを知らない、無垢そのものの瞳は、赤目をして疲れ果てた男がしっかりと映し出されている。
「うさぎさん?目が真っ赤。」
彼女は楽しそうだった。たわやかにはにかんで、肩まで伸びた黒髪を草風に遊ばせながら、彼の数歩先で立ち揺れている。
彼の鼓動は未だに速く強く胸を叩き、一向に落ち着かない。男の困惑は坂を下り出した鉄球の如く、鈍い音をゴトンゴトンと響かせながら勢いばかりが増していく。
彼は何一つ言葉を絞り出せず、心音に支配された。その様子を小さな女の子が黙って見ている。彼女は全てを受け入れそうな、本当に無抵抗な、無邪気そのもの。
笑顔と言っても、力を込めず、忌憚などもなく、男が戸惑いの渦から抜け出せるのを静かに待っている様な、ただそこにある・・・それだけの笑顔だった。