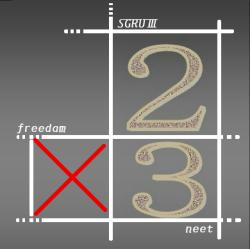男は途方に暮れた。それでも時間は過ぎる。惰眠の海に溺没して出て来られない。それでも食糧要求の合図だけは何度も鳴り響く。仕方なくそれに応じていけば、見た目は何とも無いかの様で、仕事などあってもなくてもこの男に変化など存在はしないのだ。
毎日の様に同じ服に身を包んで、行き飽きた最寄駅へと吸い込まれる。それすらなくなった今、日が暮れ、朝が出迎え、夜月が闇幕の波間で弧を描いていく。そんな時だけが過ぎていく日常。
それは、何よりも死に近く、何よりも死から遠かった。
─どうしようか。
いざ、身を縛る鎖がなくなると退屈と言う感覚すら越えて、あれほど騒々しく煩かった日々が夢だったのではないかと思えるほど空虚だ。
生きる意味などないのに、代わる代わる襲ってくる食欲と睡魔。それに突き動かされて気づけばその日を終えている。
─金さえあれば生きてしまうのか…。
やりたい事を何気なく捻り出しても、結局彼は家から出る事もなく、何もする気にならない状態を抜け出す気もなく、救いさえ求める気がない。やりたくない事だけが増えて行く。何日もそう言う日が続く、男は酒も飲めるし博打も覚えがあったが何一つ手を付ける事無く、抜け殻そのものと変わらぬ日々を過ごした。
男にとって仕事は生甲斐ではなかったはずが、結果的には大差がなかったようだ。
「いつまで、生きなきゃいけないんだ…?」
また味気ない量産品の弁当と向き合いながら、彼は嘆いた。これまでの自分がどういうものだったかを考えると、目の前の弁当よりも酷かったかもしれないと思う程に。
彼がこうして溜息を漏らしていたのも最初のうちだけだった。やがては緩慢に流れるだけの時間に身を任せ、考える事も後悔する事もなくなった。
生きながらにして、死を得たのである。
「………。」
誰かと会話することもなく、食事はある時買いだめしたインスタントラーメンやレトルト食品で何とかした。着替えをする事もなくなり、家から出る事さえ稀になり、毎日何もせずに無為徒食を続けるようになりだした。
この彼を諭す人も救い出す人も特になく、怒号の様に鳴り響いていた携帯電話はどこに行ったのかさえもうわかりはしない。
ひと月、ふた月と時は流れた。世間では大きな災害問題に苦悩したり、新進気鋭のアイドルを追いかけ回したり、一向に良くならない政治を餌にしたりと変わり映えしない。
TVすらつけなくなった彼にしてみれば、今まで自分もそれらに踊らされていたはずなのに、今となっては流行り廃りどころか自国がどうなっているのかさえわからない。
部屋にゴミが溢れ、彼の寝床以外は足の踏み場もなくなった頃、ようやく蝉の鳴き声が彼の部屋にも届き始める。
ジワジワと上がる室温。ひたひたと漂う酸っぱい匂いは猛烈な悪臭へと変わり出す。それでも男は部屋からほとんど出ず、何もせず、寝て起きて食って寝るを繰り返した。
どんなに太陽が高く昇り、ひりつくほど熱い日差しを向けても、男は目を細める事すらなく、無気力に、無抵抗でその光に炙られた。
いつしか殺す事さえしなくなった不快な害虫が部屋の中を自由に飛び交いだし、そんな荒んだ光景を見るのにも慣れ、男はいつもの様にお湯を沸かそうと電気ポットに水を汲んでいた。ちょうど即席ラーメン一つ分できる程度の量だけ淹れて、蛇口を閉める。
カタン──ふと、玄関先でそんな物音がした。ここしばらく沙汰もないそこから、確実に何かが、郵便受けから入ってきた様な…少し硬く乾いた音だった。
男は何となしに目を向け、誰か来たのだろうかと思った。思ったその次には人が訪ねてくる訳ないと自分に言い聞かせた。
次に水光熱費あたりの領収書の類だろうと思ったが、音の感じからそうではなく、何か形ある物だろう事は確かだと言う感じだった。
しばらく男は物珍しいのもあって、玄関を凝視していた。既にその玄関もゴミが散乱していて、毎日の様に履いていたビジネスシューズさえ数多のゴミに踏まれている。ゴミかゴミでない物かの境界線すらそこにはない。
─何だったのだろうか。ただの気のせいだったのだろうか
随分と長い間彼は何かに興味を抱くことすらなかった。のに、先ほどの物音が何だったのかと僅かながら気にしている。
男は身を逸らして覗き見た。読む気もなく買った雑誌や、どうやってそこまで転がっていったのかわからない空き缶や割り箸に紛れ、何やら真新しい封筒が見えた。
あまりに純白で華奢な封筒。彼は目が眩む様な錯覚がしていた。恐らく、あまりに廃頽的なこの世界の中では、その封筒の白さが恐ろしいほど白く思えたからだろう。
彼はゴミの山を蹴り分け、玄関へ向かった。薄く、すぐにでも破れてしまいそうなそれを傷つけぬ様指でつまみあげる。
つまみ上げた封筒は見れば見るほど、目に痛いぐらい白い。
「誰からだ…?」
まじまじと男は封筒を部屋の明かりにかざしながら見た。表には宛名も何も書かれていない。手首を捻って、ゆっくりと裏返す。きっちりと丁寧にのりづけされているが、文字の類は一切ない。
本当に無地で真っ白な封筒。中に何か入っていそうだが、重さはほとんどない。指の腹で探ると、少し硬い厚紙の様な物だろうか─何枚か同じ物が入っていそうだった。
「何か入っているな。」
差出人すらわからない封筒を男は開けようと思った。何も考えてはいない。彼はその中の物が少し気になっただけで、それ以上の何もない。
せっかくの綺麗な封筒を男は指で破いた。勿論、中身を避けるようにして。輝くこと等もうなかっただろう彼の瞳はほんのわずかに光りながら、封筒の中を泳ぎ回った。
─何か入っている
封筒を開け放っても尚その中の物が何かわからない。男は封筒を逆さにして、左手の掌で受け皿を作ってから振ってみた。
カサッカサッカサ…ぽとぽとぽと、と。中からカードの様な何かが落ちてきた。男にはすぐにそれが何かわかった。何しろ見覚えがよくある物だったから。
「新幹線の乗車券…?」
まさにその通りだった。だが、男はなぜそんな物が封筒に入っているのか疑問で仕方がない。行先を見ると、東京から仙台行のキップだった。
「仙台…?」
何か心当たりはないか一通り記憶を辿る。だが、訳が分からない。男は少しモヤモヤして苛立った。冷静に考えれば考えるほど訳がわからなかった。
「なんなんだこれは…?」
電気ポットは既に沸騰を告げ終わっている。白濁した蒸気をモクモクと部屋の片隅で上げている。それでも男は新幹線の乗車券から目が離せなかった。
有効期間は今日を含め3日間。席は自由席。東京から仙台までで、帰りの分…つまり仙台から東京までの乗車券は入っていない。いわゆる片道キップだ。
考えてもわかりそうにない。知人も友人も仙台には居ないし、既に自分を友としてくれる様な人さえもう居ない。親族とて関係が断絶している。
気になりだすと余計に気になってくる。これが何なのか、何故仙台なのか、そもそも誰がこれを入れたのか…男は居ても立ってもいられず、玄関の扉を思いっきり開け放つ。
ガチャン!
「…」
当然、誰も居なかった。左右に広がる通路を何度見ても、人が居た様な形跡さえ見つけることができない。
無限に広がる回廊の果てには、黒ずんだ緑葉がガサガサと揺れている。男はカチカチと明滅を繰り返している蛍光灯をしばらく見上げ、扉をバタンッと固く閉めた。
改めて何か手がかりの様な物がないものかと封筒を顔の前まで持ち上げ、くまなく隅の隅まで黒目を這わせた。
やはり何もない。どうにも手がかりはこの新幹線の切符以外にはなさそうだ。男は当然気が乗らなかった。得体の知れない相手が何の目的かも伝えず、決して安くはない新幹線の乗車券を放り込んできたのだから、気味が悪いと言うのが正直なところだった。
その気味悪さから、男はしばらくそれを捨てられずに居た。翌日も、その次の日も、まるで何かしようものならバチでも当たるとでも思っているのか、踏まないように、なくさぬように保管していた。
─とうとう今日で有効期限が…
今から出ても間に合いそうにもなく、男はその気味が悪い封筒ごと新幹線の乗車券をゴミ袋に入れ、部屋の隅へと投げた。
言いようのない妙な罪悪感。ただ、それだけが彼を駆け巡る。なぜかはわからない。それでも、とてもいけない事をした気分で、実に不愉快な気分に彼は襲われていた。
「忘れよう。」
何もなかったんだ。そう彼は自分に言い聞かせた。が、次の瞬間─カタン…再び玄関で聞き覚えのある音が聞こえたのだ。咄嗟に脳裏を過ったのはあの白い封筒。
─まさか
そのまさかだった。彼が目をやると、真っ白で綺麗な封筒が再び落ちていたのだ。中身は…中身も、もしそうなら─
男は少し違う意味での恐怖すら感じていた。気味が悪い…。おののきながら、怒り狂う猟犬を撫でる訳でもないのに、それに近い表情を彼はしていた。
封筒をそっと指で拾い上げると、厚みや重さが全く同じだとわかった。いや、実際には細かい点で違いはあるのかもしれない。しかし、男は手にした瞬間それが疑いもなくこの前に届いた封筒と同じものだと確信した。
表を見て、裏返す。予想通り差出人の名前も何もなく、中には厚紙の様な四角い物が数枚入っている。
男はしばらく開けるのをためらった。なぜなら、一度で済めば「単なる偶然」で片付くはずの話がそうではなくなるからだ。
「誰だ!?」
男は思いっきり玄関の扉を開け、鬼の形相で飛び出した。だが、まるでその怒りを全て飲み込んでしまいそうな静かな闇だけが彼を出迎える。人の居た痕跡はやはりなく、男は夢でも見ているのだろうかとさえ思った。
彼はしばらく立ちすくんだ。素足の裏をジャリジャリとうごめくアスファルトの粒を踏みしめながら、呆然と明後日の方向を眺めていた。
まだ近くに居るはず。男はそのまま酷い格好で辺りをうろついた。だが、遠くでまばらに見える人を見つけても声をかけるまでには至らない。確証はないし、どう考えても話が通じそうにないのは明白だったからだ。男は早々に諦め、部屋へと帰った。
「誰がこんな物を…?」
男は封筒をピリピリと控えめに破いた。口をポッカリ開けた封筒をそっとゆすると、中から新幹線の乗車券が出てきた。
「やはり仙台行か。」
ここまで来ると、一体何なのか突き止めたくなってくる。一度ならず二度までも、無言で届く謎の封筒。誰が入れたのか、どうして仙台なのか。
本来なら家から出る事さえ嫌になっていた彼だが、気味悪さに背中を押されるように支度を始めた。簡単かつ身軽に、必要な物以外は持たず、彼は部屋を出たのだった。
─駅は、今日も雨か
約束していた訳でもないのに、駅構内は今日も雨に濡れている。しかし、墨汁で染め固めた様な黒雲が空を覆っている割に雨脚は細く、喩えるなら他人の為にすすり泣く女の涙に近しいもので、わざと滴を捻り出したような具合だった。
男は静かにその曇天を眺め、左右を行きかう人波から一人取り残された気分を味わっていた。あれだけもがいても逃れられなかった人の濁流に、今は混ざろうとしても弾き返されてしまうような心地さえする。
─俺はあんな風だったのか
ただ前へと機械的に目を向け、傘を片手に急ぎ歩く人達。顔はどれも固く、緩む余地など一切見せない。それが本当に人なのか、中身はあるのだろうかと、そう思えてしまう程に無機質だ。
早送りされる映像の様な光景が、自分だけ避けて止まることなく流れ、けたたましい喧騒の中へと消えて行く。
かつては煩いとさえ思えた数々の構内アナウンスも、今ではとても遠くに聞こえる。
─あれは人なのか
男はポケットに潜ませた乗車券に汗を滲ませると、発車待ちをしている仙台行の新幹線へと乗り込んだ。席は自由席。平日の昼過ぎとあって、車内は閑散としている。
男は適当に奥まった窓際の席へと腰かけ、しばらく車窓から駅構内の様子を眺めていた。思い起こすのは働いていた頃の事。東奔西走の日々の渦中にいた自分が、今でもそこに居そうな、そんな気分に浸っていた。
誰の目も輝きすらしない。かつての自分同様、どこを見ているのかさえわからない。流れる人の波に巻き込まれ、全てをそこに委ねている。今の自分と、彼らと、どう大差があるのだろうか─?
シートに背を預け、手放した日常の切れ端にも別れを告げた。それを聞き遂げたかのように、新幹線はゆっくりと動き出す。
仕事以外で新幹線に乗ることなどほとんどなかったせいか、どこか落ち着かない感覚すら男にはあった。その荒削りな気分を何とかしようと、反対側の席へと目を向ける。
座っていたのは母子。母親は若く、子供は幼い男の子だ。神経質な強張った表情でその親子は向き合っていて、旅行気分で楽しそうという感じに見えない。
脈略無く、その母親はかなりの力で子供の頬を平手打ちした。それを見ていた男は、あまりに突然の事に少し胸がざわついた。
─虐待だろうか?
しかし、終始見ていた訳ではない。たまたま目を向けて、何らかのくだりがその母子にはあり、その全容がわからないのだから何とも言いようがない。
だから、関わろうとはしなかった。むしろ、子に手を上げる親の方が良いだろうとまで思っていた。叱りもせず、温室でゆっくり育てられても社会では生きてはいけないと─
その子供は泣く事なく、親子は煮え切らない様なモヤモヤした表情でずっと座っていた。
─どうしたんだろう…俺は
普段は他の客など見る事さえしなかったのに、男はいつもと違う自分に疑問ばかり湧き上がっていた。ずっと外の世界に出てなかったせいもあるかもしれない。妙な気分で身悶えしてくる。刺激のない生活を送り過ぎて、わずかな出来事すら刺激になる。
目を向けなかった事に目を向け出すと、例えそれが見飽きた日常でも違った部分が見えてくるのだろうか。
─誰もが誰かに必要とされたい。
現社会において生きる価値や存在する理由は益々得難く、どう求めれば良いのかさえわからない。だから、誰かに求められたり、誰かに必要とされたり、誰かと繋がる事で自分を無理くりにでも得ようとしているのではないかと、彼はそう思った。
新幹線の最高速度はおよそ時速300km。だが、実体感はとても希薄であり、むしろ日常的な速度の方がリアルで、人の感覚を越えたその速度に身を委ねていると、もはや移動しているのかどうかさえわからなくなる。
男はその実体のない歪な現象の中で、他人が奏でる日常を耽溺していた。それは、時速300kmと言う非日常よりも、どこにでも溢れている時速数十kmにも満たない目の前の出来事の方が身近で、より体感できるものだったから。
大きな事故を目の当たりにした時や、一目惚れした瞬間等は「非日常」であり、人に大きな衝撃を与える。
だが、この時彼が身を委ねた「非日常」は、彼にとってそうではなく。むしろ、溢れる目の前の「日常」こそが「非日常」だったのだろう。
この男は別にそう言った光景を愛でた訳ではない。ただ、かけ離れていた「普通」に身を揺すぶられ、毛を逆立てただけだった。或いは、人の日常に憐みさえ抱いた。
─どんな風に生きても、いずれ死ぬと言うのに
楽しそうに談笑している大学生ぐらいの女の子達が前の座席にやってきた。男の荒んだ目線には目もくれず、お菓子やジュースを手早く広げ、話の肴に変えていく。
自分が大学生の頃どうだったかを思い出そうとしたが、惨めな気分になるだけだろうと決めつけて、索漠とした記憶に蓋をした。
雲の切れ間から差す太陽の光は弱く、既に日暮れ時を過ぎたそれは悲しげで、泣き始めた蝉の羽を打ち続ける雨もようやく止みそうだと言うのに、まるで助けすら求めているかのようで、一日の終わりをただ儚く告げながら消えて行く。
夜の訪れ、駅弁に舌鼓を打つ人、それを眺めている男。何も口にせず、ポケットに忍ばせた乗車券に何度も汗を吸わせ、未だ湿りを含む車内の空気を何度も深く吸い込む。
駅ごとに人は入れ替わり、その度にそれぞれの日常を映し出す。もぬけの殻と化した男は何度もそれを目に映す。それらが何を意味しなくとも、人としての全てを失ったような彼にしてみれば、それらは毒に近い刺激物だったのかもしれない。
だが、例え毒ですら空の器なら拒む間もなく、ひたひたと注がれていくのだ。ありふれた日常と言う名の毒が。
「まもなく仙台、仙台です。」
彼はおもむろに立ち上がり、出口の前でドアが開くのを待った。虚ろな瞳に薄墨色の影が映り込むと、間もなくトビラはゆっくり開いた。
降り立った仙台駅構内で、男はなぜここへ来たのだろうかと思っていた。衝動的に訪れた訳だから、それに対しての答えは見当たりそうにもない。照明で青白く照らされている駅構内のどこを探しても、男の疑問が片付くことはないのだ。
あてもなく、何も考えず、男は足に身を任せた。閾値で横切って行く光景、一際強い光を放つ売店すら通過し、階段を黙々と下る。
駅構外に出ると、予想通りと言うか、来たことがある訳ではないが、仙台の街並みに男はなぜか安堵していた。途方もない距離を移動したにもかかわらず、日本独特の…見慣れた様なビルの立ち並び方だけでも今の彼にとっては安らぎの種になった。
眼下に見える大きな交差点をしばし眺めながら、彼は呼吸する事だけに溺頭した。そうして一息ついた後、ようやく歩き出す。無計画に突き進み、錯雑に人で賑わうバスのロータリーをすり抜け、四方八方に伸びる道路を目の前にして足は途端にすくむ。
─なにがあると言うんだ?
ほの闇に霞む商店街の吊るし灯り、車道をゆっくりと往来するヘッドライトに目を細めながら、男は無に投げ出された気分に立ち尽くす。頭上の歩道橋を往来しているたくさんの人を何度も見上げ、立錐しているビルの隙間から吹く風に何度も煽られ、地をうねる様に響く車走音が耳道を何度も蹂躙していく。
─俺は何をしにここへ・・・?
男がそう思って足を上げるより早く、彼の眼前に颯爽と一台の黒塗りタクシーが音を立てて急停車した。驚く間も与えず、そのタクシーはハザードランプを点灯させ、後部座席の扉をゆっくり開け放つ。
─なんだ?いったい…
彼は顔をしかめてタクシーへと近づいた。手を挙げていた訳ではないのに、一方的に停車したタクシーは「予約」と表示してあった。男は思った。このタクシーを手配した人物と仙台行のキップを投函した人物は同一人物なのではないか?と。
彼は少し乗ろうかどうか迷い、怪しげな雰囲気としばし対峙していた。タクシーは自分の前から一向に動く気配がない。交通の邪魔になろうが、後続車にクラクションを叩かれようが、相手にすらしていない様な感じだ。
男は迷っていても仕方ないと思ってはいた。だから、腑に落ちない事が胃の中を満たし尽くしていてもそのタクシーに乗らざるを得なかった。足を上げ、手を伸ばし、伽藍堂にも関わらず鈍重な体をゆっくりと車内へ滑り込ませ、彼はいよいよ真っ白なシートの座席へ腰を落ち着かせた。
座るや否や、扉は自動的に閉まり、タクシーはゆるゆると動き出す。男は運転手の顔さえ見る間も与えられず、突然流れ始めた車窓の景色に目も追いつかない。
頭を前後に揺さぶられながら、男は慌てそうな自分を落ち着かせ、運転手の顔を覗こうと身を少し前へやった。
運転手は一目でわかる程かなり老齢な男で、口を真一文字につむぎ、ただ前方それ一点のみを見据えている。
「あの、どこへ行くんですか?」
運転手は答えない。何か不機嫌そうな感じさえする固い表情で、やはり前しか見ていない。客としてもてなされている様な心地は一切しないどころか、まるで自分は乗客として認知さえされていないかの様な態度だ。
─一体、なんなんだ
男は知るすべのなさに厭き厭きして、一瞬天を仰いだ。狭い車内の天を仰いでも、そこには無機物の残滓ぐらいしかない。
タクシーは交差点を突っ切り、黙々と一般道を走る。運転手は相変わらず何一つ話そうとせず、ハンドルさえ離さない。男は何度かタクシーに乗ったことはあるが、ここまでテコでも話そうとしない運転手は前代未聞だと思った。
そんな男の困惑を無視して車は高速道路の入り口へと向かって行った。男はもう驚いたりしないと思いながらも、高速の入り口へ邁進するこの状況をどう捉えれば良いのだろうか、募り出したのは言い知れぬ不安だけだった。
仙台港北のランプから三陸自動車道を利府方面に走り出す。唸りを上げるエンジン音が一層不安をより強め、彼は慌ててタコメーターを覗く。
タクシーの時速は100kmを越えようかとしていた。
男は、先ほどの新幹線よりも今の方がよほど恐怖に思えた。時速で言えば300kmと100kmでは随分と差があるが、実態感のない300kmよりも、今こうして体感している100kmの方が心底恐ろしかった。
それは速度に対しての恐さではなく、行き先のわからない「無言の時速100km」と言う現実への恐怖だった。
─これからどうなるのだろう
白紙に戻った男の全てが、まるでこの運転手に握られているかの様だ。彼には抵抗する気力もなければ、これらに対して強硬的な態度を取る精力もない。空の器を運ばれているのと何ら変わりはなく、後部座席に埋まった体は容易には引き抜けそうにない。
仙台市内を抜け、高速道路は山林を縫うように北へと続いている。どこまで行くのだろうかと男が車窓に頭を傾けると、タクシーは本線を離れて行く。
どうやら高速を降りるらしい。料金所の表示は「利府中」だったが、彼にはそれが仙台のどの辺りなのか全く見当がつかなかった。それでも、暗がりに薄らと見え隠れする木々の数から恐らくは山間、それに近い所だろうかと思った。
猛暑の夏でも車内のクーラーがやけに涼しく、男は肌にさぶいぼが立ちそうな心地さえしていた。
ヘッドライトの光は右へ左へ拡散し、車は山手の方へ進んでいる様だった。こんな山奥に知人など居るはずもない。むしろ、人もいるのかどうかと言うところだ。
葉を乱雑に茂らせた木々が幾重にも折り重なって、車道が湾曲する度にそれらが眼前にまで迫ってくる。細く華奢なはずの枝もこの時ばかりは無数の矢束か、針金をむき出しにしたワイヤーフェンスにすら思え、ガリガリとタクシーは枝先に引き裂かれる様な喘鳴音を何度か上げているが、それでも更に加速させるこの運転手が常人とは到底思えない。
運転手は速度どころか車線も気にせず、目的地だけを目指して疾走している。
フロントガラスに何かがゴンッと激しく当たろうが、ピラーが折れ曲がろうが、タイヤはキリュキリュキリュと毟り裂かれる断末魔を上げながら山林の奥へと向かって行く。
やがて、道路ですらなくなった舗装されぬ道なき道をタクシーは走り出し、一光の灯が揺らめく民家の手前でザッと停車した。
男は着いたのだと思った。勿論、ここがどこなのかわかるはずはなく、辿り着いた民家にも見覚えは当然ない。
しばらく車内には言いようのない沈黙が訪れた。普通のタクシーなら料金の支払いがあるのでそれに付随するやり取が必ず生まれるのだが、運転手は未だに目を真っ直ぐと前だけに向け、後部座席を一瞥すらしない。
カッチカッチとハザード音だけが虚しく車内に響き、男も運転手も岩の様に動くことがない。これは動かないのではなく、動けないのだ。
─降りろと言うのか?
あれほど猪も舌を巻く程突き進んでいたタクシーは、電池を切らした様に動く気配が相変わらずないままで、逡巡する男にどうこうしろとも言わず、後部座席の扉を一方的に開き放ち、生熱い外気を飲み込んでいく。
男がどれほどの時間座席で放心していたかは定かではないが、強い光を放つヘッドライトのそれに夜蛾が群がり出した辺りで男はようやく腰を上げた。
僅かに持っていた紙幣を後部座席に無言で置いて、足からゆっくりと降りる。固い土の上に足は棒のように突き刺ささり、長旅の疲れが一挙に押し寄せる。
彼が外の空気を吸い込もうかと背を伸ばすと、その一呼吸よりも先にタクシーは急発進して、すさまじい轟音が背中を貫く。
男が慌てて振り返る頃には姿が既に夜淵の奥底にあり、一瞬だけ捉えられたのは真っ赤なテールランプのヒレだけだった。
何も考える余地がない。男は招かれるように民家へと歩を進めた。そうする以外に当てなどないのだから。
瓦屋根のその家は、男の知る「家」とは少し異なり、彼からすればそれは骨董品の一種か有形文化遺産の類に近く、その佇まいに思わず息を飲んだ。
豪邸と言う訳ではないが、恐らくは人の歴史が何百年も刻まれ、それがあらゆるカタチで充棟されているからこそ彼は畏怖したのだ。
自然と体が震え、飲んだ息に空気が含まれているのかさえあやふやなほどに。
─誰の家なんだろうか?
男は改めて一連の奇事を思いだし、心当たりを探りつつ玄関へと向かった。玄関の扉は半分開いてあり、中の様子が伺える。
温かみのある丸い光がほのかに見え、ただその光は弱く、奥は見えず、月明かりを手で掬って水に浮かべただけ程のもので、それでも彼を包む闇の中では一際眩しいものだった。
「すみません。」
思い切って彼は呼びかけた。家の中を反響していく声はどこへ向かったのか、廊下を二三回曲がった辺りで消えたのか、誰も返事を返しては来ない。
湿った土壁に声を当てても反応は悪く、何度か呼びかけても物音一つ聞こえてこない。
─誰も居ないのだろうか?
男は頭の中でそう思った。だが、妙に人の気配はするし、心底その家が無人だとは思えずにいた。彼が玄関でその矛盾に懊悩していると、奥から一人老婆が出てきた。
老婆と言っても腰が少し曲がり、顔は割とツヤツヤしていて、瞳の色は濃く、泡喰って動揺しきりの男をしっかりと捉える視線はぶれる事もない。
男はもう一度口を開いた。そう、何か話そうとしたのだ。だが、声は一向に音へと変わらず、貧粗な息だけが喉を掠めていく。何度も何か言おうと試みて、それでも声が出るどころか、言葉を手繰る糸に全身が縛られていた。
老婆は僅かに目尻を窄め、男の顔を見上げた。そして、何も話す事無く、ゆっくりと背を向け、そのまま家の奥へと消えて行く。彼はその背中を見送る事しかできない。
彼はどうすれば良いのか、答えを出せなかった。今まで人に言われた事をこなして、人の言う事が自分のやる事だったのだから、目で合図されても受け取り方などわからない。
呆然と立ち尽くす男を見兼ねたのか、どこからともなく良い匂いが彼の元へと訪れてくる。それも、次から次へと。
それでも男はどうして良いのか、どうしろと言うのかを考えずにはいられなかった。相手は見ず知らずの老婆で、自分は訳もわからず他人の玄関で立ち尽くしている。そんな状況を何とか整理しないと、気が狂いそうだった。
彼の脳裏ではまだ今なら家に帰れると言った気持ちもあるのだが、夜も本営を迎えたばかりで、ロクな所持金もなければ帰る理由もない。帰ると言う選択は既に仙台の駅を出た時点で無いに等しく、正に行く当てもなければ帰る所もない。
─だからと言って・・・
考えれば考える程訳がわからず、答えなど出せるはずもない。なのに、脳にまで染み渡りそうな旨そうな何かの匂いが絶えず呼びに来る。頭で他の事をいくら考えても、体は自然とそれに反応し、腹の奥底から沸立つような何かが全身に込み上げてくる。
彼の思考は段々と鈍りだし、費えぬ夜の闇を泳ぐ棚雲よりも遅く、鼻の管から全身へと巡り廻る匂いの誘惑に心は既に虜となっていた。
男はフラフラと玄関に向かい、僅かに隙間が空いていた扉の背を右手で掴んだ。こうなると、もう常識など瓦礫屑同様、彼の手は一呼吸置くこともなく扉を開けた。
「す…すみません。」
返事はなく、シンと静まり返っている。そして、外に居る時はあれほど溢れ返っていたはずの旨そうな匂いも、急に距離が空いた様な…「もっと奥へ」と言っているかの様だ。
男は身構えてしばらく待ってみた。夜分遅く、それも知らない人の家。了解も得ずに上がり込めば、これは警察に突き出されても文句など言えない等と男は思ったのだ。そうは思っても一度坂を転がり出した石と同じく、どうすることもできない。
彼は身を可能な限りに細め、扉の隙間以上にはならない様に恐縮した。だが、そんな彼の四苦八苦を見届ける者すら現れず、刻々と時間だけが過ぎる。
次第に彼の体は力が抜けてきたのか肩が下がり、中心に偏った血液も指の先までくまなく流れ出す。何かに背中を押された様に男は足を上げると、黒光りする足先の歪んだビジネスシューズをようやく脱ぎ捨て、廊下を儘々と歩き出した。
焦香と丁字染めが入り乱れる渡り廊下をゆっくり歩くと、ほのかに明るい橙色が一つの部屋から漏れているのが見て取れた。
匂いの根源はそこだと確信でき、男の体はゆらゆらとそちらへ傾く。中を覗くと出来立ての料理が置かれ、それを老父と老母がモクモク食べていた。
ご座敷にある小さなテーブルを囲み、老夫婦は男が物音を立てても頭を上げず、淡々と箸を進めている。
男は何も言わず、おもむろに近寄った。襖で死角になっていたので見えなかったが、まるっきり手の付けられていない夕食が一人分ある。見た感じ、恐らく誰か一人そこで食べる予定があったのだろう。箸の前にはおかずや椀物一式一通り用意されている。
─誰か他に居るのだろうか?
男はそう思って老夫婦に気遣いながらさりげなく目で人を探した。タンスや小物がどれも年代物ばかりで、老夫婦以外に人が住んでいそうな感じも特にない。
未だモウモウと湯気を立てている味噌汁。恐らく、用意されて間もない事は確かだ。誰かが座るのを心待ちにしているかの様に座布団もふっくらと待ち構えている。
彼は何もできず、乾いた生唾を何度か飲んだ。それでも喉の渇きは癒えず、目の前にある誰も手を付けないご飯がずっと視線を送ってくる。彼を見ているのはその膳だけ、とうに味噌汁すら飲み終えた老夫婦はお茶を飲んで一服していた。勿論、彼を一瞥さえせず。
見知らぬ男が他人の食卓の入り口で棒立ちしている。そんな滑稽な光景が誰にも阻まれる事無く、ゆるやかなに流れる時間の中で立ち止っている。
お茶で一服を終えた老父はノソリと立ち上がり、口を噤んだまま奥の部屋へと消えて行く。遅れて食べ終えた老婆は食器を手早く片づけ始めた。手際の良さについ見惚れてしまい、男はその一挙一動を見たままだった。
そうこうしてると、老婆は手の付けられていなかった料理をまるごと避けて台所の方へと消えて行く。誰も居なくなった空間で、その料理だけが彼を呼んでいる。
観念した訳ではないが、彼の足はズルズルと崩れながら料理の前と向かった。彼の為ではないであろう手つかずの料理と面と向かい、彼は箸を掴んだ。
理屈でどうこう繕うとも正答は見いだせないのに、男の決心はここまで来てもまだつかずにいる。さながら、遊園地でアイスクリームが欲しいのにそれをねだれず、売店で並ぶ他の子を羨ましげに見る子の様に。
既に無断で上がり込んでいるクセに、今更何を迷っているのか。恐らくは、それをしてしまった後の事を考えているのだろうが、掴んだ箸は迷いの層雲をとうに突き抜け、煮炊きされた魚の身を掬い、一直線に口へとそれを運んだのだった。
それは舌の上で様々な香艶を放ち、喉を過ぎる頃には次の芳薫が頬中を満たす。腹の辺りでもそれらはなおの事温かく、ゆるやかに腑の中で溶けて行く。
夏夜の静寂に響くのは虫の寝息だけ。男は何も言わず、考える事も辞め、人知れずその料理のあたたかさに打ちひしがれていた。空の臓袋にそれが入る度、凍てついた心を溶かしてその雫がとめどなく溢れ、いつまでも流れ続けていた。
─ごちそう様でした・・・・。
悠刻の只中にあっては数ある椀のどれも瞬く間に空となり、手持無沙汰になった男は一服がてらに廊下に出て空を見上げていた。
何も見当たらない夜空は果てなく、縁側に腰掛けた彼を照らしているのは裸電球の光だけだ。彼は誰かいないのか何度も目を配っても、先ほどの老父や老婆すら見当たらない。
あるは庭を越えて見える鬱蒼と茂った山の木々。それも夜闇でただ黒く、幾重にも混ざり合う葉のさざめきが微かに聞こえるだけ。
すっかり指先から煙になって消えたタバコの行方を男はしばらく探していた。何も力が入らない眼で、焦点すら定かでないその眼で。
その無気力な挙動の中で、男は頭の鱗片にあるホコリの積もった記憶を一つ引出していた。それが彼の中で何年ほったらかしにされてきたか、彼すらもうわからない。
ただ、これは幼い頃、誰とでもなく、恐らく母親かそれに近い人から何となく聞いた様な事だっただろうか、或いは写真などで見せられたのか、ともかく仙台に親戚が居るような話を聞いたことがあった気がしたのだ。
彼はこの家がそうなのかもしれない。と、思った。勿論、ふと思い出した記憶なのか子供の時に作った妄想なのかわりはしない。今まで交流のなかった親戚がこんな事をしてくれるとも考え難い。
男はある種、開き直った。どうでも良い、と。どうせ生きる価値すらなくし、すぐに死ねないから漂っているだけなのだから、この際どうでも良いのだと思ったのだ。
そう彼は自分で結論づけた途端、どこからともなく眠気が込み上げ、彼は誰に断わりもせず、ポカンと空いている一部屋を見つけそこで寝だした。
少し肌冷たい畳に顔を伏せ、目を閉じれば十を数え終わるより先には彼のいびきが静かに聞こえだし、久しぶりに深い眠りへと堕ちて行ったのだった。