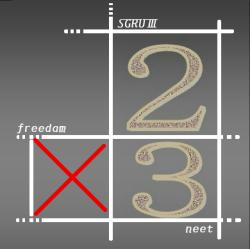ベルトコンベアに乗せられた電車とバスが荘厳なビル街に辿り着き、中からつまみだされた人駒が機械的に並べられ、社会と言う名の怪物がようやく今日も動き始める。
「おい!早くしろ!何やってる!!」
ここのところ、どの業界にも余裕と言うものがない。それは至極当然の事で、長引く不況に社会保障問題や連発している大きな災害でどこも弱り切っている。
元気な業界ですらその悪い雰囲気に当たってカビが繁殖しだし、ライバル企業と激しい競争に明け暮れている。
「お前は何年この仕事をやってるんだ!?なんだその目は!!?」
仕事の結果をどうこう言われるのは耐えられるが、仕事のスタンスをどうこう言われるのだけは未だに合点がいかない。と、言うか腹が立つ。
怒りに身を任せて叱責するこの上司は、一体何の為にこんな伽藍堂に向かって大声を浴びせているのだろうか?毎度、その様に思うが答えは得られそうにない。
「どうしたんだよ?お前最近本当にどうかしてるよ。」
同僚気取りの、同期の顔なじみはそんな言葉で俺を労った。
「どうでも良いんだよ。」
俺がそう答えると、返しにくそうに苦笑いして見せた。この笑いの奥に潜んでいるのは憐みでもなければ同情でもない。こいつからすれば俺は風景的なライバルなのだから、恐らくは歓喜を押し殺しての嘲笑に近しいものだろう。
「おいおい、そう言う態度で怒らせてるんだろ?いくら仕事ができてもそれじゃ…」
そんな事は百も承知だった。だが、この狡猾に優等生ぶってる男─目の前のこいつに指摘されると、上司が同じ事を言うのより格違いで腹が立った。
「良いだろ?お前が怒られるんじゃないし。」
つい、口が滑ってしまった。もう遅い。
「あのなぁ…!!お前が良くてもそう言うのが全部に響くんだよ!会社の雰囲気は悪くなるし、ヤル気ねぇんなら辞めちまってよそでやれ!」
周りの人は何事かと一瞬目をこちらに向ける。だが、すぐに持ち場へ目ごと戻して作業を再開させていく。茶飯事と言えばそれに近い光景だろうから。関心をいくら注いだところで他人事の領域を出る程の事でもない。
そうだ。辞めれば良い。だが、それができないからこうやって居るんだ。会社の外壁にしがみついてでも、そうやっていなければ生きていけないのだから。
或いはもう、そうしている以外に選択肢もないのだろうから。
「また、明日。」
言い足りなさそうな同僚は怒りが冷める様子もなく、俺を鋭い視線のまま見送った。俺はその視線から逃げる様に足を早め、今日も人でごったがえす駅へと向かう。
─今日も終わりか
普段より早く家に着いた俺は、何も考えずにTVを無意識的につけた。
薄い液晶モニターと自分の間には、食べ飽きたインスタントラーメンとコンビニ弁当が白濁した湯気を立てている。
俺が開けているのは目と口だけ。ドラマもバラエティもさして面白いとは思わない。似たり寄ったりの番組内容で、喉を通り過ぎて行く乾燥麺のそれよと同じく味はない。
「…以上、話題の最新携帯端末に関するトピックスでした。では、ニュースです。米経済指標は当初の予測を大幅に下回り、株式市場は…。」
暗いニュースに舌鼓を打っていたのも昔の話で、俺の目にはただ美しく、鮮明になり過ぎた現状だけが映っている。
何も考えたくはない。何にも邪魔されたくない。
─ただ時間だけが過ぎて行く
翌日、今日も図った様に駅は雨だ。薄暗がりの斑点模様、煤黒いスーツにまとわりつく重い空気が通過電車の疾風でズタズタに引き裂かれていく。
会社へと辿り着き、滴をジワジワ垂らす小型の傘を俺は手早く畳む。出て行く人、自分の横を追い抜いて行く人、その狭苦しい狭間で今日の始まりを覚悟する。一掴みの空間と人間と時間、そこに全てがある。そこ以外に何もありはしない。
「ちょっと良いか?」
出社して程なく、上司が俺に言う。いつもと変わりなく表情に何の感情も滲ませることなく俺は「はい。」と、頷く。
ただ、この時は不思議と違和感があった。社内の四方八方から襲い来る様な喧騒から放り出され、宙に浮いた様な、透明な膜に入った様な、妙な違和感が。
「最近どうかしてないか?ちゃんと休みは取れているのか?」
業務的にしか接した事のない上司からこんな言葉を聞くと、怪しげな呪いでも始められるのかと言う気分になってくる。わかっている。この上司は本心から俺を心配などはしていない。恐らくは─。
「突然ですまないが、しばらく会社を…いや、単刀直入に言おう。明日から来なくて良い。」
「クビ…ですか?」
「雇用契約終了だと思ってくれて構わない。」
立場的に、俺はどうでも良い捨て駒的位置にあるとは思っていた。ただ、何の脈略もなく捨てられる日が来るとは思っていなかった。
しかも、今日まさに今。
「君にとっては良い機会になると思う。この際だから十分静養すると良い。」
上司は優しく微笑んで俺の肩を叩き、一人先に面談室から出て行った。
取り残されているのは、上辺だけの優しさが肩から胸に突き刺さり、立つことさえできぬ抜け殻だけだった。
何もする気が起きない。どうでも良い。みんな死ねば良い。そんな事を思いながら日々を続けてきたクセに、本当に終わりを告げられると、俺には何も残りはしない。
漠然と広がる空間に投げ出され、もがく気も起きず、反転した日常の光景は現実感などどこにもなく、目を向ける場所さえ見つからない。どこを見れば良いのか、どこに向かえば良いのか、全てが無い。
いっそ物ならば、廃棄物として処理され、燃やされるか埋められるか、少なくとも終着点は確保されていただろうに、路上に投げ捨てられ、忘れられ、土に環える事さえ叶わない人工物同様。雨ざらしで、或いは極炎の烈日下で、もしくは冷たい雪に押しつぶされながら、どうする事もできずに─
俺はそんな地獄に居たはずなのに、それとは違う今…。何もする事もなく、誰にも必要とされず、ありふれた無味乾燥な日常さえ取り上げられてしまった。
物なら、容易な終わりを手軽に得られたと言うのに、人であったが為に、生きなくてはならない。どんなに苦しくとも、自ら命を絶ちでもしない限りは生きてしまうのだから。