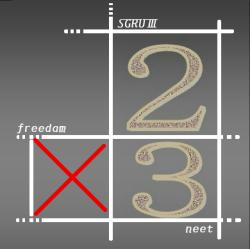この仕事をしている理由はさしてない。
それが生活の糧だから大人しくこなすだけの話で、それ以上の何かがあるのなら、それが何なのか教えて欲しいほどだ。
それに手を染め始めた辺りの頃はがむしゃらで、嫌でも不得手でも、まして背徳的であろうと同じ色に染まろうとして、そのうち抱いていた夢なんかすぐにわからなくなった。
今日も空は夜を迎え、欲望の燃え滓がスス溜まりの様に漂うビルの中で、俺はまだ働いていた。働きたくて働いている訳でも無く、その仕事に大きな意味がある訳でもないのに。
─何もする気が起きない
誰に操られている訳でもないのに、躯体の全てを鋼鉄のワイヤーで絡め取られている様な状態で、緩慢な日々に踊らされている。
これが死ぬまで続くのか、或いはゴミ同様に捨てられるまで踊り続けるのか、それらが何年…何十年続くのか、そう思うと無気力は更に輪をかけて酷く顕著になる。
それでもこの日々を続ける。雇われ社員の陥りがちな絶望は、俺にとってどうでも良い話で、自分がその一部だとしても他人事の様だった。
─どうでも良い
この言葉を繰り返している。良い言葉だけが夢物語として溢れ、宛もなく迷走する社会にしがみつき、都合と経済で割り切るこの国でも、その煽りを存分に受けていようとも。
意識などする暇もないまま一日が始まり、振り返る様な趣もないまま一日を終えて、それを積み重ねて、もう何年とそうしてきている。
─みんな死ねば良い
俺を支配しているのは憤怒ではなく、この意味もなく価値もない社会全ての滅亡でしかない。誰が憎い訳でも、何が辛い訳でもない。
ただ、死ねた方がもう幸せだと思えてしまうほど、この現代は腐敗しているように思えた。これを何とかできる者など居ないだろうし、現にどの総理大臣でも、どの党でも、この社会は変わることなく凋落の沼底へと向かって行く。
その先にあるのは容易な死ではなく、理不尽さからくる落胆と、物と同じく雑に廃棄されて生き血を吸われ尽くされてからの死だと言う事も。
家に着くと俺はいつも冷たいご飯と向き合っている。量産され、味気ない薬品の匂いで彩られているそれらと、いつも向き合っている。
それが動力源の俺が現社会と大差などない事はとうにわかっている。そして、それは俺だけの話ではないだろうから、もういっそみんな死ねば良いと思ってる。それだけだ。