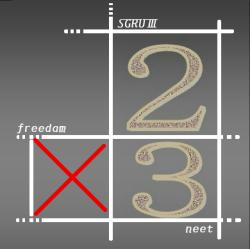今日も色を失った肉像が開閉と往来を繰り返す鉄箱の中から溢れ出し、不揃いに揺れ動きながら再び鉄箱の中へ吸い込まれて行く。
ゆっくりと動き出すその脇を激しく流動する時間が渦巻きながら流れ、歪んだ重さにキシャがりながら悲鳴に似たブレーキ音を何度も擦鐸させる。
慌ただしく人が乗り降りする駅のホームで、男は無抵抗にその渦中に飲み込まれ、既に精力の欠片すら無い虚ろな表情をただ人波の中で浮かべている。
彼がどう言う仕事を生業としているのか、どの様な一日だったかは定かではない。それでも大概の予想はつきそうで、恐らくその通りだろう。
これは、そんな彼のある日。
そして、そのある日から始まるわずかな一時。或いは、その日までの他愛もないひとは。