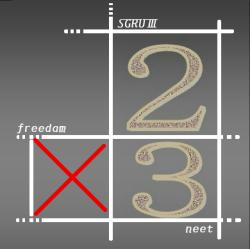男は肩を激しく震わせながら、無残に散らかったそれらを見下すようにして立っていた。
「誰が、これはあんだの分ではない。」
ふと、そう老父がおもむろに漏らした。
今まで目も合わさず、言葉も交わさず、居るのかどうかすら怪しく、見えているだけの動物園のそれと変わらない。
そんな風に思っていたそれが、今にして喋ったのだ。
─自分の分では…ない?
「あんだの分ではないのに、あんだが勝手にそれを食べてだだけです。」
粛々と言葉が続き、男は途端に我に返った。丁寧ながら確実に激しく怒っているだろう老父の声が何より響き、おののきと共にますます混乱してくる。
「何を言ってるんだよ・・・、じゃぁ、誰の分だって言うんだ・・・!?」
男は必至で虚勢を張った。そうする事で、自分がした事をどうにか誤魔化したいのだろう。この食事は勝手に老夫婦が作っているもので、有難迷惑なんだと。
男は焦りから汗を額に滲ませていた。なぜなら、部屋には再び沈黙が訪れ、口を開いたはずの老父も固く唇を締めたままだったからだ。
「誰か・・・の分なんて嘘だろ?だって、この家にはあんたら以外には住んでいない。」
独り言のようにそれは空間に消えて、何の反応もなく、誰も言葉を返してこない。言葉を吐けば吐く程息苦しくなり、胸はただならない鼓動で集まり過ぎた血液が行き場をなくしたように狂っている。
男は何かを確認する様に部屋を見渡す。いつもと変わらない光景。ここに来てからそれが微動だにする事は決して無く、どこか変化があった方がかえって現実味すらあると思える程に安寧な空間。
それが、こんな今でさえ広がっている。
「・・・。」
男は目で家探ししていた。何がどうなっているのか、恐らくその類の思考はない。まるで焦点を失い、故障してめちゃくちゃに動き回るカラクリ人形の目とそれは大差がない。
柱の陰、襖の隙間、何度も部屋の右と左を往復し、男はうろたえていた。心の中はもはや乱れに乱れ、動く眼球をどうする事もできない。
ふと、目の端で一瞬何かが動くのを捉えた。
─なんだ!?今のは!
目の端、老父の背の奥側にある格子模様の硝子戸。張り付くような人影が、一瞬揺らめいたかと思うと部屋の奥に消えた。
「あ・・・。」
男の目はそこでようやく止まった。止まったと言うより、動かなくなった。老夫婦の他に誰もこの家には居ない。それは、これまでここで過ごしてきた男にとって確証を得ている数少ない真実。
─誰なんだ!?
彼は考えもせず足を踏み出し、散乱した椀を踏んでよろけても尚老父の奥にある部屋へと突き進む。
彼は黒く曇る硝子戸の前に立って怒りを一喫すると、右手で戸を思いっきり引き開いた。
「誰か居るのか!?」
ガシャン!と、硝子戸は鈍い音を立てた。
覆うように背高い箪笥が吐き出す闇霞が押し迫る中、微かに黄橙色の灯が二つ程はためいている。
静かな瞬きを繰り返すその最奥に、人の顔がぼんやり浮かんでいる。
「え・・・・。」
その顔は無邪気そうな笑いを浮かべて、そのままを保っていた。黒縁の額の中でいつまでもこちらに向けて、男もよく知っている眼差しを屈託なく向けていた。
「嘘だ・・・。」
男の脳裏には、庭で駆け回っていた少女が山の崖から滑り落ち、岩尖の上で血を流して息絶えると言う一連の出来事がすぐさま思い浮かんだ。
それも、何度も。何度も何度も少女は崖を落ちて行く、その度に悲痛な叫び声をすぐそばで上げる。それが自分を責めて責め尽くすように、ガケから落ちる音。少女の肉が割かれる音。服が無残に破れる音。夏の草を引き千切る音。何度も男の目の前でそれを響かせる。
「う・・・・・わ・・・・。」
あまりの光景に、男は膝から崩れ落ちた。涙を流す余力すらなく、もう漏らす息さえ残らない程に声を絞り尽くして、両手を畳につけるとひたすらに懺悔を繰り返す。
「その子は、ウチの孫娘だ。」
老父はいつからだろうか、男の背後に立っていたようだ。左手で軽く硝子戸をそっと持った状態で、男よりも身長は随分低くとも、大きく雄大な山を思わせるほどだ。
いや、男が小さすぎるのだ。畳の上で平伏したかの様に縮みこまり、先ほどまでの猛烈な勢いは似非物だったのだろうかと思わせるほどに弱い。
「息子夫婦は、あの震災の日に亡くなった。娘は遺体が見つかったから、こうして供養しているだけた。私の中では、まだ息子夫婦は死んでいない。だから・・・・。」
老父はそう言うと静かに去った。男を責める事は何一つ言わず、それをしても何にもならないと背中で言うように、いつも通りどこかへと歩き去って行く。
「震災の日に・・・・?」
男は再び、黒塗りの仏壇にあるその遺影を見た。
─あの子は・・・。
夏の庭、風がすすぎ、草がささめく、白く輝く世界に彼女は居たはず。確かに居て、自分を救い出したはず。死んでも居ないのに、死んでしまった自分を呼び戻しに。
─あの子は・・・。
何度も心の扉を叩きに来た。優しく、そっと触れて、開くことを強制する事など決してなく、無邪気に、何度も何度も。
─あの子は・・・!
男はすっと立ち上がり、部屋を飛び出した。
─あの子は!
その勢いでそのまま食卓を抜け、彼は縁側に立った。
光の舞う世界。ただ白く、遠くは青く、そっと吹きかける様に流れる風とその風に揺れる緑が幾重にもたなびく。
その中で、彼は確かに見た。
生きる輝きを。

彼は声をあげて泣いた。
それは、ようやくあげる事ができた二度目の産声。
この時にして、彼はようやく生きたのである。