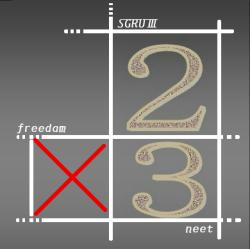やり場のない怒り、それとも違う激しい感情が抑えられず、固い地面を何度も叩き、血が滲んでも叩いて、顔を上げて目が動く限りまた周囲を見渡す。
足はいつしか、あの庭・・・少女がいつも無邪気に遊び回っているその場所へ向かっていた。
─あそこならまた会える
何度もそこで少女を見たのだから、自分にとってそれは最後の希望でもあった。崖から落ちて、そのまま変わり果てた姿になった等と、絶対に想像さえしたくはない。
─あの灯りだ
どこか懐かしさえあるあの家の灯り。
表情一つ変えず、庭を一歩ずつ行く。少女の残影は瞬く間に一つ残らず消えて、後には私だけが取り残されて、足跡さえ見つからない。
─居ない
男は気が途切れた様に立ち止ると、庭の草を足で無暗に蹴り払った。彼が足を振る度に夏草はガサッ!ガサッ!と、不器用な断末魔をあげる。
事足りないのか、男は更に草を手で引きちぎり声にならない怒りをあげだした。物を蹴散らして、顔は既に人のものではない。
「あーーーーーっ!」
目を鋭く吊り上げ、手が震えるほど拳を握り込み、男は庭から廊下へズカズカと上がり込んで、一気に食卓へ直進して行く。
ガンッ!
半分ほどは開いていた襖を渾身でこじ開けると、男は食卓の上を血走った眼で睨みつけていた。
食卓にはいつも通り、自分の分も用意されてある。今日の夕食は土地で採れた山菜の天ぷらや、小魚を煮つけたものなどで、どれも小奇麗に幾つも盛られてあった。
ただ、静かな食卓。老夫婦は何も言わず食事を続けている。その中で、男は歯ぎしりを一掃強めて、拳をギリギリと強く握った。
「いい加減にしろよっ!!」
男のやり場の無い感情は、無抵抗で優しい世界に向けられた。何故かなど、誰にもわかりはしない。
しかし、彼がどんな感情を向けようと、老夫婦は黙ったまま食事を続けていた。顔色一つ変えず、ペースも変えず、男を一瞥すらしない。
男の声が台の上の物を砕きそうなほど激しいにも関わらず、老夫婦は相も変わらずだ。
「いい加減にしろって言ってるだろっ!?」
彼は、抑えきれなくなった感情に火が付き、その宛のないもの全てを無抵抗な老夫婦にぶつけた。そこしかなかったのだ。
「なんで俺の分まで作るんだ!毎日毎日!おかしいだろっ?!他人だろっ?!なんで何も言わないんだよっ!!金が目当てなら早くそう言えよっ!」
何を言っても、まるで手ごたえはない。その事が返って彼の怒りを爆発させる。どこにも受け手がない感情をどうしようもなく腫れさせ、その天辺には赤黒い亀裂が入っていた。
「おいっ!聞いてんのかよっ!!」
ガシャンッ!
男は食卓の上にあった手のつけられていないそれを蹴散らし、息を荒立てた。これでもかと言いたげな目で老夫婦を睨みつけ、もう二度とここには居られなくなったと言う激しい後悔から、身の震えは止まらなくなっていた。
きれいな鴬色の皿も割れた。その上にあった魚の煮つけは汁ごと畳に散乱した。ひっくりかえって転がり出した椀は壁にぶつかって息の根を止めたようにコトンと音を立てた。
全てが終わった。もう戻らない。と、男は思った。