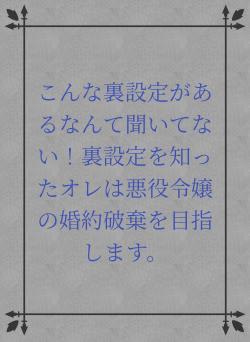食事を終えたあと、執事のグレイが「ご案内いたします」と優しく声をかけてくれた。
大人の足取りをあえてゆっくりと落とし、五歳児の歩幅に合わせて歩いてくれる。
グレイの背中は大きく、安心感のある存在だが、今日ばかりは緊張が胸の奥を締めつけていた。
廊下の空気は、朝の光が差し込んでいるはずなのに、いつもより静かで重く感じる。
絨毯の上を小さな足で踏みしめながら、俺は心の中で何度も深呼吸を繰り返していた。
執務室の前に着くと、グレイが一度膝を折るようにしゃがみ、「大丈夫ですよ」と小さく囁く。
その仕草に、ほんの少しだけ肩の力が抜けた。
コンコン、とグレイがノックをする。
「レイン様をお連れしました」
「入れ」と父のグラードの低い声。
グレイがそっと扉を開けてくれる。
その手の動きはどこまでも丁寧で、俺の歩みに合わせて一歩後ろをゆっくりついてきてくれる。
その細やかな気遣いが、今の自分には妙にありがたかった。
部屋の中は、磨かれた木の床に重厚な書棚、窓から差す光が机の上に淡く広がっている。
グラードは革張りの椅子に座り、横には長兄のオレファンと次兄のシェザン。
グレイも部屋の隅で控えたままだ。
机の上には、拳ほどの大きさの石。
その一つが、この後の緊張とざわめきを呼び込むことになる。
「レイン、座りなさない」
「はい」
言われて、シェザンの横へと腰を下ろす。
小さなお尻が座面に沈んだ。
俺が座ったところでグラードがこちらを見つめたまま、低い声で問いかけてきた。
「レイン、この石を見てみろ。何かわかるか?」
俺は恐る恐る机の上の石に目を向けた。
(……ただの石、だよな?)
つい口から漏れる。
「石、だよね」
その言葉に、兄たちとグレイの表情がふっと緩んだ。
思わず自分でもホッとしたのが伝わる。
ここで『鑑定』を試したくなり、意識を向ける。
《鉄鉱石/用途:鉄の材料》
(これが鉄鉱石か。前世でも本物を見たことなかったな)
ポツリと言葉が零れ出た。
「これが鉄鉱石かぁ……」
言った瞬間、ピンと張り詰めた空気が戻ってくる。
沈黙が広がり、父がゆっくりと息を吸い込んで吐く。
「レイン。なぜそれが鉄鉱石だと分かる?」
俺は口をつぐんだ。
「……本で見たのか?」
オレファンが言う。
だが、すぐにグレイが補足した。
「いえ、オレファン様。レイン様はまだ絵本しか――文字もようやく習い始めたところでございます」
「では、なぜわかるんだ?」とシェザンも戸惑いを隠せない。
ぐっと詰まりそうになる。
(……これは、まさかやらかしたパターンか?)
石は大丈夫で、鉄鉱石だとダメってこと?なんで?
思わずグラードと目が合う。
真剣なまなざしに、身体がかちりと固まる。
「父上……?」
「レイン、この石のことを分かる範囲で話してごらん」
(わからないって答えるのはマズいよな……もう、誤魔化せないよな、鉄鉱石って言っちゃったし。ここは腹をくくるしかないか)
「鉄鉱石です。鉄の材料になります」
そう答えると、グラードの表情が一層険しくなる。
オレファンもシェザンも、そしてグレイまでも気まずそうな顔をしている。
グラードが静かに息をつくと、少しだけ表情を緩めた。
「……レイン。お前が『鑑定』のスキルを持っていることは、もう分かった」
その言葉に、シェザンが割って入る。
「なんで、レインがスキル持ってんだよ!しかも『鑑定』なんて!選別式もやってねぇのに!」
「黙れ、シェザン」
オレファンが低く遮る。
「兄貴もそう思うだろ?! だから黙れと言っている。父上が話しているんだ」
「……チッ、分かったよ」
シェザンが不満そうに椅子に座り直す。
グラードがしばし黙り、机の上で指を組む。
「この世界では、スキルは八歳の選別式で明らかになるのが常だ。ひとりにつき、ひとつ。多くてもゼロかひとつ。もともと体に宿っているが、それを確認するのが選別式。選別式の前に分かることなど滅多にないが、全くないわけではない」
(選別式ってのがこの世界の常識なのか。選別式前に発動は驚きってわけか……でもそれだけじゃなくて、なんだか重い空気だ)
オレファンがグラードに小声で言う。
「スキルが五歳で発動するのは珍しいですが、まさか『鑑定』とは……」
「ああ。他のスキルであれば、もっと喜べたのだが……『鑑定』は……」
グラードはわずかに視線を落とし、続ける。
「スキルはその人の生き方を大きく左右する。職業に合ったスキルなら大いに役に立つ。
だが、『鑑定』は……見れば分かることしかわからない。
この鉄鉱石も石と言う者もいれば、鉄鉱石だとわかる者もいる。
お前は『鑑定』スキルで鉄鉱石とわかるが、スキルがない人でも鉄鉱石だと分かる。……私の言ってることがわかるか?」
グラードの言葉が静かに落ちる。
その声は怒りでも失望でもなく、ただ事実だけを告げるものだった。
(……なるほどな)
俺は思わず、昔科捜研で上司に「基本を見落とすな」と言われたときのことを思い出す。
どんなに最新技術があっても、現場の誰もが気付く証拠しか見抜けないなら、“特別な力”とは言えない。そういうものなんだろう。
(この世界の“鑑定”は、あくまで“見れば分かることしかわからない”スキル。特別な真実を暴く力じゃない。誰もが知る情報を、ちょっと手早く知れるだけ――)
目の前の鉄鉱石だって、現実世界でも理科好きな子ならすぐに見抜けただろう。
つまり、俺が便利だと思っている『鑑定』は、この世界の人間から見れば、他のスキルほど役に立たない=評価されにくい、という理由も分かる。
(なるほど。ハズレ扱いか。俺には便利に思えるけど、そういうことか)
自分の力の意味を、ひとつ大人の目線で静かに受け止める。
そのうえで、胸の奥にわだかまる気持ちが、少しだけ整理された気がした。
「このことは、屋敷の者たちに口外しないように。グレイ、伝えてくれ」
「承知しました」とグレイ。
「レイン、お前がスキルを使うなとは言わないが、家族以外の前で『鑑定』については話さないこと」
「……わかりました」
肩を落とした自分に、シェザンが明るい声をかける。
「スキルは残念だったかもしれないけど、こんなに小さくてスキル使えるなんてすごいよな。さすが俺の弟!」
思わず小さく笑いそうになった。
グレイもそっと微笑む。
静かな執務室に、ほんの少しの安堵と、まだ消えない不安が静かに漂っていた。
大人の足取りをあえてゆっくりと落とし、五歳児の歩幅に合わせて歩いてくれる。
グレイの背中は大きく、安心感のある存在だが、今日ばかりは緊張が胸の奥を締めつけていた。
廊下の空気は、朝の光が差し込んでいるはずなのに、いつもより静かで重く感じる。
絨毯の上を小さな足で踏みしめながら、俺は心の中で何度も深呼吸を繰り返していた。
執務室の前に着くと、グレイが一度膝を折るようにしゃがみ、「大丈夫ですよ」と小さく囁く。
その仕草に、ほんの少しだけ肩の力が抜けた。
コンコン、とグレイがノックをする。
「レイン様をお連れしました」
「入れ」と父のグラードの低い声。
グレイがそっと扉を開けてくれる。
その手の動きはどこまでも丁寧で、俺の歩みに合わせて一歩後ろをゆっくりついてきてくれる。
その細やかな気遣いが、今の自分には妙にありがたかった。
部屋の中は、磨かれた木の床に重厚な書棚、窓から差す光が机の上に淡く広がっている。
グラードは革張りの椅子に座り、横には長兄のオレファンと次兄のシェザン。
グレイも部屋の隅で控えたままだ。
机の上には、拳ほどの大きさの石。
その一つが、この後の緊張とざわめきを呼び込むことになる。
「レイン、座りなさない」
「はい」
言われて、シェザンの横へと腰を下ろす。
小さなお尻が座面に沈んだ。
俺が座ったところでグラードがこちらを見つめたまま、低い声で問いかけてきた。
「レイン、この石を見てみろ。何かわかるか?」
俺は恐る恐る机の上の石に目を向けた。
(……ただの石、だよな?)
つい口から漏れる。
「石、だよね」
その言葉に、兄たちとグレイの表情がふっと緩んだ。
思わず自分でもホッとしたのが伝わる。
ここで『鑑定』を試したくなり、意識を向ける。
《鉄鉱石/用途:鉄の材料》
(これが鉄鉱石か。前世でも本物を見たことなかったな)
ポツリと言葉が零れ出た。
「これが鉄鉱石かぁ……」
言った瞬間、ピンと張り詰めた空気が戻ってくる。
沈黙が広がり、父がゆっくりと息を吸い込んで吐く。
「レイン。なぜそれが鉄鉱石だと分かる?」
俺は口をつぐんだ。
「……本で見たのか?」
オレファンが言う。
だが、すぐにグレイが補足した。
「いえ、オレファン様。レイン様はまだ絵本しか――文字もようやく習い始めたところでございます」
「では、なぜわかるんだ?」とシェザンも戸惑いを隠せない。
ぐっと詰まりそうになる。
(……これは、まさかやらかしたパターンか?)
石は大丈夫で、鉄鉱石だとダメってこと?なんで?
思わずグラードと目が合う。
真剣なまなざしに、身体がかちりと固まる。
「父上……?」
「レイン、この石のことを分かる範囲で話してごらん」
(わからないって答えるのはマズいよな……もう、誤魔化せないよな、鉄鉱石って言っちゃったし。ここは腹をくくるしかないか)
「鉄鉱石です。鉄の材料になります」
そう答えると、グラードの表情が一層険しくなる。
オレファンもシェザンも、そしてグレイまでも気まずそうな顔をしている。
グラードが静かに息をつくと、少しだけ表情を緩めた。
「……レイン。お前が『鑑定』のスキルを持っていることは、もう分かった」
その言葉に、シェザンが割って入る。
「なんで、レインがスキル持ってんだよ!しかも『鑑定』なんて!選別式もやってねぇのに!」
「黙れ、シェザン」
オレファンが低く遮る。
「兄貴もそう思うだろ?! だから黙れと言っている。父上が話しているんだ」
「……チッ、分かったよ」
シェザンが不満そうに椅子に座り直す。
グラードがしばし黙り、机の上で指を組む。
「この世界では、スキルは八歳の選別式で明らかになるのが常だ。ひとりにつき、ひとつ。多くてもゼロかひとつ。もともと体に宿っているが、それを確認するのが選別式。選別式の前に分かることなど滅多にないが、全くないわけではない」
(選別式ってのがこの世界の常識なのか。選別式前に発動は驚きってわけか……でもそれだけじゃなくて、なんだか重い空気だ)
オレファンがグラードに小声で言う。
「スキルが五歳で発動するのは珍しいですが、まさか『鑑定』とは……」
「ああ。他のスキルであれば、もっと喜べたのだが……『鑑定』は……」
グラードはわずかに視線を落とし、続ける。
「スキルはその人の生き方を大きく左右する。職業に合ったスキルなら大いに役に立つ。
だが、『鑑定』は……見れば分かることしかわからない。
この鉄鉱石も石と言う者もいれば、鉄鉱石だとわかる者もいる。
お前は『鑑定』スキルで鉄鉱石とわかるが、スキルがない人でも鉄鉱石だと分かる。……私の言ってることがわかるか?」
グラードの言葉が静かに落ちる。
その声は怒りでも失望でもなく、ただ事実だけを告げるものだった。
(……なるほどな)
俺は思わず、昔科捜研で上司に「基本を見落とすな」と言われたときのことを思い出す。
どんなに最新技術があっても、現場の誰もが気付く証拠しか見抜けないなら、“特別な力”とは言えない。そういうものなんだろう。
(この世界の“鑑定”は、あくまで“見れば分かることしかわからない”スキル。特別な真実を暴く力じゃない。誰もが知る情報を、ちょっと手早く知れるだけ――)
目の前の鉄鉱石だって、現実世界でも理科好きな子ならすぐに見抜けただろう。
つまり、俺が便利だと思っている『鑑定』は、この世界の人間から見れば、他のスキルほど役に立たない=評価されにくい、という理由も分かる。
(なるほど。ハズレ扱いか。俺には便利に思えるけど、そういうことか)
自分の力の意味を、ひとつ大人の目線で静かに受け止める。
そのうえで、胸の奥にわだかまる気持ちが、少しだけ整理された気がした。
「このことは、屋敷の者たちに口外しないように。グレイ、伝えてくれ」
「承知しました」とグレイ。
「レイン、お前がスキルを使うなとは言わないが、家族以外の前で『鑑定』については話さないこと」
「……わかりました」
肩を落とした自分に、シェザンが明るい声をかける。
「スキルは残念だったかもしれないけど、こんなに小さくてスキル使えるなんてすごいよな。さすが俺の弟!」
思わず小さく笑いそうになった。
グレイもそっと微笑む。
静かな執務室に、ほんの少しの安堵と、まだ消えない不安が静かに漂っていた。