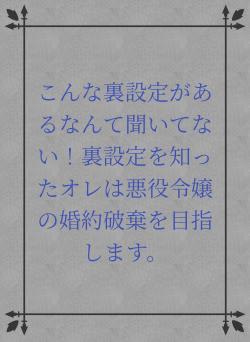――意識の底から、じわりと現実が浮かび上がる。
どこかで聞こえる、人の気配と柔らかな声。
「……坊ちゃま……」
(坊ちゃま?)
まぶたの裏側に残る眩しい光。
ぼやけた視界がゆっくりピントを取り戻していく。
シーツの感触が妙に滑らかで、頬を伝うその柔らかさが、どうにも現実味を持たない。
鼻の奥に残るのは、微かな石鹸と香水の匂い。
どこか懐かしいようで、でも決して知っているものじゃない。
天井は高い。見たこともないような、白くて金色の蔦模様が描かれている。
視界の端に、クリスタルが煌めいた。
大きなシャンデリア――俺の住んでいた部屋じゃない。
(……どこだ、ここ……?)
最初に浮かぶのは、その疑問だった。
体を動かそうとする。
だけど、まるで水中に沈んでいるみたいに、身体が重たい。
ゆっくりと指を動かしてみる。
自分の手が、やけに小さく、細く見えた。
手の甲――色白で、つやのある肌。
これは、俺の手じゃない。
頭の奥がズキリと痛む。
昨日――いや、直前まで俺はどこにいた?
コンビニの袋。
夜の街。
アスファルトの冷たさ、背中に焼けるような激痛――ナイフの刃。
(……刺された……んだっけ?)
記憶の断片が、現実と夢の境目を曖昧にしながら、ゆっくりと浮かび上がってくる。
だが、痛みはない。ただ、体の重さと妙な違和感だけが残っている。
辺りをゆっくり見回す。
そこかしこに、豪奢な家具やレースのカーテン。
窓際には季節外れの花が活けられている。
壁には西洋の絵画と見まがう油絵がかかり、書棚には背表紙の金色が目を刺すほど整然と並んでいた。
(ここ、本当に俺の部屋か?いや、そもそも日本……か?)
混乱と不安が、じわじわと首筋を這い上がってくる。
ベッドサイドで何人かが動いている気配。
誰かが、俺の顔を覗き込んでいた。
見覚えのない、けれどどこか優しげな瞳の女性。
ふくよかな体躯にエプロン、顔立ちは柔和で、心配そうに俺の頬にそっと手を当てている。
そのすぐ隣、控えめに背筋を伸ばした年配の男。
グレーの髪に端正な顔立ち、無表情の中にもちらりと安堵がにじみ、黒い燕尾服が妙に板についていた。
ベッドの反対側には、揃いのメイド服を着た少女たちが二人、髪を肩で切りそろえた子と、二つ結びにした子。
どちらもきちんと背筋を伸ばし、俺をじっと見つめている。
(……誰?)
でも、名前が――知っている、ような……いや、知らないはずなのに、頭の奥で響いてくる。
『メイレル』
『グレイ』
『レミ』
『ニレイ』
なぜだ、今初めて会うはずなのに、この人たちのことを、知っている気がする。
それだけじゃない。
前世としての記憶――天笠玲人。
二十八歳、科捜研の職員だった自分――と、今世の記憶――この屋敷で家族や使用人たちと過ごしてきた日々――が、脳裏に断片的に浮かび上がっては、渦を巻いて混じり合う。
心臓がバクバクとうるさい。
汗ばんだ手のひらを、シーツの上でぎゅっと握る。
喉が、妙に乾く。
「坊ちゃま、お気分はいかがですか?」
目の前のふくよかな女性『メイレル』が、そっと顔を覗き込む。
その視線はどこか慈しみに満ちていた。
反射的に、声を出そうとする。
でも、喉が詰まる。
出てきた声は自分でも驚くほど幼く、高かった。
「……え、と……ここ、は……?」
聞きなれない、自分のものとは思えない声。
メイレルが少し目を潤ませて、やわらかく微笑んだ。
「大丈夫ですよ、坊ちゃま。ここはお屋敷のお部屋です」
その瞬間、胸の奥に、冷たいものが落ちてきた。
ぼんやりとした頭で、どうしても腑に落ちない違和感と、奇妙な懐かしさが入り交じる。
(――俺は……なんでここに?)
断片的な今世の記憶が、ふいに蘇る。
……そうだ。昨夜のことだ。
長兄――オレファンが、仕事帰りに「お土産だ」と有名店の紙袋を渡してくれた。
本当は兄への差し入れだったものを、「レインが好きだったよな」と持ち帰ってくれたらしい。
そのお菓子――大好きなクッキーだった。
「明日まで我慢しなさい」と兄に言われて、乳母のメイレルが「坊ちゃま、こちらでお預かりしますね」と袋を受け取ろうとした。
でも、どうしても待ちきれなくて、手を離さずにそのまま袋を抱え込む。
家族や使用人たちが見守る中、ほとんど反射的に、袋を開けてクッキーをひとつ、ぱくりと口に入れた。
甘さがふわっと広がって、思わず笑顔になる。
――その直後、胸の奥がきゅっと痛んだ。
喉の奥が焼けるように熱くなり、頭がぐらぐらと揺れて、足元が崩れるような感覚。
誰かが「レイン様!?」と叫ぶ声が遠くで響いた。
そのまま、意識がどんどん遠のいていった。
(……まさか、あれが……)
天笠玲人としての知識が、脳裏の片隅でざわめく。
(毒……だったのか?)
自分の記憶に戦慄しながら、ふと、ベッドで眠り続けていたあいだ、どれほど家族や使用人たちが心配していたのか、その空気が部屋の隅々まで沁み込んでいるのを感じた。
(あっちじゃ刺されて、こっちじゃ毒って……俺の人生ハードモードすぎるだろ)
自分で心の中でツッコみながら、ぼんやりと現実と非現実の狭間に漂っていた。 それもまた、『レイン』としての自分の中に自然と流れ込んでくる。
メイドの一人――レミ、という名が頭をよぎる――が、素早く駆け寄り、枕元に手を添えてくれた。
「坊ちゃま、無理はなさらず」
表情はきゅっと引き締まっているが、どこか慣れた手つきでベッドの角度を直し、俺の背中を支えてくれる。
もう一人、ニレイという名の少女が、水差しからグラスに水を注ぐ。
その動きも妙に落ち着いていた。
「お母様を――いえ、奥様をお呼びして参ります」
レミがそう言って部屋を出ていく。
(奥様、か……。俺の母親ってことなのか?)
頭の奥に、ふわりとした記憶が浮かぶ。
金髪で柔らかそうな髪、優しい笑顔――セリィーシェ。
なぜかその名前だけは、すっと思い出せる。
「ご気分はいかがですか?」
執事のグレイが、穏やかな声でそう尋ねてきた。
彼の顔は無表情のようで、けれどその奥に心配が滲んでいる。
「……なんとなく、ぼんやりしてる」
それが精一杯だった。
自分でも、目の前にいる人間の顔や名前が、どうして知っているのか説明できない。
俺は、俺のままなのか?
それとも、『レイン』という誰かになってしまったのか?
気づけば、手が震えていた。シーツを握る指先に、ほんのり汗がにじんでいる。
「少し、呼吸が浅いご様子ですね」
グレイがさりげなく脈を取る。プロの執事らしい、無駄のない動作だ。
「無理なさらず、水をお飲みください」
差し出されたグラスを、ふらつく手で受け取る。
水がのどを滑っていく冷たさが、やけに現実的だ。
(現実……? これが、現実?)
『異世界転生』なんて、あり得ないことだ。
小説やマンガの中だけの話。
なのに今、俺は知らない体で、知らない部屋で、知らない人たちに囲まれて――けれど頭の奥には、知っているという感覚が居座っている。
(俺は……本当に、死んだのか……?)
頭の奥がじんじん痛い。
脳裏に浮かぶのは、アスファルトの上で感じた焼ける痛み。
倒れていくとき、視界の端に見えたナイフ。血の匂い。
今思い返すと、現場にはちゃんと証拠が残っているはずだ。
血痕、凶器、指紋、足跡。
俺が科捜研の職員として培ってきた知識が、なぜか次々と頭に浮かぶ。
(証拠……犯人は、捕まるだろうか……)
ふいに、胸の奥がぎゅっと締めつけられる。
「大丈夫ですよ、坊ちゃま」
隣で、乳母のメイレルがそっと手を握ってくれた。
彼女の手は大きくて、あたたかい。まるで本当の家族のような安心感があった。
「無理になさらず、少しずつでよろしいのです」
(この人たちは、俺のことを『レイン』だと思っている。けど俺は……)
思考がグルグル回る。
その隙間を縫うように、今世の『レイン』という存在の断片的な記憶が流れ込んでくる。
誕生日の豪華なケーキ。
兄たちに囲まれた晩餐。
母――奥様の優しい笑顔。
乳母や執事、メイドたちの温かな声。
同時に、現実味のない違和感が残る。
天笠玲人としての過去が、もう遠く離れてしまったかのように、どこか霞んでいく。
ノックの音が響いた。
「失礼します、奥様をお連れしました」
メイドのレミが、淡いピンク色のドレスに身を包んだ女性を連れてくる。
長い金髪、微笑みの奥にうっすらと疲れがにじんでいる。
(セリィーシェ……奥様。俺の母親……なのか)
セリィーシェはそっとベッドに近寄り、優しく俺の頬に触れた。
「レイン、心配したのよ」
その声が、思いがけず胸に響く。涙がこぼれそうになり、慌てて顔をそむける。
(やめてくれ、こんな時に涙なんて……俺、どうなってんだ……)
「まだ、ぼんやりしているのね。でも、あなたが目を覚ましてくれて、本当に良かったわ」
セリィーシェが、俺の髪をそっと撫でてくれる。
その手つきが、なぜだかものすごく懐かしく感じた。
「……お母様……?」
ぽつりと、口をついて出た。自分でも信じられないくらい自然な呼び方だった。
「ええ、何も心配いらないのよ」
その優しい声が、心に沁みる。混乱の中で、何かが少しほどけた気がした。
「レイン様、ご無理なさらずに」
執事のグレイが、一歩前に出て、控えめに声をかける。
「しばらくは安静が必要です。医師と治癒師が到着いたしますので、ご安心を」
メイドたちが部屋の隅で控えながら、心配そうにこちらをうかがっている。
俺は、しばらくベッドに身を任せるしかなかった。
外から朝日が射し込み、レースのカーテン越しに柔らかな光が差し込む。
ベッドの上で、頭の中は依然ぐるぐると渦巻いている。
(これから、どうすればいい……?)
胸の奥に、言い知れぬ不安と、名状しがたい期待が同居していた。
前の世界――あの夜、自分は刺されて、結局、犯人をこの手で捕まえることはできなかった。
(あれだけ証拠も痕跡も残したのに……死んでしまったら、もう自分じゃ何もできないのか)
でも、茅田たちがきっと見つけてくれる。証拠は現場に残した。
自分が生きていたら――きっと自分で見つけ出せたのに。
(もし、死ななければ……俺が自分で証拠をたどって、犯人にたどり着いたはずなのに……あ~くそっ!茅田ぁ~頼むぜ、俺を刺した犯人、捕まえる証拠。見つけてくれよ)
でも――もし、こっちの世界なら。
前の世界みたいに、現場を駆けずり回って証拠を集めて、自分の手で事件を解決できるかもしれない。毒を盛った犯人だって――。
……けど、ALSもパソコンも、DNAデータベースもなければ、証拠品の管理番号もない。
そもそも自分は今、子供の身体。
(……無理だよな、そんなの)
それでも、胸の奥で、小さな期待が消えきれずに燻っている。
ぼんやりとベッドに横たわりながら、ため息混じりに天井を見つめる。
――その時、不意に。
ふと、頭の奥に「鑑定」という言葉が浮かぶ。
(……鑑定、できたら――)
そんなふうに思った、その瞬間。
――ピン、と何かが頭の中で弾けた。
無意識に視線がテーブルの上へと動く。
そこに置かれた水差しを見つめた瞬間、まるで空中に浮かぶ文字のように、小さな情報がふわりと現れる。
《水差し:陶器製/用途:飲料用》
(……え?)
思わず二度見する。
たしかに水差しの上に、文字が浮かんでいる――しかも頭の中に、何か知識が流れ込むような不思議な感覚がある。
他のものにも……と視線を動かしてみるが、何も起こらない。
(今の、なんだったんだ……?)
ただの幻覚かもしれない、でも、はっきりと情報が頭に入ってくる感触が残っている。
もし、これが『鑑定』なら……。
こっちの世界でも「証拠から真実を突き止める」ことができるのかもしれない。
恐怖と興奮、そして現実感のなさと妙な納得感が入り混じる。
(本当に、俺にできるのか……?)
自分の中の職業的な癖が、思わず静かに目を覚ます。
だが、同時に、今この世界で生きていく覚悟も、少しずつ湧き上がっていた。
混乱の渦中、ふと自分の手を見下ろし、小さなため息をひとつ。
(……参ったな。俺、どうなるんだろう)
でも――絶対に、この状況、証拠と真実を見逃すことだけはしない。
ぼんやりと朝の光に包まれながら、俺は知らない天井をもう一度、じっと見つめた。
どこかで聞こえる、人の気配と柔らかな声。
「……坊ちゃま……」
(坊ちゃま?)
まぶたの裏側に残る眩しい光。
ぼやけた視界がゆっくりピントを取り戻していく。
シーツの感触が妙に滑らかで、頬を伝うその柔らかさが、どうにも現実味を持たない。
鼻の奥に残るのは、微かな石鹸と香水の匂い。
どこか懐かしいようで、でも決して知っているものじゃない。
天井は高い。見たこともないような、白くて金色の蔦模様が描かれている。
視界の端に、クリスタルが煌めいた。
大きなシャンデリア――俺の住んでいた部屋じゃない。
(……どこだ、ここ……?)
最初に浮かぶのは、その疑問だった。
体を動かそうとする。
だけど、まるで水中に沈んでいるみたいに、身体が重たい。
ゆっくりと指を動かしてみる。
自分の手が、やけに小さく、細く見えた。
手の甲――色白で、つやのある肌。
これは、俺の手じゃない。
頭の奥がズキリと痛む。
昨日――いや、直前まで俺はどこにいた?
コンビニの袋。
夜の街。
アスファルトの冷たさ、背中に焼けるような激痛――ナイフの刃。
(……刺された……んだっけ?)
記憶の断片が、現実と夢の境目を曖昧にしながら、ゆっくりと浮かび上がってくる。
だが、痛みはない。ただ、体の重さと妙な違和感だけが残っている。
辺りをゆっくり見回す。
そこかしこに、豪奢な家具やレースのカーテン。
窓際には季節外れの花が活けられている。
壁には西洋の絵画と見まがう油絵がかかり、書棚には背表紙の金色が目を刺すほど整然と並んでいた。
(ここ、本当に俺の部屋か?いや、そもそも日本……か?)
混乱と不安が、じわじわと首筋を這い上がってくる。
ベッドサイドで何人かが動いている気配。
誰かが、俺の顔を覗き込んでいた。
見覚えのない、けれどどこか優しげな瞳の女性。
ふくよかな体躯にエプロン、顔立ちは柔和で、心配そうに俺の頬にそっと手を当てている。
そのすぐ隣、控えめに背筋を伸ばした年配の男。
グレーの髪に端正な顔立ち、無表情の中にもちらりと安堵がにじみ、黒い燕尾服が妙に板についていた。
ベッドの反対側には、揃いのメイド服を着た少女たちが二人、髪を肩で切りそろえた子と、二つ結びにした子。
どちらもきちんと背筋を伸ばし、俺をじっと見つめている。
(……誰?)
でも、名前が――知っている、ような……いや、知らないはずなのに、頭の奥で響いてくる。
『メイレル』
『グレイ』
『レミ』
『ニレイ』
なぜだ、今初めて会うはずなのに、この人たちのことを、知っている気がする。
それだけじゃない。
前世としての記憶――天笠玲人。
二十八歳、科捜研の職員だった自分――と、今世の記憶――この屋敷で家族や使用人たちと過ごしてきた日々――が、脳裏に断片的に浮かび上がっては、渦を巻いて混じり合う。
心臓がバクバクとうるさい。
汗ばんだ手のひらを、シーツの上でぎゅっと握る。
喉が、妙に乾く。
「坊ちゃま、お気分はいかがですか?」
目の前のふくよかな女性『メイレル』が、そっと顔を覗き込む。
その視線はどこか慈しみに満ちていた。
反射的に、声を出そうとする。
でも、喉が詰まる。
出てきた声は自分でも驚くほど幼く、高かった。
「……え、と……ここ、は……?」
聞きなれない、自分のものとは思えない声。
メイレルが少し目を潤ませて、やわらかく微笑んだ。
「大丈夫ですよ、坊ちゃま。ここはお屋敷のお部屋です」
その瞬間、胸の奥に、冷たいものが落ちてきた。
ぼんやりとした頭で、どうしても腑に落ちない違和感と、奇妙な懐かしさが入り交じる。
(――俺は……なんでここに?)
断片的な今世の記憶が、ふいに蘇る。
……そうだ。昨夜のことだ。
長兄――オレファンが、仕事帰りに「お土産だ」と有名店の紙袋を渡してくれた。
本当は兄への差し入れだったものを、「レインが好きだったよな」と持ち帰ってくれたらしい。
そのお菓子――大好きなクッキーだった。
「明日まで我慢しなさい」と兄に言われて、乳母のメイレルが「坊ちゃま、こちらでお預かりしますね」と袋を受け取ろうとした。
でも、どうしても待ちきれなくて、手を離さずにそのまま袋を抱え込む。
家族や使用人たちが見守る中、ほとんど反射的に、袋を開けてクッキーをひとつ、ぱくりと口に入れた。
甘さがふわっと広がって、思わず笑顔になる。
――その直後、胸の奥がきゅっと痛んだ。
喉の奥が焼けるように熱くなり、頭がぐらぐらと揺れて、足元が崩れるような感覚。
誰かが「レイン様!?」と叫ぶ声が遠くで響いた。
そのまま、意識がどんどん遠のいていった。
(……まさか、あれが……)
天笠玲人としての知識が、脳裏の片隅でざわめく。
(毒……だったのか?)
自分の記憶に戦慄しながら、ふと、ベッドで眠り続けていたあいだ、どれほど家族や使用人たちが心配していたのか、その空気が部屋の隅々まで沁み込んでいるのを感じた。
(あっちじゃ刺されて、こっちじゃ毒って……俺の人生ハードモードすぎるだろ)
自分で心の中でツッコみながら、ぼんやりと現実と非現実の狭間に漂っていた。 それもまた、『レイン』としての自分の中に自然と流れ込んでくる。
メイドの一人――レミ、という名が頭をよぎる――が、素早く駆け寄り、枕元に手を添えてくれた。
「坊ちゃま、無理はなさらず」
表情はきゅっと引き締まっているが、どこか慣れた手つきでベッドの角度を直し、俺の背中を支えてくれる。
もう一人、ニレイという名の少女が、水差しからグラスに水を注ぐ。
その動きも妙に落ち着いていた。
「お母様を――いえ、奥様をお呼びして参ります」
レミがそう言って部屋を出ていく。
(奥様、か……。俺の母親ってことなのか?)
頭の奥に、ふわりとした記憶が浮かぶ。
金髪で柔らかそうな髪、優しい笑顔――セリィーシェ。
なぜかその名前だけは、すっと思い出せる。
「ご気分はいかがですか?」
執事のグレイが、穏やかな声でそう尋ねてきた。
彼の顔は無表情のようで、けれどその奥に心配が滲んでいる。
「……なんとなく、ぼんやりしてる」
それが精一杯だった。
自分でも、目の前にいる人間の顔や名前が、どうして知っているのか説明できない。
俺は、俺のままなのか?
それとも、『レイン』という誰かになってしまったのか?
気づけば、手が震えていた。シーツを握る指先に、ほんのり汗がにじんでいる。
「少し、呼吸が浅いご様子ですね」
グレイがさりげなく脈を取る。プロの執事らしい、無駄のない動作だ。
「無理なさらず、水をお飲みください」
差し出されたグラスを、ふらつく手で受け取る。
水がのどを滑っていく冷たさが、やけに現実的だ。
(現実……? これが、現実?)
『異世界転生』なんて、あり得ないことだ。
小説やマンガの中だけの話。
なのに今、俺は知らない体で、知らない部屋で、知らない人たちに囲まれて――けれど頭の奥には、知っているという感覚が居座っている。
(俺は……本当に、死んだのか……?)
頭の奥がじんじん痛い。
脳裏に浮かぶのは、アスファルトの上で感じた焼ける痛み。
倒れていくとき、視界の端に見えたナイフ。血の匂い。
今思い返すと、現場にはちゃんと証拠が残っているはずだ。
血痕、凶器、指紋、足跡。
俺が科捜研の職員として培ってきた知識が、なぜか次々と頭に浮かぶ。
(証拠……犯人は、捕まるだろうか……)
ふいに、胸の奥がぎゅっと締めつけられる。
「大丈夫ですよ、坊ちゃま」
隣で、乳母のメイレルがそっと手を握ってくれた。
彼女の手は大きくて、あたたかい。まるで本当の家族のような安心感があった。
「無理になさらず、少しずつでよろしいのです」
(この人たちは、俺のことを『レイン』だと思っている。けど俺は……)
思考がグルグル回る。
その隙間を縫うように、今世の『レイン』という存在の断片的な記憶が流れ込んでくる。
誕生日の豪華なケーキ。
兄たちに囲まれた晩餐。
母――奥様の優しい笑顔。
乳母や執事、メイドたちの温かな声。
同時に、現実味のない違和感が残る。
天笠玲人としての過去が、もう遠く離れてしまったかのように、どこか霞んでいく。
ノックの音が響いた。
「失礼します、奥様をお連れしました」
メイドのレミが、淡いピンク色のドレスに身を包んだ女性を連れてくる。
長い金髪、微笑みの奥にうっすらと疲れがにじんでいる。
(セリィーシェ……奥様。俺の母親……なのか)
セリィーシェはそっとベッドに近寄り、優しく俺の頬に触れた。
「レイン、心配したのよ」
その声が、思いがけず胸に響く。涙がこぼれそうになり、慌てて顔をそむける。
(やめてくれ、こんな時に涙なんて……俺、どうなってんだ……)
「まだ、ぼんやりしているのね。でも、あなたが目を覚ましてくれて、本当に良かったわ」
セリィーシェが、俺の髪をそっと撫でてくれる。
その手つきが、なぜだかものすごく懐かしく感じた。
「……お母様……?」
ぽつりと、口をついて出た。自分でも信じられないくらい自然な呼び方だった。
「ええ、何も心配いらないのよ」
その優しい声が、心に沁みる。混乱の中で、何かが少しほどけた気がした。
「レイン様、ご無理なさらずに」
執事のグレイが、一歩前に出て、控えめに声をかける。
「しばらくは安静が必要です。医師と治癒師が到着いたしますので、ご安心を」
メイドたちが部屋の隅で控えながら、心配そうにこちらをうかがっている。
俺は、しばらくベッドに身を任せるしかなかった。
外から朝日が射し込み、レースのカーテン越しに柔らかな光が差し込む。
ベッドの上で、頭の中は依然ぐるぐると渦巻いている。
(これから、どうすればいい……?)
胸の奥に、言い知れぬ不安と、名状しがたい期待が同居していた。
前の世界――あの夜、自分は刺されて、結局、犯人をこの手で捕まえることはできなかった。
(あれだけ証拠も痕跡も残したのに……死んでしまったら、もう自分じゃ何もできないのか)
でも、茅田たちがきっと見つけてくれる。証拠は現場に残した。
自分が生きていたら――きっと自分で見つけ出せたのに。
(もし、死ななければ……俺が自分で証拠をたどって、犯人にたどり着いたはずなのに……あ~くそっ!茅田ぁ~頼むぜ、俺を刺した犯人、捕まえる証拠。見つけてくれよ)
でも――もし、こっちの世界なら。
前の世界みたいに、現場を駆けずり回って証拠を集めて、自分の手で事件を解決できるかもしれない。毒を盛った犯人だって――。
……けど、ALSもパソコンも、DNAデータベースもなければ、証拠品の管理番号もない。
そもそも自分は今、子供の身体。
(……無理だよな、そんなの)
それでも、胸の奥で、小さな期待が消えきれずに燻っている。
ぼんやりとベッドに横たわりながら、ため息混じりに天井を見つめる。
――その時、不意に。
ふと、頭の奥に「鑑定」という言葉が浮かぶ。
(……鑑定、できたら――)
そんなふうに思った、その瞬間。
――ピン、と何かが頭の中で弾けた。
無意識に視線がテーブルの上へと動く。
そこに置かれた水差しを見つめた瞬間、まるで空中に浮かぶ文字のように、小さな情報がふわりと現れる。
《水差し:陶器製/用途:飲料用》
(……え?)
思わず二度見する。
たしかに水差しの上に、文字が浮かんでいる――しかも頭の中に、何か知識が流れ込むような不思議な感覚がある。
他のものにも……と視線を動かしてみるが、何も起こらない。
(今の、なんだったんだ……?)
ただの幻覚かもしれない、でも、はっきりと情報が頭に入ってくる感触が残っている。
もし、これが『鑑定』なら……。
こっちの世界でも「証拠から真実を突き止める」ことができるのかもしれない。
恐怖と興奮、そして現実感のなさと妙な納得感が入り混じる。
(本当に、俺にできるのか……?)
自分の中の職業的な癖が、思わず静かに目を覚ます。
だが、同時に、今この世界で生きていく覚悟も、少しずつ湧き上がっていた。
混乱の渦中、ふと自分の手を見下ろし、小さなため息をひとつ。
(……参ったな。俺、どうなるんだろう)
でも――絶対に、この状況、証拠と真実を見逃すことだけはしない。
ぼんやりと朝の光に包まれながら、俺は知らない天井をもう一度、じっと見つめた。