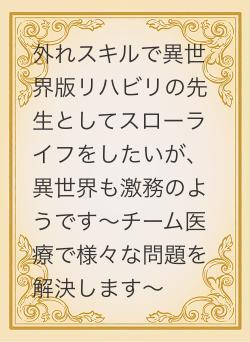「うっ……」
何日も徹夜したかのような重い頭痛に襲われる。
この体になってから、色んなことで頭が痛いな。
誰にも起こされていないところを見ると、あのメイドも動けない状況なんだろう。
ゆっくりと体を起こすと、早速スキルで分解作業に取りかかる。
「ぐへへへ、アセチル基を取り出すには……。おっ、リンゴ酢があるならいけるか?」
この世界でも、食品の保存や防腐するために酢は存在している。
リンゴ酢からは酢酸が抽出できていた。
酢酸の分子構造はシンプルでアセチル基が取り出しやすい印象がある。
機械を使った抽出や分解の方法を知らなくても、スキルでどうにかなるのが便利なところだ。
その分魔力の消費は多くなる。
頭の奥がズキズキとするが、俺の求めていたものがやっとできた。
「あとはフェノール基……」
俺が作ろうとしていたのは、アセトアミノフェンという解熱剤だ。
一般的にはタイレノールやカロナールと呼ばれているだろう。
アミノ基とアセチル基があれば、アセトアミノ基を合成して作ることができそうな気がする。
そこにフェノール基を含めた3つでアセトアミノフェンができている。
ただ、フェノール基をどうやって入手すれば良いのだろうか。
フェノール基が含まれるフェノール類は木材などに含まれている。
ただ、フェノール類はどこの資料を見ても抽出されていなかった。
「この世界に薬や消毒薬はないのか?」
部屋の中に何かないか探していると、瓶に入った液体を見つけた。
「これがこの世界の薬か?」
この世界の治療は基本ポーションが使われている。
ポーションからも抽出していたことはあるのか、紙にメモはしてあった。
ただ、エーテルエキスやマナエッセンスなど聞いたことない成分が抽出されるようだ。
それに派手な色をしている薬を飲んでいることに驚きだ。
着色している薬は薬効ではなく、識別するためにつけられていたりする。
「こっちのは何だ?」
黒く濁った水のようなものが入った瓶もあるが、メディスンの記憶の中にあるポーションとは違うようだ。
ポーションって言ったら赤色か青色が定番だ。
ゲームの中で出てきたポーションもそんな色をしていた。
ひょっとしたらメディスンが作った新しいポーションとかだろうか。
色味からして毒の可能性がある。
一度分解してみようとするが、消すことはできない。
メディスンが作った毒は基本分解ができるため、合成してできた毒薬ではないようだ。
それなら一度抽出してみれば、成分から予測はできるかもしれない。
【フェノール類を抽出しました】
「ぐへへへ、フェノール基ができるぞ」
まさかフェノール類が手に入るとは思いもしなかった。
液体の中身は色からして木酢液かもしれない。
どこかで木酢液をアルコール消毒のように、消毒薬として使っていた話を聞いたことがある。
これで材料は全て揃ったはずだ。
あとはスキルに頼るしかない。
俺はできたばかりの分解成分を合成させることにした。
「あれ……合成できないのか?」
だが、いくら合成しようとしても、合成はできないようだ。
「じゃあ、二つはどうだ?」
フェノール基とアミノ基だと合成できるらしい。
そもそも合成できないのか、スキルの影響で2つまでしかできないのかはわからない。
ただ、ここまできたらあとはアセチル基を追加で合成するだけだ。
【製成結果】
(フェノール基+アミノ基)+アセチル基
製成物:魔力アセトアミノフェン
効果:魔力が中枢神経に作用し、プロスタグランジンの合成を抑え、痛みや発熱を和らげる。
「ぐへへへへへへへへ!」
俺はできた製成結果を見て声をあげる。
まさか本当にこの世界でアセトアミノフェンができるとは思いもしなかった。
魔力って文字が付いているのはスキルの影響だろうか。
普通に作るには作業をするための道具やいくつもの工程が必要となる。
それにまさか粉状で出てくるところが、ゲームの中の薬師って感じだな。
これが俺の才能ってことだろう。
笑いが止まらずずっとニヤニヤしてしまう。
――ガチャ!
「メディスン様……」
扉を開けたのは前に会ったメイドだ。
「急いで作りましたが……お味の方は……」
まだ熱があるのかふらふらとしている。
その手にはスープが入った皿を持っていた。
意識朦朧とする中、スープを作って持ってきたのだろう。
だが、立っているのも辛いのかそのまま倒れていく。
俺はすぐに支えるが、スープはそのまま床に垂れていた。
「せっかく作ってくれたのに申し訳ないな」
すぐにベッドに寝かせると、作ったばかりの魔力アセトアミノフェンを準備する。
だが、本当に体に問題ないのか気になるところだ。
忘れていたが本来のメディスンって毒使いだからな。
俺は一度指につけて舐めることにした。
味は特に変わった様子もなく、薬っぽい独特の苦さを感じる。
即時性の高い毒ならすぐに反応は出るし、最低でも胃や腸から吸収されれば数時間後には反応が出るだろう。
しばらくの間は体を冷やすことだけをしよう。
幸い外には雪もあるため、雪解け水で布を浸せば冷やすことはできる。
「んっ……」
「起きたか?」
「メディスン様!?」
すぐに体を起こそうとするが、その場で止めて寝かせる。
まだ、熱が下がったわけではないからな。
「薬を作ったんだけど飲むか?」
「私を実験台にするつもりですか?」
やはりそういう反応をするのは仕方ない。
離れの屋敷でずっと実験をしていたからな。
ただ、あれから二時間ほど経っており、俺の体は異変を感じなかった。
あとは彼女自身に飲むか判断してもらおう。
「メディスン様の専属メイド……これぐらいは覚悟しております」
一瞬にして表情が切り替わると、俺から薬を受け取り、すぐに口の中に入れた。
薬特有の苦味に顔を歪めるが、まだ熱が高いのかそのまま倒れていく。
「ぐへへへ、これでうまくいく」
「やっぱり毒なのね……」
薬を飲めば少しは熱が下がるだろう。
雪の病魔が俺の思っている病気であればな……。
何日も徹夜したかのような重い頭痛に襲われる。
この体になってから、色んなことで頭が痛いな。
誰にも起こされていないところを見ると、あのメイドも動けない状況なんだろう。
ゆっくりと体を起こすと、早速スキルで分解作業に取りかかる。
「ぐへへへ、アセチル基を取り出すには……。おっ、リンゴ酢があるならいけるか?」
この世界でも、食品の保存や防腐するために酢は存在している。
リンゴ酢からは酢酸が抽出できていた。
酢酸の分子構造はシンプルでアセチル基が取り出しやすい印象がある。
機械を使った抽出や分解の方法を知らなくても、スキルでどうにかなるのが便利なところだ。
その分魔力の消費は多くなる。
頭の奥がズキズキとするが、俺の求めていたものがやっとできた。
「あとはフェノール基……」
俺が作ろうとしていたのは、アセトアミノフェンという解熱剤だ。
一般的にはタイレノールやカロナールと呼ばれているだろう。
アミノ基とアセチル基があれば、アセトアミノ基を合成して作ることができそうな気がする。
そこにフェノール基を含めた3つでアセトアミノフェンができている。
ただ、フェノール基をどうやって入手すれば良いのだろうか。
フェノール基が含まれるフェノール類は木材などに含まれている。
ただ、フェノール類はどこの資料を見ても抽出されていなかった。
「この世界に薬や消毒薬はないのか?」
部屋の中に何かないか探していると、瓶に入った液体を見つけた。
「これがこの世界の薬か?」
この世界の治療は基本ポーションが使われている。
ポーションからも抽出していたことはあるのか、紙にメモはしてあった。
ただ、エーテルエキスやマナエッセンスなど聞いたことない成分が抽出されるようだ。
それに派手な色をしている薬を飲んでいることに驚きだ。
着色している薬は薬効ではなく、識別するためにつけられていたりする。
「こっちのは何だ?」
黒く濁った水のようなものが入った瓶もあるが、メディスンの記憶の中にあるポーションとは違うようだ。
ポーションって言ったら赤色か青色が定番だ。
ゲームの中で出てきたポーションもそんな色をしていた。
ひょっとしたらメディスンが作った新しいポーションとかだろうか。
色味からして毒の可能性がある。
一度分解してみようとするが、消すことはできない。
メディスンが作った毒は基本分解ができるため、合成してできた毒薬ではないようだ。
それなら一度抽出してみれば、成分から予測はできるかもしれない。
【フェノール類を抽出しました】
「ぐへへへ、フェノール基ができるぞ」
まさかフェノール類が手に入るとは思いもしなかった。
液体の中身は色からして木酢液かもしれない。
どこかで木酢液をアルコール消毒のように、消毒薬として使っていた話を聞いたことがある。
これで材料は全て揃ったはずだ。
あとはスキルに頼るしかない。
俺はできたばかりの分解成分を合成させることにした。
「あれ……合成できないのか?」
だが、いくら合成しようとしても、合成はできないようだ。
「じゃあ、二つはどうだ?」
フェノール基とアミノ基だと合成できるらしい。
そもそも合成できないのか、スキルの影響で2つまでしかできないのかはわからない。
ただ、ここまできたらあとはアセチル基を追加で合成するだけだ。
【製成結果】
(フェノール基+アミノ基)+アセチル基
製成物:魔力アセトアミノフェン
効果:魔力が中枢神経に作用し、プロスタグランジンの合成を抑え、痛みや発熱を和らげる。
「ぐへへへへへへへへ!」
俺はできた製成結果を見て声をあげる。
まさか本当にこの世界でアセトアミノフェンができるとは思いもしなかった。
魔力って文字が付いているのはスキルの影響だろうか。
普通に作るには作業をするための道具やいくつもの工程が必要となる。
それにまさか粉状で出てくるところが、ゲームの中の薬師って感じだな。
これが俺の才能ってことだろう。
笑いが止まらずずっとニヤニヤしてしまう。
――ガチャ!
「メディスン様……」
扉を開けたのは前に会ったメイドだ。
「急いで作りましたが……お味の方は……」
まだ熱があるのかふらふらとしている。
その手にはスープが入った皿を持っていた。
意識朦朧とする中、スープを作って持ってきたのだろう。
だが、立っているのも辛いのかそのまま倒れていく。
俺はすぐに支えるが、スープはそのまま床に垂れていた。
「せっかく作ってくれたのに申し訳ないな」
すぐにベッドに寝かせると、作ったばかりの魔力アセトアミノフェンを準備する。
だが、本当に体に問題ないのか気になるところだ。
忘れていたが本来のメディスンって毒使いだからな。
俺は一度指につけて舐めることにした。
味は特に変わった様子もなく、薬っぽい独特の苦さを感じる。
即時性の高い毒ならすぐに反応は出るし、最低でも胃や腸から吸収されれば数時間後には反応が出るだろう。
しばらくの間は体を冷やすことだけをしよう。
幸い外には雪もあるため、雪解け水で布を浸せば冷やすことはできる。
「んっ……」
「起きたか?」
「メディスン様!?」
すぐに体を起こそうとするが、その場で止めて寝かせる。
まだ、熱が下がったわけではないからな。
「薬を作ったんだけど飲むか?」
「私を実験台にするつもりですか?」
やはりそういう反応をするのは仕方ない。
離れの屋敷でずっと実験をしていたからな。
ただ、あれから二時間ほど経っており、俺の体は異変を感じなかった。
あとは彼女自身に飲むか判断してもらおう。
「メディスン様の専属メイド……これぐらいは覚悟しております」
一瞬にして表情が切り替わると、俺から薬を受け取り、すぐに口の中に入れた。
薬特有の苦味に顔を歪めるが、まだ熱が高いのかそのまま倒れていく。
「ぐへへへ、これでうまくいく」
「やっぱり毒なのね……」
薬を飲めば少しは熱が下がるだろう。
雪の病魔が俺の思っている病気であればな……。