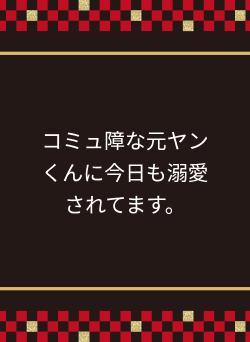体育館を離れ、選手控え室となっているテントのうち、手近なものに入った。
中に入ると自動で魔術が発動し、内からロックがかかった。
テント自体が魔術道具のようだ。
「ロイ…」
ロイが振り返ると、私は言葉をつまらせた。
涼やかな色の瞳なのに、正反対の熱を帯び、私の瞳をとらえて離さない。
鼓動が激しく波打ち、呼吸が追い付かない。
「や…約束…だから…目を閉じて。」
声…震えた…。
ロイは近くの椅子に座ると、言った通りに目を閉じた。
先ほどまでの歓声に包まれた体育館と一変、静かすぎる沈黙が私の鼓動をさらに早める。
き…キス…って
どうするの!?
唇同士を合わせればいいのよね?
そっと触れるように…でいいのよね?
ロイの頬に触れ、ゆっくり顔を近づける。
心臓がつぶれそう…。
目を閉じ、そっと唇同士を触れ合わせた。
柔らかくて熱い唇の感触が心の奥にそっと染みていく。
恥ずかしくて死にそうだわ…!!
すぐに顔を遠ざけると、ロイは金色のまつげをゆっくりと上げた。
まだなお熱を帯びる瞳が私を正面から捉える。
「や…約束は守ったわよ…。」
「ああ」
ロイは顔を手で覆い、ため息をついた。
「なんか…怒ってる…?」
「いや…めちゃくちゃ興奮した。」
「へ!!?」
ロイは座ったまま私の腰に腕を回し、引き寄せた。
上目遣いで私の顔を覗き込む。
「なぁ、ハナ。」
「っ…何…」
「お前、俺のこと好きだろ?」
「っ…」
ついさっき自分の気持ちに気づいたばかりなのに、あっという間にバレてしまったわ!!
私は何も言えずに顔をそらした。
「ハハッ…肯定してるようなもんだろ。」
ロイは軽やかに笑うと、私の腰をさらに強く引き寄せた。
「っな…」
勢いでロイの膝の上に座ってしまった。
「ごめんなさい!あの…立つわ!」
「いい。」
「でも…」
「こんな幸せなことあるんだな…」
「……」
「なぁ、もう一回キスしてくれ。」
「っな!約束は守ったじゃない!」
「頼む」
下から覗き込むロイの表情は新鮮で、そんな顔でお願いされたら断れない。
「っ…わかったわよ!」
私はもう一度ロイの唇に自分のそれを触れさせた。
その瞬間、頭を引き寄せられ、深いキスに豹変する。
「ぷはっ、ろ、ロイ…んんっ…!」
舌がからめとられ、電撃が走ったような衝撃が背筋を走る。
私の右手はロイの左手に撫でられ、くすぐったいような気持ちいいような感覚に抗えない。
「ハナ…ハナ」
愛おしそうに私を呼ぶ声
ロイが私の髪留めをほどき、ウェーブのかかった栗毛がパサリと広がる。
髪をすき、後頭部をなぞる大きな手のひら。
「んっ…ぅん…」
何度も何度も絶え間なく降り注ぐキス。
ロイの膝に座っていなかったら確実に腰が抜けていたわ…。
恥ずかしすぎて今すぐ逃げ出したいのに…
気持ちいいと思ってしまっている。
私はしがみつくようにロイの服を掴んで離さなかった。
「ハナ…大丈夫か?」
キスの雨がやみ、乱れた呼吸を整える。
「…ハァ…ハァ…」
「悪い。調子乗った…」
ロイはばつが悪そうに目をそらした。
「…謝らなくていいわ。
ロイ…私、ちゃんと言う…。」
「何を?」
「…私、ロイのことが好き。
あなたが私の幸せを祈ってくれたように、
今世では私があなたの幸せを叶えるわ。」
「……」
思いきってロイの背中に腕を回して抱きついた。
「好きよ、ロイ」
「お前は…本当にカッコいいな…。」
「だから…あの…」
「なんだ?」
「っと…」
「え?」
「…もっと…キスして」
こんないやらしいこと言うなんて、自分が信じられない。
顔が見られない…
ロイを抱き締める力を強め、彼の肩に顔をうずめる。
ロイの心臓が私と同じ速さで動いているのを感じる。
そのことがたまらなく愛おしい。
「お前は俺を殺す気か?」
ロイはため息をつくと、私を強く抱き締めた。
お互いがしがみつくように抱き留め合う。
ロイにぎゅっとされる感覚…好きだわ。
しばらく抱き締め合う心地よさに浸っていると、ロイが再びため息をついて私を膝の上から下ろした。
「これ以上こんな密室にいたら我慢できなくなるな。」
「っ我慢なんてしてないじゃない!」
「お子様にはまだ早いもっと過激なことがあんだよ。」
「っ!!」
ロイは不敵な笑顔を浮かべる。
「もうちょっとハナが慣れるまで待ってやるよ。」
「な…何を上から目線で…!」
「いつも俺のキスに腰立たなくなってるくせに。」
「う…うるさい!」
ロイは膝をポンと打ち、椅子から立ち上がった。
「そろそろ表彰式だ。」
私だけが不慣れでロイに主導権をとられてる状況が、なんか悔しいわ…。
こんなところでも負けず嫌いの性格が出てしまう。
よし…!
テントから出ようとするロイの手をとり
「ん?」
振り向いたところで足をかけ、体重をかけて組伏せた。
「なにすんだ…「余裕ぶった仕返しよ」
倒れたロイの襟首をつかみキスをして、ふんっと威張って見せた。
「お前…ふざけんなよ…」
ロイは顔を真っ赤にしている。
「フフッ」
ざまあみろだわ!
私は逃げるようにテントから飛び出し、体育館へ走り出した。
自分でもわかるくらい顔が緩んでる。
恥ずかしいのに、嬉しくて嬉しくて、走り出さずにはいられない。
もう一度祈り文を書くなら、私はなんて書くだろうか…
前世、胸の上で静かに優しく燃えて消えていった淡い祈りを、ようやく諦めることができた。
私はこの時、前世の悲劇も転生の真実も忘れて、ただ目の前の幸せに夢中だった。
その真実が悲しみと絶望に包まれていることも知らずに。