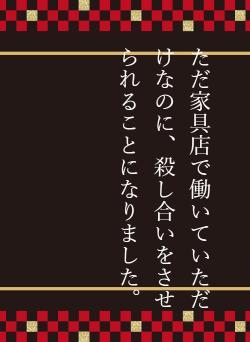「聞きました?最近、近所の公園に夕方から夜まで居るって言う、女性の話」
「聞いたわよー!怖いわよねえ。変質者かしら……」
「でも警察は、害はないって言ってたらしいですよ。誰かが一度、通報したみたい」
「そうは言ってもねえ……。気味が悪いことに変わりは無いのよ全く」
それぞれの手にベビーカーや買い物袋、ビジネスバッグを提げた三人の女性が、マンションの前で歓談している。しかし、その内容は彼女たちにとって穏やかでは無かった。
素性も意図も、何も分からない人物の出現。得体の知れない不気味な存在に、自身や、自身の子供たちへの被害を心配するのは、至極当然であった。
「ねえママー、寒いよお、おなかすいた」
一人の女性の傍に佇んでいた男児が、ぐずりだす。時刻は四時を過ぎていた。
「そうだね、帰っておやつ食べよっか。それではまた。失礼します」
「じゃあねー」
一組の親子が手を繋いでその場を去り、マンション内のエレベーターに乗り込む。残された二人は、もうしばらく話し込んでいた。
「女の人の犯罪者だって最近増えて来てるでしょう。あの子も心配だわ」
片方の女性が、上昇していったエレベーターの方を、思案気に見つめる。もう一人も大きく頷きながら続いた。
「公園はここから目と鼻の先ですからねえ。何かあってからでは遅いというのに……」
女性らは公園に、曇った表情を向ける。
中央にどんと構える桜の木は、葉を全て地に返して、銀色の肌を冷たい空気に晒している。
噂の女性が座っているというベンチは、その木に隠れて、彼女たちからは丁度見えない。それでも二人は、噂の女性の幻影に眉を顰める。
その時、木枯らしがびゅうと吹いた。女性たちは身を震わせ、寒さに耐える。
「寒ーい!私達も帰りましょ」
「ええ、そうですね、年明けすぐの風は骨身に染みます……」
ぶるぶると小刻みに動く身体を両腕で抱えながら、彼女らもエレベーターを呼び出し、乗り込む。狭い密室の束の間の暖にほっと息をつき、それぞれの階へと降りて行った。
まだ、厳冬は始まったばかりだ。
紅華は一人、馴染みの場所に立ち寄った。
小さな砂の粒がじゃりじゃりと音を立てるのを、頭の片隅で拾いながらふらふらとベンチを目指す。
ブランコや鉄棒がぽつぽつとあるだけの、ありふれた公園。昔はジャングルジムや滑り台、広い砂場があったそうだが、安全面から撤去された。
しかし、中央の一本の桜。それが、この公園を彼女にとって、特別なものにしていた。
紅華は、木を正面に臨めるベンチに腰を掛ける。
だが、何をするでもない。温かいコーヒー缶を傾けるでも、本を開くでも、仕事の続きをするためにノートパソコンを開くでもない。
ただ、座り続ける。
時には涙を流すこともある。
ぽつり、ぽつりと、大粒の雫が瞳から溢れてしまう。それでも、彼女は誰に慰めてもらうのでもない。
どれだけ気温が低くても、からっ風が吹いても、紅華は時間さえあれば、このベンチに座っていた。
待っているのだ。ただ一人の男が、この場所に現れることを。
ここは、二人が初めて手を繋いだ所。恋人になった所。そして、初めてキスをした所。
二人のあらゆる初めてが詰まっていて、あらゆる約束が詰まっている地。
だから紅華は、このベンチから、離れられない。
男が消えて、ひと月が経っても。
紅華が琴平に出会ったのは、昨年八月の初め。金曜日。自宅へ向かう道中だった。
労働環境の改善が叫ばれている社会の中、紅華の職場は珍しく黒寄りで、疲弊困憊の日々を送っていた。
退勤が定時の一時間、二時間を過ぎるのは当たり前。休憩も昼食も碌に取れない毎日で、やっと迎えられる週末に、半分意識を飛ばしながら帰宅している最中だった。
道端に、人が転がっている。
ふと目の端に映った物体が人間であることに、久々に心が動いた。驚く、なんて感情が自分の中にまだあったことに、驚いた。
近付いてみるとそれは見ず知らずの男性で、意識が無いようだった。よく見ると、頬が腫れているし、アルコールの匂いがする。
「おーい。大丈夫ですかー?」
ぺちぺちと、腫れて無い方の頬に触れた。
ほんの気まぐれだった。苦痛しか無い日常の中での、ちょっとした刺激のつもりだった。
ぱちり、と開いた男と目を合わすまでは。
なんて、綺麗な瞳だろう。
つい魅入ってしまう程、男の目は綺麗だった。
薄い茶色。言ってしまえばそれだけだが、夜間の少ない光を精一杯に吸い込んだ瞳は、ラメ入りのビロードの様だった。
美しい分繊細で、容易く破けてしまいそうな、脆い輝き。
紅華は、その男を既に放っておけなくなっていた。だから、
「帰る場所がない。泊めて」
そう言われて家に上げるまで、迷いが生じることは一切なかった。
「おはよう、朝ご飯だよ」
「……おはようございます」
エプロンを付けた男に起され、紅華は目を覚ます。
挨拶を交わすようになって、ひと月が経った。
男を拾った翌朝は、ベットですやすやと眠る男の寝顔に、我ながら大胆な事をしたものだと慄いた。
名前も住所も、全く知らない異性だ。そもそも、倒れていた経緯ですら怪しい。何をされるか分からない。物盗り、詐欺、シリアルキラー。想像だけでも、考慮すべき危険は山ほどある。
目を覚ましてきょとんとしている男の顔を見ても、紅華はまだびくびくしていた。
しかし、琴平と名乗った男は、礼儀正しかった。
紅華が距離を大きく取りながら、何故彼がここに居るのかを簡単に説明するや否や、頭を地面に擦り付ける勢いで謝罪を口にした。
うら若き女性の一人部屋に、泊めてくれなど言うべきでは無かった。彼はそう口にしながら、目尻も眉も口元も、顔のあらゆる部位を下げていた。
その表情が、捨てられた子猫のようで、紅華はつい笑ってしまった。
「ごめんね。別にもう若い、なんて歳じゃないから大丈夫」
なんて、付け加えてもしまう。
紅華の笑顔に、男はほっとしたのか、路上で転がっていた理由を話してくれた。
要は、彼は所謂ヒモで、前の家主の新しい彼氏に些か過激な方法を以て追い出されてしまったらしい。そのせいで夕飯にありつけなかった為、適当な通行人を引っ掛けて深夜まで一緒に呑んでいたのだ。
腫れた頬とアルコールの原因が判明しただけで、紅華の不安は大方取り除かれた。
話し方や雰囲気で、何となく悪い人ではなさそうだと判断していた。きっと、昨夜琴平にご飯をおごってくれた人も、彼の人懐っこさや可愛げのある笑顔に絆されたのだろう。
それに、申し訳ないとは言いながらも、
「行くとこないから、もう少しここに居てもいい……?」
と、今度は上目遣いで、まるで餌をねだる犬の様なきらきらの瞳を紅華に向けるのだ。
紅華は、考える間もなく頷いていた。
別に、琴平が演技上手で、騙されてしまっていても良いとさえ考えていた。
楽しみも、生きがいもない人生の最中だ。
それが琴平の手で、強引に、凄惨に終わらせられるのが最悪の結末だとしても、最後に目に移すのが彼の美しい瞳であるのなら、それで満足だとさえ感じた。
しかし琴平は、何日経っても紅華に手を出すどころか、一瞬たりとも触れないように注意を払っていた。
洗面所周りには迂闊に近付かないし、紅華の身支度が完全に終了するまで部屋に籠って、トイレを我慢していたこともあった。
さらに、比較的自由が利く仕事(恐らく、アルバイト)だからと、掃除、洗濯、料理などの家事全般を担ってくれた。
「家に置いてくれているから」
いつか、やんわりと遠慮を口にしたとき、琴平は屈託なく笑った。
正直、激務で身の回りの事まで手が回らなかった紅華にとっては大層有難かった。
どれだけ疲れて帰っても、おかえりと言ってくれる誰かが居る。
それだけで、どれだけ救われたか。
その上、温かくて美味しい食事に、綺麗な部屋、丁寧に畳まれた洋服もついてきた。
紅華の乾いた生活を潤してくれる琴平。
惹かれない訳が無かった。
「すみません」
「……っえ」
二月の初め。
紅華は、この日も桜の木の目の前のベンチに座っていた。
冴え冴えとした空気で、澄み切った夕空。紺の天蓋の裾が、とき色に染まる時刻。
はらはらと涙を流す彼女の傍には、誰も居ない。
静かで孤独な時間を、奥歯を噛んで耐えていた。
が。
突然声をかけられ、しかも複数名の、カメラやもふもふの毛が付いたマイクを手にした集団に囲まれたのだ。
慌てて涙を拭う紅華に、リポーターらしき女性はずけずけと話しかけてくる。
「私達、地元のテレビ局なんですけど、少しお話お伺いしても良いですか?」
「え、ごめんなさい、ええ……、え?」
戸惑っている間に、あれよあれよと取材の準備を進められてしまう。はっと気が付いた時にはもう、断れない状況になっていた。
紅華は仕方なく、リポーターと対話することにした。
だが最初に聞かれたのが、
「どうして、ここに居るんですか?」
という、至極真っ当で、純粋な野次馬根性が透けて見えるものだった。
彼女たち取材班が担当する番組名は、紅華も聞いたことがある。視聴者から番組に寄せられたテーマを深掘り、ある時には投稿者が納得のいく結論を出すこともある。
きっと、この地域に住まう誰かが、番組に投稿したのだろう。
紅華は、喉の奥がきゅっと、熱く、捩じれるのを感じながら、なんとか答えた。
「……恋人を、待っているんです」
「恋人ですか?一体何があったんですか?」
──何があったか。
そんなの、紅華自身が知りたかった。
それでも、空気を悪くしたくない一心で、恐々と口を開く。
「突然、居なくなったんです」
「突然!?それは辛いですね……。いつ頃ですか?」
紅華の低い声に反比例して、わざとらしい程悲痛なテンションで聞き返してくるリポーター。番組を作成する上で必要なリアクションなのだろうが、億劫に感じてしまう。
かと言って、強気に出れない自身の気の弱さも理解している。だから、大人しく彼女らに従うしかない。
「二か月くらい前です。仕事から帰ったら、部屋が真っ暗で──」
そう。真っ暗だった。
暖房も付いていない。人の気配のない、冷蔵庫の中の様に冷え切った部屋に足を踏み入れた瞬間、紅華は悟った。
琴平が、居なくなったことを。
慣れていたはずだった。むしろ、琴平が部屋に居て、待っていてくれたことが奇跡の様な時間だったのだ。
大丈夫、大丈夫。
非日常が、日常に戻っただけだ。何も、驚くことも、悲嘆にくれることもない。
そう言い聞かせるのだが。
「はあっ……はあ……!」
胸の辺りが痛くて堪らない。何とか呼吸をしようとするも、全く酸素が入ってこない。
目の周りが熱い。耳も。喉奥も。
それとは逆に、足先はじくじくとした痺れを伴いながら、どんどん冷えて行く。
いつの間にか、頬に冷たいものが流れていた。
嫌だ。
そう思った瞬間、
「はあっ、はあ、はあ……っ!!」
どたばたと、至る所の扉を開けて、琴平の姿を探す。
寝室、洗面所、クローゼット。果ては、台所の戸棚まで。
居るはずがないと分かっていても、あらゆる扉を開け続けることを止められなかった。気が済まなかった。
仕舞いには、
ばたん!
と大きな音を立てて玄関を開け放し、紅華は裸足で駆け出した。
嫌だ。嫌だ。いやだいやだいやだいやだ。
一人にしないで、琴平。
私は、貴方が居なければ。
寒さや足裏の痛みは感じなかった。いつまでも探し続けられると思った。
だが、日が昇っても、琴平の影も形も掴めなかった。
そうなって初めて、紅華は膝から崩れ落ちたのだ。
『この場所で、彼に言われました。来年の春は、ここでプロポーズするからねって。最近は、桜が咲くのも早いじゃないですか。だから、ここに居れば、会えるかもって』
『なるほど……、そうだったんですね。何と言うか……、頑張ってください。私はこれしか言えませんが、祈っています』
『はは、ごめんなさい、ありがとうございます。頑張りますね』
「以上がVTRになりますが、如何でした?所長」
「いやあ、悲しくも、美しい話ですね……。彼女、恋人と会えると良いのですが……」
「わあっ、所長!?珍しいですね、泣かれるなんて。この番組史上、三回目とかじゃないですか?」
「でも本当に、素晴らしい愛の物語でしたよ。今時こんな健気に……」
「そうですか?まるで夢物語ですけどねえ」
「うわ出た、毒舌芸人らしい嫌味っぷり!」
「いえいえこれは毒舌とかでは無くて、現実的な話ですよ。単純にフラれた、なんてだけじゃなくて。もしかしたらこの世に居ないかもしれないじゃないですか、下手したら。だって、誘拐、拉致、果ては戦争だって起きるような世の中ですよ?」
「そうですけどお……」
「誰か、彼女の目を覚ましてあげた方が良いんじゃないですかね。僕はそう思いますよ」
紅華は、テレビの画面をぶつっと消した。
真っ暗な画面には、紅華の泣き顔だけが映っていた。
琴平が住みついて二か月後、十月。
紅華が休みの日には、二人で良く散歩に出かけていた。
紅華は激務のおかげで、貯蓄だけは些かあった為、本当は遠出しても良かった。しかし、琴平がそれを拒むのだ。
「俺が紅華をエスコートするの!」
これが、彼の主張だった。
紅華が内に秘めた想いに知ってか知らずか、琴平は無邪気にそんなことを言う。紅華としても、一緒に居られるだけで満足だったため、問題なかった。
特に琴平は、近所の公園を気に入っていた。
そこにある、ただ一本だけの桜の木を、愛でていた。
自前の一眼レフカメラで、何枚も写真を取る程に、だ。
ほとんど着の身着のままで道端に転がっていた琴平だったが、唯一鞄に入れていたそのカメラだけは、決して手放すことは無いのだという。
「両親の形見でさ。それに、写真を取るの、すごく好きなんだ」
琴平はそう教えてくれた後、乾いた桜の幹に手を当てながら、昔話をしてくれた。
「俺はね、三百人の命を背負った、生き残りなんだ」
「え?ごめん、どういうこと……?」
「父親と母親と、三人で北海道に行く予定だったんだ。飛行機でね。五歳の時だ。でも、落ちちゃったんだ、その飛行機。生き残ったのは、俺だけ」
「……」
「でも偶然、リュックに入れていたこのカメラは無事だった。父親にせがんで、俺が持つって言い張ったんだよね、確か。そんで、何が起きたか全く分からなかった俺は、何故かそこで写真を撮った。それが、これ」
ごそごそとバッグを漁って、中からぼろぼろの紙切れを取り出す琴平。紅華は恐る恐るそれを受け取った。そして、息を呑む。
原型を留めていない機体の欠片。それらを無数の折れた木々や枝が覆っているが、それでも飛び出た鉄骨の鋭さは隠せていなかった。無数の小さな飛行機の部品が抉れた地面を埋めているが、それに紛れるように埋まっている人体の破片を見つけ、紅華は悲鳴を上げかけた。
だが、それよりも目を惹くものが映っていて、紅華の視線はそこに吸い寄せられる。
目を閉じて、こちらを向いている男性の顔。そこに傷も汚れも無く、まるで眠っているかの様に見える。しかし、写真に写る彼の全身は、それだけだ。
首以降が、紛失している。きっと、落下の衝撃に耐えられなかったことは、想像に難くない。
しかし、頭部だけのはずなのに、不思議と恐怖や嫌悪は感じなかった。むしろ、彼の穏やかな表情と、凄惨な現場の対比が現実離れしていて、美しさすら覚えた。
「これ、父親」
琴平が指をさしたのは、紅華が見つめていた生首だった。
「あ……ごめ」
自身の不謹慎さに咄嗟に謝るが、琴平は無邪気に笑った。
「いや、この写真、俺のお気に入り。上手な構図だろ?」
そう、紅華の好きなきらきらの瞳で語るものだから、そういうものなのだとすぐに納得した。
紅華の中身は、ぐちゃぐちゃだった。琴平が背負った過去の苦しさと、それでも今笑っている彼の強さと、そんな琴平への愛おしさでいっぱいで、泣きそうだった。
でも、ここで泣くのは琴平に失礼だと思った紅華は、震える声で話題を切り替えた。
「それにしても、どうしてその木が好きなの?この時期だと花も咲いていないし、撮り甲斐ないでしょ?他の所に行ってもいいんだよ」
すると琴平は、驚いた表情で紅華の方を向いた。さらに、しばらくじーっと紅華の顔を凝視していたが、不意に、頬を赤らめながら、あーと口ごもる。
不思議に思って紅華が首を傾げていると、琴平は意を決したように口火を切った。
「あの桜、さ。俺、紅華に似てると、思うんだよ。なんか、一見弱そうだけど芯の強い所とか、咲いたら、というか笑ったら綺麗な所とか」
「なっ……」
今度は、紅華が顔を朱色に染める番だった。
琴平から、綺麗と言われた。それだけで悶絶出来るほどだった。
それなのに、
「だからさ、俺と付き合ってよ。俺、紅華のことが、好き」
と、琴平が真剣な表情で両手を握ってきた際には、いよいよ夢を見ているのかとさえ考えた。
しかし、頬をつねっても目を覚ますことは無くて。
何してんの、とつねった頬を琴平に撫でられる始末だった。
夢じゃない、と理解した瞬間、涙が溢れた。
この涙は、許されるはず。
だから、紅華は迷わず答えた。
「ごめんね。私の方が、好きだよ」
と。
琴平は二人の関係に名前が付いても、安直に紅華の肌に触れようとしなかった。
一か月が経って、十一月になっても、手を繋ぐ所までしか進展していない。
紅華も二十台半ばだ。最初に言った通り、本当にうら若き乙女でもないし、全くの初心という訳でもない。
別に手を出してくれても構わないのだけれど。
そう思わないこともないが、こちらから口を出すことでもないし、そもそもそんなの恥ずかしくて出来ない。
と、そんな事を夕食の後片付けをしながら考えていると、
「ねえ、紅華。コンビニ行きたい!」
テレビの前に座り込んだ琴平が、目をきらきらさせながら、こちらを振り向き言う。
「ええ?晩御飯、足りなかった?」
濡れたお皿を水きりに立てかけながら、紅華も振り返り、尋ねた。
「違う違う!ほらCM見て!」
琴平が指を示す方に、紅華も視線を投げる。そこには、全国展開されているコンビニエンスストアで、冬季限定のあんまんが販売され始めたことを知らせる映像が流れていた。
「あんまん食べたい!買い行こ!」
「さっき沢山麻婆豆腐食べてたじゃない……」
「甘いものは別腹なの!ほら、早く!売り切れちゃう」
琴平は、あれよあれよという間に自分と紅華のコートを用意し、強引に紅華を外に連れ出した。
紅華も、冬の夜の空気を浴びるのは好きだ。それに、明日は土曜日なのに、珍しく休みである。
たまの夜更かしもいいかも、などと頬を緩めながら、琴平と手を繋いで家を出た。
十数分後。
「んーーー!美味しい!」
「最後の一個、残ってて良かったね」
幸せそうにあんまんを頬張る琴平を、紅華は眩しそうに見つめていた。
食べ物一つで、これ程感情豊かになれる琴平が羨ましくて、愛おしかった。
と、
「ほら!紅華も食べ!」
琴平が、紅華の口元にあんまんを押し付ける。
「むぐ……!」
大人しく一口齧ると、あんこの優しい甘みと、生地のほかほか具合に驚いた。
「な!美味しいだろ!」
にこにこと笑う琴平につられて、紅華も微笑む。
本当は、歩きながら食べるのは行儀が悪いよ、と言おうかと思っていた。
しかし、そんなつまらない決まりよりも、二人で学生みたいに、夜中に食べ歩きをする楽しさが勝ったのだ。
琴平と居ると、自分が変われる気がする。紅華は、琴平にそんな価値を見出していた。
厳格な父親と、そんな父親に謝ってばかりの母親。紅華も、もれなく両親の影響を受けて育った。生真面目で、でもそれを貫き通せるほどの心の強さもない。母親と同じように、すぐ謝罪を口にしてしまう。
だが琴平の自由さは、紅華の凝ってしまった考えをゆるやかに解かしていく。こうでなければならない、という強制感も、このままで良い、という甘やかさもない。
こういう生き方も、楽しみ方もあるよと、琴平を見ているとひしひしと感じるのだ。
琴平と出会えて良かった。
そんな感動をしみじみと噛み締めていると、気が付けば琴平のお気に入りの公園まで来ていた。
この桜の木を過ぎれば、家まであと数分。
素敵な時間が終わってしまう事への名残惜しさを感じていると、琴平が突然、
「最後の一口、あげる」
と、小さくなってしまったあんまんの欠片を紅華の顔に近付けた。
「ありがとう」
紅華は厚意を素直に受け取り、琴平の手ずから残りを頂く。
もぐもぐと、この季節ならではの美味に浸っていると、
「紅華、ほっぺにあんこが付いてる」
琴平が、耳元で囁いた。
「え、どこ!ごめんなさい……!」
自身のはしたなさと、耳朶をくすぐる琴平の吐息にどぎまぎした紅華は、慌てて顔を触るが、見つからない。
紅華は目を白黒させながら、ぺたぺたと頬を指先で探る。そんな紅華の手を、琴平はぐい、と掴んで自身に引き寄せた。
「ここだよ」
琴平の顔が、近い。近過ぎる。
紅華がそう認識した時にはもう、
ぺろ。
琴平の舌が、口元をなぞった。
「ひゃっ」
唐突に降ってきた温かさへの衝撃と、慣れない感覚によるぞくりとした痺れに、小さな叫び声が出る。
恥ずかしくて、思わず目を瞑った。
が、
「んんっ……!」
息せきつかぬ間に、柔らかくて温かいものに唇を塞がれる。同時に、それとは真逆の、力強い両腕に、身体全体を抱き締められた。
琴平だ、と理解するのに、数秒かかった。
「ほんとはずっと、こうしたかった……!」
「──っ!」
苦しそうに、しかし、満たされたように独り言ちる琴平の声に、紅華の頬は一瞬で赤くなる。
私も、なんて言うと、気持ち悪がられるだろうか。
いいや、琴平なら大丈夫。きっと、私の事を、受け入れてくれる。
本当は、もっともっと彼と触れ合いたかったという想いを、分かってくれる。
だから、
「続きは家に帰ってから、ね?」
紅華は一瞬琴平の唇から離れ、彼の背に両手を回しながら、そう囁いた。
目を大きく開いた琴平は、絞りだすように、紅華に問うた。
「それ、どういう意味か分かってる?」
「……うん」
真っ直ぐな視線が堪らなくて、紅華は目を逸らしながら、それでも頷いた。
突如、ぱっと身体を離され、徐に琴平は歩き出す。手は繋がれたままだったから、嫌われたのでは無いことは分かっていたけれど、大胆過ぎたかと紅華は少し不安になった。
二人で、無言で紅華の部屋の玄関前まで辿り着く。
と、
「明日休みだよね」
琴平はノブに手を掛けながら、紅華の顔も見らず、唐突に口を開いた。
「う、うん。そうだよ」
そう答えた紅華に、
「じゃあ、遠慮しなくて良いよね?」
怒っているとも、照れているともつかない表情で、琴平は言った。
ああ、これが、最後通牒だ──。
紅華は、背筋にぞくぞくとしたものが走るのを感じた。その痺れを、琴平に委ねられることへの、悦びも。
だから、
「好きにしていいよ」
そう答えたのは、当然だった。
それを聞いた時の琴平の形相は、一生忘れないだろう。
真っ赤な顔で、ぎり、と奥歯を嚙み締めて、瞳がおびただしい熱で潤んできらきらしていて。
本当に本当に、愛おしかった。
二月の三週目。近頃は、最高気温が一桁台なのが珍しくなくなってきた。
紅華は、薄暗い日の入り間近の時間を、公園で過ごしていた。夕方の五時半だというのに、辺りは不気味な暗さに包まれている。
寒風がひゅうひゅうと音を立てて、紅華と、裸の桜の木を撫でていった。反射で身体がふるるっと細かく震える。
それでも、紅華はこの場所から離れる気にはならなかった。
桜の木に、つぼみが幾つか生まれているのだ。咲くまでもうしばらくの我慢だと、根拠のない自信で己を奮い立たす。
すると。
ぱたぱたぱたっと、騒がしい足音が鼓膜を揺らした。
見ると、小学四年生位の男の子が、重たそうな鞄を揺らしながら一心不乱に公園内を駆け抜けていく。
斜めに突っ切るのが近道なのだろう。塾か何かの習い事だろうか。
若い芽ならではのエネルギーを肌で感じていた矢先だった。
「わあっ!!」
男の子が、桜の根につまづいて転んでしまった。
「ええ……、大丈夫?」
慌てて駆け寄って確認すると、膝から血が出ている。男の子は泣きこそしていないものの、痛みに涙を零しそうだ。
「手当しよう」
紅華は、男の子の手を取った。
傷口に砂が沢山付いている。水で洗って、紅華のハンカチで覆えば、出血もいくらかは止まるだろう。
男の子も紅華の提案に意義を唱えることなく、唇を噛み締めながら手を引かれて付いてくる。
公園内に備わっている、トイレの手洗い場に着く。蛇口を捻って水を流し、ポケットティッシュを濡らしては、男の子の患部をゆっくり拭き取る。
「っ──!」
「ごめんね、ちょっと我慢してね」
痛覚に呻く男の子を宥めながら、膝に付いた血や砂を拭う。
傷口がいくらか綺麗になったところで、持っていたハンカチを包帯の様に巻きつけた。それでも、白い布が少々血で滲んでしまう。
止血まがいにはなれば良いのだが。
心もとない結び目を見つめていると、頭上から声が降ってきた。
「ありがとう、お姉ちゃん」
見上げるとそこには、眼のふちはまだ赤いものの、にっこりと笑っている男の子が居た。
健気で礼儀が正しい彼がいじらしくて、紅華は頭をぽんぽんと撫でる。
二人でトイレから連れ添って出ると、男の子は手を振りながら駆けて行った。その後姿を見送っていると、紅華の表情は和らいだ。
沈んでばかりだった心が、男の子の笑顔で少し浮き上がったような気がした。
これも、琴平を待っている事の、良い兆しだ。私は間違っていない。
彼を待っていることは、間違っていない。
紅華はそう自身を奮い立たせ、再びベンチへと足を向けた。
十二月になって、琴平の様子がおかしくなった。
急に、金回りが良くなったのだ。
ブランド品のプレゼントをくれたり、二人で訪れた店の支払いを進んでするようになった。
不審感は抱いたが、今までのお返しだ、とにこにこ顔を向けられては、細かく追及することも出来ない。
しかし、どこかの企業に就いたのか、とやんわり聞いても明確な答えは返って来ない。そんな感じ、と濁される。
正直、怪しい、と思わずにはいられなかった。琴平を疑いたくないが、何か危ない仕事や、身体を悪くするような事をしているのではないか、と不安になる。
かと言って、水商売に足を踏み入れた様子はない。何故なら、夜は必ず紅華の隣で寝ているからだ。
そうなると、最悪のケースとして流行りの闇バイトなどが考えられるが、琴平に限ってそんなはずはないと断言できる。彼はそこまで愚かではないし、犯罪を行う悪性の度胸も持ち合わせていない。
だから、彼の身に何が起こっているのかは不明なままだ。それでも、心配なものは心配である。
結局、紅華はこっそりと様子を見守ることにした。
そんなある日のことだ。
二人で夕食のクリームシチューを頂いていると、琴平が出し抜けに聞いてきた。
「紅華はさ、なんで俺の事叱らないの?正社員になれ、とか、真っ当に生きろ、とかって言わないの?」
脈絡も何もない質問だったから、紅華は数秒、目を白黒させた。しかし、答えは最初から決まっている。
「信じてるからだよ」
良い淀むことなく、紅華は答える。
却って言葉に詰まったのは、琴平の方だった。
「……俺の、何を?」
空気にあえぐように、彼は苦しそうに尋ねてくる。きっと琴平にとって、重要な問いなのだろうと、紅華も慎重に文章を組み立てた。
「うーん、明確に言うのは難しいけれど、どこか、こう、目標に向かって進んでいるところを、かな?何かやりたいことがあるんだろうなあって。だから私は、それを応援するだけだよ」
「何で?」
「え?」
「どうしてそう言える?もしかしたら、紅華のことを利用して、楽したいって考えてるかもよ」
どこか怒ったように、琴平は早口で畳みかけてくる。いつもの琴平とは違う、と察しながらも、紅華は穏やかに笑って言った。
「だったらアルバイトしてないでしょ、家事も」
拍子抜けした表情の琴平が可愛くて、紅華も仕返しする。
ただ、琴平への思いを伝えるだけの、簡単な仕事だった。
「それに、利用したかったら利用しても良いよ。何の楽しみも無かった生活に、光をくれたのは琴平だから。琴平の輝が傍に在り続けるのなら、私はそれでが十分」
全てが、まごうこと無き事実。琴平への信頼を構築するのにこの三か月間は、十分すぎる期間だった。
琴平は束の間、呆然としながら、シチューの人参を見つめていた。
しかし、
「ちょっと来て」
と強引に紅華の手首を掴み、立ち上がる。そのまま、どすどすと足音も荒く上着や鞄を手に取ると、外へ出た。
琴平が向かったのは、公園だった。だが、紅華も何となく分かっていたから、何も言わなかった。
二、三本しかない街灯に青白く照らされた中央の桜の木が、幽霊の様に浮かび上がっている。そこへ、琴平はずかずかと真っ直ぐ歩いて行くと、幹の傍に紅華を立たせた。
「ここで、一枚撮らせて」
カメラを構えながら、数歩後退る琴平。紅華も指示通りに、背筋を正し、撮られる姿勢をとる。
かしゃ。かしゃ。
琴平がシャッターを切る音が、公園内に響く。冬の澄んだ空気を、小気味良い機械音が裂いていく。
しばらくすると、
「うん、満足いった」
カメラの画面をのぞき込みながら、琴平は呟いた。
その様子に、紅華は思わず、
「ふふ、またこの場所」
と笑みを零してしまう。
「え?何が?あ、いや、そうか……そうだな……」
「でしょ」
琴平は一瞬、視線を上に向けたがすぐに納得したようで、苦笑いを浮かべた。そして、木の幹に、優しく右手を添える。
「なんか俺、本能的にこの桜を頼りにしてしまうみたい。なんでだろう、両親の代わりに見守ってくれてる気がするんだよ」
ざらざらの樹皮をそっと撫でると、琴平はふと紅華の顔を正面に見据え、真剣な面持ちになった。
そして、きっぱりと告げる。
「俺、この桜が咲いたら、紅華にプロポーズするよ」
「え」
紅華の動揺に気付きつつも、琴平は続けた。それは、想いを紅華に押し付けるためではなかった。
基本、誰かに従ってばかりの紅華に、紅華自身の気持ちを確かめてもらうためだ。
「どうせならこいつの全盛期に、俺の一世一代の告白を見せてやりたい。だからそれまで、もう少しの辛抱だな」
それ、もうほとんど言っているようなもんだよ。
本当は、そう言いたかった。でも、声を出せない。
琴平と、家族になれる。ずっと一緒に居られる。そう考えるだけで、嬉しくて仕方がなかった。
そのせいで肯定の言葉ではなく、嗚咽が漏れる。両手で顔を覆い、涙でぐしゃぐしゃの有様を隠さなくてはならない。
が、ここで、変な誤解をされてはまずいことになると気が付いた。恐々、指の隙間から琴平の様子を窺う。
息を呑んだ。
今まで見たことがない程の、優しい笑みが見えた。
分かっているよ、と言わんばかりの、琴平の笑顔。ますます涙が零れるのを、止められなかった。
この人のことが、心から好きだと思った。
そこからのことは、あまり記憶にない。
二人で手を繋いで帰って、でも私は、ずっと泣いていた。
ああ、あと、もう一つ。
その後、琴平は私の事を抱いてくれたけれど、耳元でする声が何故だか涙で濡れていた気がするのだ。
「帰って来るから」
そう言って、泣いていた様な気が。
確かではないけれど。でも。
それだけは、今でもはっきりと覚えている。
二月の二十五日。
世間はすっかり卒業式ムードに包まれており、桜の蕾もその色を濃くし始めた。開花までもう二週間程度、といった所だろう。
薄闇の中を、紅華は、まだ待っていた。
寒さにはもう慣れた。
でも、心は疲弊していた。
桜が咲くのは、まだまだだった。だから、琴平が帰って来るのもまだ先だ。
そう頭では分かっていても、気持ちは今か今かと逸ってしまう。
もう無理なのかもしれない。私は捨てられたのかもしれない。
いや、いやいや。
まだ、大丈夫。
まだ、信じられる。
そんな問答に、脳内を支配される。
紅華は頭を抱えた。考えたくないことまで考え始めた自分への嫌悪感と、いつまでも続く寂寥感に、つい身体を丸めたくなった。
と、そんな紅華の耳に、ざりざりと砂を勢いよく踏みしめる音が届く。その勢いの良さは、まるで土を蹴り飛ばしているかのようで、荒々しい。
さらに、足音は真っ直ぐ紅華の方へと向かってくる。
不審に思って紅華が顔を上げると、鬼の様な形相をしたスーツの女性一人と、その背後に二人の女性の姿が見えた。
まるで取り巻きを従えた女王様の様だ。
「え、何……?」
先頭に立つ女性も、その他の女性たちにも見覚えが無く、彼女らの勢いに紅華は怯える。
女王の面持ちからすると、これから彼女は断罪の儀をしようとしているらしく、しかもその対象は紅華だということはすぐに察知できた。
紅華が逃げる間もなく、女王様は、紅華の直ぐ近くまで来ると開口一番怒鳴り散らした。
「あんた、うちの息子をそこにトイレに連れ込んだんですって!?」
「ごめんなさ!──は……?」
紅華はつい脊髄反射で謝りかけたが、身に覚えが無さ過ぎて途中で首を捻る。
いや、思い当たる節が全く無いことは無いが、あれはただの──。
「聞いたわよ、息子から!無理やりトイレに連れて行かれたって!!何てことしてくれるのよ変態!」
「いえ、ちょっ、誤解です!」
思い当たった記憶と彼女の主張が見事にマッチングしてはいるが、最悪のすれ違いを起こしている。
紅華は慌てて弁明しようと手を横に振るが、先頭に立つ女性は、聞く耳を持っていない。後ろの女性たちも、同じく紅華を睨むばかりだ。
「あなた、数か月前からここをうろついているんですってね」
「それは……」
女性の鋭い声に、紅華は口ごもる。
何も言い返せない。反論の余地は勿論あるが、細かく事情を説明する気力も、根性も無かった。
テレビ番組に面白おかしく取り扱われるほどだ。彼女らが紅華の気持ちを理解してくれるはずもない。
しかし、黙りこくる紅華を見逃す女性たちでも無かった。無言は肯定のサインとし、スーツの女性は後ろの女性に合図を送った。
突如、取り巻きらしき二人の主婦たちは、紅華を羽交い絞めにする。
「な、何ですか!?」
荒々しく後ろ手を拘束され、紅華は半ばパニックになりながら叫ぶ。
女王様も、勿論負けずに大声を上げる。
「あなたを警察に連れて行くのよ!心配で夜も眠れないのよこっちは!」
「やめて下さいっ……!」
警察に連れて行かれてしまったら、例え罪には問われなくても、この公園に居ずらくなってしまう。そうなると、紅華は琴平をここで待つ事が出来なくなる。
紅華は必死に抵抗する。しかし、単純な人数の問題で、容易には掴まれた腕を振り解けない。そもそも紅華は、余り体格に恵まれている方ではないのだ。
「もうっ……!」
紅華は焦って、ぐいぐいと力の限り自身の両腕を引っ張っていた。が、ふとある事を思いつく。
そうすると、上手くいく。
誰かにそう教えてもらったかのように、脳裏に閃くものがあったのだ。
何の予兆も見せずに、紅華はすっ、と突然力を抜いた。
「わっ」
「きゃっ」
紅華がもがくのと同じくらいの力で、二人の女性は紅華を逃すまいと腕に力を籠めていた。だが、その力の行き先が無くなって、二人とも前方につんのめる。
その隙に、紅華は再び思い切り身を捩り、彼女らを振り解くことに成功した。
はやく、はやく逃げなきゃ。
そうは気は急ぐものの、身体が上手く付いてこない。流石にショックを受けているようで、足がもつれてしまった。
二人組の女性から二、三歩程しか離れていない地点で、紅華は転んだ。
「あ」
地面に膝をついてしまう。
すかさず、ざりざりと砂粒を踏み散らす音。
その足音が耳元で止んだ途端、ぐい、と髪を掴まれる。強引に上げさせられた顔の先には、般若(スーツVer)の形相。
紅華が抵抗したことが、よっぽど気に食わなかったらしい。
「なんなのあんた!!大人しく言うことを聞きなさいよ!」
そんな金切り声を上げつつ、女王は片手を振り上げる。
殴られる。
恐怖で涙が滲む。きっといつもなら、すぐに謝って、とにかく謝って、この場を治めることに躍起になっている。
でも、でも。
「わ、わたしはっ」
震える声で、紅華は叫ぶ。
謝るということは、自身の非を認めることになる。謝罪を口にするのは簡単だが、自分の善意は否定したくない。私の善性を好きだと言ってくれる人が、居るのだから。
それにもし、琴平を待つこの時間で過ちを犯したのだと思ってしまったら、琴平がもう、本当に、帰って来ないかもしれない。
それだけは、絶対に、嫌だった。どれだけ怖くても、嫌だった。
だから、言う。今までの弱気な自分を引っ込めて、勇気を振り絞って、主張する。
「わるいことはしていません!!」
だが、
「このっ……!!」
勢い良く振り下ろされる手。
──だめだ。
紅華は落胆し、瞼を閉じる。
仕方がない。そもそも難癖をつけてきたのはあちらだ。紅華の意見を聞き入れてくれるはずもない。
私、ほんのちょっと、頑張ったんだけどな。
暴力への恐怖ではなく、悔しさによる涙が、頬を伝う。
ぽたりと音を立てて、その雫が地面に落ちた時だった。
ふわっと桜の香りが鼻腔をくすぐった。
驚いて目を開けると、還暦位の歳の女性が、女王様の背後から彼女の手首を掴んでいる光景が見えた。
着物の袖が、ゆらゆらと揺れている。
「頭を冷やしなさいな。貴女の言い分には、無理がありましてよ」
「何なのあん、た……」
くわっと目をむいて振り返ったスーツの女性は、だが、その視線の先にある人物の様相と、手首にかかる力の強さのギャップに混乱する。
威勢を失った女性に、老婦人の凛とした声が畳みかける。
「私、見ておりましたのよ」
「な、何をよ……!」
スーツの女性は、ようやく離された手首をさすりつつ、婦人を睨む。
白っぽい色の着物に身を包む、ぴんとした背筋の婦人は、鋭い眼光に怯むことなく言い返した。
「この方は、本当に転んだ少年を助けただけですのよ。咎められるようなことは何もなさっていませんわ」
紅華は目を瞠る。あの場面を見ていた第三者が居たとは、思いもよらなかった。婦人の姿が果たしてどこにあったのかは、全く見当もつかないが。
第三者の証言に、取り巻きの二人は顔を見合わせる。ぎりぎりと歯軋りをしたのは女王様ただ一人だ。
「証拠はあるの、証拠は!」
声を荒げるスーツの女は、やけに瞳が忙しい。何か焦ってでもいるのだろうか。
「証拠ならありますわ」
「どこに!」
声量だけで圧倒しようと試みる女王に対し、婦人は流れる川の様に鷹揚としている。
そして、
「ほら」
ゆっくりと、左手である場所を示した。
「今、来ましたわ」
皆、つられてそちらを向くと、
「ママ!」
まだ背丈の低い男の子が、大きな鞄を抱えながらこちらに走ってきていた。
紅華が助けた男の子だ。
「その人は僕を助けてくれた人だよ!何してるの?」
純真無垢な彼の目に、お供の二人はいよいよ眉を寄せている。ここまで露骨だと、流石に分かる。
女王様から聞いていた話と、齟齬が生じているのだ。
「ええ!?だってあなた、無理やりトイレに連れて行かれたって……」
「そうだけど、無理やりなんかじゃ無かったよ!それに、ほら!」
そう言って男の子は、ポケットから何やら白い物体を取り出した。それは、紅華が彼の膝に巻いたものだった。
「この人は、僕の怪我の手当をしてくれたんだよ!」
血が付いたハンカチは、その場に、紅華の揺るがない無実を突きつけた。
「あの、聞いてたのと少し違うんですけど……」
「息子さん、ひどい目にあったって……」
口々に疑問をぶつけるお供達。
確かに彼女の息子さんはひどい目にはあったが、それは彼が自発的に起した事故であって、紅華は無関係だ。
もの言いたげな四名の視線に、スーツの女王は顔を赤くしたとかと思えば、
「もういいわよ!」
と、強引に男の子の手を掴み、すたすたと背を向けて去って行った。
「ええ!?ちょっと!?」
「何だったんですか一体?」
連れの二人も居たたまれなくなったのか、彼女らの後を追いかける。
公園には、紅華と婦人だけが残された。
座り込んだままの紅華に、婦人はそっと、手を差し伸べてくれる。その手を有難く受け取り、紅華は立ち上がった。それでもまだ、足先に感覚がない。実感もない。
ふわふわとしたトランポリンを踏んでいる気がしながら、とにかく紅華は婦人にお礼を言う。
「あ、ありがとうございます。お陰様で、助かりました」
婦人はにこにこと微笑み、頷いた。しかし、紅華の手を離してくれない。
「あ、あの」
「少し、休みましょう。いつもの場所で、ね」
ああこの方は、全部知っているんだと、何となく感じた。
手を引かれるままに、てくてくと婦人に付いていく。二人で並んで、桜の木を正面に構えるベンチに腰掛けた。
そこで初めて、自身の手が小刻みに震えていることを知った。そりゃあ、婦人も放っておけない訳だ。
しばらく、お互い無言で過ごす。
そうして、どれだけの時間が経っただろうか。月が昇り、闇夜の緞帳に星の装飾が散りばめられ始めた頃、婦人は呟いた。
「まだ、待てますか」
それが、自身に向けられた問いであることは容易に理解した。
紅華は、言葉を選びながら答える。
「……待ってて良いと思いますか?」
「といいますと」
彼女は切れ長の目をさらに細めて、聞き返してきた。紅華は、彼女にならと、本音を隠すのをやめた。
「何だか私は、知らず知らずのうちに、誰かに迷惑をかけていたみたいです。それはやはり、この行為が間違っているということなのではないでしょうか。私は、悪いことをしていたのではないでしょうか」
「あなた……」
「私はただ、待っていたいだけなのに。彼に会いたいだけなのに。それも、許されないのでしょうか?」
一度言葉にしてしまえば、溢れて止まらない。後ろ向きな気持ちに従って、視線が勝手に足先へと向いてしまう。
ぐう、と爪が掌に食い込む。そんな紅華の拳に、婦人の手が乗せられた。
「いいえ、いいえ。顔をお上げなさいな。あなたは、何も悪いことをなさっていないのでしょう?」
「でも、でも……っ。ああやって、不安に思う人が居るっていうことは……!」
優しい言葉に、寄りかかりたくなる。甘えたくなる。何も考えずに、頷いてしまいたい。
それでも、紅華は歯を食いしばる。自身の本音と対峙する。
今、誰かに頼ってしまったら、自分の気持ちと一生向き合えない気がした。
もう、逃げ道を失ってしまうと思った。
「違う……、違う違うちがう!」
頭を抱え、髪を振り乱して、ぶんぶんと振る。
その勢いに任せて、これまで押しとどめていた考えが口を突いて出る。
「私は、理由をつけて諦めたいだけなの……!!」
今日こそは会えるかもしれないという期待。今日も駄目だったという悲しみ。その反復をいつまでも繰り返す苦しさ。それがこの先も続くかもしれないという絶望。
もういっそ、やめてしまいたい。
誰かに迷惑になるからという、さも正当性のある理由を以て、諦めたい。
でも、でも──。
「あなた、本当にそれで良いの?ここで諦めてしまって、後悔はない?」
婦人の穏やかな声が、却って深く心に刺さる。
目の奥がじわりと熱くなって、自身を取り繕う余裕も無くなった。
「……します。後悔しますっ……!もし、私を探してここに琴平が来ていて、私が私の怠慢でその機会を失ったとしたらそれは──、悔しくて悲しくて、なりません!」
言い分が、二転、三転しているのは分かっている。でも、全てが本音なのもまた事実。そしてそれらを口に出して、誰かに伝えて初めて、奥の奥の奥底の、自身の情念に辿り着けた。
「やっぱり待ちます!辛いけど、待ちます!琴平は、帰って来てくれるはずだから……!だから、」
失いかけていた覚悟を取り戻せた喜びと同時に、その重さへの苦痛で、胸がいっぱいになる。涙が一粒、滑り落ちた。
「早く帰ってきてよ、琴平……」
両手で顔を覆う。掌がみるみる、温かく濡れていく。
そんな紅華の頭を、婦人はぽんぽんと撫でてくれた。彼女が身体を動かすたびに、ふ、と花の香りがする。その優しい匂いに、胸が締め付けられた。
なんで私のことを見ていてくれたのか、とか、なんでずっと待っていた事を知っているのか、とか、聞きたいことは沢山あった。が、今はただ、見ず知らずの婦人の厚意を大人しく受け取る。不思議なもので、赤の他人に当てられた敵意は、赤の他人の善意で上書き出来る。
そうやっていくらか時間が経ち、紅華の感情の波濤が落ち着き始めた頃のことだった。
ざり。ざり。
紅華たちのものではない靴底が、公園の土を噛む音がした。
「おや。どなたでしょう」
婦人が足音の方を向く。紅華もつられて、顔を上げた。
入口から、誰かが歩いてくるのが見えた。
顔も服装も、街灯の少ない夜闇に紛れてしまって分からない。
けれどきっと。ああきっと。
こんな時期に、こんな時間に、ここに来てくれるのは。
たった一人しかいない。
「琴平……っ」
紅華は即座に立ち上がると、確信をもって、その人影に向かって駆け寄った。
「キンペイ!!」
隣のガイドの叫び声が聞こえた瞬間、琴平は廃墟の壁に身をかがめた。
ドオオン!
近くの建物に、砲弾が当たる音。
ガラガラ。パラパラ。ガララッ。
建物が崩れ落ちる音。
ぱたぱたぱたぱた。
兵士たちが、急いで駆け抜けていく音。
早口で荒ぶった異国の言語。
ブロロロロ。
戦車が去っていく音。
様々な、本当に様々な音の後に、静寂が訪れる。
琴平とガイド以外の、生命の営みすらもかき消して。
「危なかった、キンペイ。敵兵に見つかったらおしまいだった」
「そうだね、ありがとう、エド」
未だ緊張感が漂う中、ひそひそと二人は会話する。
それから、安全かつ琴平が仕事を出来る地点まで移動を開始した。
エドは、かなり頼りになる現地ガイドだ。何より、危機を察知する勘が優れている。彼が居なかったら、琴平は既にこの世に居なかっただろう。
中東の紛争地帯。兵士や傭兵、テロリストまでもがうようよいる様な、今世界で最も危ない場所に、琴平は来ていた。
写真を撮るために。
寒さでかじかむ指先を揉みながら、日本では、そろそろ受験シーズンだろうなどと考える。ここで暮らす子供たちには、全く関係のないことだが。
歩きながらふと、昨夜、この村の少年たちと交わした会話を思い出した。
「キンペイ、何見てるの?」
「これ?俺の大好きな人と大好きな木」
「ふーん、家族?」
「今はまだ違うかな。でも、帰ったら──」
「あー!だめだよキンペイ!」
「もがもが……、何なのさ、急に口塞いできて」
「そんなこと言ったら、キンペイ、死んじゃうよ」
「フラグってやつ?良く知ってるね、そんなこと」
「フラグ?はよくわかんないけど、なんか不吉な感じがする!」
「悪い予感ってのは万国共通なんだなあ」
「ともかくだめだよ」
「分かった分かった」
そう笑い合った子供たちは皆、先程死んだ。爆撃機から降ってきた焼夷弾に、建物ごとバラバラにされた。
ここは、そういう場所だ。一秒前までごく普通に波打っていた鼓動が、むやみに、簡単に、止められる。
琴平は、無表情で瓦礫の山の写真を撮る。少年らのちぎれた腕を撮る。あどけない表情のまま、燃えている顔を撮る。
「写真を撮る時のキンペイは、人が違って見える」
隣でエドは感心したように、そして、気味悪がるように言った。
「そうかな?」
ぱちり。最後の一枚の、シャッターを切る。レンズから目を離して、改めて目の前の惨状を肉眼に映し──。
「おえええええっ!!」
激しく嘔吐した。と言っても、レーションしか口にしていないから、ほとんどが胃液だ。
涙を流しながら地面に這いつくばる琴平の背をさすりながら、そういうとこだよ、とエドは呟いた。
琴平が呼吸を整えるのを待って、二人は再び歩き出す。
「それにしてもエド、よくこの時間に襲撃が来るって分かったね」
「うん、何かが聞こえた。胸騒ぎがした。それだけ。でも、時間が無かったから、皆は助けられなかった」
俺からしたら、エドも大概変だけどな。最早能力者の域だよ、それ。
と、琴平も思わなくはないが、こうして彼のお陰で命を繋げているので口には出さない。
ここで写真を撮るようになって、一か月半。そろそろフィルムのストックも貯まり始めた。もちろん、構図や配置に拘ったものも沢山ある。
しかし、まだ決め手に欠ける。そんな気がしてならない。
これでは、一人前とは認めてもらえない。帰ることは出来ない。
多くの死を踏み台に、それでもまだ生きている。そんな大きな安堵感の合間を縫って、じわじわとした焦燥感もまた、琴平の心を塗り潰していった。
むごたらしい蹂躙を後にし、琴平とエドが野営を繰り返して数日後。
爆撃機が墜落した。
轟音がした方向に二人が駆け付けた時には、黒煙と血の匂いが充満していた。
先日村を襲撃し、民間人を殺した報復だろう。ひしゃげた機体の色は、琴平たちが村からほんの数十メートル離れた所から仰ぎ見たものだから、すぐに分かった。
琴平は、目の前の光景から目が離せなかった。
だがそれは、おぞましさからくる恐怖のせいではない。
折れた翼。飛び出た鉄骨。散らばる肉片。
今まで一度も忘れたことのない悪夢の様な、それでいて心地の良い夢の様な、そんな景色。
琴平の記憶が、無意識の内に重なっていた。
気が付けば鞄からカメラを取り出し、構えていた。
「キンペイ!キンペイ、何してる!?」
エドの必死の呼び掛けにも気が付かず、琴平はシャッターを切り続ける。
足りない。足りない。そうだ、ひどさが足りなかった。
もっと、もっとだ。
もっとむごたらしくて、うつくしいしゃしんを。
そうすれば、俺は。
紅華と家族になれる。
「キンペイ!早く逃げないと、敵が来る!」
夢中になって、何枚も、何枚も目の前の光景を切り取る。
ああ、紅華。
何も言わず、置いてきてしまった。
待っていて、なんて言えなかった。
俺はいつも、待つ側だったから。
誰かが家に帰って来るのを。
俺を引き取ってくれた叔父夫婦は仕事で忙しくて、でも俺のためだと分かっていたから、寂しいなんて言えなくて。
だから、寂しい時間が辛いことなんて、誰よりも知っていた。
それでも居心地の良いこの部屋を出ていくと決めた時も、紅華を自ら手放すことが出来なかった。
俺の過去を聞いても泣かず、ただ写真を美しいと言ってくれた紅華。
俺を家から追い出すこともなく、必ず帰って来てくれた紅華。
俺の事を、信じてくれた紅華。
まだ傍に、居て欲しかった。
紅華のことは、諦めたくなかった。
待っていて欲しい。待っていて欲しくない。
相反する思いが、琴平の心の天秤を、常にどちらかに傾ける。
故に、何も言わずに紅華の元を去ってしまった。それは、琴平の甘えで、エゴだった。
待っていて、紅華。俺、必ず帰るから。
しっかり仕事を手に入れて、プロになって、紅華の側に居られる資格を得るんだ。
だからもっと、もっとステキな写真を──。
「キンペイッ!!!」
耳元で、鼓膜を破る位の大声がしてやっと我に返った。
だが、もう遅かった。
ドオオオオオオオン!!
とんでもない音が、耳を、脳をつんざく。開きっぱなしの琴平の目に、建物が盛大に散らした破片の数多が迫る。
琴平の視界は一瞬にして真っ白に、そしてその後、真っ暗になった。
「ご、ごめんなさい……」
紅華が息せき切って近付いた人物は、紅華が望んでいた人物では無かった。
華奢な体格や身長は、琴平のそれに近い。だからまあ、見間違えても仕方は無い。
しかし、間近で見れば恰好は全く違った。
琴平のゆるくウェーブがかかった茶髪とは大きく異なり、彼は短い黒髪をぴしりと整えている。また、紺色のスーツに身を包んでいるその姿はいかにもなサラリーマンで、ラフな服装が多かった琴平とは真逆の印象だ。
大きく期待を外した紅華は、初対面の男性の前であるにも関わらず、露骨に落胆した表情を浮かべた。それも、彼はただの通りすがりで、紅華に用は無かったかもしれないのに。
それでも、彼は紅華を咎めるどころか、何かを理解したように一つ、頷いた。それから落ち着いた所作でポケットから何かを取り出すと、紅華に両手で差し出した。
「私、『週刊世界』の阿岸と申します」
白く小さな紙に記された役職と名前、会社名で、男性の身元は簡単に証明された。『週刊世界』は、本屋やコンビニでもその名を目にする程の、人気のある週刊誌だ。各国の経済や財政状況にはじまり、血なまぐさい紛争の状態を報じたかと思えば、果ては流行り物の紹介など、日本に限らず世界を範囲にした記事を掲載している。
とは言え、紅華は混乱しきりだ。こんな時間に、こんな場所に、なぜこの人が私に。阿岸とは愚か、雑誌を買ったことすらない紅華に、彼が接触を計る理由など思いつかない。
琴平では無かった失望と、知らない人に話しかけてしまった気恥ずかしさと、訳の分からなさで、紅華は顔面蒼白である。そんな様子も、さも想定内だと言わんばかりに、阿岸は慌てることなく冷静に口を開いた。
「細川紅華様で、お間違いないでしょうか。琴平さんの件で、お話があって参りました。お時間宜しいでしょうか」
琴平。その名に紅華の指先が、ぴくりと跳ねる。分かりやすく動揺した紅華を見て、紅華本人だと確信した阿岸は、話を続けた。
「十日ほど前からあなたと連絡を取ろうとしていたのですが、琴平さんにお伺いした電話番号では繋がらず、ご自宅にお伺いしてもタイミングが合わず、とコンタクトが遅れてしまいまして。もしかすると、と不躾ながら近所を散策していると、お会いできた次第です」
「すみません、間が悪くて……。お手間をかけさせて申し訳ないです」
「いえいえ、こちらこそストーカーの様な真似をしていたので、誤解が無くて何よりです」
夜の公園で大人が二人、ぺこぺこし合う光景は異様だったろう。紅華は当たり前の如く謝罪を口にしていたが、途中であることに気付き、はたと顔を上げる。
「あの、琴平とは一体どういうご関係で……?」
阿岸さんが、真っ当な社会人であることと、紅華に会いたがっていたことは分かった。しかし肝心の、琴平とは全く繋がらない。
「ええ、その点も含めてあなたにはお伝えしなければならないのですが……」
紅華の疑問符でいっぱいの表情を汲み取ったのか、阿岸は質問に答えようとした。しかし、言葉を発する前に口を噤み、ちらっと腕の時計を確認した阿岸は、
「時間も時間ですし、日を改めましょうか。女性二人を、こんな寒い中に留めておくのは、社としても、個人としても気が引けますので」
と、片手を紅華のやや左側へと向けながら言った。ベンチに座っていた婦人がいつの間にか、紅華のすぐ後ろに居たのだ。
確かに、既に定時は悠に過ぎている時刻だ。そもそも忙しいであろう阿岸の身を、これ以上拘束する訳にはいかない。
だが、紅華はもう我慢が出来なかった。
スケジュールを確認しようとスマホを取り出す阿岸の袖を引き、嘆願した。
「いいえ!聞かせてください!琴平に、何があったのかを、今すぐにでも……!」
真剣さ、などでは生易しい、狂気すら孕んでいる紅華の瞳をじっと見つめていた阿岸は、
「分かりました」
と、淡々と告げた。
「でしたら、近くのカフェに場所を移しませんか?ここで立ち話というのも何ですし」
そして、立て続けに提示された案にほっとし、紅華はそれに乗ろうとした。
が、一緒に行きましょう、と声を掛けようとして振り向いて、
「行ってきなさいな」
と笑う婦人の姿に、そこはかとない不安を抱いた。
ここで別れてしまえば、彼女とは二度と会えない。
そんな予感に、襲われる。
しかし、彼女はここから動けない。具体的には分からないが、彼女に複雑な事情があることも、何となく察した。
琴平の話は聞きたい。かと言って、婦人と離れたくない。
婦人をこの場に置いていきたくなかった。初めて会って、ほんの少ししか時間を共にしていないけれど、何故だか丸っきり他人、という感じがしなかった。
何より、紅華と琴平に何が起きているのかを、彼女には知ってほしかった。
よって紅華は、
「申し訳ありませんが、ここでお話をお願いします。彼女にも同席して頂きたいので」
と、阿岸に頭を下げる。
阿岸は深く理由を問うことも無く、承諾してくれた。
三人で座るにはいつものベンチは小さいため、婦人と客人に座ってもらい、紅華は近くの小さなパンダの遊具に腰掛ける。
阿岸は、先程紅華が自販機で購入し、手渡したホットの缶コーヒーをカコン、と開けた。それから、少し口を付けると、一呼吸置いてから言葉を発した。
「琴平さんと、連絡が取れなくなりました」
阿岸の話を聞き終えた紅華は、全身の震えが止まらなかった。
寒かったからではなく、琴平の身を案じてのことだ。
阿岸から聞かされた事実の一切を、紅華は全く知らなかった。
まとめると、こういう事だ。
四か月前、『週刊世界』の部署にいたカメラマンに欠員が出てしまい、部署長である阿岸さんは困っていたらしい。そんな時、偶然、琴平が写真を撮影しているところに出くわしたのだという。それを機に琴平を仮採用して、試験的に紛争地帯に送り込んだのだ。
「まず驚いたのは、撮っていた対象です。琴平さんは、閉店したコンビニエンスストアを、まるで絶景でも前にしているかのように、楽しそうに撮影していました。あまりそういったカメラマンは見ないので、興味を惹かれました」
阿岸は目を細めながら、琴平との出会いを語った。そして紅華も、容易にその光景を想像できた。確かに琴平は、桜の他に、廃屋や壊れたオモチャなども、好んで撮っていた。
「撮影が終わったら、どのような仕上がりになったのかを聞こうと考えました。そうして彼に近付いた時です。足元に一枚の写真が落ちていました。かなりぼろぼろの」
そこまで聞いて、紅華も納得した。
あの、飛行機事故の写真だ。素人の紅華ですら心を打たれた作品だ。目が肥えた阿岸なら、より一層良さが分かるのだろう。
「その一枚を見て、その時点で琴平さんのカメラの腕を確信しました。さらに、我々が求めるカメラマン像にも近かった。だから何枚か彼の写真を買い取り、雑誌に載せるなどした後、琴平さんを正社員に迎えようとしたのです」
「カメラマン像……?」
あまりイメージが湧かず、首を傾げた紅華に、阿岸は補足してくれた。
「危険な状況下でも写真を撮る熱意がある人。凄惨さを、凄惨さ以上のものを以て写真に収められる人です。それが、琴平さんだった」
琴平の金回りが良かったのは、このおかげだ、琴平の「好き」が転じて、偉い人に認めてもらえたのだ。
しかし、大手の出版社だ。どれだけ阿岸が推薦し、説得しても、上司は名もないカメラマンを即座には採用しなかった。
「そこで、私は上司に条件を出しました。琴平さんを中東に研修取材という名目で行かせ、写真を撮ってきてもらうこと。その出来が良ければ、正社員として、カメラマンとして採用してもらうこと。
弊社としても、危ないと分かっている地域に取材班を派遣するのにリスクが伴うことは承知しています。もし、琴平さんの技量が上司の求めるラインに達していなくても、生の写真が手に入るに越したことは無い。琴平さんの腕が良ければ、腕のいいカメラマンを迎え入れられる。正直、こちらにリスクはほとんどないのです。問題は、琴平さんの説得だと、私は考えていました。ですが」
「琴平は進んで、行くと、言ったのですね」
紅華は、阿岸の言葉を引き継いだ。阿岸も肯定の頷きを返す。
「琴平さんとの話し合いから、彼も正社員という立場と、プロカメラマンの肩書を欲していることが判明しました。ですので、三か月ほど前から、現地に飛んでもらったのです。もちろん、安全面を考慮して、私共の方で、頼りになるガイドも頼んでいました」
琴平が姿を消した時期とも合致する。これで、全ての辻褄は合った。
だが段々、阿岸の顔が曇っていく。紅華も、胸の中がすうっと冷えていく感覚に陥っていた。
そんな二人を、婦人は切れ長の目で、ただじっと見つめていた。
「琴平さんとは随時、連絡を取り合っていました。撮影の状況、現場の空気など、何か異変があればすぐにでも帰って来れるように、こちらでも準備をしていました。しかし、二週間前から、ぷつりと連絡が途切れたのです」
ひゅ、ひゅ、と紅華の呼吸が浅くなる。手足の先が痺れて、ゴム製品のような感触になっていく。
「何度メールを送っても、電話を掛けても、応答がない。現地のガイドも同様です。ですので、こちらでは緊急事態……所謂、死亡事故だと判断しました。これが、紅華さんに会いに来た次第です」
とうとう、紅華の身体は遊具から滑り落ち、地面にへたり込んでしまった。
力が入らない。嘘だと思いたい。そんな、そんな、大好きな琴平は海外の戦争に巻き込まれて──。
「いや……、そんなの、いや……」
紅華の喉から、細い叫び声が漏れた。
それが聞こえたのか否か、阿岸は立ち上がり、紅華に歩み寄る。それから、わざわざしゃがみこみ、紅華と同じ目線になってくれた。
「琴平さんの希望もあったとはいえ、弊社には勿論責任があります。ですので、琴平さんが緊急連絡先を残した対象であるあなたに、賠償金を支払う所存です。他にご家族は居ないと、琴平さんも仰っていたので」
阿岸は淡々と説明しているが、よくよく見ると、彼の顔色も悪い。冷たい人なのではなく、感情を簡単に表に出せない職業病なのだろう。
そんな阿岸を目にすると、昂っていた気持ちが少し凪いだ気がした。
紅華は余り回らない頭で、直感的に返事をする。
「要りません」
「え?」
「お金、要らないです」
ああ、きっと錯乱してるって思われているんだろう。阿岸は、どんな言葉をかけるべきかを思案するように、視線を左右に彷徨わせている。
紅華は尋ねた。
「まだ、死んだって決まった訳では無いんですよね?」
「ええ、それは、まあ。ですがその確率はかなり高くて……」
「だったら大丈夫です、彼は必ず帰ってきます。ですので、お金は必要ありません」
そんな、と阿岸は反論しようと口を開きかける。だが、その言葉を紡ぐことは無かった。
涙を限界まで溜めた、紅華の瞳に気圧された。
真っ赤に充血した目から、今にも零れそうな涙。だが、阿岸の前だからと歯を食いしばり、全身を小刻みに震わせながら「理性ある大人」として振る舞おうとする懸命さに、阿岸は水を差せなかった。
阿岸はゆっくり立ち上がると、
「何かありましたら、お渡しした名刺の電話番号に、いつでもご連絡下さい。気になること、仰りたいこと等ございましたら、全てお伺い致しますので」
と告げ、一度、深く頭を下げると去っていった。
しばらく経つと、砂同士が擦れる音が消えた。阿岸はもう、公園を後にしたようだ。
それが分かった瞬間、紅華の我慢は決壊した。
「うっ……、うあああああああ!!」
周囲も憚らず、泣きじゃくる。
きらきらの瞳。ふわふわの子犬みたいな髪。気弱な紅華を好きだと言ってくれる懐の広さ。
ずっと一緒に居たかった。居られると思っていた。運命の人で、最愛の人だった。
それなのに。
「いや!いや!どうして、どうして……っ」
肉を直接、切り取られたかのように痛む胸。悲しみに窒息死してしまうと、大人げなく声を上げてしまう。
ふわり。
突如、身体を纏う温かい物体。
婦人だ。婦人が、抱き締めてくれている。
その優しさに、紅華の心はますます悲痛さを覚えてしまった。
「しんでない!しぬはずがない!!」
「ええ、そうよね」
同情している訳でも、呆れている訳でもないことが分かる心地の良い音域で、紅華を肯定してくれる婦人。
彼女の腕に全身を預け、紅華は幼子の様にうわ言を述べる。
「待つって決めたから……っ!約束、したから!だから、何年経とうが、私は、私の愛した人を待つの!帰って来るの!」
ぐしゃりと名刺を握り潰し、紅華は泣いた。
そんな紅華を、婦人は抱き締め続けていた。
──サクヤ、サクヤ。
『おや、何でしょう、この大事な時に』
──貴女、早く休まないと、いよいよ死にますよ。大人しくしていれば後五年は持つのですから、戻らなければ。
『承知しておりますよ。その上で、私はこうしているのです』
──承知している?その行動による自身の結末も?だったら、なぜ?
『……私のやるべきことだと、思うのです』
──やるべきこと、ですか。一体どうしたというのです、ここ三十年ほど、様子が変ですよ。
『私は、これまでずっと、考えていました。命とはなんなのか。命より大事なものはあるのか。その答えを、何十年もかけて探していました。そして今、至ったのです』
──貴女は初め、長生きすることにこだわっていたじゃないですか。病弱だからと、ヒトの身になる時ですらマスクを着けていたというのに。何なんですか、答えとは?
『彼女の想いを支え、繋ぐ事です』
──は。
『きっと、救うべき人やものは他にあるのかもしれません。五年後に、存在するのかもしれません。それでも、今を生きている私は、目の前のこの子の、かけがえのない愛情を途切れさせたくない気持ちで溢れているのです』
──なんと……。それが、貴女の出した結論、ということでよろしいのですか?
『構いません。かつて生き長らえることに執着していた身ですが、これまで出会った方たちとの経験から得たのです。自分の命より、何より、守りたいものが、この世には存在すると。それは多種多様ですが、私にとっては、人々の大切な想いを後へ後へと繋いでいくことなのです。それが、私の存在意義なのです』
──後悔は、ないのですね?
『ありません。私はきっと、人々の愛を、少しでも後に遺していく為に生を受けたのですよ』
「婦人、どうしたの?」
ぐすぐすと鼻を鳴らし、掌で涙を拭いながら、紅華は急に黙ってしまった婦人に聞いた。婦人は目を閉じていたが、すぐにはっと開いて、おやおやと彼女の着物の裾で、紅華の頬を撫でてくれた。
良い香りがした。
紅華はそれに安心して、真っ赤に腫らした目を、嬉しそうに細めた。
婦人が口を開く。
「一緒に、彼を待ちましょう」
紅華はえ、と頓狂な声を上げた。
そんな。見ず知らずのあなたにそんな迷惑は。
そう断ろうとした紅華だったが、婦人はそれを遮った。
歳は召しているものの、上品で美しく、紅華の唯一の味方となってくれた女性。全てが不思議で、でも、全てへの慈愛に満ちた彼女は、まるで紅華が自分の家族であるかの様に、愛おしそうな微笑みを向けて言った。
「あなたを独りにはさせませんわ」