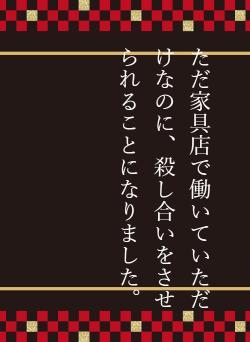「オレを殴れ、」
桜の木が完全に緑に色を変え、その合間から強い日差しが降り注ぐ、五月のことだった。
幼馴染が突然こんな事を言い出したものだから、陽春は気が動転してしまった。
「ええ!?嵐くん、急に何を言い出すの?」
目を丸くし、二、三歩後退りしながら陽春は問う。だが、嵐は真面目な顔で、真っ直ぐに見つめてくるだけだ。
薫風が二人の間を駆け抜けていく。
一体どういう事かと、陽春は近頃の嵐の言動を振り返った。
陽春と嵐は、生まれた瞬間から一緒だった。
とは言っても、双子であるとか、病床が隣同士だったとか、そう言う事情ではない。
陽春のお屋敷に嵐の母親が勤めていて、陽春の母親のお産に釣られるように嵐の母親も産気づいたのだ。医者もその状態の女性を放っておけず、屋敷の女主人とその従業員、両方の子どもを同時に取り上げる羽目になった。
そこから、陽春と嵐の関係は始まった。
親同士はあくまでも雇用状態にあるためそこまで深く関わることは無かったが、子供たちはその限りでは無かった。
嵐の母親が赤子の嵐を屋敷に連れて行くやいなや、陽春が嵐から離れなくなるのは日常茶飯事。嵐の母親が気を遣って嵐を引き離そうとすると、陽春は却って大泣きする始末だった。
そんなことが続き、二人が常に一緒に居るのは当たり前になった。お宮参りもお食い初めも、七五三も、行事ごとは全て一緒。母親の勤務時間中で、屋敷に居る間、二人は片時も離れなかった。
だが、陽春は身体が弱かった。熱を出す、お腹を壊す等の体調不良は度々起きることだった。だからそういう時は、どれだけ陽春が駄々をこねても、一緒には居られなかった。
よって、二人の成長の度合いは大きくなるにつれて、著しく差が開く。五つになる頃は、嵐は健康体そのものなのに対し、陽春は平均よりも小柄だった。
七歳になると、二人は外で遊ぶようになった。
しかし、色白で華奢な陽春は、嵐の目を離した隙によその子から虐められるようになった。豪邸に住んでいる事と、見るからにひ弱なのと、嵐が付きっきりなのが相まってしまったのだ。複数人に囲まれ蹲る陽春の下に、怒声を上げて嵐が駆け付ける。その図式は、道端でよく見かけることとなる。
こういったことから、陽春の嵐への依存度が高くなるのは、必然と言えた。
陽春の思考の中では、嵐が存在することは当たり前。何をするにも、まず嵐の事を考える。
例えば、母親同伴で、デパートで洋服を買うとする。その際、自分の分だけでなく、嵐の分も買うのは当然で、さらに、嵐のその日の気分に合うようにと店頭に並ぶ全種類の購入を頼むのだ。
嵐は、その行き過ぎた行動をやんわりと諫めつつ、それでも陽春と共に居た。
両親も含めた町の人は、陽春の家が経済力を持っているから嵐が気を回しているのか、はたまた陽春から親の雇用について脅されているのか、などの憶測も飛び交っていた。しかし嵐はただ、陽春と共に、穏やかに健やかに時を過ごしているだけだった。
そうして、二人が十歳になった、この初夏に至る。
陽春は、直近の記憶を思い返してみる。しかし、嵐の様子に何ら変わりはなかったはずだ。
冷や汗をかきながら陽春は、目の前の図体の大きい幼馴染に視線を遣る。
──一体どういう事なんだろう?僕、何か悪いことでもしただろうか。いやでも、その場合、殴られるのは僕なんじゃ?
陽春はめまぐるしく思考を巡らせ、必死に嵐の発言の真意を探るが、一向に答えに辿り着けない。
対する嵐は、静かな表情をしている。まるで、老人が通り雨を眺めているかのようだ。
「いや、どういうことなの!やっぱり分からないよ!」
堪りかねて、陽春は嵐に突っ込んだ。
寡黙な嵐に比べて口が回る陽春は、言葉足らずな嵐を、こうしてよく問いただす。そうすると大抵は、嵐がぼそぼそと補足説明をしてくれるのだ。
だが、この日は違った。
嵐は黙って首を横に振り、同じことを繰り返すのみだ。
「俺を、殴れ」
と。
「そんなこと、大事な嵐君に出来る訳ないじゃないか!全くもう、冗談はよしてよ」
嵐がそんなジョークを言う男ではないことは知っている。それでも、そうとしか考えられなかった。
「さあ、今日は何して過ごす?河原に行って、魚捕りでもするかい?それとも、駄菓子屋でおやつでも買って、ピクニックに行こうか」
陽春はいっそ聞かなかった事にして、この後の予定を立て始めた。
時刻は午後二時。夕飯までには、十分過ぎる時間がある。
わくわくと、陽春は遊びの候補を挙げた。
しかし、嵐はそんな陽春の右手をぱし、と掴んで引き寄せると、とんと自分の胸に当てる。
そして、重ねて言った。
「殴れ」
ああ、やっぱり冗談なんかじゃなかったんだな。こうなってしまったら嵐はもう、他の話を聞かない。
陽春は半ば諦観し、ため息をついた。
「……分かったよ。理由は分からないけれど、とにかく殴れば良いんだね」
嵐はこくりと頷き、陽春の手を放す。陽春は、嵐と向かい合った。
とりあえずふりだけでもすれば、嵐の気は済むだろう。
そう思い、手を振りかざす。
嵐の左頬に、握りこぶしを優しく当てるだけに留めよう。
ゆるゆるとやる気なく、右手を伸ばす。その拳が、嵐に触れかけたその瞬間──。
ガシッ!
「え」
力強く、嵐の左掌に手を包み込まれた。
そのまま、二の腕を掴まれたと気が付いた時にはもう、世界が反転していた。
ドサ。
陽春が怪我をしない様に柔らかく、だが圧倒的な力量差を見せつけながら、嵐は陽春を背負い投げた。
抜けるような青い空を背景に、陽春を覗き込む嵐の顔が瞳に映る。
突然投げ飛ばされた衝撃で顔を強張らせながら、陽春はせめてもの反抗をした。
「ひどいじゃないか。殴れって言うから君に嫌々拳を揮ったっていうのに」
陽春を起き上がらせつつ、嵐は黙ってそれを聞き入れる。さらに、陽春の服に付いた砂を丁寧に払ってくれた。
こういう所はいつも通りの、優しい友人なのだが。稀に、何を考えているのか分からない時がある。
困惑する陽春が落ち着いた時にようやく、嵐は首を横に振りながら、初めてちゃんと彼の意図を告げた。
それは、陽春にとって、全く優しくなかった。
「俺を、殴れるようになれ」
陽春の最も古い記憶は、泣きながら嵐の服の端を掴んでいるものだ。
二歳だったか三歳だったか、恐らくその位だっただろう。どうして自分が泣いているのかなど、そんな事はとうに忘れた。
陽春にとって重要なのは、それ程の幼い頃から、嵐と共に居たという事実。それだけだ。
自分が同じ歳の男子にのけ者にされているのは理解している。軟弱な見た目が、それでも生きていけるという裕福な家庭環境を裏付けているようで腹立たしいのだろう。彼らは幼いながらにも、家庭格差はひしひしと感じていたのだ。
嵐がいない隙を見計らわれ、名も知らぬ者たちに幾度と無く蹴られた。なじられた。石を投げられた。それでも、陽春は気にならなかった。
嵐が居るから。
助けてくれるとか、ボディーガードになるとか、そういう事は一切関係なく。
嵐の存在が心の内にあるだけで、陽春は無敵で、ほっとする気持ちになれるのだ。
もしかしたら、刷り込み効果なのかもしれない。ずっと一緒の、下手すれば両親よりも身近に感じる人だから、無条件に安心しているだけなのかもしれない。
ただの腕っぷしが強い、幼馴染。そう言ってしまえばそれまでだが、そんな彼に、尊敬やら家族愛やら、師弟愛やらを含めた重たい感情を抱いているのは確かだ。
これからも、一生、側に。
これは、陽春が五歳の頃から変わらない願いだ。
「こ、こうさんっ!降参だよ嵐君!勘弁して!」
ずりずりと、砂上を靴が滑る。嵐に押されている上半身が、弓の様に反って痛い。
陽春は堪らず悲鳴を上げる。しかし、
「まだ、線を出ていない」
嵐はそう言って、陽春へ力を掛けるのを止めてくれない。
これは、互いの背後に線を引いて、相手をそこから越えさせた方が勝ちという、相撲の様な取っ組み合い。だが、どちらが勝つかは明白だったし、そもそもこれは勝負ですらない。
陽春が嵐を殴れるようになるための、訓練だ。
「そうは言っても……っ、もう無理だってうわあ!!」
どたん!!
陽春の両足が宙に浮く。背中から、勢いよく地面にひっくり返った。肺が圧迫されて、息が出来ない。
「ごほっ、ごほごほ……!」
「だ、大丈夫か?」
咳き込む陽春に、慌てて駆け寄る嵐。陽春の上半身をゆっくりと引き起こし、背中をさする。
「だ、いじょぶ……けほ」
陽春は心配かけないようにと、無理やり酸素を取り込みつつ返事をした。
しかし嵐は、
「悪い、やり過ぎた」
と、陽春だけが分かる、しゅんとした面持ちで謝ってきた。
そんな嵐の肩を叩いて、陽春は笑った。
「良いんだって。これも、訓練の内だろ?」
それでも、嵐は複雑な表情を浮かべていた。
六月中旬。少しずつ陽射しが熱を帯び始め、動いたら汗ばむようになってきた頃。
陽春と嵐の特訓は、着実に行われていた。
嵐は決して、自分を殴らせたい理由は教えてくれなかった。初めはもう、それはそれは疑問と拒否の塊だった陽春だった。が、滅多に自分の意見を言わない嵐の貴重な我がままを許さない訳にはいかず、最後には折れた。
だからこうして一か月半もの間、嵐主導での鬼訓練に耐えてきたのだ。嵐が決めたトレーニングをこなす日々の中、休めるのは、陽春が体調を崩した時だけだった。
これまで走り込み、バケツ持ちなどの基礎体力の構築は勿論、先程やっていた様な相撲や取っ組み合いなどの応用訓練も実施された。だが、体力も筋力もない陽春は、嵐に付いていくだけでも大変だった。
嵐を追って、川辺を走った時。どんどん、どんどん小さくなる嵐の背に焦りを感じたものの、足と肺は思うように動いてくれない。やたらめったらに手足を前へ振っても、その差は全く埋まらず、しまいには過呼吸になってしまった。
また、筋力向上の為にと腕立て伏せやうさぎ跳びなどをさせられたが、たった数回で音を上げた。
このような苦しかった日々を思うと陽春は、つい遠い目になってしまう。
「おい、大丈夫か?陽春」
過去に記憶を飛ばしている、陽春の朧気な視線が気がかりなのか、嵐が重ねて様子を尋ねる。
慌てて現世に意識を戻した陽春は、両手を横に振って答えた。
「ごめんごめん、問題ないよ。少しぼーっとしてただけ」
しかし、陽春がそう言っても、嵐は眉を下げるばかりだ。
さらに少し逡巡した後、嵐は言う。
「今日はもう、終わりにしよう」
「ほんと!?やったー!」
陽春は思わず歓声を上げてしまう。
いつもなら日が暮れるまで行われる特訓だが、公園の時計はまだ三時だ。普段よりもかなり早く苦行から解放された。
「久々に遊びに行こうよ嵐君!偶には息抜きも大事だよ!」
きらきらと瞳を輝かす陽春を、嵐は目を細めて見つめる。それから、こくり、と頷いた。
「ああ、そうだな」
その言葉に、陽春はぱあっと顔を明るくし、嵐の腕を取った。
「やったあ!じゃあねじゃあね、お菓子屋さんに行こう!」
一目散に駆け出す陽春。
「……お前、訓練の時より走るの早くねえか?」
大人しく手を引かれつつも、嵐は呆れたように呟く。
「気のせいだってば!ほら早く!」
やれやれと首を振る嵐に構わず、陽春は弾けるように駆ける。
嵐と、何の気兼ねも無く遊べる。この時間の有意義さは、痛いほど分かっていたから。
そしてそのままの勢いで、良く訪れる駄菓子屋に飛び込んだ。
「やっほーおばちゃん!」
「あら、陽ちゃんに嵐ちゃん、久しぶりねえ」
元気な陽春の挨拶に、居間に腰掛けた老婦人が愛想よく答える。
家屋の一部を商業用に改築してあるこの菓子屋では、よくある光景だ。冬時など、下手すればこのおばあさんと共にこたつに入ることさえある。
「元気してたかい?あら、陽ちゃん、少し背が伸びたんじゃない?」
手にしていた湯呑をちゃぶ台に置き、老婦人はにこにことしながら二人に近付いてくる。
「本当!?やったね、嵐君!特訓の成果だよ」
「おばあの気のせいだろ。人間はそう簡単に大きくならない」
「ええ!ひどいよ嵐君……」
淡々としている嵐に対し、一喜一憂する陽春の対比が愉快だったのか、老婦人はころころと笑った。
それから、二人に尋ねる。
「さ、お坊ちゃん達は今日は何を所望だい?」
「んーとね、んーと……」
陽春はきょろきょろと店内を見渡した。きな粉がかかった小さなお餅に、猫が目印のガム、お煎餅。どれも美味だが、ピンとこない。
と、アイスがたくさん詰まった冷凍庫が目に入った。青、白、ピンク。色とりどりの氷菓に、一瞬で心を奪われる。
美味しそうだなあ。
陽春がそう思った途端、嵐が返答した。
「棒アイスを一つ、お願いします」
すかさず財布をポケットから取り出す嵐。
「嵐君!偶には僕にも驕らせてよ」
そう言って、自分の財布を出そうとしたが、嵐に手をがしりと掴まれ、阻まれた。その上、こう付け加えられる。
「だめだ。陽春には、頼らない」
むう、と陽春は唇を尖らすも、嵐は完全に無視している。
こういう時、嵐は一切陽春にお金を出させない。お小遣いの絶対量は陽春の方が多いのに、財布の紐すら解かせようとしないのだ。
「毎度。好きなの一つ、持っておいき」
「陽春、どれがいい」
嵐に判断を委ねられ、陽春はううん、と唸る。
どれも気になる。でも、嵐は余り甘い味を好まない。だから、
「この、青いのがいい」
るんるんと、ガラスケースから透明な小袋を取る。
それから二人で老婦人にお礼を述べて店を後にし、少し歩いた先の青いベンチに座った。
「早く早く!溶けちゃうよ」
「分かってる」
待ちきれないと言わんばかりの陽春を宥めつつ、嵐は二つの棒が付いたアイスをぱきっと割る。
「あ!嵐君のへたっぴ!」
陽春は指をさし、からかうような声を出す。
片方の棒にばかり、アイスが多くなってしまったのだ。
にへへと笑う陽春に、嵐は無言でアイスの片方を差し出す。
大きくなってしまった方を。
「え、嵐君がこっちを食べなよ。お金を出したんだから」
陽春が慌ててそう言っても、嵐は手を引っ込めない。
「暑いから、喉乾いてるだろ」
「……うん。ありがとう、嵐君」
陽春は大人しく、嵐の手からアイスを受け取る。
これも、いつもの事。量が多い方や、得な方を、必ず陽春にくれる。
その気持ちが嬉しくて、陽春は何となく、アイスを目の上に掲げてみた。
晴天に負けない程青い、ソーダ味の氷。それが、光を透かしてより一層、きらきらと輝いていた。
しばらく無言で、しゃくしゃくとアイスを齧る。ほんのり酸っぱい風味が、疲れた身体に染み渡るようだった。
アイスを食べ終わっても、二人でぼうっと空を眺める。言葉は無くても、心地の良い時間だった。
爽やかな風に、陽春の前髪が揺れる。
「僕はいつまでに、嵐君を殴れるようになればいいの?」
足をぶらぶらとさせながら、陽春は何気なく尋ねた。
しかし嵐は、それまで穏やかだった顔をむう、としかめる。それから、喉のつかえを吐き出すように、言った。
「……出来るだけ、早く」
そのただならない雰囲気に、陽春は不安になった。
嵐君は、何を考えているのだろう。何を望んでいるのだろう。
物静かで、表情もあまりない嵐の感情は、他人には読み取りにくい。それでも、幼馴染の甲斐あって、陽春なら大体理解できる。しかし、今回ばかりはてんで分からない。
──僕は、嵐君の為に在りたいのに。
もどかしい気持ちが一気に湧き起こり、陽春はぎゅっと唇を噛み締める。
すると、
「陽春」
横から、柔らかく、低い声がした。
「うん?」
顔を向けると、こつん、と額に嵐の拳が当たる。
その向こうに、嵐の優しい顔が見えた。
「考えすぎ」
ふ、と小さく笑う嵐に、陽春はどうしてもほっとしてしまう。これはもう、条件反射だ。こくりと頷く陽春を認めると、嵐は、
「帰るぞ」
と、腰を上げた。
「ええ、もう?まだ夕飯まで時間あるよ」
不満げな陽春の手を取って立ち上がらせると、嵐は言った。
「今日はもう家に帰って休め。そろそろ熱が出てもおかしくない」
そこを突かれると、陽春はぐうの音も出ない。陽春の体調管理は何故か、陽春よりも嵐の方が得意なのだ。
「はあい。じゃあ、帰ろっか」
今度は素直に従い、陽春は歩き出した。嵐もすぐ隣に並ぶ。
そうして、嵐はこれまたいつものように、陽春を家まで送ってくれた。
「また明日ね」
陽春がそう言うと、嵐は黙って片手を挙げた。
ある日のこと。
外は雨が降っていた。
それも三日連続で、だ。
時期的に雨が続くのは仕方がないのだが、陽春は気圧が低いと頭が痛くなってしまう。
この日もひどい頭痛に見舞われ、陽春は一日中床に伏していた。
夕方頃になってようやく起き上がれるようになった陽春は、喉の渇きに気が付いた。のろのろと起き上がって、台所へと向かう。
ふらふらとした足取りで勝手口に辿り着いた陽春だったが、そんな彼を見つけた台所係の婦人は、
「まあ、陽お坊ちゃま!呼び付けて下されば参りましたのに!」
と、慌てた声を上げた。即座に駆け寄り、椅子を準備してくれる。
それから陽春は、常温の水が入ったコップをもらうと、一息に飲み干してしまった。温い液体が体内を通っていく感覚に、頭の痛みが少し収まった気がする。
何となく、炊事場で働いている顔見知りの使用人たちを眺めてみた。くるくると軽快に動く三人の婦人を見ている内に、ふとあることに気が付く。
「嵐のお母さん、最近見ないね。配膳にも来ないし、ここにもいないし。台所係は辞めて、他の当番をしているの?」
陽春の疑問に、炊事に従事している婦人たちは顔を見合わせる。そして、眉を曇らせながら言った。
「いえ、一か月前位からいらっしゃってませんよ。体調不良、とかなんとかで。まあ、それ以前からも、様子がおかしい節はありましたが……」
「え、そうなの?全然知らなかったよ」
嵐はそんな事一つも言っていなかったし、陽春の両親も、それに関する言及は何もしていなかった。嵐の母親は使用人の中でも古株の方だから、少しくらい話題に上っていてもおかしくないはずだが。
しかし、別の婦人がさもありなん、と言わんばかりに話の続きを引き取った。
「それもそうでしょうね。最近は陽坊ちゃん、お台所に来なくなりましたから。ご飯を召し上がって、お風呂に入ればもうお休みになられてらっしゃるでしょう?」
「え……、ああそう言えば」
記憶を辿りながら、陽春は空を見つめる。
一か月前と言えば、嵐と特訓を始めてしばらく経った頃だ。言われてみれば近頃は、陽春は家に帰るとへとへとで、夕飯とお風呂を頂くので精一杯だった。だから以前ほど台所に顔を出すことが無くなってしまい、そのせいで気が付かなかったのだ。
嵐の突飛な提案と、嵐母の体調不良には、何か関係があるのだろうか。
首を傾げながら、陽春はもう一杯だけ水を貰った。
その後、部屋へ戻ろうとした陽春に、婦人たちは優しく微笑みながら声を掛けた。
「陽お坊ちゃま、私共に何でもお言いつけ下さいませ。皆、陽お坊ちゃまに中々会えなくて寂しい思いをしておりますから」
その顔に、陽春はほんの少しの申し訳なさを感じて、素直にうん、と答えた。
七月下旬。
蝉の声が響き渡る公園で、陽春と嵐は睨み合っていた。
「いくよ、嵐君」
「ああ」
嵐が頷いたと同時に、陽春は地面を蹴った。
嵐に向かって真っ直ぐ走る。それをじっと見据える嵐。そんな彼のすぐ手前で、陽春は跳び上がった。そして嵐の下腹部に向かって右足を突き出す。
「ほう」
嵐はさっと身体をずらし、陽春の飛び蹴りを躱す。すとん、と飛び降りた陽春に向かって、嵐は口を開いた。
「ほら、次はどうした」
「言われなくても!」
嵐の静かで激しい挑発に、陽春も応える。
二人の勝負を見守るのは、緑の葉を風に揺らす桜の木、ただ一本のみ。
陽春は着地の体勢から上半身を右回りに捻り、その勢いのまま左足を地面すれすれで振り回す。嵐の足を払おうと試みたが、嵐はタイミングよくその足を踏み、陽春の動きを止めた。
しかし、
「いっ…」
「あ、悪い……!」
陽春の呻きに、嵐は即座に足を引っ込める。
だが、それが狙いだった。
「隙だよ!」
嵐に踏んづけられていた足を、そこから真っ直ぐ蹴り上げる。顎先を砕く位の意志をもって足を振ったが、
「おっ、と」
と、軽く顔を逸らされてしまう。それを見て陽春は、
「やあっ!」
やけくそに左拳を突き出すが、その掌も簡単に捕まる。そのままどんっと腕ごと押されて、陽春は派手に転げた。
くそ!と陽春は砂に塗れながら、歯噛みする。
悉くを避けられる。体格差もさることながら、嵐は元々身体能力が高い。少し工夫しただけでは、陽春の攻撃はかすりもしない。
それでも、嵐に勝つことは目下達成すべき目標であり、(不本意ながら)義務である。
この数か月の努力の成果を、どうすれば出せる。
どうすれば、嵐君に勝てる。
土に爪を食い込ませながら、陽春は一生懸命考えを巡らす。
嵐君には、単純な力勝負では敵いっこない。かと言って、映像で見たようなアクションを真似してみても通用しない。
ぐぐっと立ち上がりながら、嵐を睨む。
対する嵐は身動ぎもせず、じっと陽春を見下ろしている。
一か月前も、こうして転がされたっけ。あの時は……、そう、無理に押し返そうとして逆に宙に飛ばされたのだった。
ああそうか。
やっぱり力では勝てない。勝てないんだ。
陽春は、ぱんぱん、と膝の砂を払うと、肺に思いっ切り酸素を取り込んだ。
すうーーーっ。よし。
正面を向き、嵐と顔を合わせる。
直後、
「うおおーーー!」
と、叫びながら、直線上に突っ込んでいった。
嵐は少々戸惑いながらも中腰になり、突っ走ってきた陽春をしっかり受け止める。
「おい、やけになったのか」
ぐいぐいと懸命に自分を押す陽春の両の掌を労せず留めつつ、嵐は呆れたように言った。
そう思われても仕方がないと、陽春は自覚している。
でも、今出来る事はこれしかない。
陽春は渾身の力を込めて、身体を前進させていく。一歩、また一歩と、嵐を追いやっていく。
それが、出来ているつもりだった。
地面が動いて見えていた。でもそれは、自身が嵐に押されているから。
力の均衡を保てているように感じていた。でもそれは、嵐が陽春の上半身をブレさせずに圧しているから。
気付いた時には、陽春は先程の位置から一メートル程も後退させられていた。
たった数か月程度の鍛錬では埋まらない、パワーの差。その圧倒さに、陽春の心は折れかける。
「わああああーーー!」
躍起になって、がむしゃらに両腕に全体重をかける。
びくともしない嵐は、その行動に眉を顰めた。
「お前が不真面目なのなら、オレも容赦はしない」
ぐっと拳に力を込め、全身全霊で陽春を追い詰め始める。
ずりずりと地面を滑る靴裏の感触に、陽春は焦った。
本当に、これで上手くいくのか。
とは言え、この手しか思いつかない。
だから、これしかないのだ。
陽春は、後ろに流れる身体を止めようと、つま先を立ててぐっと足先に力を入れた。
が。
足を踏ん張った反動で、陽春の上半身がぐわりと弓の様に仰け反る。
「何やってんだ陽春!これでは無理だと、分かっているだろう!」
陽春に怪我をさせたくない嵐は、焦燥感に満ちた怒号を飛ばす。このままでは以前と同じ様に、放り投げられて陽春が負けるからだ。
そう、このままでは。
「うん、そうだね」
陽春はふっと、微笑む。
途端、陽春はがくんと両腕の力を抜いた。
力の行き先が無くなり、つんのめる嵐。バランスを保とうと、陽春の手を掴む握力が緩む。その間に掌をするりと抜き、すかさず身をかがめて嵐の背後に陽春は回る。
とんっ。
軽く、押すだけで良かった。
後方からの不意な力に嵐は耐えられず、前のめりになって転ぶ。嵐が地面に手を突いたタイミングで、陽春は嵐の顔の前に迅速に回り込み──、
嵐の頬を、両手で挟んだ。
そして、宣言する。
「僕の勝ち。だよね?」
「まだ、殴られていない」
不服気に言う嵐に、陽春はにっこり笑って答えた。
「そうだね、でも僕は君を、今、いつでも殴れるんだよ」
嵐はしばらくじっと、陽春の満面の笑みを睨んでいた。だが、
「分かった、降参だ」
そう、ふっと笑って言った。
「……ほんとに?」
半ば信じられない陽春は、自身が言い出したことなのに、嵐に逆に聞き返す。不安そうな表情の陽春に、嵐は端的に告げた。
「本当だ。陽春の勝ちだ」
それを聞いた陽春は、身体の奥底から嬉しさが溢れるのを感じた。
「やったやった、勝ったよ!嵐君に勝った!!」
ぴょんぴょんと飛び跳ね、全身で喜びを顕わにする。
そんな陽春に、嵐はゆっくりと近付いて行った。
そして、陽春の上下する肩に、ぽんと手を置き、言う。
「そうだ。お前はオレに勝った。だからもう、」
訓練の終わりかな、なんて、陽春は呑気に続きを待っていた。そんな陽春に、絶望の言葉が降りかかる。
「絶交だ」
と。
「え……?何て?ごめんね、良く聞こえなかったみたいで」
陽春は、恐る恐る聞き返す。
本当は、しっかり聞こえていた。
でも、認めたくなくて。何かの間違いだと思って。
かすかな希望に賭けた。
だが嵐は、
「絶交、と言ったんだ。オレとお前はこれきり。さよならだ」
と、冷たく言い放つ。
「う、ええ?また急に、何を言い出すんだよ嵐君……。冗談にしたってひどいよ」
陽春は困惑しきってしまった。嵐の言葉を解読するのにいっぱいいっぱいだ。
しかし、混乱している陽春を放置し、嵐は背を向ける。そしてすたすたと、歩き出してしまった。
「ま、待ってよ嵐君っ」
陽春は追いすがる。それでも、
「付いてくるな!」
嵐は半泣きの陽春を凄まじい形相で睨み、怒鳴りつけた。陽春はびくっと身体を跳ねさせ、立ち止まる。
嵐はさらに、
「さよならだと、言っただろう」
こちらを一切振り向くことなく、そう、ぼそっと呟き、足早に公園を去っていった。
一人残された陽春は突然の事に、足に根が生えたが如く、その場に佇むことしか出来なかった。
それから数日間、陽春は布団の中で泣き暮らした。
事情が何も分からない両親はいたく心配したが、どれだけ声をかけても陽春は部屋から出なかった。せめて、と食事を部屋の前に持って行くが、手を付けるのは一日に一食のみ。日がな一日、陽春は涙を流しては眠り、起きては枕を濡らしていた。それしか、出来なかったのだ。
嵐の手を引いて、走っている。
これは、五歳の時。二人とも袴を着ているから、きっと七五三だ。
走っている理由は確か……、ああ、巫女さんが見えた、そうそう。千歳飴を貰いに行っているのだ。
陽春のお参りに、嵐の家族も強引に付き添わせたのだ。嵐の両親は他の従業員の手前、申し訳なさそうにしていたが、陽春の、嵐へのべったり具合を皆知っていたので、文句を言う者は誰も居なかった。
「はい、どうぞ」
陽春はお巫女さんから、めでたい柄が描かれた紙袋を一つ、手渡された。
中には赤と白の、二つの千歳飴。二人で一つずつ、という彼女の意図なのだろう。陽春は、どちらの色の飴を食べようか悩んだ。
すると嵐が、
「はんぶんずつにしよう」
と、飴が入ったままの紙袋を、真ん中から二つに折り曲げた。中で、ぱきっと音が鳴る。再び袋を開けてみると、しかし、不揃いな大きさの飴が四つ。
「あらしくんのへたっぴ!」
それを見て、陽春はけらけらと笑う。嵐は何も言わず、自分の飴を二つ、一色ずつ取った。そして残りを、袋ごと陽春に差し出す。
受け取った陽春は中身をごそごそと漁り、驚いた。二つとも、折られた中で、大きい方の飴だった。
「あらしくんが、かたっぽおおきいのたべなよ」
陽春は咄嗟に赤の飴を嵐に渡そうとした。しかし、嵐は受け取らない。
「いいから」
そう、突っぱねるばかりだ。
傍からだと、かなりぶっきらぼうな言い方に聞こえる。だが、陽春には分かっていた。
嵐のそれは、照れ隠しだと。
だから陽春は笑って、手に持ったままの千歳飴を口に含んだ。
優しい甘さだった。
ぱっと、景色が切り替わる。
真っ暗だ。葉っぱがちくちくと肌を刺す。茂みの中でしゃがみこんでいるのは、六歳の頃の自分だ。
指先がかじかんで、身体がぶるぶると震えている。初秋の日暮れ。その気温の低さを、この時初めて知ったのだ。
何でこんな時間に一人で……?いや、思い出した。
これは、かくれんぼの最中だ。
ただ、そう思っているのは陽春だけだ。
珍しく、いつもは虐めてくる少年たちが遊びに誘ってきた。これまでの行動を許してくれ、一緒にかくれんぼをしようと。とても嬉しくて、嵐が止めるのも聞かず、その提案に乗った。嵐は嵐で、大人に仕事を手伝う様に強引に誘われ、渋々ついて行った。
鬼は自分がするから隠れろ。
そう、いじめっ子のリーダー格が言ったので、その通りに陽春は隠れた。しかし、いつまで経っても、誰も陽春を見つけに来なかった。
それもそのはず、陽春は謀られたのだ。
最初から、彼らには陽春を探すつもりなど毛頭なかった。寒空の中放置すれば、さぞ辛い思いをさせることが出来るだろうという、幼いながらに残酷な企てをしていたのだ。
まだ他人からの悪意に鈍かった陽春は、それに気が付かなかった。純粋に、ひたすら、隠れ続けた。
しかし、数時間経つ頃には、陽春の人を信じる思いにも、とうとう限界が訪れる。
寒い。怖い。寂しい。家に帰りたい。
かと言って、足が凍えて自力で歩くことも、立ち上がることすらままならない。
──もう、嫌だ。
「ぐすっ……」
様々な辛苦が、ほんの一粒の涙となって零れる。しかし、溢れてしまったが最後、とめどが無いのはこの世の摂理で。
「ぐすん、ぐすん……、うううっ」
ごしごしと、濡れる頬を掌で拭う。それでも、顔は冷たくなる一方だし、嗚咽は止まらない。
「嵐君……、嵐君っ……」
とにかく誰かに助けて欲しかった。と言っても、陽春にとってその誰かはたった一人で、その名を小さく呼ぶことしか出来なかったけれど。
そうやって泣き続けること、十数分。
頭がぼうっとし始めた。心身に圧し掛かるストレスのせいか、意識が遠のいていく。
その上、
「……ん、…しゅん」
自分の名を呼ぶ幻聴が、幽かに耳に届いた。
きっとこのままここで、死んでしまうのだ。そんな考えに囚われ、涙がまた一つ、肌を伝う。
その直後。
「陽春!!」
がさがさがさっ。
茂みをかき分ける音と共に、切望していた声の主が現れた。
「あ、嵐君……?ぐす、なん、何で?」
驚いて、意に反してたどたどしい物言いになってしまう。
「陽春の……、泣き声が聞こえたから……」
嵐は途切れ途切れにそう答えたが、途端、愕然とした面持ちでがくりと膝を折り、項垂れた。
嵐は、陽春の憐れな風体を目にし、只々後悔の念に苛まれたのだ。
「ああ、陽春……。悪い、俺がしっかりお前を引き止めていれば、こんな事には……」
低く、呻くように、謝罪の言葉を口にする嵐。
両手で顔を覆った嵐の初めて見る姿に、却って陽春が申し訳なくなる。
「あ、嵐君、僕は、僕は大丈夫だから、ね?」
歯をかちかちと鳴らしながら、陽春は微笑む。
嵐はその笑顔に、より一層痛ましさを感じた。だが、くだらない問答で、陽春にこれ以上負担を掛ける訳にはいかない。そう思い、無言で陽春を抱き締める。
その身体はとても冷たくて、まるで氷の彫刻の様だった。
体温の低さに戦慄する嵐に、陽春は眠たげな声で、話しかける。
「嵐君が見つけてくれたから、僕は嬉しいんだ。ほら、あれ言ってよ、あれ」
「あれ?あれってなんだ」
陽春の舌足らずな声音に心配が勝りつつも、嵐は罪悪感から陽春の話に付き合うことにした。自身の肩口で綴られる言の葉に、耳を傾ける。
「僕はね、嵐君と、かくれんぼをしていたんだよ。そう思う事にするんだ。だから、」
「ああ、分かったよ。分かったから」
嵐は陽春の言いたいことを瞬時に察した。そして、望まれるままに、口を開く。
「陽春、見っけ」
それを聞いた陽春が、にっこりと笑った気配がした。
嵐が陽春の手を取り、立たせる。陽春は、一瞬だけ触れた嵐の手が、傷だらけなのに気が付いた。
きっと僕を、あちこち、探し回ってくれたんだ。
それから、嵐に背負われて、帰路に就く。嵐が一歩、地面を踏むごとに身体が揺れ、眠気に襲われる。
他人からの好意など、簡単に移ろう儚いものなのだと、しっかり理解した。
でも嵐の背中はとても、とても温かくて、その熱は昔とちっとも変わらなかった。その事実に、陽春はひどく安心する。
それより後の事は、覚えていない。ただ次の日、陽春は盛大に熱を出し、関節が痛かったことだけは記憶に鮮明に残っている。
再度、景色が変わる。
溶鉱炉のような夕陽が、正面にあった。
この光景は、印象的だった。八歳の時の、習い事を終えた帰り道だ。
この年、陽春はそろばんとヴァイオリンを習い始めた。
それにはもちろん、嵐も付き合わせた。いずれ自分の右腕になる男なのだから、同じ教養は必要だと、両親を説き伏せたのだ。
嵐の強い要望で、ヴァイオリンは共に習う事は出来なかったが、そろばんの授業は並んで受けた。そして、嵐に家まで送ってもらう。それが、いつもの流れ。
その内の、いつかの帰路だ。
家も、店も、道路も、目に映る全てが赤くて、陽春には、世界が燃えているように思えた。
「真っ赤だね」
陽春は、前を歩く嵐に声を掛ける。彼は振り返り、静かに答えた。
「そうだな」
だが、その表情は逆光で陰っていて、上手く見えない。何だか嵐が、嵐でないような気がした。
そうやって、どんどん嵐が遠くなっていくのではないか。変わってしまうのではないか。
そして最後には、離れていってしまうのではないか。
この時、そんな底知れない恐怖に陽春は囚われ、どうしようも無くなった。
だから、
「僕達ずっと、一緒だよね?」
こう、嵐に問いかけた。
脈絡も何もない、突然にしては重たい質問。尋ねられた方は困って然るべき追究だった。
それでも、嵐は笑うでも、馬鹿にするでもなく。
先生に投げられた「一足す一は?」を答えるような声音で。
言ったのだ。
「当たり前だ」
ぱち。
陽春は目を覚ました。ぼんやりした頭の中に漂うのは、ひとさじの幸福感。しかしそれは、徐々に意識がはっきりしていくにつれて、あっけなく悲しみ一色に塗り替えられていく。
夢。そう、ただの夢。幸せに溢れた、過去の記憶。
その事に気が付いて、胸がきりきりと痛む。
つう、と温かいものが、目の端から流れ出る。
嘘つき。噓つき噓つき噓つき────。
ずっと一緒に居てくれるって、言ったのに。
絶交、絶交だなんて。僕はこれからどうしたら。
僕は、僕は、僕は!
がばりと、陽春は上半身を起した。
苦しさに居ても経っても居られなくなって、突然思い立った。玄関に赴き、靴を引っ掛ける。
はあはあ、と胸に痞えたものを吐き出すように、大袈裟に呼吸をしながら走った。
走って走って、そうして訪れたのは、嵐とよく遊んだ、桜の木がある公園だった。
もちろん、嵐はおろか、人影があるはずもない。
それでも、なんとなく公園の中央を目指す。よろよろとした足取りで、ただ一本、どんとそびえる木の根元に、辿り着いた。
表皮に、そっと触れてみる。熱を持たないはずなのに、何故かほんの少し、掌に温もりを感じた。
ほっとして、そのせいで張り詰めていたものが切れてしまって、どさ、と膝から崩れ落ちる。
「う……、ううっ」
目の前の土の色がぼやける。喉の奥が、刺されたように痛くて熱い。
「あらしくんっ、あらしくん……っ」
走馬灯のように、二人で過ごした日々が思い起こされる。
でもそれはもう、二度と手に入るものではない。全て、全て、取り戻せないもの。
そう思うと、陽春はもう、耐えられなかった。
「うわああああああん!」
人目をはばかることなく、思い切り泣き叫ぶ。泣いても叫んでも、どうしようもないのに。
それでも、泣き喚きたくて仕方がなかった。
このまま、消えてしまえば良い。流れる涙と一緒に、或いは、遠く広がる暗闇に吸い込まれるこの声のように。
お願いします、神様。
僕という存在も一緒に、どこか遠くへ、消してください──。
「まったく」
突然、背後から声がした。凛としていて、だがまだあどけなさも残る、女性の声。
「泣き声が大きくて、目を覚ましてしまいましたわ」
みっともない姿を取り繕うこともせず、陽春は振り向く。
そこには、白っぽい色のワンピースに、同じ色の帽子と手袋を身にまとった、妙齢の女の人が立っていた。口元をハンカチで覆っているせいで、隠された顔から垣間見える細い目が印象的である。
こんな夜中に、一体どうして人が。目を覚ましたってことは、近所に住んでいる方なのかな。
驚いた弾みに、涙が止まる。
さらに、しゃがみこんだ陽春につかつかと近寄って来る彼女に恐怖を覚え、咄嗟に身を竦めた。
うるさいと、怒られてしまうのかも。どこの家の子かと問い詰められて、強制的に家に帰らされるかも。
そう怯える陽春の耳に、何やらぶつぶつと呟く声が届く。
「全く、もうヒトにはならない……のに。小さい子にこうも泣かれては……おけません」
ハンカチ越しで声がくぐもって良く聞こえなかったが、彼女が言っているようだ。口調から鑑みるに、どうやら怒っている訳では無いらしい。
呆れてはいそうだが。
眉を上げるでも下げるでもなく、表情の無い女性は呆然とする陽春の手を取り、立たせた。そして徐に、
「あちらでお話ししましょう。何がそこまで貴方を苦しめているのか、お教えなさいな」
相変わらずハンカチは外さずに、それでも彼女は陽春の手を柔らかく握り、ベンチへと連れて行った。手で促して、陽春を座らせる。
しかし、陽春は見ず知らずの人に、何を、どこから語ればよいか分からず、黙ってしまった。
口を開いては閉じ、開いては閉じ、を繰り返す陽春に痺れを切らしたのか、女性が先陣を切る。
「大まかな事情は知っていますわ。貴方があの彼とどれ程の時を共に過ごし、どんな別れ方をしたのか」
「え!?どうして、いや、何で……?でも、それだったら」
陽春は意味が分からず、聞きたいことで頭がぐちゃぐちゃになる。そんな陽春に、彼女は淡々と、
「生憎眠っておりましたので、声と朧げな映像しか覚えておりませんの。ごめんなさいね」
などと謝る。しかし、尚一層、意味が理解できない。
だが、女性はそんな陽春はさておいて、変わらず話を続けるのだった。
「さあ、貴方の口から、気持ちを聞かせて下さいな。そうでなければ、わざわざこうして出てきた甲斐がありませんもの」
不思議な事を言う人だ。
陽春はそう思ったが、素直に、これまでの嵐との関りや、嵐への気持ちを語った。
何故だか彼女には、語っても良い気がした。
「それは……」
美しい糸目の女性は、陽春の話を聞き終えると、低い声を発した。
「ねえ、どうすれば、仲直り出来ると思う?」
陽春は、年上のお姉さんなら何か答えを知っているかもしれないと考えていた。
しかしながら、彼女は布でほとんど隠れていても分かる程の険しい表情で、答えた。
「復縁は、厳しいでしょうね」
「ふくえん……?」
「まあ所謂、仲直り、ですわ」
「ええ!?そんな、何でそんなこと言い切れるの!?」
怒りを滲ませすらする陽春に対し、女性は長い絹糸の様な黒髪を横に揺らした。
「話を聞くに、それまで二人の関係は良好だったのでしょう?それでも、突然嵐君は関係を断とうとした」
「うん」
女性の重々しい雰囲気に、陽春は躊躇いつつも返事をする。
彼女もどうやら説明の仕方を選んでいるらしく、間を置きながら、言の葉を紡ぐ。
それが、陽春にとって残酷な葉だと知っていたからだ。
「だとすれば、その決意は固いものと思われますわ。それ程の親愛を築いてきた上で別れを告げるなど、並大抵の精神力では不可能ですことよ」
「謝ったり、お詫びの品を渡すとかじゃ無理なのかな……?」
自分の思いつく限りの、交渉材料を並べてみる。
父親は、それで何とかしていた気がするからだ。
それでも、女性は頷きはしなかった。その上、
「これまで見てきた場合から結論を述べるとすれば、それでは無理でしょう。きっと彼は、貴方を手放してでも得たい大事なものがあったのですわ」
とまで言い捨てる始末。
「僕より、大事なもの?」
陽春は、彼女の言い分をただ繰り返す事しか出来ない。目からうろこが落ちる程の、衝撃的な事実だったのだ。
嵐に、自分よりも価値が上のものがあるなど、考えたことも無かった。
共に居てくれるから。その一点のみで、自分への忠誠をただ無邪気に、純粋に、信じて疑っていなかった。
「でも、そうだとしても、僕と離れる理由にはならないはずだよ!僕と、その大事なもの、両方持っていれば良いじゃないか……!」
受け入れ難い現実とどうにかして共存できる様に、陽春は思考を振り絞る。
しかしながら、彼女は悲しい目をしたまま、言った。
「誰にだって、そういう取捨選択が必要な時は訪れますわ。『愛別離苦』とは良く言ったもので……。大事なものの為に、欲しいものを手放さなければならない時があるものです。私もかつてそうでしたし、きっと嵐君もそうなのではなくて?でなければ友人を手放すなど、よっぽどのこと」
「嵐君は、僕より大事なものを、選んだ……」
女性は、陽春よりも物知りで、陽春よりも正しい様に思えた。
だからもう大人しく、そうだと考えるほか無かった。
陽春の、あからさまに落胆した表情に、年上の彼女は流石にフォローを挟む。
「……まあ、あくまで経験上、そうなのでは、ということですし。きっと嵐君も、苦しい思いをしているはずですわ」
しかし、その口調には、自信というものがまるで無かった。とりあえず口にしてみた、といった程度の、骸のような声音。
「そっかあ……。そうなのかあ……」
陽春は彼女の意見を何とか飲み込もうと、そう、口の中で繰り返す。即座には受け入れらない現実を、無理やり自身に言い聞かす。
それでも、どうやっても飲み込めない。納得できない。
「貴方にはまだ、抱えるのは難しい感情かもしれませんね」
生きていれば、誰しもが味わう痛み。想いの重さの差によってはまり込む、失意の沼。
だがそれは、齢八歳の男の子が知るにはまだ早い、大きすぎる喪失感だった。
「うう……」
陽春は頭を抱えて、上半身を折る。
苦しくて、苦しくて、上手に息が、出来ない。
「うああっ……。ああ……」
口を開くと、意思とは裏腹に、嗚咽が漏れた。その拍子に涙も、どばどばと零れる。
「あらあら、困りましたわね。一旦泣き止ませられればとヒトになったというのに……。これでは元に戻れませんわ」
慌てた様子は見せなかったが、女性はこてん、と首を傾げた。うーん、と束の間、頬に手を当てて悩む。
しかし、一つ頷いたと思えば、
「あまり、空気中の菌に触れることはしたくないのですが……」
と呟き、ハンカチで口元を覆うのをやめた。
それから、女性は、ふんわりと陽春を抱き締める。
どこかで感じたような、ほんのりとした温かさと優しい香りに、却って涙腺と理性が緩む。
陽春は、ひと際激しい泣き声を上げた。
「わあああああああんっ────!」
と、その時。
「おい!!陽春に何してる!!」
がさがさという音の後、背後の茂みから怒声と共に人影が飛び込んできた。
固まる二人の前に、ぜいぜいと息をつきながら立つ人物。
それは、嵐、だった。
「お前……っ、陽春から離れろ!」
肩を怒らせながら、嵐は女性へと足を早めていく。女性は、そんな嵐を、押し黙って見つめていた。
「ち、違うんだよ嵐君!この人はただ僕を、」
陽春は涙を流しながらも立ち上がり、慌てて嵐と女性の間に割って入る。
が、嵐は陽春でさえも押しのける勢いだった。
「お前、陽春に何をした?」
腹に響く低い声で、圧を掛けるように女性に尋ねる。しかし彼女は、たじろぐでも、怒るでもなく、冷静に答えた。
「いいえ、私は何も」
それだけではない。女性はさらに、嵐に向かって挑戦的に言葉を重ねる。
「というよりも。察するに、貴方の方が彼に何かしたのではなくて?」
などと、澄ました顔で言ったのだ。
嵐もそれに反発する。眉間にしわを寄せて、
「何だと?」
と、今にも女性に掴みかかりそうな態度だ。
陽春は、嵐に荒事はさせられないと、彼の手を思い切り引く。そして、大きな声を出した。
「嵐君やめて!」
嵐ははっと、動きを止める。自身を咎める陽春の声に、ようやく我に返った様だった。
その合間に、陽春は両手を広げて女性の前に立ち塞がる。
「この人は、泣いてる僕を慰めてくれた良い人だよ!無礼はだめ!」
滅多に怒らない陽春が見せた鬼気迫る形相に、嵐は目を丸くした。
「……本当か?」
嵐の問いに陽春はこくりと頷く。すると嵐は、ぐい、と陽春の身体を強引に横にずらし、
「ちょっと嵐君!」
女性の正面に立った。
そして、ぺこりと頭を下げる。
「申し訳ございませんでした」
という謝罪の言葉を述べながら。
一連の流れをやきもきして見ていた陽春だったが、女性は特に気を悪くしたようでも無く、
「誤解が解けて良かったですわ」
などと、再びハンカチで口元を覆いながら涼しい顔をしている。
陽春は一旦、大人の心の広さに感謝しながら安堵して、それから、そんなことよりともかくと、嵐に向かって問い質した。
「嵐君はこんな時間に、一体どうしてここへ?」
子供が外を出歩くには夜が深過ぎる。自身のことは置いておいて、ではあるが。
嵐は、ゆっくりと振り向く。こちらを向いた表情は、とても固い。
そして彼は、心なしか気まずさが混じったような小さな声で、理由を告げた。
「布団で寝てたら、陽春の……、泣き声が聞こえたから」
そんなはずはないと断言できる。この場所と嵐の家の間には、何百メートルも距離があるのだから。
しかし、嵐がその場を誤魔化すための嘘をつくような人間ではない。だから陽春は、疑うこともしない。嵐がそうと言えば、そうなのだ。
しかし、だとすれば。
「なんだって、今更」
陽春が泣いていたのは、今に始まった事ではない。それを、辛くてどうしようもなくなって、夜中に飛び出して、知らない人に話を聞いてもらっているような、今になって。
そんな優しさがあるなら、最初から。
「絶交だなんて、言わないでよ!」
拳をぎゅうと握る。嵐を睨む目に怒りを、恨みの気持ちを込める。
「……悪いとは、思っている」
ふい、と顔を背け、嵐は呟いた。しかし、それ以上は口を噤んでしまう。
陽春も、これ以上はどう言及すれば良いか分からなくて、言葉が続かなかった。
沈黙の時間が流れる。時折夜風で鳴る葉音が、やけに大きく聞こえた。
そんな空気を吹き飛ばすかのような、清らかな、一声。
「訳を、話して下さらないかしら」
は、と、二人同時に女性の方を向く。
彼女のハンカチは、特別なのだろうか。どれだけ完全に口元を覆っていても、何故か彼女の声は籠もらない。
「貴方が陽春君と縁を切りたい訳を説明すれば、彼も諦めるかもしれませんわよ」
陽春を掌で指しながら、女性は言う。
陽春は、そんなことは絶対にない、と否定しようとしたが、これは彼女が出してくれた助け船だと理解していた。空気を読んで、出かかった反発を飲み込む。
しかし嵐は、
「……無理だ」
と、首を横に振る。
余りにかたくなで、陽春は、
「どうして?僕にも話せない事なの?」
と、思わず口を挟んだ。
だが、
「陽春にだからこそ、話せない」
などと、嵐にきっぱりと言い返されてしまった。
途方に暮れて、陽春は足元に視線を落とす。その目に、嵐が差し出す手が映った。
「ほら、帰るぞ。怒られる」
遊びの帰り。習い事の帰り。いつも差し出されたその手を、陽春は反射的に取ろうとした。
だが途中ではっとして、動きを止める。
そして、尋ねた。
「一緒に帰ったら、『また明日』って言ってくれるの?これまでみたいに、おうちに来て、会ってくれるの?」
嵐は、何も言わない。肯定してくれない。
それが、何よりの答えだった。
陽春は、身体から全てが抜け落ちていく様な感覚に襲われた。
和解の道などありはしなかったと、突き付けられた。
嵐が迎えに来てくれたことで、状況が好転するかもと淡い期待を抱いた。でも、ただの思い過ごしだったみたいだ。
であればもう、諦めるしか、ない。
嵐と離れたくない。しかしそれ以上に、嵐に迷惑をかけたくない。それだけは、絶対に嫌だ。
陽春は、必死に自分に言い聞かせる。胸の激痛には、気が付かないように。
大丈夫、大丈夫。
五年か、十年か。いつかは忘れられるかもしれない。
だから、もう。
彼を、手放してあげよう。
陽春は嵐の掌を掴もうと、震える指を伸ばす。
そして、指先が触れようとした、その時。
「お待ちなさいな」
鋭い声が、飛んできた。陽春がぼうっと視線だけ向けると、女性がゆっくりと立ち上がり、二人に近付いてくるのが見えた。
「事情がおありなのは承知しました。親御さんが心配するのも分かります。ですが、お二人とも。少々私に不義理では無くて?」
整った顔(半分位しか見えないけれど)で、感情も無く迫られると本能的に背筋が凍った。
彼女の言い分ももっともだと思い、半ば呆然としながらも陽春は答える。
「あ、ああ、そうですね、お時間取らせて申し訳ございませんでした。後日謝礼を……」
しかし、
「それでは遅いのです。私は、今宵しか出てくる気がありませんので」
陽春の言葉を途中で遮り、女性はぴしゃりと言い放つ。
さらに、彼女はこう続けた。
「私、今しか時間がありませんの。ですので、すぐ頂けるものでないと困りますわ。私の命にも等しい、時間という大事なモノ。それを使った代償を、どうお支払いして下さるの?」
「……ええと、」
陽春は困ってしまった。無論、今は一文無しだ。それに、帰って両親に頼むにしても、事の経緯を一から説明しなくてはならない。面倒極まりなくて避けたい事象ではあるが、そうは言ってもこんな夜更けに相談事にのってくれた恩を仇で返したくはない。
眉を下げる陽春に、女性は優しい声音で、容赦なく畳みかける。
「でしたら、貴方の命など、どうでしょう?」
「い、命?」
「おい!何言って……!」
突拍子もない発言に目を見開く陽春と、咄嗟に陽春の前に一歩出る嵐。当惑する二人を前に、だが彼女は、ふふ、と笑みを漏らした。
「いえ、何も全てを頂こうと言う訳ではありませんわ。そうですね、三年分の寿命など、どうでしょう?私が命を削ったこの時間と、恐らく同等の取引ですわ。いかが?」
またしても奇妙なことを言うものだ、と陽春は思った。命の譲渡など、どうやって行うつもりなのだろう。
だが、この女性なら可能なのかもしれない。彼女にはそう思わせる、不可思議な雰囲気が漂っている。
それに、頭を働かせることすら今は面倒な気分だ。重ねて、寿命の三年など、今となってはどうだっていい。だって嵐とは、ここでお別れなのだから。長生きする必要も、価値も感じられない。
だから、
「良いですよ」
陽春は、気が付けばそう答えていた。
だが、隣から否が飛んできた。
「陽春にそんなこと、させない」
見ると、嵐はひどく怖ろしい顔つきをしている。その上、ずい、と女性に一歩近寄ると、
「代わりに俺の命をやる」
と、口早に告げた。
女性は片眉を上げる。何か、もの言いたげな様子だ。
ところが、彼女より先に口を開いたのは、陽春だった。
「ううん、嵐君、それは筋が違うよ。あの人の時間を使ったのは、僕だ。嵐君が肩代わりする必要はない」
「でも、」
陽春の意見に、寸分置かずに反対しようとする嵐。そんな彼に、陽春は抑揚のない声で言った。
「それに、僕達はもう、友達でもなんでもないでしょ?だったら尚更だ。僕は、他人に代金を支払わせる教育は受けていない」
「……っ」
嵐は頬を引きつらせ、絶句する。
そんな嵐にさらに、
「あらあら、事の発端は貴方だと云うのに、頼り甲斐のないこと」
などと、火に油を注ぐ様な女性の所感が寄せられる。
嵐はぎろりと彼女を睨んだが、それだけに留まった。ぐうの音も出なかった。
涼しい顔の女性と、奥歯を噛みしめている嵐と、そんな二人をぼんやり眺める陽春。
悲喜こもごもの空気が漂う、重苦しい時間が流れる。それを断ち切るかのように、女性は言う。
「ですが、そんな貴方が、陽春君の代わりに出来ることが、一つだけあります」
「な、なんだそれは」
垂れさがった蜘蛛の糸に縋るが如く、嵐は彼女に詰め寄る。
そして、女性はその答えを、即座に示した。
「絶縁の理由を、言いなさい」
「だからそれは……!」
嵐は、苛々とした声色で首を横に振る。それに対し、彼女も毅然とした態度で続けた。
「貴方にも立派な決意があるのは理解できます。ですが私も、命が惜しい。それに見合う、対価が欲しいのですよ。それとも貴方は、陽春君の命は大事でも、その他はどうでも良いと言うのですか?」
嵐は、黙った。ああ、珍しく悩んでいるな、と陽春は思う。嵐は基本的に即断即決だ。決断を伸ばす姿は、陽春でも数回程しか見たことがない。
中々返事をしない嵐に、女性は柔らかい声で後押しする。
「どうか私のためと思って、お願いしますわ。乗りかかった船、寝起きの一口話、とでも言いましょうか。せめて私も、何かを得たいのです」
彼女の主張には、時々意味の分からない部分がある。起きたばかりだとか、時間が命に等しい、だとか。
とはいえ、彼女がそれを本当に大事にしているのは、幼いながらにも二人には良く分かった。
だからだろう。
嵐は、
「……分かりました」
と、とうとう折れた。
そして、話し始める。
嵐の最も古い記憶は、二歳の頃。ほんの断片だけの、脆い記憶。
自身と隣り合って、穏やかに眠る陽春の寝顔。市長の息子とは思えない程の、安らかな微笑み。
己にくっついて離れない、この小さくて、しかし権威のある存在を、ようよう認識し始めた位の時期だ。まだこの時は、貴族の気まぐれに付き合ってあげている気分だった。両親にもそう言い聞かせられていたし、嵐自身も、自分を陽春のお気に入りの人形程度に考えていた。
それが一変したのは、それから三年後のことだ。
仕事を終えた母親と、陽春の屋敷から帰ろうとしていた。玄関の外から差し込む陽光が明るかったのは、この日、陽春の家族はパーティーに出席していて、夕飯の準備が不要だったからだ。
早めに母親と帰宅できると、嵐はわくわくしながら靴を履いていた、その時だった。
がらりと戸が開き、ぐすぐすと泣く陽春と、彼の両親が帰ってきたのだ。
パーティーが終わったにしては早すぎる。それになぜ、陽春は泣いているのか。
陽春は、いつもにこにこしていて、周囲に癒しを与えるような優しい子供だ。泣くことなど、ほとんどありはしない。それなのに、何故。
疑問が留まることを知らず、嵐は陽春の両親を質問攻めにした。
彼らは困ったように顔を見合わせ、だが、嵐の意思を尊重して、その理由を話してくれた。
だが、語られた内容に、嵐は驚愕することとなる。
穏やかで温厚な陽春が、パーティーで同じ歳の議員の息子に飛び掛かったのだ。
二人はその場で掴み合いになり、周囲の大人が二人を引き離す事態となった。幼いからと見過ごせない程、鬼気迫る大喧嘩だったのだ。
そして、その喧嘩の原因は。
嵐の事を馬鹿にされたからだと聞かされた。従者にも品位は必要だ、汚らしくて頭の悪い奴と仲良くするものではない、と陽春は言われたらしい。
ずっと一緒に育ってきた嵐は知っている。
陽春が、優しすぎるが故に引っ込み思案で、自分の意思を示すのにも実は苦労している事を。
そんなひよっこが。
オレのために、怒ったのだと。
呆れや、悔しさや、嬉しさや。ともかく色んな感情が押し寄せてきて、まだ傍で泣いている陽春に顔を向ける。
鼻を赤くし、透明で美しい涙を流す彼を見て、嵐の中では申し訳ない気持ちが膨れ上がった。
──オレよりもっと、相応しい友人を作れたはずなのに。
それでも自分の服の裾を離さない、ちっこくて肌が白くて、顔のきれいな幼馴染。他の何よりも、自分を選んでくれた唯一無二の、兄弟分。
陽春の存在をそのように認めた瞬間、嵐は陽春を、自分だけの宝物だと思えて仕方がなかった。
これからは俺が、陽春を。陽春が傷付かないように、壊れないように。陽春だけは絶対に、守り続けるのだと。
そう、誓った。
そしてその誓約は、嵐が想定するよりも、かなり果たしやすい環境にあった。
合法的に、最も近くで陽春を守れたのだ。
本来なら嵐は、陽春と同じ待遇を受けられるはずもない立場だ。しかし、先述の様な陽春の強い希望で、嵐は陽春と共に生活すること、陽春は庶民の生活に触れること、このそれぞれを特別許された。そのお陰で、嵐は陽春と四六時中、行動を共にすることが可能になったのだ。
このままなら、自身に課した勤めをずっと果たせる。
嵐は内心そう喜びながら、堂々と、かつ、陽春にはばれないようにひっそりと、陽春を保護し続けていた。
しかし、それは上手くいかなくなってしまう。
二人が五歳を超えた辺りだった。
同じく成長したかつての喧嘩相手の男子が、陽春を虐めるように町の子供たちに命令するようになったのだ。しかもその手口は巧妙で、必ず、陽春が独りになる機会を狙う。嵐がどれだけ気を配っていても、大人たちを巻き込んで、どうしても嵐が断れない用事を作られる。そして、その隙を突かれてしまうのだ。
土埃で汚れ、蹲る陽春を目にする度に腸が煮える思いをしたが、その原因は社会的にも、年齢的にも弱い自分にあると思うと、なお腹が立った。
もっと成長して強くなって、力を付けて。陽春には誰も手を出せないように、将来は必ず。
そう、決めていた、はずなのに。
「俺は、復讐したいんです」
「ふ、復讐?」
自身らの年齢とは凡そ似つかわしくない物騒な単語に、陽春は耳を疑った。どう考えても、現実的な話には聞こえない。
何かの比喩なのだろうか。そう頭を悩ます陽春に反し、女性は、眉一つ動かさない。こういう事もある。まるで、そんな風に捉えているようだ。
しかし、例え話でも何でもないことは、嵐の話を聞いていく内に判明していった。ただ、嵐が紡ぐ物語の壮絶さに、陽春の顔は引きつっていくばかりだったが。
どうやら、嵐の母親は狂ってしまったらしい。父親はそんな母親に手を焼き、先日母親と共に命を絶ったのだと。
つまり、嵐の家族は壊れてしまったのだ。
初めて耳にした嵐の家庭内情が信じ難くて、陽春の開いた口は塞がらない。
嵐の家族との付き合いは、陽春も決して短くない。だから、彼らの仲が良かったことも十分知っている。急にそんな悲惨な事になるはずがない。
一体なぜ?どうして?
何か言葉をかけるべきなのは分かっているのに、声帯が全く仕事をしない。代わりに、女性が平然と嵐へ疑問をぶつける。
「その事は、陽春君の家族はご存知なの?確か、貴方のお母様は陽春君のお屋敷で働いていたそうですが」
嵐も無表情で、受け答えをする。
「いえ、知らないでしょう。俺が、母親は療養していると偽って伝えていますから」
「何故陽春君のご家族、或いは自身のご親戚等に相談なさらなかったの?貴方は、黙って見ることしか出来ない様な、腑抜けには見えませんが」
「父が誰にも言うなと。崩壊はしていても、体裁は繕っていたかったみたいです。内々で解決して、何も無かったことにするつもりだったのでしょう。まあそれは、不可能でしたが」
「これまでは、どうやって生活していたの?」
「色んな店で小間使いとして働いたお駄賃で、何とか。それでも足りなかったので、他所の生ごみを拾ったりもしました」
「そう……。さぞ辛かったでしょう、可哀想に」
陽春を置き去りにして二人が交わす会話が凄惨で、陽春は頭が真っ白になった。
全く知らなかった。大切な存在である嵐が、そんな酷い境遇に置かれていたなんて。
嵐の力に、いつでもなれると思っていた。何でも助けてあげられると思っていた。でもそれは、独りよがりな妄想、空想でしかなかったのだと、まざまざと見せつけられている。
自分が今、強烈に無力で、恥ずかしくて、惨めに思えて。悔しくて。知らず知らずの内に、瞳の奥が、熱くなる。
「それで、貴方の状況は十分理解しましたが、結局、誰に復讐するつもりなの?」
顔色一つ変えず、女性が話を進める。陽春一人では手に負えなかったから、彼女の存在は大きな救いだった。
それでも、現実は陽春に容赦ない。
「母親にクスリを売った、ヤクザです」
ヤクザ。嵐が発した単語に、陽春はぞっとする。
ヤクザは最近、市内での喧嘩や銃撃戦などの抗争で、悪い噂が絶えないチンピラ組織だ。とはいえその力は、裏社会を牛耳る程になっており、商店や祭りの運営にも関係してくる。故に、街を統治するには彼らと顔を合わせない訳にもいかなかった。
恐らく陽春の父親も、彼らと何度も話し合いの場を設けているはずだ。
「どういった経緯なのか、何がきっかけなのかは知りません。気が付けば、しっかり者の母親が、ぼうっとしている事が増えていました。それが段々と、まともに会話すること、動くことが出来なくなり、最後の方は、ひたすらクスリを求める廃人となりました」
滔々と語る嵐。だがよく見ると、その拳は固く握られ、震えていた。彼の行き場のない悲しみや怒りがそこに籠められている気がして、思わず陽春はその手に触れた。
ひどく、冷たかった。
「間もなく、ヤクザがお金の取り立てに来ました。母親はツケでクスリを買っていたようです。昼夜問わず、扉を激しく叩く音と怒声に、父親の精神は擦り減っていきました。そしてある夜、母を包丁で──」
「嵐君!嵐君、それ以上はもう、大丈夫だから!!」
陽春は、嵐の手をぎゅうと握った。部外者とは言え、聞くに堪えなくなってしまったのだ。
「ごめん、ごめんね、気が付かなくて、ごめん……」
陽春が謝ったって何にもならないのは分かっている。それでも、自分のこと以上に胸が痛くて、陽春は嵐にくっついて咽び泣くしかなかった。
嵐は何も言わず、陽春をじっと見つめている。
数秒流れる、得も言われぬ間。その後、核心に迫る質問が、女性から発せられた。
「それで、その復讐と絶交は、どう結び付くのかしら?」
これが、嵐と陽春を結び、離す、最後のピースなのだろう。陽春は鼻をすすりながら、嵐の言葉を待った。
嵐は一呼吸置いて、口を開く。
「俺はヤクザの事務所に入って何人かを殺すつもりです。ですが返り討ちに遭って、俺はきっと死にます」
死ぬ。その言葉を嵐から聞かされて、陽春の心臓は嫌な鼓動を打つ。冗談であってほしいと願いつつも、そんな冗談をいう人ではないと誰よりも知っているせいで、陽春の足先はすうっと冷えた。
嵐は、そんな陽春の恐怖心を知ってか知らずか、話を止めない。
耳を塞ぎたい気持ちで一杯の陽春に、言って聞かせるような柔らかい声音で。
「でもそうなると、陽春を守る奴は居なくなって、陽春は一人ぼっちになってしまう。だからこの先、陽春が一人でも生きていけるように」
そこで突然、嵐は言葉を区切って、陽春に視線を向けた。その瞳には、見たことがないほど優しさが満ちていて、陽春の呼吸は一瞬止まる。
「俺がいなくても、大丈夫なように」
──ああ、嵐君は、やっぱり優しい。
これまでも存分、その優しさを味わってきた。沢山沢山、甘やかしてくれた。だから、一瞬たりともその優しさを疑うべきでは無かったのに。
だけど、苦しい。色んな感情が胸を蠢いて、突き破って、そのまま穴が開いてしまいそうだ。
ぐちゃぐちゃと考えがまとまらない陽春だがしかし、そんな彼を置いて、女性と嵐の会話は続いていく。
「だから俺は、陽春をわざと突き放しました。ご理解頂けましたか」
「なるほど。道理は通っていますわね。感心しました」
「では、これで良いですか?貴方の気の済む程の話が出来たかは分かりませんが」
「まあ、悪くは無かったですわ。少々ありきたりではありますが、目を覚ました甲斐はあったかもしれません」
「それなら良かったです。それでは、夜も大分更けてきましたのでお暇しても?」
「そうねえ、いい加減、貴方たちを解放してあげませんと」
だが陽春は、釈然としなかった。全然納得できなかった。
待って。待って。なんで二人で終わらせようとしているの。全て終わったことに、なっているの。
僕は全然、腑に落ちていないのに。
なんだろう、凄く、凄く腹が立つ。僕を取り巻く全て、この世全てに、腹が立つ。
お腹の奥から湧き起こる感情に従って、暴れ出したい。
「ほら、帰るぞ」
目の前には、そう言ってもう一度伸ばされた、嵐の手。しかし陽春は、それをばしっと払いのける。
驚く嵐に一瞥もくれず、陽春はひたすらぐらぐらと煮える自身の中身と向き合った。
この想いを。不快感を。苛立ちを。
一体、一体、僕はどうしたら抑えられる?そう、他人に感情を露呈するなど、喜ばしいことではない。そういう教育は、山ほど受けてきた。
でも、むかつくむかつくむかつくむかつく────。
むかついて、仕方がない。
叫びたい。叫び出したい。でも、怒られちゃうかな叱られちゃうかないやいいそんなこともうどうでもいいよ!
もう知らない、知ったことか!
全部全部、吐き出してしまえ!!
「嵐君のバカ!!」
人生で一番の、大きな声を出した。その声量に、女性ですら身体を少し仰け反らした程だ。
陽春は生まれて初めて後先考えずに、溢れだす情念を誰かにそのままぶつけた。
「僕も一緒に行く!一緒に仇を討つ!嵐君一人でなんて、行かせるもんか!」
それを聞いた嵐は、目をむいて一喝する。
「バカはお前だ!お前は、大事な市長の一人息子だ。この先、俺たちの街を担っていく大事な役目を背負っているんだぞ!そんなお前を巻き込めるか!」
嵐の言い分が正しい。そしてその内容は、ずうっと昔から父親に言い聞かされ続け、十分理解しているものだ。
それでも。
「市長の息子である前に僕は一人の人間で、嵐君の親友だよ!僕の人生は、僕が決める!嵐君のためなら僕は、死んだって構わないよ!」
「陽春……」
嵐は唖然とする。
こうなってしまったら、陽春は絶対に意思を曲げないと。長年連れ添った経験が、そう告げているからだ。
さらに陽春は一度呼吸を整えると、不敵に笑い、
「僕が傍についてたら、簡単には死ねないでしょ?僕が先に死んじゃうと、嵐君はきっと冷静でいられなくなってその隙にやられちゃうし、嵐君が先に死んじゃったらもれなく僕もやられちゃうし。そうならないためにも、嵐君は生きて、僕を守らないとならない。でしょ?」
などと得意げに、独自の論を展開してくる。なまじ間違っていないだけに、憎らしい。
反論できない嵐をよそに、陽春は嵐に一歩、近寄る。
その一連の態度、所作には、先刻までの荒々しさは一切無かった。むしろ、普段よりも優雅な雰囲気を醸しだしている。
嵐はそんな、妖艶ともいえる陽春から寸分も目が離せなかった。そして、幼馴染の優しい声に、脳を、心臓を、揺さぶられる。
「なんたって僕は、嵐君を倒したんだよ?だから僕ら、向かうところ敵なしだ。ね、二人で行って、二人で生きて帰ろう」
──参った。俺は、この笑顔には、勝てないんだ。
嵐は改めて、そう思い知らされた。
「さ、行こ?僕と一緒に」
嵐は、陽春からす、と差し伸べられた両手を凝視する。
陽春と、一緒に。
その言葉を、頭の中で何度も反芻する。
それは、これまでに何度願って、何度諦めた夢だろう。
そしてたった今、その夢は持つことを、許された。
蓋をして鍵を掛けて鎖で縛って、二度と触れないように心の奥底に沈めたはずの想いが。
陽春の甘言のせいで、簡単に溢れ出し、体内を満たす。
本能のままに、震える手を、ゆっくり伸ばす嵐。
だが。
突如、きゅっとその掌を握り込む。首を横に振りながら、何かに耐える様に、掠れた声を上げた。
「この手を取ったら、俺は、俺はもう……。陽春の従者にはなれないんだ……!」
嵐は陽春を守らなくてはならない。それは、一生の誓い。
しかし、陽春と共に復讐に行くということは、陽春をみすみすと危険に晒すということであり、自身に課した約束を破ることと同義だ。
だから簡単に、陽春に流されてはならない。
それなのに、それなのに、だ。
当の陽春は、きょとんとして、
「従者?何言ってるの?」
などと、小首を傾げている。
何言ってるの、はこっちだが?と、嵐は呆れる。
俺はお前にとって単なる都合のいい護衛で、単なる身体がでかいだけの召使で、単なる──。
「嵐君は最初から最後まで、僕の大事な友達だよ」
世界が、ぴたりと静止した様に感じた。
この瞬間、嵐の中に根付いていた陽春への思慕が、別の物へと生え変わる。
これまでと少し異なる、もっと大きくて、深い親愛へと。
陽春はひと時たりとも、嵐を自身と差別したことは無かったのだ。むしろ率先して差別していたのは、嵐自身だったのかもしれない。
これだけの事を知るのに、大分遠回りしてしまったみたいだ。
ふ、と嵐は小さく笑う。
そうとなれば。これから認識を改めて、新たに俺が、するべき事は。出来る事は。
陽春を庇護する対象ではなく、対等な友として、互いに互いを守り抜くことなのだ。
何かが吹っ切れた嵐は、今度は、躊躇なく両手を握り返した。
そして、陽春の目を見てきっぱりと、言う。
「来てくれ、陽春。俺と共に、地獄まで。俺がお前を、守るから」
「もちろんだよ、嵐君」
真っ直ぐな思いを伝える嵐に、陽春もまた、月も輝き出すような笑顔で応じた。
二人は満足そうに同時に頷くと、そのまま歩き出そうとした。
しかし、そんな彼らの背後に注がれるのは、冷え冷えとした声。
「復讐を止めるという選択肢は、ございませんの?友と言うのなら、過ちは正すべきなのではなくて?」
これまで存在を消していた女性が、どこか苛立った口調で陽春を詰問する。
そんな彼女に、陽春は無邪気に聞き返した。
「どうして僕が、嵐君のやりたいことを邪魔するの?」
陽春の無垢すぎる瞳に、女性はぐ、と言葉を詰まらせる。さらに、悪意なく嵐も畳みかけた。
「ちなみに、逆の立場でも同じだ。そもそも俺は、陽春に逆らわない」
「そんなこと言って、僕にいじわるしたくせに……」
「……それは本当に反省してる」
喧嘩していた事なんて無かったことの様に、仲睦まじく話をする二人。女性はその様子に細い目を限界まで見開いて、非難にも似た疑問を投げかける。
「狂っていますわ、貴方たち。大人に刃向って生き残れる確率など、ほぼありませんのよ?死ぬのは痛くて、怖いものだと私は存じています。それなのに、何故、何故なの?」
しかし、陽春と嵐は、既に背中を向けていた。
大事なものとか取りに帰らなくて良いのか?だったり、嵐君が一番大事なものだよ、だったり、俺もだ、だったりと、まるで遊びに行くかのような他愛もないやり取りをしながら、前に向かって、一歩を踏み出す。
女性は、そんな二人にいっそ畏怖すら覚えて、我慢が出来なくなって、叫んだ。ハンカチで顔を覆うことも忘れて。
「ちょっと、貴方たち!」
手を繋いだ二人が、揃って振り向く。その晴れやかな表情に戸惑いながらも、女性は震える声で、最後に尋ねた。
「怖くは無いの?死は、怖いものではないの!?」
「二人なら、怖くない」「よ」
同時で、即答だった。
女性にこれ以上、為す術は無かった。立ち惑う彼女を、
「お姉さんありがとう!元気でね!」
という陽春の明るい声と、嵐のお辞儀が押し留める。
時折吹く風が、まだ真夏を遠ざける夜明け前。
ぎりぎり水平線上に残った月の明りが、手を繋いだ二人の影絵を映し出す。
前に、後ろに。揺れるその結び目は、その後決して、解かれることは無かった。
『昭和××年 七月十六日
H県K市△町の上屋敷ビルにて本日未明、男性四人の遺体を発見した。死因は銃殺、刺殺などと幾つか存在し、複数名の犯行と見られている。
尚、容疑者の足取りは掴めておらず、警察は鋭意、目撃情報の収集に当たっている。
被害者らは、以前から暴力団との関係を疑われており、いくつかの傷害事件を起した容疑がかけられていた。しかし、依然として確たる証拠がなく、逮捕にまで至らなかったとされている。
警察は、今回の事件と何らかの関わりがあると見て、現在捜査中である』