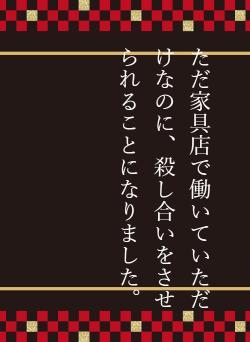望月がお河と初めて出会ったのは、カフェだった。望月はこの時、十五歳。お河は、給仕としてそこで働いていた。
望月は、父親に無理やりそのカフェに連れられていた。父親に、将来は自分の様な警察官になるのだと散々言い聞かせられていた彼は、あらゆる社交場に連れて行かれていたのだ。
しかし、望月自身はあまり社交的ではなく、そういった父親の会合には嫌々、付いて行くしかなかった。
望月にとって、父親は権威の権化だった。
まだ世間の事を詳しく理解していない望月にとっては不明瞭だったが、どうやら父親は、警察署内でもかなり上の地位に就いているらしかった。だから、社会的に“強い人”だというのは、何となく知っていた。
家庭内でもその力は凄まじく、共に暮らす母や祖母、祖父までもが、父親に頭が上がらないようだった。祖母も祖父も母方で、生活の一切を望月の父親に出してもらっているとなれば仕方のないことかもしれないが、その敬い方は極端だった。
望月は生まれてこの方、父親に反抗したことが無い。それは、祖父母の言い聞かせが頻繁だったことに由来する。
やれお父様は立派だの、とんでもないお方だの、散々褒め湛えた挙句、最後には決まってこう締めくくるのだ。
「お父さんの言うことは必ず聞くのよ。そうすれば、お父さんの様になれるからね」
と。
母親は幼い頃から貧しい暮らしをしていたと言うから、父親と結婚出来て、いくらか裕福な生活を手に入れられた。それが、その恩恵を受けている祖父母に影響したのだろう。
しかし、望月は彼らの助言を、ほんの少し疎ましく思っていた。
僕に自由は無いのかと。
僕を、見てくれはしないのかと。
だが確かに、父親は人格者で、部下からも人気があったから尊敬はしていたし、何より細胞に刷り込まれた服従心に、どうしても逆らうことは出来なかった。
だから、望月はこれまで休日となると、父親によって方々に連れ出されていたのだった。
そんな中迎えた、ある年の十二月。
──何て美しいんだろう。
ストローを咥えた口があんぐりと開いてしまう程に、望月は、視線の先の存在に衝撃を受けた。
望月は楽しくもない大人同士の会話を、オレンジジュースをすすりながら聞いていた所だった。
イマドキ流行りの、洒落たカフェ。店の中の、角席。
その、さらに奥のソファに望月は座っていた。
父親は、二人の男と楽しそうに話している。真面目な顔で、難し気な国家情勢を議題にしているかと思えば、時折近くを通りがかる女給に口笛を吹いていた。
何が面白いのか、てんで理解できない。
話の内容は、ある程度は分かる。治安維持法がどうだとか、社会主義がどうだとか、そんな会話はこれまで散々聞いてきた。
ただ、まるで興味は湧かない。
だって、話に入れないから。
少し前に、彼らの会話に矛盾点を見つけて、それに言及したことがあった。望月としては、この場に呼ばれた人間として、最低限の義務を果たしたつもりだった。
父親を含めた大人達数人はそれを聞いてしばらく黙り、それから、冷たく言い放った。
「子供は黙っていなさい」
と。
それ以来、望月はこの会合に何の意味も見いだせないでいる。
子供と分類するには、余りにこの世の事を知り過ぎている。しかし、大人の仲間にも入れてもらえない。
そんな状況で、楽しめという方が不可能だ。
望月はこの日も、テーブルに並べられた三つの濃茶のカップとたった一つのオレンジ色で満たされたコップを見比べて、些か歯がゆく思いながら、手持ち無沙汰に店内を見渡してみた。
そんな折りに、見つけたのだ。
漆器の様な艶のある黒髪をまとめ、赤色の縦じまが入った白い着物に、白エプロンを重ねた女中。
きりりとした眉から伸びた鼻筋は整っており、何より大きな二重の瞳が印象的だった。
数多いるウェイトレスの中でもひと際目を惹く彼女から、望月は目が離せなかった。
じっと見ていると、彼女はこの店の中でも人気があることが判明した。頻繁に客から声が掛っている。
それらに対して快活に返事している彼女を眺めていると、望月は納得したと同時に、諦めも付いた。
そりゃあ、モテるだろうな。あれだけの美貌と、はっきりとした性格だ。僕なんかには、到底手の届かない存在だろう。いくら気に入ったとはいえ、こんな想いはすぐに消してしまった方がよい。
望月には、彼女に声を掛けるという選択肢は無かった。
父親に従えと言われて育ったからか、自発的に動く習慣は持ち合わせていなかった。ただ父親の意思に従うだけでよいと、刷り込まれて生きてきたのだ。
さらに、持ち前の内気な性格が猛威を振るった。
よって、この日は彼女に話しかけるどころか、目を合わせる事すらできずに、退店することとなった。
美しい女中と二度目に会ったのは、一か月後の、町の古本屋だった。
望月は、本を読むのが好きだった。父親の趣味で、自宅には沢山の書籍があった。芥川は勿論、有島武郎や西田幾多郎などのベストセラーは、ガラス戸に当然の如く仕舞われていた。
幼い頃からそれらを読むことを許されていた望月は、この頃になると、透明な仕切りから見えるタイトルの全てを読み切ってしまっていた。
父親は、望月が古本屋に行くと言うと、その度に小遣いをくれた。本は読むだけ賢くなるから良いという、彼なりの持論からだった。
そうして通うようになった古本屋で望月は、小説、論文、郷土史等、ジャンルを問わずに買い漁った。
それら全てが、自分の養分になる気がして、そしてそれを元に大人になれる気がして、なんだか嬉しかった。
その日も、望月は馴染みの古本屋に顔を出していた。
扉を開けると、老いた店主がやけに目尻を下げて、ちらちらとどこかへ視線を寄越しているのが目に入った。
一体なんだろう、とは思ったものの、棚にぎっしり詰まった背表紙を追っている内に、そんなことは忘れてしまった。
数分後。
──あ、これ、面白そうだ。
そう直感して伸ばした望月の手に、
「あっ」
白く、滑らかな指が触れた。
『マルクス主義と哲学』。
その文字列に、二つの掌が重なっている。
下が望月で、その上には、女性の手。
「貴方も、この本に興味がおありなの?」
風鈴を指で弾いたような、美しい声がした方へ顔を向けるとそこには、にこにこと笑う、いつかの女中が居た。
「えっ!あ、え、」
思いがけない出会いに、舌がもつれる。返事をしたいのに、上手く言葉が出てこない。
勝手にあたふたしている望月の姿を不思議そうに眺めていた女中はその後、いつかの接客姿と同じ様に、朗らかに笑って言った。
「なんだい、びくびくと!私の顔に、何かついてでもいる?」
望月の態度に気を悪くするどころか、一層笑みを浮かべる彼女に、望月は再び声を詰まらせた。
余りにも、綺麗だった。
埃っぽく薄暗い古本屋の中なのに、彼女の周囲だけスポットライトが当たっているかのように、輝いて見えた。
店主がチラ見していたのは、不意に現れた女神にも近しい彼女に違いない。
そんなことを考えて、黙って憧れの相手を見つめる望月に、女中は流石に心配気な表情になった。
「大丈夫?体調でも悪いのかい?」
そう言って、望月の肩を揺する。
細い指が肩に食い込んで初めて、望月ははっ、と我に返った。
「ああ、いえ、大丈夫です!それでは!」
間近で浴びた美へのショックと、自身の無様さへの情けなさがない交ぜになり、望月はその場から逃げ去りたい気持ちで一杯になった。
走り出そうと出口に向かって一歩を踏み出した時、
「ちょっと待って!」
望月の背に、焦ったような声が掛かる。
そのやや強めの声色に、望月は咄嗟に足を止めた。が、すぐさま後悔する。
何か、罵倒でも浴びせられるのだろうか。はたまた、彼女は思っていたような人物ではなく、恐喝でもされてしまうのだろうか。古本を買いに来た金を寄越せ、などと言われるのだろうか。
様々な可能性が思い浮かび、びくびくしながら望月は振り返った。だがその目には、彼女によって差し出された先程の書籍が映る。
「これはもう、良いの?」
彼女は小首を傾げながら、望月に尋ねた。
その澄んだ瞳に先刻の自身の不躾な想像を恥じ入りつつ、さらに、その仕草の可愛さに参ってしまい、赤面しながら望月はすごすごと本を受け取ろうと手を伸ばす。
「あ、ありがとう、ございます」
しかし、望月の手が本に触れる直前、さっ、と彼女はその本を後ろ手に隠してしまった。
「うえっ?」
突然の事に、今度は間抜けな声を上げてしまう。
伸ばした手を空中で手持無沙汰にする望月に、彼女はくすっと微笑んで、口を開いた。
「このまま貴方に渡しちゃっても良いけど、私もこの本、どうしても読みたいの。ねえ、どうすれば良いと思う?」
悪戯っ子の様な笑みを前に、望月は深く悩む余裕などなかった。
反射で、望月は答えた。
「で、は、僕が読んだ後に貴女にお貸しします。そ、それで、どうでしょう」
本を貸す。それは裏を返せば、今日以降も、どこかで会いたいという事。
物凄い小声で、しかもつっかえながらの、まるで恰好がつかない誘い文句だった。
それでも、誰かに自分の意思を伝えられたのは、人生で初めてと言って良いくらいだ。
彼女は満足そうに頷き、言った。
「ありがとう。そうして頂けると助かるわ。でも、お互いの素性も知らなければ、物の貸し借りは出来ないわね」
彼女のさあどうする、と言わんばかりの大きな瞳を、望月はもっと見ていたいと思った。
ここでせっかく繋いだ縁を、どうしても切りたくなかった。
だから、ここが勝負だ、もうひと踏ん張りだと気力を奮い立たせて、拳一杯分の勇気を、小さな声で振り絞る。
「あ、貴女のお名前を教えてください。僕は、望月と言います」
男として、威厳の欠片も無い振る舞いだと自覚していた。
だから、数秒経って彼女が何も言わなくても。仕方のないことだと、ほとんど諦めきっていた。
よって、恐る恐る顔を上げたその先に、
「私はお河。お河よ」
大輪の花の如き笑顔がそこにあって、心底驚いた。
それから、望月とお河の交流は始まった。
古本屋で奇跡の邂逅を果たした十日後、二人は本屋の近くの公園で落ち合った。
「本当にもう読み終わったの?読むのがとってもお速いこと」
ベンチに腰掛け、隣に座るお河に件の本を渡すと、お河はまんまると目を見開いた。
「ええ、まあ……。時間は沢山あったものですから」
嘘つけ。中々のハイペースで、必死に読み進めた癖に。
心の内で、自分に向かって毒づく。
次はいつお会いしましょうか。そう本屋でお河に尋ねられた時、望月は咄嗟に、
「では、十日後で」
そう、答えてしまった。
本の厚さと内容からして、読み終わるのには大体、三週間は必要だと分かっていたはずだった。
だがそんなことよりとにかく、時を置かず、お河に会いたかったのだ。
なるべく早く、だが、不快にさせない為にはどれ程の期間を空ければ良いか、という計算の末に、はじき出された数字だった。
「十日後ね、問題ないわ。それならどこで──」
お河は手帳に視線を落としつつ、待ち合わせ場所に議題を移した。そんな彼女に重ねるように、望月は矢継ぎ早に言う。
限界が、近かった。
「あの公園に、午後三時は如何ですか」
ぴっ、と望月が指した先には、一本の桜の木があった。とりあえず目についたシンボルだったが、そこに公園があることを知っていたらしく、お河もにっこりと笑って頷いた。
ではまた、と手を降って彼女が退店した直後。
望月はその場にへたり込んだ。
緊張と、安堵と、嬉しさで、実はお河の名前を聞いた時から、足が震えて仕方がなかったのだ。
両手で口を塞ぎながら、今起きたことを全て、何とか脳内で処理する。
それでも、信じられない。
幸運すぎる。こんなに幸せなことが在って良いものだろうか。
「おーい、大丈夫かい」
店主が店の奥から顔を覗かせ、蹲って震えている望月に心配そうに言葉を掛ける。
「ああ、はい。すみません……」
溢れる感情をまだ諫められないが、お店に迷惑はかけられない。
力の入らない足を無理やり立たせ、とりあえずレジへと向かう。
手元の本を買わなければ、何も始まらないことに気が付いたのだ。
「お会計を……」
「はいはい」
店主の訝し気な視線に気まずさを感じつつ、レジカウンターに本を置く。
思えば、この本は二人を繋げるキューピットみたいなものだ。
会計を待っている間も、望月は早くその本を自分の物にしたくてうずうずしていた。
だが、財布からお金を出す際にふと冷静になり、いやいや、と考え直す。
まだ、スタート地点に立っただけだ。
神の御加護で次の約束を取り付けられたが、これからお河と仲を深められるか否かは、自身の行動や態度にかかっている。
包んでもらった本を受け取る望月の手は、人知れず震えていた。
上手くいくのかという不安と、嫌われたらどうしようという恐怖と、あとでも、少しばかりの期待と希望。
そういったものが、望月の胸を大きく弾ませていた。
だからだろうか。
「ありがとうございました」
お礼を述べて出ていく望月の足取りが、誰が見ても軽いものだったのかもしれない。
望月の背中に、カウンター内の顔見知りの老人の、ひゅう、という口笛が届いた。
余計なお世話だ。
そんな十日前の出来事を反芻しつつ、本の丁度真ん中位を開いて俯くお河の横顔を眺める望月の視界に、何かがちらりと映った。
二人が再び合うための、目印。
今はつんつるてんの桜の木。それが、ベンチから良く見えた。
いや、どこからでも良く見えるのかもしれない。何せその桜は、公園のど真ん中にその根を下ろしているのだから。
植えられてまだ、そう年月が経っていないと見える。一般的な桜と比較しても背が低い。だがその佇まいは幼くとも立派な桜然としていた。堂々と立つ一本木は、花は咲いていなくとも仄かに薄桃色をしている。全身で、間もなく開く花の存在を想起させているのだ。
「望月さん?どうされたの、ぼうっとして」
澄んだ声に、はっとする。顔をお河の方へと戻し、
「ああ、いえ、何でも無いですよ」
慌てて両手を横に振った。答える声は、未だに小さい。
それでも、優しい笑みをくれるお河に、望月はほっと胸を撫で下ろした。
しかし、それも束の間、
「さあ、これからどうなさる?」
「え」
急転直下の質問が飛んできた。
「だって、このままさよならをするつもり?それならそれで構わないけれど?」
お河の挑戦的な、猫の様な瞳に、鼓動が速くなる。
妖艶さにどぎまぎしたのと、正直この後に関して何も考えていなかったことによる焦りのせいだ。
「あ、えっと、その……」
こういう時、どうするべきかなど知らない。これまで読んだ本にも、そんなことは書いていなかった。
見るからにあたふたする望月の様子に、くすりと笑い声を漏らしたお河は、続けて言った。
「あんたがもうしばらく、あたいと一緒に居たいか居たくないかの話なんだけど?」
「い、居たいです!」
思わぬ助け船に、取り繕う間もなく即答してしまった。そんな自分に、内心驚く。そんな勇気があったのか、と。
「ふふ。じゃあ、行こう。お気に入りの喫茶店があるんだ」
直後、お河はすくっと立ち上がり、どこかへ向かって歩き出した。
その後を、慌てて追う。
……情けない。彼女に引っ張ってもらってばかりだ。
お河の背後で、がくりと肩を落とす。
だが、こうして気にかけてもらっている内に何とかしなければ、見放されてしまうだろう。
これまでは誰かに従っているだけで良かった。というより、そういう生き方しか出来なかった。しかし、お河とのことは、それではだめだ。
いつまでも彼女に頼ってばかりでは呆れられ、せっかく繋がった縁も切れてしまう。
少しでも良い所を見せたい。
望月は両手で頬をぱんっと押さえて気合を入れ直すと、早歩きでお河の隣へと並んだ。
しばらく歩いて着いたのは、洒落た店構えの喫茶店だった。
店を出してそれ程年月が経っていないことが窺える、清潔感に溢れた店内。緊張しながらも、望月は案内された二人席に座る。
お揃いでオレンジジュースを頼むとその後、二人だけの時間が訪れた。
お河は薄く笑みを浮かべながら、窓ガラスの外を見ている。
モダンな雰囲気に圧倒されて、望月は気弱になっていた。正直、この場に居続ける事すらしんどい。だが、彼女を退屈させるわけにはいかないと、決死の想いで口を開いた。
「あ、あの……!」
「ん?なあに」
にこっと、誰もが見惚れるような笑みと共に、望月に視線を移すお河。
しかし、話す内容を決めていなかった望月は、大層困ってしまった。
どうしよう。どうしようどうしようどうしよう。
混乱を極めた望月は、その時思い付いた文言を口にした。
「ご、ご趣味はっ」
まるでお見合いみたいな切り口だ。
人間、異性と対面して、焦るとこれしか言えなくなるのだなと、どこか納得しながらも顔を赤くして俯いた。
そんな望月に、柔らかく降りかかる声。
「そうねえ、趣味と言ってはなんだけど、給仕のお友達と遊びに行くのは好きよ。家族と旅行にも行くわね」
ぱっと望月が顔を上げるとそこには、昼下がりの爽やかな光を頬に湛えたお河が居た。
そして、彼女は言う。
「貴方はどうなの?望月さん」
その美麗さの前に、望月はいっそ全てがどうでもよくなってしまった。
この先彼女に嫌われようと、何でもいい。
今この瞬間、彼女と過ごせた奇跡を、後生大事にすればよいのだと、そう思った。
ここから先、、望月は素でお河と話せたと記憶している。
「僕が好きなのは、本と──」
気が付けば、一時間半が経っていた。
始めの趣味の話から、これまでに旅行で訪れた土地の話、最新の流行について等々、様々な分野で互いの好奇心を刺激し合えたみたいだ。その為、日光の大部分に茜色が混ざった頃にようやく、時計の針を確認したのだ。
「もうこんな時間なのね。時間が経つのが速くて驚いたわ」
お河が、店内の掛け時計に顔を向けて言った。
「本当だ。それではそろそろ、出ましょうか」
望月も同じ時計で時刻を確認し、名残惜しくも席を立つ。
と、レジに向かう途中の通路で、こちらに向かってくる女中が目に入った。小さい盆の端一杯まで、ジュースやコーヒーやらを乗せて運んでいる。従って、彼女の視線は飲み物にばかり注がれており、周囲を確認する余裕など無さそうだった。
危なっかしいな。
気にかかって、望月は彼女の挙動を何となく眺めていた。
そして、間もなくすれ違う、そんな時だ。
ぬうっと、歩く女中のすぐ側のソファから男性が立ち上がった。お手洗いにでも行こうとしたのだろう。彼に全く非は無い。
無いのだが。
「ひっ!」
その気配に気づかなかった女中は驚き、身体をびくりと跳ねさせる。その弾みに、ぎりぎりに保たれていたお盆のバランスは、完全に崩壊した。
傾いた盆の面の先は──、お河。
咄嗟に身体が動いた。
「危ない!」
ばしゃっ!
「きゃ!」
幾つかの音が重なった後、そこに残ったのは、唖然とするお河と、青い顔の女中と、胸から下の服をびしょびしょに濡らした望月だった。
望月は即座に背後のお河に目を向ける。目を見開いてはいるが、水滴一つかかっていないようで、安堵した。
「も、申し訳ございません!お怪我は……っ」
望月に、そう謝罪しながら布巾を取り出した女給は、今にも泣き出しそうな表情だった。
きっと新人なのだろう。この件で今後、萎縮してしまっては可哀想だ。
そう思い、望月の服を拭おうとする彼女を手で制し、言った。
「いえ、お構いなく。僕は問題ないので、気にされないで下さい」
「で、でも……!」
「大丈夫です。早く、通路の片付けの方を」
「しかし……」
「如何されましたか!」
そうやってもたもたしている内に、男性の給仕までやってきてしまった。
「おい、お前!このお客様に何かしでかしたんじゃないだろうな?」
涙目の女給に、怒声を浴びせる男。その光景に嫌悪感を抱き、望月はすぐさま彼らの間に入った。
普段なら、きっとこんなこと出来なかった。だが、お河と話せて気持ちが昂っていたのだろう。
今なら何でも出来る気がした。
「すみません、僕が前を見ていなかったのです。彼女は何も悪くありません」
「お客様。そうは言いましても、お客様に多大なる迷惑を、」
「いえ、全く。むしろ、飲み物を頂き過ぎてしまったみたいです」
望月はそう言いながら、望月たちの会計より多いお金を、その場で男の給仕に渡した。
こればかりは、父親に貰ったお小遣いが余っていたのが幸いした。
手渡された領収書とお金に何も言えないでいる男性給仕を後にし、望月は足早に店を出る。
「随分と、落ち着いているのね」
店のドアを急いで閉めた直後、お河の声が背後からした。
しかし、望月の掌は汗でいっぱいだった。
全然、落ち着いてなんかいない。
自身の振る舞いが気障すぎて、他の客からほんの少しの注目を浴びるのも気恥ずかしかっただけだ。
引きつった笑みで、お河に言葉を返す。
「父親にあちこち連れられて、やたらと大人ぶった振る舞いだけは覚えた様です……。それでも、今日は格好つけてしまいました」
ここで、一度切った。
この後も言うべきか。言ってしまったら、これきりにならないか。
だが、駄目で元々。
そう思い切り、再び口を開いた。
「貴女の前ですからね。はは、身の丈に合ってませんか」
へらりと笑いながら、じっと、お河の顔を見つめた。
彼女に何と言われても良い、初めから身の丈に合わない出会いだ。
でも、それでも。
もし、もし。
ほんの少しでも可能性があるのなら。
どうかまだ、彼女との糸が切れませんように。
そんな希望が、瞳には籠っていた。
故に、
「いいえ。そんなことないわ」
そう、お河に言ってもらえて、心底安心した。危うく、ほう、と息を吐くところだった。
そのせいか、ため息の代わりに、
「また、会ってくれますか」
するりと、正直な想いが飛び出た。
だが、これは何も驚く事ではなかった。むしろ、こんな機会を逃す方が問題だと感じていた。
しかし、己に自信などなく。お河と釣り合うはずもないと十分に理解もしており。
伝えたいことは、伝えた。だから、潔く、身を引こう。
「て、まあ、こんなびしょ濡れのの男に言われても、ですよね。すみません、それでは」
そう言い残し、望月はくるりとお河に背を向けた。
その直後。
「もちろん。本も返さなければならないわ」
と、背中の布をぐい、と掴まれた。
え、と信じられない思いで振り向くと、輪郭を橙色に染めたお河が、楽しそうに笑っていた。
「ね、そうでしょ?」
好きな人の声がそう届いて、望月は流石に神に感謝せざるを得なかった。
それからも、幾度と無く会った。
初めは十日に一回だったのが、一週間に一度、五日に一度と、徐々にその頻度を狭めていった。
喫茶店で待ち合わせて、お茶を飲みながら、ただ話す。
一か月に数回ではあれど、その時間が望月は幸せだった。
といっても、ほとんど望月の好きな本の内容を語るばかりだった。それでも、彼女は愉快そうに聞いてくれた。
彼女の事についても、少しずつ知っていった。
お河は望月と同じ年で、最近近くに引っ越してきたのだという。カフェで働き、両親の助けをしているらしい。
詳しくは語らなかったが、金銭面的な補助をしているのだろうと予測した。
同じ歳で働いているお河に対し、自分は親の力で学校に通わせてもらっている身である。そのことに、少し恥ずかしさを感じたのは記憶に新しい。どことなくお河が大人びて見えるのは、その辺りに由来があるのかもしれない。
また、お河は交友関係が広い。往来でも、いつもの喫茶店でもどこでも、老若男女を問わず気さくに彼女に話しかける。そして彼女も、そんな彼らに眩しい笑顔を見せて応対するのだ。
そんな風に、お河は様々なコミュニティに伝手を持っている為、流行りの事や新しいニュースなどを沢山知っていた。望月が聞いたことのない話をあれこれと聞かせてくれるため、望月はお河と会うたびに見聞が広がっていく気がした。
そうやってお河と共に時間を過ごし、お河の事を知るにつれて、次第に緊張しなくなっていった。
望月にとって、お河が誰よりも美しく、そして、好意を寄せている人であることに変わりはない。
それでも、微々たるものだとしても、積み重ねた時間は、確実に望月に自信を与えてくれた。
お河と交わす声ももう、家族と話す時と同じ位の大きさだ。
この日は、梅が咲き誇る公園に足を運び、花見を楽しんだ後、喫茶店へと向かっていた。
品がありつつも賑やかなお河と、静かな笑みを湛えた望月。誰が見てもお似合いの二人は、並んで商店街へと踏み入った。
雑踏の中を、雑談しつつ進む。
「梅の花って、本当にいい香りがするのね」
「気に入ってくれて良かった。近くに素敵な公園があって良かったよ」
他愛もない会話が出来る幸せに、望月は浸る。
「ああそうだ、望月さん。幼い子向けに、面白い本って何かないかしら。親戚の五歳の子が、最近文字を読むのにご執心らしくて」
と、お河が新しい話題を振ってきた。
うーん、と束の間首を捻った望月は、その問いに答える。
「そうだなあ、流行りで言うと、『蜘蛛の糸』などどうだろう。分かりやすくも道徳的で、丁度いいんじゃないかな。もし難しくても、後々意味が分かる時が来るだろうし」
「『蜘蛛の糸』?一体どんなお話なの?」
「え」
無邪気に聞き返してくるお河に、望月は一瞬違和感を覚えた。だが、気のせいだと思うことにして、頭の中であらすじを組み立てる。
そうして、口を開いた。
「それはね──」
直後。
どんっ!
「きゃっ」
何かが膝下にぶつかり、そこから高い声が上がった。
下を向くと、五歳程の女の子が、尻もちをついていた。
「大丈夫?」
望月は即座にしゃがみこみ、呆然としている女の子を両手でゆっくり立ち上がらせる。
「怪我してない?」
「うん……、あっ」
望月の声に一度は頷いた女の子だったが、すぐさま悲嘆に染まった叫びを零した。
「あめちゃんが……」
さらにそう呟き、望月の足元を指す。
指先を辿ると、棒の付いた赤い色の飴が地面に落ちていた。
望月とぶつかった拍子に、落としてしまったのだろう。砂が付いてしまって、もう食べられなくなっている。
「おかね、おかあさんにもらって、それで」
女の子の瞳にうるうると涙が溜まり始める。しかし、小さな拳をぎゅっと握りしめ、雫を零さないよう堪えていた。その上、ぶんぶんと頭を横に振ると、
「ぶつかっちゃって、ごめんなさい」
と言って、頭を下げた。
じっと女の子の一連の振る舞いを、望月は見ていた。そして、年端もいかない女の子に、彼も頭を下げる。
「お兄さんこそ、ごめんよ。考え事をしていて、前をちゃんと見ていなかったんだ」
望月は女の子の手を握ったまま、優しい声で、言った。
「さあ、おいで」
きょろきょろと辺りを見渡した望月は、ある店に当たりを付けると、そこに女の子と連れ立っていく。
その店の前で待っていたお河がしばらくして目にしたのは、新しい飴を持ってにこにこと笑う女の子だった。
「ありがとうございます!」
元気いっぱいに、望月への感謝を伝える女の子の頭の上に、望月はぽん、と掌を置いた。
その目には慈しみの色が浮かんでいることに、お河はすぐに気が付いた。
「泣かずに、我慢強い子だ。次はもう落とさないように」
はい!と力強く頷いた女の子は、ぶんぶんと手を振りながら、駆けて行った。
あれではまた飴を落としてしまうのではなかろうか。
そう、はらはらする望月に、お河の声が掛る。
「ああいう、礼儀正しい子がお好みなの?」
「そういう訳ではないよ」
彼女の冗談めいた言葉に苦笑いを浮かべながら、望月は弁明した。
「別にわんわん泣き喚いても、替えを与えるつもりだった。ただ、幼いながらに健気に頑張る姿には参っちゃってね……。僕はあまり褒められてこなかった方だから、つい、他人に“誰かに褒められた”という記憶を植え付けたいみたいだよ」
頭の後ろ側に手をやり、照れたようにはにかむ。
そんな望月を、お河は何故か苦しそうな面持ちで見つめている。
まるで、上手く呼吸が出来ていないような、どこにも逃げ場がないような、そんな時の様に。
一言も発さない彼女に対して、望月が俄かに緊張と不安を感じ始めた位になってようやく、
「素敵ね」
お河は微笑みをくれた。
その笑顔に、望月はこっそり胸を撫で下ろす。
それから、二人は再び歩き始めた。
「お父様のお仕事は最近どう?上手くいっているの?」
喫茶店でオレンジジュースを飲みながら、お河はそう尋ねてきた。
父が警察官であることは、既に話していた。昨今の警察官が多忙なのを知って、度々こうやって心配してくれる。
その心遣いに感動しつつ、望月は言葉を返した。
「うん、最近は特に調子が良いみたいだよ」
お河の前では素直になれるのだと、最近知った。
知り合って間がない時は、自分の良い面を見せようだとか、みっともない姿を晒したく無いだとか、そういった考えで一杯だったものだ。
だが、お河の心の広さや、飾り気のない言動を間近で浴びていると、素の自分を曝け出しても問題ないと、そう思えるようになってきたのだ。
望月は、続ける。
「特にここ数日は、悪の巣窟を見つけた、だの、一網打尽だ、だのと夕食の場でうるさいんだ」
「悪の巣窟?」
「うん。なんだか良く分からないけれど、父さんたち警察の敵の本拠地なんだろう」
事実だった。
やたらと上機嫌で食卓に着き、自身が近い将来手に入れるであろう栄光を豪語している。
それに乗っかり、彼を持ち上げる母親や祖父母の姿には辟易するが、望月も何も思わないでもない。
父親が嬉しそうにしている事に悪い気はしないし、その作戦が成功してほしいと思う。
「そう。上手くいくと良いわね。あたいも応援してるわ」
お河もそう言ってくれて、望月は頬が緩む思いだった。
「今日も楽しかったわ。一日が、早く感じちゃった」
店を出るなり、お河が言った。
「僕もだよ」
望月も言葉を返し、二人で帰路に着く。
もう、お別れの時間まで間もない。会えば会う程、好きが募る。それなのに、また会えない時間が始まってしまう。
隣で歩くお河の左手が、ぶらぶらと揺れている。
それが目に入ってから、望月はずっと気が気でない。
その手に、どうしても触れてみたい。
きっと温かいに違いない。それか、いっそ冷たくても良い。僕の体温が上がり過ぎているから、丁度良いかもしれない。
望月は、ひっそりと右手を伸ばしてみる。
タイミングよく。自然に。下心を感じさせないよう、努めて爽やかに。
耳のすぐ傍で、鼓動の音がする。
内臓が、鉛の様に重い。
もし、この手を繋げたら。ああ、どれだけ幸せだろうか。
そんな期待で、気が逸る。
ゆっくり、ゆっくり手を近付ける。
もう少し、後一センチ──。
「ところで、」
くるりとお河がこちらへと体を向けた。
即座に、ぱっと右手を引っ込める。
「うん、どうした?」
何でもない様な顔で、望月は答えた。だが心臓はバクバクと跳ねまくっている。
「あの公園の桜って、そろそろ咲くころかしらね?」
そんな望月の内心はつゆ知らず、お河は呑気だった。
平常心を装いつつ、望月も頷く。
「そうだね。暦的にはもう間もなく、といった所じゃないかな」
時は、既に三月の上旬だ。
しばらくあの公園の桜は見ていないが、今頃は蕾を続々と付けているのではないだろうか。
「そう。咲いたら見に行きたいものね」
お河がどこか遠い目をしていのが気になったが、望月はお河と桜の花見をしたいと思った。
そして、出来ればその際に告白をしたいとも。
「じゃあ、その頃にまた、お会いしましょう。二十五日など、どうでしょう」
だから、いつものようにお河を誘った。
「ええ。良いわ」
彼女も、いつものように笑顔を見せてくれた。
大丈夫。まだまだ、二人には時間がある。
手をつなぐのは、次で良い。
望月は、そう自分に言い聞かせた。
「失敗した!」
望月父が帰宅するなりどっかりと居間に座り込み、そう大声で嘆いたのはそれから三日と経たない内だった。
慌てて母がお酌をしているのを横目に、望月は彼に尋ねた。
「失敗したとは、どういうことですか。悪を、一網打尽に出来ると言っていたではないですか」
望月も珍しく、父親に疑問を投げかける。それ程までに、彼は異様な悔しさを滲ませていた。
父親は苦虫を嚙み潰したような形相で、言葉を返す。
「そのはずだったさ。誰にも知られるはずの無い、完璧な計画だった。客が満員に近い時間帯を狙って、突入した」
「客?どこかの店だったのですか?」
「ああ、喫茶店だった。だがな、足を踏み入れた時にはもう、もぬけの殻だった。従業員も誰も彼もが、完全に店を引き払ってしまった後だ」
「どこかから情報が漏れてしまったのでしょうか」
望月の呟きに父親も、うーむ、と顎に手をやる。
「分からん。相手はよっぽど高度な技術を用いて、盗聴やスパイ行為を仕掛けてきたのかもしれん。全く、大したものだ」
そう言うと父親は、ぐびりと酒を煽った。
望月もそれ以上は何も聞かず、部屋に下がった。
父親でも上手くいかないことがあるのだと知って、独りきりの部屋で、どこかほっとした。
お河が店を辞めた。
その事実を知ったのは、突然のことだった。
お河が、来ない。
三月二十五日。
約束したはずの日だった。
いつもの待ち合わせ場所で、いつもの時間に待っていた。
三十分待っても、一時間待っても現れないお河に、望月は心配した。
事故に遭ったのか。病に罹ったのか。
待てば待つ程、心配の種は増えて行った。
そんな折りに、あることを思いついた。
お河は約束の日を間違えて、カフェで働いているのでは無いかと。
そう不意に思った望月は、お河が働くカフェに足を向けた。お河と交流を始めてからその店に行ったことは無かったが、来ては駄目だとも言われて無かった。
ともすれば、お河のエプロン姿を再び見られるかもしれない。
そんなうきうきとした思いは、席について時間が経つにつれ、しぼんで行った。
待てど暮らせど、お河の姿が見当たらない。
一時間経過した時点で望月はしびれを切らし、別の女給に尋ねた。
お河は、今日は休みですか、と。
そうして、知らされた。
望月は、頭が真っ白になった。何も考えられなくなって、その直後には、様々な思いでぐちゃぐちゃにかき乱された。
どこに行ってしまったのだろうか。
よもや、本当に事故や事件に巻き込まれたのではないか。
だって、今まで二人の約束をすっぽかしたことなど無かった。
桜を見に行こうって、言ったのに。
望月は、あちこちを走り回った。
梅の公園。商店街。
いつもの喫茶店にも行った。中はがらんどうで、お河が居るはずも無かった。
カフェを出た時点で、午後の六時を過ぎていた。冬の終わりとはいえ日はそう保たず、あっという間に辺りは暗くなってしまった。
お河。大好きなお河。
なんて、脆い関係だったのだろう。
たった一つの約束と、共通点を失うだけで、君に会えなくなるなんて。
どこに住んでいるかなど知らない。
無条件に、また顔を見られると思っていた。
それが、こんな、焦燥感に駆られる事態になるなど、誰が予測できただろう。
土地勘のある範囲をぎりぎりまで駆け回った望月は、道のど真ん中で、膝に手を突いて呼吸を整える。彼に奇異の目を向ける人もいた。
だが、そんなことは気にせず、望月は必死に思考を巡らす。
後、行っていない所は、どこだ。
お河がいるとすれば、どこだ。
出会って二か月。たった二か月。
されど、二か月。
望月はふと思いついて、とある場所へと向かって走り出した。
薄ピンクの花びらが一枚、ひらひらと鼻先を掠めて行く。
二人で初めて約束した場所。
久しく訪れていなかった、始まりの地。
あの、若い桜の木は、今や満開となっていた。
照明も無いのに、夜闇の中でぼんやりと発光している。
きっと、花びらが周囲の幽かな光を吸い込んで、自身の輝きにしてしまっているのだろう。
そんな桜を前にして、お河はぽつんとベンチに座っていた。
その姿は、どこか泣いているように見えた。
「お河……、お河、お河!」
足をもつれそうになりながら、望月は駆け出した。
ゆっくりと振り向いたお河の表情は、桜と逆光になっていて見えない。
彼女の座るベンチへと辿り着いた望月は、縋るようにお河の膝に両手を置く。
「何も言ってくれないなんて、酷いじゃないか……。もう、二度と会えないのかと……っ」
悲しみと安堵でいっぱいの望月に対して、しかし、お河は淡々と言葉を紡ぐ。
「悪いね。こっそり消えようと思ってたんだ。前もって言うの、何となく恥ずかしくって」
「そんな……。どうして急に」
口をあんぐりと開け、驚きを顕わにする望月に、お河は冷たく言い放つ。
「もう会いたくなかったんだよ。お金をふんだんに持っている訳でもないし、話もつまらないし」
望月の好きな声が、望月の胸をえぐる。
それでも。
「ずっと退屈だったのよ。どれだけ欠伸を堪えるのが大変だったか」
聞きたくないのに、鼓膜を震わす。澄んだ声音が、心を切り刻む。
でも、それでも。
「あーあ。私なりの優しさで、黙って居なくなろうとしてやったのに。探しになんか来ちゃって……」
「嘘だっ!」
望月の大声に、お河は口を噤んだ。
「だったら、何でここに居るんだよ!」
お河は、はっとした表情を浮かべた。
「もう僕と会いたくないなら、わざわざこんな所に来る必要ないはずだ!僕が来る確率が、少しでもあるなら避けるべきだ!でも、君はここに居た。しかもこんな夜遅くまで!僕が来るのを待っていたんじゃないのか?」
「望月さん……」
お河は、いつか見たような苦しそうな顔で、俯いた。
望月は何度か深呼吸し、気持ちを落ち着かせた。
そして、口を開く。
「君に、言わなければならないことがある」
「………………なあに」
「君は、」
望月は、もう一度大きく息を吸い、覚悟を決める。
「僕の父親が警察だって知って、わざと僕に近付いたのだろう?」
「!?」
驚愕するお河に構わず、続ける。
「そもそも、妙だと思ったんだ。僕と君が偶然、本屋で出会うものか?君はまるで本を読まないのに、どうして本屋に居たんだよ」
「そんなことないわ、私だって本、読むわよ。何を言うの」
困惑したように反論するお河に、望月は事実を叩きつける。
「君は、『蜘蛛の糸』を知らなかった」
「それは、偶然読んでいなくて……」
「あれだけ流行っている芥川先生の代表作を?」
「芥川さんは、あまり好みではないのよ」
「そう。だったら何故、最初に本を貸した時、真ん中のページから開いたんだ?。本を嗜む人間は、まず一ページ目で好みを確かめるものだよ。
それに、殊更あの本は、途中から読んだって容易には理解できない内容だ。自分から手を伸ばした割には、理解が浅くないか?」
お河はとうとう、黙ってしまった。
望月は、気が付いた真相を述べ続ける。
「カフェで、父さんたちが話しているのが聞こえたのだろう。それで君は気が付いた。父さんが警察官であることと、僕の存在に。上手く利用できると思ったんだろう?僕の事を」
「……何故あたいが、そんなことをする必要があるの?」
大きな瞳で望月を真っ直ぐ見つめるお河。
その黒目から目を離さず、望月は震える声で、答えを示した。
「それは君は、社会主義者の娘だからだよ」
お河は、息を呑んだ。そして、声を絞りだす。
「どうしてそれを……」
「治安維持法の成立で、国の意向に沿わない団体は警察により粛清され始めた。それは、社会主義団体も例外では無い。君は、都会から最近引っ越してきたと言っただろう?ここは大分田舎だから、弾圧の手を逃れられる。君の家族は、そう踏んだ」
望月は、苦々し気に言葉を続ける。
「それでも、不安の種は消えない。警察の目を掻い潜りつつ、活動を続けたい。だから警察側の動きを知るために、君は僕に近付いたんだ。そうやって、スパイ活動をしていたのだろう?」
度々、お河は望月に問うてきた。
父親の仕事の調子はどうかと。
何も気づかず、望月はその質問に毎回、意気揚々と詳細を語っていた。が、彼女に警察の動向を探られているに過ぎなかったのだ。
父親が存在を危惧したスパイは、他でもない、望月自身だった。
「そんなの言いがかりだわ。私はただ、望月さんの家族について知りたくて」
苦言を呈すお河に、望月は悲し気に首を振った。
「僕は今日、ここへ来る前に、二人で良く行った喫茶店を覗いてみた。そしたら、もぬけの殻だったよ。それが、決定打だった」
お河は、がくりと項垂れた。
その姿が何よりもの証拠で、望月は胸が苦しくなった。
本当は、否定し続けて欲しかった。二人の出会いは神からの贈り物で、策略に塗れたものではないと、信じていたかった。
「父さんが検挙に踏み込んだ喫茶店は、君がよく連れて行ってくれた喫茶店だったんだ。あそこは社会主義者のたまり場だったんだね。でも、僕から情報を得ていた君は、早々に伝えていたんだろう。直に、警察が来るって。だから、父さんが突撃したときにはもう、皆が皆、逃げた後だった」
何も言わないお河に、望月は逃げ道を塞ぐように、言葉を紡ぎ続ける。
「偶然かもしれないよね。でもさ、君が店を辞めたのとほぼ同じタイミングで、君のいきつけの喫茶店も、店を畳むものかな。
僕の考えは、状況証拠ですらないよ。それでもね。こう考えれば、全ての筋が、通るんだ。だって、」
通ってしまうんだよ。
「君みたいな素敵な人が、僕を誘ってくれるわけがないんだ」
自分で言っておきながら、目の奥が熱くなるのを望月は感じた。
不甲斐なくて、幼くて、初めは碌に話も出来なかった。
そんな自分が、彼女と無条件に、交流できる訳がなかったのだ。
悲しい現実に打ち震え、望月は肩を落とした。
そんな彼の耳に、鋭い声が届く。
「違う、違うわ!」
「は……」
望月が顔を上げると、お河が必死の形相で反論してきた。
「確かに、初めはそうだったわ!両親に言われるままにカフェで働いて情報を集めて、偶々貴方たちが話をしているのを小耳に挟んで……。それをお父様とお母様に話したら、大層喜んで、貴方を追えって」
「…………」
改めて突き付けられた事実に、望月は胸が抉り取られるような痛みを覚えた。
「貴方が通う本屋を調べて、タイミングを合わせたわ。貴方が伸ばした手に、わざと触れたわ。ええそうよ、本なんて、ちっとも読まない」
これ以上、聞きたくなかった。辛くなるだけだと思って、望月は耳を塞ごうと両手を上げた。
その瞬間、するりとお河の言葉が、飛び込んできた。
「でも、でもね。今は違うわ」
「どう違うって言うんだ!」
溜まりかねて、望月は叫んだ。
膝を折り、地面に突っ伏して頭を抱える望月に、お河の優しい声が降りかかる。
「貴方の事が、本気で好きよ。自信が無いけれど、博識で、人に優しい貴方の事が、大好きなの」
「そんな……」
砂に、額をこすり付ける。
凄く凄く嬉しいはずの言葉なのに、どこか空虚に響いている。
「今更、信じられないよ。僕の気持ちを、利用したのは君なのに」
涙声で、望月は答える。
沈黙が、二人を包んだ。
その後、
「信じてくれなくても結構。こうなってしまった以上、私たちはこの町、いえ、県を離れてもっと田舎へ引っ込みます。貴方たち警察に、捕まりたくはありませんから。
貴方の事と同じくらい、私は家族を、例えどんな家族でも、愛しているの」
そう言い置いて彼女は、すたすたと歩いて行ってしまった。
その声が濡れていたように聞こえたのは、気のせいだっただろうか。
独り残された望月は、しばらく動けなかった。
ショックと悲しみと、“好き”という言葉が、胸中を飛び回る。
これまでの思い出が、墨を零したように、塗りつぶされていく。
本当に楽しかったのに。幸せで満ちていたのに。
ざりざりと、爪で土を掻きむしる。
掛けてくれた言葉も、見せてくれた笑顔も、過ごした時間も。
初めから、全部が偽物だった。
そう思うと、悲しくて悔しくて悲しくて、どうしようもなくて──。
「追いかけませんの?」
幼い声が突然、地面に伏したままの望月に聞こえた。
ばっと顔を上げるとそこには、薄ピンクの着物を纏った、七歳程の少女が居た。
その存在に全く気が付いておらず、望月は固まる。
「ずっと、ずっと見てましたわ」
驚いて動揺する望月を気にも留めず、少女は無邪気に言葉を紡ぐ。
「貴方は、これで良いのかしら?」
望月は、何も答えられなかった。
言いたいこと、したいこと、すべきことは山ほどあるのに、身体が動かない。
ただ、首を横に振ることしか出来ない望月。
その肩に、小さくて温かい掌がとん、と乗る。
「まあまあ、こちらに一旦、お掛けになってはいかが?そう俯いていては、まともに頭を働かすことも出来ませんわ」
見ず知らずの少女なのに、何故か素直に言う事を聞けた。
望月はゆるゆると緩慢な動きで立ち上がると、膝位の高さの少女に手を引かれ、ベンチに腰を掛けた。隣に、少女もすとん、と座る。
と、
「それで、貴方は彼女の事をどう思っているの?」
唐突に、そう聞かれた。
「え!」
思わず、傍らの少女に顔を向ける。
少女は真っ直ぐに、こちらを見ていた。
端正な顔立ちだと思った。
開いているのか分からない細い目に、整った鼻筋と細い眉、そして、短く切り揃えられた黒髪。それら全てのバランスが、神々しい程に釣り合っている。
まるで、人間ではないみたいだ。
話し方と見かけの年齢も、嚙み合っていないように思える。それか、とんでもない良家の子で、英才教育の賜物なだけなのか。
そんな事を考えつつも、少女の真剣な視線を浴び続けた望月は、観念して心情を吐露する。
「……好きだよ。彼女が僕を想うよりも、ずっと僕の方が好きだ」
「やっぱりそうなのね!思った通りだわ!」
望月の返答を聞いた途端、手を叩いてはしゃぐ少女。
落ち着いていた姿とは打って変わった様子に、望月は戸惑った。
だが、ここからさらに戸惑う事となる。
「それならどうして、悲しいお顔をしているの?両想いなんでしょう?」
何故空は青いのか、と幼子が尋ねるような口調だった。
ずっと見ていた、と言う割には理解が追い付いていないらしい。なるほど、やはり大人びているのは話し言葉のみのようだ。
望月は、鈍い動作で首を横に振り、答える。
「騙されていたんだよ、ずっと。そんな人が言う事を信じられない。まだ、僕を騙しているかもしれないんだ」
望月の気を引き続けて、今後も警察の情報を抜き取ろうとする可能性がある。だから、これを機にお河との縁を切るべきなのだ。
どれだけ彼女の事が好きで、離れるのが辛くとも。
そう、覚悟を決めながら、望月は言ったのだ。
しかし、それを聞いた少女は、不思議そうに首を傾げた。
「あら?過程はそうだったかもしれないけれど、彼女が告げた想いに嘘があるとお思いなの?それが、貴方の足に根っこを張っている本当の理由?」
「え」
「だってそうでしょう?どこからか、なんて分かりはしないけれど、彼女が貴方に本音で向き合った時間が、必ずあるのではないかしら」
少女の正直な言葉に、ぐ、と胸が詰まる。
真っ直ぐ過ぎて、事の真理に、望月の本音に、強引に連れて行かれる。
この子が年端も行かない少女だなんて、とんだ思い違いだと、後悔すらした。
望月の記憶が、かき乱される。
塗りつぶしたはずの思い出が、たちまちに色鮮やかに蘇る。
好きだと言ってくれた声音。それは、これまで聞いた中で、最も柔らかかった。子供に飴を買い与えた時に見せてくれた笑顔。それは、最も温かかった。
──そこに偽りが混じっていないことなど、分かっている。
そう、分かっている。全てが全て、作られた贋作ではないことなど。二人で育んだ愛が、間違いなく存在することなど、とうに分かっている。
動けない理由は。頭を抱えてしまっている理由は。心が追い付かない理由は。
ああ、分かっている──。
「だって僕には、家族と彼女、どちらかを選ぶことなんて出来ない!」
脈絡も無く、望月は叫んだ。
一度理性の壁が崩壊すると、そこから感情の波が溢れ出してしまう。
「お河の事は大好きだ。好きで好きで仕方がない!でも、彼女の家は、僕の父親が取り締まっている対象で、所謂悪者なんだよ……!僕も将来、警察官にならなくちゃいけないし、家族にもそう期待されている。そうなったら僕は彼女を捕まえなくちゃならない……!」
少女はぴくりと眉を動かすことも無く、じっと、望月の心の内を聞いていた。
望月は、涙ながらに苦悩を漏らし続ける。
「そんなこと、したくない!お河とずっと一緒に居たい!でも、家族も大事だ……。
僕は、一体、どうしたら良いんだよ……」
うう、と望月は拳で、ごしごしと両目を擦る。
十五歳が抱えるには、重すぎる天秤だった。
少しの間、沈黙が続く。
その後、ぼそりと望月は呟いた。
「それに、僕は彼女が欲しかった言葉をさっきあげられなかった。もう、とっくに見放されているさ」
ふう、と気持ちを落ち着かせるために、息を吐く。
誰かにぐちゃぐちゃとした思考を暴露したお陰か、いくらか諦めが付いた。
十五歳の恋物語など、こんなものだと、感情に整理を付ける。
そして、弱弱しい笑みを受けべて、望月は口を開いた。
「どこのご令嬢かも存じ上げないのに、申し訳ございません。さあ、こんな夜分遅くに出歩かれていては、ご家族も心配なさいますよ。僕がお送りしますから、」
「まだ時間はあるわ。貴方の切なる思い、伝えるだけ伝えてみる、というのはどう?」
手を取ろうとした少女の目が、大きく開かれた。
驚いて、吸い込まれるように、その黒い瞳を凝視する。
舞い散る桜の花びらが、映っていた。
ぼうっと、少女の眼球越しの景色に魅入ってしまう。
はっと我に返ってからようやく、少女の提案に力なく否を唱えた。
「僕の言葉には、力がない。だからぶつけても無駄なんだ。何かに響かせ、動かすことなんて、出来っこないんだよ」
話しながら望月は、目を伏せる。
かつての、苦い出来事が思い出される。子供だからと、束の間の言論の自由を奪われたあの日。
その日痛感した無力さは、望月の自我を奪うのに十分だった。
「『言葉』は元来、『こと』の『端』なんですのよ」
不意に、少女が言葉を発した。
「『こと』というのは、口に出すだけで現実になってしまう重いものなので、少しでも軽くしようと『端』を付け足したのが由来らしいですの」
突然のうんちくに、望月は困惑した。
「だから何だって……」
「そんな端くれすら、貴方は口に出来ないのかしら?」
しかし、すかさず飛んできた厳しい言及に、閉口する。
「元来、言葉に力なんて、誰も持たせられませんことよ。ただ、言葉を発した方の纏っているものが、受け取り手にそのまま圧し掛かるの。貴方は、何も纏ってないの?」
少女の元に戻った細い目は、だが、これまで以上に望月の瞳を射貫いていた。
その視線にたじろぎながら、望月は小さな声で答える。
「僕には、何も……。何も、無いよ」
「でしたら、貴方が身に着けた知識は一体なんだというのかしら。彼女と紡いだ日々は、何だったのかしら」
「────っ」
望月の弱気な部分を打ち砕くように、少女は鋭く言い返した。
それから数分間、いや、数十秒だったかもしれない。
望月は考えた。
自分の選ぶべき道を。すべき事を。行くべき場所を。
そして、決めた。
だから最後に、このベンチから立ち上がる前に、少女に問うた。
「一体、どこまで僕の事を、いや、この世のことを知っているの?」
少女はふふんと笑いながら、自慢気に言った。
「こう見えて私、遊び歩いておりますの。色んなものを、見て、聞いてきましたわ。ああでも、知らないことまで知っていることもあるの」
一体何なんだ、この少女は。
「ははは。可笑しな子だ」
堪らず笑った望月の耳に、かん高くも大人びた声が小さく響く。
「……失敗しても、良いではないですか」
「うん?」
聞き返した望月に、少女は諭すように語った。
「一夜咲きの、何が悪いでしょう。それに、貴方の花が咲くのは一度ではありませんわ。今後も、何度もその機会がありましょう。そして、そんな貴方の最初の花弁を開くのは、今宵が頃合いなのでは?ほら、」
そう言いながら、少女はどこかを指差した。
望月も、そちらを見上げる。
そして、ああ、と納得した。
「見事な、満月なのですから」
望月は再び、走り出した。
お河に追い付けるだろうか。
どこに行ったかは分からない。家の場所は、教えてくれていなかった。
でも、絶対に、今夜中に見つけてみせる。
公園を去る前に、一瞬、望月は振り返った。
ただ、美しい桜の幼木が一本、あるのみだった。
十数分後。
歩いているお河を見つけた。
全くの偶然だった。
あても無く、勘を頼りに町中を駆け回っただけだった。
それなのに、再び、彼女に出会えた。
今度こそ、今度こそ神に感謝するべきかもしれない。
「お河!!」
びくりと肩を跳ねさせて、振り返った彼女の頬は濡れていた。
その涙でさえも、美しいと感じた。
「……なあに。望月さん」
はあはあと呼吸を整える望月に、お河は鼻声で声をかける。
全く、愛おしい。愛おしいから、僕は。
「認めない。認めないよ。今は、君の家族を認められない。だって僕は、あくまでも、警察の息子だ。父さんの、息子だ。僕に沢山の栄養と、お金と、知識を授けてくれた父さんの、息子だ。裏切ることは出来ない」
「……」
お河は何も言わず、絶望したように、涙をはらはらと流す。
ああ、泣かないで。大丈夫だから。
望月は間を置かず、続きを、一息に言い切った。
「だから、一緒に探そう。僕たちの様な、国民の無傷を望む人達と、君たちの様に、遍く国民の幸せを望む人達が、共存出来る道を。決して楽ではないけれど、その両方が叶う道を、必ず」
「望月さん……」
頬を紅潮させながらも、お河の瞳はますます潤んでしまう。
望月は彼女の手を、優しく包んだ。
「僕たち、二人で、ね?」
ようやく触れられたその掌は華奢で、でも、喫茶店のガラス越しに浴びた、いつかの日光の様にぽかぽかしていた。
その後、二人は離れ離れになった。
お河の家族は、宮崎に引っ越してしまったのだ。
望月は中学校を卒業した後、警察練習署に入った。
学力の面は何も問題が無かったが、体力面では歯を食いしばらなければならない場面が多かった。
数年後、無事に警察官になった望月は、配属の希望を東京に出した。
それが叶い、父親と母親、祖父母の皆に見送られながら乗った東京行きの鉄道で、一人の女性と合流する。
二人は、手を繋いだまま東京駅に降り立ち、共に暮らす家へと歩き出した。