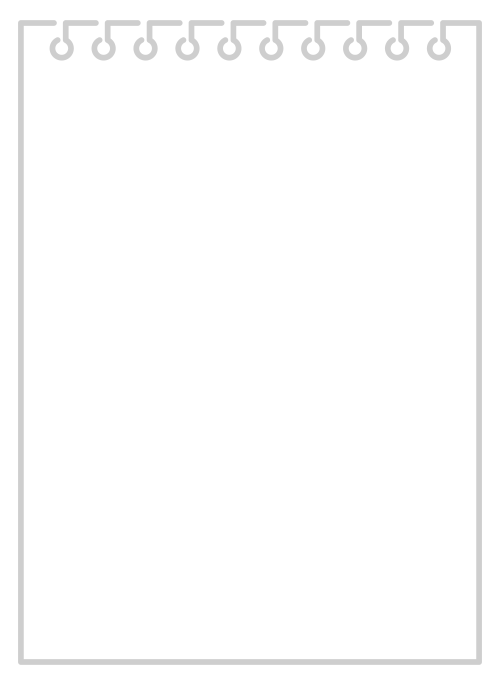鍵がないことに気づいたのは、閉店作業を終えて後は帰るばかりとなった二十一時半のことだった。うそでしょ、と悦子が鍵束を掴んだ途端、目の前が真っ暗になった。
暗くなったのは実際に明かりが落とされたからだ。店が入っている商業施設じたいのクローズが二十一時で、そこから段階的に屋内の電灯が消されるようになっている。閉店から三十分経った今、すべての店舗の照明が消えた。さらに十五分後には廊下にわずかに残っている照明も消され、二十二時前の時点でグリーンの非常口の誘導灯以外は何も見えなくなる。時間制御で機械的に明かりが落とされていくさまはまるで建物そのものが人を追い立てているかのようだ。
電気が消えるのが早いという声はあちこちから上がっているが、商業施設のオーナーにあたる管理会社は光熱費がかかりすぎているからと消灯時間をむしろ今より早めたい意向だ。蛍光灯をLED照明に切り替える話が進んでいるらしく、それが完了したら時間が延びるかもという噂も聞くが誰も期待はしていない。それで悦子たちもほかの店も閉店作業は慌ただしく逃げ出すかのように片づけをする。
悦子の勤めるクイーンルピナスは女性をメインターゲットにした雑貨店である。お部屋を明るく彩る、がコンセプトの商品に囲まれていても、この時間にはもう、二店舗ぶん離れた廊下の明かりしか届かない。そばで共に帰り支度をしていた副店長を呼び止めつつ、悦子は暗くなった手元をスマホで照らして再度鍵を確認した。
「ヤダ、落としちゃったの」
「すみません」
閉店まで店に残っていたのは悦子と副店長のゆりだけである。ゆりは悦子の五つ上で三十二歳と聞いているが、見た目も話し方も、良くも悪くも二十代前半に見られる。そのことについて本人は得意に振舞っているふしがある。それに加え、大雑把で楽観的。悦子とはまるで反対の女性だ。
なくなったのは店の鍵束に下げた七本のうちの一本で、クイーンルピナスの開店当初から使っていないという倉庫の鍵だった。この鍵束じたい二つあって、問題になっているのは普段は使わずキーボックスにしまったままの予備のほうだ。この鍵束を悦子は今日の仕事中ずっとエプロンのポケットに入れていた。
今日に限って予備の鍵束を出していたのは、常用のほうを警備員に貸していたからだ。年に何度か実施が義務づけられているという点検や測定をおこなうといって、警備の若い男が借りにきたのだった。悦子が出勤したちょうど昼の時間のことだった。そのとき普段使いの鍵束を持っていた店長がそのままそれを渡し、半休で帰る店長と入れ替わるようにして悦子が予備の鍵束を持つ役回りになった。警備員から鍵束を返却されてもわざわざ取り替えることはせず、悦子は予備を持ち続けた。
「そこらへんに落ちてないの」
ゆりもスマホを取り出して床を照らす。悦子は念のため自分のポケットやバッグを調べるが当然そんなところにはない。次に什器を順番にずらしながら一つひとつ確かめていく。それでもない。見つからない。
「ウチもう帰らなきゃだから。見つからなかったら、明日店長に話しておいてね」
明日の出勤は悦子が店長と同じく朝からで、ゆりは昼からだ。ダメージが少ない彼女は気楽なものだと恨めしく思う。ダメージ、と考えてしまい気が塞いだ。
「ゆりちゃん、えっちゃん。帰りましょ」
よく知った声がして顔を上げると、同じ二階フロアにある茶葉の店の渡邊だった。つるりとした頭の下に開いているのかいないのかわからないほど細い目が常に笑みを湛えている、お地蔵様のような風貌のおじいさんだ。休憩時間にフードコートへ行くとたまに鉢合わせて、そんなときには自前の茶葉でお茶をご馳走してくれる。
「私、もう少し探してから行きますから、お二人はどうぞお先に」
「何をお探しなのかな」
「倉庫の鍵を落としたみたいで」
「おやおや」
ほどほどにして切り上げなさいよとほがらかに返される。悦子の焦りや深刻さとはまったくかけ離れたところから言われて内心むっとする。しかし実際この人には関係のないことだし、無理をしないように言ってくれているのだと、悦子もわかっているつもりだ。
「そうだ、警備さんに電話するといいよ。あそこに落とし物の連絡が行くからね」
悦子に望みをもたらして渡邊は歩き出す。ゆりも、電話の結果を待たずに渡邊に伴った。悦子だけを残し、二人のやたらと明るい話し声は遠ざかっていった。
応対したのは崎本という男で、その特徴的な低音の声から察するに、昼にやってきた警備員だった。鍵の落とし物はないかと訊ねたが、警備室に鍵は届けられていないという。
やはり自分で探さなければならない。もう一つの鍵束にある鍵をコピーすれば、という思いつきはすぐに打ち消した。鍵を紛失したわけだから、複製で済む話ではない。もう使っていない倉庫とはいえ扉の鍵ごと取り替えなければならないし、それなりの費用がかかるだろう。店への負担は小さくない。
店長の西尾の顔が思い浮かんだ。それは自然と悦子を見上げた状態の画になる。歳でいえば一回りも上の女性だが、子どもの背丈ほどなので近くで話すとこちらが見下ろすかたちになるのだ。当人はそうは思わないだろうが、失礼だと思われている気がしていつも気が引ける。
何より今日、悦子は西尾に注意されたばかりだ。昨日の閉店作業で悦子がやり忘れていたことがあって、出勤早々に西尾に声をかけられた。悦子が謝っているところに警備の男が鍵束を借りに来たのだった。
そういうわけでなるべくなら今のうちに鍵を見つけ出して何事もなく明日を迎えたい。本当なら、遅番からの早番でただでさえ寝る時間が足りないので一秒でも早く帰るべきところではある。しかしそれをおいても鍵の発見、というより叱られる事態を回避することが悦子にとっては重要だった。
スマホのライトを頼りに店内を捜索する。什器の下、レジの中、ワゴンの底まで漁る勢いで調べるが見つからない。鍵束は基本、店内でしか出さない。しかしクイーンルピナスにないとなると、品出しのために入ったバックヤードか、休憩時間に行った三階のフードコートか、洗面室か、あるいはそれらへ向かう途中……こうなると範囲はあまりにも広すぎる。そういった共用部分に落ちているなら自分が今探しに行かなくとも、翌朝の開店前に清掃員が見つけてくれることだろう。そういう判断はできるのに、清掃員に託そう、ここで切り上げようという気は起きず、だらだらと隣の店の前まで探し始めてしまう。
気づけば廊下の電気は一つも残っていない。どこの店のスタッフもいない。二十二時をとうに過ぎ、もう半近くになっていた。遅くとも二十三時にはここを出ないと最終の電車に間に合わない。いよいよ諦める決断をすべきかと思いかけたとき、懐中電灯を持った誰かがこちらに向かってきた。
「鍵、まだ探していたんですね」
例の警備の男、崎本だった。体格の良さから顔を見るまでもなく彼だと気づいた。この建物に詰めている警備員は五十代や六十代と思しき年配の人ばかりで、自分と同年代の若い人は悦子の知る限り彼だけだ。
「すみません、遅い時間まで残ってしまって」
「こちらこそ気が利かずに申し訳ない」
暗がりで一人でいたことを咎められたり訝しまれたりするのではと身構えたが、彼のほうが恐縮しているようでひとまず安堵する。
崎本が飾り気のない白いガラケーを出して電話する。警備室にかけているらしい。相手に電気を点けるよう頼んでおり、それが自分のためだと悦子が思い至ったときにはもうクイーンルピナスの店内に煌々と光が溢れ、フロアの廊下も一部点灯し出した。
「わざわざありがとうございます」
明るくなってまともにものが見られるようになり、初めて間近で彼の顔を見た。思った以上に精悍な顔立ちで、その体つきも相まって、ここみたいなのどかなショッピングセンターではなく省庁や研究室といったお堅い建物の警備をしていそうに見えた。
せっかく点けてもらったのだから、もう少し探さないとこの人に悪い。悦子はそう考えてみる。鍵を見つけられないまま帰路につく後ろめたさを先延ばしにする口実ともいえた。
「落とした鍵というのは、具体的には」
変わった声だなという印象は昼に会ったときからあったが、その低音が耳に心地よく響くことを悦子はこのとき初めて知った。
「うちが借りている倉庫の鍵の予備です。鍵どころか、その倉庫じたい使ってないんですが」
すべて揃っているほうの鍵束を手にして、これなんですけど、と示す。
「それは――」
崎本の言葉を遮るように、バタンと大きな音が響いた。遠くで、何か大きなものが壁か何かを強く叩いたような音だった。
「えっ、何の音」
驚いた悦子は自然と崎本に体を寄せていた。見上げると彼は音の正体を知っているような顔でその方向を見つめていた。「今夜は寝られないかもな」という独り言を悦子は聞いた。
バタン、バタンと、一か所ではなくあちこちから同じような乱暴な音が続いた。得体の知れない集団が悦子たちを取り囲んで脅かしているようにも聞こえるし、何か大きな存在が癇癪を起こして所構わず暴れているようにも思えた。音が落ち着くまで悦子は怯んで動けなかった。崎本が悦子の肩に手を置いて言った。
「帰る支度を。素直に出られるかわかりませんが」
悦子が聞き返す間もなくガラケーが鳴って彼は電話に出てしまう。わけがわからないまま、悦子は自分のバッグを掴んで通話が終わるのを待った。今度も警備室と話しているらしい。スプリンクラー、防火といった、火災をイメージする言葉が聞こえてきて戦慄する。悦子の顔が強張るのを見逃さず、彼は電話の後すぐに「大丈夫です、落ち着いて」と悦子を宥めた。
「今のは防火扉が閉まる音です」
「防火って……火事なの」
「その可能性はほぼありません。火災のときに動くはずのほかの装置は動いていないようですし、何より現場はここだという表示が出ているそうですから」
でもどこも燃えていないでしょうと崎本はわざと外国人じみたポーズと表情で肩をすくめてみせる。普段、仕事中には絶対に見られない顔だと思った。今まで注意して見たことはないが警備員というのはいつも無表情でいるに決まっている。彼の気遣いを感じられて悦子の気持ちは凪いでいった。
ほどなくして館内放送が流れ出す。警備室にいる崎本の同僚が話しているのだろう、やはりこちらも火災ではないと告げていた。
「火事じゃないなら、どうしてこんなことが」
「原因はイロイロ考えられますが。まあ、今は外に出ましょう」
不自然なほどまっすぐ見つめられて悦子はどぎまぎする。いったいどういう意図でやっているのか。
「でも、まだ鍵が」
「誤発報で今後何が起こるかわかりません。スプリンクラーでびしょぬれになるのも嫌でしょう」
外まで送りますよと、悦子の返事も待たずに歩き出す。悦子は慌てて彼の隣に並んだ。
「イロイロって何ですか」
まさか自分が一人でいる間に何か触ってしまったのではないか。あるいは自分が遅くまで残っていたために誤作動を引き起こしたのではないか。悦子は気が気でない思いで崎本に問う。
崎本は歩きながら少し考えるそぶりを見せた。
「この建物、いわくつきなのはご存じですか」
「そういえば聞いたことがあります」
いつだったかゆりや渡邊が話していた。この辺りは昔、被差別部落のあった土地らしくその手の噂に事欠かない。土地や建物の値段は上げられず不動産業者は必ず説明しなければならないというから、忌まわしい過去があったのは本当なのだろう。
「ここの管理会社は安く買えてラッキーくらいにしか思っていないんでしょうが。夜中に巡回していると、出るんですよ、コレが」
崎本が体の前で手をぶらりとさせる。
「うそ、お化けのせいだっていうの」
「うそです」
崎本は即答する。真面目な顔を崩すことなく言ってのける。悦子は唖然としてしばらく彼を見つめてしまっていた。
「ちょ、ちょっと、やめてくださいよ」
「失礼。あんまり不安そうにしていたので」
そこで初めてくしゃりと破顔した彼の目尻に、小さなしわが出来た。そのしわが顔に似合わずチャーミングで悦子もつられて笑ってしまった。
「そんなにわかりやすいですか、私」
「はい、ずっと深刻な顔をしていましたよ」
「深刻な状況じゃないですか」
「そんなに深刻になることはないですよ」
前にも誰かとこんなやりとりをしたような気がした。ゆりにも、渡邊にも、前の職場の同僚にも、悦子は同じようなことを言われてきた。
――気にしすぎだってば。
――えっちゃんは考えすぎだよ。
何もかもまともに受け止めすぎて深刻になりすぎるのが、悦子の悪い癖だ。
「ま、設備の老朽化でしょうね。消防設備も含め、どこもかしこも見た目以上に古くなっていると聞きます」
「そういうのって直せるものなんでしょうか」
「直すというか、取り替えるのが一番ですけどね。設備業者も更新を勧めているそうですが、法的なこととか耐用年数とか、究極に必要に迫られるまでは補修で騙し騙しやっていくのだとか」
「いっそ丸ごと新しくしてくれたらいいのに」
「ケチなんですよ、ここのオーナー様は」
初めの印象よりもよく喋る人だと悦子は思う。警備室はいい加減な管理会社のせいで今みたいな余計な仕事を増やされているわけだから、愚痴を零したくなるのも頷ける。彼の勤める警備という仕事について、悦子の知らないことはまだまだたくさんありそうだ。
「あの、いつからここにいるんですか」
もう少し話していたくて悦子は新たに話を振ってみる。
「三年前ですかね」
「あ、ごめんなさい。今の流れだとそうなりますよね。じゃなくて、時間のほう。お昼にはもういたでしょう」
本来なら遅番の悦子だって帰っている時間だ。彼の勤務時間がさっきから気になっていた。
崎本は、ああ、と小さく笑い、八時だと答えた。
「八時って、そんな、いったい何時間働いてるんですか」
「朝八時から翌朝八時の当直勤務なんです。もちろん仮眠時間もあります」
「そ、そうなんですね」
「明日は明け休みですし、それなりに休む時間は確保できていますよ」
それにしたってしんどそうだ。自分にはとても務まりそうにない。
「もっとも、今日は寝させてもらえないでしょうが」
今晩は寝ずに誤作動した設備の対応をするのだろう。大変ですねと月並みなことしか言えないのを悦子は歯痒く思った。
あれ、ここってこんなふうだっけ。悦子は次第に、辻褄の合わない夢の中を歩いているような気分になる。
普段通り従業員出口を目指して歩いているはずなのに、違和感がある。いつの間にか現れていた壁のせいだ。防火扉や防火シャッターのために景色が変わって見えていた。
「おっと、ここは通れませんね。じゃ、あっちから出ましょう」
彼が道を変えたのは、扉の前にものが散乱して開けられそうもなかったからだ。周りに置かれていたダンボール箱や備品の類が防火扉の動きで散らかったらしい。どかすのは容易ではないし下手に手を出せば怪我をしそうだ。似たようなところはほかにもあって、防火扉の周りだけまるで別の災害が起きたような惨状だ。
営業時間に一般客が使うエレベーターやエスカレーター、階段周辺はシャッターが下りてしまって使えない。崎本の向かう先は非常口のようだ。悦子は使ったことがないがあそこから下階に出られるのだろう。
「だめになった商品とかたくさんありそうですけど、どうなるんでしょう、その、責任とか」
破れたダンボールから飛び出して歪んでしまった幼児向け玩具を見て不憫に思う。クイーンルピナスとしてもバックヤードに置いたものはどうなっているかわからない。例の倉庫は使い勝手が相当に悪かったのか、クイーンルピナスの前の店の時点で使われなくなったと聞いている。鍵束だけそのまま引き継いで、悦子もゆりも、おそらく店長の西尾も入ったことすらない。それで従業員通用口の壁際に、よその店舗と同じように商品を詰めたダンボール箱を積んである。あの付近に防火扉やシャッターがあったかどうかなど、意識したことがないのでわからない。
「ものを置くなと書いてありますからね。それでも置いていた店側の落ち度ですよ」
けろりと、いっそ冷たく言い放つ崎本に悦子はほっとしてしまう。彼や警備の人たちが頭を下げて各店に謝るところを想像したからだ。
その想像はじきに、及ばなくてもいいところまで及んでしまう。
――なんでこんなんなってんの。
――前にも言ったよね。メモしてたよね。
――社会人何年やってんの。
不意に悦子を襲う、叱責の数々。一度蘇ると次から次へと芋が連なるように出てきては悦子を苛み苦しめる。
――余計な仕事増やさないでよ。
――こんなのちょっと考えたらわかることでしょ。
――目見えてるんでしょ、なんですぐ気づけないの。
黒い土に手を突っ込んでわざわざ掘り起こしているのは自分だとわかっているのに、止まらなくなる。頭を下げて、すみません、本当にすみませんと謝っているのは悦子のほうだ。
鍵を、探さないと。
悦子は再びその思いに囚われる。鍵がないままでは帰れない。また叱られてしまう。今度こそ本当に呆れられてしまう。
ガシャン、ガラガラと何かが崩れるような音がした。その音で悦子の意識は引き戻された。
今度は防火扉や何かしらの設備の音ではない、明らかにものが崩れてひどいことになったような音だった。
二人が向かっていた非常口の通路が音の発生源で、その正体は椅子だった。催事用のプラスチックのガーデンチェアが元は堆く積まれていたのだろう。それらが通路を塞ぐように雪崩を起こしてしまっていた。その数は十や二十ではない、軽く二百脚は超えていた。
「だからここに置くなって言ってるのに」
崎本の独り言が今の悦子にはまるで自分に向けられたように思えてしまう。思わずすみませんと口をついて出そうになる。深みに嵌る思考をなんとか振り切り、悦子は手近な椅子を起こした。
「私も手伝います」
「助かります」
椅子を重ねる崎本に倣って悦子も手を動かす。椅子の数こそ多いが、先ほどの防火扉の前ほど悲惨ではない。椅子しかないぶん、かえってやることが単純なのは幸いだった。
「まるでここを出るのを拒むかのように、狙いすましたように崩れましたね」
崎本の言葉に、悦子は思わず手を止める。
「……また、お化けの冗談ですか」
「怪異というのは人の気持ちに敏感なんだとか」
まただ。また、彼は悦子の目をまっすぐ見つめて言う。何もかも見透かすような瞳に射止められ悦子は落ち着かなくなる。いや、落ち着かない心地でいるのは今に始まったことではない。
「もしかして」
崎本は悦子の耳元に口を寄せて言う。誰も聞いていないのに、内緒話をするように潜めた声でその先を続ける。
「帰りたくないんじゃありませんか」
言い当てられて、悦子は後ずさる。その拍子に近くの椅子が倒れた。シチュエーションが違えばロマンチックなセリフにもなったであろうその言葉が、悦子には重い塊となってのしかかる。
「明日を迎えるのが怖い。帰宅して眠れば否応なく朝が来る。だから、帰るのが嫌なのではないですか」
「どうして」
どうして、そんなにも私の気持ちがわかるのだろう。悦子が抱いたのは情けなさと、羞恥だった。
明日を迎えるのが怖い。彼の言う通りだ。家に帰らずとも明日は来る、そう理解していてもなお、帰りたくない。このまま帰って、明日のことを考えながら眠りにつくのが辛い。出勤して叱られる想像をしながら過ごす、翌朝までの時間が毎日、毎晩、辛くてたまらない。
こんな、子どもみたいな理由で怯える情けない姿を、会って間もない目の前の男に暴かれてしまうなんて。
「なんで、わかるんですか」
「似た思いを、かつて抱えていたことがあります」
彼は悦子から離れて、悦子が倒した椅子を戻しながら続ける。
「当直勤務は一日の勤務時間が長いぶん、月の出勤回数は減るんです。それで自覚しました。ここに移る前はずっと、朝の出勤に大きな負担を感じていたのだと」
飄々と、難なく物事をこなしているように見える彼も、悦子の知らないところでは苦しんできたのだろうか。
自分以外の人は皆、何もかも平気に毎日を過ごしている。そんな思いが悦子にはあって、たまに見かけるだけの関わりのない警備員など、その最たるものだった。無機質で完全なものと思い込んでいた。冗談を言ったり愚痴を零したり、弱みがあったりするなんて思いもしなかった。
「ふとしたときに思いつめた顔をするのが気になっていました。椅子が崩れる直前も、そうでしたよね」
気づかれていたのか。彼が特別敏いのか、悦子が思っている以上に周りに伝わってしまうものなのか、どちらにしても恥ずかしかった。
「一番最初のきっかけで言うなら、昼のことが気にかかっていました」
「昼って……あ、鍵を借りに来たんでしたね」
彼が来たときにちょうど、悦子は店長の西尾に前日の閉店作業について注意されていたのだ。
「こう言ってはなんですが、謝り方が異常だと思ったんです。店長さんも引くほどだった」
あのとき、悦子は何か取り返しのつかない過ちを犯したかのように必死に謝っていた。西尾としては、やり忘れがあったよ、気をつけてねという程度のつもりで声をかけたにすぎず、悦子の謝罪に驚いて言葉も出なくなっていた。
悦子がそれほどまでに必死だったのは、頭の中ですでに散々叱られていたからだ。そのミスは前の日の夜、布団に入ったころに気がついて、汗が噴き出すほど猛省した。そこから出勤するまで、悦子を責めるありとあらゆる言葉が妄想で作り上げられ、それらに対して謝り続けていた。実際に西尾に言われた言葉と悦子が創出した言葉は綯い交ぜになって、もはや何を言われて何を言われていないのか覚束ない。
「前の職場で、上司に毎日すごく怒られていたんです。周りの人はあんなのパワハラだ、真に受けなくていいってフォローしてくれてたんですけど、言われる内容は間違っていない気がして。そうやって受け止めているうちに、限界を超えてしまったんですね、きっと」
何をするにも叱られる理由を探し尽くす癖は、ここから始まった。今、悦子を叱る声は前の上司だったり西尾だったり、名前も知らないお客だったりする。
「ここに転職してからは、前みたいに怒鳴られることはなくなりました。意地悪な言い方をする人もいないし、皆優しいし。……でも、頭の中ではずっと怒られているんです」
脳内に響く声は悦子の行動を何一つ許さない。何をしても、何をしなくても、どんな選択をしても間違っているような気がして身動きが取れなくなる。どうすればいいのかわからなくなる。
「鍵を、見つけなきゃと思って。店長がそんなにきつい言葉を言うはずがないって、わかってはいるんですけど、それでも、ここで帰ってしまうのが怖いんです。怒られて、謝って、そんなことを頭の中でずっと繰り返してしまうんです」
小さな注意こそあれ、悦子が西尾に叱られたことは実際には一度もない。想像の中で厳しく言われ続けて、勝手に苦手意識を持っているだけだ。そのせいで悦子は帰るに帰れなくなっているのだった。
「おかしいですよね、こんなの。いつもいつも、自分で自分を苦しめてる」
「おかしくなんかないですよ。人の心がトラウマの再現をするのは自然なことです」
「そうでしょうか」
「心を回復するために必要なことだと聞きます。どんなに冷たい水も触っているうちにぬるくなってくるし慣れてもきます。心もそうやって、嫌な記憶が適度なぬるさになるまで何度も何度も出し入れしているんです」
メンタルヘルスの先生の受け売りですが、と崎本は優しく言った。彼もまた、冷たい水が温まるのを待っていた時期があるのかもしれない。それはもう触れられる温度になったのだろうか。自分にもそのときは来るのだろうか。
「鍵は、見つかり次第すぐに届けます。清掃さんにも連絡しておきますよ」
「すみません。ありがとうございます」
「ところでその鍵のことですが、気になることがあるんです」
待っててくださいと崎本はガラケーを出して電話をかけ始める。やはり相手は警備室のようで、現状の報告に加えて悦子が探している鍵の話を持ち出した。はっきりした答えが得られないまま通話が終わったらしいことを話しぶりから察する。
「気になることって何ですか」
「まだ確定していないので、なんとも。今、調べてもらっていますが」
崎本の返答は歯切れが悪いが、半端な状態では言えないということなのだろうと悦子は納得した顔をしてみせる。
「鍵については一旦置いておきましょう。何にしても、ここをどうにかしないと」
二人は椅子の片づけを再開した。悦子が五つまで重ねたものを崎本が壁際に運んで、ほかのと合わせて十脚のまとまりにする。慣れてきて作業が段々スムーズになっていく。
「本来こんなところに置いてはいけないので、せっかく重ねてもじきに解体してしまうかもしれません」
「そう考えると虚しくなりますね。何でしたっけ、石を積む……」
「ああ、賽の河原ですね。子どもの霊が石の塔を作ろうとするのに、鬼がやってきては崩してしまうから永遠に完成できないという」
「賽の河原、か」
悦子は、自分がその霊であるように思えた。何にもならない悪い想像ばかりを積み上げながら、鬼が来るのを恐れている。塔は完成しない。完成図などまったく見えない。ただただ、積んでは崩し、積んでは崩しを繰り返している。
「おや」
椅子に貼りついていた何かが落ちた。崎本が拾い、悦子も覗き込んだ。渡邊がいる茶葉の店のレシートだった。長い間椅子に挟まっていたのだろう、紙はかさかさに乾いて光沢を失い、文字もすっかり薄くなっている。
「そうだ、賽の河原の話には地蔵菩薩が出てくるんですよ。石積みを続ける子どもたちの前に現れて、彼らを救済するんだそうです」
お地蔵様の話は知らなかった。子どもの霊も永遠に苦行を続けるわけではない、いつかは救われるのだ。悦子はふと思った。彼は、悦子が賽の河原と自分の状況を重ねたことに気づいたのかもしれない。それで教えてくれたのだ。彼の気遣いが好ましかった。
「ここの店主、お地蔵さんのような顔してるんですよね」
「あっ、渡邊さんでしょう、やっぱり似てますよね」
ひそかに似ていると思っていたのが自分だけではないと知り悦子は嬉しくなる。
「びっくりするほどそのまんまですもんね。拝めば何かご利益がありそうだ」
そう言って崎本は恭しく手を合わせる。可笑しくて笑うと、釣られて崎本も笑った。
片づけのキリがついたところで崎本のガラケーが鳴った。彼が出ると、大きな声が「サキちゃん、わかったよ」と言うのが漏れ聞こえた。
「――じゃあ、元からないわけですね」
崎本が話すのを聞くうちに、悦子はまさかと思う。まさか、まさかそんなことって。
「お察しの通りです」
通話を終えた崎本が、悦子に向き直って言った。
「今日は、業者と一緒に館内を回って、設備の点検と空気の測定をしていたんです」
そういえば彼が鍵束を借りに来たのはそういう用事だったと思い出す。
「そのときに業者の人から聞いたんです。昔、ある扉の鍵穴があまりにも固くて、鍵を折ってしまったことがあると」
「それが、あの倉庫の鍵だったんですね」
「はい。業者の人は、管理会社に弁償したと話していました。だからてっきり鍵は買い直したものだと思っていました」
しかし実際にはそうではなかった。クイーンルピナスの前に入っていた店は鍵穴の固い倉庫は使えないと放置し、管理会社も使われていない倉庫の鍵をわざわざ買うことはしなかった。まだ一本あるからとそのままにしていたのだ。その状態で前の店が撤退し、クイーンルピナスが鍵束ごと継いだ――
それが、予備の鍵束に倉庫の鍵がなかった理由である。
悦子が手に取るずっと以前から、鍵はなかった。悦子は存在しない鍵を探し続けていたのだ。
「申し訳ありません。もっと早くに調べていれば、こんな時間まで残ることはなかった」
崎本が深く頭を下げる。悦子も慌てて謝り返す。
「私のほうこそごめんなさい。最初に鍵の本数を確認していたら。一本足りないことに気づいていたら。店長に確認できていたら、落としただなんて大騒ぎすることもなかったのに。本当にすみません」
「あなたが謝ることはありませんよ。鍵を揃えておかなかった管理会社のせいです。そう、全部ずさんな管理会社が悪いんです。設備がおかしくなってこんな目に遭っているのも――こっちはもしかしたら、人ならざる者の仕業かもしれませんが」
「……実は結構オカルト好きです?」
悦子はすかさずつっこみを入れる。これもまた彼の気遣いだと思えて心が温かくなるのを感じた。悦子が自責しすぎないよう話の方向をころころと転がしてくれているように思えたのだ。
「いわくのある物件なのを知ってここを職場に選んだほどですからね」
「それはさすがに冗談ですよね」
「さあ、どうでしょう」
崎本と軽口を叩いていると体の力が一気に抜けた。心の強張りがどこかへ行ってしまったようだ。椅子を積んだ後でなかったら座ってしまいたかった。
「でもよかった。鍵、なくしたんじゃなくて本当によかったです。ありがとうございます」
「さっそく地蔵パワーを発揮してくれましたね」
崎本があのレシートを出して合掌する。渡邊のお地蔵様のような顔が浮かんだ。
しかし悦子には渡邊よりも、目の前の彼こそが、自分を救うために垂迹した存在であるような気がした。鍵の顛末を抜きにしても、彼の言葉や心配りに大いに救われた心地だった。今後いつ賽の河原に迷い込んでしまっても、この夜の出来事が心を癒してくれる、救ってくれる。そう思うと気持ちが楽になった。
「外に出る前に一つだけ、わがままを言ってもいいですか」
悦子はふと思いつき、そう言ってみる。
「もちろん」
二人がやってきたのは三階のフードコートだった。フロアの照明はすべて落とされているので、崎本の懐中電灯だけが光源だった。
「お仕事中なのに、付き合ってもらってすみません」
「構いませんよ。ちょうど喉も渇いていましたし」
電車はすでになくなっていて、出勤までは近くのネットカフェで時間を潰すつもりでいる。その前にここへ寄ったのは、無性にお茶が飲みたくなったからだった。
崎本は水を、悦子はお湯を飲んでいる。茶葉はないので当然何の味もしない。それでも悦子はお湯の中にお茶の味を探しながら、じっくりと飲んでいた。
「警備室ではサキちゃんと呼ばれているんですね」
「聞こえていたんですか。似合わないと言ったんですが、定着してしまいました」
はにかむ崎本がかわいかった。渡邊がいたらすぐにサキちゃんと呼び始めただろう。
ここでお茶を飲む時間が悦子は好きだ。初めて渡邊に誘われたときには、休憩中とはいえここに勤める人間が使ってもいいものか、渡邊は平気で茶葉を持ち込むしお湯も使うし、いつか誰かに注意されるのではないかと気が気でなかった。西尾の姿が見えたときには叱られるのを覚悟したものだった。
しかし渡邊が「まーちゃん、こっちこっち」と西尾までも無邪気に呼び、三人で同じテーブルを囲んだことで、この場所は安全地帯になった。西尾も渡邊のお茶のファンだった。ここで渡邊とお茶を飲むことについては、悦子の中の誰も咎めない。それで安心してお茶が飲めるのだった。
そんな場所で、彼とお茶が飲みたいと思った。
不思議だなと悦子は思う。叱られると思って身構えても叱られるどころか一緒にお茶を飲むことになる。無機質だと思っていた警備員が実はよく冗談を言ったりオカルト好きだったり、優しく気遣ってくれたりする。なくしたと思っていた鍵に至っては元々存在しなかった。悦子の考えることは当たらないどころか現実のほうが斜め上を行く。どんな想像をしてもその通りになることはほとんどないと、今さらながら気がついた。
気持ちが緩んで思わずあくびをすると、すかさず崎本が、
「始発で帰って、明日は一日休んでしまったらどうです」と言った。さすがにそれはできませんと悦子は笑う。
「それにやっぱり、お湯じゃなくて、渡邊さんのところのちゃんとしたお茶が飲みたくなっちゃいました。明日はそれを楽しみにして乗り切ります」
「そこまで言われると飲んでみたくなりますね」
「ぜひ一緒に飲みましょう、休憩時間が合うといいんですけど……」
「いや、明日は俺、明け休みですから。ここにはいませんよ」
「あ、そうでした」
つい前のめりになった自分が恥ずかしくなる。コップにほとんど残っていないお湯を飲もうと口をつけた。懐中電灯の光から顔を隠そうと、コップを長く持ち続ける。
でも、と崎本は少し間を空けてから言う。
「午後にふらっと客として来ることはできます」
悦子は嬉しくなる。こんなに心が弾んだのはいつぶりだろう。明日を楽しみに思える日が来るなんて思いもしなかった。
心の底から、明日を迎えるのが待ち遠しかった。
暗くなったのは実際に明かりが落とされたからだ。店が入っている商業施設じたいのクローズが二十一時で、そこから段階的に屋内の電灯が消されるようになっている。閉店から三十分経った今、すべての店舗の照明が消えた。さらに十五分後には廊下にわずかに残っている照明も消され、二十二時前の時点でグリーンの非常口の誘導灯以外は何も見えなくなる。時間制御で機械的に明かりが落とされていくさまはまるで建物そのものが人を追い立てているかのようだ。
電気が消えるのが早いという声はあちこちから上がっているが、商業施設のオーナーにあたる管理会社は光熱費がかかりすぎているからと消灯時間をむしろ今より早めたい意向だ。蛍光灯をLED照明に切り替える話が進んでいるらしく、それが完了したら時間が延びるかもという噂も聞くが誰も期待はしていない。それで悦子たちもほかの店も閉店作業は慌ただしく逃げ出すかのように片づけをする。
悦子の勤めるクイーンルピナスは女性をメインターゲットにした雑貨店である。お部屋を明るく彩る、がコンセプトの商品に囲まれていても、この時間にはもう、二店舗ぶん離れた廊下の明かりしか届かない。そばで共に帰り支度をしていた副店長を呼び止めつつ、悦子は暗くなった手元をスマホで照らして再度鍵を確認した。
「ヤダ、落としちゃったの」
「すみません」
閉店まで店に残っていたのは悦子と副店長のゆりだけである。ゆりは悦子の五つ上で三十二歳と聞いているが、見た目も話し方も、良くも悪くも二十代前半に見られる。そのことについて本人は得意に振舞っているふしがある。それに加え、大雑把で楽観的。悦子とはまるで反対の女性だ。
なくなったのは店の鍵束に下げた七本のうちの一本で、クイーンルピナスの開店当初から使っていないという倉庫の鍵だった。この鍵束じたい二つあって、問題になっているのは普段は使わずキーボックスにしまったままの予備のほうだ。この鍵束を悦子は今日の仕事中ずっとエプロンのポケットに入れていた。
今日に限って予備の鍵束を出していたのは、常用のほうを警備員に貸していたからだ。年に何度か実施が義務づけられているという点検や測定をおこなうといって、警備の若い男が借りにきたのだった。悦子が出勤したちょうど昼の時間のことだった。そのとき普段使いの鍵束を持っていた店長がそのままそれを渡し、半休で帰る店長と入れ替わるようにして悦子が予備の鍵束を持つ役回りになった。警備員から鍵束を返却されてもわざわざ取り替えることはせず、悦子は予備を持ち続けた。
「そこらへんに落ちてないの」
ゆりもスマホを取り出して床を照らす。悦子は念のため自分のポケットやバッグを調べるが当然そんなところにはない。次に什器を順番にずらしながら一つひとつ確かめていく。それでもない。見つからない。
「ウチもう帰らなきゃだから。見つからなかったら、明日店長に話しておいてね」
明日の出勤は悦子が店長と同じく朝からで、ゆりは昼からだ。ダメージが少ない彼女は気楽なものだと恨めしく思う。ダメージ、と考えてしまい気が塞いだ。
「ゆりちゃん、えっちゃん。帰りましょ」
よく知った声がして顔を上げると、同じ二階フロアにある茶葉の店の渡邊だった。つるりとした頭の下に開いているのかいないのかわからないほど細い目が常に笑みを湛えている、お地蔵様のような風貌のおじいさんだ。休憩時間にフードコートへ行くとたまに鉢合わせて、そんなときには自前の茶葉でお茶をご馳走してくれる。
「私、もう少し探してから行きますから、お二人はどうぞお先に」
「何をお探しなのかな」
「倉庫の鍵を落としたみたいで」
「おやおや」
ほどほどにして切り上げなさいよとほがらかに返される。悦子の焦りや深刻さとはまったくかけ離れたところから言われて内心むっとする。しかし実際この人には関係のないことだし、無理をしないように言ってくれているのだと、悦子もわかっているつもりだ。
「そうだ、警備さんに電話するといいよ。あそこに落とし物の連絡が行くからね」
悦子に望みをもたらして渡邊は歩き出す。ゆりも、電話の結果を待たずに渡邊に伴った。悦子だけを残し、二人のやたらと明るい話し声は遠ざかっていった。
応対したのは崎本という男で、その特徴的な低音の声から察するに、昼にやってきた警備員だった。鍵の落とし物はないかと訊ねたが、警備室に鍵は届けられていないという。
やはり自分で探さなければならない。もう一つの鍵束にある鍵をコピーすれば、という思いつきはすぐに打ち消した。鍵を紛失したわけだから、複製で済む話ではない。もう使っていない倉庫とはいえ扉の鍵ごと取り替えなければならないし、それなりの費用がかかるだろう。店への負担は小さくない。
店長の西尾の顔が思い浮かんだ。それは自然と悦子を見上げた状態の画になる。歳でいえば一回りも上の女性だが、子どもの背丈ほどなので近くで話すとこちらが見下ろすかたちになるのだ。当人はそうは思わないだろうが、失礼だと思われている気がしていつも気が引ける。
何より今日、悦子は西尾に注意されたばかりだ。昨日の閉店作業で悦子がやり忘れていたことがあって、出勤早々に西尾に声をかけられた。悦子が謝っているところに警備の男が鍵束を借りに来たのだった。
そういうわけでなるべくなら今のうちに鍵を見つけ出して何事もなく明日を迎えたい。本当なら、遅番からの早番でただでさえ寝る時間が足りないので一秒でも早く帰るべきところではある。しかしそれをおいても鍵の発見、というより叱られる事態を回避することが悦子にとっては重要だった。
スマホのライトを頼りに店内を捜索する。什器の下、レジの中、ワゴンの底まで漁る勢いで調べるが見つからない。鍵束は基本、店内でしか出さない。しかしクイーンルピナスにないとなると、品出しのために入ったバックヤードか、休憩時間に行った三階のフードコートか、洗面室か、あるいはそれらへ向かう途中……こうなると範囲はあまりにも広すぎる。そういった共用部分に落ちているなら自分が今探しに行かなくとも、翌朝の開店前に清掃員が見つけてくれることだろう。そういう判断はできるのに、清掃員に託そう、ここで切り上げようという気は起きず、だらだらと隣の店の前まで探し始めてしまう。
気づけば廊下の電気は一つも残っていない。どこの店のスタッフもいない。二十二時をとうに過ぎ、もう半近くになっていた。遅くとも二十三時にはここを出ないと最終の電車に間に合わない。いよいよ諦める決断をすべきかと思いかけたとき、懐中電灯を持った誰かがこちらに向かってきた。
「鍵、まだ探していたんですね」
例の警備の男、崎本だった。体格の良さから顔を見るまでもなく彼だと気づいた。この建物に詰めている警備員は五十代や六十代と思しき年配の人ばかりで、自分と同年代の若い人は悦子の知る限り彼だけだ。
「すみません、遅い時間まで残ってしまって」
「こちらこそ気が利かずに申し訳ない」
暗がりで一人でいたことを咎められたり訝しまれたりするのではと身構えたが、彼のほうが恐縮しているようでひとまず安堵する。
崎本が飾り気のない白いガラケーを出して電話する。警備室にかけているらしい。相手に電気を点けるよう頼んでおり、それが自分のためだと悦子が思い至ったときにはもうクイーンルピナスの店内に煌々と光が溢れ、フロアの廊下も一部点灯し出した。
「わざわざありがとうございます」
明るくなってまともにものが見られるようになり、初めて間近で彼の顔を見た。思った以上に精悍な顔立ちで、その体つきも相まって、ここみたいなのどかなショッピングセンターではなく省庁や研究室といったお堅い建物の警備をしていそうに見えた。
せっかく点けてもらったのだから、もう少し探さないとこの人に悪い。悦子はそう考えてみる。鍵を見つけられないまま帰路につく後ろめたさを先延ばしにする口実ともいえた。
「落とした鍵というのは、具体的には」
変わった声だなという印象は昼に会ったときからあったが、その低音が耳に心地よく響くことを悦子はこのとき初めて知った。
「うちが借りている倉庫の鍵の予備です。鍵どころか、その倉庫じたい使ってないんですが」
すべて揃っているほうの鍵束を手にして、これなんですけど、と示す。
「それは――」
崎本の言葉を遮るように、バタンと大きな音が響いた。遠くで、何か大きなものが壁か何かを強く叩いたような音だった。
「えっ、何の音」
驚いた悦子は自然と崎本に体を寄せていた。見上げると彼は音の正体を知っているような顔でその方向を見つめていた。「今夜は寝られないかもな」という独り言を悦子は聞いた。
バタン、バタンと、一か所ではなくあちこちから同じような乱暴な音が続いた。得体の知れない集団が悦子たちを取り囲んで脅かしているようにも聞こえるし、何か大きな存在が癇癪を起こして所構わず暴れているようにも思えた。音が落ち着くまで悦子は怯んで動けなかった。崎本が悦子の肩に手を置いて言った。
「帰る支度を。素直に出られるかわかりませんが」
悦子が聞き返す間もなくガラケーが鳴って彼は電話に出てしまう。わけがわからないまま、悦子は自分のバッグを掴んで通話が終わるのを待った。今度も警備室と話しているらしい。スプリンクラー、防火といった、火災をイメージする言葉が聞こえてきて戦慄する。悦子の顔が強張るのを見逃さず、彼は電話の後すぐに「大丈夫です、落ち着いて」と悦子を宥めた。
「今のは防火扉が閉まる音です」
「防火って……火事なの」
「その可能性はほぼありません。火災のときに動くはずのほかの装置は動いていないようですし、何より現場はここだという表示が出ているそうですから」
でもどこも燃えていないでしょうと崎本はわざと外国人じみたポーズと表情で肩をすくめてみせる。普段、仕事中には絶対に見られない顔だと思った。今まで注意して見たことはないが警備員というのはいつも無表情でいるに決まっている。彼の気遣いを感じられて悦子の気持ちは凪いでいった。
ほどなくして館内放送が流れ出す。警備室にいる崎本の同僚が話しているのだろう、やはりこちらも火災ではないと告げていた。
「火事じゃないなら、どうしてこんなことが」
「原因はイロイロ考えられますが。まあ、今は外に出ましょう」
不自然なほどまっすぐ見つめられて悦子はどぎまぎする。いったいどういう意図でやっているのか。
「でも、まだ鍵が」
「誤発報で今後何が起こるかわかりません。スプリンクラーでびしょぬれになるのも嫌でしょう」
外まで送りますよと、悦子の返事も待たずに歩き出す。悦子は慌てて彼の隣に並んだ。
「イロイロって何ですか」
まさか自分が一人でいる間に何か触ってしまったのではないか。あるいは自分が遅くまで残っていたために誤作動を引き起こしたのではないか。悦子は気が気でない思いで崎本に問う。
崎本は歩きながら少し考えるそぶりを見せた。
「この建物、いわくつきなのはご存じですか」
「そういえば聞いたことがあります」
いつだったかゆりや渡邊が話していた。この辺りは昔、被差別部落のあった土地らしくその手の噂に事欠かない。土地や建物の値段は上げられず不動産業者は必ず説明しなければならないというから、忌まわしい過去があったのは本当なのだろう。
「ここの管理会社は安く買えてラッキーくらいにしか思っていないんでしょうが。夜中に巡回していると、出るんですよ、コレが」
崎本が体の前で手をぶらりとさせる。
「うそ、お化けのせいだっていうの」
「うそです」
崎本は即答する。真面目な顔を崩すことなく言ってのける。悦子は唖然としてしばらく彼を見つめてしまっていた。
「ちょ、ちょっと、やめてくださいよ」
「失礼。あんまり不安そうにしていたので」
そこで初めてくしゃりと破顔した彼の目尻に、小さなしわが出来た。そのしわが顔に似合わずチャーミングで悦子もつられて笑ってしまった。
「そんなにわかりやすいですか、私」
「はい、ずっと深刻な顔をしていましたよ」
「深刻な状況じゃないですか」
「そんなに深刻になることはないですよ」
前にも誰かとこんなやりとりをしたような気がした。ゆりにも、渡邊にも、前の職場の同僚にも、悦子は同じようなことを言われてきた。
――気にしすぎだってば。
――えっちゃんは考えすぎだよ。
何もかもまともに受け止めすぎて深刻になりすぎるのが、悦子の悪い癖だ。
「ま、設備の老朽化でしょうね。消防設備も含め、どこもかしこも見た目以上に古くなっていると聞きます」
「そういうのって直せるものなんでしょうか」
「直すというか、取り替えるのが一番ですけどね。設備業者も更新を勧めているそうですが、法的なこととか耐用年数とか、究極に必要に迫られるまでは補修で騙し騙しやっていくのだとか」
「いっそ丸ごと新しくしてくれたらいいのに」
「ケチなんですよ、ここのオーナー様は」
初めの印象よりもよく喋る人だと悦子は思う。警備室はいい加減な管理会社のせいで今みたいな余計な仕事を増やされているわけだから、愚痴を零したくなるのも頷ける。彼の勤める警備という仕事について、悦子の知らないことはまだまだたくさんありそうだ。
「あの、いつからここにいるんですか」
もう少し話していたくて悦子は新たに話を振ってみる。
「三年前ですかね」
「あ、ごめんなさい。今の流れだとそうなりますよね。じゃなくて、時間のほう。お昼にはもういたでしょう」
本来なら遅番の悦子だって帰っている時間だ。彼の勤務時間がさっきから気になっていた。
崎本は、ああ、と小さく笑い、八時だと答えた。
「八時って、そんな、いったい何時間働いてるんですか」
「朝八時から翌朝八時の当直勤務なんです。もちろん仮眠時間もあります」
「そ、そうなんですね」
「明日は明け休みですし、それなりに休む時間は確保できていますよ」
それにしたってしんどそうだ。自分にはとても務まりそうにない。
「もっとも、今日は寝させてもらえないでしょうが」
今晩は寝ずに誤作動した設備の対応をするのだろう。大変ですねと月並みなことしか言えないのを悦子は歯痒く思った。
あれ、ここってこんなふうだっけ。悦子は次第に、辻褄の合わない夢の中を歩いているような気分になる。
普段通り従業員出口を目指して歩いているはずなのに、違和感がある。いつの間にか現れていた壁のせいだ。防火扉や防火シャッターのために景色が変わって見えていた。
「おっと、ここは通れませんね。じゃ、あっちから出ましょう」
彼が道を変えたのは、扉の前にものが散乱して開けられそうもなかったからだ。周りに置かれていたダンボール箱や備品の類が防火扉の動きで散らかったらしい。どかすのは容易ではないし下手に手を出せば怪我をしそうだ。似たようなところはほかにもあって、防火扉の周りだけまるで別の災害が起きたような惨状だ。
営業時間に一般客が使うエレベーターやエスカレーター、階段周辺はシャッターが下りてしまって使えない。崎本の向かう先は非常口のようだ。悦子は使ったことがないがあそこから下階に出られるのだろう。
「だめになった商品とかたくさんありそうですけど、どうなるんでしょう、その、責任とか」
破れたダンボールから飛び出して歪んでしまった幼児向け玩具を見て不憫に思う。クイーンルピナスとしてもバックヤードに置いたものはどうなっているかわからない。例の倉庫は使い勝手が相当に悪かったのか、クイーンルピナスの前の店の時点で使われなくなったと聞いている。鍵束だけそのまま引き継いで、悦子もゆりも、おそらく店長の西尾も入ったことすらない。それで従業員通用口の壁際に、よその店舗と同じように商品を詰めたダンボール箱を積んである。あの付近に防火扉やシャッターがあったかどうかなど、意識したことがないのでわからない。
「ものを置くなと書いてありますからね。それでも置いていた店側の落ち度ですよ」
けろりと、いっそ冷たく言い放つ崎本に悦子はほっとしてしまう。彼や警備の人たちが頭を下げて各店に謝るところを想像したからだ。
その想像はじきに、及ばなくてもいいところまで及んでしまう。
――なんでこんなんなってんの。
――前にも言ったよね。メモしてたよね。
――社会人何年やってんの。
不意に悦子を襲う、叱責の数々。一度蘇ると次から次へと芋が連なるように出てきては悦子を苛み苦しめる。
――余計な仕事増やさないでよ。
――こんなのちょっと考えたらわかることでしょ。
――目見えてるんでしょ、なんですぐ気づけないの。
黒い土に手を突っ込んでわざわざ掘り起こしているのは自分だとわかっているのに、止まらなくなる。頭を下げて、すみません、本当にすみませんと謝っているのは悦子のほうだ。
鍵を、探さないと。
悦子は再びその思いに囚われる。鍵がないままでは帰れない。また叱られてしまう。今度こそ本当に呆れられてしまう。
ガシャン、ガラガラと何かが崩れるような音がした。その音で悦子の意識は引き戻された。
今度は防火扉や何かしらの設備の音ではない、明らかにものが崩れてひどいことになったような音だった。
二人が向かっていた非常口の通路が音の発生源で、その正体は椅子だった。催事用のプラスチックのガーデンチェアが元は堆く積まれていたのだろう。それらが通路を塞ぐように雪崩を起こしてしまっていた。その数は十や二十ではない、軽く二百脚は超えていた。
「だからここに置くなって言ってるのに」
崎本の独り言が今の悦子にはまるで自分に向けられたように思えてしまう。思わずすみませんと口をついて出そうになる。深みに嵌る思考をなんとか振り切り、悦子は手近な椅子を起こした。
「私も手伝います」
「助かります」
椅子を重ねる崎本に倣って悦子も手を動かす。椅子の数こそ多いが、先ほどの防火扉の前ほど悲惨ではない。椅子しかないぶん、かえってやることが単純なのは幸いだった。
「まるでここを出るのを拒むかのように、狙いすましたように崩れましたね」
崎本の言葉に、悦子は思わず手を止める。
「……また、お化けの冗談ですか」
「怪異というのは人の気持ちに敏感なんだとか」
まただ。また、彼は悦子の目をまっすぐ見つめて言う。何もかも見透かすような瞳に射止められ悦子は落ち着かなくなる。いや、落ち着かない心地でいるのは今に始まったことではない。
「もしかして」
崎本は悦子の耳元に口を寄せて言う。誰も聞いていないのに、内緒話をするように潜めた声でその先を続ける。
「帰りたくないんじゃありませんか」
言い当てられて、悦子は後ずさる。その拍子に近くの椅子が倒れた。シチュエーションが違えばロマンチックなセリフにもなったであろうその言葉が、悦子には重い塊となってのしかかる。
「明日を迎えるのが怖い。帰宅して眠れば否応なく朝が来る。だから、帰るのが嫌なのではないですか」
「どうして」
どうして、そんなにも私の気持ちがわかるのだろう。悦子が抱いたのは情けなさと、羞恥だった。
明日を迎えるのが怖い。彼の言う通りだ。家に帰らずとも明日は来る、そう理解していてもなお、帰りたくない。このまま帰って、明日のことを考えながら眠りにつくのが辛い。出勤して叱られる想像をしながら過ごす、翌朝までの時間が毎日、毎晩、辛くてたまらない。
こんな、子どもみたいな理由で怯える情けない姿を、会って間もない目の前の男に暴かれてしまうなんて。
「なんで、わかるんですか」
「似た思いを、かつて抱えていたことがあります」
彼は悦子から離れて、悦子が倒した椅子を戻しながら続ける。
「当直勤務は一日の勤務時間が長いぶん、月の出勤回数は減るんです。それで自覚しました。ここに移る前はずっと、朝の出勤に大きな負担を感じていたのだと」
飄々と、難なく物事をこなしているように見える彼も、悦子の知らないところでは苦しんできたのだろうか。
自分以外の人は皆、何もかも平気に毎日を過ごしている。そんな思いが悦子にはあって、たまに見かけるだけの関わりのない警備員など、その最たるものだった。無機質で完全なものと思い込んでいた。冗談を言ったり愚痴を零したり、弱みがあったりするなんて思いもしなかった。
「ふとしたときに思いつめた顔をするのが気になっていました。椅子が崩れる直前も、そうでしたよね」
気づかれていたのか。彼が特別敏いのか、悦子が思っている以上に周りに伝わってしまうものなのか、どちらにしても恥ずかしかった。
「一番最初のきっかけで言うなら、昼のことが気にかかっていました」
「昼って……あ、鍵を借りに来たんでしたね」
彼が来たときにちょうど、悦子は店長の西尾に前日の閉店作業について注意されていたのだ。
「こう言ってはなんですが、謝り方が異常だと思ったんです。店長さんも引くほどだった」
あのとき、悦子は何か取り返しのつかない過ちを犯したかのように必死に謝っていた。西尾としては、やり忘れがあったよ、気をつけてねという程度のつもりで声をかけたにすぎず、悦子の謝罪に驚いて言葉も出なくなっていた。
悦子がそれほどまでに必死だったのは、頭の中ですでに散々叱られていたからだ。そのミスは前の日の夜、布団に入ったころに気がついて、汗が噴き出すほど猛省した。そこから出勤するまで、悦子を責めるありとあらゆる言葉が妄想で作り上げられ、それらに対して謝り続けていた。実際に西尾に言われた言葉と悦子が創出した言葉は綯い交ぜになって、もはや何を言われて何を言われていないのか覚束ない。
「前の職場で、上司に毎日すごく怒られていたんです。周りの人はあんなのパワハラだ、真に受けなくていいってフォローしてくれてたんですけど、言われる内容は間違っていない気がして。そうやって受け止めているうちに、限界を超えてしまったんですね、きっと」
何をするにも叱られる理由を探し尽くす癖は、ここから始まった。今、悦子を叱る声は前の上司だったり西尾だったり、名前も知らないお客だったりする。
「ここに転職してからは、前みたいに怒鳴られることはなくなりました。意地悪な言い方をする人もいないし、皆優しいし。……でも、頭の中ではずっと怒られているんです」
脳内に響く声は悦子の行動を何一つ許さない。何をしても、何をしなくても、どんな選択をしても間違っているような気がして身動きが取れなくなる。どうすればいいのかわからなくなる。
「鍵を、見つけなきゃと思って。店長がそんなにきつい言葉を言うはずがないって、わかってはいるんですけど、それでも、ここで帰ってしまうのが怖いんです。怒られて、謝って、そんなことを頭の中でずっと繰り返してしまうんです」
小さな注意こそあれ、悦子が西尾に叱られたことは実際には一度もない。想像の中で厳しく言われ続けて、勝手に苦手意識を持っているだけだ。そのせいで悦子は帰るに帰れなくなっているのだった。
「おかしいですよね、こんなの。いつもいつも、自分で自分を苦しめてる」
「おかしくなんかないですよ。人の心がトラウマの再現をするのは自然なことです」
「そうでしょうか」
「心を回復するために必要なことだと聞きます。どんなに冷たい水も触っているうちにぬるくなってくるし慣れてもきます。心もそうやって、嫌な記憶が適度なぬるさになるまで何度も何度も出し入れしているんです」
メンタルヘルスの先生の受け売りですが、と崎本は優しく言った。彼もまた、冷たい水が温まるのを待っていた時期があるのかもしれない。それはもう触れられる温度になったのだろうか。自分にもそのときは来るのだろうか。
「鍵は、見つかり次第すぐに届けます。清掃さんにも連絡しておきますよ」
「すみません。ありがとうございます」
「ところでその鍵のことですが、気になることがあるんです」
待っててくださいと崎本はガラケーを出して電話をかけ始める。やはり相手は警備室のようで、現状の報告に加えて悦子が探している鍵の話を持ち出した。はっきりした答えが得られないまま通話が終わったらしいことを話しぶりから察する。
「気になることって何ですか」
「まだ確定していないので、なんとも。今、調べてもらっていますが」
崎本の返答は歯切れが悪いが、半端な状態では言えないということなのだろうと悦子は納得した顔をしてみせる。
「鍵については一旦置いておきましょう。何にしても、ここをどうにかしないと」
二人は椅子の片づけを再開した。悦子が五つまで重ねたものを崎本が壁際に運んで、ほかのと合わせて十脚のまとまりにする。慣れてきて作業が段々スムーズになっていく。
「本来こんなところに置いてはいけないので、せっかく重ねてもじきに解体してしまうかもしれません」
「そう考えると虚しくなりますね。何でしたっけ、石を積む……」
「ああ、賽の河原ですね。子どもの霊が石の塔を作ろうとするのに、鬼がやってきては崩してしまうから永遠に完成できないという」
「賽の河原、か」
悦子は、自分がその霊であるように思えた。何にもならない悪い想像ばかりを積み上げながら、鬼が来るのを恐れている。塔は完成しない。完成図などまったく見えない。ただただ、積んでは崩し、積んでは崩しを繰り返している。
「おや」
椅子に貼りついていた何かが落ちた。崎本が拾い、悦子も覗き込んだ。渡邊がいる茶葉の店のレシートだった。長い間椅子に挟まっていたのだろう、紙はかさかさに乾いて光沢を失い、文字もすっかり薄くなっている。
「そうだ、賽の河原の話には地蔵菩薩が出てくるんですよ。石積みを続ける子どもたちの前に現れて、彼らを救済するんだそうです」
お地蔵様の話は知らなかった。子どもの霊も永遠に苦行を続けるわけではない、いつかは救われるのだ。悦子はふと思った。彼は、悦子が賽の河原と自分の状況を重ねたことに気づいたのかもしれない。それで教えてくれたのだ。彼の気遣いが好ましかった。
「ここの店主、お地蔵さんのような顔してるんですよね」
「あっ、渡邊さんでしょう、やっぱり似てますよね」
ひそかに似ていると思っていたのが自分だけではないと知り悦子は嬉しくなる。
「びっくりするほどそのまんまですもんね。拝めば何かご利益がありそうだ」
そう言って崎本は恭しく手を合わせる。可笑しくて笑うと、釣られて崎本も笑った。
片づけのキリがついたところで崎本のガラケーが鳴った。彼が出ると、大きな声が「サキちゃん、わかったよ」と言うのが漏れ聞こえた。
「――じゃあ、元からないわけですね」
崎本が話すのを聞くうちに、悦子はまさかと思う。まさか、まさかそんなことって。
「お察しの通りです」
通話を終えた崎本が、悦子に向き直って言った。
「今日は、業者と一緒に館内を回って、設備の点検と空気の測定をしていたんです」
そういえば彼が鍵束を借りに来たのはそういう用事だったと思い出す。
「そのときに業者の人から聞いたんです。昔、ある扉の鍵穴があまりにも固くて、鍵を折ってしまったことがあると」
「それが、あの倉庫の鍵だったんですね」
「はい。業者の人は、管理会社に弁償したと話していました。だからてっきり鍵は買い直したものだと思っていました」
しかし実際にはそうではなかった。クイーンルピナスの前に入っていた店は鍵穴の固い倉庫は使えないと放置し、管理会社も使われていない倉庫の鍵をわざわざ買うことはしなかった。まだ一本あるからとそのままにしていたのだ。その状態で前の店が撤退し、クイーンルピナスが鍵束ごと継いだ――
それが、予備の鍵束に倉庫の鍵がなかった理由である。
悦子が手に取るずっと以前から、鍵はなかった。悦子は存在しない鍵を探し続けていたのだ。
「申し訳ありません。もっと早くに調べていれば、こんな時間まで残ることはなかった」
崎本が深く頭を下げる。悦子も慌てて謝り返す。
「私のほうこそごめんなさい。最初に鍵の本数を確認していたら。一本足りないことに気づいていたら。店長に確認できていたら、落としただなんて大騒ぎすることもなかったのに。本当にすみません」
「あなたが謝ることはありませんよ。鍵を揃えておかなかった管理会社のせいです。そう、全部ずさんな管理会社が悪いんです。設備がおかしくなってこんな目に遭っているのも――こっちはもしかしたら、人ならざる者の仕業かもしれませんが」
「……実は結構オカルト好きです?」
悦子はすかさずつっこみを入れる。これもまた彼の気遣いだと思えて心が温かくなるのを感じた。悦子が自責しすぎないよう話の方向をころころと転がしてくれているように思えたのだ。
「いわくのある物件なのを知ってここを職場に選んだほどですからね」
「それはさすがに冗談ですよね」
「さあ、どうでしょう」
崎本と軽口を叩いていると体の力が一気に抜けた。心の強張りがどこかへ行ってしまったようだ。椅子を積んだ後でなかったら座ってしまいたかった。
「でもよかった。鍵、なくしたんじゃなくて本当によかったです。ありがとうございます」
「さっそく地蔵パワーを発揮してくれましたね」
崎本があのレシートを出して合掌する。渡邊のお地蔵様のような顔が浮かんだ。
しかし悦子には渡邊よりも、目の前の彼こそが、自分を救うために垂迹した存在であるような気がした。鍵の顛末を抜きにしても、彼の言葉や心配りに大いに救われた心地だった。今後いつ賽の河原に迷い込んでしまっても、この夜の出来事が心を癒してくれる、救ってくれる。そう思うと気持ちが楽になった。
「外に出る前に一つだけ、わがままを言ってもいいですか」
悦子はふと思いつき、そう言ってみる。
「もちろん」
二人がやってきたのは三階のフードコートだった。フロアの照明はすべて落とされているので、崎本の懐中電灯だけが光源だった。
「お仕事中なのに、付き合ってもらってすみません」
「構いませんよ。ちょうど喉も渇いていましたし」
電車はすでになくなっていて、出勤までは近くのネットカフェで時間を潰すつもりでいる。その前にここへ寄ったのは、無性にお茶が飲みたくなったからだった。
崎本は水を、悦子はお湯を飲んでいる。茶葉はないので当然何の味もしない。それでも悦子はお湯の中にお茶の味を探しながら、じっくりと飲んでいた。
「警備室ではサキちゃんと呼ばれているんですね」
「聞こえていたんですか。似合わないと言ったんですが、定着してしまいました」
はにかむ崎本がかわいかった。渡邊がいたらすぐにサキちゃんと呼び始めただろう。
ここでお茶を飲む時間が悦子は好きだ。初めて渡邊に誘われたときには、休憩中とはいえここに勤める人間が使ってもいいものか、渡邊は平気で茶葉を持ち込むしお湯も使うし、いつか誰かに注意されるのではないかと気が気でなかった。西尾の姿が見えたときには叱られるのを覚悟したものだった。
しかし渡邊が「まーちゃん、こっちこっち」と西尾までも無邪気に呼び、三人で同じテーブルを囲んだことで、この場所は安全地帯になった。西尾も渡邊のお茶のファンだった。ここで渡邊とお茶を飲むことについては、悦子の中の誰も咎めない。それで安心してお茶が飲めるのだった。
そんな場所で、彼とお茶が飲みたいと思った。
不思議だなと悦子は思う。叱られると思って身構えても叱られるどころか一緒にお茶を飲むことになる。無機質だと思っていた警備員が実はよく冗談を言ったりオカルト好きだったり、優しく気遣ってくれたりする。なくしたと思っていた鍵に至っては元々存在しなかった。悦子の考えることは当たらないどころか現実のほうが斜め上を行く。どんな想像をしてもその通りになることはほとんどないと、今さらながら気がついた。
気持ちが緩んで思わずあくびをすると、すかさず崎本が、
「始発で帰って、明日は一日休んでしまったらどうです」と言った。さすがにそれはできませんと悦子は笑う。
「それにやっぱり、お湯じゃなくて、渡邊さんのところのちゃんとしたお茶が飲みたくなっちゃいました。明日はそれを楽しみにして乗り切ります」
「そこまで言われると飲んでみたくなりますね」
「ぜひ一緒に飲みましょう、休憩時間が合うといいんですけど……」
「いや、明日は俺、明け休みですから。ここにはいませんよ」
「あ、そうでした」
つい前のめりになった自分が恥ずかしくなる。コップにほとんど残っていないお湯を飲もうと口をつけた。懐中電灯の光から顔を隠そうと、コップを長く持ち続ける。
でも、と崎本は少し間を空けてから言う。
「午後にふらっと客として来ることはできます」
悦子は嬉しくなる。こんなに心が弾んだのはいつぶりだろう。明日を楽しみに思える日が来るなんて思いもしなかった。
心の底から、明日を迎えるのが待ち遠しかった。