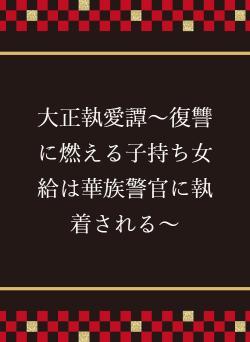しまった。
私はその顔を見て、なんだかバツが悪かった。
唇をかんで下を向いていると、いつの間にか傍に来ていた太助が私の手をつかんだ。
そして手をひいて歩き出した。太助は何も言わなかった。
心細かった。
太助に手をつないでもらった時に気がついた。
知らない場所で一人になって、置いていかれそうになるのが恐かったのだ。
今私は相当情けない顔をしているだろう。
太助は無言で、先ほどとは違い、少し遅めのペースで前へ進んでいった。無言でいてくれているのが有難かった。
どれくらい歩いたのだろうか、やがて生い茂っていた緑が徐々にその数を減らし始め、木々の間がぽっかりと開いている場所に着いた。
そこをくぐると、突然光が溢れた。
急にそれを浴びたので、反射的に手をかざし、眩しさをやり過ごす。
ようやく目が慣れてきた頃、手を下ろせば、眼前に大海原が広がっていた。
「どうや、すごいやろ」
胸を張って太助が言った。
「うん。すごい。びっくりした」
私は息をのんだ。
少し丘のようになっているここは、海を一望できるようになっていた。
水平線を境に、白い雲や、遠くの島々が浮かんでいて、それから潮の音が風に乗って聞えてくる。
深くて遠い蒼。
この島以外では、けして見ることの出来ない蒼が広がっている。
「父ちゃんと遊んでた時にここを見つけてん。たぶん展望台のなごりやろうって母ちゃんが言うてた」
ほらそこにベンチがあるやろと、太助は言葉を続けると、私たちはそこへ座った。
座ると疲れがどっと出てきた。よく歩けたなぁとぼんやりと思った。
「ここ、良いところね。連れてきてくれてありがとうね」
「ねえちゃんやから連れてきてんで。他の人にはまだ内緒やからな」
そう言って、にかっと笑った。
大きな口には歯がないところもあった。
「太助、学校楽しい?」
「おう、楽しいで。勉強はあんまり好きやないけど。友達おるしな。みんなで遊ぶの楽しいねん。ねえちゃんは?ねえちゃんは会社楽しいか?」
そう聞かれて、私は答えにつまった。
目を彷徨わせて、思わず大きな溜息をついた。
「……そうねぇ、あんまり楽しくないかな。いつの間にか心も体も疲れちゃって。だから、今、おばあの家にいるの」
「うん」
「今までね、一生懸命頑張ってきた。真面目に働いて、ねえちゃんが考えた商品がお店に並んだりしたわ。みんなの力でできたこと。とっても感謝してる」
「うん」
「私、いつも愛想よく笑っているの。よくドジも踏んで、でもそんなところが接しやすいってみんな言ってくれる。昔はもっとキツイって言われてたけどね。目なんかこんなに吊り上げて、いっつも怒ってた」
太助に向かって、自分の両目を指で吊り上げて見せると、太助は吹き出し、げらげら笑った。
「こんな目をしたままだと、みんなに好きになってもらえないから、優しい女の子になろうと思って、今の振舞いになっているんだろうなぁって思うのよ」
「……うん。ようわからへんけど」
「まぁ、聞いてよ。私ははみんなに好きになってもらいたかった。結果的に、好きになってもらってる。でもね、一番好きになってほしい人からは、好きになってもらえなかったの。私は好きで好きで、仕方がなかった。だからその人が近づきたくなるくらい、いい女になろうって頑張ってきたんだけど……なんだか、いっぱいいっぱい疲れちゃった……。」
私はそう言ってからしばらく黙った。太助も同じく黙り込んでいた。
私は子供相手に何話しているのだろう。
「……ごめん。退屈だよね」
「あ、ねえちゃん。とんびや」
蒼い空をバックに、とんびが飛んでいた。風をあやつり、勇壮で自由だった。
この自然は自分のものだと言わんばかりに、どこまでもどこまでも飛んでいった。
丘にも風は吹き、木々を揺らして優しい音を奏でていた。
「……ねえちゃん。おれ、ねえちゃんのこと好きやで。なんかな、いつも思いつかん遊びしてくれるし、優しくしてくれるし。それから他の大人と違って、子供扱いせえへんやろ。ねえちゃんといると楽しいねんで」
太助の言葉に私は顔をあげた。
「ねえちゃん、ここへ来てから悲しそうな顔しかしてなかったやん。おれ、心配やってん」
「うん……」
「ねえちゃんは、おれのこと好きか?」
「……うん。太助は真っ直ぐで、色んなこと教えてくれる。私にとって大事な人よ」
「なんや、照れるなぁ」
そう言って、太助は頭をぽりぽりとかいた。
「ねえちゃん……今もそいつのこと好きなん?」
「……嫌いにはなれないかな」
「……なんや、ようわからん」
「うーん、ちょっと難しいかもしれないけど、一度好きになったものは、嫌いにはもうなれないのよ。人間ってそういう風に出来ていると思うの」
「やっぱりわからん。おれ思うんやけど、ねえちゃん、そいつから離れたがってると思うねん。離れてもええんやで、きっと」
「え……」
「何で離れたらあかんの?」
「何でって……」
「ねえちゃんは、ねえちゃんやのに」
どうしてこの子は、こんなことを言えるのだろう。
目頭が熱くなった。
「……だって、恐いのよ。ひとりぼっちになってしまう気がして。それに傷ついて怯えている私に気づくのが嫌だった。どうしても受け入れられなかった。離れたら、その人から好きになってもらえる可能性を全部捨ててしまう気がして……恐かった」
「ねえちゃん、恐かったんかぁ。おれも恐い時いっぱいあるで。母ちゃんに怒られるときとか、お化け屋敷に入る時とかな。ほんまにぞーっとすんねん。泣きたくないのに泣いてしまうねん」
私は思わず笑ってしまった。