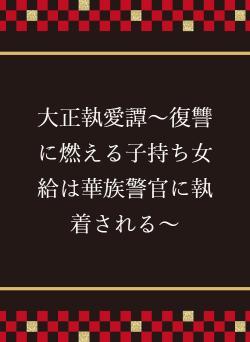その夜、久々に同僚からSNSでメッセージが入った。
内容は「元気?」から始まり、嫌いな先輩のこと、けんかしている彼氏のことについて書かれていた。
相変わらずだなと思っていると、最後の一文に、高坂さんが心配していたよと一言あった。
高坂さんは会社の上司にあたる。
私が好きだった人、そして失恋した人。
私より八つ年上で、だけど無邪気な少年の瞳を持っている人だ。
いつも気遣ってくれて、私はいつも甘えていた。奥さんがいることを知ってはいたが、否応なく、惹かれた。
私は性格上、あまり人を好きにならない。だから自分を止めることなど出来なかった。
久しぶりに人を好きになり、相手のことなんておかまいなしで、気持ちだけが先へ行って。
それから、失恋したのだ。
休職した原因の一つだと、一応は認識している。
一変に色んなことがふりかかったのだと私は思っている。
私は縁側に出て、夜空を見上げてみた。
都会の空とは違い、いつか落ちてくるんじゃないかと思ってしまうほど、まばゆい光が一面に瞬いていた。
しばらく雨の日が続いていた。
今日は結構な大降りで、祖母と二人、何をするでもなく過ごしていた。
庭の花たちに水を与える必要はなく、なんとなく縁側で雨に打たれている花たちを見ていた。
葉から葉へ落ちる雫をみていると、みんなでバケツリレーをしているように見える。
「ここの生活は慣れた?」
居間で、テレビを見ていた祖母が私に声をかけた。
「うん」
「そう」
祖母は、祖父に先立たれてから、一人でこの家に住んでいる。
私が幼い時に亡くなったため、私は祖父の顔がわからない。
祖母は南国特有の浅黒い肌をしていた。花柄の、少し派手なブラウスと布の動きやすいズボンを好んで着る。
祖母は太陽の匂いのする人だと、私は昔から思っている。
「……ねえ、おばあ。私ってどんな子に見える? 会社の人に言われる私と、学生時代の友人に言われる私では、イメージが違うみたいだから」
「昔と今が違うってことよねぇ」
「うん」
祖母が私の話を聞きたそうにしていたので、私はそれについて話してみた。
学生時代、私はかなりの行動派で、自分が決めたことは突き通さないと納得できなかったので、すぐに怒るし気が短かった。
キツイ女だとみんなは笑って言った。それから、意志の強さは並々ならぬものがあったと言う。
一方、現在会社を中心に過ごしていた私は、愛想のいい、気の優しい人だと思われ、キツイ女なんて言われたことがなかった。
ただ、私は優柔不断になり、自分の意志が分からなくなってしまっているように感じるのだ。
私は疑問に思っている。
今の私になって良かったのかと。
「そうねぇ。若いときはたくさん悩むもんよねぇ。今のあなたは、昔、あなたがなりたいと願った姿なのかもしれないわねぇ。あなたは手に入れた。それはすごいことよ、努力をちゃんとしたから。でも、自然が一番よねぇ」
雨は、私の思考を中断させる。
昔からそうだ。ただ祖母の言葉が流れてくる。
「世の中に飲み込まれそうになる。世の中は広いからねぇ。でも大丈夫。あなたが自然にしていれば。大丈夫さぁ……」
祖母はいつの間にか、私の隣に座って、そっと手を握ってくれた。
しわくちゃの骨ばった手。温かい手。
辺りは雨の音だけに支配されていて、しばらく二人で佇んでいた。
雨が上がった次の日、学校が休みだと言っていた太助がやってきた。
今日はどうやら秘密の場所へ連れて行ってくれるらしい。
私はデニムのパンツを穿き、上着を羽織って、動きやすい格好で外へ出た。
今日はいい天気だ。やさしく風が吹いていた。
太助は久々の快晴にはしゃぎ、早く早くと私を急かした。
そこへは歩いて行けるらしかった。太助は海と反対の方向に、つまり山側へと足を向けた。
まず、山の入り口に着くと、猟をする人や、山菜なんかを取りに行く人しか使わないような獣道の方へ、彼は進んでいった。
土は、ここを使用する人間が踏みしめ続けていたことがわかるように、固まっていて、自然の道が出来上がっていたが、周りを覆う、木々や雑草がすごかった。
都会ではけして見ることが出来ないくらい、頑丈で丈夫な葉が生い茂っていて、もちろん色んな虫も飛んでいた。
時折、刺されたんじゃないかと思う感触があったりする。
しかし、雨の後だからといって、じめじめしている訳じゃない。昔から感じているこの島の不思議だ。
先頭に立って歩いている太助は、そんな山の自然をものともせず、頭上を覆っている、歩くのに邪魔な木の枝や、下から生えている雑草を、手にしている木の枝でなぎ払っていた。
子供は元気だ。体をいっぱいに使って歩いている。その姿はとてもエネルギッシュだ。
私は会社と家との往復で、普段歩く事が少なかったため、この道は結構堪える。
前にいる太助はずんずん山道を歩いてゆく。
自分の行きたい場所へ向かって、ただひたすら向かっていく。
私は小さな太助になかなか追いつく事ができず、どんどん離されていった。
頑張ってついて行こうとしているのだが、息が上がって、もう苦しかった。
木々に覆われた山道、日中なのに光は半分程度しかない。
聞えてくるのは自分の弾む息と、遠くから聞える鳥の鳴き声だけだった。
私はそれに気がつくと、とたんに背筋からぞわぞわっとした感覚に支配された。
それはひやっとした冷たい感覚。
「太助!」
私は幼い背中へ向かって叫んでいた。
いてもたってもいられなかった。
太助はびっくりした顔でこちらを振り向いていた。
内容は「元気?」から始まり、嫌いな先輩のこと、けんかしている彼氏のことについて書かれていた。
相変わらずだなと思っていると、最後の一文に、高坂さんが心配していたよと一言あった。
高坂さんは会社の上司にあたる。
私が好きだった人、そして失恋した人。
私より八つ年上で、だけど無邪気な少年の瞳を持っている人だ。
いつも気遣ってくれて、私はいつも甘えていた。奥さんがいることを知ってはいたが、否応なく、惹かれた。
私は性格上、あまり人を好きにならない。だから自分を止めることなど出来なかった。
久しぶりに人を好きになり、相手のことなんておかまいなしで、気持ちだけが先へ行って。
それから、失恋したのだ。
休職した原因の一つだと、一応は認識している。
一変に色んなことがふりかかったのだと私は思っている。
私は縁側に出て、夜空を見上げてみた。
都会の空とは違い、いつか落ちてくるんじゃないかと思ってしまうほど、まばゆい光が一面に瞬いていた。
しばらく雨の日が続いていた。
今日は結構な大降りで、祖母と二人、何をするでもなく過ごしていた。
庭の花たちに水を与える必要はなく、なんとなく縁側で雨に打たれている花たちを見ていた。
葉から葉へ落ちる雫をみていると、みんなでバケツリレーをしているように見える。
「ここの生活は慣れた?」
居間で、テレビを見ていた祖母が私に声をかけた。
「うん」
「そう」
祖母は、祖父に先立たれてから、一人でこの家に住んでいる。
私が幼い時に亡くなったため、私は祖父の顔がわからない。
祖母は南国特有の浅黒い肌をしていた。花柄の、少し派手なブラウスと布の動きやすいズボンを好んで着る。
祖母は太陽の匂いのする人だと、私は昔から思っている。
「……ねえ、おばあ。私ってどんな子に見える? 会社の人に言われる私と、学生時代の友人に言われる私では、イメージが違うみたいだから」
「昔と今が違うってことよねぇ」
「うん」
祖母が私の話を聞きたそうにしていたので、私はそれについて話してみた。
学生時代、私はかなりの行動派で、自分が決めたことは突き通さないと納得できなかったので、すぐに怒るし気が短かった。
キツイ女だとみんなは笑って言った。それから、意志の強さは並々ならぬものがあったと言う。
一方、現在会社を中心に過ごしていた私は、愛想のいい、気の優しい人だと思われ、キツイ女なんて言われたことがなかった。
ただ、私は優柔不断になり、自分の意志が分からなくなってしまっているように感じるのだ。
私は疑問に思っている。
今の私になって良かったのかと。
「そうねぇ。若いときはたくさん悩むもんよねぇ。今のあなたは、昔、あなたがなりたいと願った姿なのかもしれないわねぇ。あなたは手に入れた。それはすごいことよ、努力をちゃんとしたから。でも、自然が一番よねぇ」
雨は、私の思考を中断させる。
昔からそうだ。ただ祖母の言葉が流れてくる。
「世の中に飲み込まれそうになる。世の中は広いからねぇ。でも大丈夫。あなたが自然にしていれば。大丈夫さぁ……」
祖母はいつの間にか、私の隣に座って、そっと手を握ってくれた。
しわくちゃの骨ばった手。温かい手。
辺りは雨の音だけに支配されていて、しばらく二人で佇んでいた。
雨が上がった次の日、学校が休みだと言っていた太助がやってきた。
今日はどうやら秘密の場所へ連れて行ってくれるらしい。
私はデニムのパンツを穿き、上着を羽織って、動きやすい格好で外へ出た。
今日はいい天気だ。やさしく風が吹いていた。
太助は久々の快晴にはしゃぎ、早く早くと私を急かした。
そこへは歩いて行けるらしかった。太助は海と反対の方向に、つまり山側へと足を向けた。
まず、山の入り口に着くと、猟をする人や、山菜なんかを取りに行く人しか使わないような獣道の方へ、彼は進んでいった。
土は、ここを使用する人間が踏みしめ続けていたことがわかるように、固まっていて、自然の道が出来上がっていたが、周りを覆う、木々や雑草がすごかった。
都会ではけして見ることが出来ないくらい、頑丈で丈夫な葉が生い茂っていて、もちろん色んな虫も飛んでいた。
時折、刺されたんじゃないかと思う感触があったりする。
しかし、雨の後だからといって、じめじめしている訳じゃない。昔から感じているこの島の不思議だ。
先頭に立って歩いている太助は、そんな山の自然をものともせず、頭上を覆っている、歩くのに邪魔な木の枝や、下から生えている雑草を、手にしている木の枝でなぎ払っていた。
子供は元気だ。体をいっぱいに使って歩いている。その姿はとてもエネルギッシュだ。
私は会社と家との往復で、普段歩く事が少なかったため、この道は結構堪える。
前にいる太助はずんずん山道を歩いてゆく。
自分の行きたい場所へ向かって、ただひたすら向かっていく。
私は小さな太助になかなか追いつく事ができず、どんどん離されていった。
頑張ってついて行こうとしているのだが、息が上がって、もう苦しかった。
木々に覆われた山道、日中なのに光は半分程度しかない。
聞えてくるのは自分の弾む息と、遠くから聞える鳥の鳴き声だけだった。
私はそれに気がつくと、とたんに背筋からぞわぞわっとした感覚に支配された。
それはひやっとした冷たい感覚。
「太助!」
私は幼い背中へ向かって叫んでいた。
いてもたってもいられなかった。
太助はびっくりした顔でこちらを振り向いていた。