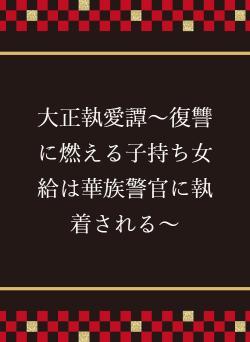私はこうでなければならないとか、自分の中にルールがあって。
いつの間にか、がんじがらめになっていたのかもしれない。
そのルールから外れそうになった時、無性に不安になって、焦って、焦って、恐れを肥大させてしまっていた。
私はただ幸せになりたかった。
私がこの島に降り立ったのは、なんと十年ぶりのことだった。
南国のおおらかな気が満ちた、海に囲まれた島。日本の南西に位置し、熱帯の美しい花々と、吸い込まれそうな空と、宝物のような深遠の海が広がる。
訪れる者をけっして拒むことのない優しい島。
私は島の空港から、バスに揺られて二時間、海沿いに走っている国道の、少し奥に入った場所にある祖母の家を訪ねに来た。
国道沿いのバス停に降り立った私は、ここから見える祖母の家を眺めた。
潮の匂いと、庭に咲き誇る美しい花々が懐かしく、昔と変わらない佇まいが私をほっとさせた。
すぐにそこに行くのがなんとなく躊躇われ、バス停に設置してあるベンチに座った。
持っていたボストンバックから、一本タバコを取り出し火をつけた。私は健康に気を使い、一ミリのタール(少し女性を意識したそれ)を好む。
私はゆっくりと吸い、肺に送り込んだ。
メンソールの冷ややかな感触と、脳内を犯す煙を味わいながら、細く吐き出す。
白い煙はゆっくりと空へのぼり、傾きかけている太陽の下に消えていった。
暦の上では既に十月であったが、この島は空気がからっとしていて気温は高かった。
しばらくベンチに腰を預け、ちりちりと燃えるタバコを吸いながら、潮の音に耳を傾けていた。
「ねえちゃん、なんやひさしぶりやなぁ」
この島では聞きなれない土地の言葉が耳に入った。
祖母の家に着くやいないや、祖母からの手厚い、そして照れくさい歓待を受けた。
電話で祖母と話してはいたが、久々に会った祖母は少し痩せたように思う。
しばらく祖母と談笑していると、縁側の方から大きな声が聞えてきた。
丸坊主の背の低い、肌が日に焼けて黒く、やんちゃな顔の少年がそこにいた。
今年で小学三年生になるいとこの太助だった。歳の離れたいとこ。
伯父さんの仕事の都合で、太助は二年前にこの島へ引っ越してきた。家は、祖母の家からバスで二駅先に行った所にある。
それまではよく遊んであげていた。
子供だからすぐに土地の言葉はなくなるだろうと思っていたが、一向に消える気配はなかった。
彼曰く、この方がモテるからだそうだ。
「太助、学校は?」
「今日からねえちゃん来るって聞いたから、早く切り上げてきたんや。今日はおれが手厚くもてなしてやるからな。後でかあちゃんも来るって言うとったで。今日はご馳走やで、ねえちゃん」
「そっか。ありがとう」
この島の人は、何もかもが優しい。
デニムのパンツに長袖のニットというラフな格好は、本当に久しぶりだと思う。
社会人になってからの殆どをスーツで過ごしていた感覚がある。
普段は、一応大きな会社で企画の仕事に就いている。
毎日がまさに戦争という言葉がぴったりなほど忙しく、気が張り詰める。一人でいくつもの業務を抱え、仕事に塗れていた。
疲れた。
そう認識できたのは、二週間前に会社で倒れたことがきっかけだった。
それからしばらく病院にも通ったが、何も改善は見られなかった。
休職を願い出て、一月だけ了承してもらい、この地へやってきた。
人の手があまり入っていない、自然だらけのこの土地。テレビのチャンネルは限られていて、買物をする場所さえ遠ざけられているこの土地が、私は急に恋しくなった。
ここでの暮らしは、毎日が単調だった。
陽が昇ると起き出して、陽が沈むと仕事をやめて夕飯になる。午後八時も回ると、みんな寝静まってしまう。
規則正しい生活。
私は毎日、庭の花に水を遣って、お風呂掃除をする。たまに祖母の畑仕事を手伝う。
ただ時折やってくる太助が祖母の家にやってくると、とたんに辺りが騒々しくなる。まさに台風だった。
祖母がこの島で暮らし始めた私に、唯一守らせていることは、太助が来たときは太助と一緒に遊ぶことだった。
それ以外はとやかく言わなかった。
夕方、遊びに来た太助と一緒に、家の近くの海に来ていた。
太助は地面に蹲り、必死にヤドカリや虫を探していて、私はテトラポットに腰かけて、タバコを燻らせていた。
「ねえちゃん、好きな人おるんか?」
「は?」
私は突拍子もない太助の言葉に驚かされた。
びっくりしてタバコを落としかけた。ここでのタバコは貴重だ。
なぜなら買いに行く店自体が、ここから遠いからだ。
「おれはおんねん。二組のクミコと、同じクラスのさえ。でもこの間、二組のしおりに告られてん。おれ、断ったんやけどな」
ふふんと、少し誇らしげで、ちょっと困ったような顔で太助は言った。
ませている。それが私の正直な感想だ。
手足を泥だらけにして、顔にまで土をつけて、精一杯遊んでいる子が、この歳になるとませてくるのか。
しかし同時に、こんな小さい子でも「切なさ」というものを感じているんだと、妙に感心させられた。
太助は、照れくさかったのか、恥ずかしかったのか、その話はそれで終わりにしてしまい、学校での話をしてくれた。
今度ある注射がどうしても嫌だという話や、難しい算数のドリルをいかにして解いたかなど。
大人の私からすれば、ほんの些細な出来事に過ぎないのだが、太助にとっては全てが大事なことらしい。
そんな太助がうらやましく、自分の幼かった日々を懐かしく思った。
小さなことでも感動できる私は、どこへ行ってしまったんだろう。
いつの間にか、がんじがらめになっていたのかもしれない。
そのルールから外れそうになった時、無性に不安になって、焦って、焦って、恐れを肥大させてしまっていた。
私はただ幸せになりたかった。
私がこの島に降り立ったのは、なんと十年ぶりのことだった。
南国のおおらかな気が満ちた、海に囲まれた島。日本の南西に位置し、熱帯の美しい花々と、吸い込まれそうな空と、宝物のような深遠の海が広がる。
訪れる者をけっして拒むことのない優しい島。
私は島の空港から、バスに揺られて二時間、海沿いに走っている国道の、少し奥に入った場所にある祖母の家を訪ねに来た。
国道沿いのバス停に降り立った私は、ここから見える祖母の家を眺めた。
潮の匂いと、庭に咲き誇る美しい花々が懐かしく、昔と変わらない佇まいが私をほっとさせた。
すぐにそこに行くのがなんとなく躊躇われ、バス停に設置してあるベンチに座った。
持っていたボストンバックから、一本タバコを取り出し火をつけた。私は健康に気を使い、一ミリのタール(少し女性を意識したそれ)を好む。
私はゆっくりと吸い、肺に送り込んだ。
メンソールの冷ややかな感触と、脳内を犯す煙を味わいながら、細く吐き出す。
白い煙はゆっくりと空へのぼり、傾きかけている太陽の下に消えていった。
暦の上では既に十月であったが、この島は空気がからっとしていて気温は高かった。
しばらくベンチに腰を預け、ちりちりと燃えるタバコを吸いながら、潮の音に耳を傾けていた。
「ねえちゃん、なんやひさしぶりやなぁ」
この島では聞きなれない土地の言葉が耳に入った。
祖母の家に着くやいないや、祖母からの手厚い、そして照れくさい歓待を受けた。
電話で祖母と話してはいたが、久々に会った祖母は少し痩せたように思う。
しばらく祖母と談笑していると、縁側の方から大きな声が聞えてきた。
丸坊主の背の低い、肌が日に焼けて黒く、やんちゃな顔の少年がそこにいた。
今年で小学三年生になるいとこの太助だった。歳の離れたいとこ。
伯父さんの仕事の都合で、太助は二年前にこの島へ引っ越してきた。家は、祖母の家からバスで二駅先に行った所にある。
それまではよく遊んであげていた。
子供だからすぐに土地の言葉はなくなるだろうと思っていたが、一向に消える気配はなかった。
彼曰く、この方がモテるからだそうだ。
「太助、学校は?」
「今日からねえちゃん来るって聞いたから、早く切り上げてきたんや。今日はおれが手厚くもてなしてやるからな。後でかあちゃんも来るって言うとったで。今日はご馳走やで、ねえちゃん」
「そっか。ありがとう」
この島の人は、何もかもが優しい。
デニムのパンツに長袖のニットというラフな格好は、本当に久しぶりだと思う。
社会人になってからの殆どをスーツで過ごしていた感覚がある。
普段は、一応大きな会社で企画の仕事に就いている。
毎日がまさに戦争という言葉がぴったりなほど忙しく、気が張り詰める。一人でいくつもの業務を抱え、仕事に塗れていた。
疲れた。
そう認識できたのは、二週間前に会社で倒れたことがきっかけだった。
それからしばらく病院にも通ったが、何も改善は見られなかった。
休職を願い出て、一月だけ了承してもらい、この地へやってきた。
人の手があまり入っていない、自然だらけのこの土地。テレビのチャンネルは限られていて、買物をする場所さえ遠ざけられているこの土地が、私は急に恋しくなった。
ここでの暮らしは、毎日が単調だった。
陽が昇ると起き出して、陽が沈むと仕事をやめて夕飯になる。午後八時も回ると、みんな寝静まってしまう。
規則正しい生活。
私は毎日、庭の花に水を遣って、お風呂掃除をする。たまに祖母の畑仕事を手伝う。
ただ時折やってくる太助が祖母の家にやってくると、とたんに辺りが騒々しくなる。まさに台風だった。
祖母がこの島で暮らし始めた私に、唯一守らせていることは、太助が来たときは太助と一緒に遊ぶことだった。
それ以外はとやかく言わなかった。
夕方、遊びに来た太助と一緒に、家の近くの海に来ていた。
太助は地面に蹲り、必死にヤドカリや虫を探していて、私はテトラポットに腰かけて、タバコを燻らせていた。
「ねえちゃん、好きな人おるんか?」
「は?」
私は突拍子もない太助の言葉に驚かされた。
びっくりしてタバコを落としかけた。ここでのタバコは貴重だ。
なぜなら買いに行く店自体が、ここから遠いからだ。
「おれはおんねん。二組のクミコと、同じクラスのさえ。でもこの間、二組のしおりに告られてん。おれ、断ったんやけどな」
ふふんと、少し誇らしげで、ちょっと困ったような顔で太助は言った。
ませている。それが私の正直な感想だ。
手足を泥だらけにして、顔にまで土をつけて、精一杯遊んでいる子が、この歳になるとませてくるのか。
しかし同時に、こんな小さい子でも「切なさ」というものを感じているんだと、妙に感心させられた。
太助は、照れくさかったのか、恥ずかしかったのか、その話はそれで終わりにしてしまい、学校での話をしてくれた。
今度ある注射がどうしても嫌だという話や、難しい算数のドリルをいかにして解いたかなど。
大人の私からすれば、ほんの些細な出来事に過ぎないのだが、太助にとっては全てが大事なことらしい。
そんな太助がうらやましく、自分の幼かった日々を懐かしく思った。
小さなことでも感動できる私は、どこへ行ってしまったんだろう。