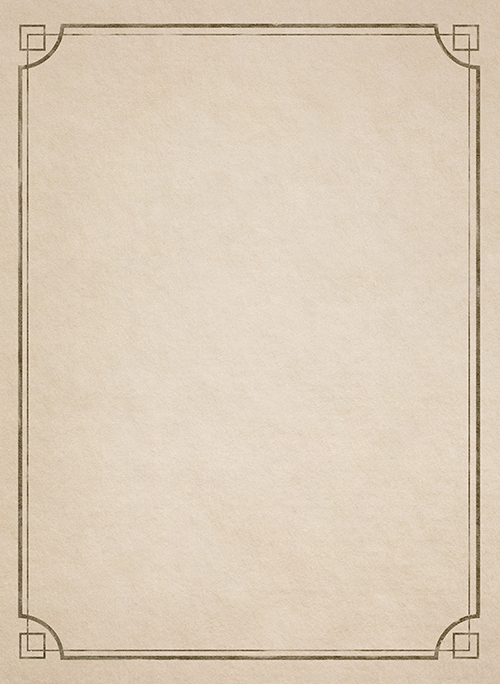――あの電車に乗れさえすれば、きっと私は家まで帰れたんだろう。
「……電車、行っちゃった。」
がらんとした駅のホームには、さっきまでたくさんの人がいた。
仕事帰りのサラリーマン、今をときめく若い子たち、ギリギリまで一緒にいたいカップル。
私はその中に混ざれず、行ってしまった電車の背中をぼんやり見つめていた。
行き場のなくなった切符1枚を握りしめて、ストンと無気力にホームのベンチに腰を下ろす。
どうしよう、これじゃ家に帰れない。タクシーでも拾って帰ろうか。
そう思って財布の中身を確認しようとするけど、持っていた小さい鞄にはおろかポケットにも財布本体がなかった。
……切符があるって事は、ホーム内のどこかにあるはず。
「あれ、誰だろ……。」
その時いきなり、隣に置いていたスマホが着信を知らせた。
反射的にスマホを手に取り見つめると、そこには《壱星》という名前が。
「壱星……って、本当に誰だっけ。」
ほぼ無意識に口から飛び出したのは、単純なのに難解な疑問。
それに、私は何でこの駅にいるんだっけ? ここに来るまで私は何をしてたんだっけ?
……思い出せない。
改めて思い返すと、そもそもこんなところで何をしてたんだという疑問が脳裏をよぎる。
けれど思い出そうとすると、頭の中が全て空っぽになっているような虚無感ばかりで少し気持ち悪くなってしまった。
「わたし、は……名前、なんだっけ……。」
自分の名前、それすらも今の私には分からない。脳ごとなくなってしまったのかと錯覚するほどに、私の手元には引き出せる情報が残っていなかった。
あの電車にさえ乗れていたら、違ったのだろうか。
……いや、そんな事ないか。乗ったら乗ったで変なところで降りそうだ、この頭のままじゃ家には帰れないだろうし。
どこか他人事のように考えながら、星が見えない夜空を視界いっぱいに映す。
私、これからどうしたらいいんだろう。秋の夜は冷えるから、とりあえずホームを出て財布を見つけてカプセルホテルにでも泊まるべきだろうか。
はぁ……と息を吐いて、《壱星》さんからの不在着信通知を眺める。スマホのパスワードも分からないから、電話はかけられない。
「壱星って、綺麗な名前……。」
言い換えれば一番星になるその名前に、なんだかじわっと心が温かくなる。この人は私にとってどんな人なんだろう……そんな興味も湧いてきた。
よくよく通知を遡ってみれば、壱星さんは何度も電話をかけてきていたらしい。スワイプする度に不在着信の文字が目に入る。
5、10、20……大体30件くらいか。それほど壱星さんという人は私を気にしてくれているのか。
首を傾げつつ、どうにもできない私はスマホをポケットに突っ込もうとした。
だけどそのポケットの中に、さっきは気が付かなった何かが入っていた。
これは……メモ用紙?
訝しみながら手に取った何かはくしゃくしゃの紙切れで、開くと丁寧な字でこう書いてある。
《また思い出せなくなったら、あの駅のロータリーで待っていて。きっと迎えに来てくれるから。大丈夫、あなたは一人じゃない。》
「……これ、誰が書いたんだろう。」
優しい字と言葉に、秋風で冷えた指先が熱を持つ。このメモは、壱星さんという人が持たせてくれたものなのかな。
でも“また”って事は、私はこれまでに何度も記憶を失くしている……?
確証はないけれど、何故かそう感じて突き動かされるようにベンチから立ち上がった。
そのままメモに書かれているロータリーまで歩いてみると、外はホームよりかは幾分か暗く街灯の淡い明かりだけが頼りになる。
ロータリーまで出たはいいもののこの後どうしていいか分からない私は、下手に動かないほうがいいと考えて駅の壁を背にしゃがんだ。
……迎えって、誰が来てくれるんだろう。白馬の王子様とか……なんて。
冷え込んできた空気のせいかふざけた事を思ってしまい、ぷっと一人吹き出す。
そもそも、迎えなんて来るのかな。
歩く人もまばらで閑散としているロータリーを見つめながら、きゅっと唇を引き結ぶ。
自分のことさえ分かっていない私からすれば、このメモも得体が知れない。自分で持っていたんだから疑う余地はないんだろうけど……。
……迎え、来てくれるんだったら早く来て。
「っ、見つけた……!」
必死な男性の声が近付いてきたのは、愚痴が口から零れる寸前の事だった。
突然の声に驚いて肩を跳ねさせた私に、声の主は駆け足でやってくる。
「良かった、ちゃんとここにいてくれたんだね。」
「……あの、あなたは?」
ちょっとだけ厚めのニットにロングスカートという私の格好を気にしたのか、彼はやってくるとすぐに自分のコートを脱いで私の肩にかけてきた。
垂れ目気味で大人しそうな印象を受ける彼の表情は、不安と心配に駆られているような影を落としている。
迎えって、この人の事かな……?
一目散に私の元に来てくれたんだから多分間違ってないだろうけど、今の私にとって彼は“知らない人”。
思わず尋ねると、彼は一瞬だけ目を見開いた後悲しそうに微笑んだ。
「俺のこと、分かんない?」
「……すみません。私、自分の名前も分からなくて……財布も、なくしちゃって……」
財布には身分証明となるものが入っていたかもしれない。そうしたら自分のことも分かって、多少なりとも記憶が戻ったかもしれない。
ゆっくり彼に向けて言葉にするとたらればばかりが浮かんできて、自分の情けなさにうっとえづく。
けれど彼は、こんな私に優しく声をかけてくれた。
「大丈夫だよ、ゆっくり深呼吸しよう。分からない事は俺が全部、また教えるから。」
「……っ、すー、はー……」
「うん、上手。落ち着くまでこうしていよっか、焦らないで全然いいよ。」
「あ、りがとう……ございます。」
ポンポンと一定のリズムで背中をさすられると、心地よくて徐々に落ち着きを取り戻していく。
心臓も嫌なくらいうるさかったはずなのに、呼吸が安定してくると同時に嫌悪感がなくなった。
「……あなたのお名前、聞いてもいいですか?」
「もちろん。俺の名前は八萩壱星、だよ。」
「壱星、さん?」
「うーん、さん付けも新鮮で嬉しいけどできれば呼び捨てで呼んでくれるともっと嬉しいかも。敬語もいらないから。」
「……じゃあ壱星、私の名前って、何?」
「君は小春、千代水小春って名前。君にぴったりの、暖かくて優しい名前だよ。」
冷えるからコートちゃんと着よっか、と言われながら壱星に教えてもらう。
小春か……うん、覚えた。
自分の名前が分かるだけで底知れない安堵を感じて、強く閉じていた口元を緩ませる。
すると今度は彼のことが気になって、率直な疑問を口にした。
「壱星は……私にとって、どんな存在なの?」
「……俺は、小春の彼氏だよ。俺たち、恋人なんだよ。」
「こい、びと……。」
壱星がどんな存在か分かれば、記憶が少しは戻るんじゃないかと思った。
でも流石にそう簡単にはいかなくて、彼の口から“恋人”だという関係性を聞いてもいまいちピンとこない。
申し訳なく思いながら、コートをちゃんと着た私を慈しむような瞳で見てくる彼を見つめ返す。
私より20㎝くらい高い彼を見る為にはぐっと首を上げなくちゃいけなくて、ずっとやっていると首を痛めそう。
「小春、この駅にいてくれてありがとう。」
「えっ……?」
その時、壱星が突然そんな事を口にした。
何に対してのありがとうなのかが分からなくて、頭の上にはてなマークを浮かべてしまう。
だから『どういう意味?』と思わず尋ねそうになると、それより先に壱星が目を細めた。
「……何でもない。それよりも、せっかくならちょっと歩いてから帰らない? 車で来たからいつでも帰れはするんだけど、ここまで来てすぐ帰るのは味気ないからさ。」
「家、遠いの?」
「まぁそれなりには。ほら小春、行こう。……あ、でも先に小春の財布探さなきゃか。」
すっと、何でもない事のように手を差し出される。
けど私は、咄嗟に腕を引っ込めてしまった。
「っ……ごめ、ん……。」
分かっている、彼はきっと嘘を吐いていない。ちゃんと、私の恋人なはずだと。
それでもどうしてか、彼の手を取る事に不安を抱いてしまう。
恋人だと分かったんだから、彼は知らない人じゃない。
なのに……。
「――いいよ、小春。じゃあ俺、ちょっと駅員さんに小春の財布届いてないか聞いてくるから、ここで待っててくれる? すぐ戻ってくるから。」
「あ……ま、待って壱星……っ!」
「わっ……⁉」
彼は、壱星は優しさの権化だと思った。
私に変な気を遣わせないようにってボディタッチを一切せずに、慈愛に溢れた笑顔だけを置いてホームへと歩いていく。
だから私は、言われた通りここにいるべきだ。
そう、思うのに……壱星が遠ざかるのが何故か嫌で、考えるよりも先に腕が伸びていた。
上手く力のこもっていない手は頼りなく壱星の袖を掴んでいて、彼を引き留めてしまう。
突然の事に少し体勢を崩してしまった壱星は、どうしていいか分からない不安に苛まれている私の顔を覗き込んでから優しく手を握った。
「ごめん、小春の状態考えられてなかったね。……このまま手繋いでても、いい?」
「……う、ん。だいじょう、ぶ。」
「それならよかった。あっ、すみません駅員さん!」
拙い返事とぎこちない頷きに、壱星は慣れたように口元を綻ばせる。
そしてそのままホームのシャッターを閉めようとしている駅員さんに声をかけ、私の手を引きながら事情を説明した。
「あの、桃色の小さめの財布って届いてたりしませんか? C.Kってイニシャルが入ってるやつなんですけど……」
「あぁっ、ちょっと待っててください! 確かついさっき……えっと、これですかね?」
思い当たるものがあるのか、駅員さんは足元に置いてあった段ボール箱に視線を移すと、中から小ぶりの財布を取り出した。
それはキルティングが施されている桃色のもので、端っこには金色のイニシャルが入っている。
思い描いていた財布で合っていたのか、壱星は嬉しそうな声色でその財布を受け取った。
「身分証になるかは分からないんですが……財布の中に写真が入っているはずです。俺と彼女の。」
「こちらですね。……はい、大丈夫ですよ。」
「すみません、こんな真夜中に。助かりました、ありがとうございます。」
ぺこりと頭を下げてお礼を伝える壱星に倣うように、私も軽く会釈をする。
握られた手が熱を帯び始めたのを感じながら、壱星と二人夜空の下を歩く。
その道中にある、コンビニ近くの公園に入った壱星は私にベンチに座るよう促した。
「小春、今から君にはクイズを出してもらいます。」
「クイズ?」
「そう、クイズ。この中に“クイズ”って書かれた小さいメモ帳が入ってるから、その中のクイズ全部を俺に出して。」
「……どうして?」
「今の小春からしたら俺は知らない人だから。俺は答え見ないから、小春の準備ができたらお願い。」
「……わ、分かった。」
そう言って財布を私に預け、目を瞑った壱星。
クイズ……一体どんなものだろう。そんな興味が手元の財布へと移る。
壱星が言ったように財布からミニミニサイズのメモ帳を取って開いてみると、そこにはさっき見た紙切れと同じ丁寧な字で全5問のクイズと答えが書かれていた。
これを読み上げれば、いいんだよね……?
「じゃあ……私と壱星が出会ったのは、いつ?」
「小学1年生。校外学習で同じ班になってから、たくさん話すようになっていったよね。」
「せ、正解……?」
確かに、メモ帳には小学1年生の時と書かれている。
今の私の年齢が……えっと、保険証の生年月日から計算して25歳だから、壱星とは結構な付き合いだ。
まさか10年以上の付き合いだったとは……そんな大事な人を忘れてしまっているなんて、やっぱり申し訳ない。
次のクイズを出す事が躊躇われて、ちらっと壱星を盗み見る。
と、一瞬だったのに確実にこちらを見据えてくる壱星の瞳とぶつかって急いで逸らした。
……もしかして、ずっと見てきてたのかな。
なんて考えが脳裏をよぎって、少し気恥ずかしくなる。
「つ、次はっ……私の好きなものと苦手なものは、何?」
「好きなものは甘いものと程よく辛いものなら何でも。苦手なものは苦めの野菜。でも小春、あんまり好き嫌いしないよね。そういうところも好き。」
「っ……正解。えと、わ、私たちが付き合い始めたのは⁉」
「高校の卒業式の後。俺のほうから告って、小春ってば全然信じなくて1週間経ってやっと分かってくれたっけ。」
「……は、初デートの場所は?」
「行きつけのカフェ。初デートって言っても頻繁に言ってたカフェだったから新鮮さはあんまりなかったけどね。」
全部合ってる……。じゃあ壱星が彼氏だっていうのは、本当だって思っていいんだよね。
ここに書いてある事が本当かどうか今の私には分からないけど、何も知らない私に何かを言える権利はない気がする。
「それじゃあ、最後……私たちがよく、利用する駅は?」
「務台駅。俺と小春の思い出の駅でもある場所。」
「この駅って……さ、さっきの駅?」
「うん。あの駅に小中高大の母校全部あるし、事あるごとに利用してたから思い入れがあるんだよね。それはもちろん、小春も。」
「私、も……」
そう言われても分からない。あの駅に見覚えがあるかと言われれば、ある気もするしない気もする。
曖昧な感覚だけが残って、ついうーんと小首を捻った。
百面相する私を見守るように、壱星は両手を組んだ。
「何か思い出した?」
「……あ、あんまり。」
「そっか。ごめんね、焦らせるような事言って。」
「私のほうこそ……ごめん。早く思い出せるように頑張る!」
「……やっぱり小春は、そう言ってくれるんだね。」
へ? そう言ってくれる、とは……?
独り言のように呟かれた言葉に、きょとんと呆気に取られてしまう。
でも壱星はそんな私には気付かず、ポケットからスマホを取り出すと軽く操作してから一つの動画を表示させた。
「壱星、これは……?」
「今の小春に見てほしい動画、かな。でも見てる途中に気持ち悪くなったりしたらちゃんと言って、すぐ止めるから。」
「う、うん……。」
壱星の言葉の意味が理解できないまま、スタートボタンが押される。
動画自体は1分ちょっとの短いもので、小さな液晶画面の奥には清潔感のある家の内装と……私が映っていた。
《これを見てるって事は、私また記憶なくしちゃったんだね。》
画面にいる私は寂しそうににこりと笑ってから、噛みしめるような声色を零す。
やっぱり私は今まで何度も……記憶喪失になってる、みたいだ。
でも記憶喪失なんて頻繁になるものじゃないよね……? 記憶を失くした用の動画があるというなら、頭を打ってってわけでもないだろうし。
不思議がる私の心を見透かしたように、画面の中の私は一息置いてから答えを連ね始めた。
《多分記憶喪失の私は何にも分かってないだろうから、簡単に説明するんだけど……私、千代水小春って人間はストレスが許容範囲を超えるとね、現実逃避みたいな感覚で記憶を失くしちゃうの。お医者さんは心因性健忘、だって言ってるんだ。原因は、あんまり分かってないんだけど……どんなストレスでもなっちゃうんだって。困っちゃうね、こんな体。》
「心因性、健忘……。」
画面の中の私が口にした自分の病を、小さく反芻してみる。
じゃあ私は……何かしらのストレスにやられて、全部綺麗さっぱり忘れちゃったんだ。
理解すると案外あっさり納得できて、画面の中の私をじっと見つめる。
《でも安心して。この動画を見れてるんだったら、隣に壱星って男がいるはず。この心因性健忘は外部からの接触……要するにきっかけさえあればゆっくりだけど思い出せる。だから思い出したいなって思ったら、壱星を頼って。壱星は絶対、私を助けてくれるから。無理に思い出さなくていいからね、私。》
「あ……そ、っか。」
……私だったんだ。あのメモ書きも、クイズ用意したのも。
寄り添ってくれるような私の笑顔に、ちょっとだけだけど頭に浮かんできた。
そうだよ、記憶喪失になった私が困らないようにって……残したもの、だったはず。
「っ、痛っ……。」
「小春、大丈夫っ?」
「うん……うん、大丈夫だよ。記憶を失くす前の私って、こんなに優しいんだね……。」
反射的に思い出してしまった影響か、一瞬ガンッと頭を殴られたような痛みが電流みたいに走る。
動画の中の私が言っていた通り、確かに今すぐ全部は思い出せない。現に、ふわふわっとしか記憶が戻ってきていないから。
スマホのパスワードも、どうして私があの駅にいたのかも、壱星がどんな人なのかも、まだ今の私には分からない。
頭の中はまだ、満たされないで空っぽ。
「……壱星。」
「どうしたの?」
「私って、壱星の彼女、なんだよね?」
「そうだよ。小春は俺の、大事な彼女。」
「ふふっ、そっか。じゃあ私、壱星をもう一度知り尽くせるようにならなきゃだねっ。」
「っ……ほんと、小春って――」
「んわっ⁉」
動画の再生バーが完全に右にやってきたのを見届けて、壱星に決意を伝える。
と同時に何故か壱星が泣きそうな声で、私の事をぎゅっと強く抱きしめてきた。
記憶を失くす前はきっと、何回もこの暖かい腕の中で愛しさを感じていたんだろう。
けれど今、何も知らない状態の私の心臓は急なハグによる驚きのドキドキで埋め尽くされていて。
「好きだよ、小春。小春が何回俺を忘れても、また好きにさせてみせる。だから本当に、無理はしないで。」
「……分かった。壱星も、無理しちゃダメだよ。」
「もちろん。ずっと小春の傍にいたいから、そう簡単には倒れないよ。」
「壱星って意外にも重ためなんだね、愛。」
「え、そう、かな……重たい男になるつもりは、なかったんだけどね……はは。」
私にはこんな、私を愛してくれる彼氏がいたのか。ちょっぴりくすぐったい。
包容力ある腕の中で照れつつも、ふっと息が漏れる。
私も、壱星にたくさん愛を返したい。返せるようになるまでどれだけかかるか分からないけど。
壱星に身を委ねるよう、瞼を閉じて自分でも精一杯手を伸ばしてみる。
大丈夫だ、思い出せなくても壱星がいてくれるなら……ここまで想ってくれる人がいるなら、未来が真っ暗でも頑張れる。
「……電車、行っちゃった。」
がらんとした駅のホームには、さっきまでたくさんの人がいた。
仕事帰りのサラリーマン、今をときめく若い子たち、ギリギリまで一緒にいたいカップル。
私はその中に混ざれず、行ってしまった電車の背中をぼんやり見つめていた。
行き場のなくなった切符1枚を握りしめて、ストンと無気力にホームのベンチに腰を下ろす。
どうしよう、これじゃ家に帰れない。タクシーでも拾って帰ろうか。
そう思って財布の中身を確認しようとするけど、持っていた小さい鞄にはおろかポケットにも財布本体がなかった。
……切符があるって事は、ホーム内のどこかにあるはず。
「あれ、誰だろ……。」
その時いきなり、隣に置いていたスマホが着信を知らせた。
反射的にスマホを手に取り見つめると、そこには《壱星》という名前が。
「壱星……って、本当に誰だっけ。」
ほぼ無意識に口から飛び出したのは、単純なのに難解な疑問。
それに、私は何でこの駅にいるんだっけ? ここに来るまで私は何をしてたんだっけ?
……思い出せない。
改めて思い返すと、そもそもこんなところで何をしてたんだという疑問が脳裏をよぎる。
けれど思い出そうとすると、頭の中が全て空っぽになっているような虚無感ばかりで少し気持ち悪くなってしまった。
「わたし、は……名前、なんだっけ……。」
自分の名前、それすらも今の私には分からない。脳ごとなくなってしまったのかと錯覚するほどに、私の手元には引き出せる情報が残っていなかった。
あの電車にさえ乗れていたら、違ったのだろうか。
……いや、そんな事ないか。乗ったら乗ったで変なところで降りそうだ、この頭のままじゃ家には帰れないだろうし。
どこか他人事のように考えながら、星が見えない夜空を視界いっぱいに映す。
私、これからどうしたらいいんだろう。秋の夜は冷えるから、とりあえずホームを出て財布を見つけてカプセルホテルにでも泊まるべきだろうか。
はぁ……と息を吐いて、《壱星》さんからの不在着信通知を眺める。スマホのパスワードも分からないから、電話はかけられない。
「壱星って、綺麗な名前……。」
言い換えれば一番星になるその名前に、なんだかじわっと心が温かくなる。この人は私にとってどんな人なんだろう……そんな興味も湧いてきた。
よくよく通知を遡ってみれば、壱星さんは何度も電話をかけてきていたらしい。スワイプする度に不在着信の文字が目に入る。
5、10、20……大体30件くらいか。それほど壱星さんという人は私を気にしてくれているのか。
首を傾げつつ、どうにもできない私はスマホをポケットに突っ込もうとした。
だけどそのポケットの中に、さっきは気が付かなった何かが入っていた。
これは……メモ用紙?
訝しみながら手に取った何かはくしゃくしゃの紙切れで、開くと丁寧な字でこう書いてある。
《また思い出せなくなったら、あの駅のロータリーで待っていて。きっと迎えに来てくれるから。大丈夫、あなたは一人じゃない。》
「……これ、誰が書いたんだろう。」
優しい字と言葉に、秋風で冷えた指先が熱を持つ。このメモは、壱星さんという人が持たせてくれたものなのかな。
でも“また”って事は、私はこれまでに何度も記憶を失くしている……?
確証はないけれど、何故かそう感じて突き動かされるようにベンチから立ち上がった。
そのままメモに書かれているロータリーまで歩いてみると、外はホームよりかは幾分か暗く街灯の淡い明かりだけが頼りになる。
ロータリーまで出たはいいもののこの後どうしていいか分からない私は、下手に動かないほうがいいと考えて駅の壁を背にしゃがんだ。
……迎えって、誰が来てくれるんだろう。白馬の王子様とか……なんて。
冷え込んできた空気のせいかふざけた事を思ってしまい、ぷっと一人吹き出す。
そもそも、迎えなんて来るのかな。
歩く人もまばらで閑散としているロータリーを見つめながら、きゅっと唇を引き結ぶ。
自分のことさえ分かっていない私からすれば、このメモも得体が知れない。自分で持っていたんだから疑う余地はないんだろうけど……。
……迎え、来てくれるんだったら早く来て。
「っ、見つけた……!」
必死な男性の声が近付いてきたのは、愚痴が口から零れる寸前の事だった。
突然の声に驚いて肩を跳ねさせた私に、声の主は駆け足でやってくる。
「良かった、ちゃんとここにいてくれたんだね。」
「……あの、あなたは?」
ちょっとだけ厚めのニットにロングスカートという私の格好を気にしたのか、彼はやってくるとすぐに自分のコートを脱いで私の肩にかけてきた。
垂れ目気味で大人しそうな印象を受ける彼の表情は、不安と心配に駆られているような影を落としている。
迎えって、この人の事かな……?
一目散に私の元に来てくれたんだから多分間違ってないだろうけど、今の私にとって彼は“知らない人”。
思わず尋ねると、彼は一瞬だけ目を見開いた後悲しそうに微笑んだ。
「俺のこと、分かんない?」
「……すみません。私、自分の名前も分からなくて……財布も、なくしちゃって……」
財布には身分証明となるものが入っていたかもしれない。そうしたら自分のことも分かって、多少なりとも記憶が戻ったかもしれない。
ゆっくり彼に向けて言葉にするとたらればばかりが浮かんできて、自分の情けなさにうっとえづく。
けれど彼は、こんな私に優しく声をかけてくれた。
「大丈夫だよ、ゆっくり深呼吸しよう。分からない事は俺が全部、また教えるから。」
「……っ、すー、はー……」
「うん、上手。落ち着くまでこうしていよっか、焦らないで全然いいよ。」
「あ、りがとう……ございます。」
ポンポンと一定のリズムで背中をさすられると、心地よくて徐々に落ち着きを取り戻していく。
心臓も嫌なくらいうるさかったはずなのに、呼吸が安定してくると同時に嫌悪感がなくなった。
「……あなたのお名前、聞いてもいいですか?」
「もちろん。俺の名前は八萩壱星、だよ。」
「壱星、さん?」
「うーん、さん付けも新鮮で嬉しいけどできれば呼び捨てで呼んでくれるともっと嬉しいかも。敬語もいらないから。」
「……じゃあ壱星、私の名前って、何?」
「君は小春、千代水小春って名前。君にぴったりの、暖かくて優しい名前だよ。」
冷えるからコートちゃんと着よっか、と言われながら壱星に教えてもらう。
小春か……うん、覚えた。
自分の名前が分かるだけで底知れない安堵を感じて、強く閉じていた口元を緩ませる。
すると今度は彼のことが気になって、率直な疑問を口にした。
「壱星は……私にとって、どんな存在なの?」
「……俺は、小春の彼氏だよ。俺たち、恋人なんだよ。」
「こい、びと……。」
壱星がどんな存在か分かれば、記憶が少しは戻るんじゃないかと思った。
でも流石にそう簡単にはいかなくて、彼の口から“恋人”だという関係性を聞いてもいまいちピンとこない。
申し訳なく思いながら、コートをちゃんと着た私を慈しむような瞳で見てくる彼を見つめ返す。
私より20㎝くらい高い彼を見る為にはぐっと首を上げなくちゃいけなくて、ずっとやっていると首を痛めそう。
「小春、この駅にいてくれてありがとう。」
「えっ……?」
その時、壱星が突然そんな事を口にした。
何に対してのありがとうなのかが分からなくて、頭の上にはてなマークを浮かべてしまう。
だから『どういう意味?』と思わず尋ねそうになると、それより先に壱星が目を細めた。
「……何でもない。それよりも、せっかくならちょっと歩いてから帰らない? 車で来たからいつでも帰れはするんだけど、ここまで来てすぐ帰るのは味気ないからさ。」
「家、遠いの?」
「まぁそれなりには。ほら小春、行こう。……あ、でも先に小春の財布探さなきゃか。」
すっと、何でもない事のように手を差し出される。
けど私は、咄嗟に腕を引っ込めてしまった。
「っ……ごめ、ん……。」
分かっている、彼はきっと嘘を吐いていない。ちゃんと、私の恋人なはずだと。
それでもどうしてか、彼の手を取る事に不安を抱いてしまう。
恋人だと分かったんだから、彼は知らない人じゃない。
なのに……。
「――いいよ、小春。じゃあ俺、ちょっと駅員さんに小春の財布届いてないか聞いてくるから、ここで待っててくれる? すぐ戻ってくるから。」
「あ……ま、待って壱星……っ!」
「わっ……⁉」
彼は、壱星は優しさの権化だと思った。
私に変な気を遣わせないようにってボディタッチを一切せずに、慈愛に溢れた笑顔だけを置いてホームへと歩いていく。
だから私は、言われた通りここにいるべきだ。
そう、思うのに……壱星が遠ざかるのが何故か嫌で、考えるよりも先に腕が伸びていた。
上手く力のこもっていない手は頼りなく壱星の袖を掴んでいて、彼を引き留めてしまう。
突然の事に少し体勢を崩してしまった壱星は、どうしていいか分からない不安に苛まれている私の顔を覗き込んでから優しく手を握った。
「ごめん、小春の状態考えられてなかったね。……このまま手繋いでても、いい?」
「……う、ん。だいじょう、ぶ。」
「それならよかった。あっ、すみません駅員さん!」
拙い返事とぎこちない頷きに、壱星は慣れたように口元を綻ばせる。
そしてそのままホームのシャッターを閉めようとしている駅員さんに声をかけ、私の手を引きながら事情を説明した。
「あの、桃色の小さめの財布って届いてたりしませんか? C.Kってイニシャルが入ってるやつなんですけど……」
「あぁっ、ちょっと待っててください! 確かついさっき……えっと、これですかね?」
思い当たるものがあるのか、駅員さんは足元に置いてあった段ボール箱に視線を移すと、中から小ぶりの財布を取り出した。
それはキルティングが施されている桃色のもので、端っこには金色のイニシャルが入っている。
思い描いていた財布で合っていたのか、壱星は嬉しそうな声色でその財布を受け取った。
「身分証になるかは分からないんですが……財布の中に写真が入っているはずです。俺と彼女の。」
「こちらですね。……はい、大丈夫ですよ。」
「すみません、こんな真夜中に。助かりました、ありがとうございます。」
ぺこりと頭を下げてお礼を伝える壱星に倣うように、私も軽く会釈をする。
握られた手が熱を帯び始めたのを感じながら、壱星と二人夜空の下を歩く。
その道中にある、コンビニ近くの公園に入った壱星は私にベンチに座るよう促した。
「小春、今から君にはクイズを出してもらいます。」
「クイズ?」
「そう、クイズ。この中に“クイズ”って書かれた小さいメモ帳が入ってるから、その中のクイズ全部を俺に出して。」
「……どうして?」
「今の小春からしたら俺は知らない人だから。俺は答え見ないから、小春の準備ができたらお願い。」
「……わ、分かった。」
そう言って財布を私に預け、目を瞑った壱星。
クイズ……一体どんなものだろう。そんな興味が手元の財布へと移る。
壱星が言ったように財布からミニミニサイズのメモ帳を取って開いてみると、そこにはさっき見た紙切れと同じ丁寧な字で全5問のクイズと答えが書かれていた。
これを読み上げれば、いいんだよね……?
「じゃあ……私と壱星が出会ったのは、いつ?」
「小学1年生。校外学習で同じ班になってから、たくさん話すようになっていったよね。」
「せ、正解……?」
確かに、メモ帳には小学1年生の時と書かれている。
今の私の年齢が……えっと、保険証の生年月日から計算して25歳だから、壱星とは結構な付き合いだ。
まさか10年以上の付き合いだったとは……そんな大事な人を忘れてしまっているなんて、やっぱり申し訳ない。
次のクイズを出す事が躊躇われて、ちらっと壱星を盗み見る。
と、一瞬だったのに確実にこちらを見据えてくる壱星の瞳とぶつかって急いで逸らした。
……もしかして、ずっと見てきてたのかな。
なんて考えが脳裏をよぎって、少し気恥ずかしくなる。
「つ、次はっ……私の好きなものと苦手なものは、何?」
「好きなものは甘いものと程よく辛いものなら何でも。苦手なものは苦めの野菜。でも小春、あんまり好き嫌いしないよね。そういうところも好き。」
「っ……正解。えと、わ、私たちが付き合い始めたのは⁉」
「高校の卒業式の後。俺のほうから告って、小春ってば全然信じなくて1週間経ってやっと分かってくれたっけ。」
「……は、初デートの場所は?」
「行きつけのカフェ。初デートって言っても頻繁に言ってたカフェだったから新鮮さはあんまりなかったけどね。」
全部合ってる……。じゃあ壱星が彼氏だっていうのは、本当だって思っていいんだよね。
ここに書いてある事が本当かどうか今の私には分からないけど、何も知らない私に何かを言える権利はない気がする。
「それじゃあ、最後……私たちがよく、利用する駅は?」
「務台駅。俺と小春の思い出の駅でもある場所。」
「この駅って……さ、さっきの駅?」
「うん。あの駅に小中高大の母校全部あるし、事あるごとに利用してたから思い入れがあるんだよね。それはもちろん、小春も。」
「私、も……」
そう言われても分からない。あの駅に見覚えがあるかと言われれば、ある気もするしない気もする。
曖昧な感覚だけが残って、ついうーんと小首を捻った。
百面相する私を見守るように、壱星は両手を組んだ。
「何か思い出した?」
「……あ、あんまり。」
「そっか。ごめんね、焦らせるような事言って。」
「私のほうこそ……ごめん。早く思い出せるように頑張る!」
「……やっぱり小春は、そう言ってくれるんだね。」
へ? そう言ってくれる、とは……?
独り言のように呟かれた言葉に、きょとんと呆気に取られてしまう。
でも壱星はそんな私には気付かず、ポケットからスマホを取り出すと軽く操作してから一つの動画を表示させた。
「壱星、これは……?」
「今の小春に見てほしい動画、かな。でも見てる途中に気持ち悪くなったりしたらちゃんと言って、すぐ止めるから。」
「う、うん……。」
壱星の言葉の意味が理解できないまま、スタートボタンが押される。
動画自体は1分ちょっとの短いもので、小さな液晶画面の奥には清潔感のある家の内装と……私が映っていた。
《これを見てるって事は、私また記憶なくしちゃったんだね。》
画面にいる私は寂しそうににこりと笑ってから、噛みしめるような声色を零す。
やっぱり私は今まで何度も……記憶喪失になってる、みたいだ。
でも記憶喪失なんて頻繁になるものじゃないよね……? 記憶を失くした用の動画があるというなら、頭を打ってってわけでもないだろうし。
不思議がる私の心を見透かしたように、画面の中の私は一息置いてから答えを連ね始めた。
《多分記憶喪失の私は何にも分かってないだろうから、簡単に説明するんだけど……私、千代水小春って人間はストレスが許容範囲を超えるとね、現実逃避みたいな感覚で記憶を失くしちゃうの。お医者さんは心因性健忘、だって言ってるんだ。原因は、あんまり分かってないんだけど……どんなストレスでもなっちゃうんだって。困っちゃうね、こんな体。》
「心因性、健忘……。」
画面の中の私が口にした自分の病を、小さく反芻してみる。
じゃあ私は……何かしらのストレスにやられて、全部綺麗さっぱり忘れちゃったんだ。
理解すると案外あっさり納得できて、画面の中の私をじっと見つめる。
《でも安心して。この動画を見れてるんだったら、隣に壱星って男がいるはず。この心因性健忘は外部からの接触……要するにきっかけさえあればゆっくりだけど思い出せる。だから思い出したいなって思ったら、壱星を頼って。壱星は絶対、私を助けてくれるから。無理に思い出さなくていいからね、私。》
「あ……そ、っか。」
……私だったんだ。あのメモ書きも、クイズ用意したのも。
寄り添ってくれるような私の笑顔に、ちょっとだけだけど頭に浮かんできた。
そうだよ、記憶喪失になった私が困らないようにって……残したもの、だったはず。
「っ、痛っ……。」
「小春、大丈夫っ?」
「うん……うん、大丈夫だよ。記憶を失くす前の私って、こんなに優しいんだね……。」
反射的に思い出してしまった影響か、一瞬ガンッと頭を殴られたような痛みが電流みたいに走る。
動画の中の私が言っていた通り、確かに今すぐ全部は思い出せない。現に、ふわふわっとしか記憶が戻ってきていないから。
スマホのパスワードも、どうして私があの駅にいたのかも、壱星がどんな人なのかも、まだ今の私には分からない。
頭の中はまだ、満たされないで空っぽ。
「……壱星。」
「どうしたの?」
「私って、壱星の彼女、なんだよね?」
「そうだよ。小春は俺の、大事な彼女。」
「ふふっ、そっか。じゃあ私、壱星をもう一度知り尽くせるようにならなきゃだねっ。」
「っ……ほんと、小春って――」
「んわっ⁉」
動画の再生バーが完全に右にやってきたのを見届けて、壱星に決意を伝える。
と同時に何故か壱星が泣きそうな声で、私の事をぎゅっと強く抱きしめてきた。
記憶を失くす前はきっと、何回もこの暖かい腕の中で愛しさを感じていたんだろう。
けれど今、何も知らない状態の私の心臓は急なハグによる驚きのドキドキで埋め尽くされていて。
「好きだよ、小春。小春が何回俺を忘れても、また好きにさせてみせる。だから本当に、無理はしないで。」
「……分かった。壱星も、無理しちゃダメだよ。」
「もちろん。ずっと小春の傍にいたいから、そう簡単には倒れないよ。」
「壱星って意外にも重ためなんだね、愛。」
「え、そう、かな……重たい男になるつもりは、なかったんだけどね……はは。」
私にはこんな、私を愛してくれる彼氏がいたのか。ちょっぴりくすぐったい。
包容力ある腕の中で照れつつも、ふっと息が漏れる。
私も、壱星にたくさん愛を返したい。返せるようになるまでどれだけかかるか分からないけど。
壱星に身を委ねるよう、瞼を閉じて自分でも精一杯手を伸ばしてみる。
大丈夫だ、思い出せなくても壱星がいてくれるなら……ここまで想ってくれる人がいるなら、未来が真っ暗でも頑張れる。