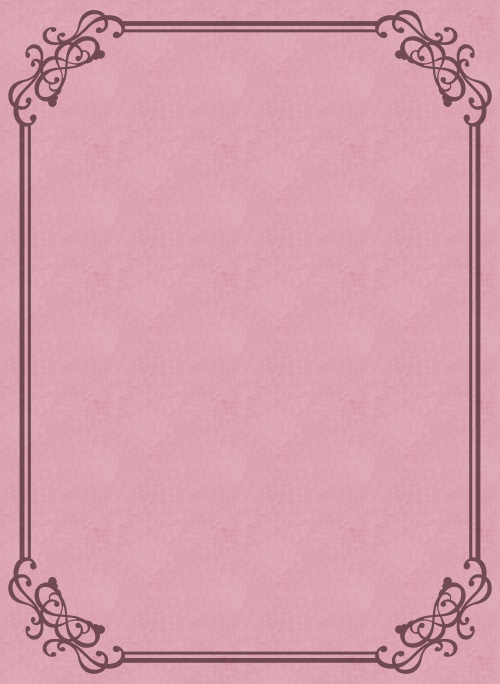私の入ってるサークルは、写真を撮ってコンテストにあげたり、頼まれた写真でアルバムを作ったりしてる。
今回夏休み中のコンテストの締め切りが終わって、打ち上げに来たものの、なかなか解散しないみんなに合わせるのも少し疲れた。
明日学校がないとはいえ、早く帰りたいのに。
こっちの気持ちも考えてほしい。
そんなことを考えながら呑むお酒は、あまり美味しくない。
そんなお酒でも飲んだら余計に暑い、溶ける。
「来夏呑んでる??」
私の顔をみながら、体を寄りかかるように絡んできたサークル仲間。
名前は確か、香奈ちゃんだっけ。
あんまりサークルの人全員と仲がいいわけじゃないから、たまに名前を忘れるのは内緒のはなし。
よく知りもしない人の名前まで覚えるのは大変。
でも割とサークル内の仲はいい方だと思う。
「ん-そんなに。だって、みんながみんな吞んでたら誰が介抱するの」
だってほら、ため口で話してるぐらいには仲がいい。
え?ため口だからって仲がいいわけじゃない?
わたしだけ、か。
仲良く思ってるのは、いや、私も名前とか忘れるし。
「そんなこと気にしてるからまじめだって言われるんだよ」
まじめじゃない、ぜんぜん。
ほんとは否定したい。
「まじめでいいよ、事実だし」
みんなの思う私って何。
「それって、人生つまんなくない?」
人生何してたら楽しいのかな。
22歳まで生きてきて、生き方につまんないとか言われて、気にしない人がいる?
「ごめん、外の空気吸ってくるね」
何か言われてる気もするけど、気にしたら負けだ、そのまま外に出た。
わたしはなにとたたかって、……。
酔ったわけでもなく、気持ち悪い。
でも外は少し風が吹いてて涼しい。
「来夏?こんなとこにいた」
別に見に来なくていいのに。
「あー、亜季くん、ごめん抜けちゃってて、だれか心配してた?」
そのごまかすような顔。
「いや、そういうわけじゃないけど、いないなと思って見に来ただけ」
誰も見てないんだから、でもなんで、亜季くんは来てくれたの……?
「まぁ、誰も気にしないよね」
またこんなこと言うから嫌われるんだって。
「香奈も気にしてたよ、強く言い過ぎたかもって」
あー、それで、香奈ちゃんの言いなりで来たんだ。
むしろそれ以外に答えが見つからない。
性格悪い、わたしって。
「ねぇ亜季くん、私って人生つまんなそうに見える?」
「何急に」
やっぱり、酔ってんのかな。
こんなこと聞いちゃうなんて。
「なんかさ、別に周りに何思われようがどうでもいいと思うんだけど、特別だなって思えることとかしてみたり、普段なら絶対しないなって思うことしてみたりしたらいいよ。自分が楽しむことが大事ね」
特別なこと……。
自分がまじめすぎるがゆえに、とくに何もないせいでしたいことがわからない。
このサークルに入ったのだって、ただ何気なく写真撮ることが多いから軽い気持ちで入っただけ。
それなのに、人間関係で悩んでる私は、人付き合いとか向いてなさすぎるな。
でもしたいことって、ほんとに写真?
例えば、あこがれてたんじゃないの?
みんなとはしゃいだりすることに。
青春することに。
それこそ恋愛とか、してみたかったり、あーだめ、こんな面倒なタイプ私なら彼女にしないわ。
「……来夏、もしかして今考えてる?」
「え、うん。え?あ、ごめん黙り込んで」
「ほんと素直だね、来夏って」
素直……?
「何その驚いた顔」
まじめだねと言われることはよくあったけど、素直なんて言われたことない。
「素直なんて、初めて言われた」
そんな風に言ってくれるの、初めて。
まじめって言われるの気にしてたから。
「来夏は素直だよ、気配り屋さんで、疲れやすいのも知ってる」
私、亜季くんとまともに話すの初めてなのに。
何でこんなほめてくれて、わたしなんかのことまで見てくれてるの。
「よくみてるね、さすが、ムードメーカー」
「来夏、時間平気?終電」
スマホの時計を見ながら亜季くんは終電を気にしてくれた。
不思議と、ほかの人とは違う感じがした。
終電を聞かれてあー時間が止まればいいのにと思った私は、
「あ……あと数分で出ちゃうや」
まだ間に合うはずなのに、間に合わないふりをした。
「みんな帰らないのかな」
本音は、亜季くんは帰っちゃう?って聞きたかった。
「朝まで呑むんだと思う。
なぁ、人生このままつまんないと思われながら過ごすより、ちょっと来夏がしなさそうなことみんなに仕掛けてみない?」
「……例えば?」
「二人で抜け出すとか」
なに、それ。
相手私だよ?いいの?
「変な噂出てきちゃうよ」
「俺は来夏ならいいよ」
ねぇそれって、どういう意味で言ってるの。
なんて言葉を封印して出た言葉は、「亜季くんがいいなら」だった。
「俺かばん取ってくる」
二人で抜け出すのなんて付き合ってる二人とかがするものだと思ってた。
特別のこと。
亜季くんにとって、わたしとの時間は特別になるのかな。
スマホの時計は、23時45分、私の終電の時間だった。
いつもみたいに流されて終電を逃すのとは、何かが違った。
「お待たせ」
私が自らの意思で終電を逃すと思わなかった。
荷物を私に渡すと、センターわけの前髪をかきあげて、亜季くんは「いこっか」と言う。
私たちはどこに向かうんだろう。
「来夏、吞み足りないんじゃない?いつも人のことばっかり気にしてるから」
ほら、また私のことよく知ってるふり、いや当たってるけどさ。
「まぁ、そんなに酔っては無いかな」
「コンビニで缶チューハイ買って呑みなおそう、公園とかで」
「なにそれ」
「いや、来夏そういうのしたことないんじゃないかなと思って」
「めっちゃいいじゃん」
「だろ、じゃまずはコンビニ」
「なんか抜け出すって変な感じ」
「どきどきするっしょ、普段と違うことすると」
「どきどき、する」
亜季くんと喋ることはあんまりない。
ムードメーカーでだれとでも話す人って感じ。
人気者なのに私と二人きりでなんか、何考えてんのか分からない。
だからちょっと怖い。
でも、亜季くんと過ごす時間は、落ち着いてて好きなんだよね。
「来夏何呑む?」
そう言ってコンビニの出入り口のドアを開けて先に通してくれる。
そんなのだれにでもやってるのかなと思うと、少し胸がずきずきと痛む。
私、思ってるよりも亜季くんのこと好きなんだなと、客観視する。
「私カシオレにしようかな」
「じゃ俺、レモンチューハイしよ。ほかにも適当にいくつか買っておこっか、あ、俺が払うからいいよ」
「え、貸しは作りたくないし」
「俺が誘ったんだから、いいの」
それを押し切って出そうとした財布は、手で押さえられてしまった。
買い出しを済ませて、近くの公園に向かう。
抜け出した私たちはどう思われてるんだろう。
私たちは公園のベンチに座った。
「お酒の写真撮ってもいい?」
「いいよ、俺のも撮る?」
「うん、一緒に写したい」
フラッシュが一瞬だけあたりを照らす。
「どうせならストーリー上げなよ」
そう言って、亜季くんもスマホを取り出した。
「ストーリーに?ただのお酒じゃん」
「んー、じゃあ、こうやってお酒だけをとるんじゃなくて、肩を寄せて、お酒と一緒に顔下だけ映っちゃうとか」
暗くてあまり表情が見れないけど、亜季くんの香水がふんわりっと香って、頭がぼーっとした。
フラッシュがあたりを照らし、ふいに亜季くんの顔がお酒のせいかほてって見える。
「俺の顔見てた?なんかついてる?やべ、はず」
「いや、そういうわけじゃないけど」
そう言って亜季くんがスマホをベンチに置いた瞬間にシャッターがまた押されてしまって、フラッシュがあたりを照らす。
明らかに、亜季くんの表情は、照れて赤くなっていた。
「亜季くんはさ、何で私を連れだしてくれたの?」
「なんかいつも思いつめたような顔してるから、心配してたんだよね、俺にしかできないかなって思ったから」
「そんなこと思ってくれてたんだ、やっぱり、人生つまんなそうに見える?」
「逆に聞くけど、俺といるのつまんない?」
「ううん、すごく落ち着くし、楽しい」
もっと一緒にいたい。
このまま時間が止まればいいのに。
「それでいいじゃん、楽しいなら連れ出したかいがあったよ、よし呑もうか開けれる?」
私のネイルを気にしてくれて、亜季くんは開けてくれた。
こういう気の回せるところが優しい。
「「かんぱーい」」
缶チューハイをこつんと当てると私たちはお酒を口に運んだ。
おいしい。
あれ、お酒苦手なはずなのに。
なんで?
「私、缶チューハイ初めて飲んだけど、おいしいね」
「え、はじめて?マジで言ってる?」
「んー私が嘘ついたり冗談言うようなひとにみえてるってこと?」
左頬を膨らませながら、唇を少しかみ、亜季くんを見つめた。
「ごめんごめん、そうじゃなくて、そんな普段お酒呑まない人なのに打ち上げよく来てくれたよなーと思って」
「人付き合い覚えたいから」
「無理しなくていいのに」
なぜか亜季くんには思うこと全部話せた。
お酒がおいしくて、話が進んでってよく聞くけど自分がなると思わなかった。
「亜季くんが吞んでるのもおいしそう、レモンだっけ」
「吞んでみる?うまいよ」
え
「……亜季くんって間接?とか気にしない人?」
「来夏にしか女子には言ったことないけど?」
なにその沈黙、何で私の顔そんな真剣なまなざしで見るの。
「なんか試してる?あ、わかった、罰ゲームで……「来夏」」
缶チューハイを片手に、もう片方の手で、あふれ出た涙をぬぐっていると、名前を呼んで、私の両腕をつかんだ。
そして静かにもう一度私の名前を呼んだ。
「来夏」
「な、なによっっ!!……だってわたしなんて……っ」
「もういいから、来夏、そんなこと気にしなくていいよ」
あー、酔ってる。
ただの間接で泣きわめいて迷惑かけて。
亜季くんは、私が持ってる缶チューハイを横に置いて、強く私を抱きしめた。
わんわんと親とはぐれた子犬がお母さんに慰められるように泣いた。
「来夏?よく聞いて、俺なぁ……来夏のことずっと目で追ってたんよ、だからすぐ無理するとこも知ってる」
「……うぅっ…っ…」
「来夏が好きだから、そばで支えたいとも思ってた」
亜季くんは真剣だった。
「わたし、恋愛なんてしたことないよ……っ、絶対すぐ興味なくなるって……っ」
「俺じゃ不満?」
「……その聞き方ずるいっ……亜季くんは私でいいの……っ……?」
「来夏しか見てない、来夏しか見る気ない」
「亜季くんのこと、私も気になって、た……信じられないくらい今嬉しいっ……」
「うれし泣きならいっか」
そう言って亜季くんはわたしのなみだを右手でぬぐって、私の長い横髪を耳にかけて毛先が揺れた。
そして、私の唇に亜季くんは手で触れた。
「な、なに」
亜季くんは私をやさしく触れる。
「緊張してるかなって」
「そりゃ、すごいドキドキしてるよ?触れられるだけで心臓爆発しそうだもん」
「でも泣き止んだね」
そう言われてみればドキドキしすぎて泣き止んでた。
ところで、この手はなに。
ずっとむにむに唇や頬っぺた触られてて、はずかしい。
「確かに泣き止んだけど、この手、リップとれちゃうんだけど……?」
「あ、つい……やわらかいなぁって、……ごめんきもいよねこんなこといって」
なにその感想、恋愛初心者みたいな。
「亜季くんもしかして彼女いたことない?」
「ないよ、何なら初恋、来夏しか見てないって言ったじゃん」
「わたし、彼女?なの?」
「不満?」
じらされてもっと、亜季くんに触れたくて、
「わたしからしてもいい?」
「なにを?」
「鈍感、亜季くんのばか」
そういって、わたしから亜季くんの唇にキスをした。
柔らかな唇に、さらりと揺れる亜季くんの髪。
亜季くんはそっと、私の後頭部に手を添えて、濃厚な口づけにかえた。
「んんっ……」
漏れる吐息と夏の風に、じんわりと汗が垂れる。
唇を離すと唾液が糸を引いた。
はずかしさに横に合ったお酒を手に取り、飲み干した。
「————あれ、なんか酸っぱい?」
「それ俺の」
「え、あ、えっと、ま、まぁもう口づけしたし、いっしょ、ほ、ほら、亜季くんも呑んで呑んで」
動揺したけど、キスしたんだし。
私に急かされて、亜季くんも私の飲みかけを呑み干した。
「あの、アカウント交換しよ?」
「いいよ」
raika@k.raika.pic
あき@aki.anndo_ki
「あ、さっきのストーリー、良いね押しとくね」
そう言われて飛んできたいいねの通知。
なんか、キスする前の二人、なんだかぎこちない。
「初々しい二人だね」
時刻は、3時50分。
「もう4時だね、家近くだからウチくる?」
「行かせてもらいます」
「そんなかたくならんといて、呑みなおそ」
「まだ呑むの」
「一緒に寝る?さすがに添い寝以上は付き合いたてでしないからね?」
「わ、わかってるよ、鈍感な奥手だもんね」
「ばかにしてんな?」
そういって、私の横腹をくすぐった。
「ま、まって!ごめんってあはははくすぐったい」
幸せってこういうことを言うんだろうか。
何気ない毎日に、幸福が訪れる日が来るなんて、思ってもいなかった。
朝焼けをバックにストーリーをあげた。
raika@k.raika.pic[わたしはいまがしあわせです]
今回夏休み中のコンテストの締め切りが終わって、打ち上げに来たものの、なかなか解散しないみんなに合わせるのも少し疲れた。
明日学校がないとはいえ、早く帰りたいのに。
こっちの気持ちも考えてほしい。
そんなことを考えながら呑むお酒は、あまり美味しくない。
そんなお酒でも飲んだら余計に暑い、溶ける。
「来夏呑んでる??」
私の顔をみながら、体を寄りかかるように絡んできたサークル仲間。
名前は確か、香奈ちゃんだっけ。
あんまりサークルの人全員と仲がいいわけじゃないから、たまに名前を忘れるのは内緒のはなし。
よく知りもしない人の名前まで覚えるのは大変。
でも割とサークル内の仲はいい方だと思う。
「ん-そんなに。だって、みんながみんな吞んでたら誰が介抱するの」
だってほら、ため口で話してるぐらいには仲がいい。
え?ため口だからって仲がいいわけじゃない?
わたしだけ、か。
仲良く思ってるのは、いや、私も名前とか忘れるし。
「そんなこと気にしてるからまじめだって言われるんだよ」
まじめじゃない、ぜんぜん。
ほんとは否定したい。
「まじめでいいよ、事実だし」
みんなの思う私って何。
「それって、人生つまんなくない?」
人生何してたら楽しいのかな。
22歳まで生きてきて、生き方につまんないとか言われて、気にしない人がいる?
「ごめん、外の空気吸ってくるね」
何か言われてる気もするけど、気にしたら負けだ、そのまま外に出た。
わたしはなにとたたかって、……。
酔ったわけでもなく、気持ち悪い。
でも外は少し風が吹いてて涼しい。
「来夏?こんなとこにいた」
別に見に来なくていいのに。
「あー、亜季くん、ごめん抜けちゃってて、だれか心配してた?」
そのごまかすような顔。
「いや、そういうわけじゃないけど、いないなと思って見に来ただけ」
誰も見てないんだから、でもなんで、亜季くんは来てくれたの……?
「まぁ、誰も気にしないよね」
またこんなこと言うから嫌われるんだって。
「香奈も気にしてたよ、強く言い過ぎたかもって」
あー、それで、香奈ちゃんの言いなりで来たんだ。
むしろそれ以外に答えが見つからない。
性格悪い、わたしって。
「ねぇ亜季くん、私って人生つまんなそうに見える?」
「何急に」
やっぱり、酔ってんのかな。
こんなこと聞いちゃうなんて。
「なんかさ、別に周りに何思われようがどうでもいいと思うんだけど、特別だなって思えることとかしてみたり、普段なら絶対しないなって思うことしてみたりしたらいいよ。自分が楽しむことが大事ね」
特別なこと……。
自分がまじめすぎるがゆえに、とくに何もないせいでしたいことがわからない。
このサークルに入ったのだって、ただ何気なく写真撮ることが多いから軽い気持ちで入っただけ。
それなのに、人間関係で悩んでる私は、人付き合いとか向いてなさすぎるな。
でもしたいことって、ほんとに写真?
例えば、あこがれてたんじゃないの?
みんなとはしゃいだりすることに。
青春することに。
それこそ恋愛とか、してみたかったり、あーだめ、こんな面倒なタイプ私なら彼女にしないわ。
「……来夏、もしかして今考えてる?」
「え、うん。え?あ、ごめん黙り込んで」
「ほんと素直だね、来夏って」
素直……?
「何その驚いた顔」
まじめだねと言われることはよくあったけど、素直なんて言われたことない。
「素直なんて、初めて言われた」
そんな風に言ってくれるの、初めて。
まじめって言われるの気にしてたから。
「来夏は素直だよ、気配り屋さんで、疲れやすいのも知ってる」
私、亜季くんとまともに話すの初めてなのに。
何でこんなほめてくれて、わたしなんかのことまで見てくれてるの。
「よくみてるね、さすが、ムードメーカー」
「来夏、時間平気?終電」
スマホの時計を見ながら亜季くんは終電を気にしてくれた。
不思議と、ほかの人とは違う感じがした。
終電を聞かれてあー時間が止まればいいのにと思った私は、
「あ……あと数分で出ちゃうや」
まだ間に合うはずなのに、間に合わないふりをした。
「みんな帰らないのかな」
本音は、亜季くんは帰っちゃう?って聞きたかった。
「朝まで呑むんだと思う。
なぁ、人生このままつまんないと思われながら過ごすより、ちょっと来夏がしなさそうなことみんなに仕掛けてみない?」
「……例えば?」
「二人で抜け出すとか」
なに、それ。
相手私だよ?いいの?
「変な噂出てきちゃうよ」
「俺は来夏ならいいよ」
ねぇそれって、どういう意味で言ってるの。
なんて言葉を封印して出た言葉は、「亜季くんがいいなら」だった。
「俺かばん取ってくる」
二人で抜け出すのなんて付き合ってる二人とかがするものだと思ってた。
特別のこと。
亜季くんにとって、わたしとの時間は特別になるのかな。
スマホの時計は、23時45分、私の終電の時間だった。
いつもみたいに流されて終電を逃すのとは、何かが違った。
「お待たせ」
私が自らの意思で終電を逃すと思わなかった。
荷物を私に渡すと、センターわけの前髪をかきあげて、亜季くんは「いこっか」と言う。
私たちはどこに向かうんだろう。
「来夏、吞み足りないんじゃない?いつも人のことばっかり気にしてるから」
ほら、また私のことよく知ってるふり、いや当たってるけどさ。
「まぁ、そんなに酔っては無いかな」
「コンビニで缶チューハイ買って呑みなおそう、公園とかで」
「なにそれ」
「いや、来夏そういうのしたことないんじゃないかなと思って」
「めっちゃいいじゃん」
「だろ、じゃまずはコンビニ」
「なんか抜け出すって変な感じ」
「どきどきするっしょ、普段と違うことすると」
「どきどき、する」
亜季くんと喋ることはあんまりない。
ムードメーカーでだれとでも話す人って感じ。
人気者なのに私と二人きりでなんか、何考えてんのか分からない。
だからちょっと怖い。
でも、亜季くんと過ごす時間は、落ち着いてて好きなんだよね。
「来夏何呑む?」
そう言ってコンビニの出入り口のドアを開けて先に通してくれる。
そんなのだれにでもやってるのかなと思うと、少し胸がずきずきと痛む。
私、思ってるよりも亜季くんのこと好きなんだなと、客観視する。
「私カシオレにしようかな」
「じゃ俺、レモンチューハイしよ。ほかにも適当にいくつか買っておこっか、あ、俺が払うからいいよ」
「え、貸しは作りたくないし」
「俺が誘ったんだから、いいの」
それを押し切って出そうとした財布は、手で押さえられてしまった。
買い出しを済ませて、近くの公園に向かう。
抜け出した私たちはどう思われてるんだろう。
私たちは公園のベンチに座った。
「お酒の写真撮ってもいい?」
「いいよ、俺のも撮る?」
「うん、一緒に写したい」
フラッシュが一瞬だけあたりを照らす。
「どうせならストーリー上げなよ」
そう言って、亜季くんもスマホを取り出した。
「ストーリーに?ただのお酒じゃん」
「んー、じゃあ、こうやってお酒だけをとるんじゃなくて、肩を寄せて、お酒と一緒に顔下だけ映っちゃうとか」
暗くてあまり表情が見れないけど、亜季くんの香水がふんわりっと香って、頭がぼーっとした。
フラッシュがあたりを照らし、ふいに亜季くんの顔がお酒のせいかほてって見える。
「俺の顔見てた?なんかついてる?やべ、はず」
「いや、そういうわけじゃないけど」
そう言って亜季くんがスマホをベンチに置いた瞬間にシャッターがまた押されてしまって、フラッシュがあたりを照らす。
明らかに、亜季くんの表情は、照れて赤くなっていた。
「亜季くんはさ、何で私を連れだしてくれたの?」
「なんかいつも思いつめたような顔してるから、心配してたんだよね、俺にしかできないかなって思ったから」
「そんなこと思ってくれてたんだ、やっぱり、人生つまんなそうに見える?」
「逆に聞くけど、俺といるのつまんない?」
「ううん、すごく落ち着くし、楽しい」
もっと一緒にいたい。
このまま時間が止まればいいのに。
「それでいいじゃん、楽しいなら連れ出したかいがあったよ、よし呑もうか開けれる?」
私のネイルを気にしてくれて、亜季くんは開けてくれた。
こういう気の回せるところが優しい。
「「かんぱーい」」
缶チューハイをこつんと当てると私たちはお酒を口に運んだ。
おいしい。
あれ、お酒苦手なはずなのに。
なんで?
「私、缶チューハイ初めて飲んだけど、おいしいね」
「え、はじめて?マジで言ってる?」
「んー私が嘘ついたり冗談言うようなひとにみえてるってこと?」
左頬を膨らませながら、唇を少しかみ、亜季くんを見つめた。
「ごめんごめん、そうじゃなくて、そんな普段お酒呑まない人なのに打ち上げよく来てくれたよなーと思って」
「人付き合い覚えたいから」
「無理しなくていいのに」
なぜか亜季くんには思うこと全部話せた。
お酒がおいしくて、話が進んでってよく聞くけど自分がなると思わなかった。
「亜季くんが吞んでるのもおいしそう、レモンだっけ」
「吞んでみる?うまいよ」
え
「……亜季くんって間接?とか気にしない人?」
「来夏にしか女子には言ったことないけど?」
なにその沈黙、何で私の顔そんな真剣なまなざしで見るの。
「なんか試してる?あ、わかった、罰ゲームで……「来夏」」
缶チューハイを片手に、もう片方の手で、あふれ出た涙をぬぐっていると、名前を呼んで、私の両腕をつかんだ。
そして静かにもう一度私の名前を呼んだ。
「来夏」
「な、なによっっ!!……だってわたしなんて……っ」
「もういいから、来夏、そんなこと気にしなくていいよ」
あー、酔ってる。
ただの間接で泣きわめいて迷惑かけて。
亜季くんは、私が持ってる缶チューハイを横に置いて、強く私を抱きしめた。
わんわんと親とはぐれた子犬がお母さんに慰められるように泣いた。
「来夏?よく聞いて、俺なぁ……来夏のことずっと目で追ってたんよ、だからすぐ無理するとこも知ってる」
「……うぅっ…っ…」
「来夏が好きだから、そばで支えたいとも思ってた」
亜季くんは真剣だった。
「わたし、恋愛なんてしたことないよ……っ、絶対すぐ興味なくなるって……っ」
「俺じゃ不満?」
「……その聞き方ずるいっ……亜季くんは私でいいの……っ……?」
「来夏しか見てない、来夏しか見る気ない」
「亜季くんのこと、私も気になって、た……信じられないくらい今嬉しいっ……」
「うれし泣きならいっか」
そう言って亜季くんはわたしのなみだを右手でぬぐって、私の長い横髪を耳にかけて毛先が揺れた。
そして、私の唇に亜季くんは手で触れた。
「な、なに」
亜季くんは私をやさしく触れる。
「緊張してるかなって」
「そりゃ、すごいドキドキしてるよ?触れられるだけで心臓爆発しそうだもん」
「でも泣き止んだね」
そう言われてみればドキドキしすぎて泣き止んでた。
ところで、この手はなに。
ずっとむにむに唇や頬っぺた触られてて、はずかしい。
「確かに泣き止んだけど、この手、リップとれちゃうんだけど……?」
「あ、つい……やわらかいなぁって、……ごめんきもいよねこんなこといって」
なにその感想、恋愛初心者みたいな。
「亜季くんもしかして彼女いたことない?」
「ないよ、何なら初恋、来夏しか見てないって言ったじゃん」
「わたし、彼女?なの?」
「不満?」
じらされてもっと、亜季くんに触れたくて、
「わたしからしてもいい?」
「なにを?」
「鈍感、亜季くんのばか」
そういって、わたしから亜季くんの唇にキスをした。
柔らかな唇に、さらりと揺れる亜季くんの髪。
亜季くんはそっと、私の後頭部に手を添えて、濃厚な口づけにかえた。
「んんっ……」
漏れる吐息と夏の風に、じんわりと汗が垂れる。
唇を離すと唾液が糸を引いた。
はずかしさに横に合ったお酒を手に取り、飲み干した。
「————あれ、なんか酸っぱい?」
「それ俺の」
「え、あ、えっと、ま、まぁもう口づけしたし、いっしょ、ほ、ほら、亜季くんも呑んで呑んで」
動揺したけど、キスしたんだし。
私に急かされて、亜季くんも私の飲みかけを呑み干した。
「あの、アカウント交換しよ?」
「いいよ」
raika@k.raika.pic
あき@aki.anndo_ki
「あ、さっきのストーリー、良いね押しとくね」
そう言われて飛んできたいいねの通知。
なんか、キスする前の二人、なんだかぎこちない。
「初々しい二人だね」
時刻は、3時50分。
「もう4時だね、家近くだからウチくる?」
「行かせてもらいます」
「そんなかたくならんといて、呑みなおそ」
「まだ呑むの」
「一緒に寝る?さすがに添い寝以上は付き合いたてでしないからね?」
「わ、わかってるよ、鈍感な奥手だもんね」
「ばかにしてんな?」
そういって、私の横腹をくすぐった。
「ま、まって!ごめんってあはははくすぐったい」
幸せってこういうことを言うんだろうか。
何気ない毎日に、幸福が訪れる日が来るなんて、思ってもいなかった。
朝焼けをバックにストーリーをあげた。
raika@k.raika.pic[わたしはいまがしあわせです]