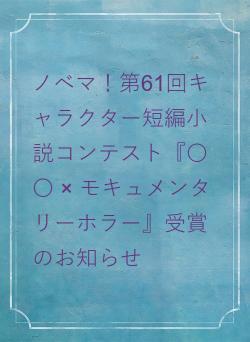「こんな熱帯夜に外で寝るなんて、死ぬがな」
終電を逃して公園のベンチで手枕している啓太に話しかけたオッチャンには前歯が二本なかった。
「ついてこい。クーラーあるから」
着たきりスズメと祖母が言っていたなと思う。啓太が引きこもりつづけ着替えもろくにできなかった五年前のことだ。オッチャンの服は泥で煮しめたような色で着たきりスズメだったときの啓太と同じようなニオイを放っている。
かなり小柄なオッチャンの背中についていく。やや左に重心が傾いているような歩き方。七十歳は超えているだろうに軽やかに歩く。
「ここや、ここや」
ブロック塀に囲まれた空き地にブルーシートで組まれた小屋がある。オッチャンはシートを掻き分けて入っていく。啓太は顔だけを突っ込んでみた。
小屋の中はムッとしている。真っ暗で臭くて湿って暑くて不快指数が明らかに高い。
「待ってな。今クーラーつけるからよ」
ブゥンと重い音がした。小さな緑のランプが地面スレスレのところで光る。なにか機械が起動したようだ。ブゥンブゥンと鳴る音はモーター音のようだ。
灯りがともった。オッチャンが古臭い自転車にまたがり猛烈にペダルをこいでいる。自転車は台座に固定され台座から伸びるコードが屋根にくくりつけられた電灯と小屋の隅にある円筒形のスツール程度の大きさのスポットクーラーに接続されている。
「すぐに涼しくなるからな」
ブゥンブゥンと自転車が唸りを上げる。オッチャンの脚は筋肉の盛り上がりが岩のようだ。硬い岩がゴロゴロ動いてペダルをこいで電気を産む。
スポットクーラーから風が吹き出す。伸ばしっぱなしの啓太の髪を揺らす風はすぐに冷たくなった。冷風を逃さないために小屋に入りブルーシートをきちんと合わせて閉じる。
オッチャンの額に汗が浮いている。クーラーの風がオッチャンの背中に当たっても汗は流れ続ける。
「まあ、その辺に座りな」
オッチャンが顎で指し示したその辺にはガラクタが積み上げられていて座れそうにはない。チューハイの空き缶が詰め込まれたポリ袋の山と近所のスーパーの名前があるショッピングカートと煤だらけのだるまストーブを少しずつ押しやって作った隙間に太った体を押し込めた。
自転車のタイヤは見たこともないスピードで回転する。オッチャンの汗がしたたるごとに小屋は涼しくなっていく。
「オッチャンはなあ、こう見えても昔は競輪選手やったんや」
こいでいる自転車は競輪にはむかないだろうママチャリだ。
「万車券出したこともあるんや」
かけた金額の万倍儲かるということはかけた選手が不人気だったということだ。不人気だったが勝ったということだ。自慢になるのかならないのかわからないことを語るオッチャンの岩のような脚は止まらない。クーラーは冷え冷えと熱帯夜を小屋の外へ押し出す。膝を抱えて座る啓太の汗は止まった。
汗をかいて働く人は信用できると祖母が言っていたなと思う。万車券を出したオッチャンは常勝選手ではなかっただろうが信用できる人間だろう。汗が光る。
競輪も競馬も競艇も啓太はやらない。同じような体型の同じような動きをする人の中からたった一人を選びだす方法などわからない。だから同じ年頃の同じくらいの頭の出来の人たちと同じような動きが出来ない啓太は教室を飛び出したのだから。
「背広脱いだらどうや。暑いやろ」
黒のネクタイは外してジャケットのポケットに入れていた。分厚く黒いジャケットを着たままなのは泣けなかったからだ。終電をわざと逃したのも泣けなかったからだ。ブゥンブゥンとクーラーが啓太を冷やしてくれる。
オッチャンは祖母より十歳は年上だろうにオッチャンの脚はよく動く。日焼けした重い脚は猛然と回転する。オッチャンの顎から落ちる汗が地面に染みていく。クーラーが小屋を冷やせば冷やすほどオッチャンは汗をかく。啓太を熱帯夜から救うためにオッチャンが汗をかく。
立ち上がりジャケットを脱いでシャツの袖をまくり上げる。
「どうした?」
「かわるよ」
オッチャンはしばらく黙って啓太を見つめた。その間も岩のような脚は回転を続けた。
「ほうか」
オッチャンが脚を止めると電灯の明かりがぼんやりと薄れてふいっと消えた。
手探りで自転車のサドルを見つけてまたがりこぎだす。ペダルはいやに重い。歯を食いしばって右脚左脚と踏み込む。踏み込み踏み込む。踏み込み踏み込む。額に汗がにじむ。踏み込み踏み込む。踏み込み、ブゥンと音が鳴った。ブゥンブゥンとリズミカルに鳴る音に合わせて電灯が明るくなったり暗くなったりする。クーラーから風は出ない。
ブゥンブゥン。明滅。ブゥンブゥン。明滅。冷えていた小屋は少しずつ暑くなる。啓太はサドルから尻を浮かせて体重をかけてペダルを踏み込む。踏み込み踏み込む。電灯が明るくなりクーラーが風を吹き出す。オッチャンは風の吹き出し口に顔を近づけ目を細めた。
「涼しいのう。おかげで気持ちええわ」
啓太の顎からしたたり落ちる汗が地面にしみた。オッチャンと交代でクーラーの風を浴びて交代で自転車をこぐ。こいでもこいでもこぎたりない。
「おー、かわろか」
啓太のふくらはぎは悲鳴をあげているがオッチャンの脚は変わらず岩のようにゴロゴロ動いてクーラーから冷風を吹き出させる。
汗みどろになったシャツが肌に張り付く。クーラーの冷風が寒く感じられるが体の芯は冷えることなく熱をもっている。自転車をこぎ続けるからだ。ジャケットはもう必要ない。屈伸運動をしてふくらはぎを騙し騙しオッチャンと交代する。
「クーラーは良えなあ。こんなに良えもんやったなんて忘れとったなあ」
自転車をこぐだけで必死で答えられない啓太にはかまわずオッチャンは語る。
「オッチャンだけやったらクーラーはつけんのや。なんでかわかるか?」
啓太はかろうじて首を縦に振って見せることができた。
「ほなら、またこぎに来てくれるか」
もう啓太にはうなずくだけの力も残っていない。返事もできずにハンドルにもたれかかる。ブウンという音が止まっても冷風はしばらく吹き続けた。
「おー、もう明るくなっとるなあ」
ブルーシートをかき分けたオッチャンがまぶしそうに目をしばたたく。夏の朝日とセミの声が小屋に入り込む。
「ばあちゃんが言ってたけど」
オッチャンが振り返る。啓太はぐしょぐしょになった袖で顔の汗をぬぐう。
「セミは七日しか生きないなんて大ウソだって」
「なんや、だれかに騙されとったんか? セミは七日ぽっちしか生きんて?」
啓太はうなずく。
「良かったなあ」
オッチャンはない歯を見せて笑う。
「ばあちゃんがおらなんだら、セミに笑われるところやったなあ」
啓太はうつむく。
「これからは笑われっぱなしだ」
オッチャンは大きくブルーシートを引き開ける。
「今日はえらい良え天気や。自転車日和や」
早朝だというのにすでに蒸した空気は毛布のように重く肌にまとわりつく。
「よっしゃ。もひとつこぐか」
「もう無理だよ。脚がパンパンなんだ」
「ならクーラーの前におり。オッチャンがいくらでもこぐ」
ブルーシートを開けて熱気にさらされたままオッチャンはブゥンブゥンと自転車をこぐ。スポットクーラーは冷風を吹き出す。オッチャンの額の汗が止まらない。
啓太はシャツの袖で顔をぬぐう。ぼたぼたと涙が顎を伝って落ちる。祖母の四十九日の夜が明けた。今日、喪服を脱ぐ。
終電を逃して公園のベンチで手枕している啓太に話しかけたオッチャンには前歯が二本なかった。
「ついてこい。クーラーあるから」
着たきりスズメと祖母が言っていたなと思う。啓太が引きこもりつづけ着替えもろくにできなかった五年前のことだ。オッチャンの服は泥で煮しめたような色で着たきりスズメだったときの啓太と同じようなニオイを放っている。
かなり小柄なオッチャンの背中についていく。やや左に重心が傾いているような歩き方。七十歳は超えているだろうに軽やかに歩く。
「ここや、ここや」
ブロック塀に囲まれた空き地にブルーシートで組まれた小屋がある。オッチャンはシートを掻き分けて入っていく。啓太は顔だけを突っ込んでみた。
小屋の中はムッとしている。真っ暗で臭くて湿って暑くて不快指数が明らかに高い。
「待ってな。今クーラーつけるからよ」
ブゥンと重い音がした。小さな緑のランプが地面スレスレのところで光る。なにか機械が起動したようだ。ブゥンブゥンと鳴る音はモーター音のようだ。
灯りがともった。オッチャンが古臭い自転車にまたがり猛烈にペダルをこいでいる。自転車は台座に固定され台座から伸びるコードが屋根にくくりつけられた電灯と小屋の隅にある円筒形のスツール程度の大きさのスポットクーラーに接続されている。
「すぐに涼しくなるからな」
ブゥンブゥンと自転車が唸りを上げる。オッチャンの脚は筋肉の盛り上がりが岩のようだ。硬い岩がゴロゴロ動いてペダルをこいで電気を産む。
スポットクーラーから風が吹き出す。伸ばしっぱなしの啓太の髪を揺らす風はすぐに冷たくなった。冷風を逃さないために小屋に入りブルーシートをきちんと合わせて閉じる。
オッチャンの額に汗が浮いている。クーラーの風がオッチャンの背中に当たっても汗は流れ続ける。
「まあ、その辺に座りな」
オッチャンが顎で指し示したその辺にはガラクタが積み上げられていて座れそうにはない。チューハイの空き缶が詰め込まれたポリ袋の山と近所のスーパーの名前があるショッピングカートと煤だらけのだるまストーブを少しずつ押しやって作った隙間に太った体を押し込めた。
自転車のタイヤは見たこともないスピードで回転する。オッチャンの汗がしたたるごとに小屋は涼しくなっていく。
「オッチャンはなあ、こう見えても昔は競輪選手やったんや」
こいでいる自転車は競輪にはむかないだろうママチャリだ。
「万車券出したこともあるんや」
かけた金額の万倍儲かるということはかけた選手が不人気だったということだ。不人気だったが勝ったということだ。自慢になるのかならないのかわからないことを語るオッチャンの岩のような脚は止まらない。クーラーは冷え冷えと熱帯夜を小屋の外へ押し出す。膝を抱えて座る啓太の汗は止まった。
汗をかいて働く人は信用できると祖母が言っていたなと思う。万車券を出したオッチャンは常勝選手ではなかっただろうが信用できる人間だろう。汗が光る。
競輪も競馬も競艇も啓太はやらない。同じような体型の同じような動きをする人の中からたった一人を選びだす方法などわからない。だから同じ年頃の同じくらいの頭の出来の人たちと同じような動きが出来ない啓太は教室を飛び出したのだから。
「背広脱いだらどうや。暑いやろ」
黒のネクタイは外してジャケットのポケットに入れていた。分厚く黒いジャケットを着たままなのは泣けなかったからだ。終電をわざと逃したのも泣けなかったからだ。ブゥンブゥンとクーラーが啓太を冷やしてくれる。
オッチャンは祖母より十歳は年上だろうにオッチャンの脚はよく動く。日焼けした重い脚は猛然と回転する。オッチャンの顎から落ちる汗が地面に染みていく。クーラーが小屋を冷やせば冷やすほどオッチャンは汗をかく。啓太を熱帯夜から救うためにオッチャンが汗をかく。
立ち上がりジャケットを脱いでシャツの袖をまくり上げる。
「どうした?」
「かわるよ」
オッチャンはしばらく黙って啓太を見つめた。その間も岩のような脚は回転を続けた。
「ほうか」
オッチャンが脚を止めると電灯の明かりがぼんやりと薄れてふいっと消えた。
手探りで自転車のサドルを見つけてまたがりこぎだす。ペダルはいやに重い。歯を食いしばって右脚左脚と踏み込む。踏み込み踏み込む。踏み込み踏み込む。額に汗がにじむ。踏み込み踏み込む。踏み込み、ブゥンと音が鳴った。ブゥンブゥンとリズミカルに鳴る音に合わせて電灯が明るくなったり暗くなったりする。クーラーから風は出ない。
ブゥンブゥン。明滅。ブゥンブゥン。明滅。冷えていた小屋は少しずつ暑くなる。啓太はサドルから尻を浮かせて体重をかけてペダルを踏み込む。踏み込み踏み込む。電灯が明るくなりクーラーが風を吹き出す。オッチャンは風の吹き出し口に顔を近づけ目を細めた。
「涼しいのう。おかげで気持ちええわ」
啓太の顎からしたたり落ちる汗が地面にしみた。オッチャンと交代でクーラーの風を浴びて交代で自転車をこぐ。こいでもこいでもこぎたりない。
「おー、かわろか」
啓太のふくらはぎは悲鳴をあげているがオッチャンの脚は変わらず岩のようにゴロゴロ動いてクーラーから冷風を吹き出させる。
汗みどろになったシャツが肌に張り付く。クーラーの冷風が寒く感じられるが体の芯は冷えることなく熱をもっている。自転車をこぎ続けるからだ。ジャケットはもう必要ない。屈伸運動をしてふくらはぎを騙し騙しオッチャンと交代する。
「クーラーは良えなあ。こんなに良えもんやったなんて忘れとったなあ」
自転車をこぐだけで必死で答えられない啓太にはかまわずオッチャンは語る。
「オッチャンだけやったらクーラーはつけんのや。なんでかわかるか?」
啓太はかろうじて首を縦に振って見せることができた。
「ほなら、またこぎに来てくれるか」
もう啓太にはうなずくだけの力も残っていない。返事もできずにハンドルにもたれかかる。ブウンという音が止まっても冷風はしばらく吹き続けた。
「おー、もう明るくなっとるなあ」
ブルーシートをかき分けたオッチャンがまぶしそうに目をしばたたく。夏の朝日とセミの声が小屋に入り込む。
「ばあちゃんが言ってたけど」
オッチャンが振り返る。啓太はぐしょぐしょになった袖で顔の汗をぬぐう。
「セミは七日しか生きないなんて大ウソだって」
「なんや、だれかに騙されとったんか? セミは七日ぽっちしか生きんて?」
啓太はうなずく。
「良かったなあ」
オッチャンはない歯を見せて笑う。
「ばあちゃんがおらなんだら、セミに笑われるところやったなあ」
啓太はうつむく。
「これからは笑われっぱなしだ」
オッチャンは大きくブルーシートを引き開ける。
「今日はえらい良え天気や。自転車日和や」
早朝だというのにすでに蒸した空気は毛布のように重く肌にまとわりつく。
「よっしゃ。もひとつこぐか」
「もう無理だよ。脚がパンパンなんだ」
「ならクーラーの前におり。オッチャンがいくらでもこぐ」
ブルーシートを開けて熱気にさらされたままオッチャンはブゥンブゥンと自転車をこぐ。スポットクーラーは冷風を吹き出す。オッチャンの額の汗が止まらない。
啓太はシャツの袖で顔をぬぐう。ぼたぼたと涙が顎を伝って落ちる。祖母の四十九日の夜が明けた。今日、喪服を脱ぐ。