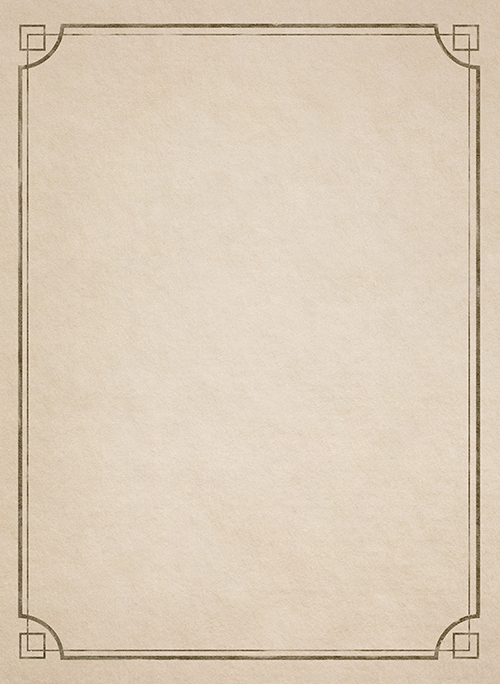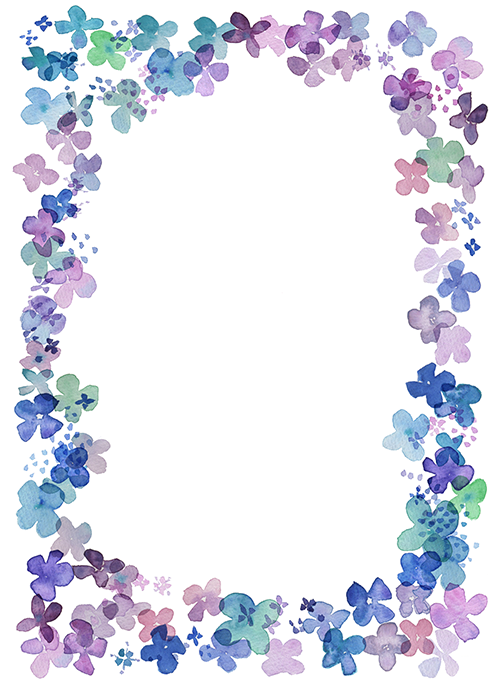俺の世界には色がなかった。
目に映るものすべてが、まるで何十年も前の古い映画みたいに白黒で、聞こえてくる音は分厚い壁の向こう側から聞こえてくるみたいに、どこか遠くてくぐもっている。それが当たり前の日常。それが、俺という人間の世界のすべてだった。
教室はいつも騒がしい。特に昼休みは最悪だ。昨日見た動画の話、次の予定、好きなやつの話。そういう、俺にとっては異世界の言語みたいに聞こえる会話の断片が、四方八方から飛んでくる。もちろん、俺はその輪の中にはいない。いるはずもない。だから、イヤホンは俺にとっての必需品だ。外部の音を遮断するための壁であり、誰にも話しかけさせないための盾。お気に入りのバンドの、激しいギターリフだけが、俺の世界で唯一、クリアに聞こえる音だった。
窓際の一番後ろ。そこが俺の定位置。特等席、なんて呼ぶやつもいるけど、俺にとってはただの隔離席だ。今日も今日とて、机の上に文庫本を開いて、熱心な読書家を演じている。別に物語に夢中になっているわけじゃない。これはポーズだ。一種の擬態。本の世界に没入している俺、というキャラクターを演じることで、周囲からのあらゆるコンタクトをシャットアウトする。誰とも目を合わせず、誰にも話しかけられず、ただ時間が過ぎるのを待つ。俺が学校生活で身につけた、数少ないスキルのひとつだ。
たまに、この演技すら面倒になるときがある。そういうときは、机に突っ伏して眠ったふりをする。もちろん、こんな騒がしい場所で眠れるわけがない。閉じたまぶたの裏側で、答えの出ない自問自答が無限にループするだけ。『どうして俺は、ここにいるんだろう』それを考えたって仕方ない。答えは分かってる。でも、思考は止まってくれない。まるで壊れたレコードみたいに、同じ問いを繰り返し、俺の意識を少しずつ削っていく。
別に、いじめられているわけじゃない。ただ、存在感がないだけだ。俺が休んだところで、たぶん誰も気づかない。その他大勢。風景の一部。それが俺。
他人に関心がない。たぶん周りからはそう思われているだろうし、俺自身、意識してそう振る舞っている。誰かと親しくなるのは、面倒くさい。期待して、がっかりして、勝手に傷つく。そんな馬鹿らしいことの繰り返し。だったら、最初から一人でいる方が、ずっとスマートで、楽に決まってる。何年もかけて、俺は自分の周りに『孤独』っていう名前の、高くて分厚い壁を築き上げた。そこは静かで、誰にも邪魔されない安全な場所。だけど、そこは時間が意味もなく、ゆっくりと流れる場所でもあった。
授業終了を告げるチャイムが鳴り渡ると、教室は解放感に満ちた空気に包まれる。一瞬にして活気づき、そこかしこでグループができて、楽しそうな声が上がる。そういう会話のすべてが、俺とは違う次元で交わされているみたいだった。俺は誰に挨拶するでもなく、誰からも呼び止められるでもなく、ゆっくりと自分の荷物をまとめる。まるでスローモーションの映像みたいに、周りの世界から俺だけが切り離されている。音のない映画のエキストラみたいに、静かに教室を出て、人の流れに乗って昇降口へ向かう。この一連の動きに、何の感情も乗っかっていない。ただ、毎日繰り返される、プログラムされた行動。それだけだった。
マンションに到着する。
オートロックを開けて、自宅マンションの廊下へ入る。自分の部屋のドアを開けると、いつもと同じ、しんとした冷たい空気が流れ出てきた。
「ただいま」
返事がないのは分かっている。それでも、この言葉を口にするのは、もう何年も続けている習慣だった。がらんとしたリビングに、俺の声が虚しく吸収されていく。この広い空間に、俺以外の生命の気配はない。
仕事人間だった両親は、俺が物心ついた頃からほとんど家にいなかった。最近じゃ、海外出張が当たり前になって、顔を合わせることなんて年に数回あるかないかだ。そんな親子関係をかろうじて繋ぎとめているのが、スマートフォンのメッセージアプリ。でも、そこに並ぶのは、業務連絡みたいな短い文章だけ。
『今月の生活費、振り込んでおきました』
『出張が長引くので、体に気を付けてね』
たまに送られてくる『体に気を付けてね』っていう一文が、せめてもの親心なんだろうか。だとしても、その文字からは何の温度も感じられなかった。最後に親父とオフクロの顔を見たのって、いつだっけ。思い出そうとしても、記憶には霞がかかったみたいに、ぼんやりとしていた。
夕食は、近所のコンビニで買ったカルビ弁当。電子レンジの『あたため』ボタンを押して、無機質な動作音を聞きながら数分待つ。チン、という軽い音と共に取り出した弁当は、熱いだけで、少しも美味そうには見えなかった。テレビやスマホを見る気すら起きない。だだっ広いダイニングテーブルの隅っこに座って、ただ黙々とプラスチックの箸を動かす。静寂が、まるでスパイスみたいに、食べ物の味をすべて消し去っていく。カチャ、という食器の音だけが、俺が今、ここで生きている唯一の証拠だった。
味気ない食事を終えると、俺は予備校へ行く準備を始めた。大学受験を控えた高校三年生の俺にとって、予備校は第二の学校みたいなものだ。隣の駅にあるその場所でも、俺のスタンスは学校と何も変わらない。誰とも喋らず、授業が終われば自習室にこもり、ひたすら参考書と睨めっこする。学校っていうコミュニティから逃げ出した先にも、結局は似たような孤独が広がっているだけ。それでも、家に一人でいるよりは、何かをしている方がマシだ。そんな消極的な理由だけで、自らの身体を引きずるようにして家を出た。
夜の道を駅まで歩く。電車に揺られながら、窓ガラスに映る自分の顔をぼんやりと眺めた。少し長めの黒髪がうっとうしく目にかかっている。生気のない、自分でも嫌になるような顔。場違いな雰囲気。俺は、いつからこんなに、世界の景色から浮き上がってしまったんだろう。そんな答えのない問いにふけっているうちに、電車は目的の駅に停車する。
予備校の授業は、眠気を誘う子守唄のようだった。有名だという講師の熱弁も、俺の耳にはただの単調なノイズとして届くだけ。蛍光灯の白い光が、机に広げたテキストの文字を冷たく照らしている。周りの連中は、みんな必死の形相でノートを取っていた。そのぎらついた熱意が、俺には眩しすぎて、直視できなかった。俺だけが、この空間で浮いている。そんな感覚が、じわじわと俺を追い詰めていた。
最後の授業が終わっても、俺はすぐには帰らなかった。閉館時間ギリギリまで、自習室の隅っこで時間を潰す。家に帰っても、待っているのは冷たい静寂だけだ。それなら、受験生に囲まれて、勉強している『フリ』をしている方が、まだ少しは有意義な時間を過ごしている気になれる。だが、そんなささやかな自己満足も、閉館の時間を迎えて、その終わりを迎えた。
やばい。
そう直感したのは、予備校のビルを飛び出して、駅へ向かう道を全力で走っている時だった。スマホの画面に表示された時刻は、とっくに最終電車の発車時刻を過ぎていた。なんで気づかなかったんだ、俺のバカ。自分の鈍感さを呪いながらも、諦めきれずに足を動かす。万に一つ、奇跡が起きて電車が遅れていやしないか。そんな淡い期待を抱いて。
駅の階段を、肺が張り裂けそうになるのも構わずに駆け上がる。息は切れ、喉の奥が鉄の味がした。ホームの方から、あの聞き慣れた発車のメロディが流れてくるのが聞こえた。ああ、終わった。そう思った瞬間、目の前のホームから、俺が乗るはずだった最後の電車が、ゆっくりと動き出すのが見えた。
固く閉ざされた電車のドア。窓の向こうには、疲れ切った顔のサラリーマンや、スマホに夢中な学生たちの顔が見える。彼らは、ホームで立ち尽くす俺のことなんて気にも留めずに、日常へと帰っていく。そして、赤いテールランプが、まるで俺をあざ笑うかのように、あっという間に夜の闇に消えていった。
俺が呆然と立ち尽くしていると、ホームの端にあった電光掲示板の表示が切り替わった。そこに現れたのは、『本日の営業は終了いたしました』という、あまりにも冷たくて、無慈悲な文字列だった。
喉の奥から、乾いたため息が漏れた。
どうする。マジでどうする。タクシーに乗る金なんて、当然持っていない。親に電話?いや、そもそも海外にいるんだから無理に決まってる。詰んだ。完全に詰んだ。
選択肢は、もう一つしか残されていなかった。この駅から、隣の駅にある自宅まで、歩いて帰る。ただ、それだけ。考えただけで、全身の力が抜け、地面にへたり込みそうになった。
駅前のロータリーは、もうほとんど人がいなかった。数台のタクシーが、手持ち無沙汰に客を待っている。その横を、俺は力なく通り過ぎた。そして、線路に沿って伸びる、街灯もまばらな暗い道を歩き始めた。この道が家への一番の近道だってことは、某マップアプリの情報で分かった。
街灯と街灯の間が、やけに遠い。明るい場所と暗い場所を、俺はゾンビみたいにふらふらと進んでいく。自分のスニーカーがアスファルトを蹴る、乾いた音だけが、やけに大きくこだましていた。時々、地鳴りのような音を立てて、貨物列車がすぐ横を通り過ぎていく。その圧倒的な鉄の塊と、耳を貫くような轟音に、自分のちっぽけな存在が根こそぎ消し去られてしまうような、不思議な安心感を覚えた。いっそのこと、このまま消えてなくなれたら、どんなに楽だろうか。
そんなネガティブな思考を繰り返しながら、どれだけの時間、歩き続けたんだろう。足はもう、自分のものじゃないみたいに重く、感覚がなかった。頭もぼーっとして、何も考えられない。ただ、家に帰らなきゃ、というぼんやりとした義務感だけが、俺の足を前に進ませていた。
その時だ。前方に、踏切が見えたのは。
カン、カン、カン、カン……。
単調で、どこか聞く者の心をかき乱すような警報音が、深夜のしじまに鳴り渡っていた。遮断機が下りていて、二つの赤いランプが、まるで意志を持っているかのように、交互に点滅を繰り返している。
もう旅客列車は走っていない時間だ。また貨物列車か。俺は足を止め、それが通り過ぎるのを待つことにした。
俺の視界の隅に、何かがちらりと映った。
遮断機の向こう。二本のレールが闇に吸い込まれていく、ちょうどその真ん中あたり。
何だ? 誰かが立っているのか?
目を細めて、暗がりを見つめた。
見間違いじゃない。夜の闇の中に、白い何かがぽつんと浮かび上がって見える。人だ。遠くてよく見えないが、尋常じゃない雰囲気が伝わってくる。白いセーラー服を着た女子生徒だった。
胸元の紺色のスカーフが見え、長い黒髪らしきものが輪郭をぼんやりと縁取っているのが分かる。
は? なんで? こんな真夜中に、踏切のど真ん中で、一人で何やってんだ? 自殺か。あるいは、何かヤバいことに巻き込まれているのか。どっちにしろ、関わったら面倒なことになるのは確実だ。見なかったことにして、さっさと通り過ぎるのが正解だ。
そう、頭では完璧に理解しているのに、俺の足はアスファルトに根が生えたみたいに、一歩も動かせなかった。その女子生徒から発せられる、言葉では説明できない、ただ事じゃない雰囲気を、肌で感じ取ってしまったからだ。
疲れてるんだ。そうだ、俺は、疲労のせいで幻覚を見てるんだ。深夜に何キロも歩いたんだから、無理もない。これは幻だ。非科学的なオカルトなんて、この世にあるわけがない。
そう必死に自分に言い聞かせても、俺の視線は、強力な磁石に引きつけられたみたいに、その女子生徒の姿から逸らすことができなかった。
その時、地響きと共に、さっきとは逆方向から、巨大な貨物列車が迫ってきた。二つのヘッドライトが闇を引き裂き、俺と女子生徒のいる空間を、昼間のように白く照らし出した。ゴオオオオッ、という轟音が空気を震わせ、巻き起こった猛烈な風圧が、俺の前髪をめちゃくちゃにかき上げた。俺は、あまりの眩しさに思わず目を細めた。
列車は、けたたましい金属音を立てて、女子生徒が立っていた、まさにその場所を通り過ぎていった。
俺は、息をすることさえ忘れて、その先を凝視していた。
何十両もある長い長い編成の貨車が、目の前を通り過ぎていく。そして、再び世界に静寂が戻った。ゆっくりと遮断機が上がり、耳障りだった警報音も止んだ。
女子生徒は、まだ、そこにいた。
俺が最初に見たのと、寸分たがわぬ場所に、寸分たがわぬ姿で。まるで、今しがた、自分の中を鋼鉄の巨体が通り抜けていったなんてこと、まるでありませんでした、とでも言うかのように。風に乱れた様子もなく、ただ、すっ、とそこに立っている。その神々しささえ覚える姿は、もはや美しいというより、畏怖の対象だった。
ありえない。
そんなこと、絶対にありえない。
もし、彼女が物理的にそこに存在していたなら、今頃、跡形もなくなっているはずだ。こんな風に、平然と立っていられるわけがない。
背筋に、冷たいものが走った。手足の指先から、急速に血の気が引いていくのが分かった。全身の産毛が逆立つような、原始的な感覚。これが、理解を超えたものに対する本能的な反応なのか。
その女子生徒が、まるでスローモーションの映像みたいに、ゆっくりと、こちらに顔を向けた。
その瞬間、俺の目に飛び込んできたのは、腰まである長い黒髪がふわりと流れる様子だった。
どうしてこんな暗闇の中で、髪の一本一本まで分かるんだ?
まるで絹糸みたいに滑らかで、濡れたような艶まで感じられる。その光景が俺の目に焼き付いた。
そして、振り向いたその顔を見た瞬間、俺は言葉を失った。
その彼女の顔色に血の気が感じられなかった。それなのに、いや、それだからこそか、人間離れした美しさが際立って見えた。
そして、何よりも俺の目を釘付けにしたのは、その瞳だった。
長いまつ毛に縁取られた大きな瞳が、こちらをまっすぐに見つめている。何の感情も読み取れない。ただ、どこまでも深くて暗くて、見ているうちに吸い込まれそうな気がしてくる。
その瞳にまっすぐに見つめられた瞬間、俺が感じていた畏れさえ、どこか遠い出来事のように感じ始めていた。
世界から、音が消えた。
自分の呼吸の音も、周囲の物音も、何も聞こえない。まるで時間が止まってしまったような、不思議な感覚。俺の視界には、目の前の非現実的なほどに美しい少女の姿だけが、写真みたいに焼き付いていた。
やがて、彼女の薄い唇が、ほんの少しだけ、動いた。
「…見えて、いるのですか?」
その声は、綺麗な鈴の音を思わせるほどに澄み切っていた。だけど、全く現実感がなくて、まるで俺の頭の中に直接、その言葉がダウンロードされたみたいだった。心の最も柔らかな部分に、そっと染み込んでくるような、不思議な声だった。
俺は答えられない。声を出そうにも、喉がぎゅっと締め付けられたみたいに、ひとかけらの音も出てこなかった。イエスもノーも言えない。彼女の圧倒的な美しさと、この異常な状況とが、俺の思考回路を完全にショートさせていた。まるで体中の自由を奪われたみたいに、ただその場に立ち尽くすことしかできなかった。
俺のフリーズしたような反応を見て、彼女は何かを理解したようだった。それまでの能面のような無表情に、ほんのわずかな、さざ波のような変化が生まれた。静寂を保っていた大きな瞳が、ほんの少しだけ見開かれる。それは、純粋な驚きだったのかもしれない。あるいは、もっと別の、俺なんかの想像もつかないような感情だったのか。
彼女は、もう一度、今度はさっきよりもはっきりとした、確信のこもった声で言った。
「あなたには、私が見えているのですね」
それは、問いかけではなく、事実の確認だった。
その言葉に、俺は、見えない何かに操られているみたいに、小さく、そしてゆっくりと、こくりと頷いてしまった。なんでそんなことをしたのか、自分でもまったく分からなかった。ただ、目の前の、この美しすぎる存在を、否定することなんてできっこなかった。そうするのが当たり前のように、首が勝手に動いた。
俺の肯定を、その大きな瞳で真正面から受け止めた少女は、その整いすぎた顔に、ゆっくりと、本当にゆっくりと、微笑みを浮かべた。
それは、何百年も固く閉ざされていた花が、生まれて初めて綻び始める瞬間を目撃するような、奇跡的な光景だった。
まず、感情を映さなかった瞳に、微かな、柔らかな気配がともる。そして、ずっと一文字に結ばれていた唇の片端が、ためらうように、ほんの少しだけ持ち上がる。やがて、それがゆっくりと広がり、完璧な弧を描く。
その微笑みは、俺が今まで生きてきた中で見てきた、どんなものよりも美しかった。
ああ、綺麗だ。
畏れも、混乱も、自分が置かれた異常な状況も、その瞬間、すべてが頭から消し飛んだ。ただ、目の前の少女の微笑みだけが、俺の世界の全てだった。ずっと俺の世界を覆っていた、分厚くて、うっとうしい灰色のフィルターが、剥がれ落ちていくように感じていた。
「よかった」
心の底から、本当に、本当に安堵したような、そんな一言。その言葉が俺の鼓膜を震わせて――今までくぐもって聞こえていた周囲の音が、急にボリュームを上げたみたいに、鮮明に、クリアに、俺の耳に飛び込んできた。遠くで鳴っている救急車のサイレンの音。草むらで合唱する虫たちの声。そして、忘れていた、俺自身の、ドクン、ドクンと激しく波打つ命の音。
さっきまで点滅していた踏切の信号機は、こんなにも目に焼き付くような、鮮烈な赤色だったのか。遠くに見える夜景や星が見える空はこれほどまでに力強い色を持っていたのか。これまで色のなかった白黒の世界に、奔流のように、色が流れ込んでくる。
そして、目の前にいるはずの少女のセーラー服は――。
はっとして、俺は少女が立っていた場所に視線を戻した。
だが、そこに彼女の姿はなかった。
さっきまで、間違いなくそこにいたはずの、まばゆいほどの純白が、忽然と消え失せている。まるで、最初から何もなかったかのように。後に残されたのは、ただ闇に続く二本のレールと、空虚な静寂だけだった。
幻覚。やはり、そうだったのか。終電を逃し、何キロも歩いた疲労が生み出した、あまりにも鮮明で、美しい、ただの幻。そう思った瞬間、安堵に似た感情と、それとは正反対の、説明のできない喪失感が、同時に胸の内に広がった。色づいた世界が、またあの灰色の風景に戻ってしまうのではないかという、漠然とした不安が頭をよぎる。
俺は、あまりの混乱に、一度強くまぶたを閉じた。そして、もう一度、ゆっくりと目を開けた、その時だった。
「……?」
すぐ目の前から、吐息ともつかない、かすかな声が聞こえた。
視線を下ろすと、そこには、信じられないほど間近に、彼女の顔があった。さっきまで遮断機の向こうにいたはずの少女が、俺が瞬きをするほんのわずかな間に、音もなく、気配もなく、俺の目と鼻の先に立っていたのだ。
全身の産毛が逆立つような、本能的な警鐘が鳴り響いた。だが、それ以上に、至近距離で見る彼女の人間離れした美しさが、俺の思考を完全に停止させた。恐怖という感情が、目の前の圧倒的な美しさに塗り潰されていく。
夜の闇を溶かして作ったかのような、どこまでも深い瞳。その中に、戸惑った様子の俺の顔が、小さく映り込んでいる。わずかに開かれた唇は、まるで熟す前の果実のようで、その非人間的なまでの完璧な造形を前に、俺は呼吸の仕方さえ忘れてしまっていた。声が出ない。それは恐怖による金縛りなどではなかった。この世のものとは思えない芸術品を前にした時のような、畏敬の念。そして、それを目に焼き付けたいという、抗いがたい欲求。怖い、はずなのに、それ以上に、もっと見ていたい。
「あの……そんなに驚かなくても。大丈夫ですか?」
彼女は、こてん、と効果音がつきそうなほど無垢な動きで首を傾げた。心配そうに俺の顔を覗き込む彼女の表情は、自分の移動方法が相手にどれほどの衝撃を与えたのか、まったく理解していないようだった。
「ごめんなさい。驚かすつもりは、なかったんです。ただ……」
彼女はそう言うと、どこか嬉しそうに、そして少しだけ恥ずかしそうに目を伏せた。
「どうしてか、あそこの踏切から一歩も動けなくて。でも、あなたが私を見つけてくれたから、もう、大丈夫みたい。あなたが私を見つけてくれたから……私、もう一人じゃないんです。なんだか……あなたと私、見えない赤い糸で結ばれちゃった、のかもしれませんね」
赤い糸。その言葉は、俺が置かれた異常な状況には、あまりにも不釣り合いで、ロマンチックだった。この子は、自分の存在が何なのか、どうして踏切から動けなかったのか、たぶんよく分かっていないんだろう。ただ、俺と出会えたことで、その呪縛のようなものから解放された。その純粋な喜びだけを、伝えようとしてくれている。その健気さが、俺の警戒心を、いともたやすく解いていった。
「あ……あの、そろそろ行かないと」
俺は、このままここにいたら、この美しい存在に飲み込まれてしまうような気がして、逃げ出すように踵を返した。自宅まで、まだ距離がある。
「はいっ」
俺が歩き出すと、すぐ後ろから、弾むような明るい返事が聞こえてきた。振り返る気にはなれなかったが、彼女が数歩後ろを、ふわりとついてきている気配ははっきりと感じられた。
踏切から離れ、再び自宅へと向かう道を歩き始める。だが、さっきまでの道のりとは、何もかもが違って見えた。アスファルトの黒、センターラインの白、道端の雑草の緑。その一つ一つが、脳に直接焼き付けられるように鮮やかだ。俺の足は、自然と速度を落としていた。
「……あかり」
不意に、隣から少女の小さな呟きが聞こえた。彼女が見つめていたのは、道端に設置された、ごく普通の自動販売機だった。煌々と光を放つ、ただの機械。俺にとっては、見慣れた夜の風景の一部でしかない。彼女は、言葉を発するというより、ただ、その光景に心を奪われているようだった。その姿を見ていると、この子は本当に、長い間、同じ場所にいたのかもしれない、と漠然と思った。彼女がなぜあの踏切から動けなかったのか、俺には知る由もない。ただ、その純粋な反応が、彼女の置かれていた異常な状況を、何よりも雄弁に物語っていた。
「あの……きみの、名前は?」
俺は、たまらずに聞いた。この不思議な同伴者を、いつまでも「きみ」と呼ぶわけにはいかないだろう。
俺の問いに、少女は少しだけ驚いたように目を丸くした。そして、すぐに、ふわりと花が綻ぶような微笑みを浮かべた。
「柊、と申します。柊ユイ、です」
「ひいらぎ、ゆい……」
冬の静けさを思わせる、清らかな響き。彼女の持つ、どこか儚い雰囲気に、あまりにも似合いすぎている名前だった。
「はい」
ユイは、嬉しそうに頷くと、今度は期待を込めた眼差しで、まっすぐに俺を見つめてきた。
「あの……よろしければ、あなたのお名前も、教えていただけますか?」
俺は、一瞬、言葉に詰まった。自分の名前。そういえば、最後に誰かに自分から名乗ったのは、いつのことだっただろうか。クラスの人間は俺の名前を知っているだろうが、それはクラスのグループトーク上にいる無色透明で無害な記号でしかない。そもそも、誰かが俺を、名前で呼ぶことなんて、もうずっと長い間なかった。
俺が口ごもっていると、ユイは何かを察したように、慌てて付け加えた。
「あ、ごめんなさい。言いたくなければ、無理にとは……」
「……神楽」
彼女の言葉を遮るように、俺は、ようやくそれだけを口にした。
「神楽リョウスケだ」
自分でも驚くほどに、ぶっきらぼうで、低い声が出た。
だが、ユイはそんな俺の態度を気にする様子もなく、俺の名前を、宝物のように、そっと口の中で確かめるように繰り返した。
「かぐら……りょうすけくん」
その声は、ただの名前の確認ではなかった。まるで、世界でたった一つの大切な言葉を見つけたかのように、優しくて、慈しむような響きを持っていた。自分の名前を、こんな風に呼ばれたのは、生まれて初めてのようにすら感じた。
「はい、神楽くん。よろしくお願いしますね」
そう言って、ユイは悪戯っぽく微笑んだ。
ぎこちない沈黙の中、二人で夜道を歩く。いや、一人と、一体か。ユイは、しばらく静かだったが、やがて、ぽつりと言った。
「コンビニ、ですね。昔は、学校の帰りに、よく友達と寄りました。アイスを買って、お店の前で食べるのが、すごく好きだったんです」
彼女の視線の先には、煌々と明かりを灯すコンビニエンスストアがあった。その横顔は、懐かしさと、ほんの少しの寂しさを帯びていた。
「生きていたら、今頃、どんなアイスが出ていたのかな、とか。友達と、やっぱりこっちの方が美味しかったって、笑い合ったり、できたのかなって」
その言葉は、俺の胸の奥に、小さな棘のように、ちくりと刺さった。彼女が失った「もしも」の世界。俺が当たり前のように享受し、そして持て余している日常。
「……何か、食うか?」
気づいたら、そんな言葉が口をついて出ていた。
ユイは、俺の言葉に、一瞬だけ、はっとしたように目を見開いた。そして、すぐに、寂しさと嬉しさが織りなすような、複雑な微笑みを浮かべた。
そして、しまった、と思った。彼女は、幽霊なのだ。おそらく、何かを食べられるわけがない。だとすれば、あまりにも無神経な一言だった。
「お気持ちだけで、十分です。神楽くんが食べているところを、見せてくださいませんか?それだけで、私も、あの頃に戻れたような気持ちになれますから」
その健気な言葉に、俺は何も言えなくなった。
ただ、黙ってコンビニに入り、一番新しい味だというアイスを一つだけ買って、店の前のベンチに腰掛けた。ユイは、俺の隣に、ちょこんと座る。俺の隣に、彼女がいる。その事実が、奇妙なほど俺の心を落ち着かせた。
アイスの包装を破る。パリ、という乾いた音が、静かな夜に小さく響いた。一口かじる。冷たいバニラの甘さが、口の中に広がった。うまい、と思った。昨日まで、まるで砂を噛むようだった食事が、嘘のようだった。食べ物に、味がする。これも、彼女のせいなのだろうか?それは分からなかったが、一つだけ言えるのは、隣のユイが、楽しそうに見ていることだけだった。
「どうです? 美味しいですか?」
「……まあ」
素直にうまいと言うのがなんだか癪に触って、そっけない返事をする。それでも、彼女は嬉しそうだった。
「よかった。誰かが食事をしているのを、こんなに間近で見ることが、初めてな気がします。なんだか、私までお腹がいっぱいになってくるような気がします」
彼女は、自分が食べるわけでもないのに、本当に幸せそうに、俺がアイスを食べる様子を眺めている。
その姿を見ていると、なんだか調子が狂ってしまう。
いつもは五分もかからずに終えるようなものを、その日は十分以上かけて、ゆっくりと食べた。静寂は、もうそこにはなかった。代わりに、彼女の穏やかな声と、俺が立てる微かな音が、がらんとした夜の空気を満たしていた。
それは、孤独とは違う、不思議な静けさだった。
食べ終えたアイスの棒をゴミ箱に捨て、再び歩き出す。ユイは、さっきよりも少しだけ、元気になったように見えた。
深夜の静まり返った道で、彼女はふと足を止めた。
「私がいた頃は、みんな折りたたみ式の携帯電話でした。ボタンを押すたびに『ピッピッ』と音がして、メールを打つのに慣れていったものです」
ユイは遠い目をして、もう閉店している携帯ショップを見つめていた。そこにあるポスターには、スマホの割引キャンペーンの広告。
「あれが、今の最新機種なのですね」
彼女の声には、置き去りにされた時間への切ない響きが込められていた。
「あの踏切で、どれくらいの時が過ぎるのを見ていたのでしょう。気がついたら、世界はこんなにも変わっていて……私だけが、あの場所で止まったままで…」
その言葉は、俺の胸に小さく突き刺さった。俺が当たり前のように過ごしている日々が、彼女にとってはもう手の届かない、遠い出来事なのだと思うと、胸の奥が重くなった。
しばらく無言で歩いていると、ユイが小さくつぶやいた。
「でも、神楽くんに見つけてもらえて、本当によかった。一人で、あの場所にいた時間がどれほど長かったとしても、今こうして、誰かと一緒に歩けているなんて」
彼女は俺の横顔を見上げて、安らかな笑みを浮かべた。
その純粋な信頼に、俺は何と答えていいか分からなかった。
横を歩く彼女の髪が、月の光を受けて絹のように輝いているように見えた。
「私、神楽くんと出会えて、本当によかった」
ユイの言葉が周囲に優しく響き渡った。
「ああ。」
俺は辛うじてそれだけ答えた。
そうだ、確かに俺は、彼女に呪われたのかもしれない。
けれども、それは決して悪い気分のするものではなかった。
目に映るものすべてが、まるで何十年も前の古い映画みたいに白黒で、聞こえてくる音は分厚い壁の向こう側から聞こえてくるみたいに、どこか遠くてくぐもっている。それが当たり前の日常。それが、俺という人間の世界のすべてだった。
教室はいつも騒がしい。特に昼休みは最悪だ。昨日見た動画の話、次の予定、好きなやつの話。そういう、俺にとっては異世界の言語みたいに聞こえる会話の断片が、四方八方から飛んでくる。もちろん、俺はその輪の中にはいない。いるはずもない。だから、イヤホンは俺にとっての必需品だ。外部の音を遮断するための壁であり、誰にも話しかけさせないための盾。お気に入りのバンドの、激しいギターリフだけが、俺の世界で唯一、クリアに聞こえる音だった。
窓際の一番後ろ。そこが俺の定位置。特等席、なんて呼ぶやつもいるけど、俺にとってはただの隔離席だ。今日も今日とて、机の上に文庫本を開いて、熱心な読書家を演じている。別に物語に夢中になっているわけじゃない。これはポーズだ。一種の擬態。本の世界に没入している俺、というキャラクターを演じることで、周囲からのあらゆるコンタクトをシャットアウトする。誰とも目を合わせず、誰にも話しかけられず、ただ時間が過ぎるのを待つ。俺が学校生活で身につけた、数少ないスキルのひとつだ。
たまに、この演技すら面倒になるときがある。そういうときは、机に突っ伏して眠ったふりをする。もちろん、こんな騒がしい場所で眠れるわけがない。閉じたまぶたの裏側で、答えの出ない自問自答が無限にループするだけ。『どうして俺は、ここにいるんだろう』それを考えたって仕方ない。答えは分かってる。でも、思考は止まってくれない。まるで壊れたレコードみたいに、同じ問いを繰り返し、俺の意識を少しずつ削っていく。
別に、いじめられているわけじゃない。ただ、存在感がないだけだ。俺が休んだところで、たぶん誰も気づかない。その他大勢。風景の一部。それが俺。
他人に関心がない。たぶん周りからはそう思われているだろうし、俺自身、意識してそう振る舞っている。誰かと親しくなるのは、面倒くさい。期待して、がっかりして、勝手に傷つく。そんな馬鹿らしいことの繰り返し。だったら、最初から一人でいる方が、ずっとスマートで、楽に決まってる。何年もかけて、俺は自分の周りに『孤独』っていう名前の、高くて分厚い壁を築き上げた。そこは静かで、誰にも邪魔されない安全な場所。だけど、そこは時間が意味もなく、ゆっくりと流れる場所でもあった。
授業終了を告げるチャイムが鳴り渡ると、教室は解放感に満ちた空気に包まれる。一瞬にして活気づき、そこかしこでグループができて、楽しそうな声が上がる。そういう会話のすべてが、俺とは違う次元で交わされているみたいだった。俺は誰に挨拶するでもなく、誰からも呼び止められるでもなく、ゆっくりと自分の荷物をまとめる。まるでスローモーションの映像みたいに、周りの世界から俺だけが切り離されている。音のない映画のエキストラみたいに、静かに教室を出て、人の流れに乗って昇降口へ向かう。この一連の動きに、何の感情も乗っかっていない。ただ、毎日繰り返される、プログラムされた行動。それだけだった。
マンションに到着する。
オートロックを開けて、自宅マンションの廊下へ入る。自分の部屋のドアを開けると、いつもと同じ、しんとした冷たい空気が流れ出てきた。
「ただいま」
返事がないのは分かっている。それでも、この言葉を口にするのは、もう何年も続けている習慣だった。がらんとしたリビングに、俺の声が虚しく吸収されていく。この広い空間に、俺以外の生命の気配はない。
仕事人間だった両親は、俺が物心ついた頃からほとんど家にいなかった。最近じゃ、海外出張が当たり前になって、顔を合わせることなんて年に数回あるかないかだ。そんな親子関係をかろうじて繋ぎとめているのが、スマートフォンのメッセージアプリ。でも、そこに並ぶのは、業務連絡みたいな短い文章だけ。
『今月の生活費、振り込んでおきました』
『出張が長引くので、体に気を付けてね』
たまに送られてくる『体に気を付けてね』っていう一文が、せめてもの親心なんだろうか。だとしても、その文字からは何の温度も感じられなかった。最後に親父とオフクロの顔を見たのって、いつだっけ。思い出そうとしても、記憶には霞がかかったみたいに、ぼんやりとしていた。
夕食は、近所のコンビニで買ったカルビ弁当。電子レンジの『あたため』ボタンを押して、無機質な動作音を聞きながら数分待つ。チン、という軽い音と共に取り出した弁当は、熱いだけで、少しも美味そうには見えなかった。テレビやスマホを見る気すら起きない。だだっ広いダイニングテーブルの隅っこに座って、ただ黙々とプラスチックの箸を動かす。静寂が、まるでスパイスみたいに、食べ物の味をすべて消し去っていく。カチャ、という食器の音だけが、俺が今、ここで生きている唯一の証拠だった。
味気ない食事を終えると、俺は予備校へ行く準備を始めた。大学受験を控えた高校三年生の俺にとって、予備校は第二の学校みたいなものだ。隣の駅にあるその場所でも、俺のスタンスは学校と何も変わらない。誰とも喋らず、授業が終われば自習室にこもり、ひたすら参考書と睨めっこする。学校っていうコミュニティから逃げ出した先にも、結局は似たような孤独が広がっているだけ。それでも、家に一人でいるよりは、何かをしている方がマシだ。そんな消極的な理由だけで、自らの身体を引きずるようにして家を出た。
夜の道を駅まで歩く。電車に揺られながら、窓ガラスに映る自分の顔をぼんやりと眺めた。少し長めの黒髪がうっとうしく目にかかっている。生気のない、自分でも嫌になるような顔。場違いな雰囲気。俺は、いつからこんなに、世界の景色から浮き上がってしまったんだろう。そんな答えのない問いにふけっているうちに、電車は目的の駅に停車する。
予備校の授業は、眠気を誘う子守唄のようだった。有名だという講師の熱弁も、俺の耳にはただの単調なノイズとして届くだけ。蛍光灯の白い光が、机に広げたテキストの文字を冷たく照らしている。周りの連中は、みんな必死の形相でノートを取っていた。そのぎらついた熱意が、俺には眩しすぎて、直視できなかった。俺だけが、この空間で浮いている。そんな感覚が、じわじわと俺を追い詰めていた。
最後の授業が終わっても、俺はすぐには帰らなかった。閉館時間ギリギリまで、自習室の隅っこで時間を潰す。家に帰っても、待っているのは冷たい静寂だけだ。それなら、受験生に囲まれて、勉強している『フリ』をしている方が、まだ少しは有意義な時間を過ごしている気になれる。だが、そんなささやかな自己満足も、閉館の時間を迎えて、その終わりを迎えた。
やばい。
そう直感したのは、予備校のビルを飛び出して、駅へ向かう道を全力で走っている時だった。スマホの画面に表示された時刻は、とっくに最終電車の発車時刻を過ぎていた。なんで気づかなかったんだ、俺のバカ。自分の鈍感さを呪いながらも、諦めきれずに足を動かす。万に一つ、奇跡が起きて電車が遅れていやしないか。そんな淡い期待を抱いて。
駅の階段を、肺が張り裂けそうになるのも構わずに駆け上がる。息は切れ、喉の奥が鉄の味がした。ホームの方から、あの聞き慣れた発車のメロディが流れてくるのが聞こえた。ああ、終わった。そう思った瞬間、目の前のホームから、俺が乗るはずだった最後の電車が、ゆっくりと動き出すのが見えた。
固く閉ざされた電車のドア。窓の向こうには、疲れ切った顔のサラリーマンや、スマホに夢中な学生たちの顔が見える。彼らは、ホームで立ち尽くす俺のことなんて気にも留めずに、日常へと帰っていく。そして、赤いテールランプが、まるで俺をあざ笑うかのように、あっという間に夜の闇に消えていった。
俺が呆然と立ち尽くしていると、ホームの端にあった電光掲示板の表示が切り替わった。そこに現れたのは、『本日の営業は終了いたしました』という、あまりにも冷たくて、無慈悲な文字列だった。
喉の奥から、乾いたため息が漏れた。
どうする。マジでどうする。タクシーに乗る金なんて、当然持っていない。親に電話?いや、そもそも海外にいるんだから無理に決まってる。詰んだ。完全に詰んだ。
選択肢は、もう一つしか残されていなかった。この駅から、隣の駅にある自宅まで、歩いて帰る。ただ、それだけ。考えただけで、全身の力が抜け、地面にへたり込みそうになった。
駅前のロータリーは、もうほとんど人がいなかった。数台のタクシーが、手持ち無沙汰に客を待っている。その横を、俺は力なく通り過ぎた。そして、線路に沿って伸びる、街灯もまばらな暗い道を歩き始めた。この道が家への一番の近道だってことは、某マップアプリの情報で分かった。
街灯と街灯の間が、やけに遠い。明るい場所と暗い場所を、俺はゾンビみたいにふらふらと進んでいく。自分のスニーカーがアスファルトを蹴る、乾いた音だけが、やけに大きくこだましていた。時々、地鳴りのような音を立てて、貨物列車がすぐ横を通り過ぎていく。その圧倒的な鉄の塊と、耳を貫くような轟音に、自分のちっぽけな存在が根こそぎ消し去られてしまうような、不思議な安心感を覚えた。いっそのこと、このまま消えてなくなれたら、どんなに楽だろうか。
そんなネガティブな思考を繰り返しながら、どれだけの時間、歩き続けたんだろう。足はもう、自分のものじゃないみたいに重く、感覚がなかった。頭もぼーっとして、何も考えられない。ただ、家に帰らなきゃ、というぼんやりとした義務感だけが、俺の足を前に進ませていた。
その時だ。前方に、踏切が見えたのは。
カン、カン、カン、カン……。
単調で、どこか聞く者の心をかき乱すような警報音が、深夜のしじまに鳴り渡っていた。遮断機が下りていて、二つの赤いランプが、まるで意志を持っているかのように、交互に点滅を繰り返している。
もう旅客列車は走っていない時間だ。また貨物列車か。俺は足を止め、それが通り過ぎるのを待つことにした。
俺の視界の隅に、何かがちらりと映った。
遮断機の向こう。二本のレールが闇に吸い込まれていく、ちょうどその真ん中あたり。
何だ? 誰かが立っているのか?
目を細めて、暗がりを見つめた。
見間違いじゃない。夜の闇の中に、白い何かがぽつんと浮かび上がって見える。人だ。遠くてよく見えないが、尋常じゃない雰囲気が伝わってくる。白いセーラー服を着た女子生徒だった。
胸元の紺色のスカーフが見え、長い黒髪らしきものが輪郭をぼんやりと縁取っているのが分かる。
は? なんで? こんな真夜中に、踏切のど真ん中で、一人で何やってんだ? 自殺か。あるいは、何かヤバいことに巻き込まれているのか。どっちにしろ、関わったら面倒なことになるのは確実だ。見なかったことにして、さっさと通り過ぎるのが正解だ。
そう、頭では完璧に理解しているのに、俺の足はアスファルトに根が生えたみたいに、一歩も動かせなかった。その女子生徒から発せられる、言葉では説明できない、ただ事じゃない雰囲気を、肌で感じ取ってしまったからだ。
疲れてるんだ。そうだ、俺は、疲労のせいで幻覚を見てるんだ。深夜に何キロも歩いたんだから、無理もない。これは幻だ。非科学的なオカルトなんて、この世にあるわけがない。
そう必死に自分に言い聞かせても、俺の視線は、強力な磁石に引きつけられたみたいに、その女子生徒の姿から逸らすことができなかった。
その時、地響きと共に、さっきとは逆方向から、巨大な貨物列車が迫ってきた。二つのヘッドライトが闇を引き裂き、俺と女子生徒のいる空間を、昼間のように白く照らし出した。ゴオオオオッ、という轟音が空気を震わせ、巻き起こった猛烈な風圧が、俺の前髪をめちゃくちゃにかき上げた。俺は、あまりの眩しさに思わず目を細めた。
列車は、けたたましい金属音を立てて、女子生徒が立っていた、まさにその場所を通り過ぎていった。
俺は、息をすることさえ忘れて、その先を凝視していた。
何十両もある長い長い編成の貨車が、目の前を通り過ぎていく。そして、再び世界に静寂が戻った。ゆっくりと遮断機が上がり、耳障りだった警報音も止んだ。
女子生徒は、まだ、そこにいた。
俺が最初に見たのと、寸分たがわぬ場所に、寸分たがわぬ姿で。まるで、今しがた、自分の中を鋼鉄の巨体が通り抜けていったなんてこと、まるでありませんでした、とでも言うかのように。風に乱れた様子もなく、ただ、すっ、とそこに立っている。その神々しささえ覚える姿は、もはや美しいというより、畏怖の対象だった。
ありえない。
そんなこと、絶対にありえない。
もし、彼女が物理的にそこに存在していたなら、今頃、跡形もなくなっているはずだ。こんな風に、平然と立っていられるわけがない。
背筋に、冷たいものが走った。手足の指先から、急速に血の気が引いていくのが分かった。全身の産毛が逆立つような、原始的な感覚。これが、理解を超えたものに対する本能的な反応なのか。
その女子生徒が、まるでスローモーションの映像みたいに、ゆっくりと、こちらに顔を向けた。
その瞬間、俺の目に飛び込んできたのは、腰まである長い黒髪がふわりと流れる様子だった。
どうしてこんな暗闇の中で、髪の一本一本まで分かるんだ?
まるで絹糸みたいに滑らかで、濡れたような艶まで感じられる。その光景が俺の目に焼き付いた。
そして、振り向いたその顔を見た瞬間、俺は言葉を失った。
その彼女の顔色に血の気が感じられなかった。それなのに、いや、それだからこそか、人間離れした美しさが際立って見えた。
そして、何よりも俺の目を釘付けにしたのは、その瞳だった。
長いまつ毛に縁取られた大きな瞳が、こちらをまっすぐに見つめている。何の感情も読み取れない。ただ、どこまでも深くて暗くて、見ているうちに吸い込まれそうな気がしてくる。
その瞳にまっすぐに見つめられた瞬間、俺が感じていた畏れさえ、どこか遠い出来事のように感じ始めていた。
世界から、音が消えた。
自分の呼吸の音も、周囲の物音も、何も聞こえない。まるで時間が止まってしまったような、不思議な感覚。俺の視界には、目の前の非現実的なほどに美しい少女の姿だけが、写真みたいに焼き付いていた。
やがて、彼女の薄い唇が、ほんの少しだけ、動いた。
「…見えて、いるのですか?」
その声は、綺麗な鈴の音を思わせるほどに澄み切っていた。だけど、全く現実感がなくて、まるで俺の頭の中に直接、その言葉がダウンロードされたみたいだった。心の最も柔らかな部分に、そっと染み込んでくるような、不思議な声だった。
俺は答えられない。声を出そうにも、喉がぎゅっと締め付けられたみたいに、ひとかけらの音も出てこなかった。イエスもノーも言えない。彼女の圧倒的な美しさと、この異常な状況とが、俺の思考回路を完全にショートさせていた。まるで体中の自由を奪われたみたいに、ただその場に立ち尽くすことしかできなかった。
俺のフリーズしたような反応を見て、彼女は何かを理解したようだった。それまでの能面のような無表情に、ほんのわずかな、さざ波のような変化が生まれた。静寂を保っていた大きな瞳が、ほんの少しだけ見開かれる。それは、純粋な驚きだったのかもしれない。あるいは、もっと別の、俺なんかの想像もつかないような感情だったのか。
彼女は、もう一度、今度はさっきよりもはっきりとした、確信のこもった声で言った。
「あなたには、私が見えているのですね」
それは、問いかけではなく、事実の確認だった。
その言葉に、俺は、見えない何かに操られているみたいに、小さく、そしてゆっくりと、こくりと頷いてしまった。なんでそんなことをしたのか、自分でもまったく分からなかった。ただ、目の前の、この美しすぎる存在を、否定することなんてできっこなかった。そうするのが当たり前のように、首が勝手に動いた。
俺の肯定を、その大きな瞳で真正面から受け止めた少女は、その整いすぎた顔に、ゆっくりと、本当にゆっくりと、微笑みを浮かべた。
それは、何百年も固く閉ざされていた花が、生まれて初めて綻び始める瞬間を目撃するような、奇跡的な光景だった。
まず、感情を映さなかった瞳に、微かな、柔らかな気配がともる。そして、ずっと一文字に結ばれていた唇の片端が、ためらうように、ほんの少しだけ持ち上がる。やがて、それがゆっくりと広がり、完璧な弧を描く。
その微笑みは、俺が今まで生きてきた中で見てきた、どんなものよりも美しかった。
ああ、綺麗だ。
畏れも、混乱も、自分が置かれた異常な状況も、その瞬間、すべてが頭から消し飛んだ。ただ、目の前の少女の微笑みだけが、俺の世界の全てだった。ずっと俺の世界を覆っていた、分厚くて、うっとうしい灰色のフィルターが、剥がれ落ちていくように感じていた。
「よかった」
心の底から、本当に、本当に安堵したような、そんな一言。その言葉が俺の鼓膜を震わせて――今までくぐもって聞こえていた周囲の音が、急にボリュームを上げたみたいに、鮮明に、クリアに、俺の耳に飛び込んできた。遠くで鳴っている救急車のサイレンの音。草むらで合唱する虫たちの声。そして、忘れていた、俺自身の、ドクン、ドクンと激しく波打つ命の音。
さっきまで点滅していた踏切の信号機は、こんなにも目に焼き付くような、鮮烈な赤色だったのか。遠くに見える夜景や星が見える空はこれほどまでに力強い色を持っていたのか。これまで色のなかった白黒の世界に、奔流のように、色が流れ込んでくる。
そして、目の前にいるはずの少女のセーラー服は――。
はっとして、俺は少女が立っていた場所に視線を戻した。
だが、そこに彼女の姿はなかった。
さっきまで、間違いなくそこにいたはずの、まばゆいほどの純白が、忽然と消え失せている。まるで、最初から何もなかったかのように。後に残されたのは、ただ闇に続く二本のレールと、空虚な静寂だけだった。
幻覚。やはり、そうだったのか。終電を逃し、何キロも歩いた疲労が生み出した、あまりにも鮮明で、美しい、ただの幻。そう思った瞬間、安堵に似た感情と、それとは正反対の、説明のできない喪失感が、同時に胸の内に広がった。色づいた世界が、またあの灰色の風景に戻ってしまうのではないかという、漠然とした不安が頭をよぎる。
俺は、あまりの混乱に、一度強くまぶたを閉じた。そして、もう一度、ゆっくりと目を開けた、その時だった。
「……?」
すぐ目の前から、吐息ともつかない、かすかな声が聞こえた。
視線を下ろすと、そこには、信じられないほど間近に、彼女の顔があった。さっきまで遮断機の向こうにいたはずの少女が、俺が瞬きをするほんのわずかな間に、音もなく、気配もなく、俺の目と鼻の先に立っていたのだ。
全身の産毛が逆立つような、本能的な警鐘が鳴り響いた。だが、それ以上に、至近距離で見る彼女の人間離れした美しさが、俺の思考を完全に停止させた。恐怖という感情が、目の前の圧倒的な美しさに塗り潰されていく。
夜の闇を溶かして作ったかのような、どこまでも深い瞳。その中に、戸惑った様子の俺の顔が、小さく映り込んでいる。わずかに開かれた唇は、まるで熟す前の果実のようで、その非人間的なまでの完璧な造形を前に、俺は呼吸の仕方さえ忘れてしまっていた。声が出ない。それは恐怖による金縛りなどではなかった。この世のものとは思えない芸術品を前にした時のような、畏敬の念。そして、それを目に焼き付けたいという、抗いがたい欲求。怖い、はずなのに、それ以上に、もっと見ていたい。
「あの……そんなに驚かなくても。大丈夫ですか?」
彼女は、こてん、と効果音がつきそうなほど無垢な動きで首を傾げた。心配そうに俺の顔を覗き込む彼女の表情は、自分の移動方法が相手にどれほどの衝撃を与えたのか、まったく理解していないようだった。
「ごめんなさい。驚かすつもりは、なかったんです。ただ……」
彼女はそう言うと、どこか嬉しそうに、そして少しだけ恥ずかしそうに目を伏せた。
「どうしてか、あそこの踏切から一歩も動けなくて。でも、あなたが私を見つけてくれたから、もう、大丈夫みたい。あなたが私を見つけてくれたから……私、もう一人じゃないんです。なんだか……あなたと私、見えない赤い糸で結ばれちゃった、のかもしれませんね」
赤い糸。その言葉は、俺が置かれた異常な状況には、あまりにも不釣り合いで、ロマンチックだった。この子は、自分の存在が何なのか、どうして踏切から動けなかったのか、たぶんよく分かっていないんだろう。ただ、俺と出会えたことで、その呪縛のようなものから解放された。その純粋な喜びだけを、伝えようとしてくれている。その健気さが、俺の警戒心を、いともたやすく解いていった。
「あ……あの、そろそろ行かないと」
俺は、このままここにいたら、この美しい存在に飲み込まれてしまうような気がして、逃げ出すように踵を返した。自宅まで、まだ距離がある。
「はいっ」
俺が歩き出すと、すぐ後ろから、弾むような明るい返事が聞こえてきた。振り返る気にはなれなかったが、彼女が数歩後ろを、ふわりとついてきている気配ははっきりと感じられた。
踏切から離れ、再び自宅へと向かう道を歩き始める。だが、さっきまでの道のりとは、何もかもが違って見えた。アスファルトの黒、センターラインの白、道端の雑草の緑。その一つ一つが、脳に直接焼き付けられるように鮮やかだ。俺の足は、自然と速度を落としていた。
「……あかり」
不意に、隣から少女の小さな呟きが聞こえた。彼女が見つめていたのは、道端に設置された、ごく普通の自動販売機だった。煌々と光を放つ、ただの機械。俺にとっては、見慣れた夜の風景の一部でしかない。彼女は、言葉を発するというより、ただ、その光景に心を奪われているようだった。その姿を見ていると、この子は本当に、長い間、同じ場所にいたのかもしれない、と漠然と思った。彼女がなぜあの踏切から動けなかったのか、俺には知る由もない。ただ、その純粋な反応が、彼女の置かれていた異常な状況を、何よりも雄弁に物語っていた。
「あの……きみの、名前は?」
俺は、たまらずに聞いた。この不思議な同伴者を、いつまでも「きみ」と呼ぶわけにはいかないだろう。
俺の問いに、少女は少しだけ驚いたように目を丸くした。そして、すぐに、ふわりと花が綻ぶような微笑みを浮かべた。
「柊、と申します。柊ユイ、です」
「ひいらぎ、ゆい……」
冬の静けさを思わせる、清らかな響き。彼女の持つ、どこか儚い雰囲気に、あまりにも似合いすぎている名前だった。
「はい」
ユイは、嬉しそうに頷くと、今度は期待を込めた眼差しで、まっすぐに俺を見つめてきた。
「あの……よろしければ、あなたのお名前も、教えていただけますか?」
俺は、一瞬、言葉に詰まった。自分の名前。そういえば、最後に誰かに自分から名乗ったのは、いつのことだっただろうか。クラスの人間は俺の名前を知っているだろうが、それはクラスのグループトーク上にいる無色透明で無害な記号でしかない。そもそも、誰かが俺を、名前で呼ぶことなんて、もうずっと長い間なかった。
俺が口ごもっていると、ユイは何かを察したように、慌てて付け加えた。
「あ、ごめんなさい。言いたくなければ、無理にとは……」
「……神楽」
彼女の言葉を遮るように、俺は、ようやくそれだけを口にした。
「神楽リョウスケだ」
自分でも驚くほどに、ぶっきらぼうで、低い声が出た。
だが、ユイはそんな俺の態度を気にする様子もなく、俺の名前を、宝物のように、そっと口の中で確かめるように繰り返した。
「かぐら……りょうすけくん」
その声は、ただの名前の確認ではなかった。まるで、世界でたった一つの大切な言葉を見つけたかのように、優しくて、慈しむような響きを持っていた。自分の名前を、こんな風に呼ばれたのは、生まれて初めてのようにすら感じた。
「はい、神楽くん。よろしくお願いしますね」
そう言って、ユイは悪戯っぽく微笑んだ。
ぎこちない沈黙の中、二人で夜道を歩く。いや、一人と、一体か。ユイは、しばらく静かだったが、やがて、ぽつりと言った。
「コンビニ、ですね。昔は、学校の帰りに、よく友達と寄りました。アイスを買って、お店の前で食べるのが、すごく好きだったんです」
彼女の視線の先には、煌々と明かりを灯すコンビニエンスストアがあった。その横顔は、懐かしさと、ほんの少しの寂しさを帯びていた。
「生きていたら、今頃、どんなアイスが出ていたのかな、とか。友達と、やっぱりこっちの方が美味しかったって、笑い合ったり、できたのかなって」
その言葉は、俺の胸の奥に、小さな棘のように、ちくりと刺さった。彼女が失った「もしも」の世界。俺が当たり前のように享受し、そして持て余している日常。
「……何か、食うか?」
気づいたら、そんな言葉が口をついて出ていた。
ユイは、俺の言葉に、一瞬だけ、はっとしたように目を見開いた。そして、すぐに、寂しさと嬉しさが織りなすような、複雑な微笑みを浮かべた。
そして、しまった、と思った。彼女は、幽霊なのだ。おそらく、何かを食べられるわけがない。だとすれば、あまりにも無神経な一言だった。
「お気持ちだけで、十分です。神楽くんが食べているところを、見せてくださいませんか?それだけで、私も、あの頃に戻れたような気持ちになれますから」
その健気な言葉に、俺は何も言えなくなった。
ただ、黙ってコンビニに入り、一番新しい味だというアイスを一つだけ買って、店の前のベンチに腰掛けた。ユイは、俺の隣に、ちょこんと座る。俺の隣に、彼女がいる。その事実が、奇妙なほど俺の心を落ち着かせた。
アイスの包装を破る。パリ、という乾いた音が、静かな夜に小さく響いた。一口かじる。冷たいバニラの甘さが、口の中に広がった。うまい、と思った。昨日まで、まるで砂を噛むようだった食事が、嘘のようだった。食べ物に、味がする。これも、彼女のせいなのだろうか?それは分からなかったが、一つだけ言えるのは、隣のユイが、楽しそうに見ていることだけだった。
「どうです? 美味しいですか?」
「……まあ」
素直にうまいと言うのがなんだか癪に触って、そっけない返事をする。それでも、彼女は嬉しそうだった。
「よかった。誰かが食事をしているのを、こんなに間近で見ることが、初めてな気がします。なんだか、私までお腹がいっぱいになってくるような気がします」
彼女は、自分が食べるわけでもないのに、本当に幸せそうに、俺がアイスを食べる様子を眺めている。
その姿を見ていると、なんだか調子が狂ってしまう。
いつもは五分もかからずに終えるようなものを、その日は十分以上かけて、ゆっくりと食べた。静寂は、もうそこにはなかった。代わりに、彼女の穏やかな声と、俺が立てる微かな音が、がらんとした夜の空気を満たしていた。
それは、孤独とは違う、不思議な静けさだった。
食べ終えたアイスの棒をゴミ箱に捨て、再び歩き出す。ユイは、さっきよりも少しだけ、元気になったように見えた。
深夜の静まり返った道で、彼女はふと足を止めた。
「私がいた頃は、みんな折りたたみ式の携帯電話でした。ボタンを押すたびに『ピッピッ』と音がして、メールを打つのに慣れていったものです」
ユイは遠い目をして、もう閉店している携帯ショップを見つめていた。そこにあるポスターには、スマホの割引キャンペーンの広告。
「あれが、今の最新機種なのですね」
彼女の声には、置き去りにされた時間への切ない響きが込められていた。
「あの踏切で、どれくらいの時が過ぎるのを見ていたのでしょう。気がついたら、世界はこんなにも変わっていて……私だけが、あの場所で止まったままで…」
その言葉は、俺の胸に小さく突き刺さった。俺が当たり前のように過ごしている日々が、彼女にとってはもう手の届かない、遠い出来事なのだと思うと、胸の奥が重くなった。
しばらく無言で歩いていると、ユイが小さくつぶやいた。
「でも、神楽くんに見つけてもらえて、本当によかった。一人で、あの場所にいた時間がどれほど長かったとしても、今こうして、誰かと一緒に歩けているなんて」
彼女は俺の横顔を見上げて、安らかな笑みを浮かべた。
その純粋な信頼に、俺は何と答えていいか分からなかった。
横を歩く彼女の髪が、月の光を受けて絹のように輝いているように見えた。
「私、神楽くんと出会えて、本当によかった」
ユイの言葉が周囲に優しく響き渡った。
「ああ。」
俺は辛うじてそれだけ答えた。
そうだ、確かに俺は、彼女に呪われたのかもしれない。
けれども、それは決して悪い気分のするものではなかった。