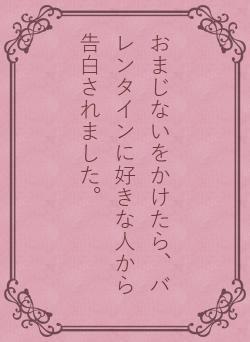文化祭が終わり、本格的な寒さが訪れ冬になった。冬になっても相変わらず空き教室に集まってご飯を食べたり、くっついたりして過ごしていた。
琥珀くんと付き合うようになってからの関係は付き合う前と比べると、少し変わった。どう変わったのかというと……。
「ねぇ、どうしてこっち向いてくれないの?」
「それはちょっと恥ずかしいと言いますか……」
「じゃあ俺がそっち行く」
「そういう問題じゃ……」
「だったらどういう問題なの!? ゆっきーが赤くなるの知ってるんだから、俺にもう隠さなくていいよ。なんなら見たいんだけど」
琥珀くんは僕と目を合わせようとして、右に行ったり左に行ったりと慌ただしい。そうしている原因は僕が顔を合わせてご飯を食べようとしないから。
琥珀くんはつき合い始めた途端、勢いが明らかに増した。前まではセーブしてくれていたみたいだけど、今はそうではないらしい。
それに対して僕は、まだ恥ずかしさがあると言って抵抗して手で顔を覆って隠したりしている。やっぱり着ぐるみを被っている、いないでは話が変わってくる。
「ゆっきーは俺が嫌い?」
「……っ、そんなことない! 僕は琥珀くんが大好き……。あ」
琥珀くんの言葉に乗せられて、背けていた顔を琥珀くんの方に向けて告白していた。
向けた先にいる満面の笑みを浮かべている琥珀くんは、「ふふっ、そっかー」と言葉にしている。
(またやられた)
何やらこのやりとりはゲームの一種みたいになっていて会うたびに行われている。僕はいつも琥珀くんにいいように言葉で揺さぶられて、負けている。悔しい。
「俺は、ゆっきーをいじめたい訳じゃないからね。俺もゆっきーが好きだから、顔が赤くてもいいから普通に時間を過ごしたいって思ってるんだよ」
琥珀くんは僕の手を取って優しく撫でた。大切なものを触るみたいに、傷つけないよう丁寧に触れようとする思いが感じられた。
(琥珀くんはこんな僕を選んでくれた。僕がいいって言ってくれたんだ。それに応えられないなんて彼氏失格じゃないか……)
僕は勇気を振り絞って、琥珀くんの手を握り返した。
(温かくて小さな手。自分から手を握ると違うんだな)
「……」
急に黙り込んだ琥珀くんの方を見ると、微かにだが顔と耳を赤くして固まっている。
「ん? 琥珀くん?」
──ボスッ。
琥珀くんが頭ごと倒れてきて、僕の胸に顔をうずめる体勢になった。何が起こったのか分からない僕は、ただ心配する。
「大丈夫? 気分悪い?」
「……大丈夫だけど、だいじょばない」
「それはどっち?」
「体調は大丈夫だけど、ゆっきーの不意にカッコよくしてくるところがだいじょばない!」
琥珀くんにそう言われたが、言っている意味が一切分からず頭の中ではハテナが駆け巡った。
どうしたらいいのか分からずそっとしていると、琥珀くんが思い切り顔をあげた。
「うおっ! びっくりした」
「ねぇ、ゆっきーは前にした約束覚えてる?」
唐突な質問に何のことを言われているのか、さっぱりだった。
「どの約束……、えっと、着ぐるみ脱げたら行こうって話してたカフェの?」
「そう! あれ、行こうよ」
「い、きたいけどまだ赤面克服したわけじゃないし……」
「そう言うけどさ、俺がいたら関係ないよね?」
──ギクッ。
僕はわかりやすく肩をビクつかせた。行きたくないわけじゃない。隣を歩いてて琥珀くんに恥をかかせちゃうのが嫌なだけ。
「俺は周りの目なんて気にしないよ。俺が気になっているのはゆっきーだけ。まぁ無理ならもう少し経ってからでも……」
冗談交じりに放たれた言葉が、心に響いた。
「──く」
「え?」
「行く。琥珀くんと一緒にカフェに」
「え、えーーー!!!」
琥珀くんの声は、廊下まで広がる大声を出して驚いていた。僕は今まで頑なに首を縦に振らなかったのに、行くとなればそりゃ驚くだろう。
「いいの? 人も多いし、それに俺がいるよ?」
「僕も約束した時から行ってみたいと思ってたんだ。それに琥珀くんのために赤くなるのって存外悪い気もしないんだよね」
僕はいたずらっ子のような笑みを浮かべ琥珀くんに気持ちを伝えた。
「ゆ、っき……。うー、俺の彼氏がイケメン過ぎてツラい……」
「僕も可愛くてカッコいい彼氏が隣にいてくれて、毎日が愛おしい」
本心からの言葉を言うと、今度は顔真っ赤にして俯いた。それを見た僕はよりいっそう愛おしい気持ちに包まれながら微笑んだ。
◇
冬休みに入り数日経ったある日、琥珀くんと約束していた遊園地とコラボしているカフェに行くことになった。
どこにいつ行くか決まったあたりから、ずっとソワソワしていた。着ていく服、髪型、持ち物、こんなにワクワクしながら用意したのは花火大会の時以来。
(珍しく自分で服買いに行ってみたけど、変じゃないかな?)
ショッピングモールのメンズ服を扱うお店で、店員さんから勧められた組み合わせを何着か着てみて、その中で気に入ったものを選んだ。
真っ白なパーカーに黒のスラックス、チェックのチェスターコートと少しシンプルだけど、大人な雰囲気が出ていて気に入っている。
「今更だけど、琥珀くんの服に合わせたらペアルック的なことできたのでは」
遊園地併設のカフェを選んだ時にその考えがあったならば、今ここで後悔はしていない。
「ねぇ、あの人カッコよくない?」
「1人なのかな? 話しかけてみる?」
琥珀くんを待っていると、近くから女性2人が猫なで声で話かけてきた。
「あのー、すみませぇーん。お兄さんお1人ですか?」
「え、まぁ(今は1人ですが)」
「よかったら私たちと一緒にー、遊……」
「雪兎、お待たせ!」
女性たち2人の声など聞こえなくなった。それは琥珀くんが少し離れたところから僕のことを呼んだから。
「え、何この子。可愛いんだけど」
女性2人は琥珀くんを見て心奪われているように見えた。
「すみません、俺の彼氏になにか用ですか?」
「え、あ、いえ。お邪魔しました」
女性たちは琥珀くんに声をかけられると、そそくさとその場を去って行った。
(なにか言いかけていた気がしたけど、気のせいかな)
「もう少し早くこればよかったや」
琥珀くんは渋い顔をしながら親指の爪を軽く噛む。
「どうして? 待ち合わせ時間の10分前だよ」
今でも早いのにもっと早く来ないとって凄い意識だなぁと感心する。琥珀くんは僕の顔を見てため息をついた。
「雪兎はもっとカッコいいことを自覚したほうがいいよ。さっきのナンパだから」
「ナンパ!? 僕が?」
「そうだよ! いつもよりカッコいいからさっきの人絶対惚れてる」
(そんな大げさなと言いたいけど、言ったら琥珀くんから睨まれそうだから言わないでおこう)
琥珀くんは僕の服の裾を強く握っている。僕のこと取られるかもと不安になって、無意識にそうしてしまっているなら申し訳ないけど少しだけ嬉しい。
「琥珀くん、今日はデートだよ。ナンパされたことなんて忘れて楽しもう!」
「デート……うん!」
僕は強く握られていた手を包み込んでギュッと手を繋いだ。
入場券を買って中に入った僕たちは、近くにあった園内マップをもらい広げてみた。
「せっかくなら遊園地で遊んでから行こうよ」という琥珀くんの案から、先に遊ぶことになっている。
「どれから回ろうか?」
「ねぇ、ゆっきー。まずはさ、これしない?」
目を輝かせて琥珀くんはあるところを指さした。それはカチューシャとかの被り物やグッズを売っている屋外ショップだった。
とてもやりたかったのか、引かれる手がものすごく強い。
「いらっしゃいませー」
エリアの世界観に合わせた制服を着たお姉さんが手を振って迎えてくれる。こういう時は振り返したらいいのかわからなくて困る。
「どれが似合うかな? ゆっきーは、やっぱりウサギがいいよね。これつけてみて」
「うん、分かった」
琥珀くんに渡された小さな王冠が付いたウサギのカチューシャをつけてみた。少し恥ずかしいけど、そんなことを言っていたら楽しむことできない。
「ゆっきー、似合い過ぎない?」
琥珀くんの1言に周りにいたお客さんたちやスタッフさんも頷いているのを見た。そんなに似合っているのだろうか。
「似合っているみたいだし、僕はこれにしようかな。琥珀くんはどうする?」
「わがままじゃないなら、ゆっきーに決めてもらいたい」
(こんな可愛いわがままってあるんだ)
「……いいよ。選んであげるね」
可愛さに悶えたいと思いつつ、僕は琥珀くんに似合う被り物を探した。改めて見るとたくさんの種類があるんだとわかる。
遊園地特有の顎のところで留める着ぐるみもどきや、僕が選んでもらったようなキャラクターモチーフの耳カチューシャ、期間限定コラボのカチューシャもあった。
(琥珀くんと言えば、可愛い、カッコいい、空手、どれもモチーフになるようなものじゃないな。うーん、あ!)
僕はショップを一回りして商品を見た。そして見つけた琥珀くんに似合うもの。
「琥珀くん、お待たせ」
「全然待ってないよ。すごく楽しみにしてた!」
「僕が琥珀くんのために選んだのは、これ」
僕は琥珀くんの頭に選んできた商品をあててみた。
選んだのは、名前にちなんだトラの可愛い丸耳のカチューシャ。僕には王冠が付いていたけど、琥珀くんの方は小さなティアラが付いている。
(ティアラだから女の子が付けるのを想定されているかもだけど、琥珀くんに似合う唯一無二の物だと思うな)
鏡を見た琥珀くんは「ゆっきー、これ可愛い!!」と、とても喜んでくれた。
僕たちはそれぞれのカチューシャを購入してアトラクションを目指した。どこもかしこも人が並び長蛇の列となっている。
「さて、どれから乗ろうか?」
「選んでいいの?」
「もちろん、琥珀くん楽しみにしてたもんね」
「楽しみだったけど、来れただけで満足しちゃってたや」
「そうなの? 僕はもっとはしゃいでる琥珀くんを見れるかもって期待したのにな」
「じゃ、じゃあジェットコースターに乗りたい。CMで流れてて気になってたの」
「行こうか」
僕は琥珀くんに手を差し伸べた。思いのほか僕も浮かれてるみたいだ。
「いいの?」
「いいのって。僕たちは付き合ってるんでしょ? いいも何も普通だよ」
「……っ! ゆっきー!」
「うおっ」
琥珀くんが勢いよく抱き着いてきたので、夏祭りとは違って今度は倒れないように僕はしっかりと受け止めた。力強く抱きしめてくる腕が愛おしい。
「よし、行こう!」
いつもは隣に並んで歩くだけだったけど、手を繋いで歩くのは一味違う気がした。告白をされた時のような幸せが込み上がってくる。
(離したくない。ずっと繋いでいたい)
僕は繋いだ手をギュッと握ると、琥珀くんも同じ力加減で握り返してくれた。これが僕たちの愛の証だと言いたくなるほどに。
ジェットコースターの列に並んで1時間半ほどで自分たちの番がやってきた。案内された座席の列は1番前。荷物置きに、鞄とカチューシャを預けて席に着く。
「久々に遊園地に来たから不安すぎる。今更だけど、ゆっきーは絶叫系大丈夫だった?」
「うーん、初めて来たから絶叫系いけるのかすらわからないかな」
「え? それって本当に大丈夫? 止めておいた方が……」
「前から乗ってみたいと思ってたから気にしなくていいよ。楽しもう!」
「ゆっきーがそう言うなら。でももし気分悪くなったら言うんだよ」
琥珀くんと話していると時間になり、係員がベルトとバーの確認に回ってくる。そして陽気なアナウンスが流れてくる。
「わんぱくコースターにお乗りくださりありがとうございます! これからハチャメチャなお散歩が始まります。途中にカメラが設置してあるところがありますので、お気付きになりましたらポーズお願いします! それではいってらっしゃーい」
4人くらいいる係員さんが全員手を振ってくれるのに対して、こちらも振り返したり「いってきまーす」と返事をする。
発射してすぐ、ゆっくりと勾配を登っていく。まだスピードが早くないから安心だ。
「俺、今すっごいドキドキしてる」
「僕も。なんて言ったらいいのかわからないけど、ワクワクして……るぅーうわぁぁぁ」
話しているといつの間にか頂上まで到達していたみたいで、コースターは購買のてっぺんから勢いよく降りていった。斜めや真横、回転なんてお手の物。
みんな声を出しているけど、僕は重力に耐えるのに必死だった。琥珀くんの方を見ると、手をバンザイしながら笑顔で楽しんでいる。
(琥珀くんすごい)
走っている速度が速いからどこまで来ているのか、カメラはどこかなんてわかるはずもなく、気がつけば乗り場に戻っていた。
「おかえりなさーい! バーを外しますので手を放してお待ちください。撮れたお写真はアトラクションの出口で販売しておりますので見て行ってくだいね。それではこの後もお楽しみくださーい」
乗っていた人たちは各自荷物を取って出口に向かって歩いていく。
「楽しかったね、ゆっきー。え、ゆっきー!?」
「うん。楽しかっ、たね。一瞬死んだおばあちゃんが手招きしてた気が……」
「それ絶対ダメだよね。ちょっと休憩しよう! えーっとあそこに座ってて」
琥珀くんが指さした先にあったベンチに座って目を瞑る。
しばらくして少しだけ回復した僕は、どこかへ行ってしまった琥珀くんが一向に帰ってこないことに心配になる。
「電話したほうがいいか」
スマホを取りだし、チャットアプリから電話を繋げようとした時「ごめん、お待たせ―!」と遠くから琥珀くんの声が聞こえた。
「遅かったね、どうしたの? 迷子になってた?」
「迷子にはなってないんだけど、心配させてごめん。とりあえず飲み物」
「ありがとう」
カップに入った冷たい飲み物を受け取り、ストローからごくごくと飲む。中はさっぱりとしたオレンジジュースだった。
「あのね、遅れたのはこれの所為なんだよね」
「これって」
琥珀くんが見せてくれたのは、フォトフレームに入っていたジェットコースターの写真だった。
(そういえば、出口からすぐにベンチに行ったんだった)
どこに設置していたのか分からないカメラの所為で、何ともまぁ写りが悪い。
右手をあげて思い切り叫んでいる琥珀くんと、目を閉じてバーを離すまいと必死にしがみ付く僕。だけど琥珀くんの左手と僕の右手は自然と繋がれていた。
「あれ、僕たち手繋いでたっけ?」
「これはカメラ見つけたから、勝手に繋いでみたの」
「カメラ見つけたんだ、すごい。ってそうじゃなくて、どうして──」
「ただ手を繋いでる写真ほしいなーと思って。改めて口にすると恥ずかしいんだけど」
いつもと逆で、今日は見た事ないくらい顔を赤くさせている琥珀くんを僕が見てる。
(こんなに想ってくれてるなんて、可愛いなぁ)
「琥珀くん、次は直接頼んでよ。写真、琥珀くんとなら何枚でも撮るから。ね?」
「……! 本当に!?」
「もちろん」
琥珀くんは向日葵のような温かい笑顔をみせた。
「じゃあ、1枚だけでいいから今撮りたい。ゆっきーが体調悪くなかったらだけど……」
(こんなに可愛いお願い聞いたことないよ)
つき合い始めてから、前よりも琥珀くんのことを可愛いと感じることが多くなった。今日もずっと可愛いの言葉が止まらない。
「いいよ。一緒に撮ろうか」
琥珀くんは僕の隣に座って、スマホのカメラを起動させる。色々と調整しているみたいだけど、そのことに関してはわからないからお任せしよう。
「じゃあ、ゆっきー撮るね。ハイチーズ」
──パシャ。
カメラロールを開くと、撮れた写真が1番前に来ていた。
「綺麗に撮れたね」
「うん! ありがとう、ゆっきー」
嬉しそうにしている琥珀くんを見て、僕も嬉しい気持でいっぱいになった。
「まだまだ回るんでしょ? だから色々な場所でたくさん写真を撮ろう!」
「うん!」
写真を撮り終わった後も座って少しだけ話をした。何をしたいのか、何に乗りたいのかを相談して決めていく。お陰で気が紛れて僕の体調も少しずつ回復してきた。
「お待たせ、そろそろ行こうか」
「もう大丈夫なの?」
「うん、休んだら治ってきたよ。でもまだ不安だから手を繋いでくれる? ……ってこんな誘い方は良くないね」
一度手を差し伸べたけど、引いて頬を掻いた。上手く誘えなくて反省するしかない。
(もっと上手に誘えたらカッコいいのに……)
左手が小さい手に包まれ、前にいた琥珀くんを見つめる。
「俺も、倒れられたら困るから支えるために手繋いであげる」
照れくさそうにしている琥珀くんが僕の手に触れている。僕が言った口実にノってくれるなんて思ってもいなかった。
(そういうところが可愛いんだけどね)
僕は強く握り返して、次の場所に向かって歩いた。
「次はメリーゴーラウンドだっけ、行こうよ」
「うん、楽しみ」
メリーゴーラウンドまではそんなに遠くなかったはず。でも僕は繋いだ手を離したくなくて、着かないで欲しいなと思ってしまった。
そんな願いとは裏腹にメリーゴーラウンドにはすぐについてしまい、幼い子たちがキャッキャとはしゃいでいる声が響き渡っていた。
「少し並んでいるみたい。やっぱり人気だね」
「小さい子たちの乗れるものなんて限られてるしね」
親子連れが多く並ぶ列の一番後ろに僕らも並んだ。楽しそうな姿に微笑ましく思っていると、前に並んでいた5歳くらいの女の子から声をかけられた。
「ねぇねぇおにいちゃん」
「ん? どうしたのかな」
「おにいちゃんたち、おててつないでるけどどうしてなの?」
思わぬ質問にお互いポカンとした。小さな子にそんなこと聞かれるとは思っていなかったからだ。
答えずらい話をしていることに気付いたその子の母親は、「何言ってるの! すみません」とその子を無理に前に向けようとしていた。
「大丈夫ですよ」
僕は琥珀くんと手を繋いだままその子と目線を合わせるようにしゃがんだ。
「お名前は?」
「しずか」
「しずかちゃん、可愛い名前だね。さっき聞いてくれたことについてお返事するね。僕たちは恋人同士、好きな人同士だから手を繋いでいるんだよ。しずかちゃんはママのこと好き?」
「うん! だいすきだよ!」
「そうだよね! しずかちゃんが大好きなママと手を繋ぐのと同じ、僕もこの人が好きだから手を繋いでるんだ。いいでしょ」
「うわぁ、ふたりはなかよしなんだね! わたしもママとなかよしだよ!」
「本当だね。あ、しずかちゃんの番が来たみたいだよ」
母親に連れられて柵の中に入ったしずかちゃん。目の前で列が別れてしまった僕たちはしずかちゃんが楽しそうに乗っている姿を見て笑顔になれた。
「どうしてあの子には話したの?」
「どうしてだろう。付き合うということが分からなくても、一緒にいたい大好きな人は色々な形で存在することを知ってほしかったのかも。それと嘘はいけないかなって」
「そっか。いい教育だね」
「でもお母さんに変なこと教えたって怒られないかな? 今はそれが一番の心配だよ」
「それはそうだね。もしそうなったら俺も一緒に謝ってあげる」
琥珀くんと笑いながらが柵が開くのを待った。
「次の方どうぞ―」
前の人達のターンが終り、やっと僕たちの番になった。どれに乗ろうかと話したら琥珀くんからのリクエストで、白馬に乗ることになった。琥珀くんは隣に並んでいる少し小さめの馬に乗った。
「それではお馬さんのお散歩が始まります。いってらっしゃーい」
スタッフの合図で回り始め、馬も上下したりしている。
「ゆっきー、やっぱり白馬似合うね! こっち向いてー」
ポケットからスマホを取りだした琥珀くんはスマホを向けている。
「撮れた?」
「うーん、ゆっきーごめん。これ動画」
「なんで教えてくれないの!」
「あはは」
写真だと思ってポーズを取っていた少しの間を思い出すと、途端に恥かしくなって少し顔回りが熱くなる。
「ははっ、ゆっきー真っ赤だね」
「誰の所為だと……」
「でもそれは普通に恥ずかしい感情からきたものだもんね」
言われてみれば、今日は琥珀くんに対して赤面するタイミングが少なかった。その分楽しい気持ちの方が上回っていた。
「琥珀くんと来れたことが楽しくて赤くなるってこと忘れてたや」
「ひう……。ゆっきー、つよぉ」
琥珀くんはスマホを持ちながら顔を覆った。完全に見えない隠し方で、どんな顔をしているのかわからなかった。
「琥珀くん、どうし……」
「おかえりなさーい! お散歩は楽しめたかな? また一緒にお散歩いこうねー」
手を伸ばしたタイミングとスタッフの声が被さった。先に馬を降りた琥珀くんは「早くいこ!」と先ほどまでの顔を赤くして照れていた態度とはうって変わって、元気になって出口に向かった。
「あ、おにいちゃーん」
しずかちゃんが待ってくれていたみたいで、出口に出た途端話しかけてくれた。琥珀くんもしずかちゃんに気付いたようで、足を止めた。
「あのね、これあげたくてまってたの」
「ん?」
見せてくれたのは、しずかちゃんが持っていたチェキカメラで撮った笑い合っている僕ら2人のチェキ。
「すみません、しずかがどうしてもお2人のこと撮ってあげたいって言うもので。ご迷惑でなければ、もらっていただけますか?」
「え、いいんですか?」
「もちろん。失礼な話、同性でおつき合いされている方を私も初めて見ました。遠ざけようとするのが一般的な親だと思うのですが、お2人がしずかに対して優しくてそれにお似合いだなと思って私も応援したくなりました」
つき合っていることをいつもなら隠している僕たちからすると、しずかちゃんや母親の言葉には勇気をもらった。
しずかちゃん親子と別れた後は、気ままに園内を歩きまわって空いてそうな乗り物に乗ったり、綺麗に咲いている花の道を通ったり、お昼を食べたりして気が付けば夕方になっていた。
そろそろ帰る時間が迫ってきたので、僕たちは最後に観覧車に乗ることにした。
混んでいたり、恋人同士が多いのかなと思っていたが、思いのほか観覧車には人が少なくすぐに乗り込むことができた。
「空いていてよかったね。観覧車までたくさん並んでたら諦めて帰るところだったよ」
「その時はまた並んで待てばいいよ」
「え?」
琥珀くんは諦めると言ったけど、僕は一緒に待つ方を選ぶ。
「今日みたいにどのアトラクションも並ばないと乗れないのなら、琥珀くんと並んで待って、最後の最後まで楽しいと思える景色を見たい」
琥珀くんの膝の上に乗せられた手に、自分の手を被せるように包み伝えた。言っている内容は恥ずかしいけれど、間違ったことは言っていないからよしとしよう。
「俺も待つ。ゆっきーと幸せな日常を忘れないために」
琥珀くんは僕の手をほどいて抱きしめてきた。ぎゅと強くなる力に僕も応える。
「雪兎、大好き」
「……僕も大好き。琥珀くん、愛してる」
知らぬ間に到着した頂上。誰も見ていない夕焼けの空間で、僕たちはいつもより長くキスをしてお互いの愛を確かめ合った。
「おかえりなさーい!」
外から鍵を開けてもらい「ありがとうございます」と言って降りた。
この時間になってもお客さんは思いのほかいるみたいで、建物から漏れる明かりがまぶしい。
手を繋いで売店に寄ると、それぞれ悩みながらお土産を探した。僕は鷹也と獅埜、それに両親と演劇部へ見繕っていた。
「いいの決まった?」
「お菓子系でも個数が合うのなくて悩んでるところ。琥珀くんは?」
「僕も同じ。家と入院している母さんには決まったんだけど、空手部の方がね」
琥珀くんのカゴに入っていたのは、動物の焼き印が入ったお饅頭と小さなトラのぬいぐるみ。そのぬいぐるみは、お母さんにだろうとすぐにわかった。
「ゆっきーはどんな感じ? ってなんでライオンの被り物?」
「あ、それは鷹也っていう幼馴染みの小学生の義弟が欲しいって頼んできた物だから。あとはスナック菓子辺りにしてみてるかな」
「なるほどね。もう少し見ていい?」
「うん、いいよ」
お土産を渡す人数が多いと考えることも多くて大変そうと思いつつ、人数の少ない部にさり気なく感謝した。
店内を見回っていると、ウサギとトラが仲良く身を寄せ合っているスノードームを見つけた。
「すみません、これプレゼント用に包装していただけますか」
お互い買い物を終えて売店を出る。荷物を持つ反対の手は変わらず繋いでいる。駅に着いてしまえば、本格的に帰ることになってしまう。
「琥珀くん、家まで送らせて」
「でもゆっき―逆方向じゃなかったっけ?」
「それでも送らせて。最後まで一緒にいたいから」
「うぐっ……。それならお願いしようかな」
琥珀くんの家に近い沿線の電車に2人で乗る。心の中では断られなかったことに一安心していた。
車内で撮った写真やしずかちゃんに貰った写真、メリーゴーラウンドに乗っていた時の動画を見返しているとどれも笑顔だった。
(今日遊園地に行けてよかった。琥珀くん、ずっと楽しそうにしていたから)
しばらくすると、琥珀くんの最寄り駅に着きそこから少し歩いた。
「あ、ここが俺の家。送ってくれてありがとう」
思ったよりも早く着いた琥珀くんの家。和風だけど大きい平屋で驚いた。
「ちょっと待って、琥珀くん。これ受け取って」
紙袋に入っていた箱状のプレゼントを手渡した。琥珀くんの目は見開かれていて、今にも落ちそうだった。
「いいの? 俺、なにも……」
「気にしないで! 僕が渡したくてしてることだから。それにこのプレゼントは僕の気持ちです。……じゃあ帰るね」
「あ、うん! また連絡するね」
僕は手を振って琥珀くんの家を後にした。
(あんなにカッコつけて渡すものでもなかった気がする。でも他に上手く言えなかったし……)
駅に着くまで、1人で反省をしていた。
◇
一方その頃、琥珀は貰ったプレゼントをその場で開けて確認していた。中には冬にピッタリのスノードームが入っていた。
「うわぁ、綺麗」
電柱の光に当ててみてみるとさらに綺麗に雪が舞う。ドームの中のウサギとトラは勘違いしそうなほどに、俺と雪兎を想像させる。
「そう言えばさっき“このプレゼントは僕の気持ちです”って言ってたな。どういうことなんだろう」
ポケットに入れていたスマホを取りだし、検索アプリを開いて【スノードーム プレゼント 意味】で調べてみる。
すると出てきた答えに、ドキッとした。
「ほんと、ゆっきーはやってくれるね」
思わずしゃがみ込んでしまった俺は髪をかき上げて、もう一度内容を見た。
【スノードームをプレゼントする意味は、『永遠』や『一緒にいたい』と言う願いから、「あなたと共に過ごす時間が永遠に続きますように」というロマンチックな意味合いを持つことが多い】
「ゆっきーの気持ち、強すぎでしょ。でもそんなところが、好きなんだけどね」
愛おしい気持ちがいっぱいになりながら俺はスノードームを眺めた。
(楽しい思い出になった。遊園地でアトラクションたくさん乗ったし、念願のカチューシャも付けれたし、美味しいご飯だって……)
「あー!」
俺は気付いてしまった。今日の本来の約束は遊園地に併設されているカフェに行くことだったのに、そっちのけで遊んでしまっていたことを。
多分、雪兎も気づいていない。でもまぁ、いっか。次また行ったらいいしね。
もちろん雪兎と一緒に。
琥珀は持っていた紙袋を下げて家の中に入った。スノードームは部屋で1番目に行く机の上に置いた。
「次はどこに行こうかな」
俺は幸せな気持ちに浸りながら眠りについた。
今日のことは忘れることはないだろう。ずっと、ずっと。
琥珀くんと付き合うようになってからの関係は付き合う前と比べると、少し変わった。どう変わったのかというと……。
「ねぇ、どうしてこっち向いてくれないの?」
「それはちょっと恥ずかしいと言いますか……」
「じゃあ俺がそっち行く」
「そういう問題じゃ……」
「だったらどういう問題なの!? ゆっきーが赤くなるの知ってるんだから、俺にもう隠さなくていいよ。なんなら見たいんだけど」
琥珀くんは僕と目を合わせようとして、右に行ったり左に行ったりと慌ただしい。そうしている原因は僕が顔を合わせてご飯を食べようとしないから。
琥珀くんはつき合い始めた途端、勢いが明らかに増した。前まではセーブしてくれていたみたいだけど、今はそうではないらしい。
それに対して僕は、まだ恥ずかしさがあると言って抵抗して手で顔を覆って隠したりしている。やっぱり着ぐるみを被っている、いないでは話が変わってくる。
「ゆっきーは俺が嫌い?」
「……っ、そんなことない! 僕は琥珀くんが大好き……。あ」
琥珀くんの言葉に乗せられて、背けていた顔を琥珀くんの方に向けて告白していた。
向けた先にいる満面の笑みを浮かべている琥珀くんは、「ふふっ、そっかー」と言葉にしている。
(またやられた)
何やらこのやりとりはゲームの一種みたいになっていて会うたびに行われている。僕はいつも琥珀くんにいいように言葉で揺さぶられて、負けている。悔しい。
「俺は、ゆっきーをいじめたい訳じゃないからね。俺もゆっきーが好きだから、顔が赤くてもいいから普通に時間を過ごしたいって思ってるんだよ」
琥珀くんは僕の手を取って優しく撫でた。大切なものを触るみたいに、傷つけないよう丁寧に触れようとする思いが感じられた。
(琥珀くんはこんな僕を選んでくれた。僕がいいって言ってくれたんだ。それに応えられないなんて彼氏失格じゃないか……)
僕は勇気を振り絞って、琥珀くんの手を握り返した。
(温かくて小さな手。自分から手を握ると違うんだな)
「……」
急に黙り込んだ琥珀くんの方を見ると、微かにだが顔と耳を赤くして固まっている。
「ん? 琥珀くん?」
──ボスッ。
琥珀くんが頭ごと倒れてきて、僕の胸に顔をうずめる体勢になった。何が起こったのか分からない僕は、ただ心配する。
「大丈夫? 気分悪い?」
「……大丈夫だけど、だいじょばない」
「それはどっち?」
「体調は大丈夫だけど、ゆっきーの不意にカッコよくしてくるところがだいじょばない!」
琥珀くんにそう言われたが、言っている意味が一切分からず頭の中ではハテナが駆け巡った。
どうしたらいいのか分からずそっとしていると、琥珀くんが思い切り顔をあげた。
「うおっ! びっくりした」
「ねぇ、ゆっきーは前にした約束覚えてる?」
唐突な質問に何のことを言われているのか、さっぱりだった。
「どの約束……、えっと、着ぐるみ脱げたら行こうって話してたカフェの?」
「そう! あれ、行こうよ」
「い、きたいけどまだ赤面克服したわけじゃないし……」
「そう言うけどさ、俺がいたら関係ないよね?」
──ギクッ。
僕はわかりやすく肩をビクつかせた。行きたくないわけじゃない。隣を歩いてて琥珀くんに恥をかかせちゃうのが嫌なだけ。
「俺は周りの目なんて気にしないよ。俺が気になっているのはゆっきーだけ。まぁ無理ならもう少し経ってからでも……」
冗談交じりに放たれた言葉が、心に響いた。
「──く」
「え?」
「行く。琥珀くんと一緒にカフェに」
「え、えーーー!!!」
琥珀くんの声は、廊下まで広がる大声を出して驚いていた。僕は今まで頑なに首を縦に振らなかったのに、行くとなればそりゃ驚くだろう。
「いいの? 人も多いし、それに俺がいるよ?」
「僕も約束した時から行ってみたいと思ってたんだ。それに琥珀くんのために赤くなるのって存外悪い気もしないんだよね」
僕はいたずらっ子のような笑みを浮かべ琥珀くんに気持ちを伝えた。
「ゆ、っき……。うー、俺の彼氏がイケメン過ぎてツラい……」
「僕も可愛くてカッコいい彼氏が隣にいてくれて、毎日が愛おしい」
本心からの言葉を言うと、今度は顔真っ赤にして俯いた。それを見た僕はよりいっそう愛おしい気持ちに包まれながら微笑んだ。
◇
冬休みに入り数日経ったある日、琥珀くんと約束していた遊園地とコラボしているカフェに行くことになった。
どこにいつ行くか決まったあたりから、ずっとソワソワしていた。着ていく服、髪型、持ち物、こんなにワクワクしながら用意したのは花火大会の時以来。
(珍しく自分で服買いに行ってみたけど、変じゃないかな?)
ショッピングモールのメンズ服を扱うお店で、店員さんから勧められた組み合わせを何着か着てみて、その中で気に入ったものを選んだ。
真っ白なパーカーに黒のスラックス、チェックのチェスターコートと少しシンプルだけど、大人な雰囲気が出ていて気に入っている。
「今更だけど、琥珀くんの服に合わせたらペアルック的なことできたのでは」
遊園地併設のカフェを選んだ時にその考えがあったならば、今ここで後悔はしていない。
「ねぇ、あの人カッコよくない?」
「1人なのかな? 話しかけてみる?」
琥珀くんを待っていると、近くから女性2人が猫なで声で話かけてきた。
「あのー、すみませぇーん。お兄さんお1人ですか?」
「え、まぁ(今は1人ですが)」
「よかったら私たちと一緒にー、遊……」
「雪兎、お待たせ!」
女性たち2人の声など聞こえなくなった。それは琥珀くんが少し離れたところから僕のことを呼んだから。
「え、何この子。可愛いんだけど」
女性2人は琥珀くんを見て心奪われているように見えた。
「すみません、俺の彼氏になにか用ですか?」
「え、あ、いえ。お邪魔しました」
女性たちは琥珀くんに声をかけられると、そそくさとその場を去って行った。
(なにか言いかけていた気がしたけど、気のせいかな)
「もう少し早くこればよかったや」
琥珀くんは渋い顔をしながら親指の爪を軽く噛む。
「どうして? 待ち合わせ時間の10分前だよ」
今でも早いのにもっと早く来ないとって凄い意識だなぁと感心する。琥珀くんは僕の顔を見てため息をついた。
「雪兎はもっとカッコいいことを自覚したほうがいいよ。さっきのナンパだから」
「ナンパ!? 僕が?」
「そうだよ! いつもよりカッコいいからさっきの人絶対惚れてる」
(そんな大げさなと言いたいけど、言ったら琥珀くんから睨まれそうだから言わないでおこう)
琥珀くんは僕の服の裾を強く握っている。僕のこと取られるかもと不安になって、無意識にそうしてしまっているなら申し訳ないけど少しだけ嬉しい。
「琥珀くん、今日はデートだよ。ナンパされたことなんて忘れて楽しもう!」
「デート……うん!」
僕は強く握られていた手を包み込んでギュッと手を繋いだ。
入場券を買って中に入った僕たちは、近くにあった園内マップをもらい広げてみた。
「せっかくなら遊園地で遊んでから行こうよ」という琥珀くんの案から、先に遊ぶことになっている。
「どれから回ろうか?」
「ねぇ、ゆっきー。まずはさ、これしない?」
目を輝かせて琥珀くんはあるところを指さした。それはカチューシャとかの被り物やグッズを売っている屋外ショップだった。
とてもやりたかったのか、引かれる手がものすごく強い。
「いらっしゃいませー」
エリアの世界観に合わせた制服を着たお姉さんが手を振って迎えてくれる。こういう時は振り返したらいいのかわからなくて困る。
「どれが似合うかな? ゆっきーは、やっぱりウサギがいいよね。これつけてみて」
「うん、分かった」
琥珀くんに渡された小さな王冠が付いたウサギのカチューシャをつけてみた。少し恥ずかしいけど、そんなことを言っていたら楽しむことできない。
「ゆっきー、似合い過ぎない?」
琥珀くんの1言に周りにいたお客さんたちやスタッフさんも頷いているのを見た。そんなに似合っているのだろうか。
「似合っているみたいだし、僕はこれにしようかな。琥珀くんはどうする?」
「わがままじゃないなら、ゆっきーに決めてもらいたい」
(こんな可愛いわがままってあるんだ)
「……いいよ。選んであげるね」
可愛さに悶えたいと思いつつ、僕は琥珀くんに似合う被り物を探した。改めて見るとたくさんの種類があるんだとわかる。
遊園地特有の顎のところで留める着ぐるみもどきや、僕が選んでもらったようなキャラクターモチーフの耳カチューシャ、期間限定コラボのカチューシャもあった。
(琥珀くんと言えば、可愛い、カッコいい、空手、どれもモチーフになるようなものじゃないな。うーん、あ!)
僕はショップを一回りして商品を見た。そして見つけた琥珀くんに似合うもの。
「琥珀くん、お待たせ」
「全然待ってないよ。すごく楽しみにしてた!」
「僕が琥珀くんのために選んだのは、これ」
僕は琥珀くんの頭に選んできた商品をあててみた。
選んだのは、名前にちなんだトラの可愛い丸耳のカチューシャ。僕には王冠が付いていたけど、琥珀くんの方は小さなティアラが付いている。
(ティアラだから女の子が付けるのを想定されているかもだけど、琥珀くんに似合う唯一無二の物だと思うな)
鏡を見た琥珀くんは「ゆっきー、これ可愛い!!」と、とても喜んでくれた。
僕たちはそれぞれのカチューシャを購入してアトラクションを目指した。どこもかしこも人が並び長蛇の列となっている。
「さて、どれから乗ろうか?」
「選んでいいの?」
「もちろん、琥珀くん楽しみにしてたもんね」
「楽しみだったけど、来れただけで満足しちゃってたや」
「そうなの? 僕はもっとはしゃいでる琥珀くんを見れるかもって期待したのにな」
「じゃ、じゃあジェットコースターに乗りたい。CMで流れてて気になってたの」
「行こうか」
僕は琥珀くんに手を差し伸べた。思いのほか僕も浮かれてるみたいだ。
「いいの?」
「いいのって。僕たちは付き合ってるんでしょ? いいも何も普通だよ」
「……っ! ゆっきー!」
「うおっ」
琥珀くんが勢いよく抱き着いてきたので、夏祭りとは違って今度は倒れないように僕はしっかりと受け止めた。力強く抱きしめてくる腕が愛おしい。
「よし、行こう!」
いつもは隣に並んで歩くだけだったけど、手を繋いで歩くのは一味違う気がした。告白をされた時のような幸せが込み上がってくる。
(離したくない。ずっと繋いでいたい)
僕は繋いだ手をギュッと握ると、琥珀くんも同じ力加減で握り返してくれた。これが僕たちの愛の証だと言いたくなるほどに。
ジェットコースターの列に並んで1時間半ほどで自分たちの番がやってきた。案内された座席の列は1番前。荷物置きに、鞄とカチューシャを預けて席に着く。
「久々に遊園地に来たから不安すぎる。今更だけど、ゆっきーは絶叫系大丈夫だった?」
「うーん、初めて来たから絶叫系いけるのかすらわからないかな」
「え? それって本当に大丈夫? 止めておいた方が……」
「前から乗ってみたいと思ってたから気にしなくていいよ。楽しもう!」
「ゆっきーがそう言うなら。でももし気分悪くなったら言うんだよ」
琥珀くんと話していると時間になり、係員がベルトとバーの確認に回ってくる。そして陽気なアナウンスが流れてくる。
「わんぱくコースターにお乗りくださりありがとうございます! これからハチャメチャなお散歩が始まります。途中にカメラが設置してあるところがありますので、お気付きになりましたらポーズお願いします! それではいってらっしゃーい」
4人くらいいる係員さんが全員手を振ってくれるのに対して、こちらも振り返したり「いってきまーす」と返事をする。
発射してすぐ、ゆっくりと勾配を登っていく。まだスピードが早くないから安心だ。
「俺、今すっごいドキドキしてる」
「僕も。なんて言ったらいいのかわからないけど、ワクワクして……るぅーうわぁぁぁ」
話しているといつの間にか頂上まで到達していたみたいで、コースターは購買のてっぺんから勢いよく降りていった。斜めや真横、回転なんてお手の物。
みんな声を出しているけど、僕は重力に耐えるのに必死だった。琥珀くんの方を見ると、手をバンザイしながら笑顔で楽しんでいる。
(琥珀くんすごい)
走っている速度が速いからどこまで来ているのか、カメラはどこかなんてわかるはずもなく、気がつけば乗り場に戻っていた。
「おかえりなさーい! バーを外しますので手を放してお待ちください。撮れたお写真はアトラクションの出口で販売しておりますので見て行ってくだいね。それではこの後もお楽しみくださーい」
乗っていた人たちは各自荷物を取って出口に向かって歩いていく。
「楽しかったね、ゆっきー。え、ゆっきー!?」
「うん。楽しかっ、たね。一瞬死んだおばあちゃんが手招きしてた気が……」
「それ絶対ダメだよね。ちょっと休憩しよう! えーっとあそこに座ってて」
琥珀くんが指さした先にあったベンチに座って目を瞑る。
しばらくして少しだけ回復した僕は、どこかへ行ってしまった琥珀くんが一向に帰ってこないことに心配になる。
「電話したほうがいいか」
スマホを取りだし、チャットアプリから電話を繋げようとした時「ごめん、お待たせ―!」と遠くから琥珀くんの声が聞こえた。
「遅かったね、どうしたの? 迷子になってた?」
「迷子にはなってないんだけど、心配させてごめん。とりあえず飲み物」
「ありがとう」
カップに入った冷たい飲み物を受け取り、ストローからごくごくと飲む。中はさっぱりとしたオレンジジュースだった。
「あのね、遅れたのはこれの所為なんだよね」
「これって」
琥珀くんが見せてくれたのは、フォトフレームに入っていたジェットコースターの写真だった。
(そういえば、出口からすぐにベンチに行ったんだった)
どこに設置していたのか分からないカメラの所為で、何ともまぁ写りが悪い。
右手をあげて思い切り叫んでいる琥珀くんと、目を閉じてバーを離すまいと必死にしがみ付く僕。だけど琥珀くんの左手と僕の右手は自然と繋がれていた。
「あれ、僕たち手繋いでたっけ?」
「これはカメラ見つけたから、勝手に繋いでみたの」
「カメラ見つけたんだ、すごい。ってそうじゃなくて、どうして──」
「ただ手を繋いでる写真ほしいなーと思って。改めて口にすると恥ずかしいんだけど」
いつもと逆で、今日は見た事ないくらい顔を赤くさせている琥珀くんを僕が見てる。
(こんなに想ってくれてるなんて、可愛いなぁ)
「琥珀くん、次は直接頼んでよ。写真、琥珀くんとなら何枚でも撮るから。ね?」
「……! 本当に!?」
「もちろん」
琥珀くんは向日葵のような温かい笑顔をみせた。
「じゃあ、1枚だけでいいから今撮りたい。ゆっきーが体調悪くなかったらだけど……」
(こんなに可愛いお願い聞いたことないよ)
つき合い始めてから、前よりも琥珀くんのことを可愛いと感じることが多くなった。今日もずっと可愛いの言葉が止まらない。
「いいよ。一緒に撮ろうか」
琥珀くんは僕の隣に座って、スマホのカメラを起動させる。色々と調整しているみたいだけど、そのことに関してはわからないからお任せしよう。
「じゃあ、ゆっきー撮るね。ハイチーズ」
──パシャ。
カメラロールを開くと、撮れた写真が1番前に来ていた。
「綺麗に撮れたね」
「うん! ありがとう、ゆっきー」
嬉しそうにしている琥珀くんを見て、僕も嬉しい気持でいっぱいになった。
「まだまだ回るんでしょ? だから色々な場所でたくさん写真を撮ろう!」
「うん!」
写真を撮り終わった後も座って少しだけ話をした。何をしたいのか、何に乗りたいのかを相談して決めていく。お陰で気が紛れて僕の体調も少しずつ回復してきた。
「お待たせ、そろそろ行こうか」
「もう大丈夫なの?」
「うん、休んだら治ってきたよ。でもまだ不安だから手を繋いでくれる? ……ってこんな誘い方は良くないね」
一度手を差し伸べたけど、引いて頬を掻いた。上手く誘えなくて反省するしかない。
(もっと上手に誘えたらカッコいいのに……)
左手が小さい手に包まれ、前にいた琥珀くんを見つめる。
「俺も、倒れられたら困るから支えるために手繋いであげる」
照れくさそうにしている琥珀くんが僕の手に触れている。僕が言った口実にノってくれるなんて思ってもいなかった。
(そういうところが可愛いんだけどね)
僕は強く握り返して、次の場所に向かって歩いた。
「次はメリーゴーラウンドだっけ、行こうよ」
「うん、楽しみ」
メリーゴーラウンドまではそんなに遠くなかったはず。でも僕は繋いだ手を離したくなくて、着かないで欲しいなと思ってしまった。
そんな願いとは裏腹にメリーゴーラウンドにはすぐについてしまい、幼い子たちがキャッキャとはしゃいでいる声が響き渡っていた。
「少し並んでいるみたい。やっぱり人気だね」
「小さい子たちの乗れるものなんて限られてるしね」
親子連れが多く並ぶ列の一番後ろに僕らも並んだ。楽しそうな姿に微笑ましく思っていると、前に並んでいた5歳くらいの女の子から声をかけられた。
「ねぇねぇおにいちゃん」
「ん? どうしたのかな」
「おにいちゃんたち、おててつないでるけどどうしてなの?」
思わぬ質問にお互いポカンとした。小さな子にそんなこと聞かれるとは思っていなかったからだ。
答えずらい話をしていることに気付いたその子の母親は、「何言ってるの! すみません」とその子を無理に前に向けようとしていた。
「大丈夫ですよ」
僕は琥珀くんと手を繋いだままその子と目線を合わせるようにしゃがんだ。
「お名前は?」
「しずか」
「しずかちゃん、可愛い名前だね。さっき聞いてくれたことについてお返事するね。僕たちは恋人同士、好きな人同士だから手を繋いでいるんだよ。しずかちゃんはママのこと好き?」
「うん! だいすきだよ!」
「そうだよね! しずかちゃんが大好きなママと手を繋ぐのと同じ、僕もこの人が好きだから手を繋いでるんだ。いいでしょ」
「うわぁ、ふたりはなかよしなんだね! わたしもママとなかよしだよ!」
「本当だね。あ、しずかちゃんの番が来たみたいだよ」
母親に連れられて柵の中に入ったしずかちゃん。目の前で列が別れてしまった僕たちはしずかちゃんが楽しそうに乗っている姿を見て笑顔になれた。
「どうしてあの子には話したの?」
「どうしてだろう。付き合うということが分からなくても、一緒にいたい大好きな人は色々な形で存在することを知ってほしかったのかも。それと嘘はいけないかなって」
「そっか。いい教育だね」
「でもお母さんに変なこと教えたって怒られないかな? 今はそれが一番の心配だよ」
「それはそうだね。もしそうなったら俺も一緒に謝ってあげる」
琥珀くんと笑いながらが柵が開くのを待った。
「次の方どうぞ―」
前の人達のターンが終り、やっと僕たちの番になった。どれに乗ろうかと話したら琥珀くんからのリクエストで、白馬に乗ることになった。琥珀くんは隣に並んでいる少し小さめの馬に乗った。
「それではお馬さんのお散歩が始まります。いってらっしゃーい」
スタッフの合図で回り始め、馬も上下したりしている。
「ゆっきー、やっぱり白馬似合うね! こっち向いてー」
ポケットからスマホを取りだした琥珀くんはスマホを向けている。
「撮れた?」
「うーん、ゆっきーごめん。これ動画」
「なんで教えてくれないの!」
「あはは」
写真だと思ってポーズを取っていた少しの間を思い出すと、途端に恥かしくなって少し顔回りが熱くなる。
「ははっ、ゆっきー真っ赤だね」
「誰の所為だと……」
「でもそれは普通に恥ずかしい感情からきたものだもんね」
言われてみれば、今日は琥珀くんに対して赤面するタイミングが少なかった。その分楽しい気持ちの方が上回っていた。
「琥珀くんと来れたことが楽しくて赤くなるってこと忘れてたや」
「ひう……。ゆっきー、つよぉ」
琥珀くんはスマホを持ちながら顔を覆った。完全に見えない隠し方で、どんな顔をしているのかわからなかった。
「琥珀くん、どうし……」
「おかえりなさーい! お散歩は楽しめたかな? また一緒にお散歩いこうねー」
手を伸ばしたタイミングとスタッフの声が被さった。先に馬を降りた琥珀くんは「早くいこ!」と先ほどまでの顔を赤くして照れていた態度とはうって変わって、元気になって出口に向かった。
「あ、おにいちゃーん」
しずかちゃんが待ってくれていたみたいで、出口に出た途端話しかけてくれた。琥珀くんもしずかちゃんに気付いたようで、足を止めた。
「あのね、これあげたくてまってたの」
「ん?」
見せてくれたのは、しずかちゃんが持っていたチェキカメラで撮った笑い合っている僕ら2人のチェキ。
「すみません、しずかがどうしてもお2人のこと撮ってあげたいって言うもので。ご迷惑でなければ、もらっていただけますか?」
「え、いいんですか?」
「もちろん。失礼な話、同性でおつき合いされている方を私も初めて見ました。遠ざけようとするのが一般的な親だと思うのですが、お2人がしずかに対して優しくてそれにお似合いだなと思って私も応援したくなりました」
つき合っていることをいつもなら隠している僕たちからすると、しずかちゃんや母親の言葉には勇気をもらった。
しずかちゃん親子と別れた後は、気ままに園内を歩きまわって空いてそうな乗り物に乗ったり、綺麗に咲いている花の道を通ったり、お昼を食べたりして気が付けば夕方になっていた。
そろそろ帰る時間が迫ってきたので、僕たちは最後に観覧車に乗ることにした。
混んでいたり、恋人同士が多いのかなと思っていたが、思いのほか観覧車には人が少なくすぐに乗り込むことができた。
「空いていてよかったね。観覧車までたくさん並んでたら諦めて帰るところだったよ」
「その時はまた並んで待てばいいよ」
「え?」
琥珀くんは諦めると言ったけど、僕は一緒に待つ方を選ぶ。
「今日みたいにどのアトラクションも並ばないと乗れないのなら、琥珀くんと並んで待って、最後の最後まで楽しいと思える景色を見たい」
琥珀くんの膝の上に乗せられた手に、自分の手を被せるように包み伝えた。言っている内容は恥ずかしいけれど、間違ったことは言っていないからよしとしよう。
「俺も待つ。ゆっきーと幸せな日常を忘れないために」
琥珀くんは僕の手をほどいて抱きしめてきた。ぎゅと強くなる力に僕も応える。
「雪兎、大好き」
「……僕も大好き。琥珀くん、愛してる」
知らぬ間に到着した頂上。誰も見ていない夕焼けの空間で、僕たちはいつもより長くキスをしてお互いの愛を確かめ合った。
「おかえりなさーい!」
外から鍵を開けてもらい「ありがとうございます」と言って降りた。
この時間になってもお客さんは思いのほかいるみたいで、建物から漏れる明かりがまぶしい。
手を繋いで売店に寄ると、それぞれ悩みながらお土産を探した。僕は鷹也と獅埜、それに両親と演劇部へ見繕っていた。
「いいの決まった?」
「お菓子系でも個数が合うのなくて悩んでるところ。琥珀くんは?」
「僕も同じ。家と入院している母さんには決まったんだけど、空手部の方がね」
琥珀くんのカゴに入っていたのは、動物の焼き印が入ったお饅頭と小さなトラのぬいぐるみ。そのぬいぐるみは、お母さんにだろうとすぐにわかった。
「ゆっきーはどんな感じ? ってなんでライオンの被り物?」
「あ、それは鷹也っていう幼馴染みの小学生の義弟が欲しいって頼んできた物だから。あとはスナック菓子辺りにしてみてるかな」
「なるほどね。もう少し見ていい?」
「うん、いいよ」
お土産を渡す人数が多いと考えることも多くて大変そうと思いつつ、人数の少ない部にさり気なく感謝した。
店内を見回っていると、ウサギとトラが仲良く身を寄せ合っているスノードームを見つけた。
「すみません、これプレゼント用に包装していただけますか」
お互い買い物を終えて売店を出る。荷物を持つ反対の手は変わらず繋いでいる。駅に着いてしまえば、本格的に帰ることになってしまう。
「琥珀くん、家まで送らせて」
「でもゆっき―逆方向じゃなかったっけ?」
「それでも送らせて。最後まで一緒にいたいから」
「うぐっ……。それならお願いしようかな」
琥珀くんの家に近い沿線の電車に2人で乗る。心の中では断られなかったことに一安心していた。
車内で撮った写真やしずかちゃんに貰った写真、メリーゴーラウンドに乗っていた時の動画を見返しているとどれも笑顔だった。
(今日遊園地に行けてよかった。琥珀くん、ずっと楽しそうにしていたから)
しばらくすると、琥珀くんの最寄り駅に着きそこから少し歩いた。
「あ、ここが俺の家。送ってくれてありがとう」
思ったよりも早く着いた琥珀くんの家。和風だけど大きい平屋で驚いた。
「ちょっと待って、琥珀くん。これ受け取って」
紙袋に入っていた箱状のプレゼントを手渡した。琥珀くんの目は見開かれていて、今にも落ちそうだった。
「いいの? 俺、なにも……」
「気にしないで! 僕が渡したくてしてることだから。それにこのプレゼントは僕の気持ちです。……じゃあ帰るね」
「あ、うん! また連絡するね」
僕は手を振って琥珀くんの家を後にした。
(あんなにカッコつけて渡すものでもなかった気がする。でも他に上手く言えなかったし……)
駅に着くまで、1人で反省をしていた。
◇
一方その頃、琥珀は貰ったプレゼントをその場で開けて確認していた。中には冬にピッタリのスノードームが入っていた。
「うわぁ、綺麗」
電柱の光に当ててみてみるとさらに綺麗に雪が舞う。ドームの中のウサギとトラは勘違いしそうなほどに、俺と雪兎を想像させる。
「そう言えばさっき“このプレゼントは僕の気持ちです”って言ってたな。どういうことなんだろう」
ポケットに入れていたスマホを取りだし、検索アプリを開いて【スノードーム プレゼント 意味】で調べてみる。
すると出てきた答えに、ドキッとした。
「ほんと、ゆっきーはやってくれるね」
思わずしゃがみ込んでしまった俺は髪をかき上げて、もう一度内容を見た。
【スノードームをプレゼントする意味は、『永遠』や『一緒にいたい』と言う願いから、「あなたと共に過ごす時間が永遠に続きますように」というロマンチックな意味合いを持つことが多い】
「ゆっきーの気持ち、強すぎでしょ。でもそんなところが、好きなんだけどね」
愛おしい気持ちがいっぱいになりながら俺はスノードームを眺めた。
(楽しい思い出になった。遊園地でアトラクションたくさん乗ったし、念願のカチューシャも付けれたし、美味しいご飯だって……)
「あー!」
俺は気付いてしまった。今日の本来の約束は遊園地に併設されているカフェに行くことだったのに、そっちのけで遊んでしまっていたことを。
多分、雪兎も気づいていない。でもまぁ、いっか。次また行ったらいいしね。
もちろん雪兎と一緒に。
琥珀は持っていた紙袋を下げて家の中に入った。スノードームは部屋で1番目に行く机の上に置いた。
「次はどこに行こうかな」
俺は幸せな気持ちに浸りながら眠りについた。
今日のことは忘れることはないだろう。ずっと、ずっと。