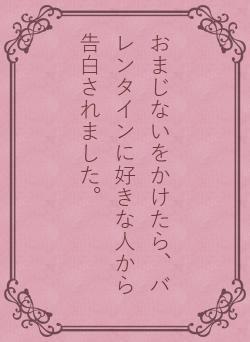体育館から屋上までの道のりが、普段よりも長く感じた。どこに行っても「ウサギの王子様どこー?」と僕を探す女子が道を阻んでいく。
「琥珀くんに連絡……。あ、スマホ体育館に忘れた」
スマホは開演前にステージ横の机に置いて来たままだった。今から戻ろうにも捕まるリスクが高すぎて、そのまま目的地へ進んでいくことを決めた。
着替えることもままならず、王子衣装のまま来てしまった。
「もう少しで屋上だ」
校舎の3階から屋上へ行くための階段には、立ち入り禁止のトラテープがかけられていたが構わずくぐって錆びついたドアを慎重に開けた。
久々に来た開けた屋上。誰にも見られないよう走ってきた僕は、息が乱れていて整える時間が必要だった。屋上の中央に陣取って楽に座る。
(琥珀くんに連絡できないから待つしかないよな。文化祭が閉会したらお客さんも引いて動きやすくなるから、その時までここで身を隠していれば……)
どうやって琥珀くんに会おうか考えていたら、再び錆びたドアがキィーっと鳴る音が背後からした。
(ここまで来たのか!?)
僕のことを探している人だったらどうしようと思って、焦って振り返った。すると、そこにいたのは琥珀くんだった。
「え、琥珀くん!?」
驚きが隠せなかった。まだ文化祭終わっていないのに、どうしてここにいるのだろう。
僕は合わさった視線を思わず逸らしてしまった。
(あ、逸らしちゃった……)
琥珀くんが近づいてくる足音がだんだん近くなってきている。「どうして正体を隠していたんだ」と罵詈雑言を言われてもいいようにギュッと目を瞑って覚悟した。
「ゆっきーだよね?」
目の前から聞こえた言葉は、想像していたものより優しい問いだった。
名前を言われたら顔を上げるしかない。そぉーっと琥珀くんを見上げると、優しい笑顔でこちらを見ている。
「なーに絶望した顔してるの。俺に黙ってから、申し訳ないって思ってる?」
グサッと核心を突かれて一気に息苦しくなった。
申し訳ない気持ちが溢れ返り、何から言ったらいいのか困惑してきた。だけどバレてしまう時があれば、絶対に言うと決めていたことがずっとあった。
「……騙すつもりはなかったんだ。ただ君と普通に話せる方法がこれしかなかっただけで。それで」
あとは「ごめんなさい」と伝えるだけなのに、どうしても言葉が口から出なかった。僕の周りの空気だけが重くなって、自然と頭が垂れていく。
「俺もゆっきーに謝らないといけないこと、あるんだよね」
目の前でしゃがみこんだ琥珀くんから声を聞くために、ゆっくりと顔を上げて視線を合わせた。琥珀くんの綺麗なクリーム色の髪が風でなびいている。
(こんな時でも綺麗だと思ってしまう)
すうっと息を吸った琥珀くんに「俺、初めからゆっきーのこと知ってたよ」と衝撃的な告白をされた。
「……え!?」
瞬間フリーズしてから、驚きの反応をする僕。さっきまでの重苦しい場の雰囲気が一気に変わった。
「知ってたんだ。全然分からなかった……」
琥珀くんは揶揄って遊ぶ人じゃないと、数か月一緒に過ごしてきて知っている。だけど、知っていることを話さなかったってことはどこか楽しんでたんじゃないかとも思えてしまう。
僕は惨めにも隠していたことに話を合わせてくれたんだとしか、思えなくなってしまった。
「どうして知ってるって教えてくれなかったの? そうしたら、僕も嘘をつかなくて済んだのに」
(琥珀くんを責めるなんて情けない。嘘をついたのは、琥珀くんのせいじゃない。僕が勇気を持てなかっただけ)
だけど琥珀くんは僕を責めたりはせず、話すのを待ってくれている。
「これは昔話なんだけどね。……俺はゆっきーと会う前にね、如月雪兎と言う人物を見たことがあったんだ」
(それはもちろん覚えてる。僕の一目惚れをした瞬間だから)
「1年の秋かな、校舎裏に3年の先輩に呼び出しを食らった同じ1年生を助けたんだ。じいちゃんから『弱い者を守るのが強者の使命』って教えられてきたから助けただけなのに、雪兎は腰抜けてたにも関わらず、感謝を伝えてくれて。その時、お礼って渡してくれたんだ。覚えてる?」
「あ、それ……」
琥珀くんがポケットから取り出したのは、当時雪兎がハマっていた毛糸で作るミニ人形のウサギだった。
「俺は昔から可愛いものに目がなくて、でも家では禁止されてつまんない人生だなって思ってたんだ。だから貰った時は嬉しかったし、大事にしようって決めた。そこから可愛いものを作れる雪兎の存在が気になってずっと見てたんだ」
ダメだと言われていても大切にしてくれていた。話し声に“嬉しい”という感情が乗っていることは僕でも感じ取れた。
「2年で同じクラスになれたら話しかけてみようと思ったけど、また離れちゃって。どうしようと思った時に、演劇部の倉庫から段ボールを担いで屋上に向かう雪兎を見つけて後を追った。そのあとは雪兎も知ってる通りだよ」
僕が知らない琥珀くんが雪(ぼ)兎(く)を知ってくれていた理由。
初めから琥珀くん『ゆっきー』じゃなくて、『雪兎』と接してくれていたということが伝わってきた。
僕の目から心の中で爆発した感情が涙となって流れ出していた。
この涙は彼の思いを疑ってしまったことへの罪悪感と、ずっと覚えてくれていたことの嬉しさから。
「……琥珀くん、ずっと覚えててくれてありがとう」
「うん」
「……琥珀くん、好きです。助けてもらった時からずっと、ずっと」
鼻を啜りながらのカッコ悪い告白にも琥珀くんは笑顔を浮かべながら黙って聞いてくれている。
「雪兎、俺も好きだよ。こんなにも赤くなる顔も相手の気持ちを考えて行動できるところも。それに隠すの下手だからわかっちゃうところも」
琥珀くんは僕の頬に手を添えて大切なもののように触れる。色々聞きたいところがあったがそんなのは今どうでもいい。
好きだと言ってくれた事実が1番大事だった。
「ほんと? 夢じゃない?」
「夢じゃないよ。せっかく告白したのに夢にしないで」
琥珀くんは僕を抱きしめてくれた。僕も、琥珀くんの背中に手を回して強く抱きしめた。
(夢じゃないけど、現実味が湧かないなぁ)
実感がまだ湧かなくて、嬉し涙が止まらない。
「もー泣き虫だなぁ、ゆっきーは」
琥珀くんは僕の両頬に触れて、キスをしてきた。軽くされたキスだったが、触れた唇の感触が残っている。
「あ、泣き止んだ。ふふっ、赤くなってるのちゃんと見るの初めて」
琥珀くんは余裕と言わんばかりに普通に振舞っている。それどころか驚いて涙が引っ込んで照れる僕を軽くいじる。
「あんまり見ないで……。恥ずかしいから」
「ファーストキスだった?」
「……そうだけど、悪い?」
「全然、悪くない。嬉しいよ。だからほら、顔見せて」
顔を隠したい僕と赤くなっている顔を見たい琥珀くんの攻防戦が繰り広げられた。力の強さを出されて、僕は押し倒される形になってしまった。
「可愛いよ、ゆっきー」
琥珀くんの表情はカッコいい雄の顔をしている。僕は至近距離で見たせいで喉を鳴らさずにはいられない。
「可愛いのは琥珀くんの方だよ」
「そうかなー? 俺のこの可愛さは、好きを表に出してできたものだから自然にできたものじゃないんだけどな」
「そうだとしてもだよ」
「じゃあ、雪兎はカッコいい俺と可愛い俺、どっちが好き?」
「もちろん、どっちの琥珀くんも好きだよ」
琥珀くんは目を見開いた。だけど一瞬で目尻を垂らして優しい笑顔を見せた。
「ねぇ雪兎、俺とつき合って」
琥珀くんからのつき合ってという告白に驚きを隠せなかった。「ダメ?」と可愛い子ぶって聞いてくるが、僕の答えは決まっているようなものだ。
(本当は僕から言おうと思ってたのにな。先を越されちゃった)
「僕でよければお願いします。絶対に幸せにする」
「やった!」
僕は、奥底に仕舞ったはずの好きを直接伝えることができた。
それがどれだけ幸せなことか。
僕は起き上がり、琥珀くんを抱き抱えて一緒にクルクルと回った。どこのドラマシーンだよ、なんて言われてもそんな言葉気にしない。
「あははっ、ゆっきーすごい!」
楽しんでいる琥珀くんに目を合わせて心を込めて伝えた。
「琥珀くん、好きだよ」
◇
1日目の文化祭を終えるアナウンスが流れる。僕らは屋上で人が引いていくのを待っていた。その間に準備期間会えず貯まっていた積もる話をして時間を潰した。
「あ、さっき赤面してるところ見たことあるみたいに言ってたよね」
「ソーダッケ?」
「僕ずーっと着ぐるみ被ってたから見せた記憶ないんだけど、どこで見たの?」
「えーっと……」
琥珀くんは話したくないのか、歯切れの悪い返事しか返ってこない。
「怒らないでよ?」
琥珀くんはバツが悪そうな表情をしながら確認してくる。
「分かった、怒らないって約束する」
「雪兎が一緒に食べてくれるようになった時にたまたま見ちゃった。……というか見えちゃったが正解!」
「でも背中合わせてたでしょ?」
「空き教室の雪兎側にある小さい鏡が俺の前にあった大きな鏡に反射して見えちゃってたという、話ですよ」
僕は話を聞いて呆気に取られていたと思う。でも、安心した。
「備品の置き方が悪かったって話かぁ。じゃあ怒れないね」
たまたまが重なってできてしまった偶然が、琥珀くんに顔や秘密を知られる原因になろうとは思ってもいなかった。
「それじゃあ、俺も聞いていい? どうして緊張して顔を隠してるって嘘ついたの?」
うぐっ、答えづらい質問が飛んできてしまった。このことはずっと話さないでいるつもりだったのに。
前のめりに聞いてくる琥珀くんに根負けして、正直に口を割った。
「琥珀くんにだけ赤面するから恥ずかしくて。好きな人にって言えばバレるし、初対面で顔が赤い奴がいたら気持ち悪いと思われるから、咄嗟に考えた理由が『緊張するから』だったんだ」
「ふぅーん、顔が赤くなっちゃうのは好きな人限定ってことかー」
「うぐっ……、そうだよ! 悪い!?」
こうなったら、やけくそだとしか思えなくなった。半ギレみたいな形に突っかかったけど、琥珀くんは「別に! 悪くないよ!」と言って嬉しそうにキスをしてきた。
◇
文化祭2日目は、風邪で休んでいた部員が回復して正式な王子役としてステージに立つことになった。もうステージに立たなくていい状態になったのは嬉しかったけど、寂しい気持ちもどこかにあった。
劇を舞台袖でひばり先輩と見ていた。
「先輩、昨日はありがとうございました。背中押して逃がしてくれたおかげで、好きな人とつき合うことができました」
「そうか、気持ちが伝わってよかったな雪兎。幸せになった新しい雪兎でぜひとも舞台に上がってくれ!」
「上がりません」
ひばり先輩と顔を見合わせ笑いあった。こうやって応援して幸せを願ってくれている人がいるって、改めて痛感した。
「じゃあ、僕クラスの方に行ってきます」
「その子また紹介してくれ」
「もちろんです」
僕は舞台が終わる前に裏出入口から校舎に移動し、2年2組の衣装レンタル写真館に舞い戻った。
「ただいまーって忙しそうだね」
「ここにいる人全員、雪兎くん待ちのお客さんだよ。早く着替えてきて!」
「あ、うん」
僕は昨日と同じように試着室で執事服を着て教室に戻ると、反応は昨日と同じで耳が痛くなるほどの悲鳴が上がる。
「昨日と同じだから大丈夫だよね?」
カメラ係の子が確認してきたから首を縦に振って頷いた。
(今日はクラスに貢献しなきゃな)
待ってもらっていたお客さんを順番に中に入れて対応していた。カーテンの隙間から見た長い列を捌ききるにはすごい時間がかかりそうだった。
(これ終わるのかな……)
見なきゃよかったかもと少しだけ後悔した。
どれだけ時間が経ったのか分からない。外に設置されている野外ステージから『続きましてーお笑い同好会のコントです。どうぞ』と言っているから多分、お昼の時間にはなっている頃だろう。
「まだ終わらなさそう?」
「そうねぇ、もうすぐシフト交代だし締め切ってもいいかも。伝えてくるね」
カメラ係の女子がカーテンの外にいる受付係に伝えてくれた。そのおかげで「如月雪兎シフト交代のため、13時で終了となります」と大声で言われて若干恥ずかしい。
その言葉が届いたのか、「お役がさらにたくさん集まっている」と案内係の男子がコソっと教えてくれた。
「外見てきたけどざっと50人くらいいたかもな」
「50人!? 嘘でしょ……」
「マジだって。だから最後の1人まで対応しないとブーイングくるかもなー」
「えーそれは怖い」
そんな話をしていると次のお客さんが入ってきて、チェキを撮った。なんだかアイドルになった気分に感じてきた。
「うわぁーーー!!!」
カーテンの外から甲高い歓喜の声が聞こえた。区切られたこの場所からは、外で何があったのかが分からなかった。
気にせず続けようとするカメラ係が「次の方どうぞー」と声をかけた。
「こんにちは、写真館へようこそ……って、琥珀くん!?」
琥珀くんはクラスの出し物であるメルヘン喫茶の制服のまま来てくれた。僕の知っているクラシカルなメイド服ではなく、ジャージメイド姿だった。
「ゆっきーとチェキ撮れるって聞いてきてみた」
「来てくれるなんて嬉しいよ!」
「2人仲いいね、いいじゃん。それじゃあ撮るよー」
パシャっとカメラのシャッターを切る音がして、本体から出てきたチェキを受け取って見ると、顔を近づけ片手をハートの形にして挟むようにするルダハートしていた。
「可愛く撮れたね」
「うん、嬉しい」
嬉しそうにしている琥珀くんの周りには花が飛んでいるように見えた。本当に可愛い。
「雪兎くん、終わりの時間だからもう上がっていいよ」
受付係の子が伝えに来たのを合図にカメラ係の子も外に出た。カーテンで区切られた中には2人だけになった。
「琥珀くんはこれからどうするの?」
「俺はゆっきーと出し物見て回ろうと誘いに来た。どう?」
「もちろん良いよ。行こうか。あ、でも着替え」
「ゆっきー似合ってるから着替えなくてもいいよ。それに宣伝になるから着といたほうが良いんじゃない? 俺もクラスの女子に言われたからさ」
琥珀くんに上手く乗せられた感があるけど、衣装のまま2人で校舎内を回った。歩けば「可愛い」や「カッコいい」の言葉が飛び交う。
(確かにジャージメイド似合う琥珀くんは可愛いな)
「ゆっきーどこ行く?」
「とりあえずお腹空いたかな」
「じゃあ、外行くか」
階段を下りてグラウンドに出た。外では体育祭の時でしか見ないようなテントがずらっと並んでいる。
たこ焼き、焼きそば、フランクフルト、ポテト、うどんなどのごはん系もあれば、クレープ、ミルクせんべい、タピオカミルクティなどのスイーツ系もあってお祭りの屋台に負けないくらいの種類の多さに驚愕した。
「多いね、どれにしよう」
「俺も食べてなかったから一緒に食べる。1通り買って中庭で食べよう」
「そうだね、行こう」
僕たちは食べられる分のごはんを買い込んだ。だけど1人の腕の中には収まらないほどの量になってしまった。
「高校生の胃袋だから多くなるよね」
「そうだね。てかこの量はパーティーで分ける時くらいの量でしょ。食べれる?」
琥珀くんは買ったものを持ちながらお腹をかかえて笑っていた。
問いに対して、「多分、大丈夫!」と不安になりながら答えておいた。
「なんとか食べきれたね」
「俺、お腹いっぱいで動けない……」
買ってきたごはんを始めは好きなものを中心に選んで食べて、後半には分担して食べた。その姿はまるで大食いしているかのようだった。
「それにしても、ここは静かでいいね」
「違う世界にいるみたいだよね」
グラウンドから聞こえる司会の声も校舎から流れる放送もこの中には微かにしか聞こえない。人もおらずで本当の本当に2人きりだ。
「ゆっきー、今日の終わり後夜祭あるでしょ? 一緒に屋上行って見ない?」
ごはんを食べて眠くなってたのか、琥珀くんは目を瞑りながら僕にそう言って誘ってきてくれた。
「いいよ。2人で見よう」
僕はもたれかかってくる琥珀くんの頭を撫でながら答えた。
琥珀くんはそのまま寝てしまったけど、安心できる場所と思ってくれているようで嬉しかった。
◇
夕方になり一般のお客さんがいなくなったことを確認してから、出し物の片づけをしつつ後夜祭の準備が始まった。
僕らは約束していた時間まで、各々のクラスの片づけをすることにしている。装飾で元々教室にあったものと捨てるもので分けたり、作った衣装を折角だからと演劇部に譲ってくれたりとそこそこ忙しかった気がする。
「こっちの段ボール持っていくねー」
「ゴミもうない? 持って下りるけど」
「あー、もう少し待って!」
窓の外ではキャンプファイヤーの準備がされていた。毎年恒例なんだそうだ。
「何かいいのあったか?」
「鷹也。キャンプファイヤー今年もするんだなと思って。そういえば鷹也ほぼずっとクラスの出し物に捕まってたって聞いたけど大丈夫だった?」
「まぁ、休憩取りながらだったし平気かな」
鷹也は獅埜と遊んであげるくらいだし体力が僕よりもあるのだろうな。
(あ、鷹也には伝えておこう……)
「ねぇ鷹也、耳貸して」
「あぁ?」
「あのね、僕琥珀くんとつき合えることになったよ」
「……そう、か。良かったじゃん」
「鷹也には直接伝えておきたくて。色々と聞いてくれてありがとうね」
「気にすんなって。これからが頑張り時だな」
「うん! あ、琥珀くんと約束してるから行ってくるね」
「あぁ。……幸せになれよ」
僕はこの時知らなかったことがあった。鷹也は僕のことが好きだったってこと。
知らなかったとはいえ、好きな人がずっと思っていた人とつき合ったと報告されたらどうだろう。僕だったら苦しくて耐えられない。
だけど鷹也は僕の幸せを願ってくれたカッコよくて優しい、大切な友達──。
「お待たせ、琥珀くん」
「俺もさっき来たところ。ほら、見て」
さっきまで準備していたキャンプファイヤーに火が灯り輝いていた。
「綺麗に燃えてるね。近くに見に行こうか」
「ううん、ここで良いよ」
琥珀くんがフェンスにもたれかかったのを見て、僕も当然のように隣に座った。肩に頭を寄せてきた琥珀くんが、「終わってほしくないなぁ」と呟いた。
「そうだね。僕も終わってほしくない。でも来年も一緒に出し物見て回ったり、クラスが一緒なら同じ係になって時間を共にしようよ」
肩にもたれている琥珀くんの表情は見えないからわからないけど、ピクっと動いた感じから驚いているってわかる。
「来年も……」
──ヒュー、バーン。
突如、夜空に花が咲いた。次々と上がる花火は赤にも青にも色を変える。
「綺麗だなぁー」
キャンプファイヤーを見た後じゃあ、比べるのは可哀そうだけど綺麗なのはどちらも同じ。
何発も上がる花火に見惚れていると、琥珀くんが制服の袖を引っ張ってきた。
「ゆっきー、僕とつき合うって決めてくれてありがとう。来年も同じ景色が見れるように頑張るね」
その言葉が心に響いて泣きそうになった。瞳をウルウルさせながらも、僕も言葉に紡ぐ。
「琥珀くん、僕の方こそお礼を言いたい。ありがとう。頼りない僕だけど、大切にするって誓う。大好きだよ」
琥珀くんは僕に抱きついてきた。まるで幸せを嚙みしめるかのようにギュッと。
僕らは花火そっちのけでキスをした。綺麗な光景をそのまま脳裏に刻みこむかのように大切に──。
「琥珀くんに連絡……。あ、スマホ体育館に忘れた」
スマホは開演前にステージ横の机に置いて来たままだった。今から戻ろうにも捕まるリスクが高すぎて、そのまま目的地へ進んでいくことを決めた。
着替えることもままならず、王子衣装のまま来てしまった。
「もう少しで屋上だ」
校舎の3階から屋上へ行くための階段には、立ち入り禁止のトラテープがかけられていたが構わずくぐって錆びついたドアを慎重に開けた。
久々に来た開けた屋上。誰にも見られないよう走ってきた僕は、息が乱れていて整える時間が必要だった。屋上の中央に陣取って楽に座る。
(琥珀くんに連絡できないから待つしかないよな。文化祭が閉会したらお客さんも引いて動きやすくなるから、その時までここで身を隠していれば……)
どうやって琥珀くんに会おうか考えていたら、再び錆びたドアがキィーっと鳴る音が背後からした。
(ここまで来たのか!?)
僕のことを探している人だったらどうしようと思って、焦って振り返った。すると、そこにいたのは琥珀くんだった。
「え、琥珀くん!?」
驚きが隠せなかった。まだ文化祭終わっていないのに、どうしてここにいるのだろう。
僕は合わさった視線を思わず逸らしてしまった。
(あ、逸らしちゃった……)
琥珀くんが近づいてくる足音がだんだん近くなってきている。「どうして正体を隠していたんだ」と罵詈雑言を言われてもいいようにギュッと目を瞑って覚悟した。
「ゆっきーだよね?」
目の前から聞こえた言葉は、想像していたものより優しい問いだった。
名前を言われたら顔を上げるしかない。そぉーっと琥珀くんを見上げると、優しい笑顔でこちらを見ている。
「なーに絶望した顔してるの。俺に黙ってから、申し訳ないって思ってる?」
グサッと核心を突かれて一気に息苦しくなった。
申し訳ない気持ちが溢れ返り、何から言ったらいいのか困惑してきた。だけどバレてしまう時があれば、絶対に言うと決めていたことがずっとあった。
「……騙すつもりはなかったんだ。ただ君と普通に話せる方法がこれしかなかっただけで。それで」
あとは「ごめんなさい」と伝えるだけなのに、どうしても言葉が口から出なかった。僕の周りの空気だけが重くなって、自然と頭が垂れていく。
「俺もゆっきーに謝らないといけないこと、あるんだよね」
目の前でしゃがみこんだ琥珀くんから声を聞くために、ゆっくりと顔を上げて視線を合わせた。琥珀くんの綺麗なクリーム色の髪が風でなびいている。
(こんな時でも綺麗だと思ってしまう)
すうっと息を吸った琥珀くんに「俺、初めからゆっきーのこと知ってたよ」と衝撃的な告白をされた。
「……え!?」
瞬間フリーズしてから、驚きの反応をする僕。さっきまでの重苦しい場の雰囲気が一気に変わった。
「知ってたんだ。全然分からなかった……」
琥珀くんは揶揄って遊ぶ人じゃないと、数か月一緒に過ごしてきて知っている。だけど、知っていることを話さなかったってことはどこか楽しんでたんじゃないかとも思えてしまう。
僕は惨めにも隠していたことに話を合わせてくれたんだとしか、思えなくなってしまった。
「どうして知ってるって教えてくれなかったの? そうしたら、僕も嘘をつかなくて済んだのに」
(琥珀くんを責めるなんて情けない。嘘をついたのは、琥珀くんのせいじゃない。僕が勇気を持てなかっただけ)
だけど琥珀くんは僕を責めたりはせず、話すのを待ってくれている。
「これは昔話なんだけどね。……俺はゆっきーと会う前にね、如月雪兎と言う人物を見たことがあったんだ」
(それはもちろん覚えてる。僕の一目惚れをした瞬間だから)
「1年の秋かな、校舎裏に3年の先輩に呼び出しを食らった同じ1年生を助けたんだ。じいちゃんから『弱い者を守るのが強者の使命』って教えられてきたから助けただけなのに、雪兎は腰抜けてたにも関わらず、感謝を伝えてくれて。その時、お礼って渡してくれたんだ。覚えてる?」
「あ、それ……」
琥珀くんがポケットから取り出したのは、当時雪兎がハマっていた毛糸で作るミニ人形のウサギだった。
「俺は昔から可愛いものに目がなくて、でも家では禁止されてつまんない人生だなって思ってたんだ。だから貰った時は嬉しかったし、大事にしようって決めた。そこから可愛いものを作れる雪兎の存在が気になってずっと見てたんだ」
ダメだと言われていても大切にしてくれていた。話し声に“嬉しい”という感情が乗っていることは僕でも感じ取れた。
「2年で同じクラスになれたら話しかけてみようと思ったけど、また離れちゃって。どうしようと思った時に、演劇部の倉庫から段ボールを担いで屋上に向かう雪兎を見つけて後を追った。そのあとは雪兎も知ってる通りだよ」
僕が知らない琥珀くんが雪(ぼ)兎(く)を知ってくれていた理由。
初めから琥珀くん『ゆっきー』じゃなくて、『雪兎』と接してくれていたということが伝わってきた。
僕の目から心の中で爆発した感情が涙となって流れ出していた。
この涙は彼の思いを疑ってしまったことへの罪悪感と、ずっと覚えてくれていたことの嬉しさから。
「……琥珀くん、ずっと覚えててくれてありがとう」
「うん」
「……琥珀くん、好きです。助けてもらった時からずっと、ずっと」
鼻を啜りながらのカッコ悪い告白にも琥珀くんは笑顔を浮かべながら黙って聞いてくれている。
「雪兎、俺も好きだよ。こんなにも赤くなる顔も相手の気持ちを考えて行動できるところも。それに隠すの下手だからわかっちゃうところも」
琥珀くんは僕の頬に手を添えて大切なもののように触れる。色々聞きたいところがあったがそんなのは今どうでもいい。
好きだと言ってくれた事実が1番大事だった。
「ほんと? 夢じゃない?」
「夢じゃないよ。せっかく告白したのに夢にしないで」
琥珀くんは僕を抱きしめてくれた。僕も、琥珀くんの背中に手を回して強く抱きしめた。
(夢じゃないけど、現実味が湧かないなぁ)
実感がまだ湧かなくて、嬉し涙が止まらない。
「もー泣き虫だなぁ、ゆっきーは」
琥珀くんは僕の両頬に触れて、キスをしてきた。軽くされたキスだったが、触れた唇の感触が残っている。
「あ、泣き止んだ。ふふっ、赤くなってるのちゃんと見るの初めて」
琥珀くんは余裕と言わんばかりに普通に振舞っている。それどころか驚いて涙が引っ込んで照れる僕を軽くいじる。
「あんまり見ないで……。恥ずかしいから」
「ファーストキスだった?」
「……そうだけど、悪い?」
「全然、悪くない。嬉しいよ。だからほら、顔見せて」
顔を隠したい僕と赤くなっている顔を見たい琥珀くんの攻防戦が繰り広げられた。力の強さを出されて、僕は押し倒される形になってしまった。
「可愛いよ、ゆっきー」
琥珀くんの表情はカッコいい雄の顔をしている。僕は至近距離で見たせいで喉を鳴らさずにはいられない。
「可愛いのは琥珀くんの方だよ」
「そうかなー? 俺のこの可愛さは、好きを表に出してできたものだから自然にできたものじゃないんだけどな」
「そうだとしてもだよ」
「じゃあ、雪兎はカッコいい俺と可愛い俺、どっちが好き?」
「もちろん、どっちの琥珀くんも好きだよ」
琥珀くんは目を見開いた。だけど一瞬で目尻を垂らして優しい笑顔を見せた。
「ねぇ雪兎、俺とつき合って」
琥珀くんからのつき合ってという告白に驚きを隠せなかった。「ダメ?」と可愛い子ぶって聞いてくるが、僕の答えは決まっているようなものだ。
(本当は僕から言おうと思ってたのにな。先を越されちゃった)
「僕でよければお願いします。絶対に幸せにする」
「やった!」
僕は、奥底に仕舞ったはずの好きを直接伝えることができた。
それがどれだけ幸せなことか。
僕は起き上がり、琥珀くんを抱き抱えて一緒にクルクルと回った。どこのドラマシーンだよ、なんて言われてもそんな言葉気にしない。
「あははっ、ゆっきーすごい!」
楽しんでいる琥珀くんに目を合わせて心を込めて伝えた。
「琥珀くん、好きだよ」
◇
1日目の文化祭を終えるアナウンスが流れる。僕らは屋上で人が引いていくのを待っていた。その間に準備期間会えず貯まっていた積もる話をして時間を潰した。
「あ、さっき赤面してるところ見たことあるみたいに言ってたよね」
「ソーダッケ?」
「僕ずーっと着ぐるみ被ってたから見せた記憶ないんだけど、どこで見たの?」
「えーっと……」
琥珀くんは話したくないのか、歯切れの悪い返事しか返ってこない。
「怒らないでよ?」
琥珀くんはバツが悪そうな表情をしながら確認してくる。
「分かった、怒らないって約束する」
「雪兎が一緒に食べてくれるようになった時にたまたま見ちゃった。……というか見えちゃったが正解!」
「でも背中合わせてたでしょ?」
「空き教室の雪兎側にある小さい鏡が俺の前にあった大きな鏡に反射して見えちゃってたという、話ですよ」
僕は話を聞いて呆気に取られていたと思う。でも、安心した。
「備品の置き方が悪かったって話かぁ。じゃあ怒れないね」
たまたまが重なってできてしまった偶然が、琥珀くんに顔や秘密を知られる原因になろうとは思ってもいなかった。
「それじゃあ、俺も聞いていい? どうして緊張して顔を隠してるって嘘ついたの?」
うぐっ、答えづらい質問が飛んできてしまった。このことはずっと話さないでいるつもりだったのに。
前のめりに聞いてくる琥珀くんに根負けして、正直に口を割った。
「琥珀くんにだけ赤面するから恥ずかしくて。好きな人にって言えばバレるし、初対面で顔が赤い奴がいたら気持ち悪いと思われるから、咄嗟に考えた理由が『緊張するから』だったんだ」
「ふぅーん、顔が赤くなっちゃうのは好きな人限定ってことかー」
「うぐっ……、そうだよ! 悪い!?」
こうなったら、やけくそだとしか思えなくなった。半ギレみたいな形に突っかかったけど、琥珀くんは「別に! 悪くないよ!」と言って嬉しそうにキスをしてきた。
◇
文化祭2日目は、風邪で休んでいた部員が回復して正式な王子役としてステージに立つことになった。もうステージに立たなくていい状態になったのは嬉しかったけど、寂しい気持ちもどこかにあった。
劇を舞台袖でひばり先輩と見ていた。
「先輩、昨日はありがとうございました。背中押して逃がしてくれたおかげで、好きな人とつき合うことができました」
「そうか、気持ちが伝わってよかったな雪兎。幸せになった新しい雪兎でぜひとも舞台に上がってくれ!」
「上がりません」
ひばり先輩と顔を見合わせ笑いあった。こうやって応援して幸せを願ってくれている人がいるって、改めて痛感した。
「じゃあ、僕クラスの方に行ってきます」
「その子また紹介してくれ」
「もちろんです」
僕は舞台が終わる前に裏出入口から校舎に移動し、2年2組の衣装レンタル写真館に舞い戻った。
「ただいまーって忙しそうだね」
「ここにいる人全員、雪兎くん待ちのお客さんだよ。早く着替えてきて!」
「あ、うん」
僕は昨日と同じように試着室で執事服を着て教室に戻ると、反応は昨日と同じで耳が痛くなるほどの悲鳴が上がる。
「昨日と同じだから大丈夫だよね?」
カメラ係の子が確認してきたから首を縦に振って頷いた。
(今日はクラスに貢献しなきゃな)
待ってもらっていたお客さんを順番に中に入れて対応していた。カーテンの隙間から見た長い列を捌ききるにはすごい時間がかかりそうだった。
(これ終わるのかな……)
見なきゃよかったかもと少しだけ後悔した。
どれだけ時間が経ったのか分からない。外に設置されている野外ステージから『続きましてーお笑い同好会のコントです。どうぞ』と言っているから多分、お昼の時間にはなっている頃だろう。
「まだ終わらなさそう?」
「そうねぇ、もうすぐシフト交代だし締め切ってもいいかも。伝えてくるね」
カメラ係の女子がカーテンの外にいる受付係に伝えてくれた。そのおかげで「如月雪兎シフト交代のため、13時で終了となります」と大声で言われて若干恥ずかしい。
その言葉が届いたのか、「お役がさらにたくさん集まっている」と案内係の男子がコソっと教えてくれた。
「外見てきたけどざっと50人くらいいたかもな」
「50人!? 嘘でしょ……」
「マジだって。だから最後の1人まで対応しないとブーイングくるかもなー」
「えーそれは怖い」
そんな話をしていると次のお客さんが入ってきて、チェキを撮った。なんだかアイドルになった気分に感じてきた。
「うわぁーーー!!!」
カーテンの外から甲高い歓喜の声が聞こえた。区切られたこの場所からは、外で何があったのかが分からなかった。
気にせず続けようとするカメラ係が「次の方どうぞー」と声をかけた。
「こんにちは、写真館へようこそ……って、琥珀くん!?」
琥珀くんはクラスの出し物であるメルヘン喫茶の制服のまま来てくれた。僕の知っているクラシカルなメイド服ではなく、ジャージメイド姿だった。
「ゆっきーとチェキ撮れるって聞いてきてみた」
「来てくれるなんて嬉しいよ!」
「2人仲いいね、いいじゃん。それじゃあ撮るよー」
パシャっとカメラのシャッターを切る音がして、本体から出てきたチェキを受け取って見ると、顔を近づけ片手をハートの形にして挟むようにするルダハートしていた。
「可愛く撮れたね」
「うん、嬉しい」
嬉しそうにしている琥珀くんの周りには花が飛んでいるように見えた。本当に可愛い。
「雪兎くん、終わりの時間だからもう上がっていいよ」
受付係の子が伝えに来たのを合図にカメラ係の子も外に出た。カーテンで区切られた中には2人だけになった。
「琥珀くんはこれからどうするの?」
「俺はゆっきーと出し物見て回ろうと誘いに来た。どう?」
「もちろん良いよ。行こうか。あ、でも着替え」
「ゆっきー似合ってるから着替えなくてもいいよ。それに宣伝になるから着といたほうが良いんじゃない? 俺もクラスの女子に言われたからさ」
琥珀くんに上手く乗せられた感があるけど、衣装のまま2人で校舎内を回った。歩けば「可愛い」や「カッコいい」の言葉が飛び交う。
(確かにジャージメイド似合う琥珀くんは可愛いな)
「ゆっきーどこ行く?」
「とりあえずお腹空いたかな」
「じゃあ、外行くか」
階段を下りてグラウンドに出た。外では体育祭の時でしか見ないようなテントがずらっと並んでいる。
たこ焼き、焼きそば、フランクフルト、ポテト、うどんなどのごはん系もあれば、クレープ、ミルクせんべい、タピオカミルクティなどのスイーツ系もあってお祭りの屋台に負けないくらいの種類の多さに驚愕した。
「多いね、どれにしよう」
「俺も食べてなかったから一緒に食べる。1通り買って中庭で食べよう」
「そうだね、行こう」
僕たちは食べられる分のごはんを買い込んだ。だけど1人の腕の中には収まらないほどの量になってしまった。
「高校生の胃袋だから多くなるよね」
「そうだね。てかこの量はパーティーで分ける時くらいの量でしょ。食べれる?」
琥珀くんは買ったものを持ちながらお腹をかかえて笑っていた。
問いに対して、「多分、大丈夫!」と不安になりながら答えておいた。
「なんとか食べきれたね」
「俺、お腹いっぱいで動けない……」
買ってきたごはんを始めは好きなものを中心に選んで食べて、後半には分担して食べた。その姿はまるで大食いしているかのようだった。
「それにしても、ここは静かでいいね」
「違う世界にいるみたいだよね」
グラウンドから聞こえる司会の声も校舎から流れる放送もこの中には微かにしか聞こえない。人もおらずで本当の本当に2人きりだ。
「ゆっきー、今日の終わり後夜祭あるでしょ? 一緒に屋上行って見ない?」
ごはんを食べて眠くなってたのか、琥珀くんは目を瞑りながら僕にそう言って誘ってきてくれた。
「いいよ。2人で見よう」
僕はもたれかかってくる琥珀くんの頭を撫でながら答えた。
琥珀くんはそのまま寝てしまったけど、安心できる場所と思ってくれているようで嬉しかった。
◇
夕方になり一般のお客さんがいなくなったことを確認してから、出し物の片づけをしつつ後夜祭の準備が始まった。
僕らは約束していた時間まで、各々のクラスの片づけをすることにしている。装飾で元々教室にあったものと捨てるもので分けたり、作った衣装を折角だからと演劇部に譲ってくれたりとそこそこ忙しかった気がする。
「こっちの段ボール持っていくねー」
「ゴミもうない? 持って下りるけど」
「あー、もう少し待って!」
窓の外ではキャンプファイヤーの準備がされていた。毎年恒例なんだそうだ。
「何かいいのあったか?」
「鷹也。キャンプファイヤー今年もするんだなと思って。そういえば鷹也ほぼずっとクラスの出し物に捕まってたって聞いたけど大丈夫だった?」
「まぁ、休憩取りながらだったし平気かな」
鷹也は獅埜と遊んであげるくらいだし体力が僕よりもあるのだろうな。
(あ、鷹也には伝えておこう……)
「ねぇ鷹也、耳貸して」
「あぁ?」
「あのね、僕琥珀くんとつき合えることになったよ」
「……そう、か。良かったじゃん」
「鷹也には直接伝えておきたくて。色々と聞いてくれてありがとうね」
「気にすんなって。これからが頑張り時だな」
「うん! あ、琥珀くんと約束してるから行ってくるね」
「あぁ。……幸せになれよ」
僕はこの時知らなかったことがあった。鷹也は僕のことが好きだったってこと。
知らなかったとはいえ、好きな人がずっと思っていた人とつき合ったと報告されたらどうだろう。僕だったら苦しくて耐えられない。
だけど鷹也は僕の幸せを願ってくれたカッコよくて優しい、大切な友達──。
「お待たせ、琥珀くん」
「俺もさっき来たところ。ほら、見て」
さっきまで準備していたキャンプファイヤーに火が灯り輝いていた。
「綺麗に燃えてるね。近くに見に行こうか」
「ううん、ここで良いよ」
琥珀くんがフェンスにもたれかかったのを見て、僕も当然のように隣に座った。肩に頭を寄せてきた琥珀くんが、「終わってほしくないなぁ」と呟いた。
「そうだね。僕も終わってほしくない。でも来年も一緒に出し物見て回ったり、クラスが一緒なら同じ係になって時間を共にしようよ」
肩にもたれている琥珀くんの表情は見えないからわからないけど、ピクっと動いた感じから驚いているってわかる。
「来年も……」
──ヒュー、バーン。
突如、夜空に花が咲いた。次々と上がる花火は赤にも青にも色を変える。
「綺麗だなぁー」
キャンプファイヤーを見た後じゃあ、比べるのは可哀そうだけど綺麗なのはどちらも同じ。
何発も上がる花火に見惚れていると、琥珀くんが制服の袖を引っ張ってきた。
「ゆっきー、僕とつき合うって決めてくれてありがとう。来年も同じ景色が見れるように頑張るね」
その言葉が心に響いて泣きそうになった。瞳をウルウルさせながらも、僕も言葉に紡ぐ。
「琥珀くん、僕の方こそお礼を言いたい。ありがとう。頼りない僕だけど、大切にするって誓う。大好きだよ」
琥珀くんは僕に抱きついてきた。まるで幸せを嚙みしめるかのようにギュッと。
僕らは花火そっちのけでキスをした。綺麗な光景をそのまま脳裏に刻みこむかのように大切に──。