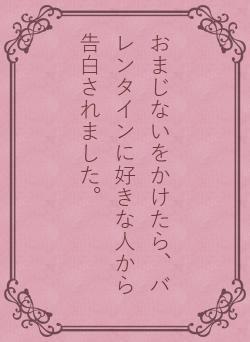昔から可愛いと言われることが多かった。だが、幼い頃は可愛いものが嫌いだった。
「なんでおれはこんなフリフリの服を着ないといけないの?」
「ごめんな、琥珀。小さいときだけでいいから、母さんを笑顔にさせるために協力してくれないか?」
母さんは女の子を望んでいた。だが“俺”が生まれたせいでショックを受け、病んでいるのだと父さんから聞いたことがある。
その時の俺は理解できていなかったけど、我慢をしないといけないのだということだけ分かった。
「あら琥珀ちゃん、来てくれたのね」
母さんの姿はいつも自室のベッドの上にあった。僕に我慢をさせる母さんが嫌いだった。
でも大好きな父さんの頼みだったから、笑顔で「お母さん」と言って歩み寄った。
会うたびに言われる呪いの言葉。
「琥珀ちゃんは綺麗な髪をしてて羨ましいわー。それに可愛い顔立ちしているからワンピースが似合うわね」
髪に触れられながら言われるそれは、当時ストレスとして蓄積していった。
「そろそろ琥珀を男の子として扱った方が良いんじゃないの?」
小学生に入ってすぐの頃、広い家の廊下で父さんとばあちゃんが話しているのをたまたま聞いてしまった。
「俺、ワンピースとかもう着なくていいのかな……」
確定したことではないのに、とても嬉しかった。それと同時に母さんと会う時にズボンだったら、どうなるんだろうかとも思った。
試しに部屋の箪笥に入っているズボンを履いて、母さんの部屋に行ってみる。自分の意志で来たのは初めてだ。
──コンコン。
「お母さん、今いい?」
「その声は琥珀ちゃんね! 入ってきてちょうだいな」
明るい声に期待が増大しすぎてしまった。入った途端、母さんの顔が青ざめて「イヤー――!!!」と家中に声が響いた。
「なんだ、どうした?!」
走って母さんの部屋に来た父さんが、ズボンを履いている俺とブツブツと言って小さくなっている母さんの両方を見た。
「お義母さん、琥珀を部屋に」
「分かったわ」
俺は何も分からず、ばあちゃんに連れられて自室に戻されてしまった。振り返れば母に寄りそう父さんの姿があって、とんでもないことをしてしまったんだと気がついた。
──コンコン。
「琥珀、入っていいかい?」
「……うん」
若干、疲れ切っている父さんが部屋に入ってきた。
「琥珀……」
「ごめんなさい! お母さんに会いに行っちゃって」
「会いに行くことは構わないよ。琥珀はどうしてズボンを履いて会いに行ったんだ? 聞かせてくれないか?」
父さんは怒ることはせず、俺の話を聞いてくれた。廊下で話していたのを聞いていたこと、母さんはどう反応するのか気になったことを全て伝えた。
「聞いてたんだな。琥珀は男の子として生活したいか?」
「うん……」
「じゃあ、父さんに任せなさい」
「あの、お父さん。お母さんは大丈夫?」
「落ち着いて寝てるよ。心配してくれてありがとうな」
話しを終えた父さんは部屋を出て行った。母さんに対しての罪悪感がありつつも俺は男として生活できることが嬉しく思えた。
翌日、起きて食卓に行けば普通に接してくれている父さんとばあちゃんがいた。
「おはよう」
「おはよう、琥珀ちゃん。よく寝れた?」
「おはよう琥珀、後で話あるから聞いてくれるか?」
「うん」
並べられている朝ご飯を3人で囲んで食べた。
ごはんを食べ終わったら言われていた通り、父さんから話をされた。それは家の隣に建っている道場で、空手の師範をしているじいちゃんに空手を習うことの提案だった。
じいちゃんとはあまり話したりはしないけど、漢って感じでカッコいいと思っていた。
「琥珀がやりたくないならいいがどうする?」
「したい。俺頑張って強くなりたい!」
そうして俺は強くなるために空手を習い始めた。じいちゃんの指導は身内だからと言って、優しいものではなかった。
「いいな、琥珀。男に可愛いものは不要。そんな気持ちは精神的にも強くはなれん。お前には可愛いもの禁止という条件もつける」
「わかったよ、じいちゃん。別に禁止されても困ることないし」
辞めたいと思ったこともあったけど、男として暮らしたいという気持ちの支えがあって何回も乗り越えることができた。そして気がつけば9年経ち、高校生になっていた。
◇
高校生になっても、じいちゃんは変わらず可愛いものを禁止してきた。そのおかげか、精神が統一されてずっと空手で大会で勝つほどの強さを維持してきた。
「あ、可愛い……」
部活からの帰る途中、雑貨屋のショーウィンドウに赤いリボンを首に巻いたクマのぬいぐるみが飾ってあった。
嫌いだった可愛いものに違いないのに、嫌悪感がなくどちらかと言えば好意を抱いた。
「入ってみようかな……」
初めて自分の意志で可愛い雑貨屋さんに入った。
「いらっしゃいませ。ごゆっくりご覧ください」
制服の可愛い店員さんが、優しく声をかけてきてくれて思わず会釈する。店内を見て回ると、ぬいぐるみもあれば鞄や筆記用具などを売っていた。
「可愛いなぁ」
「気になる商品がございましたか?」
「あ、えーっと、ショーウィンドウのぬいぐるみが気になって……」
「あー! あちらですね。とても人気商品なんですよ! この店舗でもあと少ししかないもので。触ってみますか?」
店員さんも勧めるくらい人気のテディベア。触らせてもらって確信した、俺は可愛いものが好き。思わず口走っていた。
「すみません、これください」
「ありがとうございました。またお越しください」
出口まで見送ってもらい、紙袋を受け取った。しばらく歩いてからテディベアを見ると心も足取りも軽くなった。
家に帰ってからは、買ってきたことがバレないようにするのに必死だった。静かに玄関を開けて靴を脱ぎ、誰にもバレないように素早く部屋へ直行した。
(何か悪いことをしている気分だ)
襖を開けて部屋に入って紙袋だけ手に持ち、他の荷物を放りだす。
「ふぁあ! 可愛い、もふもふだぁ」
紙袋から中身を取りだしてギュッと抱きしめてみた。ずっと抱きしめていられる。
「琥珀ちゃん? 帰ってるの?」
ばあちゃんが帰宅したことに気づいて声をかけてきてくれた。静かに入ったはずなのにどうしてバレてしまったのだろう。
「か、帰ってるよ」
「干し終わった洗濯物持ってきたのだけど渡してもいいかしら? とりあえず開けるわね?」
「ちょっ……」
待ってと言う前に、襖を開けて入ってきてしまった。テディベアを抱えている俺が立っているから、ばあちゃんはびっくりしたと思う。
「あ、えっと……」
戸惑う俺は、ばあちゃんがじいちゃんに告げ口されるのではないかと不安になった。だけどそれは杞憂で、ぬいぐるみのことを知ろうと親身に温かい言葉をかけてくれる。
「可愛らしい子ね。お名前はあるの?」
「まだ、決めてない」
「そうなの。決まったら教えてちょうだいね。はい、洗濯物。片づけておいてね」
そう言って、ばあちゃんは洗濯物を俺に渡して出て行った。どうして何も言わなかったんだろうと疑問が生まれたが、不思議と安心もした。
季節が進む毎に可愛い雑貨が少しづつ増えていった。部屋には飾れない可愛すぎる物たちは押し入れに隠して飾っている。
ばあちゃんは俺が可愛いものを好きだと知ってから、「琥珀ちゃん、この服可愛いと思わない? 好きだといいんだけど」と言って、シンプルだけど可愛い色の服を選んできてくれることもあった。
俺は知らぬ間に可愛いのが好きだと隠さなくなった。制服のブレザーの下にパーカーを着るときはもらったものを着たりした。その時は気分が上がって、頑張ろうと思えた。
◇
1年生の秋だった。たまたま自販機に飲み物を買いに校舎から出た時、どこからか「助けて」と聞こえた。
はじめは気のせいと思ったけど、何度も聞こえれば気のせいでは済まされない。
辿れば、学年でいや学校内でイケメン男子と有名な如月雪兎がモヒカンの先輩に捕まっていたのを見た。
関係ないことだし、首を突っ込まないのがいいと思った。だけど、じいちゃんから教えられた『弱い者を守るのが強者の使命』と言う言葉が脳裏をよぎり、身体が自然と動き、助けに行ってしまった。
尻もちをついている雪兎に殴りかかろうとしている先輩を止め、脅し程度に拳を突きつけたら、悪役みたいなセリフを吐き背中を見せて去っていく。
「大丈夫だった?」
立ち上がりやすいように手を差し伸べると、雪兎はおずおずと取った。
「ありがとう、ございます」
「じゃあ、俺はこれで」
その場を去ろうとした時、琥珀に手首を掴まれ掌に何か載せられた。
「これは……?」
「それは最近ハマっている毛糸の人形です。いらないかもしれないですけどお礼にもらってください」
「あ、ありがとう」
あの時の人形を俺はずっと持ち歩くようになって、暇さえあればずっと見ていた。とっても可愛いウサギだった。
「頼んだら仲間作ってくれたりするのかな」
一度期待してしまうと会いたい気持ちが高まっていった。次会った時は絶対に聞いてみようとそう思って過ごしていた。
何回か学校で見かけたことがあったが、話すところまではいかなかった。だって同じクラスでもなければ、共通の話題もないのだから。
「どうしたら話せるんだろう」
何か口実が欲しいが適した理由が見つからず、家に帰るときも考えたけど答えが出せない。
「ただいまー」
「あぁ、琥珀ちゃん。おかえりなさい」
玄関の引き戸を開けると、ばあちゃんが青ざめた表情で僕を迎えた。
「ばあちゃんどうしたの、そんなに慌てて」
「琥珀ちゃんの秘密がバレてしまって、おじいさんが勝手にあなたの部屋に入っちゃってるのよ。止めたんだけど振り切られちゃって」
可愛いものを禁止したじいちゃんが、コソコソと収集した可愛いものを見たらどう反応するのだろう。俺の背に冷や汗が流れる。
急いで靴を脱ぎ走って部屋に向かった。
じいちゃんは、押し入れの中に入っていたぬいぐるみや小物を部屋中にまき散らかしてしていた。
「何してるの、じいちゃん」
「帰ったか琥珀。なんだこれらは」
「これは……」
「ワシは空手を始める時に言ったはずだ。可愛いものを禁止すると。それを了承したのはお前だ、そうだな」
「……」
「ばあさん、これを捨てなさい」
「何を言ってるんですか、これは琥珀ちゃんの……」
「聞こえんかったか! ワシは捨てろといたのだ、二度も言わせるな」
じいちゃんは、ばあちゃんに怒鳴って部屋を後にした。出された物の中には大切にしていたものが壊れているものもあった。
「琥珀ちゃん……」
「ごめん、ばあちゃん。怒られちゃって。捨てる、捨てるよ」
俺の目から大粒の涙が溢れてきた。
(悔しい……)
それから集めていたものを全てゴミ袋に入れて、言われた通り捨てた。幸いテディベアは奥に隠していたからバレずに済んだ。
見つかったからと言って可愛いもの好きを止められるはずはなく、その日から可愛いものを買うときは細心の注意を払うようにしていた。
それと同時に家にいると息が詰まって、過ごしにくいと感じるようになった。
2年生の春、陽だまりが集まっている廊下を歩いていると演劇部の倉庫から段ボールを持って屋上に行く雪兎を見つけた。
何をするために屋上に行ったのかは分からないけど、偶然を装って屋上のドアを開いた。
わざとらしく「ふわぁ、いい天気であくびが出ちゃった......」なんて言って入ってみたけど、雪兎の姿は見えず。
振り返ってみると雪兎ではなく、ウサギの着ぐるみを被っている誰かがいた。
(雪兎、だよな?)
じっと見ていると、綺麗に縫いなおされている輪郭と耳についている王冠が目を引いた。だけど雪兎の手は止まったままで、何かあったのではないかと心配にもなった。
「あれ、ウサギ……さん? えっと迷子とか、ではなさそうだね」
このウサギは本当に雪兎なのか、俺は不安になりながらもわざとらしくウサギに声をかけた。名前を聞けば雪兎と答えたので、探していた本人に間違いないらしい。
「はじめまして」のていで話しかけたので、雪兎はかぶりものしているのが自分だとバレてないと勘違いしてすぐに心を開いてくれた。
その日から屋上に行く回数が圧倒的に増えてた。何より俺自身が放課後に屋上へ行くことが楽しくなってしまったから。
何気ない話をするのも楽しいし、雪兎を知れて嬉しいと感じていた。でも一番は雪兎が可愛いものを作っている魔法使いみたいな姿を好きになった。
雪兎と過ごす時間を、初めて誰にも奪われたくないものとして認識したのも、この時くらいだったような気がする。
「どうしていつもウサギなんか被ってるの?」
俺は中身を知っていたけど、雪兎がウサギの着ぐるみを被っている理由を知りたかった。普段は顔を出しているのに、ここにいる時は被っているから明らかにおかしい。
(花粉症とか? でもそれにしても分厚いし重そうな気が……)
雪兎からの答えは「緊張すると赤面する」と言うものだった。慣れた人なら耐性がついて赤面になりづらいと聞いた。
(確かに。毎日と言っていいほど会っているけど、一緒にいる時間はまだ短いよね)
どうすれば協力してあげることができるのだろうか。ハッと俺の頭にいい方法が浮かんだ。
「俺が緊張せずに話せるように手伝ってやるよ」
こうすれば、これまで通り話すこともできるし雪兎の赤面も治ると思って提案してみた。雪兎からは「じゃあ、お願いします」と返答をもらうことができた。
雪兎は優しいからドレスに使う予定だったリボンをブローチにしてくれたり、申し訳ないほどたくさんのものをくれたりした。
次の日から昼休みに集まるようにした。俺が昼飯に手をつける中、雪兎は持ってきていた弁当を食べなかった。
ずっと食べる俺と食べない雪兎の光景が数か月続き、梅雨が来てしまった。
外に出ることができないからと先輩に教えてもらっていた空き教室で集まるようになり、雪兎に一緒に食べたいと申し出た。
俺の説得が通って、背中合わせでだが一緒に食べることができて嬉しかった。
ある時、ウサギと同じく気になっていたことを尋ねてみた。
「雪兎は、男なのに裁縫するの嫌じゃないの?」
僕はじいちゃんが『男に可愛いものは不要』と長年言われていたのもあって、男にはカッコいいもの、女には可愛いものという考えが頑固な汚れのようにこべりついていた。
「うーん、僕は裁縫や手芸が好きだから嫌だと思わないかな。昔は揶揄われること多かったんだけど、否定されて辞めるんじゃなくて、“好きなことが好き”って言える方がカッコいいと思ったんだよね」
雪兎の言葉が心に刺さった。
そして“好きなものは好き”と言える雪兎をより好きになった。
それから、雪兎に対しての想いが、友達から好きな人へと変わった。
(雪兎と並べるようになりたい。俺も可愛いものが好きだって誇りたい)
家に帰ってから、俺は押し入れに隠していたテディベアをベッドの上に置いた。他にも隠していた可愛い小物たちを机や本棚に並べたりした。
「琥珀ちゃん、おかえり」
「ただいま、ばあちゃん」
「琥珀ちゃん、おじいさんが部屋を見たらまた……」
「大丈夫だよ。俺、今度こそ“好きなものは好き”って言いたいんだ」
俺は久々に家で笑顔を見せることができた。これも雪兎のおかげ。
ごはんを食べてる時にじいちゃんと父さんに、可愛いものが好きだと告白した。何か言ってくると思ったじいちゃんは「好きにしろ」とさっぱりしていた。
今までダメと言い続けていたのに思いのほかさっぱりとした返事だった。
「おじいさんは言葉足らずね」
「そうだな」
父さんとばあちゃんにはわかったようだった。ばあちゃんが教えてくれたのは、俺が可愛いものを隠さず、自らの意見を言えるようにという意図があった。
父さんは相変わらず俺のことを優先に考えてくれて「好きなようにしたらいいさ」と抱きしめてくれた。
次の日の昼休み、空き教室に行くと雪兎は待ってくれていた。
(雪兎に好きだと告白したらどんな反応するんだろう)
赤くなる顔がもっと赤くなってゆでだこみたいになるのか、はたまた気持ち悪いと言って拒絶するのか。
(伝えるのはまだ先の方がいいな。でも、いつか伝えるから覚悟しておいてよ)
この時はまだ知らない。念願叶って、雪兎とつき合えるようになるなんて。
「なんでおれはこんなフリフリの服を着ないといけないの?」
「ごめんな、琥珀。小さいときだけでいいから、母さんを笑顔にさせるために協力してくれないか?」
母さんは女の子を望んでいた。だが“俺”が生まれたせいでショックを受け、病んでいるのだと父さんから聞いたことがある。
その時の俺は理解できていなかったけど、我慢をしないといけないのだということだけ分かった。
「あら琥珀ちゃん、来てくれたのね」
母さんの姿はいつも自室のベッドの上にあった。僕に我慢をさせる母さんが嫌いだった。
でも大好きな父さんの頼みだったから、笑顔で「お母さん」と言って歩み寄った。
会うたびに言われる呪いの言葉。
「琥珀ちゃんは綺麗な髪をしてて羨ましいわー。それに可愛い顔立ちしているからワンピースが似合うわね」
髪に触れられながら言われるそれは、当時ストレスとして蓄積していった。
「そろそろ琥珀を男の子として扱った方が良いんじゃないの?」
小学生に入ってすぐの頃、広い家の廊下で父さんとばあちゃんが話しているのをたまたま聞いてしまった。
「俺、ワンピースとかもう着なくていいのかな……」
確定したことではないのに、とても嬉しかった。それと同時に母さんと会う時にズボンだったら、どうなるんだろうかとも思った。
試しに部屋の箪笥に入っているズボンを履いて、母さんの部屋に行ってみる。自分の意志で来たのは初めてだ。
──コンコン。
「お母さん、今いい?」
「その声は琥珀ちゃんね! 入ってきてちょうだいな」
明るい声に期待が増大しすぎてしまった。入った途端、母さんの顔が青ざめて「イヤー――!!!」と家中に声が響いた。
「なんだ、どうした?!」
走って母さんの部屋に来た父さんが、ズボンを履いている俺とブツブツと言って小さくなっている母さんの両方を見た。
「お義母さん、琥珀を部屋に」
「分かったわ」
俺は何も分からず、ばあちゃんに連れられて自室に戻されてしまった。振り返れば母に寄りそう父さんの姿があって、とんでもないことをしてしまったんだと気がついた。
──コンコン。
「琥珀、入っていいかい?」
「……うん」
若干、疲れ切っている父さんが部屋に入ってきた。
「琥珀……」
「ごめんなさい! お母さんに会いに行っちゃって」
「会いに行くことは構わないよ。琥珀はどうしてズボンを履いて会いに行ったんだ? 聞かせてくれないか?」
父さんは怒ることはせず、俺の話を聞いてくれた。廊下で話していたのを聞いていたこと、母さんはどう反応するのか気になったことを全て伝えた。
「聞いてたんだな。琥珀は男の子として生活したいか?」
「うん……」
「じゃあ、父さんに任せなさい」
「あの、お父さん。お母さんは大丈夫?」
「落ち着いて寝てるよ。心配してくれてありがとうな」
話しを終えた父さんは部屋を出て行った。母さんに対しての罪悪感がありつつも俺は男として生活できることが嬉しく思えた。
翌日、起きて食卓に行けば普通に接してくれている父さんとばあちゃんがいた。
「おはよう」
「おはよう、琥珀ちゃん。よく寝れた?」
「おはよう琥珀、後で話あるから聞いてくれるか?」
「うん」
並べられている朝ご飯を3人で囲んで食べた。
ごはんを食べ終わったら言われていた通り、父さんから話をされた。それは家の隣に建っている道場で、空手の師範をしているじいちゃんに空手を習うことの提案だった。
じいちゃんとはあまり話したりはしないけど、漢って感じでカッコいいと思っていた。
「琥珀がやりたくないならいいがどうする?」
「したい。俺頑張って強くなりたい!」
そうして俺は強くなるために空手を習い始めた。じいちゃんの指導は身内だからと言って、優しいものではなかった。
「いいな、琥珀。男に可愛いものは不要。そんな気持ちは精神的にも強くはなれん。お前には可愛いもの禁止という条件もつける」
「わかったよ、じいちゃん。別に禁止されても困ることないし」
辞めたいと思ったこともあったけど、男として暮らしたいという気持ちの支えがあって何回も乗り越えることができた。そして気がつけば9年経ち、高校生になっていた。
◇
高校生になっても、じいちゃんは変わらず可愛いものを禁止してきた。そのおかげか、精神が統一されてずっと空手で大会で勝つほどの強さを維持してきた。
「あ、可愛い……」
部活からの帰る途中、雑貨屋のショーウィンドウに赤いリボンを首に巻いたクマのぬいぐるみが飾ってあった。
嫌いだった可愛いものに違いないのに、嫌悪感がなくどちらかと言えば好意を抱いた。
「入ってみようかな……」
初めて自分の意志で可愛い雑貨屋さんに入った。
「いらっしゃいませ。ごゆっくりご覧ください」
制服の可愛い店員さんが、優しく声をかけてきてくれて思わず会釈する。店内を見て回ると、ぬいぐるみもあれば鞄や筆記用具などを売っていた。
「可愛いなぁ」
「気になる商品がございましたか?」
「あ、えーっと、ショーウィンドウのぬいぐるみが気になって……」
「あー! あちらですね。とても人気商品なんですよ! この店舗でもあと少ししかないもので。触ってみますか?」
店員さんも勧めるくらい人気のテディベア。触らせてもらって確信した、俺は可愛いものが好き。思わず口走っていた。
「すみません、これください」
「ありがとうございました。またお越しください」
出口まで見送ってもらい、紙袋を受け取った。しばらく歩いてからテディベアを見ると心も足取りも軽くなった。
家に帰ってからは、買ってきたことがバレないようにするのに必死だった。静かに玄関を開けて靴を脱ぎ、誰にもバレないように素早く部屋へ直行した。
(何か悪いことをしている気分だ)
襖を開けて部屋に入って紙袋だけ手に持ち、他の荷物を放りだす。
「ふぁあ! 可愛い、もふもふだぁ」
紙袋から中身を取りだしてギュッと抱きしめてみた。ずっと抱きしめていられる。
「琥珀ちゃん? 帰ってるの?」
ばあちゃんが帰宅したことに気づいて声をかけてきてくれた。静かに入ったはずなのにどうしてバレてしまったのだろう。
「か、帰ってるよ」
「干し終わった洗濯物持ってきたのだけど渡してもいいかしら? とりあえず開けるわね?」
「ちょっ……」
待ってと言う前に、襖を開けて入ってきてしまった。テディベアを抱えている俺が立っているから、ばあちゃんはびっくりしたと思う。
「あ、えっと……」
戸惑う俺は、ばあちゃんがじいちゃんに告げ口されるのではないかと不安になった。だけどそれは杞憂で、ぬいぐるみのことを知ろうと親身に温かい言葉をかけてくれる。
「可愛らしい子ね。お名前はあるの?」
「まだ、決めてない」
「そうなの。決まったら教えてちょうだいね。はい、洗濯物。片づけておいてね」
そう言って、ばあちゃんは洗濯物を俺に渡して出て行った。どうして何も言わなかったんだろうと疑問が生まれたが、不思議と安心もした。
季節が進む毎に可愛い雑貨が少しづつ増えていった。部屋には飾れない可愛すぎる物たちは押し入れに隠して飾っている。
ばあちゃんは俺が可愛いものを好きだと知ってから、「琥珀ちゃん、この服可愛いと思わない? 好きだといいんだけど」と言って、シンプルだけど可愛い色の服を選んできてくれることもあった。
俺は知らぬ間に可愛いのが好きだと隠さなくなった。制服のブレザーの下にパーカーを着るときはもらったものを着たりした。その時は気分が上がって、頑張ろうと思えた。
◇
1年生の秋だった。たまたま自販機に飲み物を買いに校舎から出た時、どこからか「助けて」と聞こえた。
はじめは気のせいと思ったけど、何度も聞こえれば気のせいでは済まされない。
辿れば、学年でいや学校内でイケメン男子と有名な如月雪兎がモヒカンの先輩に捕まっていたのを見た。
関係ないことだし、首を突っ込まないのがいいと思った。だけど、じいちゃんから教えられた『弱い者を守るのが強者の使命』と言う言葉が脳裏をよぎり、身体が自然と動き、助けに行ってしまった。
尻もちをついている雪兎に殴りかかろうとしている先輩を止め、脅し程度に拳を突きつけたら、悪役みたいなセリフを吐き背中を見せて去っていく。
「大丈夫だった?」
立ち上がりやすいように手を差し伸べると、雪兎はおずおずと取った。
「ありがとう、ございます」
「じゃあ、俺はこれで」
その場を去ろうとした時、琥珀に手首を掴まれ掌に何か載せられた。
「これは……?」
「それは最近ハマっている毛糸の人形です。いらないかもしれないですけどお礼にもらってください」
「あ、ありがとう」
あの時の人形を俺はずっと持ち歩くようになって、暇さえあればずっと見ていた。とっても可愛いウサギだった。
「頼んだら仲間作ってくれたりするのかな」
一度期待してしまうと会いたい気持ちが高まっていった。次会った時は絶対に聞いてみようとそう思って過ごしていた。
何回か学校で見かけたことがあったが、話すところまではいかなかった。だって同じクラスでもなければ、共通の話題もないのだから。
「どうしたら話せるんだろう」
何か口実が欲しいが適した理由が見つからず、家に帰るときも考えたけど答えが出せない。
「ただいまー」
「あぁ、琥珀ちゃん。おかえりなさい」
玄関の引き戸を開けると、ばあちゃんが青ざめた表情で僕を迎えた。
「ばあちゃんどうしたの、そんなに慌てて」
「琥珀ちゃんの秘密がバレてしまって、おじいさんが勝手にあなたの部屋に入っちゃってるのよ。止めたんだけど振り切られちゃって」
可愛いものを禁止したじいちゃんが、コソコソと収集した可愛いものを見たらどう反応するのだろう。俺の背に冷や汗が流れる。
急いで靴を脱ぎ走って部屋に向かった。
じいちゃんは、押し入れの中に入っていたぬいぐるみや小物を部屋中にまき散らかしてしていた。
「何してるの、じいちゃん」
「帰ったか琥珀。なんだこれらは」
「これは……」
「ワシは空手を始める時に言ったはずだ。可愛いものを禁止すると。それを了承したのはお前だ、そうだな」
「……」
「ばあさん、これを捨てなさい」
「何を言ってるんですか、これは琥珀ちゃんの……」
「聞こえんかったか! ワシは捨てろといたのだ、二度も言わせるな」
じいちゃんは、ばあちゃんに怒鳴って部屋を後にした。出された物の中には大切にしていたものが壊れているものもあった。
「琥珀ちゃん……」
「ごめん、ばあちゃん。怒られちゃって。捨てる、捨てるよ」
俺の目から大粒の涙が溢れてきた。
(悔しい……)
それから集めていたものを全てゴミ袋に入れて、言われた通り捨てた。幸いテディベアは奥に隠していたからバレずに済んだ。
見つかったからと言って可愛いもの好きを止められるはずはなく、その日から可愛いものを買うときは細心の注意を払うようにしていた。
それと同時に家にいると息が詰まって、過ごしにくいと感じるようになった。
2年生の春、陽だまりが集まっている廊下を歩いていると演劇部の倉庫から段ボールを持って屋上に行く雪兎を見つけた。
何をするために屋上に行ったのかは分からないけど、偶然を装って屋上のドアを開いた。
わざとらしく「ふわぁ、いい天気であくびが出ちゃった......」なんて言って入ってみたけど、雪兎の姿は見えず。
振り返ってみると雪兎ではなく、ウサギの着ぐるみを被っている誰かがいた。
(雪兎、だよな?)
じっと見ていると、綺麗に縫いなおされている輪郭と耳についている王冠が目を引いた。だけど雪兎の手は止まったままで、何かあったのではないかと心配にもなった。
「あれ、ウサギ……さん? えっと迷子とか、ではなさそうだね」
このウサギは本当に雪兎なのか、俺は不安になりながらもわざとらしくウサギに声をかけた。名前を聞けば雪兎と答えたので、探していた本人に間違いないらしい。
「はじめまして」のていで話しかけたので、雪兎はかぶりものしているのが自分だとバレてないと勘違いしてすぐに心を開いてくれた。
その日から屋上に行く回数が圧倒的に増えてた。何より俺自身が放課後に屋上へ行くことが楽しくなってしまったから。
何気ない話をするのも楽しいし、雪兎を知れて嬉しいと感じていた。でも一番は雪兎が可愛いものを作っている魔法使いみたいな姿を好きになった。
雪兎と過ごす時間を、初めて誰にも奪われたくないものとして認識したのも、この時くらいだったような気がする。
「どうしていつもウサギなんか被ってるの?」
俺は中身を知っていたけど、雪兎がウサギの着ぐるみを被っている理由を知りたかった。普段は顔を出しているのに、ここにいる時は被っているから明らかにおかしい。
(花粉症とか? でもそれにしても分厚いし重そうな気が……)
雪兎からの答えは「緊張すると赤面する」と言うものだった。慣れた人なら耐性がついて赤面になりづらいと聞いた。
(確かに。毎日と言っていいほど会っているけど、一緒にいる時間はまだ短いよね)
どうすれば協力してあげることができるのだろうか。ハッと俺の頭にいい方法が浮かんだ。
「俺が緊張せずに話せるように手伝ってやるよ」
こうすれば、これまで通り話すこともできるし雪兎の赤面も治ると思って提案してみた。雪兎からは「じゃあ、お願いします」と返答をもらうことができた。
雪兎は優しいからドレスに使う予定だったリボンをブローチにしてくれたり、申し訳ないほどたくさんのものをくれたりした。
次の日から昼休みに集まるようにした。俺が昼飯に手をつける中、雪兎は持ってきていた弁当を食べなかった。
ずっと食べる俺と食べない雪兎の光景が数か月続き、梅雨が来てしまった。
外に出ることができないからと先輩に教えてもらっていた空き教室で集まるようになり、雪兎に一緒に食べたいと申し出た。
俺の説得が通って、背中合わせでだが一緒に食べることができて嬉しかった。
ある時、ウサギと同じく気になっていたことを尋ねてみた。
「雪兎は、男なのに裁縫するの嫌じゃないの?」
僕はじいちゃんが『男に可愛いものは不要』と長年言われていたのもあって、男にはカッコいいもの、女には可愛いものという考えが頑固な汚れのようにこべりついていた。
「うーん、僕は裁縫や手芸が好きだから嫌だと思わないかな。昔は揶揄われること多かったんだけど、否定されて辞めるんじゃなくて、“好きなことが好き”って言える方がカッコいいと思ったんだよね」
雪兎の言葉が心に刺さった。
そして“好きなものは好き”と言える雪兎をより好きになった。
それから、雪兎に対しての想いが、友達から好きな人へと変わった。
(雪兎と並べるようになりたい。俺も可愛いものが好きだって誇りたい)
家に帰ってから、俺は押し入れに隠していたテディベアをベッドの上に置いた。他にも隠していた可愛い小物たちを机や本棚に並べたりした。
「琥珀ちゃん、おかえり」
「ただいま、ばあちゃん」
「琥珀ちゃん、おじいさんが部屋を見たらまた……」
「大丈夫だよ。俺、今度こそ“好きなものは好き”って言いたいんだ」
俺は久々に家で笑顔を見せることができた。これも雪兎のおかげ。
ごはんを食べてる時にじいちゃんと父さんに、可愛いものが好きだと告白した。何か言ってくると思ったじいちゃんは「好きにしろ」とさっぱりしていた。
今までダメと言い続けていたのに思いのほかさっぱりとした返事だった。
「おじいさんは言葉足らずね」
「そうだな」
父さんとばあちゃんにはわかったようだった。ばあちゃんが教えてくれたのは、俺が可愛いものを隠さず、自らの意見を言えるようにという意図があった。
父さんは相変わらず俺のことを優先に考えてくれて「好きなようにしたらいいさ」と抱きしめてくれた。
次の日の昼休み、空き教室に行くと雪兎は待ってくれていた。
(雪兎に好きだと告白したらどんな反応するんだろう)
赤くなる顔がもっと赤くなってゆでだこみたいになるのか、はたまた気持ち悪いと言って拒絶するのか。
(伝えるのはまだ先の方がいいな。でも、いつか伝えるから覚悟しておいてよ)
この時はまだ知らない。念願叶って、雪兎とつき合えるようになるなんて。