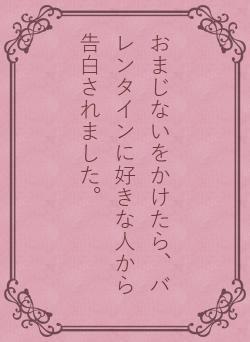僕は心臓をバクバクさせながら屋上に向かっていた。
それもそのはず。あの日、琥珀くんと約束した『赤面にならない練習』を今日から開始するからだ。
前は部活時間と被っている放課後に会っていたけど、時間が短いから練習はお昼休みにすると言われていた。
「大丈夫、練習するだけ。何もない。よし!」
僕はドア横に隠していたウサギの着ぐるみを被って、相変わらずきしんだ音を立てながらドアを開ける。
(まだ来てない、かな?)
恐る恐る屋上に足を踏み入れると、頭上から「あー、来たー」と可愛らしい声が聞こえ天を仰いだ。
塔屋(とうや)に目をむけると、太陽に照らされて綺麗に反射しているクリーム色の髪がなびき僕の視線を奪う。
(いつ見ても綺麗なクリーム色……。階段で会った時と変わってない)
「ずーっと待ってたんだよ?」
「ごめん、先生に質問してたら遅くなっちゃった。お昼は食べた?」
「ううん、一緒に食べようと思って待ってたんだぁ」
「あ、そうだったんだ。待たせてごめんね、食べようか」
持ってきていたお弁当を片手に塔屋にもたれかかる。上から降りてきた琥珀くんは当たり前のように僕の隣に座る。
ちょこんと座る姿がなんとも小動物みたいで可愛らしい。
琥珀くんがビニール袋から出したのは、多分購買で買ったであろう焼きそばパンとコロッケサンドパン。そして購買で一番人気と言っていいほど有名な、いちごをふんだんに使った数量限定のクリームパンを広げてどれから食べるか悩んでいた。
(僕もお弁当食べ……いや、着ぐるみしてたら食べられないじゃん! 外す手もあるけどそうしたらもっと赤くなって今まで隠してきた意味がなくなっちゃう……。明日からお昼ご飯をどうするか考えないとな)
「焼きそばパンから食べようっと。あれ、ゆっきーは食べないの? 美味しそうなお弁当なのに」
「あー、今日はそんなにお腹空いてなくて。よかったら食べる?」
「え、いいの?」
「もちろん、食べてくれたら食材が無駄にならなくて済むし助かるよ」
「じゃあ、遠慮なく。それじゃあ、俺からお返しにクリームパンあげるね」
「それこそいいの? 数量限定だし、甘いもの好きだよね?」
「いーの。美味しそうなこのお弁当に釣り合ってるって俺が思ったから受け取って。てか、甘いもの好きってよくわかったね」
「それは……」
(君を見てたらわかるよ。キャンディーを食べていたり、いちごミルクのパックを持っているのを見たことある──。なんて、そんな気持ち悪いこと言えないな)
「このクリームパン買ってたから甘いの好きなのかなって思っただけだよ」
「そっか。言われてみれば確かにそうかも。甘いの好きだからついつい買っちゃうんだよなぁ。そうだ、今度カフェついてきてよ」
「カフェ?」
「うん、スイーツ食べ放題のカフェ。それか前から気になっていた遊園地とコラボしているカフェ。クラスの女子に教えてもらったところなんだけど、1人じゃ入りづらいからさ。もちろん、着ぐるみが外せるようになったご褒美みたいな感じで」
琥珀くんとカフェに行けるなんて夢のような約束。その場に行くのが僕でいいのだろうか。
(琥珀くんがせっかくご褒美にって言ってくれたんだ。頑張って克服、できそうな気がしないけど頑張るしかないよね)
「じゃあ、ご褒美に行こう。僕頑張るね」
琥珀くんは満面の笑みを浮かべた。
◇
練習を始めるようになって早1ヵ月、僕はと言うと休み時間になるたびにおにぎりを教室で頬張り、急ぎ足で屋上へ向かうことが習慣と化していた。
どうして急いでいるのか、それは着ぐるみを着たままだとご飯を食べることができないからだ。
周りから見れば「早く外せばいいのに」「別に琥珀気にしてないはずだよ」とか言われると思うけど、僕からしたらとてつもなく決心のいることだった。
(琥珀くんが扉の向こうにいるってだけでドキドキして顔の周りが熱いのに、外せる人の度胸を分けてもらいたいくらいだ)
スゥーっと深呼吸を1つ。僕は扉を押して屋上に出た。
今日は曇り空で、太陽の光がどこにもない。
(何気に、太陽に照らされた琥珀くんの綺麗に反射する髪を見るの楽しみにしてたんだけどな。今日は見れないのか)
残念がっていると、どこからか声が聞こえた。あちこち歩き回っても誰もいない。そうなれば心当たりはあそこしかない。
僕は塔屋の出入口の反対側に回り、上に続くはしごを上る。
「琥珀くん、みっけ」
「わぁー、見つかっちゃったー。ふふ、なーんてね。気づいてたでしょ?」
「なんとなく。琥珀くん、僕より早く来るから姿見えないときはここかなって」
「だんだん俺のことわかってきてるね」
「っ……」
好きだから、見ているとクセや好きなものを勝手に発見していくから、完全に無自覚だった。
「まだ出会って間もないからそんなに多くないよ。逆に僕のこと何かわかってたりするの?」
「んー、どうしよっかなー」
(悩んでるってことは思うところがあるってことだよね?)
琥珀くんの表情はすごくニヤニヤしてる。話してほしいような、話してほしくないような複雑な感情が心の中でグルグルと巡る。
「やっぱ、内緒」
琥珀くんは口元に指を当ててシーっとポーズをとる。小悪魔的な表情に僕はまたキュンとさせられ、好きの気持ちが大きくなっていく。
「話変わるんだけど、練習って何か特別なことしないの? 僕といつもご飯食べて話してくらいだよね」
琥珀くんは僕が朝早くから作って持ってきているお弁当を美味しそうに頬張っている。リスのほっぺみたいに膨らんでいるそれを思わず触りたくなる。
「まずは俺と気軽に話せるようにならないと。そこから少しずつレベル上げていくから安心して」
僕はそう聞いて「緊張したり、赤くなったりするのは琥珀くんの前だけだから安心できないよ」と心の中でツッコみをしていた。
「……うん、次のステップに進めるといいなー」
本心だが、どうしてだか嘘っぽく聞こえてしまう。それに顔引きつってそう。見えてないけど。
(演劇部なのに演技ヘタクソでしょ……)
「はははっ」
琥珀くんはお腹を抱えながら、声を高くして笑った。
「ゆっきー、もう大丈夫そうだね」
(大丈夫そう? って何が?!)
「何がって顔してる。さっき言ってた次のステップに上がれそうって今感じた」
「どこを見て?」
「会話のテンポ? いやノリかな? ツッコミが入れられる時点で友達の感覚でいてくれてるのかなと思って」
琥珀くんにはそう捉えることができたのか。別に友達って思われるのが嫌ってわけではない。けど、僕がもう少し頑張れれば。
「へぇー、分からなかったや。僕も成長できてるってこと琥珀くんが気づいてくれて嬉しい」
僕の返事を聞いた琥珀くんは、花が咲くようにパァッと笑った。
「もうすぐチャイム鳴っちゃうね。琥珀くんは先に教室に戻りなよ」
「や、でも……」
「僕は着ぐるみを片付けたら戻るからさ」
ずるい手を使ってしまった。こう言えば、琥珀くんは引き下がってくれるとわかっていたから。
「……わかった。じゃあ、また明日」
「うん。また明日ね」
琥珀くんはお弁当箱を僕に返し、自分で持ってきたビニール袋を吊り下げて校舎の中に入っていった。
屋上から出て行ったのを確認して僕は、着ぐるみを頭から外した。
「あっつー」
曇り空とはいえ、最近は気温が高くなっていると天気予報で聞いた。この先、着ぐるみを被るのは少しリスキーになってくるだろう。
「何か対策を考えておいた方がいいかな
熱中症になるのだけは避けないとと対策を練り始めるが、いつまで被っていられるかなんてこの時まったくもって考えていなかった。
◇
6月に入り、雨の日が多くなった。世間では梅雨と言われている季節には入り、塔屋から屋上に出られなくなってしまった。
「雨だねぇ」
「俺、雨苦手なんだよね」
「意外かも。どうして?」
「笑わない?」
「うん。笑わない」
琥珀くんはモジモジと身体をくねらせながら、「髪の毛がクルってなって戻らなくなるんだよね」と恥ずかしそうに告白してくれた。
「……ふふっ」
「あー! 笑った! 笑わないって約束したのに!」
「ごめんごめん、ふふっ。理由が可愛いなって思って」
プクッと頬に空気を入れて不貞腐れて、話しかけても「知らない!」と言って軽く無視をしてくる。そんな姿も愛おしい。
「これあげるから許してくれる?」
僕の手には、琥珀くんがたまに糖分欲しさで買ってくることがある、いちごの棒キャンディーが2本ある。
たまたまコンビニで見つけて、渡そうと思って買っておいたもの。
「……」
チラッとこちらを見ては顔を元に戻して気にしていないそぶりを見せるが、雰囲気が柔らかくなってご機嫌になっている模様。
「はい、琥珀くん。笑ってごめんね」
「……仕方ないなー。許してあげるのは今回だけだよ?」
琥珀くんは棒キャンディーの包みを開けて口に頬張った。
「んー! 美味しいなぁ」
「それは良かった」
ニコニコと笑う琥珀くんがご機嫌状態のままある提案をしてきた。それは人慣れの練習を次の段階に進めるというもの。
どういうことをしていくのがいいのかと話し合い、結果少しづつ慣らしていくために手を繋いでみたり、見つめ合ったりしてみようという話になった。
「今日から早速やってみる?」
「心臓がすごい速さでドキドキしてる」
「どれどれー? あはっ、本当だ!」
琥珀くんは服越しに僕の心臓のある辺りに耳を当てて確かめてきた。
──ドクン、ドクン、ドクン、ドクン。
(琥珀くんが無防備なのも気になるけど、耳を離してほしいと思う自分と離さずずっと触れててほしい自分が葛藤してる……)
「……きー。ねぇ、ゆっきーてば」
「あ、え、何?」
悶々と頭の中で1人語りをしていれば、気がつくと触れられていた耳が離れてしまっていた。
「ぼーっとしてどうかした? 体調悪い?」
「大丈夫だよ、考えごとしてただけ」
「そう? じゃあ、無理しない程度で手を触るとこから始めようか?」
(琥珀くんと手を繋ぐって? さっきの服越しで触られているのでもヤバかったのに?)
レベルが1番低いと言っても過言ではないのに、更に下げてもらうなんてそんな情けないところは見せたくない。
(既にこうやってダサい姿見せてしまっているけど……)
「何考えてるのさ、ほら手を繋ぐよ」
「え、待っ……」
言葉の最後まで言う前に琥珀くんの手と僕の手は繋がれた。
なんて小さな手なんだろう。僕の手より1回り小さく、だけどか細く見えて意外にしなやかな強さが感じ取れる。さすが、空手をしている人の手だ。
(それに、温かい……)
繋がれている手を見つめていると、「そんなに手を見てどうしたのさ。それっ」と言って指を絡ませてきた。
そこで僕は、やっと『手を繋ぐ=恋人繋ぎ』の意味だったことに気がついた。予想もしていなかった繋ぎ方に内心大焦りをかます。
「琥珀くん、この繋ぎ方はちょっと……」
(恥ずかしいと申しますか、全然心の準備ができていないといいますか)
顔に熱が集まってきて着ぐるみでいるのが正直言って苦しくなってきた。
「別にいいでしょ。俺がこう繋ぎたいって思ったんだから異論は認めないよ」
「うっ、そう言われたら断れない」
「やった。じゃあ、しばらく繋いだままね」
琥珀くんが宣言した通り、時間の制限なく繋いだままだった。片手が塞がった状態で何ができるだろうか。ただ僕は煩悩を消し去ることだけに集中して休み時間終了まで過ごすことになった。
「これから雨が続くみたいだし、ここじゃなくて空き教室にしようか」
「空き教室は鍵が締まってるはずじゃ……」
「そこは任せてよ。空手部の先輩から良いところ教えてもらってるから。案内してあげるから明日の昼休み、3階の屋上前階段に集合ね」
その先輩はどうして琥珀くんに教えたのか気になるが、とりあえず、屋上へのドア前の暗いところに集まらなくていいのは助かるかも。だって琥珀くんの綺麗な髪が見れないのを少し寂しいと思っていたから。
──キーンコーンカーンコーン。
「予鈴鳴ったね、そろそろ行くよ」
「うん、今日もありがとう」
「全然気にしないで。また明日ね」
「うん、また明日」
先に教室へ戻ってもらうことが普通になってきて、琥珀くんの姿を見送った後は本鈴が鳴る間に着ぐるみを脱いで、食べれなかったごはんを食べたりする。
「早く教室戻らないと」
急いで階段を駆け降りていた俺は、足がもつれて身体が宙に舞う。
「え、うそ……」
(これは助からない……!)
最悪落ちても骨折、もしくは記憶喪失になることを願った。心の中では「死にたくない」と唱え続ける。
──ドサドサッ。
だが、落ちた先は硬いコンクリートではなくふわりと包容感のある何か。
「い……ったくない? あ、鷹也!」
「お前、なんで上から落ちてくるんだよ!」
「うーっ、鷹也! 助かったよ。危うく死んじゃうかと思った」
生きている喜びから下敷きにしてしまっている鷹也に再び抱きついた。でもすぐにはがされてしまった。
2人の身体に怪我がないか確認をしてから教室に帰るその道中で、「もうすぐ本鈴が鳴るのにどうしてそこにいたのか」と聞いてみた。だが鷹也は「あー、自販機に飲み物買いに行ってた」なんて、バレバレの嘘を俺についた。
(鷹也は気づいてないだろうけど、手にペットボトル持っていないし嘘つく時の目を泳がして右耳を触る癖が出ているな。ここは合わせておきつつ嘘ついてるって分かる指摘でもしようかな)
「そうなんだ。でもペットボトルないけど置いてきた?」
「え! っとー、欲しいの無かったから買わなかったんだよ」
「ふふっ、そっか」
「なんだよ、気持ち悪りぃな。ほら行くぞ」
僕たちは並んで教室に向かった。入ろうと扉に手を当てたと同時にチャイムが鳴り、先生に「はい、アウトー」遅刻判定されてしまった。
◇
次の日のお昼休み、俺は琥珀くんのところに行く前に演劇部の部室に向かった。
琥珀くんと特訓している間も、頼まれていた衣装直しをちょうど昨日全て終えたのだった。
「お疲れ様でーす。ひばり先輩衣装でき上がりました。あれ?」
いつもお昼は部室で過ごしていると部内で有名なひばり先輩の姿がなかった。今日は気分ではなかったのだろうか。
(直した衣装はどこにおいて置けばいいのか聞いておけばよかったな)
折りたたみ机の上に置いてあった付箋に『衣装の直し終わりました。どこに置いておけばいいのかわからなかったので、とりあえずココに置いておきます。如月雪兎』と書いて机に貼りつけた。
「んー、こらぁ。それはここにって言ったでしょ……むにゃ」
「え?」
書いたメモ虚しく、部屋の奥にあるソファから声がして恐る恐る近づくけばひばり先輩が寝ていた。
(ここにいたんだ。急に話し出すからびっくりした)
「ひばり先輩、すみません。少しお聞きしたいことが……」
ひばり先輩の肩を揺らして起こそうと試みるが、寝起きが悪いのか「んー」と言って動かなかった。
僕は諦めてメモに追加で『何かあれば連絡ください』と書いておいた。
琥珀くんに会うのだから着ぐるみを被らないといけない。
(絶対これを被って歩いてたら不審者として扱われそうだな。近くまで被らずに行くか)
返す用の箱に入れていた着ぐるみ。それだけを拝借して部室を出て行った。
「あ、琥珀くんお待たせ」
「ゆっきー遅いよ? 何してたの」
僕は演劇部に寄ってきたことを伝えれば、琥珀くんは許してくれた。そのあと、同じ3階フロアの普段人が通らない物置として使われている奥の教室に向かって歩いた。
「ここだよ。この2つ目の窓の鍵が壊れてるから、少しコツをつかめば……ほらっ」
ガキンと金属音を立てた窓はガラッと音を立てて開いた。少し埃っぽいけど、過ごしやすそうな場所だった。
(これくらいなら換気すればいいか)
「ゆっきーもおいで」
窓に足をかけてヒョイっと身軽に中に入った琥珀くん。振り返った彼は、僕に向けて手を差しのべてきて、その手を迷わず取った。
中は外から見た通り埃っぽく、窓を開けて換気をする。
雨が入ってくるかもと心配したが、幸いにも入ってくるような角度ではなかった。
窓の近くの壁に腰を下ろし、もたれかかって弁当を広げる。
(今日はお昼食べ損ねたから後で食べることになりそうだな)
「ねぇ、ゆっきーはさ今日お昼まだだよね」
「え、うん」
急に聞かれて僕は驚いた。どうしてお昼がまだだと気づいたのだろう。わからないように行動にも気をつけていたはずなのに。
「俺、後ろ向くから一緒に食べない? いつもゆっきーに1人で食べさせて申し訳ないなと思ってて、いつ言うかタイミング見計らってたんだ」
琥珀くんは申し訳なさそうな顔をして伝えてくれた。
(琥珀くんがこんなことを考えてくれてたなんて知らなかった。ずっと寂しい思いをさせてたのかな)
「無理強いしているわけじゃないから、断ってくれても……」
「無理じゃないよ。僕も一緒に食べれたらと思ってたからそう言ってもらえて嬉しい。ありがとう」
「……! うん、早く食べよ!」
琥珀くんは身体いっぱいで嬉しそうにしている。僕も一緒したいのは本心だし、そう答えることができて僕も嬉しくなった。
「ゆっきー今日は何食べるの? お弁当?」
「そうだね。持ってきてはいるから弁当かな」
「ゆっきーがこの間くれたお弁当の卵焼き美味しかったの覚えてる! お弁当はお母さんが作ってるの?」
「いや、基本僕が作ってるかな」
「え! うそ、すごすぎ! ゆっきーは本当に何でもできるね」
いつも美味しいと言って食べてくれる琥珀くんに、僕が自分で作っていることを明かす日が来るとは思ってもみなかった。
琥珀くんは言っていたみたいに背中を向けて見ないようにしてくれた。僕は甘えて着ぐるみを脱いでご飯を食べた。
(ありのままの姿で並んで食べれるなんて、これは夢かな)
「俺ね最近、ごはんを食べるのが楽しいって思えるようになって来たんだよね」
「そうだったんだ。それはどうしてか聞いてもいい?」
琥珀くんがコクンと頷く気配がして、話してくれた。
「クラスのみんなが、誰かと一緒に楽しく食べる様子を見て憧れてたんだ」
(意外だ。仲のいい女子たちと一緒に食べているイメージだったのに)
「ゆっきーと話すようになって、一緒にお昼食べるようになって。そこから人生が変わったみたいに楽しい。ずっと言いたかったんだ、ありがとう」
お礼を言うのはこちらだ。つき合ってもらっているのに一向に顔を見て話すことができない。
僕も早く琥珀くんと対面でご飯を食べられるように頑張らないと、と不甲斐なさを感じつつもその言葉は素直に受け取ることにした。
◇
梅雨が明けて、夏本番に向かってさらに気温が高くなってきていた。
じめっとした空気よりカラッとした方が過ごしやすいが、今年の気温は高いうえに湿度も高めとのことなので厳重注意とテレビで流れるニュースで言っていた。
それに伴い、着ぐるみで過ごすことも危ないと宣言されているようだった。
「ねぇ、鷹也。着ぐるみで過ごすの難しい時期になってきたね」
「急になんだよ。てか、まだ続いてたんだ、霜月との特訓」
事情を知っている鷹也に説明なくこの話ができるのは、なにかと助かっている。
「そろそろ良いんじゃないの? 結果変わってないんだし、正直に言ってしまった方が熱中症で死ななくて済むぞ」
「それはそうなんだけどねー」
言われていることは確かだが、『気持ち悪い』なんて言われればそれこそ死んでしまう。
「……鷹也は彼女と上手くいってるの?」
「まぁーな、早くお前もつき合え」
「そうできてたら長く片想いなんてしてないよ」
最近できた彼女とチャットでやり取りしている鷹也にそう伝えた。
4限目の始まるチャイムが鳴り、先生が入ってくる。挨拶を済ませれば、黒板にチョークの当たる音が聞こえ始める。
(これが終われば琥珀くんとお昼。昨日は僕が食べちゃったからお弁当作ってみたんだよね。喜んでくれるかな)
「……らぎ。如月」
「は、はい」
「どうかしたか? 体調が悪いとか」
「いえ、考えごとをしていただけです」
「そうか、なら問3の答えを書きに来なさい」
先生に当てられていたことが分からなくなるほど、頭が琥珀くん一色に染まっている。それでもなんの支障もなく問題は解けた。
「正解だ。さすがだな」
「ありがとうございます」
僕はそそくさと自分の席に戻った。時計を見ながら近づく休憩時間に内心そわそわし始めている。
そして待っていた休憩時間に入る授業終了のチャイムが鳴った。先生が教室から出て行ったのを合図に、クラスメイトもざわざわとし始めた。
かく言う僕も、5限目の準備をしてから机の横にかけてあったトートバックを持って「じゃあ、行ってくるね」と鷹也に伝えて教室を出た。
屋上前に隠してある着ぐるみを取りに行ってから、空き教室に向かった。あの部屋は思っていたよりも勝手がよく、過ごしやすかった。驚いたのは冷房や暖房が使えることだった。
階段を降り、角を曲がればすぐそこに教室がある。着ぐるみを被ると籠った空気が熱になり襲いかかってくる。
「夏に着ぐるみはやっぱり暑いな」
教室の窓を触って中に入る。まだ琥珀くんは来ていなかった。
(暑いから少しの間だけ)
着ぐるみを脱ぎ、窓を開けて風に当たった。今日の空はカラッと晴れていて、外にいたらどれだけ心地が良いのだろうと想像してしまう。
「はぁー、涼しい。生き返る」
リラックスしていると外窓下の方で男女の話し声が聞こえ、相手に気づかれにようにこっそり聞き耳を立てた。
「いいじゃないですか! 手合わせしてください」
「嫌だよ。他のやつに頼みなって」
「そう言われると思って、他の部員たちとは既に手合わせ済ませて勝ってきてます!」
「……なんで俺なの」
「ずっとつまらないと思って続けていた空手。中学の大会でセンパイを見て憧れを抱き、それでいつか勝負したいという夢もできました。だからお願いします! 琥珀センパイ!」
手合わせという単語でなんとなくスポーツ系の部活の先輩後輩の言い合いだと察した。だが、後輩であろう彼女は「琥珀センパイ」と口にしていた。
窓から覗き込むと確かに琥珀くんだった。
「そう言われても俺は……」
琥珀くんは言葉を止めて不意にこちらを向いた。僕は反対に逃げるようにして身を隠した。
(バレちゃった? でも一瞬目が合っただけだし。気のせいって思ってくれたら……)
「相手の子、可愛かったな……」
一瞬だけ見えた話し相手の姿を思い出す。親しい後輩といえば空手部の子だろうか。
ショートボブが似合っていて琥珀くんと並んでも目劣りしない可愛らしい子。
琥珀くんがつき合うとしたらああいう子なのかと考えたら、胸が痛い。
殻に閉じこもるように足を抱えて縮こまった。
──ガタン。
「ゆっきー、入るよ」
「あ、うん」
気持ちを半分切り替えて着ぐるみを被った。気分がズンと落ちている今、声のトーンが低くなり分かりやすくなってしまっている。
(切り替えよう。琥珀くんとの時間は楽しいものにしたいから)
「お待たせゆっきー」
「全然大丈夫だよ。早くご飯食べよう?」
僕はさっき見た光景をあえて話題にしなかった。だけどそういう時に限って琥珀くんは話題にする。
「そういえばさっきこの教室の真下にいたんだけど、知らない生徒がいた気がしたんだけど見てない?」
琥珀くんが、『黒髪で宝石のように綺麗な赤い瞳』と言っているのを聞いて「それは僕ですね」と心の中で呟いた。
正体を明かせるわけもなく「見てないかも」と言ってはぐらかした。
「どうしてその人のこと聞きたいの?」
「ん? だってカッコよかったから」
予想と違った琥珀くんの告白に咽てしまった。後ろを向いてお茶で喉を潤し落ち着いてみるが、思い出しで顔が赤くなるくらいドキドキしている。
「また会えたらいいなぁ」
(ここにいるよ。なんて言うことができたなら)
僕は琥珀くんにカッコいいと言われた姿を見せることを目標として心に刻み、特訓もいつも以上に頑張ることを誓った。
ご飯を食べてからは、着ぐるみ越しで20秒見つめ合う特訓をした。だけどいつも赤くなったり、ギブアップしてしまったりと迷惑をかけまくっている。
「今日は17秒までいけたね。少しづつ伸びてきてるからもう少しで治ったりして」
「そうだといいな」
「ゆっきーは今日の放課後すぐ帰る?」
琥珀くんから放課後の話をされたのは初めてだった。いや、昼休みに会うようになってからは初めてと言うほうが正しいだろう。
「今日は特に用事ないかな」
「そうなんだ! よかったらさ……」
──プルルル、プルルル。
電話の鳴る音が教室中に響いた。僕のポケットに入っていたスマホが震えているのではなく琥珀くんのスマホが鳴っていたらしい。
画面を見た琥珀くんは盛大にため息を吐いた。
「ごめん、ゆっきー」
「うん、いいよ」
琥珀くんは電話を取った。僕と話す時みたいな明るい声ではなく、先ほど見たあの子と会話していた時みたいな、心を許している人に出す低い声で話しだした。
「もしも……」
『あ! やっと出ましたね』
「急に電話してきて何? 雛(ひな)」
電話から漏れる声でなんとなく相手がわかった。多分、さっき話していたであろう後輩。
連絡先を交換するような仲なんだろうと少しだけ、ほんの少しだけ嫉妬してしまう。
『今日の放課後にセッティングしたんで絶対来てくださいね!』
ブチっと音を立てて切れた電話に、珍しく琥珀くんも静かにキレていた。どうしてわかったのか、それは琥珀くんの纏う雰囲気が冷たいものに変わったからだ。
「何かあったの?」
「あ、後輩がね俺と勝負したいって言ってきて。断ってるんだけどね、無理やり今日の放課後に試合するって」
「大変だね。頑張って!」
「えー、行きたくないよー」
僕は尊敬されている琥珀くんを応援したい。でも琥珀くんは乗り気ではないみたいで、ぐでーっと溶けるような体勢になって面倒くさがっている。
「でも、相手の子後輩でしょ? 期待に応えてあげないと」
「うえー……。そういや、ゆっきー放課後用事ないってさっき言ってたよね?」
「え、うん。言ったね」
「応援に来て欲しいんだけどダメかな?」
琥珀くんは身体を起き上がられせて口元で手を合わせるポーズをとった。
「え、僕が?!」
「ゆっきーが来てくれたら勝てそうな気がする」
琥珀くんには可愛いくてカッコいい姿であってほしい。
「そういうことなら……わかった。応援に行くから絶対に勝ってね!」
僕は応援に行くと琥珀くんに約束した。
予鈴のチャイムが鳴り、いつも通り順番に教室を出ていく。帰る際に琥珀くんから「待ってるね」と釘を刺されたよな気がした。
だけど1つ問題が発生していることにこの時気がついた。
「僕はどうやって応援に行けばいいんだ?」
ウサギの着ぐるみだと不審者に思われそう。だけどそのままの姿で行ったら琥珀くんがわからないような。
「後ろの方から見ておくしかないか」
僕は悩みに悩んだ結果、素顔の状態で応援しに行ってみることにした。琥珀くんからしたら僕が来ていることわからないと思うけどそこは仕方ない。後日弁明でも図ろう。
それに、ちょっとだけ『気づいてくれないかな』と期待感がある。まぁ素顔で会ったことないから無理だろうけど。
◇
放課後になり、部活が休みの鷹也も連れて空手部の道場を訪れた。
琥珀くんが手合わせすることが、休み時間から放課後の短い時間に広まったようで、出入り口には男女問わずたくさんの生徒が集まっていた。
「琥珀くんが絶対勝つわよ」
「うちらの琥珀くんだしねー」
以前琥珀くんと一緒にいた同じクラスの女子も応援に来ていた。
「ねぇ、あの人!!」
「わぁ、雪兎くんだ。道場に来るなんてどうしたんだろう? ……もしかして、空手部に彼女が!?」
「えー!? 嘘よ!」
「やめてー! 雪兎くんはみんなのものなんだから!」
あちらこちらから女子のコソコソ話す声が聞こえてくる。
「ねぇ鷹也」
「なんだ?」
「みんなこっち見て何か言っている気がするんだけど、気のせいかな?」
「……気のせいだろ」
(その間は何なんだ。絶対気のせいじゃないじゃん)
女子の多い空間でコソコソと言われるとすれば、悪口しか思いつかなかった。
僕は勝手に身の狭い思いをしていたが、本当は僕がここに来ていることに驚かれていたなんて知る由もない。
「これより、霜月琥珀VS弥生(やよい)雛(ひな)の一本勝負を始めます。こちらは特別ルールとして、1回でも技が決まれば勝負終了とします」
審判である生徒の1人が声を出すと、女子の視線が僕たちから道場の中の方へ向いた。
(助かった。琥珀くんは……いた!)
「鷹也いたよ。琥珀くんいた」
「わかったから離せ」
見つけた喜びで思わず鷹也の袖を掴んでいた。
琥珀くんは普段見ることのない道着姿でとてもカッコいい。相手の弥生さん? も長年空手をやってきたことが分かるくらい堂々としている。
「逃げないで来てくださって光栄です、琥珀センパイ」
「本当は逃げようと思ったんだけどね、好きな人に見に来てって言ったから少しでもカッコいいところ見せないと」
「……! センパイ、好きな人って」
「ほら始まるよ」
集団の1番後ろ辺り、扉のそばにいた僕たち2人、幸いにも琥珀くんが見える。だが道場内の声はここまで届かず、中にいる2人が何を話しているのかは不明だった。
だから、こちらを向いた琥珀くんの鋭く獲物を狙ったような目とかち合い、ドキッとさせられる。
「後で教えてくださいね!」
元気いっぱいの弥生さんの声が道場中、いや外にまで聞こえてきて訳の分からない僕らにとったら「何かを賭けてるのかな」とくらいしか思っていなかった。
「よーい、始め」
審判から試合開始の合図を出されると2人は組手の状態になり、動き始めた。お互いタイミングを見て拳で突いたり、横から蹴りを飛ばしたりと接戦だった。
少し押され気味の琥珀くん。僕は無意識に「琥珀くん頑張ってー!」と叫んでいた。周りは僕に視線を向けてきて、大声を出していたことを自覚するととても恥ずかしい気持ちになった。
「ふっ、ゆっきー声でかっ」
琥珀くんの口元が微かに動いた。僕の位置からでは何を言っているのか分からなかったけど、なぜか嬉しそうに笑みを浮かべている。
そして決着がついた。空手のこと詳しくないからすごいとしか言いようがない。
琥珀くんが弥生さんから飛んできた拳を避けて、伸ばされたままの道着の袖を引っ張って相手の背を床につける一本背負いをする。
空手に詳しくない僕はただ『すごい』や『カッコいい』の感想しか出てこなかった。
「勝者、霜月琥珀」
「ありがとうございました」
「ありがとうございました。うぅー、悔しい! 私途中まで勝てるかと思ってました。センパイまた強くなりましたね」
「俺なんてまだまだ。今日は元気がみなぎっていただけ」
「あ、そういえば試合始まる前の好きな人って一体誰のことを言ってたんですか?」
「知りたいなら自分で探してみるか、俺に勝って聞いてみな」
楽しそうに話す琥珀くんは僕の前ではしないような表情ばかりで、寂しい? 感情があった。
「終わったみたいだな。帰るか」
「あ、待って鷹也。もう1つお願いが」
ギャラリーが帰っていき、いつの間にか道場近くにいるのは僕と鷹也だけになっていた。
「じゃあ、行ってくるな」
「うん、よろしく」
鷹也にお願いしたことは、僕の代わりに差し入れを持って行ってもらうことだった。飲み物や部内で休憩の時に食べれるようなものを用意してみた。
僕は道場から見えないところで1人、鷹也が戻ってくるのを待っていた。
「鷹也、ちゃんと渡してくれてるかな」
「雪兎」
道場から小走りで鷹也は帰ってきた。手に何も持っていないところを見ると受け取ってくれたみたいで安心した。
「ちゃんとお前だって言って渡してきた」
「ありがとう」
「……もう話してもいいような気がするけどな」
「何が?」
鷹也を見ると『なんで気がつかねぇの』と言いたそうな引いた顔をしていた。僕には何を言いたいのか、どうしてそんな顔をしているのかわからなかった。
「なんでもねーよ」
「え、待ってよ!」
鷹也は足早で校舎に入っていった後ろを、僕もついていった。
それもそのはず。あの日、琥珀くんと約束した『赤面にならない練習』を今日から開始するからだ。
前は部活時間と被っている放課後に会っていたけど、時間が短いから練習はお昼休みにすると言われていた。
「大丈夫、練習するだけ。何もない。よし!」
僕はドア横に隠していたウサギの着ぐるみを被って、相変わらずきしんだ音を立てながらドアを開ける。
(まだ来てない、かな?)
恐る恐る屋上に足を踏み入れると、頭上から「あー、来たー」と可愛らしい声が聞こえ天を仰いだ。
塔屋(とうや)に目をむけると、太陽に照らされて綺麗に反射しているクリーム色の髪がなびき僕の視線を奪う。
(いつ見ても綺麗なクリーム色……。階段で会った時と変わってない)
「ずーっと待ってたんだよ?」
「ごめん、先生に質問してたら遅くなっちゃった。お昼は食べた?」
「ううん、一緒に食べようと思って待ってたんだぁ」
「あ、そうだったんだ。待たせてごめんね、食べようか」
持ってきていたお弁当を片手に塔屋にもたれかかる。上から降りてきた琥珀くんは当たり前のように僕の隣に座る。
ちょこんと座る姿がなんとも小動物みたいで可愛らしい。
琥珀くんがビニール袋から出したのは、多分購買で買ったであろう焼きそばパンとコロッケサンドパン。そして購買で一番人気と言っていいほど有名な、いちごをふんだんに使った数量限定のクリームパンを広げてどれから食べるか悩んでいた。
(僕もお弁当食べ……いや、着ぐるみしてたら食べられないじゃん! 外す手もあるけどそうしたらもっと赤くなって今まで隠してきた意味がなくなっちゃう……。明日からお昼ご飯をどうするか考えないとな)
「焼きそばパンから食べようっと。あれ、ゆっきーは食べないの? 美味しそうなお弁当なのに」
「あー、今日はそんなにお腹空いてなくて。よかったら食べる?」
「え、いいの?」
「もちろん、食べてくれたら食材が無駄にならなくて済むし助かるよ」
「じゃあ、遠慮なく。それじゃあ、俺からお返しにクリームパンあげるね」
「それこそいいの? 数量限定だし、甘いもの好きだよね?」
「いーの。美味しそうなこのお弁当に釣り合ってるって俺が思ったから受け取って。てか、甘いもの好きってよくわかったね」
「それは……」
(君を見てたらわかるよ。キャンディーを食べていたり、いちごミルクのパックを持っているのを見たことある──。なんて、そんな気持ち悪いこと言えないな)
「このクリームパン買ってたから甘いの好きなのかなって思っただけだよ」
「そっか。言われてみれば確かにそうかも。甘いの好きだからついつい買っちゃうんだよなぁ。そうだ、今度カフェついてきてよ」
「カフェ?」
「うん、スイーツ食べ放題のカフェ。それか前から気になっていた遊園地とコラボしているカフェ。クラスの女子に教えてもらったところなんだけど、1人じゃ入りづらいからさ。もちろん、着ぐるみが外せるようになったご褒美みたいな感じで」
琥珀くんとカフェに行けるなんて夢のような約束。その場に行くのが僕でいいのだろうか。
(琥珀くんがせっかくご褒美にって言ってくれたんだ。頑張って克服、できそうな気がしないけど頑張るしかないよね)
「じゃあ、ご褒美に行こう。僕頑張るね」
琥珀くんは満面の笑みを浮かべた。
◇
練習を始めるようになって早1ヵ月、僕はと言うと休み時間になるたびにおにぎりを教室で頬張り、急ぎ足で屋上へ向かうことが習慣と化していた。
どうして急いでいるのか、それは着ぐるみを着たままだとご飯を食べることができないからだ。
周りから見れば「早く外せばいいのに」「別に琥珀気にしてないはずだよ」とか言われると思うけど、僕からしたらとてつもなく決心のいることだった。
(琥珀くんが扉の向こうにいるってだけでドキドキして顔の周りが熱いのに、外せる人の度胸を分けてもらいたいくらいだ)
スゥーっと深呼吸を1つ。僕は扉を押して屋上に出た。
今日は曇り空で、太陽の光がどこにもない。
(何気に、太陽に照らされた琥珀くんの綺麗に反射する髪を見るの楽しみにしてたんだけどな。今日は見れないのか)
残念がっていると、どこからか声が聞こえた。あちこち歩き回っても誰もいない。そうなれば心当たりはあそこしかない。
僕は塔屋の出入口の反対側に回り、上に続くはしごを上る。
「琥珀くん、みっけ」
「わぁー、見つかっちゃったー。ふふ、なーんてね。気づいてたでしょ?」
「なんとなく。琥珀くん、僕より早く来るから姿見えないときはここかなって」
「だんだん俺のことわかってきてるね」
「っ……」
好きだから、見ているとクセや好きなものを勝手に発見していくから、完全に無自覚だった。
「まだ出会って間もないからそんなに多くないよ。逆に僕のこと何かわかってたりするの?」
「んー、どうしよっかなー」
(悩んでるってことは思うところがあるってことだよね?)
琥珀くんの表情はすごくニヤニヤしてる。話してほしいような、話してほしくないような複雑な感情が心の中でグルグルと巡る。
「やっぱ、内緒」
琥珀くんは口元に指を当ててシーっとポーズをとる。小悪魔的な表情に僕はまたキュンとさせられ、好きの気持ちが大きくなっていく。
「話変わるんだけど、練習って何か特別なことしないの? 僕といつもご飯食べて話してくらいだよね」
琥珀くんは僕が朝早くから作って持ってきているお弁当を美味しそうに頬張っている。リスのほっぺみたいに膨らんでいるそれを思わず触りたくなる。
「まずは俺と気軽に話せるようにならないと。そこから少しずつレベル上げていくから安心して」
僕はそう聞いて「緊張したり、赤くなったりするのは琥珀くんの前だけだから安心できないよ」と心の中でツッコみをしていた。
「……うん、次のステップに進めるといいなー」
本心だが、どうしてだか嘘っぽく聞こえてしまう。それに顔引きつってそう。見えてないけど。
(演劇部なのに演技ヘタクソでしょ……)
「はははっ」
琥珀くんはお腹を抱えながら、声を高くして笑った。
「ゆっきー、もう大丈夫そうだね」
(大丈夫そう? って何が?!)
「何がって顔してる。さっき言ってた次のステップに上がれそうって今感じた」
「どこを見て?」
「会話のテンポ? いやノリかな? ツッコミが入れられる時点で友達の感覚でいてくれてるのかなと思って」
琥珀くんにはそう捉えることができたのか。別に友達って思われるのが嫌ってわけではない。けど、僕がもう少し頑張れれば。
「へぇー、分からなかったや。僕も成長できてるってこと琥珀くんが気づいてくれて嬉しい」
僕の返事を聞いた琥珀くんは、花が咲くようにパァッと笑った。
「もうすぐチャイム鳴っちゃうね。琥珀くんは先に教室に戻りなよ」
「や、でも……」
「僕は着ぐるみを片付けたら戻るからさ」
ずるい手を使ってしまった。こう言えば、琥珀くんは引き下がってくれるとわかっていたから。
「……わかった。じゃあ、また明日」
「うん。また明日ね」
琥珀くんはお弁当箱を僕に返し、自分で持ってきたビニール袋を吊り下げて校舎の中に入っていった。
屋上から出て行ったのを確認して僕は、着ぐるみを頭から外した。
「あっつー」
曇り空とはいえ、最近は気温が高くなっていると天気予報で聞いた。この先、着ぐるみを被るのは少しリスキーになってくるだろう。
「何か対策を考えておいた方がいいかな
熱中症になるのだけは避けないとと対策を練り始めるが、いつまで被っていられるかなんてこの時まったくもって考えていなかった。
◇
6月に入り、雨の日が多くなった。世間では梅雨と言われている季節には入り、塔屋から屋上に出られなくなってしまった。
「雨だねぇ」
「俺、雨苦手なんだよね」
「意外かも。どうして?」
「笑わない?」
「うん。笑わない」
琥珀くんはモジモジと身体をくねらせながら、「髪の毛がクルってなって戻らなくなるんだよね」と恥ずかしそうに告白してくれた。
「……ふふっ」
「あー! 笑った! 笑わないって約束したのに!」
「ごめんごめん、ふふっ。理由が可愛いなって思って」
プクッと頬に空気を入れて不貞腐れて、話しかけても「知らない!」と言って軽く無視をしてくる。そんな姿も愛おしい。
「これあげるから許してくれる?」
僕の手には、琥珀くんがたまに糖分欲しさで買ってくることがある、いちごの棒キャンディーが2本ある。
たまたまコンビニで見つけて、渡そうと思って買っておいたもの。
「……」
チラッとこちらを見ては顔を元に戻して気にしていないそぶりを見せるが、雰囲気が柔らかくなってご機嫌になっている模様。
「はい、琥珀くん。笑ってごめんね」
「……仕方ないなー。許してあげるのは今回だけだよ?」
琥珀くんは棒キャンディーの包みを開けて口に頬張った。
「んー! 美味しいなぁ」
「それは良かった」
ニコニコと笑う琥珀くんがご機嫌状態のままある提案をしてきた。それは人慣れの練習を次の段階に進めるというもの。
どういうことをしていくのがいいのかと話し合い、結果少しづつ慣らしていくために手を繋いでみたり、見つめ合ったりしてみようという話になった。
「今日から早速やってみる?」
「心臓がすごい速さでドキドキしてる」
「どれどれー? あはっ、本当だ!」
琥珀くんは服越しに僕の心臓のある辺りに耳を当てて確かめてきた。
──ドクン、ドクン、ドクン、ドクン。
(琥珀くんが無防備なのも気になるけど、耳を離してほしいと思う自分と離さずずっと触れててほしい自分が葛藤してる……)
「……きー。ねぇ、ゆっきーてば」
「あ、え、何?」
悶々と頭の中で1人語りをしていれば、気がつくと触れられていた耳が離れてしまっていた。
「ぼーっとしてどうかした? 体調悪い?」
「大丈夫だよ、考えごとしてただけ」
「そう? じゃあ、無理しない程度で手を触るとこから始めようか?」
(琥珀くんと手を繋ぐって? さっきの服越しで触られているのでもヤバかったのに?)
レベルが1番低いと言っても過言ではないのに、更に下げてもらうなんてそんな情けないところは見せたくない。
(既にこうやってダサい姿見せてしまっているけど……)
「何考えてるのさ、ほら手を繋ぐよ」
「え、待っ……」
言葉の最後まで言う前に琥珀くんの手と僕の手は繋がれた。
なんて小さな手なんだろう。僕の手より1回り小さく、だけどか細く見えて意外にしなやかな強さが感じ取れる。さすが、空手をしている人の手だ。
(それに、温かい……)
繋がれている手を見つめていると、「そんなに手を見てどうしたのさ。それっ」と言って指を絡ませてきた。
そこで僕は、やっと『手を繋ぐ=恋人繋ぎ』の意味だったことに気がついた。予想もしていなかった繋ぎ方に内心大焦りをかます。
「琥珀くん、この繋ぎ方はちょっと……」
(恥ずかしいと申しますか、全然心の準備ができていないといいますか)
顔に熱が集まってきて着ぐるみでいるのが正直言って苦しくなってきた。
「別にいいでしょ。俺がこう繋ぎたいって思ったんだから異論は認めないよ」
「うっ、そう言われたら断れない」
「やった。じゃあ、しばらく繋いだままね」
琥珀くんが宣言した通り、時間の制限なく繋いだままだった。片手が塞がった状態で何ができるだろうか。ただ僕は煩悩を消し去ることだけに集中して休み時間終了まで過ごすことになった。
「これから雨が続くみたいだし、ここじゃなくて空き教室にしようか」
「空き教室は鍵が締まってるはずじゃ……」
「そこは任せてよ。空手部の先輩から良いところ教えてもらってるから。案内してあげるから明日の昼休み、3階の屋上前階段に集合ね」
その先輩はどうして琥珀くんに教えたのか気になるが、とりあえず、屋上へのドア前の暗いところに集まらなくていいのは助かるかも。だって琥珀くんの綺麗な髪が見れないのを少し寂しいと思っていたから。
──キーンコーンカーンコーン。
「予鈴鳴ったね、そろそろ行くよ」
「うん、今日もありがとう」
「全然気にしないで。また明日ね」
「うん、また明日」
先に教室へ戻ってもらうことが普通になってきて、琥珀くんの姿を見送った後は本鈴が鳴る間に着ぐるみを脱いで、食べれなかったごはんを食べたりする。
「早く教室戻らないと」
急いで階段を駆け降りていた俺は、足がもつれて身体が宙に舞う。
「え、うそ……」
(これは助からない……!)
最悪落ちても骨折、もしくは記憶喪失になることを願った。心の中では「死にたくない」と唱え続ける。
──ドサドサッ。
だが、落ちた先は硬いコンクリートではなくふわりと包容感のある何か。
「い……ったくない? あ、鷹也!」
「お前、なんで上から落ちてくるんだよ!」
「うーっ、鷹也! 助かったよ。危うく死んじゃうかと思った」
生きている喜びから下敷きにしてしまっている鷹也に再び抱きついた。でもすぐにはがされてしまった。
2人の身体に怪我がないか確認をしてから教室に帰るその道中で、「もうすぐ本鈴が鳴るのにどうしてそこにいたのか」と聞いてみた。だが鷹也は「あー、自販機に飲み物買いに行ってた」なんて、バレバレの嘘を俺についた。
(鷹也は気づいてないだろうけど、手にペットボトル持っていないし嘘つく時の目を泳がして右耳を触る癖が出ているな。ここは合わせておきつつ嘘ついてるって分かる指摘でもしようかな)
「そうなんだ。でもペットボトルないけど置いてきた?」
「え! っとー、欲しいの無かったから買わなかったんだよ」
「ふふっ、そっか」
「なんだよ、気持ち悪りぃな。ほら行くぞ」
僕たちは並んで教室に向かった。入ろうと扉に手を当てたと同時にチャイムが鳴り、先生に「はい、アウトー」遅刻判定されてしまった。
◇
次の日のお昼休み、俺は琥珀くんのところに行く前に演劇部の部室に向かった。
琥珀くんと特訓している間も、頼まれていた衣装直しをちょうど昨日全て終えたのだった。
「お疲れ様でーす。ひばり先輩衣装でき上がりました。あれ?」
いつもお昼は部室で過ごしていると部内で有名なひばり先輩の姿がなかった。今日は気分ではなかったのだろうか。
(直した衣装はどこにおいて置けばいいのか聞いておけばよかったな)
折りたたみ机の上に置いてあった付箋に『衣装の直し終わりました。どこに置いておけばいいのかわからなかったので、とりあえずココに置いておきます。如月雪兎』と書いて机に貼りつけた。
「んー、こらぁ。それはここにって言ったでしょ……むにゃ」
「え?」
書いたメモ虚しく、部屋の奥にあるソファから声がして恐る恐る近づくけばひばり先輩が寝ていた。
(ここにいたんだ。急に話し出すからびっくりした)
「ひばり先輩、すみません。少しお聞きしたいことが……」
ひばり先輩の肩を揺らして起こそうと試みるが、寝起きが悪いのか「んー」と言って動かなかった。
僕は諦めてメモに追加で『何かあれば連絡ください』と書いておいた。
琥珀くんに会うのだから着ぐるみを被らないといけない。
(絶対これを被って歩いてたら不審者として扱われそうだな。近くまで被らずに行くか)
返す用の箱に入れていた着ぐるみ。それだけを拝借して部室を出て行った。
「あ、琥珀くんお待たせ」
「ゆっきー遅いよ? 何してたの」
僕は演劇部に寄ってきたことを伝えれば、琥珀くんは許してくれた。そのあと、同じ3階フロアの普段人が通らない物置として使われている奥の教室に向かって歩いた。
「ここだよ。この2つ目の窓の鍵が壊れてるから、少しコツをつかめば……ほらっ」
ガキンと金属音を立てた窓はガラッと音を立てて開いた。少し埃っぽいけど、過ごしやすそうな場所だった。
(これくらいなら換気すればいいか)
「ゆっきーもおいで」
窓に足をかけてヒョイっと身軽に中に入った琥珀くん。振り返った彼は、僕に向けて手を差しのべてきて、その手を迷わず取った。
中は外から見た通り埃っぽく、窓を開けて換気をする。
雨が入ってくるかもと心配したが、幸いにも入ってくるような角度ではなかった。
窓の近くの壁に腰を下ろし、もたれかかって弁当を広げる。
(今日はお昼食べ損ねたから後で食べることになりそうだな)
「ねぇ、ゆっきーはさ今日お昼まだだよね」
「え、うん」
急に聞かれて僕は驚いた。どうしてお昼がまだだと気づいたのだろう。わからないように行動にも気をつけていたはずなのに。
「俺、後ろ向くから一緒に食べない? いつもゆっきーに1人で食べさせて申し訳ないなと思ってて、いつ言うかタイミング見計らってたんだ」
琥珀くんは申し訳なさそうな顔をして伝えてくれた。
(琥珀くんがこんなことを考えてくれてたなんて知らなかった。ずっと寂しい思いをさせてたのかな)
「無理強いしているわけじゃないから、断ってくれても……」
「無理じゃないよ。僕も一緒に食べれたらと思ってたからそう言ってもらえて嬉しい。ありがとう」
「……! うん、早く食べよ!」
琥珀くんは身体いっぱいで嬉しそうにしている。僕も一緒したいのは本心だし、そう答えることができて僕も嬉しくなった。
「ゆっきー今日は何食べるの? お弁当?」
「そうだね。持ってきてはいるから弁当かな」
「ゆっきーがこの間くれたお弁当の卵焼き美味しかったの覚えてる! お弁当はお母さんが作ってるの?」
「いや、基本僕が作ってるかな」
「え! うそ、すごすぎ! ゆっきーは本当に何でもできるね」
いつも美味しいと言って食べてくれる琥珀くんに、僕が自分で作っていることを明かす日が来るとは思ってもみなかった。
琥珀くんは言っていたみたいに背中を向けて見ないようにしてくれた。僕は甘えて着ぐるみを脱いでご飯を食べた。
(ありのままの姿で並んで食べれるなんて、これは夢かな)
「俺ね最近、ごはんを食べるのが楽しいって思えるようになって来たんだよね」
「そうだったんだ。それはどうしてか聞いてもいい?」
琥珀くんがコクンと頷く気配がして、話してくれた。
「クラスのみんなが、誰かと一緒に楽しく食べる様子を見て憧れてたんだ」
(意外だ。仲のいい女子たちと一緒に食べているイメージだったのに)
「ゆっきーと話すようになって、一緒にお昼食べるようになって。そこから人生が変わったみたいに楽しい。ずっと言いたかったんだ、ありがとう」
お礼を言うのはこちらだ。つき合ってもらっているのに一向に顔を見て話すことができない。
僕も早く琥珀くんと対面でご飯を食べられるように頑張らないと、と不甲斐なさを感じつつもその言葉は素直に受け取ることにした。
◇
梅雨が明けて、夏本番に向かってさらに気温が高くなってきていた。
じめっとした空気よりカラッとした方が過ごしやすいが、今年の気温は高いうえに湿度も高めとのことなので厳重注意とテレビで流れるニュースで言っていた。
それに伴い、着ぐるみで過ごすことも危ないと宣言されているようだった。
「ねぇ、鷹也。着ぐるみで過ごすの難しい時期になってきたね」
「急になんだよ。てか、まだ続いてたんだ、霜月との特訓」
事情を知っている鷹也に説明なくこの話ができるのは、なにかと助かっている。
「そろそろ良いんじゃないの? 結果変わってないんだし、正直に言ってしまった方が熱中症で死ななくて済むぞ」
「それはそうなんだけどねー」
言われていることは確かだが、『気持ち悪い』なんて言われればそれこそ死んでしまう。
「……鷹也は彼女と上手くいってるの?」
「まぁーな、早くお前もつき合え」
「そうできてたら長く片想いなんてしてないよ」
最近できた彼女とチャットでやり取りしている鷹也にそう伝えた。
4限目の始まるチャイムが鳴り、先生が入ってくる。挨拶を済ませれば、黒板にチョークの当たる音が聞こえ始める。
(これが終われば琥珀くんとお昼。昨日は僕が食べちゃったからお弁当作ってみたんだよね。喜んでくれるかな)
「……らぎ。如月」
「は、はい」
「どうかしたか? 体調が悪いとか」
「いえ、考えごとをしていただけです」
「そうか、なら問3の答えを書きに来なさい」
先生に当てられていたことが分からなくなるほど、頭が琥珀くん一色に染まっている。それでもなんの支障もなく問題は解けた。
「正解だ。さすがだな」
「ありがとうございます」
僕はそそくさと自分の席に戻った。時計を見ながら近づく休憩時間に内心そわそわし始めている。
そして待っていた休憩時間に入る授業終了のチャイムが鳴った。先生が教室から出て行ったのを合図に、クラスメイトもざわざわとし始めた。
かく言う僕も、5限目の準備をしてから机の横にかけてあったトートバックを持って「じゃあ、行ってくるね」と鷹也に伝えて教室を出た。
屋上前に隠してある着ぐるみを取りに行ってから、空き教室に向かった。あの部屋は思っていたよりも勝手がよく、過ごしやすかった。驚いたのは冷房や暖房が使えることだった。
階段を降り、角を曲がればすぐそこに教室がある。着ぐるみを被ると籠った空気が熱になり襲いかかってくる。
「夏に着ぐるみはやっぱり暑いな」
教室の窓を触って中に入る。まだ琥珀くんは来ていなかった。
(暑いから少しの間だけ)
着ぐるみを脱ぎ、窓を開けて風に当たった。今日の空はカラッと晴れていて、外にいたらどれだけ心地が良いのだろうと想像してしまう。
「はぁー、涼しい。生き返る」
リラックスしていると外窓下の方で男女の話し声が聞こえ、相手に気づかれにようにこっそり聞き耳を立てた。
「いいじゃないですか! 手合わせしてください」
「嫌だよ。他のやつに頼みなって」
「そう言われると思って、他の部員たちとは既に手合わせ済ませて勝ってきてます!」
「……なんで俺なの」
「ずっとつまらないと思って続けていた空手。中学の大会でセンパイを見て憧れを抱き、それでいつか勝負したいという夢もできました。だからお願いします! 琥珀センパイ!」
手合わせという単語でなんとなくスポーツ系の部活の先輩後輩の言い合いだと察した。だが、後輩であろう彼女は「琥珀センパイ」と口にしていた。
窓から覗き込むと確かに琥珀くんだった。
「そう言われても俺は……」
琥珀くんは言葉を止めて不意にこちらを向いた。僕は反対に逃げるようにして身を隠した。
(バレちゃった? でも一瞬目が合っただけだし。気のせいって思ってくれたら……)
「相手の子、可愛かったな……」
一瞬だけ見えた話し相手の姿を思い出す。親しい後輩といえば空手部の子だろうか。
ショートボブが似合っていて琥珀くんと並んでも目劣りしない可愛らしい子。
琥珀くんがつき合うとしたらああいう子なのかと考えたら、胸が痛い。
殻に閉じこもるように足を抱えて縮こまった。
──ガタン。
「ゆっきー、入るよ」
「あ、うん」
気持ちを半分切り替えて着ぐるみを被った。気分がズンと落ちている今、声のトーンが低くなり分かりやすくなってしまっている。
(切り替えよう。琥珀くんとの時間は楽しいものにしたいから)
「お待たせゆっきー」
「全然大丈夫だよ。早くご飯食べよう?」
僕はさっき見た光景をあえて話題にしなかった。だけどそういう時に限って琥珀くんは話題にする。
「そういえばさっきこの教室の真下にいたんだけど、知らない生徒がいた気がしたんだけど見てない?」
琥珀くんが、『黒髪で宝石のように綺麗な赤い瞳』と言っているのを聞いて「それは僕ですね」と心の中で呟いた。
正体を明かせるわけもなく「見てないかも」と言ってはぐらかした。
「どうしてその人のこと聞きたいの?」
「ん? だってカッコよかったから」
予想と違った琥珀くんの告白に咽てしまった。後ろを向いてお茶で喉を潤し落ち着いてみるが、思い出しで顔が赤くなるくらいドキドキしている。
「また会えたらいいなぁ」
(ここにいるよ。なんて言うことができたなら)
僕は琥珀くんにカッコいいと言われた姿を見せることを目標として心に刻み、特訓もいつも以上に頑張ることを誓った。
ご飯を食べてからは、着ぐるみ越しで20秒見つめ合う特訓をした。だけどいつも赤くなったり、ギブアップしてしまったりと迷惑をかけまくっている。
「今日は17秒までいけたね。少しづつ伸びてきてるからもう少しで治ったりして」
「そうだといいな」
「ゆっきーは今日の放課後すぐ帰る?」
琥珀くんから放課後の話をされたのは初めてだった。いや、昼休みに会うようになってからは初めてと言うほうが正しいだろう。
「今日は特に用事ないかな」
「そうなんだ! よかったらさ……」
──プルルル、プルルル。
電話の鳴る音が教室中に響いた。僕のポケットに入っていたスマホが震えているのではなく琥珀くんのスマホが鳴っていたらしい。
画面を見た琥珀くんは盛大にため息を吐いた。
「ごめん、ゆっきー」
「うん、いいよ」
琥珀くんは電話を取った。僕と話す時みたいな明るい声ではなく、先ほど見たあの子と会話していた時みたいな、心を許している人に出す低い声で話しだした。
「もしも……」
『あ! やっと出ましたね』
「急に電話してきて何? 雛(ひな)」
電話から漏れる声でなんとなく相手がわかった。多分、さっき話していたであろう後輩。
連絡先を交換するような仲なんだろうと少しだけ、ほんの少しだけ嫉妬してしまう。
『今日の放課後にセッティングしたんで絶対来てくださいね!』
ブチっと音を立てて切れた電話に、珍しく琥珀くんも静かにキレていた。どうしてわかったのか、それは琥珀くんの纏う雰囲気が冷たいものに変わったからだ。
「何かあったの?」
「あ、後輩がね俺と勝負したいって言ってきて。断ってるんだけどね、無理やり今日の放課後に試合するって」
「大変だね。頑張って!」
「えー、行きたくないよー」
僕は尊敬されている琥珀くんを応援したい。でも琥珀くんは乗り気ではないみたいで、ぐでーっと溶けるような体勢になって面倒くさがっている。
「でも、相手の子後輩でしょ? 期待に応えてあげないと」
「うえー……。そういや、ゆっきー放課後用事ないってさっき言ってたよね?」
「え、うん。言ったね」
「応援に来て欲しいんだけどダメかな?」
琥珀くんは身体を起き上がられせて口元で手を合わせるポーズをとった。
「え、僕が?!」
「ゆっきーが来てくれたら勝てそうな気がする」
琥珀くんには可愛いくてカッコいい姿であってほしい。
「そういうことなら……わかった。応援に行くから絶対に勝ってね!」
僕は応援に行くと琥珀くんに約束した。
予鈴のチャイムが鳴り、いつも通り順番に教室を出ていく。帰る際に琥珀くんから「待ってるね」と釘を刺されたよな気がした。
だけど1つ問題が発生していることにこの時気がついた。
「僕はどうやって応援に行けばいいんだ?」
ウサギの着ぐるみだと不審者に思われそう。だけどそのままの姿で行ったら琥珀くんがわからないような。
「後ろの方から見ておくしかないか」
僕は悩みに悩んだ結果、素顔の状態で応援しに行ってみることにした。琥珀くんからしたら僕が来ていることわからないと思うけどそこは仕方ない。後日弁明でも図ろう。
それに、ちょっとだけ『気づいてくれないかな』と期待感がある。まぁ素顔で会ったことないから無理だろうけど。
◇
放課後になり、部活が休みの鷹也も連れて空手部の道場を訪れた。
琥珀くんが手合わせすることが、休み時間から放課後の短い時間に広まったようで、出入り口には男女問わずたくさんの生徒が集まっていた。
「琥珀くんが絶対勝つわよ」
「うちらの琥珀くんだしねー」
以前琥珀くんと一緒にいた同じクラスの女子も応援に来ていた。
「ねぇ、あの人!!」
「わぁ、雪兎くんだ。道場に来るなんてどうしたんだろう? ……もしかして、空手部に彼女が!?」
「えー!? 嘘よ!」
「やめてー! 雪兎くんはみんなのものなんだから!」
あちらこちらから女子のコソコソ話す声が聞こえてくる。
「ねぇ鷹也」
「なんだ?」
「みんなこっち見て何か言っている気がするんだけど、気のせいかな?」
「……気のせいだろ」
(その間は何なんだ。絶対気のせいじゃないじゃん)
女子の多い空間でコソコソと言われるとすれば、悪口しか思いつかなかった。
僕は勝手に身の狭い思いをしていたが、本当は僕がここに来ていることに驚かれていたなんて知る由もない。
「これより、霜月琥珀VS弥生(やよい)雛(ひな)の一本勝負を始めます。こちらは特別ルールとして、1回でも技が決まれば勝負終了とします」
審判である生徒の1人が声を出すと、女子の視線が僕たちから道場の中の方へ向いた。
(助かった。琥珀くんは……いた!)
「鷹也いたよ。琥珀くんいた」
「わかったから離せ」
見つけた喜びで思わず鷹也の袖を掴んでいた。
琥珀くんは普段見ることのない道着姿でとてもカッコいい。相手の弥生さん? も長年空手をやってきたことが分かるくらい堂々としている。
「逃げないで来てくださって光栄です、琥珀センパイ」
「本当は逃げようと思ったんだけどね、好きな人に見に来てって言ったから少しでもカッコいいところ見せないと」
「……! センパイ、好きな人って」
「ほら始まるよ」
集団の1番後ろ辺り、扉のそばにいた僕たち2人、幸いにも琥珀くんが見える。だが道場内の声はここまで届かず、中にいる2人が何を話しているのかは不明だった。
だから、こちらを向いた琥珀くんの鋭く獲物を狙ったような目とかち合い、ドキッとさせられる。
「後で教えてくださいね!」
元気いっぱいの弥生さんの声が道場中、いや外にまで聞こえてきて訳の分からない僕らにとったら「何かを賭けてるのかな」とくらいしか思っていなかった。
「よーい、始め」
審判から試合開始の合図を出されると2人は組手の状態になり、動き始めた。お互いタイミングを見て拳で突いたり、横から蹴りを飛ばしたりと接戦だった。
少し押され気味の琥珀くん。僕は無意識に「琥珀くん頑張ってー!」と叫んでいた。周りは僕に視線を向けてきて、大声を出していたことを自覚するととても恥ずかしい気持ちになった。
「ふっ、ゆっきー声でかっ」
琥珀くんの口元が微かに動いた。僕の位置からでは何を言っているのか分からなかったけど、なぜか嬉しそうに笑みを浮かべている。
そして決着がついた。空手のこと詳しくないからすごいとしか言いようがない。
琥珀くんが弥生さんから飛んできた拳を避けて、伸ばされたままの道着の袖を引っ張って相手の背を床につける一本背負いをする。
空手に詳しくない僕はただ『すごい』や『カッコいい』の感想しか出てこなかった。
「勝者、霜月琥珀」
「ありがとうございました」
「ありがとうございました。うぅー、悔しい! 私途中まで勝てるかと思ってました。センパイまた強くなりましたね」
「俺なんてまだまだ。今日は元気がみなぎっていただけ」
「あ、そういえば試合始まる前の好きな人って一体誰のことを言ってたんですか?」
「知りたいなら自分で探してみるか、俺に勝って聞いてみな」
楽しそうに話す琥珀くんは僕の前ではしないような表情ばかりで、寂しい? 感情があった。
「終わったみたいだな。帰るか」
「あ、待って鷹也。もう1つお願いが」
ギャラリーが帰っていき、いつの間にか道場近くにいるのは僕と鷹也だけになっていた。
「じゃあ、行ってくるな」
「うん、よろしく」
鷹也にお願いしたことは、僕の代わりに差し入れを持って行ってもらうことだった。飲み物や部内で休憩の時に食べれるようなものを用意してみた。
僕は道場から見えないところで1人、鷹也が戻ってくるのを待っていた。
「鷹也、ちゃんと渡してくれてるかな」
「雪兎」
道場から小走りで鷹也は帰ってきた。手に何も持っていないところを見ると受け取ってくれたみたいで安心した。
「ちゃんとお前だって言って渡してきた」
「ありがとう」
「……もう話してもいいような気がするけどな」
「何が?」
鷹也を見ると『なんで気がつかねぇの』と言いたそうな引いた顔をしていた。僕には何を言いたいのか、どうしてそんな顔をしているのかわからなかった。
「なんでもねーよ」
「え、待ってよ!」
鷹也は足早で校舎に入っていった後ろを、僕もついていった。