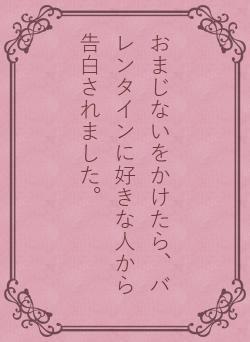はじめはただ、話に聞いていた通りの可愛い子だと思っていた。
「なぁ、このクラスに如月(きさらぎ)雪兎(ゆきと)って奴いる?」
1年生の秋、突然3年生の先輩からのお呼び出し。しかも男の。
告白をされるような雰囲気ではなく、ただ怖いという感情が上回った。
なぜならその先輩は、ピアスがバチバチでモヒカン。いかにもヤバそうって感じの人だったからだ。
教室にいる大半のクラスメイトは名前を聞いてこちらに視線を送ってくる。中には俯いたり、同情して視線を送らなかったりする人もいたが多分全員こう思っているだろう。
早くどこかに行ってくれ、と。
「……僕が如月雪兎ですけど」
本当は隠れていたいが、みんなの視線に応えるように僕は椅子から立って扉に向かった。
「お前か、ちょっとツラ貸せや」
先を歩く先輩の2歩後ろを無言でついて歩く。
校舎裏の人気がない場所で足を止めた先輩、僕も距離を開けながらその場に止まる。
何が始まるのかと警戒していると、先輩からよくわからない言葉が口から飛び出る。
「あのさ俺の彼女、お前と付き合うから別れてとか言い出してきたんだけど」
突然言われた心当たりのないそれに、なんと返したらいいのか分からず言葉が詰まる。
(「お気の毒ですね? でも僕、そんな人知りませんよ」うーん、何を言ってもヤバイ気がする)
頭の中で考えながら、黙って聞いていると先輩の苛立ちが限界に達し、ついに突っかかってきた。
「なんだよ、その余裕をかましてる感じ。気に食わねーよ」
(余裕も何もなんて言えばいいのか考えていただけなんだけどな)
なんて言えるはずもなく、腕を掴まれてもっと人目のつかない校舎裏の奥の方に連れて行かれそうになる。
(これ以上奥に行くと、本当に助けが来なくなってしまう)
僕は必死に足を踏ん張って行くことを拒否した。
「……やめてください!」
「うるせぇ」
休み時間のせいか、騒がしい声に僕の声はかき消されて、誰も気付いてくれそうにない。
引っ張って抵抗していた腕がパッと離されて、勢い余って尻もちをついた。
(イテテ……)
痛い尻を気にするより、頭上にできた影の方が気になってしまった。
僕の視線にあったのは、先輩の腕。振り上げられた拳が、頭上から勢いよく降ってくる。
(あ、殴られる……)
僕は殴られる直前、走馬灯を見た。
「雪兎くん、ずっと前から好きでした。付き合ってください!」
「雪兎には私がお似合いだよ。だから付き合おう?」
この当時、特別好きな人はいなかったけど僕はいつも断っていた。考えが幼いかもしれないけど、僕自身をちゃんと好きでいてくれる人と付き合いたいと思っていたからだ。
告白してきた子たちに「どこが好き?」と聞いてみれば、口をそろえて「顔」と伝えられる。僕はそんなにカッコよくないし、イケメンと言われる程でもない。
それでも周りが勝手に「カッコいい」と言って近づいてくるだけなのに、どうして理不尽に殴られないといけないんだろう。
殴られると悟った僕は、ギュッと強く目を瞑り覚悟した。
「……うわぁ!」
痛さを感じるより先に、誰かの悲鳴が上がった。目を開けると僕より身長の低い子が僕の前に立ち、先輩の顔に向かって握り拳を突きつけている。
さっきまでの喧騒が止み、風に揺れている赤々とした木々の音だけがサーっと抜けていく。
「人を巻き込んだケンカはダサすぎませんか、先輩」
低く言葉を発したその子は、向けていた手を降ろした。
「なになに? どうしたの」
「ケンカか? 先生呼んでくる?」
いつの間にかギャラリーが集まってきていた。
先輩はビビったのか、はたまた彼の言葉が刺さり恥ずかしくなったのか一歩後ずさりして、「覚えてろよー」と悪役が去っていくときに使うセリフを吐いて帰っていった。
(た、助かった……)
その場で安堵すると、指先が微かに震えていた。『怖かった』。ただその一言が、恐怖心と共にやってくる。
「大丈夫だった?」
見上げると助けてくれた子がこちらを振り向いて手を差し伸べる。太陽の光が後ろから差していて、ヒーローの様に輝いて見えた。
「だ、大丈夫です。ありがとう、ございます」
(見たことがある顔。確か同じ1年生の……誰だっけ?)
クルっとした毛先から可愛さを感じ、空手で追い返したカッコよさにギャップがあった。
(それに、僕を、いや困っていた人にまで気遣えるなんて、本当にヒーローみたいだ)
僕が惚れるには十分だった。助けてもらったからではなく、カッコよさからの一目惚れ。
「そっか、良かった。もしケガしてるなら保健室に行ってね」
差し伸べられた手にすがる僕を、力強く起き上がらせてくれた彼に目が離せない。
「じゃあ、俺はこれで」
「あの!」
僕は咄嗟にポケットに入れていた毛糸で作った手作りのウサギの人形を渡した。
「それ、最近ハマっている圭との人形です。いらないかもしれないですけど、お礼にもらってください」
「あ、ありがとう」
彼は戸惑いながらも受け取って校舎の中へ消えていった。
「……あ、名前」
ボーっと彼を見つめていて名前を聞くタイミングを逃したミスをし、1人この場に取り残された。
◇
僕は一目惚れをした名も知らぬあの子のことを考えていて、心ここにあらずになっていたらしい。教室に戻れば幼馴染みの葉月鷹也(はづきたかや)が僕の下に来て肩を掴んできた。
「おい、呼び出されたって聞いたぞ。大丈夫かよ。殴られた感じは……ないな」
身体を触りながら確認する姿は、お医者さんよりお母さんの方が近い。
「頭か? 頭、殴られたからそんなにボーっとしてるのか!? よし、俺がやり返してやるよ」
鷹也は腕をまくる素振りを見せて、教室を出て行こうとした。クラスメトの男子らも乗り気でワイワイ騒いでいたが、僕は何もなかったと説明しその場を収めた。
「鷹也、大丈夫だよ。殴られてない。尻もちついただけだからケガなんて……。あ、血出てる」
掌に擦り傷が少しできていた。多分これは尻もちついた時にできたものだろう。
傷口を水で流したら問題ないと思っていたが、傷を見ていた鷹也が「うわぁーーー!」と騒ぎ始めた。
「誰かガーゼ、いや絆創膏……持ってないよな」
クラスメイトの女子がこちらにやってきて、「私、絆創膏なら持ってるよ」と大きめサイズの絆創膏をくれた。
「ありがとう。鷹也、一旦落ち着こうよ。ね?」
鷹也は肩を上下に動かし深呼吸をして、高ぶっていた気持ちを落ち着かせる。
その間、僕は水道で手を洗い綺麗に拭いた。席に戻って絆創膏の封を開けると、落ち着きを取り戻した鷹也が「貼ってやる」と丁寧な処置をしてくれる。
「さっきは取り乱した。悪い」
「全然。鷹也が心配性だってこと昔から知ってる。ありがとう」
鷹也はお礼を言われて、顔を真っ赤にして照れていた。
(女の子にいつも甘い言葉囁いているだろうに。逆に言われ慣れてない姿を見ると可愛いよね)
伝えると怒るから、僕は静かに言葉を飲み込んだ。
「それで、あの先輩なんの用だったんだ?」
前の席に座り直した鷹也は気になった様子で、聞いてくる。このクラスでアレを目撃していた人なら誰もが気になる内容だろう。
「なんか、先輩の彼女さん? が僕と付き合うから別れてと言ったらしくて。そのことで呼び出された」
「それってつまり、言いがかり?」
結局どうだったのか分からないから否定も肯定もしづらい。僕は静かに言葉を噤(つぐ)む。それが僕の考えだと言わんばかりに。
「やっぱ俺、先輩殴ってくる」
真顔で立ち上がった鷹也を「まぁまぁ」と再度なだめる形になった。
(鷹也は優しいのにすぐ突っ走るからな、あはは)
「それにしても、よく大きなケガせずに帰ってこれたな。尻もちと手に擦り傷だけとかミラクルすぎるだろ」
「あ、そうだ! 聞いてよ鷹也」
僕は詳しく助けてもらったことについて話した。そして、あの子に一目惚れをしたことも。
「もう無理、殴られる! って思って目を瞑った時、僕より先に叫び声が上がって。見ると目の前にヒーローがいて。カッコよくて好きになったんだ」
「ヒーローって、そんな子供みたいな」
「本当だって! 身長は俺より低かったから160㎝台でズボン履いていたから男だと思う。どこかで見たことあるから同じ1年生だと思うんだけど……。可愛い感じの雰囲気の子なのに空手でシュッって。名前知りたいなー」
「……聞かなかったのか?」
鷹也は最初興味を示したものの、ヒーローと言った辺りから冗談だと思って聞いているらしい。本当なのに。
「聞きそびれたから、次学校で見かけたら名前聞きたくて」
鷹也は「……俺も、協力してやるよ」と言ってくれたので、僕は笑顔で「ありがとう、鷹也」と伝えた。
◇
あれから3か月経つが、助けてくれたあの人に会うことなく学校生活を過ごしていた。校内の色々なところを探してはいるが、見つからない。
助けてくれた人は幽霊だったとか、もしかして別の学校の生徒だったのか、とかつまらない理由をつけて仕方ないと思うしかできなかった。
「僕があの人に会えないのはどうしてなんだろう? 神様のいじわる」
「神様は忙しいから、雪兎の願いを聞いてる暇がないんじゃないか?」
「そんなことは……あってほしくないけどな」
落ち込んで机の上に突っ伏していると、クラスメイトの1人が「次、移動だって!」と大声でクラス中に教えてくれた。
(次は家庭科室で裁縫だっけ? 僕、手芸得意だから今やってる授業が楽しくて好きなんだよな)
少し気持ちが浮上している。家庭科の教科書と筆箱、裁縫セットを持って鷹也と並んで教室を後にした。
1階が僕のクラス1年2組の教室、家庭科室は3階にあるため階段を上らないといけない。誰がどう設計して学校を建てたのだろうと上がるたびに毎回思う。
そんなことを考えていると、同じく3階にある音楽室から出てくる別クラスの女子のグループが前から歩いてくる。彼女たちが楽しそうに会話していることはすれ違い様にだが分かる。
「──がいなかった時に行った雑貨屋が可愛くてさ、今度行こうよ」
「うん、連れてって。どんな感じのが多かった?」
「ゆるふわって感じだから私らには合わなかったけど、ここは琥珀のイメージに合ってるねって話してたんだ」
自然と目で追ってしまう、女子の輪の中に混じる柔らかくてふわっとしているクリーム色の髪。
「あ……いた」
「ん? なにが?」
俺の足が止まったのに気付いた鷹也も止まって振り返る。
──ドクッ、ドクッ、ドクッ。
(あの人だ、あの人が僕のことを助けてくれた)
離れていく彼を目で追う。会ったら話しかけて名前を聞くって決めたじゃないか。
「雪兎、お前」
「──え、何?」
「顔真っ赤だけど大丈夫か?」
(顔が真っ赤?)
頬に手を当ててみると、いつもより熱がこもって温かくなっていた。
「あっつ! なんで!」
「熱でもあるのか?」
鷹也は自身と僕のおでこに手を当てて熱を測ったが、顔をしかめるほどで大したことなかった。だけど、それより。
「あの子、女子の輪にいるクリーム色髪の子なんて名前……」
「あー、あいつは霜月(しもつき)琥珀(こはく)だな。可愛いけど男って有名だぞ」
「霜月、琥珀……くん」
名前を知るとまるで呪文のように、心の中で忘れないように唱え始める。
「あいつなんだ……」
「うん、そうだよ。僕を助けてくれたヒーローは。ねぇ鷹也、知ってることなんでもいいから教えて。僕はあの子を、琥珀くんを知りたい」
僕は赤くなった顔のことは忘れて琥珀くんのことで頭をいっぱいにした。
自己満足でしかないけど、また会えたことが本当に嬉しかったんだ。
◇
「えーっと、俺が知ってるのはウワサ程度のものだぞ?」
「それでもいい、教えて鷹也」
僕たちは、家庭科室で班に分かれて座りながら、前々からやっているクッション作りをしつつ話していた。同じ班だからこそ、授業中でもこうやって話せる。
「1年3組霜月琥珀。可愛いものに囲まれて生きているってイメージがあって、見た目も身長が低くて、クリーム色の柔らかい猫っ毛。男子と話すこともあるらしいが基本は女子の輪に交じって過ごしているとか……イテッ」
話しながら作業をしていた鷹也は指に針を刺してしまう。刺したところからぷくっと血が溢れ、慌てて指を口に咥える。
「女子の輪、確かにさっきすれ違った時もそうだったな。……あ、ここ間違ってるよ」
ほとんど作り終わって僕は、鷹也の手の動きを見ながら指摘を入れる役を担う。昔からの付き合いだけど、鷹也は不器用だなと改めて思った。
「あんなにカッコいいのにどうして女子の輪に?」
「逆に空手をしてたなんて俺からしたら初耳だったぞ。可愛くないから隠してたとかが原因じゃ?」
鷹也と考察してみるが僕の中で納得いく理由が見つからず、疑問が残ったまま家庭科の授業が終わるチャイムが鳴った。
昼休みに入ると、僕のお腹はぐぅーっと鳴ってしまうほどペコペコになっていた。
(やっとご飯を食べることができる……。じゃなくて、さっきの話の続き)
「ねぇ鷹也、さっきの」
横に座っているはずの鷹也の姿はなく、空っぽの席だけがそこにあった。
「おーい、俺こっち。購買行くから来いよ」
(そのままどこかで食べると言う意味か)
通学鞄に入れていた弁当とペットボトルのお茶を持って、鷹也の待つ方へ向かった。
購買には人だかりができていた。男子女子関係なく押し合っていて、おしくらまんじゅうをしているようだった。
ついて来ただけの僕は、鷹也に階段で待っていると伝えると人の波をかき分けて隙間を縫っていくように購買から姿を消した。
この人だかりだとしばらくかかりそうだ。
「マンガでも読んでよう」
ポケットに入れていたスマホを取りだし、アプリを開く。選んだマンガは少女マンガだ。
【主人公の女子高校生がガラの悪い連中に絡まれ、その場を目撃したヒーローの男子高校生が助ける。その後2人は同じ学校で再会する】
最近この作品にハマっていて、更新を今か今かと待ち望んでいる読者の一人だ。
(今後の2人の関係性がどう変わっていくのか更新が待ち遠しい! でも、どこかで見たような話だよな。どこだっただろ……)
そんなことを考えていると、制服の上からぶかぶかのパーカーを着てフードを被った小柄な子が前を通り、ハンカチを落としていった。
すぐに拾い上げた僕は、渡さないとと気が急ぎその子の肩を叩く。
「すみません、ハンカチ落としましたよ……」
振り返ったその子の顔は、深く被っているフードで見ることはできなかった。
「あ、ほんとだ。ありがとうございます。助かりました」
見た目とは裏腹に礼儀正しさと丁寧さが垣間見えた。階段を降りていくその子を視線で追っていると、真正面にある窓から突風が吹きフードが後ろに返される。
中から出てきたのは、クリーム色の髪。そして少しだけ見えた優しい色をした薄紫色の瞳。
「あぁ!」
僕は片方の手で口元を押さえる。周りにいた生徒たちがこちらに視線を向けているのが分かる。だが周りの視線が気にならないくらい、今のことが衝撃的だった。
(今のは、琥珀くんだよね。喋っちゃった……)
「待たせたな、いつもならもっと早いんだけど今日はめっちゃ混んでた……ってどうした? 顔赤いけど」
言い訳をしながら帰ってきた鷹也を見ると現実なのか夢なのかわからない。
「今さ、ハンカチを落とした人がいたから渡してあげたんだけど」
「ん? なんの話?」
突如始まった話の内容に追いつけていない鷹也。それはそうだろうが、今は黙って聞いてほしい。
「ぶかぶかのパーカーでフード被ってたから分からなかったんだけど、風で取れた時に琥珀くんだって気づいて」
「え、会ったのか!?」
「……会ったと思う」
「え、話したんだろ?」
「『落としたよ』、『ありがとう』って会話しか」
鷹也はため息をついてから「ついてこい」と屋上へ向かった。本来は鍵がかかっているが、たまに点検不備で開いていることがあるらしい。
フェンスにもたれかかった鷹也の隣に座り、弁当を広げる。
「で、何で話さなかったんだよ」
「だって離れてからわかったし、話しかけたくても緊張して……」
焼きそばパンをほおばる鷹也に言い訳じみたの言葉を返す。
「お前が早く結ばれてくれないと、俺がしんどいわ……」
「ん? 今何か言った?」
「いや、なんも」
小さく呟かれた鷹也の言葉は僕に気づかれることなく、青く広がる空に消えていった。
◇
あの日を境に、今まで見かけることのなかった琥珀くんの姿をたびたび目にするようになった。と言っても、話すことも話しかける勇気もなくただずっと見ているだけだった。
初めは「話したい!」「名前を知りたい」と思っていたのに、今ではすっかり静かに見守ることが使命として僕の中に刻まれている気がした。
「もう疲れた。どうして僕は先生の仕事を手伝っているんでしょうか」
「知らん、てか俺の方が被害者だろ」
ぼやく僕に鷹也がジト目でツッコみを入れる。
おじいちゃん先生の持っていた書類の山を見て助けたことから始まった作業。一向に終わる気配のないホッチキス地獄。これは何クラス分あるんだ?
現実から目を背けようと窓の外を見た。部活に励んでいる野球部やサッカー部、陸上部が声を出して頑張っている。
グラウンド横にある校門までのレンガ道に人影が見えた。
「あ、琥珀くんだ」
「……なに言ってんだ? ついに目もおかしくなったか?」
「本当だって見てみなよ!」
教室の中央で真剣に作業をしていた鷹也もこちらに来て窓から顔を出し見た。
指定の制服に薄黄色のセーターを着て、同色のチェック柄マフラーを首に巻いている琥珀くんが寒そうにしている。
(俺が緊張せずに話しかけることができて、友達や恋人として隣に立てていたなら温めてあげることができるのに。いや、友達でそれをするのは気持ち悪いか)
1人でツッコんでいたが、元気がみなぎってきた。
「よし! 早く終わらせて帰ろう」
「急になんだ、怖いヤツ」
とは言いつつも作業の手を止めていない鷹也は流石。感心しながら僕も手を再び動かし始めた。
「終わったー!!」
それから1時間ほどかかってプリント全てにホッチキスを留めた。外は暗くなり、校庭からの元気な声はいつの間にかなくなっていた。
職員室に抱えてプリントの束を持っていき、先生にプリントを預けて校舎を出る。
帰り道、もうすぐ2年生になることが頭をよぎった。琥珀くんと同じクラスになれたらいいなと願うが叶いそうな予感がしない。
たとえ叶わなくても今日みたいに姿を見ることができるなら十分。
2年生になるのが楽しみな気持ちがより一層、冬の空を煌めかせた。
「なぁ、このクラスに如月(きさらぎ)雪兎(ゆきと)って奴いる?」
1年生の秋、突然3年生の先輩からのお呼び出し。しかも男の。
告白をされるような雰囲気ではなく、ただ怖いという感情が上回った。
なぜならその先輩は、ピアスがバチバチでモヒカン。いかにもヤバそうって感じの人だったからだ。
教室にいる大半のクラスメイトは名前を聞いてこちらに視線を送ってくる。中には俯いたり、同情して視線を送らなかったりする人もいたが多分全員こう思っているだろう。
早くどこかに行ってくれ、と。
「……僕が如月雪兎ですけど」
本当は隠れていたいが、みんなの視線に応えるように僕は椅子から立って扉に向かった。
「お前か、ちょっとツラ貸せや」
先を歩く先輩の2歩後ろを無言でついて歩く。
校舎裏の人気がない場所で足を止めた先輩、僕も距離を開けながらその場に止まる。
何が始まるのかと警戒していると、先輩からよくわからない言葉が口から飛び出る。
「あのさ俺の彼女、お前と付き合うから別れてとか言い出してきたんだけど」
突然言われた心当たりのないそれに、なんと返したらいいのか分からず言葉が詰まる。
(「お気の毒ですね? でも僕、そんな人知りませんよ」うーん、何を言ってもヤバイ気がする)
頭の中で考えながら、黙って聞いていると先輩の苛立ちが限界に達し、ついに突っかかってきた。
「なんだよ、その余裕をかましてる感じ。気に食わねーよ」
(余裕も何もなんて言えばいいのか考えていただけなんだけどな)
なんて言えるはずもなく、腕を掴まれてもっと人目のつかない校舎裏の奥の方に連れて行かれそうになる。
(これ以上奥に行くと、本当に助けが来なくなってしまう)
僕は必死に足を踏ん張って行くことを拒否した。
「……やめてください!」
「うるせぇ」
休み時間のせいか、騒がしい声に僕の声はかき消されて、誰も気付いてくれそうにない。
引っ張って抵抗していた腕がパッと離されて、勢い余って尻もちをついた。
(イテテ……)
痛い尻を気にするより、頭上にできた影の方が気になってしまった。
僕の視線にあったのは、先輩の腕。振り上げられた拳が、頭上から勢いよく降ってくる。
(あ、殴られる……)
僕は殴られる直前、走馬灯を見た。
「雪兎くん、ずっと前から好きでした。付き合ってください!」
「雪兎には私がお似合いだよ。だから付き合おう?」
この当時、特別好きな人はいなかったけど僕はいつも断っていた。考えが幼いかもしれないけど、僕自身をちゃんと好きでいてくれる人と付き合いたいと思っていたからだ。
告白してきた子たちに「どこが好き?」と聞いてみれば、口をそろえて「顔」と伝えられる。僕はそんなにカッコよくないし、イケメンと言われる程でもない。
それでも周りが勝手に「カッコいい」と言って近づいてくるだけなのに、どうして理不尽に殴られないといけないんだろう。
殴られると悟った僕は、ギュッと強く目を瞑り覚悟した。
「……うわぁ!」
痛さを感じるより先に、誰かの悲鳴が上がった。目を開けると僕より身長の低い子が僕の前に立ち、先輩の顔に向かって握り拳を突きつけている。
さっきまでの喧騒が止み、風に揺れている赤々とした木々の音だけがサーっと抜けていく。
「人を巻き込んだケンカはダサすぎませんか、先輩」
低く言葉を発したその子は、向けていた手を降ろした。
「なになに? どうしたの」
「ケンカか? 先生呼んでくる?」
いつの間にかギャラリーが集まってきていた。
先輩はビビったのか、はたまた彼の言葉が刺さり恥ずかしくなったのか一歩後ずさりして、「覚えてろよー」と悪役が去っていくときに使うセリフを吐いて帰っていった。
(た、助かった……)
その場で安堵すると、指先が微かに震えていた。『怖かった』。ただその一言が、恐怖心と共にやってくる。
「大丈夫だった?」
見上げると助けてくれた子がこちらを振り向いて手を差し伸べる。太陽の光が後ろから差していて、ヒーローの様に輝いて見えた。
「だ、大丈夫です。ありがとう、ございます」
(見たことがある顔。確か同じ1年生の……誰だっけ?)
クルっとした毛先から可愛さを感じ、空手で追い返したカッコよさにギャップがあった。
(それに、僕を、いや困っていた人にまで気遣えるなんて、本当にヒーローみたいだ)
僕が惚れるには十分だった。助けてもらったからではなく、カッコよさからの一目惚れ。
「そっか、良かった。もしケガしてるなら保健室に行ってね」
差し伸べられた手にすがる僕を、力強く起き上がらせてくれた彼に目が離せない。
「じゃあ、俺はこれで」
「あの!」
僕は咄嗟にポケットに入れていた毛糸で作った手作りのウサギの人形を渡した。
「それ、最近ハマっている圭との人形です。いらないかもしれないですけど、お礼にもらってください」
「あ、ありがとう」
彼は戸惑いながらも受け取って校舎の中へ消えていった。
「……あ、名前」
ボーっと彼を見つめていて名前を聞くタイミングを逃したミスをし、1人この場に取り残された。
◇
僕は一目惚れをした名も知らぬあの子のことを考えていて、心ここにあらずになっていたらしい。教室に戻れば幼馴染みの葉月鷹也(はづきたかや)が僕の下に来て肩を掴んできた。
「おい、呼び出されたって聞いたぞ。大丈夫かよ。殴られた感じは……ないな」
身体を触りながら確認する姿は、お医者さんよりお母さんの方が近い。
「頭か? 頭、殴られたからそんなにボーっとしてるのか!? よし、俺がやり返してやるよ」
鷹也は腕をまくる素振りを見せて、教室を出て行こうとした。クラスメトの男子らも乗り気でワイワイ騒いでいたが、僕は何もなかったと説明しその場を収めた。
「鷹也、大丈夫だよ。殴られてない。尻もちついただけだからケガなんて……。あ、血出てる」
掌に擦り傷が少しできていた。多分これは尻もちついた時にできたものだろう。
傷口を水で流したら問題ないと思っていたが、傷を見ていた鷹也が「うわぁーーー!」と騒ぎ始めた。
「誰かガーゼ、いや絆創膏……持ってないよな」
クラスメイトの女子がこちらにやってきて、「私、絆創膏なら持ってるよ」と大きめサイズの絆創膏をくれた。
「ありがとう。鷹也、一旦落ち着こうよ。ね?」
鷹也は肩を上下に動かし深呼吸をして、高ぶっていた気持ちを落ち着かせる。
その間、僕は水道で手を洗い綺麗に拭いた。席に戻って絆創膏の封を開けると、落ち着きを取り戻した鷹也が「貼ってやる」と丁寧な処置をしてくれる。
「さっきは取り乱した。悪い」
「全然。鷹也が心配性だってこと昔から知ってる。ありがとう」
鷹也はお礼を言われて、顔を真っ赤にして照れていた。
(女の子にいつも甘い言葉囁いているだろうに。逆に言われ慣れてない姿を見ると可愛いよね)
伝えると怒るから、僕は静かに言葉を飲み込んだ。
「それで、あの先輩なんの用だったんだ?」
前の席に座り直した鷹也は気になった様子で、聞いてくる。このクラスでアレを目撃していた人なら誰もが気になる内容だろう。
「なんか、先輩の彼女さん? が僕と付き合うから別れてと言ったらしくて。そのことで呼び出された」
「それってつまり、言いがかり?」
結局どうだったのか分からないから否定も肯定もしづらい。僕は静かに言葉を噤(つぐ)む。それが僕の考えだと言わんばかりに。
「やっぱ俺、先輩殴ってくる」
真顔で立ち上がった鷹也を「まぁまぁ」と再度なだめる形になった。
(鷹也は優しいのにすぐ突っ走るからな、あはは)
「それにしても、よく大きなケガせずに帰ってこれたな。尻もちと手に擦り傷だけとかミラクルすぎるだろ」
「あ、そうだ! 聞いてよ鷹也」
僕は詳しく助けてもらったことについて話した。そして、あの子に一目惚れをしたことも。
「もう無理、殴られる! って思って目を瞑った時、僕より先に叫び声が上がって。見ると目の前にヒーローがいて。カッコよくて好きになったんだ」
「ヒーローって、そんな子供みたいな」
「本当だって! 身長は俺より低かったから160㎝台でズボン履いていたから男だと思う。どこかで見たことあるから同じ1年生だと思うんだけど……。可愛い感じの雰囲気の子なのに空手でシュッって。名前知りたいなー」
「……聞かなかったのか?」
鷹也は最初興味を示したものの、ヒーローと言った辺りから冗談だと思って聞いているらしい。本当なのに。
「聞きそびれたから、次学校で見かけたら名前聞きたくて」
鷹也は「……俺も、協力してやるよ」と言ってくれたので、僕は笑顔で「ありがとう、鷹也」と伝えた。
◇
あれから3か月経つが、助けてくれたあの人に会うことなく学校生活を過ごしていた。校内の色々なところを探してはいるが、見つからない。
助けてくれた人は幽霊だったとか、もしかして別の学校の生徒だったのか、とかつまらない理由をつけて仕方ないと思うしかできなかった。
「僕があの人に会えないのはどうしてなんだろう? 神様のいじわる」
「神様は忙しいから、雪兎の願いを聞いてる暇がないんじゃないか?」
「そんなことは……あってほしくないけどな」
落ち込んで机の上に突っ伏していると、クラスメイトの1人が「次、移動だって!」と大声でクラス中に教えてくれた。
(次は家庭科室で裁縫だっけ? 僕、手芸得意だから今やってる授業が楽しくて好きなんだよな)
少し気持ちが浮上している。家庭科の教科書と筆箱、裁縫セットを持って鷹也と並んで教室を後にした。
1階が僕のクラス1年2組の教室、家庭科室は3階にあるため階段を上らないといけない。誰がどう設計して学校を建てたのだろうと上がるたびに毎回思う。
そんなことを考えていると、同じく3階にある音楽室から出てくる別クラスの女子のグループが前から歩いてくる。彼女たちが楽しそうに会話していることはすれ違い様にだが分かる。
「──がいなかった時に行った雑貨屋が可愛くてさ、今度行こうよ」
「うん、連れてって。どんな感じのが多かった?」
「ゆるふわって感じだから私らには合わなかったけど、ここは琥珀のイメージに合ってるねって話してたんだ」
自然と目で追ってしまう、女子の輪の中に混じる柔らかくてふわっとしているクリーム色の髪。
「あ……いた」
「ん? なにが?」
俺の足が止まったのに気付いた鷹也も止まって振り返る。
──ドクッ、ドクッ、ドクッ。
(あの人だ、あの人が僕のことを助けてくれた)
離れていく彼を目で追う。会ったら話しかけて名前を聞くって決めたじゃないか。
「雪兎、お前」
「──え、何?」
「顔真っ赤だけど大丈夫か?」
(顔が真っ赤?)
頬に手を当ててみると、いつもより熱がこもって温かくなっていた。
「あっつ! なんで!」
「熱でもあるのか?」
鷹也は自身と僕のおでこに手を当てて熱を測ったが、顔をしかめるほどで大したことなかった。だけど、それより。
「あの子、女子の輪にいるクリーム色髪の子なんて名前……」
「あー、あいつは霜月(しもつき)琥珀(こはく)だな。可愛いけど男って有名だぞ」
「霜月、琥珀……くん」
名前を知るとまるで呪文のように、心の中で忘れないように唱え始める。
「あいつなんだ……」
「うん、そうだよ。僕を助けてくれたヒーローは。ねぇ鷹也、知ってることなんでもいいから教えて。僕はあの子を、琥珀くんを知りたい」
僕は赤くなった顔のことは忘れて琥珀くんのことで頭をいっぱいにした。
自己満足でしかないけど、また会えたことが本当に嬉しかったんだ。
◇
「えーっと、俺が知ってるのはウワサ程度のものだぞ?」
「それでもいい、教えて鷹也」
僕たちは、家庭科室で班に分かれて座りながら、前々からやっているクッション作りをしつつ話していた。同じ班だからこそ、授業中でもこうやって話せる。
「1年3組霜月琥珀。可愛いものに囲まれて生きているってイメージがあって、見た目も身長が低くて、クリーム色の柔らかい猫っ毛。男子と話すこともあるらしいが基本は女子の輪に交じって過ごしているとか……イテッ」
話しながら作業をしていた鷹也は指に針を刺してしまう。刺したところからぷくっと血が溢れ、慌てて指を口に咥える。
「女子の輪、確かにさっきすれ違った時もそうだったな。……あ、ここ間違ってるよ」
ほとんど作り終わって僕は、鷹也の手の動きを見ながら指摘を入れる役を担う。昔からの付き合いだけど、鷹也は不器用だなと改めて思った。
「あんなにカッコいいのにどうして女子の輪に?」
「逆に空手をしてたなんて俺からしたら初耳だったぞ。可愛くないから隠してたとかが原因じゃ?」
鷹也と考察してみるが僕の中で納得いく理由が見つからず、疑問が残ったまま家庭科の授業が終わるチャイムが鳴った。
昼休みに入ると、僕のお腹はぐぅーっと鳴ってしまうほどペコペコになっていた。
(やっとご飯を食べることができる……。じゃなくて、さっきの話の続き)
「ねぇ鷹也、さっきの」
横に座っているはずの鷹也の姿はなく、空っぽの席だけがそこにあった。
「おーい、俺こっち。購買行くから来いよ」
(そのままどこかで食べると言う意味か)
通学鞄に入れていた弁当とペットボトルのお茶を持って、鷹也の待つ方へ向かった。
購買には人だかりができていた。男子女子関係なく押し合っていて、おしくらまんじゅうをしているようだった。
ついて来ただけの僕は、鷹也に階段で待っていると伝えると人の波をかき分けて隙間を縫っていくように購買から姿を消した。
この人だかりだとしばらくかかりそうだ。
「マンガでも読んでよう」
ポケットに入れていたスマホを取りだし、アプリを開く。選んだマンガは少女マンガだ。
【主人公の女子高校生がガラの悪い連中に絡まれ、その場を目撃したヒーローの男子高校生が助ける。その後2人は同じ学校で再会する】
最近この作品にハマっていて、更新を今か今かと待ち望んでいる読者の一人だ。
(今後の2人の関係性がどう変わっていくのか更新が待ち遠しい! でも、どこかで見たような話だよな。どこだっただろ……)
そんなことを考えていると、制服の上からぶかぶかのパーカーを着てフードを被った小柄な子が前を通り、ハンカチを落としていった。
すぐに拾い上げた僕は、渡さないとと気が急ぎその子の肩を叩く。
「すみません、ハンカチ落としましたよ……」
振り返ったその子の顔は、深く被っているフードで見ることはできなかった。
「あ、ほんとだ。ありがとうございます。助かりました」
見た目とは裏腹に礼儀正しさと丁寧さが垣間見えた。階段を降りていくその子を視線で追っていると、真正面にある窓から突風が吹きフードが後ろに返される。
中から出てきたのは、クリーム色の髪。そして少しだけ見えた優しい色をした薄紫色の瞳。
「あぁ!」
僕は片方の手で口元を押さえる。周りにいた生徒たちがこちらに視線を向けているのが分かる。だが周りの視線が気にならないくらい、今のことが衝撃的だった。
(今のは、琥珀くんだよね。喋っちゃった……)
「待たせたな、いつもならもっと早いんだけど今日はめっちゃ混んでた……ってどうした? 顔赤いけど」
言い訳をしながら帰ってきた鷹也を見ると現実なのか夢なのかわからない。
「今さ、ハンカチを落とした人がいたから渡してあげたんだけど」
「ん? なんの話?」
突如始まった話の内容に追いつけていない鷹也。それはそうだろうが、今は黙って聞いてほしい。
「ぶかぶかのパーカーでフード被ってたから分からなかったんだけど、風で取れた時に琥珀くんだって気づいて」
「え、会ったのか!?」
「……会ったと思う」
「え、話したんだろ?」
「『落としたよ』、『ありがとう』って会話しか」
鷹也はため息をついてから「ついてこい」と屋上へ向かった。本来は鍵がかかっているが、たまに点検不備で開いていることがあるらしい。
フェンスにもたれかかった鷹也の隣に座り、弁当を広げる。
「で、何で話さなかったんだよ」
「だって離れてからわかったし、話しかけたくても緊張して……」
焼きそばパンをほおばる鷹也に言い訳じみたの言葉を返す。
「お前が早く結ばれてくれないと、俺がしんどいわ……」
「ん? 今何か言った?」
「いや、なんも」
小さく呟かれた鷹也の言葉は僕に気づかれることなく、青く広がる空に消えていった。
◇
あの日を境に、今まで見かけることのなかった琥珀くんの姿をたびたび目にするようになった。と言っても、話すことも話しかける勇気もなくただずっと見ているだけだった。
初めは「話したい!」「名前を知りたい」と思っていたのに、今ではすっかり静かに見守ることが使命として僕の中に刻まれている気がした。
「もう疲れた。どうして僕は先生の仕事を手伝っているんでしょうか」
「知らん、てか俺の方が被害者だろ」
ぼやく僕に鷹也がジト目でツッコみを入れる。
おじいちゃん先生の持っていた書類の山を見て助けたことから始まった作業。一向に終わる気配のないホッチキス地獄。これは何クラス分あるんだ?
現実から目を背けようと窓の外を見た。部活に励んでいる野球部やサッカー部、陸上部が声を出して頑張っている。
グラウンド横にある校門までのレンガ道に人影が見えた。
「あ、琥珀くんだ」
「……なに言ってんだ? ついに目もおかしくなったか?」
「本当だって見てみなよ!」
教室の中央で真剣に作業をしていた鷹也もこちらに来て窓から顔を出し見た。
指定の制服に薄黄色のセーターを着て、同色のチェック柄マフラーを首に巻いている琥珀くんが寒そうにしている。
(俺が緊張せずに話しかけることができて、友達や恋人として隣に立てていたなら温めてあげることができるのに。いや、友達でそれをするのは気持ち悪いか)
1人でツッコんでいたが、元気がみなぎってきた。
「よし! 早く終わらせて帰ろう」
「急になんだ、怖いヤツ」
とは言いつつも作業の手を止めていない鷹也は流石。感心しながら僕も手を再び動かし始めた。
「終わったー!!」
それから1時間ほどかかってプリント全てにホッチキスを留めた。外は暗くなり、校庭からの元気な声はいつの間にかなくなっていた。
職員室に抱えてプリントの束を持っていき、先生にプリントを預けて校舎を出る。
帰り道、もうすぐ2年生になることが頭をよぎった。琥珀くんと同じクラスになれたらいいなと願うが叶いそうな予感がしない。
たとえ叶わなくても今日みたいに姿を見ることができるなら十分。
2年生になるのが楽しみな気持ちがより一層、冬の空を煌めかせた。