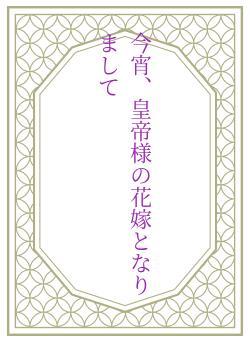私は、桜の花も満開を迎え、もうそろそろ散るかというときに、お義母様に呼び出された。
このときの私は、大きな不安と、一抹の希望を持っていた。
しかし、毎回呼び出されても、話の内容はお小言だったり、私がどれだけ卑しいのかなどということしか話さない。
呼び出す理由は、自分にとって、嫌なことが会ったときや、誰かに八つ当たりしたいときなどが主だった。
その時には、必ずと言っていいほどお姉様もいて、私にお茶をかけたり、偶然と見せかけて転ばせたりなどもした。
ここ最近では、お姉様の私に対する風当たりは日に日に強くなっていて、数年前の怒鳴りつけられるくらいのことなんて、とってもちっぽけに見えるほどだった。
そのため、いつしか希望は薄れ、反対に何をされるのだろうという、不安や恐怖が大きくなっていった。
そうしているうちに本邸の居間についた。
本邸の居間は、私の離れとは真反対にあり、日当たりも庭も良家の風姿になっている。
コンコンコン
「失礼します。
奥様、お嬢様。参りました。」
「、、、入りなさい。」
「はい。」
中に入ってみると、予想外の人物までもがいた。
「涼太さん、、、」
そこには、一応私の婚約者で、良家の長子であられる斎藤 涼太さんがいた。
更には、涼太さんはお姉様と腕を組んでいた。
お姉様は、その抱擁をまんざらでもないような顔で受け入れていた。
そうして、私が放心していると、お母様がお言葉をのべられた。
「いいこと。
涼太さんは、愛凛と結婚させます。」
、、、一瞬、私の周りの時間という時間が止まったのではないかと思うくらいの衝撃を受けた。
しかし、その間もお義母様は口を休ますことなく私を射落とさんばかりの熱量で喋ってきた。
その時、私は衝撃が強すぎて、何を言っているのか聞き取ることができなかった。
しかし、お義母様が満足そうに全てを話しきったという顔になった頃には、私はもう、『はい』としか言うことができなくなっていた。
「わかりましたね。」
「はい、奥様。」
しかし、このときの私は、これが呼び出された理由の全てだと思っていた。
そして、お義母様は、私にさらなる衝撃と絶望を与えてきた。
「では、明日にはここを出ていきなさい。
あなたは、この家のために生贄として出さなければなりませんからね。」
「はい、、、えっ?」
生、贄?私が、、、?
この人は、私に女性にとって最大の屈辱とも言える婚約を破棄させて、さらには生贄になれ、とおっしゃたの。
だか、確かにこの家には、他家の良家とは違う特徴が1つだけあった。
それは、この家が100年に1度生贄を出さなくてはならないという掟だ。
理由は、たしかお父様に聞いたことがある。
昔の昔、そのまた昔に、この家には大きな厄災が降り掛かってきったらしい。
そのときに、炎南神社に、なぜだかはわからないが生贄を捧げ、繁栄をもたらした、という話があるらしい。
「なにを呆けているの?
さっさと荷物をまとめて、出ていきなさいよ。」
私が放心していると、お姉様が私を嘲笑うようにいってきた。
その時に、私に見せつけるよう涼太さんと腕を組んで、仲睦まじい様子を見せつけてくるようにしながら。
また、涼太さんは私が見えていない透明人間だとでも言うように、元婚約者の私に挨拶も、さらには目すらも合わせてくれなかった。
こうした態度を見て、私の中のなんとか、ピンッと張っていたような糸がプツンとちぎれてしまった。
「はい、、、
今まで、お世話になりました。」
、、、でも、そうなのかもしれない。
私は、この家に産まれてはいけなかった、卑しい子だ。
私は、私ですら好きになれない。
好きになってはいけないのだ、、、
*
そのようなことがあってから、私はほとんど荷物のないような巾着に、少しばかりまともな服を着て山の麓に来ていた。
お付のものは誰もいない。
私なんかについてきたいと思う使用人なんて、いるわけがないだろう。
逃げれば良いと、私の心の中はそう言っていた。
しかし、それはできなかった。
なぜなら、お姉様が私を逃げられないようにと、縄で手首と足首を縛ってしまったからだ。
だが、縛られなかったとしても動くことはできないだろう。
私の中にはまだ、あの人達にそこまで非情に慣れる自信がなかったからだ。
「私、死ぬのかな、、、」
きっと死ぬのだろう。
本当に、神様なんているわけない、、、
迎えに来てくれる人なんて、私にはいないのだから、、、
狼や、犬に食われるのか、はたまた餓死して死ぬのか、いっそのことこの世から解放されるなんて、嬉しいことだなぁ。
そうして、私が人生のどん底に突き落とされていると、突然森のほうが騒がしくなってきた。
ザワザワ、、、
森が騒がしい、、、
動物の音も、植物の音もどことなくだがなにかにおそれをなしているような気がする、、、
まぁ良いか、どうせ散りさる命なのだから。
そうして、私は目を閉じ今世を諦め、去ろうとした時、その人は現れた。
「もし、そこのお嬢さん。
捨て去る命なら、私に預けてみませんか?」
きれい、、、
容姿が端麗という言葉では表せないほどの、芸術的なまでの美しさが私の目の前に現れた。
更に良く見てみると、長髪の髪は真紅のように美しく頭部から下部にかけて、黄色いグラデーションになっており、瞳は燃え盛るような赤に少しの青がかかっていた。
私が思わずその人見とれていると、その人は私を心配したのか話しかけてきた。
「大丈夫ですか?」
ハッ
「大丈夫です。、、、あの、あなたは?」
その人は私が尋ねると、ハッとしたように言った。
「すいません。私が何者なのかは、後ほどゆっくりお聞きください。」
その人は茶目っ気たっぷりに笑うと、手をかかげ唱えた。
「我が名は四神が一人、朱南。
幽世の門よ、我の問いに答え、開門せよ——」
このときの私は、大きな不安と、一抹の希望を持っていた。
しかし、毎回呼び出されても、話の内容はお小言だったり、私がどれだけ卑しいのかなどということしか話さない。
呼び出す理由は、自分にとって、嫌なことが会ったときや、誰かに八つ当たりしたいときなどが主だった。
その時には、必ずと言っていいほどお姉様もいて、私にお茶をかけたり、偶然と見せかけて転ばせたりなどもした。
ここ最近では、お姉様の私に対する風当たりは日に日に強くなっていて、数年前の怒鳴りつけられるくらいのことなんて、とってもちっぽけに見えるほどだった。
そのため、いつしか希望は薄れ、反対に何をされるのだろうという、不安や恐怖が大きくなっていった。
そうしているうちに本邸の居間についた。
本邸の居間は、私の離れとは真反対にあり、日当たりも庭も良家の風姿になっている。
コンコンコン
「失礼します。
奥様、お嬢様。参りました。」
「、、、入りなさい。」
「はい。」
中に入ってみると、予想外の人物までもがいた。
「涼太さん、、、」
そこには、一応私の婚約者で、良家の長子であられる斎藤 涼太さんがいた。
更には、涼太さんはお姉様と腕を組んでいた。
お姉様は、その抱擁をまんざらでもないような顔で受け入れていた。
そうして、私が放心していると、お母様がお言葉をのべられた。
「いいこと。
涼太さんは、愛凛と結婚させます。」
、、、一瞬、私の周りの時間という時間が止まったのではないかと思うくらいの衝撃を受けた。
しかし、その間もお義母様は口を休ますことなく私を射落とさんばかりの熱量で喋ってきた。
その時、私は衝撃が強すぎて、何を言っているのか聞き取ることができなかった。
しかし、お義母様が満足そうに全てを話しきったという顔になった頃には、私はもう、『はい』としか言うことができなくなっていた。
「わかりましたね。」
「はい、奥様。」
しかし、このときの私は、これが呼び出された理由の全てだと思っていた。
そして、お義母様は、私にさらなる衝撃と絶望を与えてきた。
「では、明日にはここを出ていきなさい。
あなたは、この家のために生贄として出さなければなりませんからね。」
「はい、、、えっ?」
生、贄?私が、、、?
この人は、私に女性にとって最大の屈辱とも言える婚約を破棄させて、さらには生贄になれ、とおっしゃたの。
だか、確かにこの家には、他家の良家とは違う特徴が1つだけあった。
それは、この家が100年に1度生贄を出さなくてはならないという掟だ。
理由は、たしかお父様に聞いたことがある。
昔の昔、そのまた昔に、この家には大きな厄災が降り掛かってきったらしい。
そのときに、炎南神社に、なぜだかはわからないが生贄を捧げ、繁栄をもたらした、という話があるらしい。
「なにを呆けているの?
さっさと荷物をまとめて、出ていきなさいよ。」
私が放心していると、お姉様が私を嘲笑うようにいってきた。
その時に、私に見せつけるよう涼太さんと腕を組んで、仲睦まじい様子を見せつけてくるようにしながら。
また、涼太さんは私が見えていない透明人間だとでも言うように、元婚約者の私に挨拶も、さらには目すらも合わせてくれなかった。
こうした態度を見て、私の中のなんとか、ピンッと張っていたような糸がプツンとちぎれてしまった。
「はい、、、
今まで、お世話になりました。」
、、、でも、そうなのかもしれない。
私は、この家に産まれてはいけなかった、卑しい子だ。
私は、私ですら好きになれない。
好きになってはいけないのだ、、、
*
そのようなことがあってから、私はほとんど荷物のないような巾着に、少しばかりまともな服を着て山の麓に来ていた。
お付のものは誰もいない。
私なんかについてきたいと思う使用人なんて、いるわけがないだろう。
逃げれば良いと、私の心の中はそう言っていた。
しかし、それはできなかった。
なぜなら、お姉様が私を逃げられないようにと、縄で手首と足首を縛ってしまったからだ。
だが、縛られなかったとしても動くことはできないだろう。
私の中にはまだ、あの人達にそこまで非情に慣れる自信がなかったからだ。
「私、死ぬのかな、、、」
きっと死ぬのだろう。
本当に、神様なんているわけない、、、
迎えに来てくれる人なんて、私にはいないのだから、、、
狼や、犬に食われるのか、はたまた餓死して死ぬのか、いっそのことこの世から解放されるなんて、嬉しいことだなぁ。
そうして、私が人生のどん底に突き落とされていると、突然森のほうが騒がしくなってきた。
ザワザワ、、、
森が騒がしい、、、
動物の音も、植物の音もどことなくだがなにかにおそれをなしているような気がする、、、
まぁ良いか、どうせ散りさる命なのだから。
そうして、私は目を閉じ今世を諦め、去ろうとした時、その人は現れた。
「もし、そこのお嬢さん。
捨て去る命なら、私に預けてみませんか?」
きれい、、、
容姿が端麗という言葉では表せないほどの、芸術的なまでの美しさが私の目の前に現れた。
更に良く見てみると、長髪の髪は真紅のように美しく頭部から下部にかけて、黄色いグラデーションになっており、瞳は燃え盛るような赤に少しの青がかかっていた。
私が思わずその人見とれていると、その人は私を心配したのか話しかけてきた。
「大丈夫ですか?」
ハッ
「大丈夫です。、、、あの、あなたは?」
その人は私が尋ねると、ハッとしたように言った。
「すいません。私が何者なのかは、後ほどゆっくりお聞きください。」
その人は茶目っ気たっぷりに笑うと、手をかかげ唱えた。
「我が名は四神が一人、朱南。
幽世の門よ、我の問いに答え、開門せよ——」