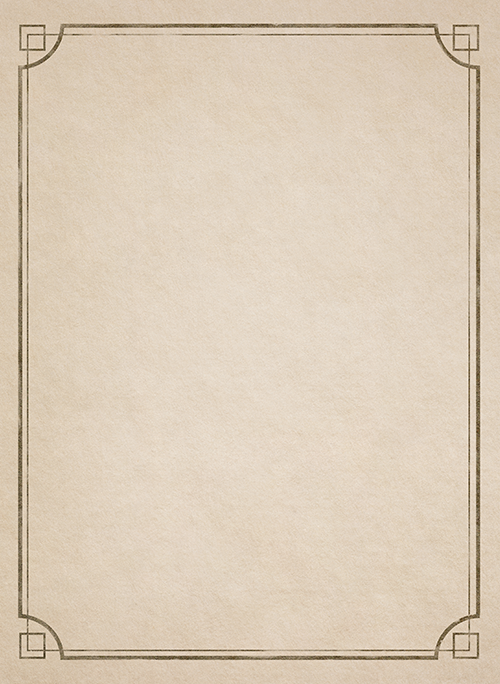「ごめん。寝ぼけてた」
平手打ちをくらった頬を赤くしながら、頭を下げる詩。
対して紬は、怒りで頬を赤く染めていた。
「最初、賭けをする時に言ってたわよね。私の嫌がるようなことは絶対にしないって」
「ごめんなさい」
シュンと俯いて、ガックリと肩を落とす詩。
それを見て、紬も文句を言う口を閉じる。
(言い過ぎた? でも、これは怒っていいわよね。まあ、これ以上強く言う必要もないか)
もういい。そう言って終わりにしようとするが、その前に詩が口を開いた。
「夢の中では、俺たちすっかり仲良くなってたんだ。起きたら目の前に紬の顔があったものだから、ついその続きをしたくなって……」
「どんな夢見てたのよ!」
ますます頬を赤くしながら、アヤカシの世界にセクハラという言葉はあるのだろうかと考える。
そんな二人の言い合いが聞こえたのか、いつの間にか部屋の前には何体ものアヤカシが集まっていた。
「なんだ、詩様が押し倒そうとして怒らせたのか?」
「と言っても、奥方だろう。やってダメということはあるまい」
「夫婦と言っても、形だけのものだからな」
「なに言ってるんだい。たとえ本当の夫婦だって、無理強いなんて許されるわけないじゃないか」
この屋敷のアヤカシたちは、二人が形だけの夫婦であることも、紬が詩を好きになるかという賭けのことも知っている。
そのこともあって面白おかしく話しているが、紬としては全く面白くない。
「もういいわ。起きたんだから、私の仕事はこれで終わりでしょ」
これ以上あれこれ言われるのはごめんだ。
さっさと部屋から出ていこうとするが、そこで詩が呼び止める。
「待って、紬。起こしてくれて、ありがとう」
「あなたが頼んだんでしょ」
「それを引き受けてくれたのは紬だよ。嫌なら断ればいいんだもの」
「ああ、その手があったわね」
ハッとしたように、足を止める紬。
すると詩は、途端に慌て出す。
「ちょっと待って。まさか、明日からはもう起こさないなんてことないよね?」
「だって、起こしたらまた無理やり抱きしめられるかもしれないじゃない」
「明日からはしないから。次抱きしめるのは、紬が俺を好きになった時にするから」
「来ないわよ、そんな時」
「とにかくお願い。朝一番に紬の顔が見たいんだよ」
結局、詩があまりにも頼むものだから、明日からもこれまでと同じように起こすことになった。
そうして今度こそ部屋を出るが、なんだかすごく疲れたような気がする。
「なんで私、こんなことしているんだろう?」
詩と夫婦になったから。
そう言ってしまえばそれまでなのだが、想像していたアヤカシ相手の嫁入りとは、まるで違う。
しかし、ただ霊力を得るための餌として扱われるのを思うと、遥かにマシではあるのだ。
「しっかし、なんだかんだで明日からも起こしに行くつもりみたいだし、本当は紬様も満更じゃないんじゃないですかい?」
そう言って笑うのは、屋敷の使用人の喜八だ。緑の体に頭に皿を持つアヤカシ。要は河童だ。
「なに言ってるんですか?」
「だってうちの詩様、人間から見ても相当な男前じゃないですか。そんな人にあんなに好き好き言われたら、悪い気はしないんじゃないんですか?」
「あんな軽い調子で軽々好きって言われて、本気になれるわけないでしょ」
良い扱いをしてもらっていることには、正直なところ感謝はしている。
しかしだからといって、詩のことを好きになるかというと、全くの別問題だ。
「そうですよ喜八さん。女心は複雑なんですからね」
「なんだよ忍。お前、詩様の恋路が上手くいかなくてもいいのかよ?」
「もちろん私だって、詩様には幸せになってほしいですよ。けどね、いくら男前だろうとイケメンだろうと、好いた惚れたってのは当人の気持ち次第なんですから。他人が口出しするのは野暮ってもんですよ」
忍は、紬と詩の賭けの話を知った時から、好きになるのは当人次第と言ってくれていた。
紬としては、そういう態度で見守ってくれるのはありがたい。
「ところで忍さん。あなた、イケメンって言葉知ってるの?」
「ええ。詩様から借りたマンガってのに書いてありましたよ。他にも人間の世界の色んなものを見せてもらって、大したものだと驚きましたよ」
忍が感心したように言うと、喜八も大きく頷いた。
「あっしもそうなんですよね。言ってはなんですが、大抵のアヤカシってのは、なんの力も持たない人間なんて興味なし。紬様みたいにアヤカシが見えたり霊力を持ってたりしたら、ちょっかい出したり食いたいって思うやつはいるでしょうけどね」
「でしょうね」
サラリと物騒な言葉が飛び出すが、紬が知っているアヤカシは、まさにそんな奴らだ。
自分たちの姿が見えない人間は歯牙にもかけず、紬のように見える者、つまり霊力のある者とわかると、それを狙ってやって来ていた。
なので正直なところ、この屋敷のアヤカシたちがまともな扱いをしてくれるのにも、最初は驚いたものだ。
「最近じゃ、人間だって案外面白かもって思ってきたんですよね。なので、そう思うきっかけをくれた詩様には感謝してるんですよ」
「ただでさえ、詩様は下の者たちには人気ですからね。だからみんな、本家や他の玉藻の若い衆じゃなくて、詩様のお付きになるのを志願したんですよ」
「本家や、他の玉藻の若い衆?」
ふと、気になる言葉が出てきたので聞いてみる。
「ああ。本家ってのは今のご当主の家で、若い衆は次の玉藻の当主を争う候補者みたいなもん。玉藻の当主ってのは、代々何人もの候補者が競い合って、その中でも一番優れたやつがなるってのが習わしなんですよ」
そういえば、詩もそんなこと言っていた。
月城でも、紬の父親が駆け落ちしてから次の当主が誰になるかで揉めたと聞いたことがあるが、どこの世界でも似たようなことはあるらしい。
「ってことは、その何人もの候補者の中で、詩が一番すごいの?」
「そりゃもう。最初あの人が当主になるって言い出した時は、みんな身の程知らずって笑ったもんだけど、そんな評判を実力でひっくり返したんだから大したもんだ。紬様も、街でゴロツキどもに襲われた時、その力は見たでしょう」
「まあね」
アヤカシの強さの基準がどれほどかは知らないが、ゴロツキどもを苦もなく退散させたのを見ると、詩が相当強い力を持っているというのは間違いないだろう。
「今になって思えば、当主になろうとしたのも、人間と歩み寄ろうとしているのも、母上殿のことがあったからなのかもな」
「母上?」
喜八がしみじみと言うが、紬は何のことだかさっぱりわからない。
だがそこで喜八は、しまったという顔をして、慌てて口を押さえた。
「いけね。その辺のことは、勝手に喋っちゃいけねえって言われてたんだ。紬様、悪いけど、今の話は忘れてくだせぇ」
そんなことを言われると余計に気になるが、ここで尋ねるような無神経さは持っていない。
それに親の話となると、どのみち深く聞くことはできなかったかもしれない。
母。その言葉を聞いただけで、強く心がザワつく。それを抑えるのに必死で、とても尋ねる余裕などなかった。
喜八はそんな紬の心情など知らず、黙ったのを見て、ホッとしたように続ける。
「とりあえず俺から言えるのは、詩様はあなたが来てくれて大層喜んでるってことですよ。紬様だって、詩様と一緒になるのは悪い話じゃないんじゃないですか? さっき言った通りイケメンだし、こんな屋敷の奥方として居座れるんですよ。美味いもんだってたらふく食える」
「大きな家に興味は無いから。確かにご飯は美味しいけど……なんていうか、退屈」
この家に来てから三日。
身の回りのことは、ほとんど忍やその他使用人のアヤカシたちがやってくれている。
そんな生活は楽といえば楽なのだが、何もやることがないというのもある意味では大変だ。
仕方ないので、詩が用意してくれたマンガやゲームで時間を潰していた。
すると、それを聞いた忍や喜八も、気まずそうな顔をする
「その辺は、詩様も心痛めていましたね。新婚なのに、おいたわしい」
「昨日なんて、本当は自分が四六時中構ってやりたいのにと叫んでましたね」
実はこの家に来てからというもの、最初の一日と毎朝起こしに行くのを除いては、詩と顔を合わせることはほとんどなかった。
その理由は、詩の仕事のためだそうだ。
なんでも、本当なら紬が嫁入りしてしばらくは他の者に仕事を任せ、彼は紬にかかりきりになるつもりだったらしい。
しかし、急遽彼抜きではどうにもならない事態が起こり、一日の大部分をそちらに当てることになってしまったそうだ。
「そうですよね。紬様も、せっかく結婚したのに構ってもらえないのでは、不満になるのも当然」
「いや、そうは言ってないから」
いくら退屈だからといって、わざわざ詩に構ってほしいとは思わない。
そう言おうとした時、別の声が割って入ってきた。
「そうかそうか。紬、俺が構ってこないこと、そんなに寂しく思ってたんだ。ごめんね」
「全然違う!」
反射的に大事で叫ぶと、紬はいつの間にやらその場に来ていた詩を、ジトッとした目で見つめた。
平手打ちをくらった頬を赤くしながら、頭を下げる詩。
対して紬は、怒りで頬を赤く染めていた。
「最初、賭けをする時に言ってたわよね。私の嫌がるようなことは絶対にしないって」
「ごめんなさい」
シュンと俯いて、ガックリと肩を落とす詩。
それを見て、紬も文句を言う口を閉じる。
(言い過ぎた? でも、これは怒っていいわよね。まあ、これ以上強く言う必要もないか)
もういい。そう言って終わりにしようとするが、その前に詩が口を開いた。
「夢の中では、俺たちすっかり仲良くなってたんだ。起きたら目の前に紬の顔があったものだから、ついその続きをしたくなって……」
「どんな夢見てたのよ!」
ますます頬を赤くしながら、アヤカシの世界にセクハラという言葉はあるのだろうかと考える。
そんな二人の言い合いが聞こえたのか、いつの間にか部屋の前には何体ものアヤカシが集まっていた。
「なんだ、詩様が押し倒そうとして怒らせたのか?」
「と言っても、奥方だろう。やってダメということはあるまい」
「夫婦と言っても、形だけのものだからな」
「なに言ってるんだい。たとえ本当の夫婦だって、無理強いなんて許されるわけないじゃないか」
この屋敷のアヤカシたちは、二人が形だけの夫婦であることも、紬が詩を好きになるかという賭けのことも知っている。
そのこともあって面白おかしく話しているが、紬としては全く面白くない。
「もういいわ。起きたんだから、私の仕事はこれで終わりでしょ」
これ以上あれこれ言われるのはごめんだ。
さっさと部屋から出ていこうとするが、そこで詩が呼び止める。
「待って、紬。起こしてくれて、ありがとう」
「あなたが頼んだんでしょ」
「それを引き受けてくれたのは紬だよ。嫌なら断ればいいんだもの」
「ああ、その手があったわね」
ハッとしたように、足を止める紬。
すると詩は、途端に慌て出す。
「ちょっと待って。まさか、明日からはもう起こさないなんてことないよね?」
「だって、起こしたらまた無理やり抱きしめられるかもしれないじゃない」
「明日からはしないから。次抱きしめるのは、紬が俺を好きになった時にするから」
「来ないわよ、そんな時」
「とにかくお願い。朝一番に紬の顔が見たいんだよ」
結局、詩があまりにも頼むものだから、明日からもこれまでと同じように起こすことになった。
そうして今度こそ部屋を出るが、なんだかすごく疲れたような気がする。
「なんで私、こんなことしているんだろう?」
詩と夫婦になったから。
そう言ってしまえばそれまでなのだが、想像していたアヤカシ相手の嫁入りとは、まるで違う。
しかし、ただ霊力を得るための餌として扱われるのを思うと、遥かにマシではあるのだ。
「しっかし、なんだかんだで明日からも起こしに行くつもりみたいだし、本当は紬様も満更じゃないんじゃないですかい?」
そう言って笑うのは、屋敷の使用人の喜八だ。緑の体に頭に皿を持つアヤカシ。要は河童だ。
「なに言ってるんですか?」
「だってうちの詩様、人間から見ても相当な男前じゃないですか。そんな人にあんなに好き好き言われたら、悪い気はしないんじゃないんですか?」
「あんな軽い調子で軽々好きって言われて、本気になれるわけないでしょ」
良い扱いをしてもらっていることには、正直なところ感謝はしている。
しかしだからといって、詩のことを好きになるかというと、全くの別問題だ。
「そうですよ喜八さん。女心は複雑なんですからね」
「なんだよ忍。お前、詩様の恋路が上手くいかなくてもいいのかよ?」
「もちろん私だって、詩様には幸せになってほしいですよ。けどね、いくら男前だろうとイケメンだろうと、好いた惚れたってのは当人の気持ち次第なんですから。他人が口出しするのは野暮ってもんですよ」
忍は、紬と詩の賭けの話を知った時から、好きになるのは当人次第と言ってくれていた。
紬としては、そういう態度で見守ってくれるのはありがたい。
「ところで忍さん。あなた、イケメンって言葉知ってるの?」
「ええ。詩様から借りたマンガってのに書いてありましたよ。他にも人間の世界の色んなものを見せてもらって、大したものだと驚きましたよ」
忍が感心したように言うと、喜八も大きく頷いた。
「あっしもそうなんですよね。言ってはなんですが、大抵のアヤカシってのは、なんの力も持たない人間なんて興味なし。紬様みたいにアヤカシが見えたり霊力を持ってたりしたら、ちょっかい出したり食いたいって思うやつはいるでしょうけどね」
「でしょうね」
サラリと物騒な言葉が飛び出すが、紬が知っているアヤカシは、まさにそんな奴らだ。
自分たちの姿が見えない人間は歯牙にもかけず、紬のように見える者、つまり霊力のある者とわかると、それを狙ってやって来ていた。
なので正直なところ、この屋敷のアヤカシたちがまともな扱いをしてくれるのにも、最初は驚いたものだ。
「最近じゃ、人間だって案外面白かもって思ってきたんですよね。なので、そう思うきっかけをくれた詩様には感謝してるんですよ」
「ただでさえ、詩様は下の者たちには人気ですからね。だからみんな、本家や他の玉藻の若い衆じゃなくて、詩様のお付きになるのを志願したんですよ」
「本家や、他の玉藻の若い衆?」
ふと、気になる言葉が出てきたので聞いてみる。
「ああ。本家ってのは今のご当主の家で、若い衆は次の玉藻の当主を争う候補者みたいなもん。玉藻の当主ってのは、代々何人もの候補者が競い合って、その中でも一番優れたやつがなるってのが習わしなんですよ」
そういえば、詩もそんなこと言っていた。
月城でも、紬の父親が駆け落ちしてから次の当主が誰になるかで揉めたと聞いたことがあるが、どこの世界でも似たようなことはあるらしい。
「ってことは、その何人もの候補者の中で、詩が一番すごいの?」
「そりゃもう。最初あの人が当主になるって言い出した時は、みんな身の程知らずって笑ったもんだけど、そんな評判を実力でひっくり返したんだから大したもんだ。紬様も、街でゴロツキどもに襲われた時、その力は見たでしょう」
「まあね」
アヤカシの強さの基準がどれほどかは知らないが、ゴロツキどもを苦もなく退散させたのを見ると、詩が相当強い力を持っているというのは間違いないだろう。
「今になって思えば、当主になろうとしたのも、人間と歩み寄ろうとしているのも、母上殿のことがあったからなのかもな」
「母上?」
喜八がしみじみと言うが、紬は何のことだかさっぱりわからない。
だがそこで喜八は、しまったという顔をして、慌てて口を押さえた。
「いけね。その辺のことは、勝手に喋っちゃいけねえって言われてたんだ。紬様、悪いけど、今の話は忘れてくだせぇ」
そんなことを言われると余計に気になるが、ここで尋ねるような無神経さは持っていない。
それに親の話となると、どのみち深く聞くことはできなかったかもしれない。
母。その言葉を聞いただけで、強く心がザワつく。それを抑えるのに必死で、とても尋ねる余裕などなかった。
喜八はそんな紬の心情など知らず、黙ったのを見て、ホッとしたように続ける。
「とりあえず俺から言えるのは、詩様はあなたが来てくれて大層喜んでるってことですよ。紬様だって、詩様と一緒になるのは悪い話じゃないんじゃないですか? さっき言った通りイケメンだし、こんな屋敷の奥方として居座れるんですよ。美味いもんだってたらふく食える」
「大きな家に興味は無いから。確かにご飯は美味しいけど……なんていうか、退屈」
この家に来てから三日。
身の回りのことは、ほとんど忍やその他使用人のアヤカシたちがやってくれている。
そんな生活は楽といえば楽なのだが、何もやることがないというのもある意味では大変だ。
仕方ないので、詩が用意してくれたマンガやゲームで時間を潰していた。
すると、それを聞いた忍や喜八も、気まずそうな顔をする
「その辺は、詩様も心痛めていましたね。新婚なのに、おいたわしい」
「昨日なんて、本当は自分が四六時中構ってやりたいのにと叫んでましたね」
実はこの家に来てからというもの、最初の一日と毎朝起こしに行くのを除いては、詩と顔を合わせることはほとんどなかった。
その理由は、詩の仕事のためだそうだ。
なんでも、本当なら紬が嫁入りしてしばらくは他の者に仕事を任せ、彼は紬にかかりきりになるつもりだったらしい。
しかし、急遽彼抜きではどうにもならない事態が起こり、一日の大部分をそちらに当てることになってしまったそうだ。
「そうですよね。紬様も、せっかく結婚したのに構ってもらえないのでは、不満になるのも当然」
「いや、そうは言ってないから」
いくら退屈だからといって、わざわざ詩に構ってほしいとは思わない。
そう言おうとした時、別の声が割って入ってきた。
「そうかそうか。紬、俺が構ってこないこと、そんなに寂しく思ってたんだ。ごめんね」
「全然違う!」
反射的に大事で叫ぶと、紬はいつの間にやらその場に来ていた詩を、ジトッとした目で見つめた。