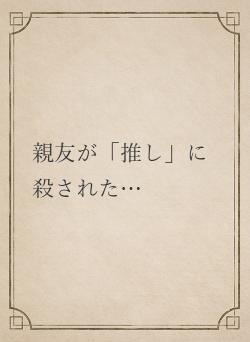お母さんと松崎さんがこれほど喧嘩しているのは見たことがない。
「お母さん、やめてっ!こ、これ以上…喧嘩したら、私たち本当に『家族』じゃなくなっちゃうー」
「瑠璃にとって私は『家族』じゃないんでしょ!赤の他人なんでしょ!いくら瑠璃を大事にしてもいつまでも『家族』って認識されないんでしょ!あの人の元妻だから!瑠璃は…瑠璃は、いつまでもそのことを引きずって…ずっと、ずっと」
「許してよ、お母さん。『家族じゃない』とか言ってごめん。でもさ、お母さんなら分かると思うんだけど、なんか…だれかに、分かってほしいの。よくわからないけど、友達でも、先生でもない、誰か『大切な人』に遭いたいの。だけど、その人が誰なのか、よくわからないの、いや、わかりたくないのかもしれない。もし、その人が、あいつみたいにー『嫌な人』だったら、辛いからっ」
「じゃあ、私は?私は、瑠璃にとってなにものなの?」
「涼花ちゃん、ダメだ。瑠璃ちゃんは、精神を病んでいるんだ。あの、事件のせいで」
私は、おかしいのか。私の心は…狂っているのか。
「違う!瑠璃はおかしくなんかない!全部、私のせい…私のせいなの!だから、私は大丈夫だから」
思いきりお母さんを引っぱたいた。
「お母さん、もう言わないって言ったよね?約束したよね?あいつと離婚した時に、もう言わないって言ったでしょ!」
「ごめんなさい…ごめんなさい…ごめんなさい」
「これ以上、言わないであげて」
松崎さんが、お母さんをかばう。でも、少しも嬉しくない。
「瑠璃の心は、きれいなの。繊細で怒りっぽくて、それでもきれいなの。ー瑠璃って名前は、私が考えたの」
「そ、そうなの?」
「青く澄んだ綺麗な心を持っているから、瑠璃なの。別に、可愛い名前だからとか、そういう理由じゃない。」
沈黙が流れる。
「瑠璃色の地球って、美しいじゃない。だから、瑠璃の心は美しいの」
何を言っているのか意味が分からない。でも、必死に、もがきながら生きている私を思い浮かべた。
怪獣でも何でもない。私は、人間だ。ただ、必死に生きているだけの。
「生きてきた瑠璃を、『汚い』っていう奴がいるなら許さない。絶対に、許さない。」
お母さんは、言い切った。お母さんが言っていることが正しいとは思わない。
人間は汚い。私も同じように汚い。素直で、まっすぐな女の子ではない。
私は、『家族』というものを知らない、愛に餓えた汚い女の子だ。
そんな私を、「美しい」といってくれる人はいるのか。
いや、いる。ここに、確実に一人、いる。
こんな私を、確実に愛してくれる人が、いるんだ。
その人を私は『家族』と言えなかった。とてもみっともない。
私は、自分で『愛』というものを隠していたんだ。その『哀』が嘘だと知ったら、辛いから。
自分が、ずっと可哀そうだったんだ。
そのことに気づいた瞬間、私の心は舞い上がった。
「お母さん、やめてっ!こ、これ以上…喧嘩したら、私たち本当に『家族』じゃなくなっちゃうー」
「瑠璃にとって私は『家族』じゃないんでしょ!赤の他人なんでしょ!いくら瑠璃を大事にしてもいつまでも『家族』って認識されないんでしょ!あの人の元妻だから!瑠璃は…瑠璃は、いつまでもそのことを引きずって…ずっと、ずっと」
「許してよ、お母さん。『家族じゃない』とか言ってごめん。でもさ、お母さんなら分かると思うんだけど、なんか…だれかに、分かってほしいの。よくわからないけど、友達でも、先生でもない、誰か『大切な人』に遭いたいの。だけど、その人が誰なのか、よくわからないの、いや、わかりたくないのかもしれない。もし、その人が、あいつみたいにー『嫌な人』だったら、辛いからっ」
「じゃあ、私は?私は、瑠璃にとってなにものなの?」
「涼花ちゃん、ダメだ。瑠璃ちゃんは、精神を病んでいるんだ。あの、事件のせいで」
私は、おかしいのか。私の心は…狂っているのか。
「違う!瑠璃はおかしくなんかない!全部、私のせい…私のせいなの!だから、私は大丈夫だから」
思いきりお母さんを引っぱたいた。
「お母さん、もう言わないって言ったよね?約束したよね?あいつと離婚した時に、もう言わないって言ったでしょ!」
「ごめんなさい…ごめんなさい…ごめんなさい」
「これ以上、言わないであげて」
松崎さんが、お母さんをかばう。でも、少しも嬉しくない。
「瑠璃の心は、きれいなの。繊細で怒りっぽくて、それでもきれいなの。ー瑠璃って名前は、私が考えたの」
「そ、そうなの?」
「青く澄んだ綺麗な心を持っているから、瑠璃なの。別に、可愛い名前だからとか、そういう理由じゃない。」
沈黙が流れる。
「瑠璃色の地球って、美しいじゃない。だから、瑠璃の心は美しいの」
何を言っているのか意味が分からない。でも、必死に、もがきながら生きている私を思い浮かべた。
怪獣でも何でもない。私は、人間だ。ただ、必死に生きているだけの。
「生きてきた瑠璃を、『汚い』っていう奴がいるなら許さない。絶対に、許さない。」
お母さんは、言い切った。お母さんが言っていることが正しいとは思わない。
人間は汚い。私も同じように汚い。素直で、まっすぐな女の子ではない。
私は、『家族』というものを知らない、愛に餓えた汚い女の子だ。
そんな私を、「美しい」といってくれる人はいるのか。
いや、いる。ここに、確実に一人、いる。
こんな私を、確実に愛してくれる人が、いるんだ。
その人を私は『家族』と言えなかった。とてもみっともない。
私は、自分で『愛』というものを隠していたんだ。その『哀』が嘘だと知ったら、辛いから。
自分が、ずっと可哀そうだったんだ。
そのことに気づいた瞬間、私の心は舞い上がった。