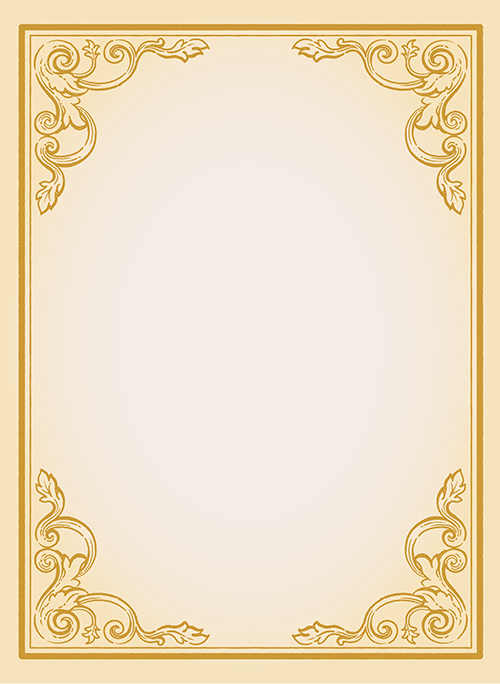その日、白石家の中庭には、藍色の天幕が張られていた。石の共鳴を確かめる〈選定の儀〉──貴族の家々では、年に一度、契約者たちの力量を測るための場が設けられる。
綾乃は、紫水晶の髪飾りをつけて天幕の中心に立っていた。 その佇まいだけで、人々の目を引いた。涼しげな瞳、きりりと結ばれた唇。
「白石綾乃。紫水晶との共鳴、試みます」
その声とともに、彼女の背後に立つ石台の上の紫水晶が、ふわりと淡紫の光を放った。そして、鈴の音にも似た、心地よい音色が響く。
貴族たちの間に、どよめきが広がった。完全共鳴の証。
「さすが……」「あれが紫水晶の選んだ娘か」
綾乃は軽く一礼し、視線を翠に向けた。そのまなざしは、冷たく、静かだった。
「次。白石翠」
名を呼ばれ、翠はびくりと肩を揺らした。 足元がおぼつかない。
「し、白石翠、翡翠との共鳴……参ります……」
緊張で指が震える。袖の内に忍ばせた翡翠を石台に乗せた。
だが、何も起こらない。
静寂が落ちた。 風すらも止まったようだった。
──そして、くすり、と誰かが笑った。
「またか……」「やっぱり落ちこぼれだ」
その声に、翠の指先がわずかに強ばる。
そのとき。
天幕の隅、蒼真がふと前へ出た。
「彼女の石に、触れても?」
周囲がざわつく。
「瑠璃小路殿……何を……?」
翠が慌てて首を横に振る。
「い、いけません、そんな──」
だが蒼真は、静かに微笑んで彼女の翡翠に手を添えた。
その瞬間だった。
淡い光が、彼の指先から翡翠へ流れ込む。 翡翠が応えるように、まばゆい翠の光を放つ。
──共鳴。
ざわめきが、今度は驚きに変わった。
「今のは……」「まさか、瑠璃と翡翠が……?」
翠はただ、呆然とその光を見つめていた。 胸の奥が、震えていた。
夜。
灯りを落とした部屋の片隅で、翠はじっと、翡翠を手のひらに乗せていた。
昼間の光景が、まだ胸の奥でざわめいている。 蒼真が、自分の石に触れた。 そして、翡翠が応えた。
あれは幻だったのだろうか。 それとも──
「……おまえ」
かすかに、声が聞こえた気がした。
翠は息をのむ。 手のひらの翡翠が、ほんの少し、温かい。
「おまえは、なぜ、怯える……」
それは、誰の声でもなかった。しかし、翡翠が語りかけているようだった。
翠はそっと、石を胸に引き寄せる。
「……わからないの。怖いのよ。私は、ずっと……」
翡翠は沈黙した。
その代わり、翠の胸の奥に柔らかな揺れが残った。 それは、目覚めの気配だった。
*
翌日も、蒼真は白石家の離れを訪れた。
形式上は、選定の儀の礼を述べに来たということになっていたが、それが口実であることは、翠にも何となくわかっていた。
離れの庭先に座った蒼真は、静かに湯呑を手に取り、ひと口だけ茶を含んだ。
「昨日の君の顔、忘れられなかったんだ。袖を直そうとして草履を脱いで、転んで、目を見開いて……」
その横顔は笑っていたが、どこか乾いていた。見た目の柔らかさとは裏腹に、その瞳には凍った湖のような静寂がある。
「……お恥ずかしいところを、お見せしました」
翠がぽつりと呟くと、蒼真は一瞬だけ目を見開いた。 そして、ふと目を細める。
「いや。君のおかげで、ほんとうに笑えたんだ。あんなふうに笑ったの、いつ以来だろう」
翠は黙ったまま、湯呑を手に取る。手の中の翡翠が、かすかに温かい。
「君の翡翠──まだ、完全には目覚めていない。でも、ちゃんと目を向けてる。君が、自分自身に向き合おうとしたからだ」
「……でも、私は。なにもできなくて。選ばれたのに、ずっと……」
言いかけて、翠は言葉を呑んだ。 しかし蒼真は、ふっと表情を緩めた。
「僕だって、選ばれたことに意味なんて感じてなかった。兄が死んだから、代わりに選ばれただけ。みんな『代替』の僕に期待してる。でも──君と翡翠は、違うよね」
その声に、翡翠が微かに震えた気がした。
「……綺麗なだけの石なら、誰にでも微笑める。けど、翡翠は君を選んだ。迷いがある君を。だからこそ、誰よりも人の痛みに近づける」
蒼真は立ち上がると、翠に背を向けて言った。
「君がどんな姿でも、君の石はちゃんと見てるよ。……僕も、だ」
その背が、庭の青葉のなかへと静かに溶けていった。
残された翠の胸の奥で、翡翠がぽう、と一瞬だけ明るく灯った。
綾乃は、紫水晶の髪飾りをつけて天幕の中心に立っていた。 その佇まいだけで、人々の目を引いた。涼しげな瞳、きりりと結ばれた唇。
「白石綾乃。紫水晶との共鳴、試みます」
その声とともに、彼女の背後に立つ石台の上の紫水晶が、ふわりと淡紫の光を放った。そして、鈴の音にも似た、心地よい音色が響く。
貴族たちの間に、どよめきが広がった。完全共鳴の証。
「さすが……」「あれが紫水晶の選んだ娘か」
綾乃は軽く一礼し、視線を翠に向けた。そのまなざしは、冷たく、静かだった。
「次。白石翠」
名を呼ばれ、翠はびくりと肩を揺らした。 足元がおぼつかない。
「し、白石翠、翡翠との共鳴……参ります……」
緊張で指が震える。袖の内に忍ばせた翡翠を石台に乗せた。
だが、何も起こらない。
静寂が落ちた。 風すらも止まったようだった。
──そして、くすり、と誰かが笑った。
「またか……」「やっぱり落ちこぼれだ」
その声に、翠の指先がわずかに強ばる。
そのとき。
天幕の隅、蒼真がふと前へ出た。
「彼女の石に、触れても?」
周囲がざわつく。
「瑠璃小路殿……何を……?」
翠が慌てて首を横に振る。
「い、いけません、そんな──」
だが蒼真は、静かに微笑んで彼女の翡翠に手を添えた。
その瞬間だった。
淡い光が、彼の指先から翡翠へ流れ込む。 翡翠が応えるように、まばゆい翠の光を放つ。
──共鳴。
ざわめきが、今度は驚きに変わった。
「今のは……」「まさか、瑠璃と翡翠が……?」
翠はただ、呆然とその光を見つめていた。 胸の奥が、震えていた。
夜。
灯りを落とした部屋の片隅で、翠はじっと、翡翠を手のひらに乗せていた。
昼間の光景が、まだ胸の奥でざわめいている。 蒼真が、自分の石に触れた。 そして、翡翠が応えた。
あれは幻だったのだろうか。 それとも──
「……おまえ」
かすかに、声が聞こえた気がした。
翠は息をのむ。 手のひらの翡翠が、ほんの少し、温かい。
「おまえは、なぜ、怯える……」
それは、誰の声でもなかった。しかし、翡翠が語りかけているようだった。
翠はそっと、石を胸に引き寄せる。
「……わからないの。怖いのよ。私は、ずっと……」
翡翠は沈黙した。
その代わり、翠の胸の奥に柔らかな揺れが残った。 それは、目覚めの気配だった。
*
翌日も、蒼真は白石家の離れを訪れた。
形式上は、選定の儀の礼を述べに来たということになっていたが、それが口実であることは、翠にも何となくわかっていた。
離れの庭先に座った蒼真は、静かに湯呑を手に取り、ひと口だけ茶を含んだ。
「昨日の君の顔、忘れられなかったんだ。袖を直そうとして草履を脱いで、転んで、目を見開いて……」
その横顔は笑っていたが、どこか乾いていた。見た目の柔らかさとは裏腹に、その瞳には凍った湖のような静寂がある。
「……お恥ずかしいところを、お見せしました」
翠がぽつりと呟くと、蒼真は一瞬だけ目を見開いた。 そして、ふと目を細める。
「いや。君のおかげで、ほんとうに笑えたんだ。あんなふうに笑ったの、いつ以来だろう」
翠は黙ったまま、湯呑を手に取る。手の中の翡翠が、かすかに温かい。
「君の翡翠──まだ、完全には目覚めていない。でも、ちゃんと目を向けてる。君が、自分自身に向き合おうとしたからだ」
「……でも、私は。なにもできなくて。選ばれたのに、ずっと……」
言いかけて、翠は言葉を呑んだ。 しかし蒼真は、ふっと表情を緩めた。
「僕だって、選ばれたことに意味なんて感じてなかった。兄が死んだから、代わりに選ばれただけ。みんな『代替』の僕に期待してる。でも──君と翡翠は、違うよね」
その声に、翡翠が微かに震えた気がした。
「……綺麗なだけの石なら、誰にでも微笑める。けど、翡翠は君を選んだ。迷いがある君を。だからこそ、誰よりも人の痛みに近づける」
蒼真は立ち上がると、翠に背を向けて言った。
「君がどんな姿でも、君の石はちゃんと見てるよ。……僕も、だ」
その背が、庭の青葉のなかへと静かに溶けていった。
残された翠の胸の奥で、翡翠がぽう、と一瞬だけ明るく灯った。