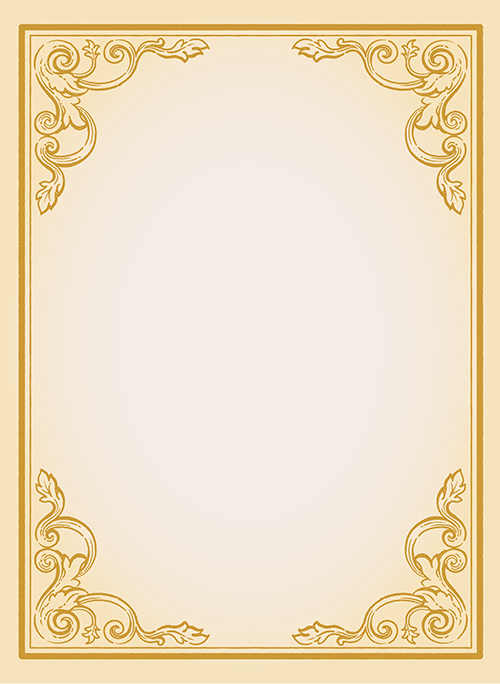白石家の朝は、紫の香りで目を覚ます。だが、翠の胸に沈む翡翠だけは、今日も静かに息を潜めていた──まるで、何かを待ち続けるように。
菖蒲の香を焚きしめた座敷の奥で、姉・綾乃が静かに髪を結っていた。
艶のある黒髪が、すっと一本の線を描くように背に落ちる。
「綾乃お姉さま……おはようございます」
襖の隙間から顔を出した翠は、思わず足を止めた。自分の乱れた裾、はねた髪、色褪せた着物が、座敷の紫とまるで釣り合わない。
綾乃は振り返らない。細い手が紫の紐を器用に操り、最後の結びを作る。美しい蝶々結び。その気高さに、翠の背筋が自然とすくんだ。
「……へらへら笑って、楽しいことでもあった?」
声が冷えた水のように落ちた。
「い、いえ、そんなつもりは──」
「裾。踏んでるわよ」
翠はあわてて足元を見た。片方の袂が草履に絡んでいた。ほどいた途端、裾がばさりとめくれて足首が見えた。
綾乃はちらりとも視線を寄越さず、香を持って立ち上がる。
「お父様のお迎えに、遅れないでね。今日は来客があるのだから。本当にのろま」
「は、はいっ」
返事の勢いで、翠はまた裾を踏んだ。つんのめるようにして座敷から出た彼女の背に、綾乃の吐息がわずかに重なった。
「馬鹿馬鹿しいわ」
その言葉は、菖蒲の香よりも長く、重く、翠の胸に残る。
「……私は、なんでこうなのでしょう」
翠の視界はうっすらと涙で滲んでいた。
*
この世界では、石が人を選ぶ。
誰もが、生まれつきひとつの石と結ばれている。 ほとんどの人は、河原に転がる石のような小さな力しか持たない。
だが、ごくまれに、宝石と呼ばれる存在に選ばれる者がいた。
宝石に選ばれた者は、石の力を引き出し、風を動かし、天を染め、心を読む。そうした者たちは〈契約者〉と呼ばれ、この国の支配階級となってゆく。
紫水晶に選ばれた綾乃は、家の誉れだった。 そして翡翠に選ばれた翠は──家の恥だった。
石は力をくれるが、従わせるには心が要る。 翡翠は翠の手にあるのに、何も語らない。何も応えない。
それでも、翠は心のどこかで信じていた。 この石は、きっと何かを知っている。 ──自分と、同じように、迷っているのだと。
だから今日もまた、袖の内側に翡翠を忍ばせて、翠は歩き出す。 誰にも届かない祈りを胸に秘めながら。
*
朝靄のなかに、馬車の車輪が軋む音が響いた。
白石家の門に、瑠璃小路家の紋が描かれた馬車が止まる。
翠は玄関の柱陰に身を寄せていた。
姉の綾乃はもう正装を整え、紫の帯を絞めて立っている。横に立つ翠の着物は、数年前の綾乃のお下がりだ。
着付けでいくら工夫しても、裾が長すぎる。
何度も踏んでしまい、そのたびに母の眉がぴくりと動いた。
「ご挨拶だけは、失礼のないように」
小声で母が言い、翠はこくこくと何度も頷いた。
門が開く。 ゆっくりと馬車の扉が開かれた。
降り立ったのは、青みを帯びた黒髪の青年だった。瑠璃小路家当主・蒼真。
深い青の礼装。すらりとした長身に、紋章のついた上衣を纏っている。
そして、彼が翠を見た。
「……君、袖が逆だよ」
瞬間、翠の顔が真っ赤になった。
「あっ、えっ、す、すみません……!すぐに直します……っ」
もたもたと袖を直す間に、草履が脱げ、よろけて石畳に手をつく。
「あっ、わわわ……!」
そのとき、静かに笑い声が落ちた。
「君は……なんて面白い子なんだろう」
顔を上げた翠の瞳に、青年の笑顔が映った。
だがその笑顔は、どこか壊れたように儚くて。
胸元に隠していた翡翠が、かすかに光った。
──はじめて、震えた。
菖蒲の香を焚きしめた座敷の奥で、姉・綾乃が静かに髪を結っていた。
艶のある黒髪が、すっと一本の線を描くように背に落ちる。
「綾乃お姉さま……おはようございます」
襖の隙間から顔を出した翠は、思わず足を止めた。自分の乱れた裾、はねた髪、色褪せた着物が、座敷の紫とまるで釣り合わない。
綾乃は振り返らない。細い手が紫の紐を器用に操り、最後の結びを作る。美しい蝶々結び。その気高さに、翠の背筋が自然とすくんだ。
「……へらへら笑って、楽しいことでもあった?」
声が冷えた水のように落ちた。
「い、いえ、そんなつもりは──」
「裾。踏んでるわよ」
翠はあわてて足元を見た。片方の袂が草履に絡んでいた。ほどいた途端、裾がばさりとめくれて足首が見えた。
綾乃はちらりとも視線を寄越さず、香を持って立ち上がる。
「お父様のお迎えに、遅れないでね。今日は来客があるのだから。本当にのろま」
「は、はいっ」
返事の勢いで、翠はまた裾を踏んだ。つんのめるようにして座敷から出た彼女の背に、綾乃の吐息がわずかに重なった。
「馬鹿馬鹿しいわ」
その言葉は、菖蒲の香よりも長く、重く、翠の胸に残る。
「……私は、なんでこうなのでしょう」
翠の視界はうっすらと涙で滲んでいた。
*
この世界では、石が人を選ぶ。
誰もが、生まれつきひとつの石と結ばれている。 ほとんどの人は、河原に転がる石のような小さな力しか持たない。
だが、ごくまれに、宝石と呼ばれる存在に選ばれる者がいた。
宝石に選ばれた者は、石の力を引き出し、風を動かし、天を染め、心を読む。そうした者たちは〈契約者〉と呼ばれ、この国の支配階級となってゆく。
紫水晶に選ばれた綾乃は、家の誉れだった。 そして翡翠に選ばれた翠は──家の恥だった。
石は力をくれるが、従わせるには心が要る。 翡翠は翠の手にあるのに、何も語らない。何も応えない。
それでも、翠は心のどこかで信じていた。 この石は、きっと何かを知っている。 ──自分と、同じように、迷っているのだと。
だから今日もまた、袖の内側に翡翠を忍ばせて、翠は歩き出す。 誰にも届かない祈りを胸に秘めながら。
*
朝靄のなかに、馬車の車輪が軋む音が響いた。
白石家の門に、瑠璃小路家の紋が描かれた馬車が止まる。
翠は玄関の柱陰に身を寄せていた。
姉の綾乃はもう正装を整え、紫の帯を絞めて立っている。横に立つ翠の着物は、数年前の綾乃のお下がりだ。
着付けでいくら工夫しても、裾が長すぎる。
何度も踏んでしまい、そのたびに母の眉がぴくりと動いた。
「ご挨拶だけは、失礼のないように」
小声で母が言い、翠はこくこくと何度も頷いた。
門が開く。 ゆっくりと馬車の扉が開かれた。
降り立ったのは、青みを帯びた黒髪の青年だった。瑠璃小路家当主・蒼真。
深い青の礼装。すらりとした長身に、紋章のついた上衣を纏っている。
そして、彼が翠を見た。
「……君、袖が逆だよ」
瞬間、翠の顔が真っ赤になった。
「あっ、えっ、す、すみません……!すぐに直します……っ」
もたもたと袖を直す間に、草履が脱げ、よろけて石畳に手をつく。
「あっ、わわわ……!」
そのとき、静かに笑い声が落ちた。
「君は……なんて面白い子なんだろう」
顔を上げた翠の瞳に、青年の笑顔が映った。
だがその笑顔は、どこか壊れたように儚くて。
胸元に隠していた翡翠が、かすかに光った。
──はじめて、震えた。