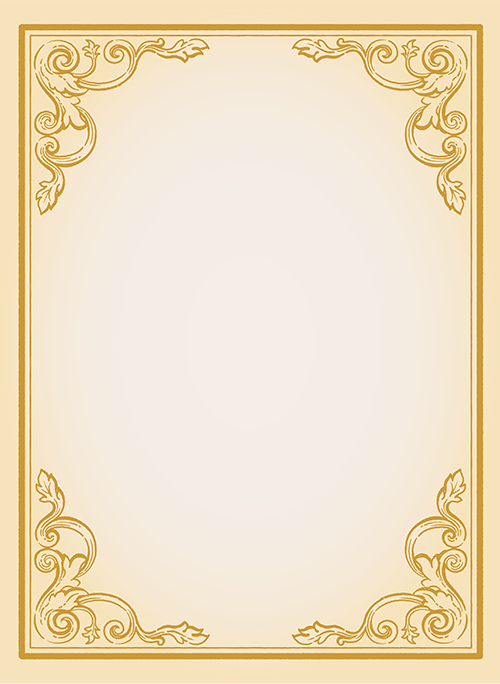花宴の日──
年に一度、花々の精霊にその加護を仰ぎ、今代の花巫女を選ぶ神事、花宴。
庭園は牡丹、芍薬、藤の垣に彩られ、名家の娘たちが花の加護を競う。艶やかな香が春の空気を満たす中、ひときわ輝いていたのは──撫子。
白百合を模した刺繍のドレス、柔らかな栗色の髪をふわりと結い上げた姿に、客人たちの称賛の声が絶えなかった。
「まあ、あれが撫子さま。噂どおりね」 「本当にお美しいわ……」
その隣に、静かな影がひとつ。
──紫乃。
色褪せた古布の着物に、飾り気のない髪型。だが、その眼差しには静かな決意が宿っていた。
(お母様……どうか、見ていてください)
祈るように目を伏せ、紫乃はしずしずと庭の奥へと歩を進めた。
そのとき。
銀の靴音が響く。 現れたのは、藤真。軍装に身を包み、漆黒の髪を後ろで束ねた青年。
詰め襟の制帽の影から覗く藤色の眼差しが、まっすぐに紫乃を見つめていた。
撫子の微笑が、揺らいだ。
──ここからが、選定の本番である。
庭園の中央には、ふたつの黒檀の杭が立ち、純白のしめ縄が張られていた。
このしめ縄を花精の力で断ち切ること──それが、神に選ばれし花巫女の証となる。
巫女長が神木の枝を手に、祭壇の前へと進み出る。
「これより、花精の顕現の儀を執り行います。御身に精霊が宿りし者あらば、その証を、この場にて示しなさい」
その言葉とともに、庭に静寂が降りた。
最初に進み出たのは、撫子だった。
華やかな白百合の刺繍が眩しい衣の裾を翻し、彼女は堂々と庭園の中央へ歩み出る。
指先をそっと胸元にあて、目を閉じる。
その場の誰もが息を呑む中、撫子は囁いた。
「花精よ。どうか、あなたの光を……」
しかし、しめ縄は、ぴくりとも動かない。
木々も花も、ただ風に揺れるばかり。
ざわ……と、観衆の間に微かな波が走った。
撫子は、もう一度、声を重ねる。
「『撫子』の花精……私を、お忘れになったのですか……?」
焦りの色が浮かぶ。完璧な微笑が崩れ、唇が震えた。
足元に、はらりと花びらが落ちる。撫子はそれに手を伸ばしかけ──途中でその手を握り締めた。
やがて巫女長が、静かに首を横に振る。
その仕草は、何よりも重たかった。
「……次の方」
撫子は、踵を返すことができなかった。
その場に立ち尽くしたまま、誰の目も合わさず、空ろな足取りで一礼すると、よろめくように人々の間へと戻っていった。
そのとき。紫乃は、庭の隅にて小さく息を吐いた。
「紫苑よ……私に、力を」
刹那、冷たく鋭い風が天地を貫いた。
藤の花がざわめき、空へ舞う中、紫の光が天を裂 く。
雷鳴のような衝撃が庭を揺らし、紫乃の背に紫苑の花精が顕れた。
だがその姿は、もはや「花精」と呼ぶにはあまりに異形だった。
漆黒と紫の甲冑を纏い、背に花弁の後光を差す戦神の姿。瞳には冷徹と慈悲が宿り、紫苑の香が辺りを満たした。
「あれは……!」
誰かの震える声が空気を裂く。
藤真は目を見張り、撫子は凍りついた。
戦神はゆっくりと歩を進め、白きしめ縄の前に立つ。
そして──
彼の指先が、虚空をひと撫でした。
轟。空気が裂ける。
花吹雪のように紫の花弁が渦巻くなか、しめ縄は真っ二つに断ち切られた。
その瞬間、地面がうねり、中央にひびが走る。
それは、神の力にこの地が耐えられなかった証だった。
人々が息を呑み、誰もが声を失った。
紫乃は、ゆっくりと目を閉じた。その肩に、彼の手が添えられる。花精の祝福であり──神の裁きであった。
「……見ていてくれたのですね」
紫乃の呟きに応えるように、花精は一度だけ頷き、すう……と紫の光と共に、その身を紫乃の内奥へと融かしていった。
地に残ったのは、圧倒的な沈黙と、選ばれし者にのみ宿る神意の気配。
巫女長が、深く頭を垂れた。
「──紫乃さま。
あなたこそ、神に選ばれし花巫女でございます」
静寂。
それは、あまりに美しく、そして──
撫子にとっては、残酷な瞬間だった。
「……なんで、姉さまなの?」
撫子の声は、最初はかすれた囁きだった。
しかし、次第に震えを帯び、爪を握り込んだ手が白くなるほどに、憎悪が膨れ上がっていく。
「姉さまなんか……ただの日陰のみすぼらしい雑草でしょ!」
庭の空気が揺らいだ。
令嬢たちが息を呑み、女中たちも顔を見合わせる。
「雑草でも根を張るのが、花です」
紫乃は静かに答えた。俯かず、怯えもせず。
ただ、まっすぐに撫子を見ていた。
その瞳には、憐れみがあった。
「撫子。あなたの目は美しいけれど、何も見ていなかったのですね」
静かな声が、風のように届く。
「神を信じ、寝食も忘れて祈ったこと。あなたに、一度でも、あったでしょうか?」
撫子の笑顔が、わずかに引きつった。
その言葉は刃のように淡々としていた。しかし容赦なく、撫子の胸に突き立った。
「っ、ちがう……私のほうが、ふさわしいはずよ……っ、私のほうが……皆に愛されて──!」
撫子が叫んだ、そのときだった。
花弁は、刃のように飛んだ。
空気を裂き、風を纏いながら。
一閃。
「……っ!」
撫子の袖口が、裂けた。絹の生地が音もなくほつれ、白い肌が露わになる。
花弁はそのまま、まっすぐ撫子の背後へと飛んでいく。
ひと息ののち。
背後の大木が、縦に割れた。木は呻きもせず、音もなく、崩れ落ちた。
誰も声を上げなかった。
紫乃は、ひとつも動じていなかった。静かに、ただそこに立ち尽くしていた。
その背には、淡く光る紫苑の花精が、ふわりと揺れていた。
そして紫乃は、最後にひとこと、告げる。
「……花精は、真を見ています」
紫乃の声音は、あまりに優しかった。
同時に、もう一人の男の影が静かに歩み寄った。
「香りをまとうだけで、根を張らなかった花は、すぐに枯れてしまうのですよ」
──藤真。
黒の礼装に身を包んだその姿は、まるで闇夜を切り裂くように冴えていた。
彼の足音が、ひとつ、またひとつと刻まれていく。
視線が彼を追う。
誰もが、何かが起こると直感していた。
藤真は、壇の下で立ち止まり、紫乃を見つめる。その瞬間、彼女の胸はどくんと打った。
彼は一歩進み出て、跪く。
「紫乃さん」
その名を、誰よりもまっすぐな声で呼んだ。
「──君を、我が伴侶として迎えたい」
時が止まったような静寂が、場を包んだ。
紫乃は、答えられなかった。震える唇に、言葉が宿らなかった。それでも、心は答えていた。
(この人は……私の、花を見つけてくれた)
撫子は、藤真の前へ一歩踏み出した。その目には涙が滲み、声は震えていた。
「ちがうわ……なにかの、間違いでしょう? あなたが愛すべきは私よ……私のほうが、ずっと相応しいはず……!」
揺らめく声が、必死に縋る。
彼の袖に手を伸ばしかけたその瞬間──
藤真の瞳が、ぴたりと撫子を射抜いた。
「君は、花ではなかった。香りだけをまとい、土にも根を張らず、精霊にも祈らなかった。──空虚だ」
その声に呼応するように、藤真の背後に紫の風が立つ。
空中に藤の花が舞い落ち、やがて一本の巨大な蔓が、彼の背から立ちのぼるように現れた。
それは藤の花精──神の気配を帯びた、静謐でありながら威圧的な存在。
撫子の息が止まり、足元がぐらりと崩れそうになる。誰かが駆け寄ろうとしたが──藤真が右手を挙げて、制した。
紫乃の目に、ほんの少し涙が滲んだ。
(わたしは……ようやく、ここに立てたのだ)
そう思ったとき、紫苑の香りが、すうっと風に漂った。それは── 誇りある花の、静かな香りだった。
「──神の御意により、紫乃さまを今代の花巫女と定めます」
巫女長の宣言が、庭に静かに響いた。
祝詞が奏上され、白い花弁が空から舞い落ちる。
その花弁は、どれも藤や紫苑のような薄紫で──
まるで花精が紫乃に、静かに祝福を与えているようだった。
紫乃は深く頭を垂れ、手を重ね、祈りの姿勢を取った。
その所作はたおやかで、しかし芯の通ったものだった。
(お母様……わたし、ようやく……)
亡き母の姿が脳裏に浮かぶ。
静かで、優しく、けれどどこまでも気高い女性だった。
あのひとの娘として、今ここに立てたことが、紫乃のすべてだった。
だが、その背後で。
「……嘘よ……こんなの、夢に決まってる……!」
撫子は肩を震わせながら、庭の片隅で膝をついていた。
誰も、彼女に手を差し伸べない。
これまで撫子を褒めそやしてきた令嬢たちは、静かに目をそらし、女中たちも口を閉ざしたままだった。
撫子の世界から、音が消えていく。
彼女の手の中で、いつも香り高く整えていたレースの扇子が、地面に落ちていた。
藤真の視線も、もうそこにはなかった。
撫子は歯を噛みしめ、顔をゆがめて叫ぶ。ひとひらの紫苑の花弁を、握りつぶしながら。
「あなたなんか、ただの、ただの……っ、草のくせにっ!」
その声に誰かが息を呑み、誰かが眉をひそめた。
「まだ……終わらない。私にも、力があるはず……!」
撫子の手のひらににじむように現れたのは──黒い光。それは光ではなく、闇を孕む濁流のようだった。彼女の怒りに呼応し、掌から這うようにうごめいている。
花精の憐れみか、それとも──それすら偽る、何か邪なるものか。
紫乃は、もう振り返らなかった。
背筋を伸ばし、花巫女としての道を歩み始めていた。
(わたしは、わたしのままで──)
その背に、薄紫の光がふたたび、やわらかく灯る。それは、撫子には見えない花精の光だった。
陽が傾き、庭に長い影が伸びるころ──
儀はすべて終わり、祝詞も祈祷も静かに収まっていた。
紫乃は一人、神殿の裏手の庭に立っていた。
風に揺れる薄紫の花──紫苑が咲いている。
「忘らるる 身をば思はず……」
低く、落ち着いた声が背後から響いた。
紫乃が振り向くと、そこには藤真がいた。
黒尽くめの軍服に身を包み、凛とした佇まい。
その藤色の瞳は、どこまでも優しく、まっすぐに彼女を見つめていた。
「……あの日のこと、覚えていたのですね?」
紫乃はそっと問いかける。
「古今和歌集を、口ずさんでいただろう。あのとき、あなたは……気丈で、美しかった」
藤真の微笑みは、花弁のように柔らかかった。
「小さな庭で咲く、ひとひらの花が。こんなにも、強く、美しくなるとは。わたしの初恋は、やはり見誤っていなかった」
紫乃は微かに目を見張ったが、やがて、ふっと微笑んだ。
「……あなたは、変わりませんね。あの日と同じ眼差しで、わたしを見てくださる」
「そうだな。変わることができなかった。どれほど時が流れても、君を想う気持ちは、何一つ、褪せなかった」
藤真が一歩、紫乃に近づいた。
「君は、ただの花巫女ではない。神に選ばれし、我が心の唯一だ。この先の人生を……どうか、私と共に」
紫乃は藤真の瞳を見つめ、少しだけ唇を震わせた。
「……わたしなどで、よろしければ。どうか、あなたの隣に立たせてください。光栄すぎる願いであることは、重々承知のうえで」
その声はか細かったが、凛とした芯の強さを秘めていた。
「この上なき誉れ。応じてくれたこと、まことに有難く思う」
「……とんでもございません」
「今度、ともに甘味処へ行こう」
不意に藤真がそう告げたとき、紫乃は思わず目を見張った。それから、ふわりと笑みを咲かせる。
「……本当に、甘いものがお好きなのですね」
藤真もまた、静かに笑った。
そして、彼女の手をそっと包み込む。
「君でなければ、意味がない。
神の声を聞く、その横顔を──誰よりも近くで、見ていたいのだ」
彼の言葉は、まっすぐに心の奥へ届いていく。
彼女は、そっとその手を握り返した。
そして、深く、深く、頭を垂れる。
「……はい」
そのひと言に、揺るぎなき想いが込められていた。
やがてふたりは、ゆるやかに顔を上げる。
夕暮れの空には、淡い藤色の光が静かに滲んでゆく。
かつて見えなかった花がいま、永遠の誓いのもとで咲き誇っていた。
年に一度、花々の精霊にその加護を仰ぎ、今代の花巫女を選ぶ神事、花宴。
庭園は牡丹、芍薬、藤の垣に彩られ、名家の娘たちが花の加護を競う。艶やかな香が春の空気を満たす中、ひときわ輝いていたのは──撫子。
白百合を模した刺繍のドレス、柔らかな栗色の髪をふわりと結い上げた姿に、客人たちの称賛の声が絶えなかった。
「まあ、あれが撫子さま。噂どおりね」 「本当にお美しいわ……」
その隣に、静かな影がひとつ。
──紫乃。
色褪せた古布の着物に、飾り気のない髪型。だが、その眼差しには静かな決意が宿っていた。
(お母様……どうか、見ていてください)
祈るように目を伏せ、紫乃はしずしずと庭の奥へと歩を進めた。
そのとき。
銀の靴音が響く。 現れたのは、藤真。軍装に身を包み、漆黒の髪を後ろで束ねた青年。
詰め襟の制帽の影から覗く藤色の眼差しが、まっすぐに紫乃を見つめていた。
撫子の微笑が、揺らいだ。
──ここからが、選定の本番である。
庭園の中央には、ふたつの黒檀の杭が立ち、純白のしめ縄が張られていた。
このしめ縄を花精の力で断ち切ること──それが、神に選ばれし花巫女の証となる。
巫女長が神木の枝を手に、祭壇の前へと進み出る。
「これより、花精の顕現の儀を執り行います。御身に精霊が宿りし者あらば、その証を、この場にて示しなさい」
その言葉とともに、庭に静寂が降りた。
最初に進み出たのは、撫子だった。
華やかな白百合の刺繍が眩しい衣の裾を翻し、彼女は堂々と庭園の中央へ歩み出る。
指先をそっと胸元にあて、目を閉じる。
その場の誰もが息を呑む中、撫子は囁いた。
「花精よ。どうか、あなたの光を……」
しかし、しめ縄は、ぴくりとも動かない。
木々も花も、ただ風に揺れるばかり。
ざわ……と、観衆の間に微かな波が走った。
撫子は、もう一度、声を重ねる。
「『撫子』の花精……私を、お忘れになったのですか……?」
焦りの色が浮かぶ。完璧な微笑が崩れ、唇が震えた。
足元に、はらりと花びらが落ちる。撫子はそれに手を伸ばしかけ──途中でその手を握り締めた。
やがて巫女長が、静かに首を横に振る。
その仕草は、何よりも重たかった。
「……次の方」
撫子は、踵を返すことができなかった。
その場に立ち尽くしたまま、誰の目も合わさず、空ろな足取りで一礼すると、よろめくように人々の間へと戻っていった。
そのとき。紫乃は、庭の隅にて小さく息を吐いた。
「紫苑よ……私に、力を」
刹那、冷たく鋭い風が天地を貫いた。
藤の花がざわめき、空へ舞う中、紫の光が天を裂 く。
雷鳴のような衝撃が庭を揺らし、紫乃の背に紫苑の花精が顕れた。
だがその姿は、もはや「花精」と呼ぶにはあまりに異形だった。
漆黒と紫の甲冑を纏い、背に花弁の後光を差す戦神の姿。瞳には冷徹と慈悲が宿り、紫苑の香が辺りを満たした。
「あれは……!」
誰かの震える声が空気を裂く。
藤真は目を見張り、撫子は凍りついた。
戦神はゆっくりと歩を進め、白きしめ縄の前に立つ。
そして──
彼の指先が、虚空をひと撫でした。
轟。空気が裂ける。
花吹雪のように紫の花弁が渦巻くなか、しめ縄は真っ二つに断ち切られた。
その瞬間、地面がうねり、中央にひびが走る。
それは、神の力にこの地が耐えられなかった証だった。
人々が息を呑み、誰もが声を失った。
紫乃は、ゆっくりと目を閉じた。その肩に、彼の手が添えられる。花精の祝福であり──神の裁きであった。
「……見ていてくれたのですね」
紫乃の呟きに応えるように、花精は一度だけ頷き、すう……と紫の光と共に、その身を紫乃の内奥へと融かしていった。
地に残ったのは、圧倒的な沈黙と、選ばれし者にのみ宿る神意の気配。
巫女長が、深く頭を垂れた。
「──紫乃さま。
あなたこそ、神に選ばれし花巫女でございます」
静寂。
それは、あまりに美しく、そして──
撫子にとっては、残酷な瞬間だった。
「……なんで、姉さまなの?」
撫子の声は、最初はかすれた囁きだった。
しかし、次第に震えを帯び、爪を握り込んだ手が白くなるほどに、憎悪が膨れ上がっていく。
「姉さまなんか……ただの日陰のみすぼらしい雑草でしょ!」
庭の空気が揺らいだ。
令嬢たちが息を呑み、女中たちも顔を見合わせる。
「雑草でも根を張るのが、花です」
紫乃は静かに答えた。俯かず、怯えもせず。
ただ、まっすぐに撫子を見ていた。
その瞳には、憐れみがあった。
「撫子。あなたの目は美しいけれど、何も見ていなかったのですね」
静かな声が、風のように届く。
「神を信じ、寝食も忘れて祈ったこと。あなたに、一度でも、あったでしょうか?」
撫子の笑顔が、わずかに引きつった。
その言葉は刃のように淡々としていた。しかし容赦なく、撫子の胸に突き立った。
「っ、ちがう……私のほうが、ふさわしいはずよ……っ、私のほうが……皆に愛されて──!」
撫子が叫んだ、そのときだった。
花弁は、刃のように飛んだ。
空気を裂き、風を纏いながら。
一閃。
「……っ!」
撫子の袖口が、裂けた。絹の生地が音もなくほつれ、白い肌が露わになる。
花弁はそのまま、まっすぐ撫子の背後へと飛んでいく。
ひと息ののち。
背後の大木が、縦に割れた。木は呻きもせず、音もなく、崩れ落ちた。
誰も声を上げなかった。
紫乃は、ひとつも動じていなかった。静かに、ただそこに立ち尽くしていた。
その背には、淡く光る紫苑の花精が、ふわりと揺れていた。
そして紫乃は、最後にひとこと、告げる。
「……花精は、真を見ています」
紫乃の声音は、あまりに優しかった。
同時に、もう一人の男の影が静かに歩み寄った。
「香りをまとうだけで、根を張らなかった花は、すぐに枯れてしまうのですよ」
──藤真。
黒の礼装に身を包んだその姿は、まるで闇夜を切り裂くように冴えていた。
彼の足音が、ひとつ、またひとつと刻まれていく。
視線が彼を追う。
誰もが、何かが起こると直感していた。
藤真は、壇の下で立ち止まり、紫乃を見つめる。その瞬間、彼女の胸はどくんと打った。
彼は一歩進み出て、跪く。
「紫乃さん」
その名を、誰よりもまっすぐな声で呼んだ。
「──君を、我が伴侶として迎えたい」
時が止まったような静寂が、場を包んだ。
紫乃は、答えられなかった。震える唇に、言葉が宿らなかった。それでも、心は答えていた。
(この人は……私の、花を見つけてくれた)
撫子は、藤真の前へ一歩踏み出した。その目には涙が滲み、声は震えていた。
「ちがうわ……なにかの、間違いでしょう? あなたが愛すべきは私よ……私のほうが、ずっと相応しいはず……!」
揺らめく声が、必死に縋る。
彼の袖に手を伸ばしかけたその瞬間──
藤真の瞳が、ぴたりと撫子を射抜いた。
「君は、花ではなかった。香りだけをまとい、土にも根を張らず、精霊にも祈らなかった。──空虚だ」
その声に呼応するように、藤真の背後に紫の風が立つ。
空中に藤の花が舞い落ち、やがて一本の巨大な蔓が、彼の背から立ちのぼるように現れた。
それは藤の花精──神の気配を帯びた、静謐でありながら威圧的な存在。
撫子の息が止まり、足元がぐらりと崩れそうになる。誰かが駆け寄ろうとしたが──藤真が右手を挙げて、制した。
紫乃の目に、ほんの少し涙が滲んだ。
(わたしは……ようやく、ここに立てたのだ)
そう思ったとき、紫苑の香りが、すうっと風に漂った。それは── 誇りある花の、静かな香りだった。
「──神の御意により、紫乃さまを今代の花巫女と定めます」
巫女長の宣言が、庭に静かに響いた。
祝詞が奏上され、白い花弁が空から舞い落ちる。
その花弁は、どれも藤や紫苑のような薄紫で──
まるで花精が紫乃に、静かに祝福を与えているようだった。
紫乃は深く頭を垂れ、手を重ね、祈りの姿勢を取った。
その所作はたおやかで、しかし芯の通ったものだった。
(お母様……わたし、ようやく……)
亡き母の姿が脳裏に浮かぶ。
静かで、優しく、けれどどこまでも気高い女性だった。
あのひとの娘として、今ここに立てたことが、紫乃のすべてだった。
だが、その背後で。
「……嘘よ……こんなの、夢に決まってる……!」
撫子は肩を震わせながら、庭の片隅で膝をついていた。
誰も、彼女に手を差し伸べない。
これまで撫子を褒めそやしてきた令嬢たちは、静かに目をそらし、女中たちも口を閉ざしたままだった。
撫子の世界から、音が消えていく。
彼女の手の中で、いつも香り高く整えていたレースの扇子が、地面に落ちていた。
藤真の視線も、もうそこにはなかった。
撫子は歯を噛みしめ、顔をゆがめて叫ぶ。ひとひらの紫苑の花弁を、握りつぶしながら。
「あなたなんか、ただの、ただの……っ、草のくせにっ!」
その声に誰かが息を呑み、誰かが眉をひそめた。
「まだ……終わらない。私にも、力があるはず……!」
撫子の手のひらににじむように現れたのは──黒い光。それは光ではなく、闇を孕む濁流のようだった。彼女の怒りに呼応し、掌から這うようにうごめいている。
花精の憐れみか、それとも──それすら偽る、何か邪なるものか。
紫乃は、もう振り返らなかった。
背筋を伸ばし、花巫女としての道を歩み始めていた。
(わたしは、わたしのままで──)
その背に、薄紫の光がふたたび、やわらかく灯る。それは、撫子には見えない花精の光だった。
陽が傾き、庭に長い影が伸びるころ──
儀はすべて終わり、祝詞も祈祷も静かに収まっていた。
紫乃は一人、神殿の裏手の庭に立っていた。
風に揺れる薄紫の花──紫苑が咲いている。
「忘らるる 身をば思はず……」
低く、落ち着いた声が背後から響いた。
紫乃が振り向くと、そこには藤真がいた。
黒尽くめの軍服に身を包み、凛とした佇まい。
その藤色の瞳は、どこまでも優しく、まっすぐに彼女を見つめていた。
「……あの日のこと、覚えていたのですね?」
紫乃はそっと問いかける。
「古今和歌集を、口ずさんでいただろう。あのとき、あなたは……気丈で、美しかった」
藤真の微笑みは、花弁のように柔らかかった。
「小さな庭で咲く、ひとひらの花が。こんなにも、強く、美しくなるとは。わたしの初恋は、やはり見誤っていなかった」
紫乃は微かに目を見張ったが、やがて、ふっと微笑んだ。
「……あなたは、変わりませんね。あの日と同じ眼差しで、わたしを見てくださる」
「そうだな。変わることができなかった。どれほど時が流れても、君を想う気持ちは、何一つ、褪せなかった」
藤真が一歩、紫乃に近づいた。
「君は、ただの花巫女ではない。神に選ばれし、我が心の唯一だ。この先の人生を……どうか、私と共に」
紫乃は藤真の瞳を見つめ、少しだけ唇を震わせた。
「……わたしなどで、よろしければ。どうか、あなたの隣に立たせてください。光栄すぎる願いであることは、重々承知のうえで」
その声はか細かったが、凛とした芯の強さを秘めていた。
「この上なき誉れ。応じてくれたこと、まことに有難く思う」
「……とんでもございません」
「今度、ともに甘味処へ行こう」
不意に藤真がそう告げたとき、紫乃は思わず目を見張った。それから、ふわりと笑みを咲かせる。
「……本当に、甘いものがお好きなのですね」
藤真もまた、静かに笑った。
そして、彼女の手をそっと包み込む。
「君でなければ、意味がない。
神の声を聞く、その横顔を──誰よりも近くで、見ていたいのだ」
彼の言葉は、まっすぐに心の奥へ届いていく。
彼女は、そっとその手を握り返した。
そして、深く、深く、頭を垂れる。
「……はい」
そのひと言に、揺るぎなき想いが込められていた。
やがてふたりは、ゆるやかに顔を上げる。
夕暮れの空には、淡い藤色の光が静かに滲んでゆく。
かつて見えなかった花がいま、永遠の誓いのもとで咲き誇っていた。