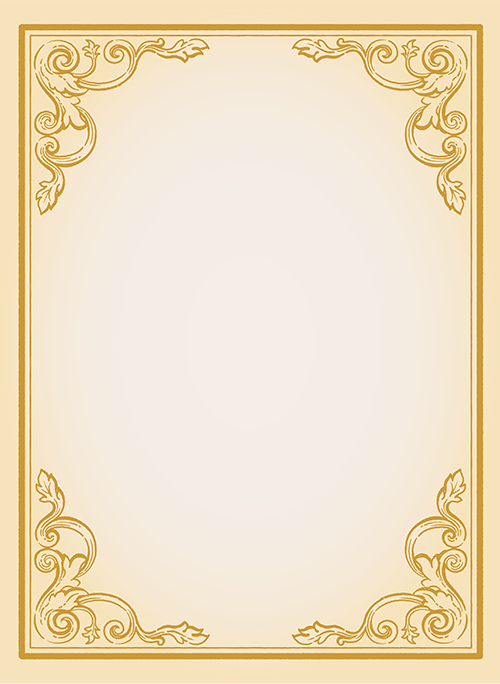──神にさえ、見放されたのかもしれない。
紫乃は、濡れた足元に視線を落とした。
泥水に浮かぶ、片方の下駄。鼻緒は切れ、白木は薄汚れていた。
井戸水で静かに洗いながら、指先に沁みる冷たさを、ただ受け入れる。
誰も気づかない。誰も助けない。
この国、花祀ノ國を生んだ、八百万の花神さえもが沈黙していた。
それが、紫乃の日常だった。
*
午後の花神女学院の中庭は、鈴蘭の香と陽光に満ちていた。
花壇の間で、娘たちが花の名で呼び合う。
「百合」「撫子」「牡丹」──声が響くたび、花々がそっと揺れた。まるで、花神がその子孫の声を慈しむかのように。
紫乃もまた、「紫苑」の名を持つひとり。だが彼女の名は、ほとんど呼ばれることがなかった。
彼女は箒を手にし、艶のない黒髪を小さな団子にまとめる。
さらさら、さらさら。箒の音が響く。
掃除は神を迎える清め。紫乃が掃くと、花壇の花々が祈りに応えるように生き生きとした。
ふいに風が吹き、甘い香りが鼻先をかすめる。撫子の栗色の髪がふわりと広がった。
「まあ、姉さま。まだお掃除?」
撫子は白い手袋で口元を隠して笑った。その優雅な仕草に、紫乃さえ一瞬目を奪われる。
「その下駄、ずいぶん濡れていますわ。まさか、水溜まりで遊んでいらしたの?」
紫乃は答えなかった。ただ濡れた下駄の冷たさが足の裏に沁みた。
*
紫乃のいない教室は、噂話で持ちきりだった。
「藤の精霊は、気高くて孤高で、人に心を開かないのだとか。しかも、穢れた者が近づくと、寿命を縮めるらしいわ」
「藤宮さまって、まさにそういうお方ですわよね。いつも微笑まないし、誰とも目を合わせないし……怖いのに、綺麗で……」
神話の続きを語るかのように、声は次第に小さく、甘くなる。
そのとき、学院の正門から、異なる気配が近づいた。
コツ、コツ。
足音が正門に響くと、女生徒たちのざわめきがふっと静まった。
神の使いが降りたかのように、空気が張り詰める。
「花神女学院の視察に参った。神祇院筆頭、藤宮 藤真と申す」
黒の詰襟軍装に、制帽。
漆黒の髪が、冷たく光をはね返した。
神祇院──祭を司り、神の力で国を護る者たち。
その頂に立つ彼は、神官にして軍人。静けさの奥に、刃を宿していた。
紫乃は息を呑み、箒を握る手に力を込める。
彼の藤色の瞳が、少女たちを一瞬だけなぞった。まるで、誰かを探しているかのように。
撫子がそれに気づくのは早かった。
「──ようこそお越しくださいました。藤宮さま」
撫子は誰よりも早く一歩前へ出ると、優雅に裾を揺らして一礼した。
白い手袋が風をはらみ、彼女の輪郭を柔らかく縁取る。
その姿に、周囲の女子生徒たちから小さな溜息がもれた。
撫子はそのまま迷いなく、藤真の前へと進み出る。
「妾腹の身ではございますが、花名は『撫子』と申します。どうぞお見知りおきくださいませ」
顔を上げた彼女の微笑みは、まるでよく手入れされた西洋の花だった。
だが、藤真は何も言わなかった。
撫子のすぐ脇をすり抜けて歩くと、視線はすっと逸れていく。
石畳の隅──白襟のほつれた少女へと。
紫乃だった。
彼女は箒で花びらを集め、姿勢はか細くも凛としている。
たったひとりで、神を迎えるように清めていた。
藤真は立ち止まり、静かに息を吐く。
「誰も見ていなくとも、祈っているのだな」
風が彼の裾を揺らし、紫苑の香りがうっすらと漂った。
──藤と、紫苑の香。
「……香りまで、似ているのか」
その声もまた、誰にも届かない。それでも、藤真の胸の奥で、ひとつの花が静かに咲きはじめていた。
紫乃は、濡れた足元に視線を落とした。
泥水に浮かぶ、片方の下駄。鼻緒は切れ、白木は薄汚れていた。
井戸水で静かに洗いながら、指先に沁みる冷たさを、ただ受け入れる。
誰も気づかない。誰も助けない。
この国、花祀ノ國を生んだ、八百万の花神さえもが沈黙していた。
それが、紫乃の日常だった。
*
午後の花神女学院の中庭は、鈴蘭の香と陽光に満ちていた。
花壇の間で、娘たちが花の名で呼び合う。
「百合」「撫子」「牡丹」──声が響くたび、花々がそっと揺れた。まるで、花神がその子孫の声を慈しむかのように。
紫乃もまた、「紫苑」の名を持つひとり。だが彼女の名は、ほとんど呼ばれることがなかった。
彼女は箒を手にし、艶のない黒髪を小さな団子にまとめる。
さらさら、さらさら。箒の音が響く。
掃除は神を迎える清め。紫乃が掃くと、花壇の花々が祈りに応えるように生き生きとした。
ふいに風が吹き、甘い香りが鼻先をかすめる。撫子の栗色の髪がふわりと広がった。
「まあ、姉さま。まだお掃除?」
撫子は白い手袋で口元を隠して笑った。その優雅な仕草に、紫乃さえ一瞬目を奪われる。
「その下駄、ずいぶん濡れていますわ。まさか、水溜まりで遊んでいらしたの?」
紫乃は答えなかった。ただ濡れた下駄の冷たさが足の裏に沁みた。
*
紫乃のいない教室は、噂話で持ちきりだった。
「藤の精霊は、気高くて孤高で、人に心を開かないのだとか。しかも、穢れた者が近づくと、寿命を縮めるらしいわ」
「藤宮さまって、まさにそういうお方ですわよね。いつも微笑まないし、誰とも目を合わせないし……怖いのに、綺麗で……」
神話の続きを語るかのように、声は次第に小さく、甘くなる。
そのとき、学院の正門から、異なる気配が近づいた。
コツ、コツ。
足音が正門に響くと、女生徒たちのざわめきがふっと静まった。
神の使いが降りたかのように、空気が張り詰める。
「花神女学院の視察に参った。神祇院筆頭、藤宮 藤真と申す」
黒の詰襟軍装に、制帽。
漆黒の髪が、冷たく光をはね返した。
神祇院──祭を司り、神の力で国を護る者たち。
その頂に立つ彼は、神官にして軍人。静けさの奥に、刃を宿していた。
紫乃は息を呑み、箒を握る手に力を込める。
彼の藤色の瞳が、少女たちを一瞬だけなぞった。まるで、誰かを探しているかのように。
撫子がそれに気づくのは早かった。
「──ようこそお越しくださいました。藤宮さま」
撫子は誰よりも早く一歩前へ出ると、優雅に裾を揺らして一礼した。
白い手袋が風をはらみ、彼女の輪郭を柔らかく縁取る。
その姿に、周囲の女子生徒たちから小さな溜息がもれた。
撫子はそのまま迷いなく、藤真の前へと進み出る。
「妾腹の身ではございますが、花名は『撫子』と申します。どうぞお見知りおきくださいませ」
顔を上げた彼女の微笑みは、まるでよく手入れされた西洋の花だった。
だが、藤真は何も言わなかった。
撫子のすぐ脇をすり抜けて歩くと、視線はすっと逸れていく。
石畳の隅──白襟のほつれた少女へと。
紫乃だった。
彼女は箒で花びらを集め、姿勢はか細くも凛としている。
たったひとりで、神を迎えるように清めていた。
藤真は立ち止まり、静かに息を吐く。
「誰も見ていなくとも、祈っているのだな」
風が彼の裾を揺らし、紫苑の香りがうっすらと漂った。
──藤と、紫苑の香。
「……香りまで、似ているのか」
その声もまた、誰にも届かない。それでも、藤真の胸の奥で、ひとつの花が静かに咲きはじめていた。