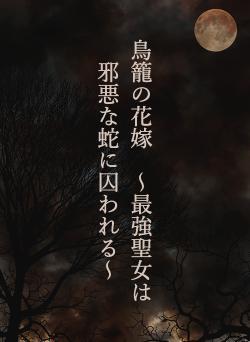「なら俺のこと切れよ」
放たれた言葉の意味がまったく理解できず、門崎咲帆―― 「さき」が二つ続いてあまり格好良くはない名前だと思っている――は、ただ呆然としたように彼の顔を見てしまった。
(この人は何を言っているんだろう)
一見まともな、大人然とした見た目。
なんとなく頭が良さそうだと思わせる切長の目に細い銀縁の眼鏡をかけた冷静な表情と、身長の高さを感じさせる低めの声。それが目の前にいる人物だ。
それなのに、口にしたのは「切る」という単語。
「何黙ってんの」
不思議そうに声をかけられて咲帆はハッと意識を戻す。
「切る?」
彼は頷いた。
「……先生を?」
「しつけえな」
今度は呆れたようにため息をつかれてしまった。
そう、目の前にいるのは男性教師だ。
その顔を見ながら、どうしてこうなったんだろうと、放課後の咲帆はいつも通りのごくありふれた一日だった今日のことを思い出していた。
つい先ほどまで、完璧に普通の一日だった今日。
◀︎◀︎
四月の木曜である今日。桜はとうに散り、新緑が芽吹き始めている。
朝八時。
咲帆はたいして来たくもない高校に、いつも通り遅刻もせず真面目に登校した。
私立晴山高校三年B組。それが彼のクラス。
「咲帆、おはー!」
「おわ!」
「『おわ!』だって〜!」
自席に黒いリュックを置いた瞬間背後から抱きつかれ、咲帆は驚いた声を上げた。驚かせた張本人の柳楽真香は嬉しそうにケラケラ笑った。
真香は付き合って三年になる咲帆の彼女だ。黒く艶やかなセミロングヘア、くりっとした黒めがちな瞳という可愛らしい見た目をしている。天真爛漫を絵に描いたような明るい女子で、毎日こんな風にイタズラっぽい笑顔を浮かべている。
その笑顔を見ながら、期待されていたであろうリアクションができたんだ、と彼は安堵した。
「咲帆、宿題やってきた?」
「数学? 英語?」
間のやりとりを省いたような察しの良い彼の言葉に、真香はまた「あはは」と笑った。
「両方」
咲帆は小さくため息をついて眉を下げると、リュックから取り出したノートを二冊、真香に差し出した。
「ありがと咲帆! 大好き!」
「わっ」
正面から思いきり抱きしめられた咲帆があげた声に、彼女はまた嬉しそうに無邪気な笑顔を見せた。
「朝から何イチャついてんだよ」
「目の毒ー」
クラスメイトの揶揄う声に、真香は「うるさいなぁ」と頬を膨らめ、ふたたび咲帆を見上げて笑いかけた。
その顔を純粋にかわいいと思いながらも、咲帆の頭に別の気持ちもよぎる。
(はじめから、自力で宿題をやろうなんて気は無かったんだろうな)
そしてごく微かなため息が、つくと同時に空中に溶けていく。
◀︎◀︎
咲帆と真香はいわゆる幼なじみだ。
家が同じ町内にあるから、小学校に上がるより前から近所の子どもたちと一緒に遊ぶ仲だった。
小学校や中学校では同じクラスになることも何度かあり、日直や部活などがなければ、登下校も家までの道を並んで歩くのが当たり前になっていた。
そんな二人が彼氏と彼女になるのは必然といえば必然だったのかもしれない。
『そろそろはっきりさせようよ』
中学三年の五月。
向かい合ったかと思うと、上目遣いでそう口にしたのは真香。
普段通り二人で登校する途中、学校近くのひと気のない路地に差し掛かった時だった。
『はっきり……?』
咲帆の言葉に、彼女は小さく頷いた。
『何を?』
今度は不満そうに眉根を寄せる。
『私たちの関係に決まってるでしょ?』
(関係……決まってる……)
咲帆は頭の中で真香の言葉を反芻した。
ピンとはこなくても、彼女が何を言っているのかは理解できた。
『私たち、周りから見たら付き合ってることになってるよね』
語気と語尾に強さを感じる口調だ。
『え……うーん……そう、なのかな』
見上げた自分から目を逸らすようにやや上を見た咲帆の態度に、真香は唇をツンと尖らせる。
『そうよ。昨日だって結衣たちに聞かれたんだから』
『聞かれたって、何を?』
真香は『もう!』と呆れたような声を出した。
『「マナと咲帆って実際どうなの?」って聞かれたの』
『へえ』
『だから「へえ」じゃないでしょう? はっきりさせてって言ってるの』
先ほどよりも語気を強めた彼女に視線を捉えられてしまった。
『付き合ってるってことでいいんだよね?』
(僕は今、告白されているんだろうか)
これは意思の確認というより“言質を取られている”と言った方が相応しい状況だなと咲帆は思った。
『ね?』
拒否権は無さそうだ、と。
『う、うん。それでいいと思う』
たじたじといった表情の咲帆の言葉に、真香の吊り上がっていた眉が緩やかなアーチを描く。
『じゃあ、今日から彼氏彼女だねっ! 行こ!』
『えっ』
唇を三日月型にしてニコリと満足げな笑みを浮かべたかと思うと、真香は咲帆の左手を取り、グイと引っ張るように路地を出た。
『あ、真香! おはよ』
路地を出たところには二、三、見知った顔があった。
『鈴ちゃん、おはよう』
『……おはよう』
咲帆が戸惑った表情を平常運転に戻そうとしていたところへ、クラスメイトの女子が現れた。
『え!?』
眠そうな目をしていた彼女が驚いた表情と声に変化したのを見て、真香はニヤリと口角を上げた。
クラスメイトの視線は、二人のつながれた手元に注がれていた。真香の指が咲帆の指に絡められている。
『やっぱり二人って』
『んーまあ、今日からね』
真香は『ふふ』と鼻唄でも歌い出しそうな声色で告げた。
『えー! おめでとー!』
鈴の幾分甲高くなった声に、近くにいたクラスメイトや顔見知りの生徒が群がるように『なになに?』と集まってくる。
真香はその一人ひとりに見せつけるかのように繋いだ手を胸元につけた。
そして鈴が『今日からなんだって』とはしゃぐように伝えた。
(遅かれ早かれこうなっていた気はする)
咲帆の頭に浮かんでいた言葉は“まあいいか”であった。
そうしてそのまま高三の今日まで、咲帆と真香は公認カップルを続けている。
▶︎▶︎
授業だって、いつもと変わらず真面目に受けた。
三時間目、英語。
「“If I were a bird, I could fly all over the world.” この文を訳してもらおうかな。わかる人、手上げて」
英語教師の常田が、B組の教室内を見渡す。
常田は二十七歳の若い男性教師だ。バスケ部の顧問を任されているだけあって、スポーツマンらしい爽やかさがある。
明るく人当たりの良い常田は人気ではあるが、その親しみやすさ故生徒に舐められている節もあり、こうした時に手が上がらないことも少なくない。
室内はシンと、水を打ったように静かになる。
「お前たちは、授業中だけは本当におとなしいな。高二の復習だぞ」
常田は苦笑いだ。
(みんな目立ちたくないだけだ)
窓際の席の咲帆は心の中でつぶやくと、グラウンドを横切るように飛んでいったカラスを見つめた。
「じゃあ……門崎。わかるか?」
常田が名簿から咲帆を指名した。
指されてまた彼の微かなため息が、誰にも気づかれずに消えていく。
「“もし私が鳥なら、世界中を飛び回れるのに” です」
仮定法過去を用いた英文の訳。咲帆にとってはごく簡単な問いだ。
「That's right!」
常田が英語で「正解だ」と告げる。
咲帆は常田のこういう陽キャ的な明るさが少し苦手である。
彼の成績は上の下、あるいは中の上といったところだ。テストの成績ではいつも二五〇人ほどの学年の十位から二十位程度を行ったり来たりしている。
週一で塾に通っているし、努力をすれば十位以内をキープすることだって可能ではある。
けれど咲帆はそれをしない。
“目立ちたくないから”
理由はそれだけだ。
良い方にも悪い方にも目立たず、地味にその他大勢に紛れているのが、彼にとっての正解なのだ。
「じゃあ次、“If I had met you before him, we would have become lovers.” 柳楽」
次に指名されたのは真香だった。
「はい、えーっと……」
咲帆が同じ列の二つ席を挟んだ真香の席の方を見ると、彼女も咲帆の方を見た。
(宿題に無かった問題だからわからないのか)
とはいえ、隣の席でもない咲帆には助け船を出すこともできない。
「えっと、わかりません」
真香はあっさりと答えた。
「お前なあ、ちょっとは考えろよ」
常田に言われて、真香はぺろっと小さく舌を出した。
それから咲帆の方をチラッと横目に見たのがわかった。
「この訳は“もし彼より先にあなたに出会っていたら――」
常田が訳を言い終えると、真香はまた一瞬咲帆の方に視線を送ってから着席した。
答えられなかったことが恥ずかしかったのか、その頬は赤くなっているように見えた。
(真香ももう少し自力で勉強すれば、このくらい答えられたんじゃないかな)
慣れた光景に、咲帆はまた退屈な目をして窓の外を見た。
▶︎▶︎
昼休み。
今日は真香の友だちカップル二組と一緒に屋上で昼食をとった。
昼食は真香と二人きりの日もあれば、こうして真香の友人と一緒の日もある。
そのどちらだったとしても決まっていることがある。
「はい。咲帆の分」
「ありがとう」
「いつもすごいよねー、マナのお弁当」
そう言って真香の友人の結衣と広菜が感心してみせたのは、真香が咲帆に渡した弁当だ。
弁当箱こそ黒い飾りけのないものだが、卵焼きにエビフライ、ミニトマトや小さなグラタンなど細々としてカラフルで可愛らしい。
「これ作るのに早起きしなくちゃいけないんじゃない?」
真香の隣に座った結衣が言う。
「まあねー」
真香はどこか得意げだ。
「結衣には絶対無理だよな」
今度は結衣の彼氏が言う。
「私は部活の朝練があるから無理だよ」
彼氏も結衣も購買で買った惣菜パンを手にしている。
「マナがすごすぎるから私がダメ女みたいじゃない」
結衣が冗談めかしながらも不満げに真香を見た。
「だって咲帆のことが好きなんだもん。頑張るでしょ」
真香が「えへ」と笑えば、他の四人が冷やかすように揶揄った。
(頑張る?)
その場の空気に合わせるようにやんわりと照れたような笑顔を作りながら、咲帆は考えていた。
(おかずのほとんどが冷凍食品なのに?)
それでもたしかに、弁当を詰める時間の分だけは早起きをしなければいけないのだからありがたくないわけではない。
それに、ハート型に盛り付けられた卵焼きは手作りだ。
(でも嫌いなんだよな、甘い卵焼き)
付き合い始めてから――というより幼なじみなので以前から――咲帆は何度か真香に、自分の好みは甘くない卵焼きだと言ったことがある。
しかしその度に『私は甘い方が好きなの』と一蹴されてしまい、もうそんな好みを伝えることもなくなった。
彼女は第三者のいる場で弁当を食べる時は、必ずフタを開けた状態で咲帆に手渡す。
二人の時はランチ用の小さなバッグに入れたままだ。
そしてどちらの時でも、フタを開けるとすぐに弁当箱を二つ並べてSNS用の写真を撮る。
真香の作る弁当が誰のためなのか、咲帆にはなんとなく察しがついている。
(真香は多分、自分が褒められたい)
彼から見る真香は、そういう女の子だ。
いつも“見られる”ことを意識している。
「咲帆くん、幸せ者ね。こんなに可愛い彼女に想われて」
広菜が笑いかけてくる。
真香はたしかに可愛い。
幼馴染や彼女であるという贔屓目を差し引いて客観的に見ても万人受けするような、リスやウサギといった小動物のような可愛さがある。
実際、高校に入学してから何度か告白もされているようだ。
「マナはきっといい奥さんになるね」
結衣が真香の頭を撫でながら言った。
その言葉に、咲帆の喉がごくごくわずかに唾を押し込む。
「えーそんなぁ。気が早いよ」
真香は頭をフルフルと子犬のように振って、結衣の手を払う。
そして流れるように咲帆に甘さのある視線を向ける。
「ねぇ?」
咲帆は一瞬泳ぎそうになった目を、内心必死で留めた。
「……はは」
コメントを求められそうになるのを笑って誤魔化すことしかできない彼に、真香の眉がピクリと反応する。
「あー……真香、SNSの写真は?」
「あ! そうだった」
真香の気を逸らすことに成功して、咲帆はホッと胸を撫で下ろした。
「でも咲帆くんも背が高めでかっこいいよね」
せっかく自分から話題が逸れたと思っていたのに、ボールが戻ってきて今度は咲帆が頭の中で眉間を寄せる。
「いや、全ぜ――」
「全然だよ。一七二センチなんていっぱいいるでしょ。それに背が高めってことくらいしか無いもん。咲帆の見た目は」
弁当にスマホのカメラと、そして画面に視線を向けたまま、真香が淡々と答えた。
「ひでー」
広菜の彼氏が咲帆に同情するように言った。
「咲帆は中身がいいの。私にしかわからないんだから」
「たとえばどこよ」
今度は広菜が尋ねる。
「優しいしー、そこそこ頭もいいしー、私の話をきいてくれるしー、それにSNSなんか全然興味ないって感じの流行りに乗らないマイペースなところとか」
「それってなんか……」
広菜は言い淀んだが、咲帆には彼女が何を言おうとしたのか予想がついた。
(“真香にとって都合がいい”だよな)
「最後のっていいところなわけ? それとも嫌味?」
結衣が遠慮なく聞いた。
「いいところだよ。D組の木元くんだっけ? あのメガネの」
「木元がどうかした?」
「なんかぁ、二年の時に裏垢でクラスのこと愚痴ってたらしいよ。それがバレちゃったらしくて」
「えーマジ? 超気まずいじゃん」
「あ、それ俺も聞いた」
友人たち四人が騒つく。
「超根暗だよね。そんなことになるくらいなら、SNSなんて無くていいの」
咲帆以外の五人が笑う。咲帆も口元だけはうっすらと弧を描いている。
(真香は木元のことをよく“根暗でオタク”と揶揄している)
どうやら高校に入学してから告白されたうちの一人らしい。
実際の木元自体がどうなのか、とくに付き合いのない咲帆にはわからない。
(だけど、そんな木元と僕が真香の中では同じカテゴリの人間ってことだ)
真香の中での咲帆と木元の違いが、先ほどの“背が高め”、“優しい”、“ そこそこ頭がいい”、“自分の話を聞く”、“ SNSに全然興味がない”というところなのだ。
そして真香の言う優しさとは、宿題を見せるようなことなわけで、どう考えても都合のいい存在であるとしか考えられないのである。
真香に笑いかけられ、咲帆はまた喉の奥に息苦しさにも似た引っかかりを感じた。
“この先、ずっとこうなのだろうか?”、“真香にずっと付き合っていくのだろうか?”
そんな靄がかかったように霞んだ視界。
“真香のような可愛い女子と付き合うチャンスはもうないかもしれない”という濁った思考。
ここのところ、その二つが咲帆の脳内で天秤を揺らしている。
▶︎▶︎
そして、何事もなく午後の授業を終えて放課後。
悪目立ちすることもなく、真香の機嫌を損ねることもなく終業のチャイムを聞けば、今日も咲帆にとっての完璧な一日が終わる。
「帰ろ」
ぬいぐるみのマスコットをいくつかつけたカバンを肩にかけ、真香が咲帆に声をかける。
「うん」ただそう言って、一緒に帰路につけば良いはずだった。
しかし、今日の咲帆にはそれができなかった。
昼休みの『えーそんなぁ。気が早いよ』という真香のセリフとこちらを見た甘ったるい目が、午後の授業中もずっと頭にこびりついていた。そんな中、ホームルームでは進路調査票が配られ、将来のことをリアルに考えてしまった。
「ご、ごめん。今日委員会のことで先生に呼ばれてて」
「えー! 明日でいいじゃない」
「そういうわけにはいかないよ。悪いけど、真香先に帰っててくれる?」
真香は一瞬不満そうな顔を作ったが、すぐに元に戻って大人しく同意した。
「じゃあ、気をつけて」
咲帆はそう言ってリュックを手に取ると、小走り気味にある場所へ向かった。
(ああ……まずいな、早く……早く)
ガラッと音を立てて、咲帆はとある部屋のドアを焦り気味に開けた。
そして今度はゆっくりとドアを閉め、キョロキョロと部屋の中を見回して誰もいないことを確認すると「ふぅ」と落ち着きを取り戻すように息を吐いた。そして、静かにドアの鍵をかける。
薬品のような匂いを微かに鼻に感じた気がするのは、ここが誰もいない放課後の理科室だからだ。どこか香ばしい匂いも感じる気がしたが、アルコールランプを燃やした後か何かなのだろうと咲帆は思った。
黒い天板の、広い実験用のテーブルの上にリュックを置くと、咲帆はネイビーの合皮でできたスリムなペンケースを取り出した。
そして、ファスナーを開けると、カッターナイフを取り出した。
黄色くて幅が一.五センチほどの細い、どこにでもよく売っているタイプのカッターだ。
そのスライダーをカチカチと鳴らして刃を二センチほど出すと、二の腕までシャツを捲った自分の左腕のヒジのくぼみの近くに当てた。
そして、線を引くように左から右へ引いた。
「何やってんの?」
その声に、咲帆は“心臓が喉から飛び出すかと思った”という状況を初めて体験した。
そして一旦縮み上がった心臓がドクドクと脈打つのを感じながら、声の方を見た。
咲帆の右斜め後ろ、理科室とつながっている理科準備室から、白衣にメガネの若い男性がこちらを見ている。
手には茶色い液体の入ったビーカーを持っている。彼は咲帆に話しかけながら、それを口にした。香ばしい匂いの正体はビーカーに淹れられたコーヒーだった。
「どうした?」
落ち着き払った彼とは対照的に、咲帆は口を小さくパクつかせ、言葉を発せずにいた。
――カランッ
咲帆の手に握られていたカッターが、彼の手から滑り落ちて乾いた音を鳴らした。
「何? もしかしてリスカ?」
自分の足元に転がったそれを拾い上げ、男性が咲帆に話しかける。
捲られた袖とカッターナイフから、咲帆がリストカット――つまり手首や腕を傷つけること――をしようとしたことを察したようだった。
それは、咲帆が息苦しさから逃れたいと願ったときに行う行為だった。
「ふーん」
彼はつかつかと、躊躇なく咲帆の方に歩み寄ってきた。
「腕見せろよ」
教師にしては粗暴さを感じさせる口調だ。
そこでやっと、彼がこの春赴任してきた理科教師の山井賢太郎だということに咲帆の意識が追いついた。
「なんだよこれ」
彼は咲帆の左腕を掴んでまじまじと見ると、不満そうな声を漏らした。
「全然傷になってねえじゃん」
そこにある皮膚には髪の毛ほどの白い線が引かれている。血が出るような傷ではなく、皮膚のほんの表層の部分にうっすら傷がついたような状態。
咲帆のこの行為はいつもこうだ。
「あ、当たり前じゃないですか!」
咲帆は振り払うように腕をバッと上げた。
「何で当たり前なんだよ。リスカしたかったんじゃないのか?」
「…………」
あまりにも淡々と、何でもないことのように聞かれ、咲帆の方が言葉を失ってしまう。
(目の前で生徒が……自殺未遂紛いのことをしたんだぞ? 普通はもっと……)
「何とか言えよ。お前、リスカしようとしたんだよな? あ、わかんねえかリスカって」
「わ、わかります。自分がやろうとしてたことの名称くらい……」
「やっぱそうなんだ」
咲帆は観念して小さく頷いた。
「何で?」
「何でって……何でそんなこと、先生にいわなくちゃいけないんですか」
「バーカ。“先生だから”に決まってんだろ」
とても教師とは思えないような言葉遣いである。
「…………」
「じゃあ今から一緒に職員室行くか。お前のクラスの担任に引き渡すわ」
「え!」
咲帆の声はわかりやすく動揺の色を見せた。その声と彼の顔色を見て、山井はニヤリと企みでもあるかのようにほくそ笑んだ。
「なら話せよ、先生が聞いてやるから」
咲帆は渋々、山井にリストカットの原因である今の自分を取り巻く環境と抱えている気持ちを白状した。
「はーなるほどなぁ。若いなー十代」
静かに話を聞いてくれたかと思っていた山井が最初に放ったのがそんな言葉だったので、咲帆はどこか落胆したような気持ちになった。
「若いとか十代なんてまとめる人に話すんじゃなかった」
まずいところを見られ、事情も聞かれた咲帆は、気にせず悪態をつく。
「あーそうだよな。悪い悪い」
山井は全く悪いと思ってなさそうな軽さで謝罪する。
(こんな人間に秘密を知られるなんて不覚だ)
きっと明日には担任にも話がいって、親との話し合いの場を持たれるか、カウンセラーの紹介なんかをされるのだろうと想像する。
そして見えないため息をつく。
「にしてもダセーな」
山井の口から出たのは咲帆が予想もしない言葉だった。
「そんなんじゃ死なねーじゃん」
「……死ぬ気はないです」
自身の言葉が自分でも情けなくなった。
「その程度じゃストレス解消にもなんねーだろ」
「先生には関係ない」
山井の遠慮のない物言いは、死ぬ気がないどころか痛みを感じる気も、傷跡を残す気も無い弱い自分を突きつけられるようだ。
しかし、続く山井の言葉はさらに意外なものだった。
「なら俺のこと切れよ」
山井は咲帆の目をまっすぐ見て言った。
(この人は何を言っているんだろう)
咲帆はぼーっと、その顔を眺めてしまった。
「何黙ってんの」
そしてハッと意識を戻す。
「切る?」
彼は頷いた。
「……先生を?」
「しつけえな」
今度は呆れたようにため息をつかれてしまう。
今日一日のことを回想してみても、そのあまりにも意外な言葉に納得できる要素はどこにもなかった。
「いや、何で先生を……」
当然の疑問である。
「まあそうだよな」
山井はため息まじりに苦笑いをすると、咲帆に背を向けて白衣を、それからその下のシャツを……と次々と脱いでいった。
「な、何して――」
目の前の教師が急に服を脱ぎ出したことに戸惑った咲帆だったが、露わになった山井の背中を見た瞬間、戸惑いを通り越して言葉を失った。
(なんだこれ……)
山井の広い背中いっぱいに、ナスカの地上絵やどこかの先住民を思わせるような渦や三角形などが使われた幾何学模様のタトゥー、それに、同じような模様のボコっと盛り上がった……まるでミミズのような赤い線が何本も走っている。
(これ、傷……?)
「タトゥーはわかるよな」
「はっはい」
彼の背中の異様な迫力に、咲帆は思わず緊張して背筋を伸ばしてしまった。
「じゃあ、スカリフィケーションは知ってるか?」
咲帆はブンブンと無言で首を振ってから、山井が背中を向けていることを思い出した。
「し、知らないです!」
「何ビビってんだよ」
山井は咲帆の方を振り向いてまた苦笑いを浮かべた。
「簡単に言うと、皮膚に傷をつけて模様を作るんだよ。焼いたりする場合もあるけど、俺は傷の方。タトゥーとスカリフィケーション……まあ平たく言うと“身体改造”ってやつが俺の趣味なわけ」
「へ、へえ」
山井はごく普通の趣味のように言ってのける。
「だからさぁ、自分の身体に刃立てらんないんだったら俺を切れよ。他人の身体でもスカッとすんだろ、きっと」
「な、何で」
「何でが多いな」
山井はまた呆れたように言う。しかし、どう考えても自分の疑問の方が正しいはずだ、と咲帆は思っていた。
「だってそんな、傷なんて」
「言っただろ? 趣味なんだよ。身体に傷つけんのが」
「だからって」
「いいから、まずはやってみろよ。ちょっと待ってろ」
山井は上半身が露わなまま理科準備室に入って行った。
咲帆は逃げることもできず立ち尽くすように、ただその場で山井が戻ってくるのを待っている。
彼はすぐに戻ってきた。
「これ使え。カッターよりよく切れる」
そう言って、山井はペンケースほどの黒い箱を手渡した。
咲帆がパカっとフタを開けると、赤いビロードの真ん中で銀色の細いものが光り輝いている。
「これ……メス……?」
山井が差し出したのは医療用のメスだった。
(この人はこんなものを持ち歩いているのか?)
疑問が浮かんだが、飲み込んでしまった。
咲帆がメスを見つめている間に、山井は背もたれのない理科室の椅子に腰掛けた。
「やれよ。どこでもいいから」
再び咲帆に背中を向けて声をかける。
「い、いや」
「俺がいいって言ってんだから、やれよ」
「いやでも……」
「なら職員室行くか?」
「…………」
咲帆が黙ると、山井は「ふ」っと息を漏らすように笑った。
「お前さあ、そんなんじゃいつまでたっても利用される側だぜ? それでいいのか? 殻を破るチャンスだと思うぞ?」
咲帆のコンプレックスを刺激するような言葉のセットだ。
(殻を破るチャンス……)
咲帆の脳裏に、真香の顔が浮かぶ。
「まずはメスを持って、俺の肌に当ててみるところからだな」
まるで優しくハードルを下げるかのような言葉に、とうとう咲帆はメスを持ち上げた。
それはひんやりとして、彼が想像したよりずっと軽かった。
「そうそう。そしたら背中に当てて、サクッといけばいいんだよ」
背中を向けたままの山井が、見えているかのように言う。派手な背中に似合わない、優しく誘導するような声色に変わっている。
咲帆はゴクリと唾を飲み込むと、小さく一回、深呼吸をした。
そして、右手に持ったメスの先端を山井の背中に向けた。
他人に刃物を向けるという行為が初めてで、どうしたらいいのかがわからない。
まっすぐ向けて行ったが、背中に当たる直前になって刺さるのが怖くて刃を寝かせるようにして、肌にぴたりとくっつけた。
ひんやりとしたメスが当たったからだろう、山井の肌がかすかに動いたように見えた。
その小さな動きに咲帆の背がゾクリと、寒気のようでそれともちがう感じたことのない感覚を覚えた。
(バターナイフみたいだ)
うるさいぐらいに柄の入った背中だが、肌に沿うように寝ている銀色のナイフ状のものを見てそう思った。
「そのまま刃を立ててもいいし、スライドさせてもいい」
山井が唆すように促すが、咲帆の手はその場に貼り付いてしまったかのようにピタリと止まって動かない。
というより動かせなかった。
(本当に切っていいのか?)
異常な状況に、そう簡単に順応できる性格ではない。
(痛いに決まってるよな)
様々な考えがぐるぐると巡る。
(何を考えているかわからない、よく知らない粗暴な教師だ)
山井のことを分析してみる。
(実際にメスを入れたら訴えられるのかもしれない。そうしたら……傷害罪とかになるのか?)
――キーンコーン……
長い沈黙を破るかのように、チャイムが鳴った。
そこで咲帆はハッと我にかえる。
山井の背中にメスを当てたまま三十分以上の時間を過ごしていたことに気づいた。
「す、すみません先生。僕にはやっぱり無理みたいです」
咲帆はメスをケースに戻した。
そんな彼を見て、山井は「はぁ」とため息をついた。
しかし呆れているという雰囲気ではない。
「初日だし、メスを持って背中に当てただけでも上出来だ」
山井はニヤリと笑う。
「え? 初日?」
「明日も来いよ。いや、明日じゃなくてもいいけど。ストレス溜まったら、自分じゃなくて俺に傷つけてよ」
「い、いや、無理です」
山井の笑顔に恐怖を覚える。
「だいたい何で僕が」
「また“何で”。自分じゃ背中に傷つけらんねーからさ」
納得がいくような、いかないような答えである。
「ちなみにスカって俺の秘密なんだわ」
「は、はあ」
「お互いの秘密を知った者同士、仲良くしようぜ」
山井は不敵な笑みを浮かべた。
その顔に、咲帆は言いようのない恐怖を感じた。
「か、帰ります!」
そう言い捨てて、リュックを手に取ると急いで鍵を開けて理科室を後にした。
部屋を出る際、山井がクツクツと愉しそうに笑っているのが目の端に映って、また背筋がゾクリと鳥肌を立てた。
その夜、咲帆はベッドの中でスマホ画面に【スカリフィケーション】と入力した。
WEBの辞書から、目を背けたくなる施術レポートのブログまで、たくさんの肌の写真が目に飛び込んでくる。
山井と同じ民族的な模様もあれば、文字やハートなどのポップな模様を刻んでいる人もいる。
見てはいけないものを見ているかのようで、誰もいない自分の部屋だというのに思わず布団を被ってしまった。
そして、誰にも教えていないSNSのアカウントでも次々と傷の画像を検索しては薄目を開けて見ていく。
(怖いけど……すごい……)
山井と同じ嗜好の人間がいるのだという事実に、新しい世界を知ってしまったような興奮でその夜咲帆はなかなか寝付けなかった。
▶︎▶︎
翌朝。
咲帆は真香と登校している。
この時間も彼を憂鬱な気持ちにする。
学校への道順で言うなら真香の家の方が遠いのに迎えに行くのは咲帆、そして一方的に自分の話ばかりをする真香に付き合うような時間だからだ。当然のように真香のカバンは咲帆が持っている。
けれど、今朝はどこか気分が違った。
というより、自分の周りに広がる世界そのものが違って見える。
昨日、山井と過ごした背徳的とも言える放課後の異様な時間と、スカリフィケーションという新しい世界を知ったせいだ。
そしてそれは、真香の知らない世界でもある。
「なんか今日、咲帆ちょっと変じゃない?」
「え?」
意外な鋭い指摘に心臓がギクリと音を立てる。
「なんか楽しそうっていうか」
「そうかな」
「うん。なんか、らしくないね」
(らしくない?)
楽しそうな自分は、真香の中の咲帆像にマッチしないらしい。そしてどうやらそれはお気に召さないようだ。
「いや全然。いつも通り。あー、でも昨日見た動画がおもしろかったからそのせいかも」
「なーんだ。そんなことで喜んでたんだ」
そしてこれが、真香の中の地味な咲帆像なのだとわかりやすく機嫌を直されてしまう。
▶︎▶︎
放課後。
咲帆は今日も理科室にいる。
そしてなぜか、山井の背中にまたメスを当てている。
今日もメスを持つ手は動かない。
「柳楽だっけ、あれがお前の彼女?」
背中越しに問われる。
「……はい」
つい先ほど、真香と一緒に下校しようとしているところに山井が現れた。
そして『門崎くんに頼みたいことがあるんだ』と言って、ここに連れて来られた。
(誘拐みたいなものだ)
もうここへは来ないつもりだったはずの咲帆は、文句を閉じ込めるように口をギュッと結んだ。
「そんなに好きじゃねーならさっさと別れればいいんじゃないのか?」
(そんなに簡単なことじゃない)
何も知らずに口を挟んでくる山井に腹が立つ。
「幼なじみなんです。生活圏もクラスも一緒で、別れてメリットなんてないですよね」
「まあたしかに、顔は可愛いか」
咲帆の意見にはあまり興味が無いのか、山井は自分の感想だけを述べた。
「でもちょうどよかっただろ? 俺が連れ出して」
「え?」
「お前昨日ここに来た時と同じような死にかけの野良猫みたいな目してたぞ」
(死にかけの野良猫なんて見たことがないけど、まあ確かに生き生きとはしてないだろうな)
今日の真香はどこかピリピリとしていた。
朝の不機嫌さももしかしたらそれと関係があるのかもしれない。
昼ごはんは二人だったが、途中で食べるのをやめて机に突っ伏して寝てしまった。
正直、そんな真香と放課後まで一緒に過ごすのはキツいと思っていた。
(八つ当たりされるのが目に見えてる)
同等であるはずの彼氏彼女、ましてや自分が告白して付き合ってもらったというわけでもない彼女だというのに、八つ当たりに文句を言うことすらできない。
そんな時には真香にも自分にも腹が立つ。
そしてそんな日は、きっと普段なら理科室で昨日と同じことをしていたはずだ。
「で? そろそろいけそう?」
「…………」
昨日あれだけネットで画像を見て慣れたと思っていたが、山井の背中のタトゥーと傷あとの数は群を抜いて多い。一日や二日ではまだ迫力に圧倒されてしまう。
そして、他人を傷つける行為自体もできそうにない。
「無理です」
「まあゆっくりやっていけばいいよな」
「は?」
「嫌か?」
「当たり前じゃないですか。今日で最後です。もう帰ります」
咲帆は語気を強めた。
「お前さあ、生物部入れよ」
また、咲帆の言葉は無視された。
「柳楽と一緒にいる時間、減らしたいんだろ? ならここに来ればいいんだよ」
「なんでそこまでして……」
「結構良くね? お互いの秘密を知ってるってさ」
背中を向けたままの山井の声は軽く弾んでいるように明るい。
「お前が俺の背中にメスを入れられるようになればお互い利害が一致してハッピーだしな」
「教師のセリフとは思えないんですけど」
「教師と生徒じゃなくて、人間同士として喋ってんだよ」
山井は振り向いた。
「人間同士?」
「そ。俺はリスカするやつの人間臭さ、好きだからな」
言われてみれば、山井はリストカットそのものについてはバカにしたようなことも否定するようなことも言ってこなかった。
ますます教師らしくないと思うが、「人間」と言われれば、たしかにそう思える。
「でも僕、やっぱり他人を傷つけるのは無理です」
「いいんだよ、ゆっくりで。メスの冷たさが気持ちいいしな」
(山井先生はヘンタイなんだろうか)
男子生徒にメスを当てられて上機嫌な山井を見ていたら、そんなことを考えてしまった。
▶︎▶︎
二日後の昼休み。
「え? 生物部?」
「うん」
結局咲帆は山井の誘いに乗って生物部に入ることにした。
そして今、誰もいない空き教室で隣り合ってお昼を食べながらそのことを真香に報告している。
「写真部は?」
「掛け持ちすることにした」
「えー! そんなことしたら私と過ごす時間が減っちゃうじゃない! だいたいもう三年ですぐに引退じゃないの」
「大学に行くのに、理系の部活に入っておくと有利なんだ」
もちろんそんなのは大嘘だ。
そもそも山井が顧問を務める生物部は、入部希望者がいなかったせいで活動実態がない。
そして、咲帆が入部したところで、活動は二人が放課後に理科室で行なっている秘密の儀式だけだ。
「なら写真部を――」
「カメラはさ、コンクールで賞も貰ってるから、これも進学に有利だから続けたいんだ」
真香は咲帆の口にする“大学”や“進学”の言葉に弱く、すぐにおとなしく黙ってしまう。
それは咲帆との将来を考えているからだろう。
(僕がいい大学に行くことを期待している)
そして、その先は一流企業に就職してほしいと思っているであろうことが容易に想像できてしまう。
他人頼みの真香の将来設計に、いっそ大学受験でわざと失敗すれば真香のほうから振ってくれるのではないかと考えてしまうこともあるが、そんなことのために自分の人生を棒に振るのもバカらしい。
しかしこれで、真香と一緒に下校する機会が随分と減りそうだ。
「ねえ……」
真香が咲帆を見つめる。
「お休みの日は、会えるよね?」
「う、うん。もちろん」
「さみしい……」
彼女は瞳を潤ませる。
こういう表情を見ると、真香はやはり自分のことが好きなのだと実感させられる。
「ねえ咲帆」
「ん?」
「キスして」
「えっ」
思わず椅子をガタッと引いてしまった。
もう三年も付き合っているのだから、もちろんキスくらいはしている。
それでも昼間の学校で……となると、咲帆には若干ハードルが高い。
「誰もいないよ?」
照れる咲帆に真香はクスッと笑う。
ここで待たせれば、またどんどん真香の機嫌が氷点下に近づいていくのは目に見えている。
誰もいないのはわかりきっているが、咲帆はキョロキョロと周りを確認して真香にキスをした。
「え」
一瞬の口づけで終わるつもりだった咲帆に対して、真香は首に腕を回してせがむようにキスを続けた。
「ねえ咲帆」
吐息を漏らしながら咲帆を見つめる真香は、十七歳の男子高校生が目を逸らすことを許さない。
「私、咲帆のこと大好きだから」
「う、うん。わかってる」
(やっぱり真香って可愛いんだな)
▶︎▶︎
そんなことがあったせいで、翌週月曜日の放課後の咲帆は後悔していた。
(真香と一緒に帰る方が楽しかったんじゃないか?)
山井の背中を眺めながらそう思っていた。
つい先日までの真香は、休みの日は別々に行動したがっていたが、この土日は両日を咲帆とのデートに費やし、その最中ずっと上目遣いで咲帆を眺めてははにかんでいた。
「ふぅ」
思わずため息を漏らして、山井の背中からメスを外した。
「なんだよ、今日はもうギブ?」
(べつに試合でも勝負でもないけどな)
ふと、山井の左手が目に入った。
左手の甲、親指と人差し指の境のあたりに古い傷あとのようなものが見えた。
「それも、スカリフィケーションの一つ?」
「ん? ああ、これ?」
山井は咲帆に見せるように手を肩の近くに一瞬上げ、その後右手で愛おしそうに撫でた。
山井の傷あととタトゥーは、首元を広く残して背中と胸側の胴の部分に限定されている。肩から先には決してはみ出さない。
それは彼が教師だからで、半袖を着ても外からわからないようにしているそうだ。
だから、手に傷あとがあるのはいささか不自然さを感じてしまう。
「先生って、なんで僕に切らせようとするんですか?」
山井の表情から、その傷あとに関係があるような気がした。
山井は咲帆の方に身体を向けた。
「なんだよ。興味湧いちゃったわけ?」
いつものようにどこかふざけたように言われる。
「理由がわからないと、実際切ったら訴えられたりするんじゃないかって気が気じゃないです」
手の傷あとのことが気になっているのが本音だが、これも本心である。山井のようなマトモじゃない人間を、そう簡単には信用できない。
「なんだ、結構鋭いじゃん」
山井は咲帆の考えを見通している様子だ。
「お前が考えてる通り、この傷が原因だよ」
そして山井は、自身の中学時代のことを話し始めた。
◀︎◀︎
十四年前。
山井は中学二年の十四歳。
今のように背が高いわけでもなく、声変わりもしていなかった山井は女の子のような見た目で、一人の男子生徒にパシリ役をさせられていた。
同級生の彼の名は、満島といった。
そして時に彼は、山井に暴力を振るっていた。
『お前、マジでひょろひょろしててムカつく』
理由なんてそんなものだった。
(嫌いだなぁ、満島)
そうは思っていても、反抗すれば殴る蹴るの暴力がエスカレートするだけだ。
ある日の放課後の教室で、満島は山井の指の間にカッターを素早く突き立ていく危険な遊びをしていた。
『怖いだろ?』
そう笑ってみせた満島を、山井は冷めた気持ちで見ていた。
満島が殴ったり蹴ったりはできても、カッターを突き刺したりタバコを押し付けたりはできない小心者だと知っていたから。
つい出来心だった。
山井は満島がカッターを振り下ろす瞬間、スッと少しだけ手をスライドさせた。
『え……』
手から伝わる感触に違和感があったのだろう。満島は不安げな声を漏らした。
視線の先には血を流した山井の手の甲があった。
『え……』
普段は威勢のいい満島が、慌てふためいて声を出せずにいるのを山井は笑いをこらえて見ていた。
『お。俺……』
『ねえ満島くん』
『ご――』
『謝らなくていいよ』
そう言って山井はニコリと微笑んだ。
『その代わり、もっとやってくれないかな。左手がズタズタになってもいいからさ』
『な、何言ってんだよお前……痛くないのか?』
『痛いよ。痛いけど、なんか気持ちがいいんだよね』
山井は心臓が躍るように震えているのを感じていた。興奮しているのが自分でもわかる。
その原因が、手の傷だけでなく満島の泣きそうな表情にもあることもわかっていた。
『ねえ、満島くん。お願いだから』
『な、何言ってんだよ! 気持ち悪い!』
そう吐き捨てると、満島は荷物を持って走って教室から出て行ってしまった。
▶︎▶︎
「それから俺の身長が伸び出したこともあって、満島くんはもう構ってくれなくなって」
虐めに近しいことを“構う”と表現する山井。
若干引いている咲帆の前で、恍惚とも取れる表情を浮かべて昔を懐かしんでいる。
「この傷が案外深くてずっと消えなくてさ」
また、手の傷をゆるりと撫でた。
「見るたびに満島くんのあの泣きそうな表情を思い出させてくれるんだよな」
(そんなものを思い出すのが、そんなに嬉しいことなのか?)
「それで傷あとっていいなって思ってスカとタトゥーに手を出してはみたものの、いまいちあの時の感動が無くてさ」
山井は残念そうにため息をつく。
「俺が思うに、プロに頼むんじゃなくて満島くんみたいな……傷をつけたいと思ってない人間につけてもらうのが良かったんだよな」
「それで僕に……?」
山井はニヤリと笑う。
(絶対にヘンタイ教師だ……)
咲帆の中にまずいことに足を踏み入れてしまったのではないかと後悔の念が芽生える。
「そういえばお前の彼女、どっかで見たなと思ったんだけど」
「え?」
シャツを羽織りながら山井が急に真香の話題を出したのは意外だった。
「どこで?」
「春休みの……んーいや」
「いやって何ですか?」
「やっぱ勘違いだわ。顔よく見てなかった」
ぼんやりとした歯切れの悪さを感じながらも、咲帆はそれ以上詮索しなかった。
▶︎▶︎
便宜上の生物部に入部して半月が経とうとしている。
入部以来、写真部や委員会との兼ね合いで真香との下校はほとんど実現していない。
一緒に過ごす時間が減ったせいか、真香は登校時間も昼休みも、そして休日も咲帆にベッタリとして機嫌を悪くすることもない。
山井のヘンタイっぷりは若干気持ちが悪いが、リストカットの衝動も起こらず平和に過ごしている。
(こんなにすべてが上手く回るなんて)
そう思っていた咲帆に事件が起きたのは次の日曜午後だった。
咲帆の部屋に真香が勉強をしにやって来た。
そう、勉強をするはずだった。
「ちょ! 落ち着いて、真香」
「どうして?」
「どうしてって、勉強しに来たんだろ?」
今、咲帆は真香に床に押し倒され、真香は咲帆を見下ろしている。
「勉強なんてしなくても、咲帆なら大丈夫でしょ? いつもテストで手抜いてるって知ってるんだから」
真香はベタついた声音で笑う。
「いいじゃない。しよ? 私たちもう何年も付き合ってるんだし。私成人したもん」
真香はキス以上の関係に進もうと、咲帆に迫っていた。
「いや、だってまだ全然そんなつもりなかったから避妊とか全然――」
咲帆は真香とそういう関係になるのは高校を卒業してからのつもりでいた。
というより、これ以上真香のわがままに振り回される要素を増やすようなことをしたくなかった。
ここのところの真香との良好な関係をみれば、進展があってもいいのかもしないが――。
真香はなんとか上体だけを起こした彼の右手を取り、自分の左胸にそっと当てた。
五月の気候に合わせた薄手のワンピースの上から、胸のふくらみの感触がはっきりとわかる。
(キモチワルイ)
真香のあまりの積極的な様子に、咲帆は恐怖すら感じていた。
どこか違和感を覚えるほどの積極性。
「ねえ、しようよ」
「いや、真香、なんかおか――」
「おかしい」と指摘しようとした唇を塞がれる。
「もう黙ろうか」
真香は頬を赤らめて笑った。
拒否できそうにない。
そう思った時だった。
「ただいまー!」
玄関の方から咲帆の姉の声が聞こえた。
(助かった)
彼がそう思うと同時に「チッ」という舌打ちのような音が聞こえた気がした。
「真香?」
「ん?」
体勢を直して服と髪を整えている真香は、いつも通りの小動物っぽい笑顔を見せた。
▶︎▶︎
「お前ってマジでダセーな」
金曜、咲帆はその週の間中浮かない顔だったことを山井に指摘され、日曜の出来事を白状させられた。
「女に迫られたら普通ヤるだろ」
山井という人間は、どこまでも教師らしからぬ反応をする。
“真香が怖くて動けなかった”と、つい正直に言ってしまったことを咲帆は激しく後悔する。
(我ながら情けない)
この一週間、咲帆の頭を埋め尽くしていた言葉だ。
山井以外だったとしても同じ反応が返ってくるだろうとも思う。
「と、言いたいところだけど」
「え?」
「お前の彼女、なんか隠してんじゃねえ? 焦ってるってのかな」
「焦る? 何に?」
「さあ」
そうは言っているが、山井は心当たりのありそうな口ぶりだ。
「そういえば先生、春休みに彼女を見たとか言ってましたよね」
「ああ、言ったっけ」
「どこで?」
山井はまたしても、不敵にニヤリと笑った。
▶︎▶︎
次の日曜日も、真香が咲帆の家で勉強したいと言い出した。
咲帆はそれに同意した。
「今日はさすがにその気でしょ?」
咲帆の予想した通り、真香はまた関係を迫ってきた。
その顔には“今日は咲帆も同意してるよね?”と書いてある。
「ね、いいよね?」
そう言ってキスをしようと近づけられた真香の口を手で塞いで押し退ける。
「え?」
「……真香、浮気しただろ」
咲帆がジッと見つめると、真香の目が小さく泳いだのがわかった。
「な、なんの話? そんなわけ――」
「見たって人がいるんだよ」
――『どこで?』
――『隣町のラブホ街』
山井の言葉はそれだけでもにわかには信じられなかったが、続いた言葉はさらに信じられないものだった。
「相手は常田先生なんだろ?」
――『背が高いバスケ部の顧問と一緒にな。それで目立ってた』
「もしかしてさあ……」
真香は顔面蒼白で黙り込んでいる。
「妊娠……でもしてるのか?」
言いながら、咲帆は胸焼けのような気持ち悪さを感じていた。
真香が何を企んでいたのか、その未来を想像してしまったからだ。
「僕を……父親にしようとした……?」
言っていて、えづきそうなほどの吐き気をもよおす。
「……帰る」
真香は俯いたままボソリとつぶやくと、すっくと立ち上がって荷物を手にして部屋を出ていった。
「おい真香!」
咲帆が止めるのも聞かずに出ていってしまった。
その日、咲帆は食欲もなくよく眠ることもできなかった。
その感情が、真香への怒りなのか悲しみなのか、それとも同情も入っているのか判断がつかない。
ここ最近の真香の態度が浮気を誤魔化すためだったのだとわかって、怒りも湧くが妙に納得している自分もいて、それがまた虚しさを誘った。
当然といえば当然だが、真香からはメッセージも電話もなかった。
▶︎▶︎
翌月曜はさすがに真香を迎えに行くこともなく、昼も一緒には食べなかった。
といっても真香が登校してきたのは午後だった。
放課後になって、真香が咲帆に声をかけてきた。
「咲帆、ちょっと話があるんだけど」
もう二人の関係は終わったものだと思っていた咲帆は驚いたが、ケジメの話をするのだと想像して真香についていくことにした。
ついていった空き教室で、彼は信じられない言葉を耳にする。
「は?」
「だからぁ、中絶するから咲帆が父親ってことにしてほしいの」
彼女の発した「中絶」という言葉の扱いの軽さにも、咲帆を父親にするという有り得ない提案にも、あまりのことに言葉が見つからない。
「あ、もちろんお金とかは大丈夫なんだけど」
(言葉が頭に入ってこない……)
「パパとママに言うにも、相手が先生だなんて言えなくて。だけど咲帆だったら二人も公認だったじゃない?」
言葉がうまく入ってこなくても、咲帆の手は無意識に拳を作り、わなわなと震えていた。
「無理に決まってるだろ」
「お願い! 咲帆しか頼れる人がいないの」
真香は目を潤ませるが、その表情が余計に軽蔑心を煽る。
「常田先生に頼るのが筋だろ」
「……無理よ、先生結婚してるもん。奥さんにバレたらお金取られちゃうかも」
(何泣きそうな声出してんだよ。そういうことをしたんだろ?)
責め立ててやりたいが、弱っている相手を責めるのはなんとなく気が引ける。
「無理だよ。もう関わりたくない」
そう言って咲帆はドアの方へと向かった。
「……何よ。悪いのは咲帆じゃない」
耳を疑うような言葉に、咲帆は思わず振り向いた。
「何年も付き合ってるのに全然手だって出してこないし」
「は?」
「成績だってもっと上が目指せるのに手抜いてパッとしないし」
それが今、何の関係があるというのか咲帆にはさっぱりわからない。
「見た目だってもっとカッコよくできたはずでしょ?」
「もしかして、だから浮気したとか言いたいわけ?」
真香は睨むように咲帆を見た。
「私のことが好きなら、浮気されないように努力しなさいよ!」
その言葉に、咲帆の胸に耐えられないくらいの吐き気が込み上げる。
“お前なんか好きじゃない”
言ってやりたい言葉が出てこない。
なんて情けないんだろうかと、自分を責めてしまう。
何も言わず、走って教室を出るので精一杯だった。
吐き気を堪えて理科室へ向かう。
(卵焼きすら真香本人じゃなくての母親の手作りだって知ってたよ)
(僕の身長が伸びてから、成績が良くなってから、急に二人で登下校するようになったのだって気づいてたよ)
(嫌いだよ、お前なんか)
言ってやりたかった言葉が浮かんでは消えていく。
咲帆は理科室に着くと、実験用のテーブルに備え付けられた流し台に向かって、ゲーゲーと嘔吐してしまった。
真香という存在の汚さと、十年以上の時間、そして自分への嫌悪感が一気に押し寄せてきた。
「おーおー。すげーな」
いつもと変わらない山井が準備室から現れた。
すべて察知しているかのような表情だ。
「今日ならいけんじゃね?」
理科室のドアの鍵を閉め、山井がメスを差し出す。そして上半身を露わにして着席する。
「今の絶望感と、憎しみ? なんの感情があるのか知らねーけど、ひと思いにグサっとやっちゃってくださいよ」
この教師はこんな時でも茶化すのか、と呆れるが、咲帆はメスを手にした。
そして、山井の背中に当てた。
瞬間、真香と常田の顔が浮かぶ。
メスを握った手に力が入る。
「――――っ」
山井が声になっていない微かな声を漏らしたのが聞こえて、咲帆はハッと意識を取り戻した。
「うわぁっ」
素っ頓狂な声を出してしまった彼の目の前には、人の肌から流れる赤い血。
「ついに切れたか」
対照的に、山井は嬉しそうな声を出す。
そして壁にかけられた鏡の前で小さな手鏡を使い、背中を確認した。
生まれてはじめて人を傷つけたことに、咲帆の手は罪悪感と恐怖で震えている。
(どうしよう……どうしよう……)
そんな風に思い悩んでいた。
「ぷっ」
吹き出したのは山井だった。
「たったこれだけ?」
咲帆のつけた傷を見て笑っている。
その傷は一センチ程度しかない。
「もっとデカくても全然大丈夫だぜ? もう一回切るか?」
そう言っている間も、山井はずっと笑っている。
真剣に思い悩んだ自分がバカにされているようで、咲帆は急激に恥ずかしくなり、顔がカァッと耳まで熱くなるのを感じた。
「なあ、もう一回――」
――カラーーーンッ
メスを差し出した山井の手を咲帆が払い除けた弾みで、メスが床に落ちて金属の冷たい音を鳴らす。
咲帆は何も言わずに、また走って部屋を後にした。
真香も常田も、そして山井も、全員が寄ってたかって自分をバカにしているような気がした。
▶︎▶︎
「まさか俺まで敵視されちゃうとはな」
三週間後、咲帆は山井に呼び出されて理科室にいた。
「まあなかなか濃密で楽しかったよ、お前との時間」
山井が学校に来るのは今日が最後だ。
「…………」
あの日、家に帰った咲帆はSNSのアカウント名を変えた。
【晴山高校暴露アカウント】
そして、生徒と不倫している英語教師がいること、生徒が妊娠していること、さらにはスカリフィケーションを趣味にして、生徒に強要している理科教師がいることを書き込んだ。
投稿は瞬く間に炎上し、拡散。
翌日には真香の名前まで特定され、三人は学校の聴取を受けることとなった。
私立高校としてのブランドイメージを守りたい学校側は、三人が学校に残ることを許さなかった。
「邪魔者を全員まとめて排除とはな。なかなかやるじゃん」
「山井先生のことは……正直、巻き込んで申し訳なかったと思ってます」
衝動的な行動を後悔した時にはもう、後の祭りだった。
「おいおい謝んなよ。鉄槌の価値が下がるだろ」
山井は冗談めかして笑う。
「お前のつけた背中の傷」
山井はシャツを脱いだ。この異様な背中を見るのも今日が最後だ。
「もう全然残ってねーの」
「そのほうがいいです。他人に傷を残すなんて人生の汚点です」
咲帆の言葉に山井はまた、不敵に口角を上げる。
「残されたけどな、傷」
「え?」
「こんな風に追い出されるなんて、傷以外の何ものでもないだろ」
山井はケラケラと笑う。
「咲帆くんのことは、きっと一生忘れらんねーわ」
そう言った山井の妖艶さを孕んだような笑顔に、咲帆の背筋がゾクリと慄いた。
「じゃーな」
そう言って、山井は理科室を後にしていった。
――『こんな風に追い出されるなんて、傷以外の何ものでもないだろ』
咲帆の頭に山井の言葉が響く。
追い出した側の咲帆にだって、傷が残っている。
真香、常田、山井、それぞれに付けられた見えない傷が、これから一生自分の背中で疼き続けるのだろう。
咲帆の微かなため息が、空中に溶けていった。
END
放たれた言葉の意味がまったく理解できず、門崎咲帆―― 「さき」が二つ続いてあまり格好良くはない名前だと思っている――は、ただ呆然としたように彼の顔を見てしまった。
(この人は何を言っているんだろう)
一見まともな、大人然とした見た目。
なんとなく頭が良さそうだと思わせる切長の目に細い銀縁の眼鏡をかけた冷静な表情と、身長の高さを感じさせる低めの声。それが目の前にいる人物だ。
それなのに、口にしたのは「切る」という単語。
「何黙ってんの」
不思議そうに声をかけられて咲帆はハッと意識を戻す。
「切る?」
彼は頷いた。
「……先生を?」
「しつけえな」
今度は呆れたようにため息をつかれてしまった。
そう、目の前にいるのは男性教師だ。
その顔を見ながら、どうしてこうなったんだろうと、放課後の咲帆はいつも通りのごくありふれた一日だった今日のことを思い出していた。
つい先ほどまで、完璧に普通の一日だった今日。
◀︎◀︎
四月の木曜である今日。桜はとうに散り、新緑が芽吹き始めている。
朝八時。
咲帆はたいして来たくもない高校に、いつも通り遅刻もせず真面目に登校した。
私立晴山高校三年B組。それが彼のクラス。
「咲帆、おはー!」
「おわ!」
「『おわ!』だって〜!」
自席に黒いリュックを置いた瞬間背後から抱きつかれ、咲帆は驚いた声を上げた。驚かせた張本人の柳楽真香は嬉しそうにケラケラ笑った。
真香は付き合って三年になる咲帆の彼女だ。黒く艶やかなセミロングヘア、くりっとした黒めがちな瞳という可愛らしい見た目をしている。天真爛漫を絵に描いたような明るい女子で、毎日こんな風にイタズラっぽい笑顔を浮かべている。
その笑顔を見ながら、期待されていたであろうリアクションができたんだ、と彼は安堵した。
「咲帆、宿題やってきた?」
「数学? 英語?」
間のやりとりを省いたような察しの良い彼の言葉に、真香はまた「あはは」と笑った。
「両方」
咲帆は小さくため息をついて眉を下げると、リュックから取り出したノートを二冊、真香に差し出した。
「ありがと咲帆! 大好き!」
「わっ」
正面から思いきり抱きしめられた咲帆があげた声に、彼女はまた嬉しそうに無邪気な笑顔を見せた。
「朝から何イチャついてんだよ」
「目の毒ー」
クラスメイトの揶揄う声に、真香は「うるさいなぁ」と頬を膨らめ、ふたたび咲帆を見上げて笑いかけた。
その顔を純粋にかわいいと思いながらも、咲帆の頭に別の気持ちもよぎる。
(はじめから、自力で宿題をやろうなんて気は無かったんだろうな)
そしてごく微かなため息が、つくと同時に空中に溶けていく。
◀︎◀︎
咲帆と真香はいわゆる幼なじみだ。
家が同じ町内にあるから、小学校に上がるより前から近所の子どもたちと一緒に遊ぶ仲だった。
小学校や中学校では同じクラスになることも何度かあり、日直や部活などがなければ、登下校も家までの道を並んで歩くのが当たり前になっていた。
そんな二人が彼氏と彼女になるのは必然といえば必然だったのかもしれない。
『そろそろはっきりさせようよ』
中学三年の五月。
向かい合ったかと思うと、上目遣いでそう口にしたのは真香。
普段通り二人で登校する途中、学校近くのひと気のない路地に差し掛かった時だった。
『はっきり……?』
咲帆の言葉に、彼女は小さく頷いた。
『何を?』
今度は不満そうに眉根を寄せる。
『私たちの関係に決まってるでしょ?』
(関係……決まってる……)
咲帆は頭の中で真香の言葉を反芻した。
ピンとはこなくても、彼女が何を言っているのかは理解できた。
『私たち、周りから見たら付き合ってることになってるよね』
語気と語尾に強さを感じる口調だ。
『え……うーん……そう、なのかな』
見上げた自分から目を逸らすようにやや上を見た咲帆の態度に、真香は唇をツンと尖らせる。
『そうよ。昨日だって結衣たちに聞かれたんだから』
『聞かれたって、何を?』
真香は『もう!』と呆れたような声を出した。
『「マナと咲帆って実際どうなの?」って聞かれたの』
『へえ』
『だから「へえ」じゃないでしょう? はっきりさせてって言ってるの』
先ほどよりも語気を強めた彼女に視線を捉えられてしまった。
『付き合ってるってことでいいんだよね?』
(僕は今、告白されているんだろうか)
これは意思の確認というより“言質を取られている”と言った方が相応しい状況だなと咲帆は思った。
『ね?』
拒否権は無さそうだ、と。
『う、うん。それでいいと思う』
たじたじといった表情の咲帆の言葉に、真香の吊り上がっていた眉が緩やかなアーチを描く。
『じゃあ、今日から彼氏彼女だねっ! 行こ!』
『えっ』
唇を三日月型にしてニコリと満足げな笑みを浮かべたかと思うと、真香は咲帆の左手を取り、グイと引っ張るように路地を出た。
『あ、真香! おはよ』
路地を出たところには二、三、見知った顔があった。
『鈴ちゃん、おはよう』
『……おはよう』
咲帆が戸惑った表情を平常運転に戻そうとしていたところへ、クラスメイトの女子が現れた。
『え!?』
眠そうな目をしていた彼女が驚いた表情と声に変化したのを見て、真香はニヤリと口角を上げた。
クラスメイトの視線は、二人のつながれた手元に注がれていた。真香の指が咲帆の指に絡められている。
『やっぱり二人って』
『んーまあ、今日からね』
真香は『ふふ』と鼻唄でも歌い出しそうな声色で告げた。
『えー! おめでとー!』
鈴の幾分甲高くなった声に、近くにいたクラスメイトや顔見知りの生徒が群がるように『なになに?』と集まってくる。
真香はその一人ひとりに見せつけるかのように繋いだ手を胸元につけた。
そして鈴が『今日からなんだって』とはしゃぐように伝えた。
(遅かれ早かれこうなっていた気はする)
咲帆の頭に浮かんでいた言葉は“まあいいか”であった。
そうしてそのまま高三の今日まで、咲帆と真香は公認カップルを続けている。
▶︎▶︎
授業だって、いつもと変わらず真面目に受けた。
三時間目、英語。
「“If I were a bird, I could fly all over the world.” この文を訳してもらおうかな。わかる人、手上げて」
英語教師の常田が、B組の教室内を見渡す。
常田は二十七歳の若い男性教師だ。バスケ部の顧問を任されているだけあって、スポーツマンらしい爽やかさがある。
明るく人当たりの良い常田は人気ではあるが、その親しみやすさ故生徒に舐められている節もあり、こうした時に手が上がらないことも少なくない。
室内はシンと、水を打ったように静かになる。
「お前たちは、授業中だけは本当におとなしいな。高二の復習だぞ」
常田は苦笑いだ。
(みんな目立ちたくないだけだ)
窓際の席の咲帆は心の中でつぶやくと、グラウンドを横切るように飛んでいったカラスを見つめた。
「じゃあ……門崎。わかるか?」
常田が名簿から咲帆を指名した。
指されてまた彼の微かなため息が、誰にも気づかれずに消えていく。
「“もし私が鳥なら、世界中を飛び回れるのに” です」
仮定法過去を用いた英文の訳。咲帆にとってはごく簡単な問いだ。
「That's right!」
常田が英語で「正解だ」と告げる。
咲帆は常田のこういう陽キャ的な明るさが少し苦手である。
彼の成績は上の下、あるいは中の上といったところだ。テストの成績ではいつも二五〇人ほどの学年の十位から二十位程度を行ったり来たりしている。
週一で塾に通っているし、努力をすれば十位以内をキープすることだって可能ではある。
けれど咲帆はそれをしない。
“目立ちたくないから”
理由はそれだけだ。
良い方にも悪い方にも目立たず、地味にその他大勢に紛れているのが、彼にとっての正解なのだ。
「じゃあ次、“If I had met you before him, we would have become lovers.” 柳楽」
次に指名されたのは真香だった。
「はい、えーっと……」
咲帆が同じ列の二つ席を挟んだ真香の席の方を見ると、彼女も咲帆の方を見た。
(宿題に無かった問題だからわからないのか)
とはいえ、隣の席でもない咲帆には助け船を出すこともできない。
「えっと、わかりません」
真香はあっさりと答えた。
「お前なあ、ちょっとは考えろよ」
常田に言われて、真香はぺろっと小さく舌を出した。
それから咲帆の方をチラッと横目に見たのがわかった。
「この訳は“もし彼より先にあなたに出会っていたら――」
常田が訳を言い終えると、真香はまた一瞬咲帆の方に視線を送ってから着席した。
答えられなかったことが恥ずかしかったのか、その頬は赤くなっているように見えた。
(真香ももう少し自力で勉強すれば、このくらい答えられたんじゃないかな)
慣れた光景に、咲帆はまた退屈な目をして窓の外を見た。
▶︎▶︎
昼休み。
今日は真香の友だちカップル二組と一緒に屋上で昼食をとった。
昼食は真香と二人きりの日もあれば、こうして真香の友人と一緒の日もある。
そのどちらだったとしても決まっていることがある。
「はい。咲帆の分」
「ありがとう」
「いつもすごいよねー、マナのお弁当」
そう言って真香の友人の結衣と広菜が感心してみせたのは、真香が咲帆に渡した弁当だ。
弁当箱こそ黒い飾りけのないものだが、卵焼きにエビフライ、ミニトマトや小さなグラタンなど細々としてカラフルで可愛らしい。
「これ作るのに早起きしなくちゃいけないんじゃない?」
真香の隣に座った結衣が言う。
「まあねー」
真香はどこか得意げだ。
「結衣には絶対無理だよな」
今度は結衣の彼氏が言う。
「私は部活の朝練があるから無理だよ」
彼氏も結衣も購買で買った惣菜パンを手にしている。
「マナがすごすぎるから私がダメ女みたいじゃない」
結衣が冗談めかしながらも不満げに真香を見た。
「だって咲帆のことが好きなんだもん。頑張るでしょ」
真香が「えへ」と笑えば、他の四人が冷やかすように揶揄った。
(頑張る?)
その場の空気に合わせるようにやんわりと照れたような笑顔を作りながら、咲帆は考えていた。
(おかずのほとんどが冷凍食品なのに?)
それでもたしかに、弁当を詰める時間の分だけは早起きをしなければいけないのだからありがたくないわけではない。
それに、ハート型に盛り付けられた卵焼きは手作りだ。
(でも嫌いなんだよな、甘い卵焼き)
付き合い始めてから――というより幼なじみなので以前から――咲帆は何度か真香に、自分の好みは甘くない卵焼きだと言ったことがある。
しかしその度に『私は甘い方が好きなの』と一蹴されてしまい、もうそんな好みを伝えることもなくなった。
彼女は第三者のいる場で弁当を食べる時は、必ずフタを開けた状態で咲帆に手渡す。
二人の時はランチ用の小さなバッグに入れたままだ。
そしてどちらの時でも、フタを開けるとすぐに弁当箱を二つ並べてSNS用の写真を撮る。
真香の作る弁当が誰のためなのか、咲帆にはなんとなく察しがついている。
(真香は多分、自分が褒められたい)
彼から見る真香は、そういう女の子だ。
いつも“見られる”ことを意識している。
「咲帆くん、幸せ者ね。こんなに可愛い彼女に想われて」
広菜が笑いかけてくる。
真香はたしかに可愛い。
幼馴染や彼女であるという贔屓目を差し引いて客観的に見ても万人受けするような、リスやウサギといった小動物のような可愛さがある。
実際、高校に入学してから何度か告白もされているようだ。
「マナはきっといい奥さんになるね」
結衣が真香の頭を撫でながら言った。
その言葉に、咲帆の喉がごくごくわずかに唾を押し込む。
「えーそんなぁ。気が早いよ」
真香は頭をフルフルと子犬のように振って、結衣の手を払う。
そして流れるように咲帆に甘さのある視線を向ける。
「ねぇ?」
咲帆は一瞬泳ぎそうになった目を、内心必死で留めた。
「……はは」
コメントを求められそうになるのを笑って誤魔化すことしかできない彼に、真香の眉がピクリと反応する。
「あー……真香、SNSの写真は?」
「あ! そうだった」
真香の気を逸らすことに成功して、咲帆はホッと胸を撫で下ろした。
「でも咲帆くんも背が高めでかっこいいよね」
せっかく自分から話題が逸れたと思っていたのに、ボールが戻ってきて今度は咲帆が頭の中で眉間を寄せる。
「いや、全ぜ――」
「全然だよ。一七二センチなんていっぱいいるでしょ。それに背が高めってことくらいしか無いもん。咲帆の見た目は」
弁当にスマホのカメラと、そして画面に視線を向けたまま、真香が淡々と答えた。
「ひでー」
広菜の彼氏が咲帆に同情するように言った。
「咲帆は中身がいいの。私にしかわからないんだから」
「たとえばどこよ」
今度は広菜が尋ねる。
「優しいしー、そこそこ頭もいいしー、私の話をきいてくれるしー、それにSNSなんか全然興味ないって感じの流行りに乗らないマイペースなところとか」
「それってなんか……」
広菜は言い淀んだが、咲帆には彼女が何を言おうとしたのか予想がついた。
(“真香にとって都合がいい”だよな)
「最後のっていいところなわけ? それとも嫌味?」
結衣が遠慮なく聞いた。
「いいところだよ。D組の木元くんだっけ? あのメガネの」
「木元がどうかした?」
「なんかぁ、二年の時に裏垢でクラスのこと愚痴ってたらしいよ。それがバレちゃったらしくて」
「えーマジ? 超気まずいじゃん」
「あ、それ俺も聞いた」
友人たち四人が騒つく。
「超根暗だよね。そんなことになるくらいなら、SNSなんて無くていいの」
咲帆以外の五人が笑う。咲帆も口元だけはうっすらと弧を描いている。
(真香は木元のことをよく“根暗でオタク”と揶揄している)
どうやら高校に入学してから告白されたうちの一人らしい。
実際の木元自体がどうなのか、とくに付き合いのない咲帆にはわからない。
(だけど、そんな木元と僕が真香の中では同じカテゴリの人間ってことだ)
真香の中での咲帆と木元の違いが、先ほどの“背が高め”、“優しい”、“ そこそこ頭がいい”、“自分の話を聞く”、“ SNSに全然興味がない”というところなのだ。
そして真香の言う優しさとは、宿題を見せるようなことなわけで、どう考えても都合のいい存在であるとしか考えられないのである。
真香に笑いかけられ、咲帆はまた喉の奥に息苦しさにも似た引っかかりを感じた。
“この先、ずっとこうなのだろうか?”、“真香にずっと付き合っていくのだろうか?”
そんな靄がかかったように霞んだ視界。
“真香のような可愛い女子と付き合うチャンスはもうないかもしれない”という濁った思考。
ここのところ、その二つが咲帆の脳内で天秤を揺らしている。
▶︎▶︎
そして、何事もなく午後の授業を終えて放課後。
悪目立ちすることもなく、真香の機嫌を損ねることもなく終業のチャイムを聞けば、今日も咲帆にとっての完璧な一日が終わる。
「帰ろ」
ぬいぐるみのマスコットをいくつかつけたカバンを肩にかけ、真香が咲帆に声をかける。
「うん」ただそう言って、一緒に帰路につけば良いはずだった。
しかし、今日の咲帆にはそれができなかった。
昼休みの『えーそんなぁ。気が早いよ』という真香のセリフとこちらを見た甘ったるい目が、午後の授業中もずっと頭にこびりついていた。そんな中、ホームルームでは進路調査票が配られ、将来のことをリアルに考えてしまった。
「ご、ごめん。今日委員会のことで先生に呼ばれてて」
「えー! 明日でいいじゃない」
「そういうわけにはいかないよ。悪いけど、真香先に帰っててくれる?」
真香は一瞬不満そうな顔を作ったが、すぐに元に戻って大人しく同意した。
「じゃあ、気をつけて」
咲帆はそう言ってリュックを手に取ると、小走り気味にある場所へ向かった。
(ああ……まずいな、早く……早く)
ガラッと音を立てて、咲帆はとある部屋のドアを焦り気味に開けた。
そして今度はゆっくりとドアを閉め、キョロキョロと部屋の中を見回して誰もいないことを確認すると「ふぅ」と落ち着きを取り戻すように息を吐いた。そして、静かにドアの鍵をかける。
薬品のような匂いを微かに鼻に感じた気がするのは、ここが誰もいない放課後の理科室だからだ。どこか香ばしい匂いも感じる気がしたが、アルコールランプを燃やした後か何かなのだろうと咲帆は思った。
黒い天板の、広い実験用のテーブルの上にリュックを置くと、咲帆はネイビーの合皮でできたスリムなペンケースを取り出した。
そして、ファスナーを開けると、カッターナイフを取り出した。
黄色くて幅が一.五センチほどの細い、どこにでもよく売っているタイプのカッターだ。
そのスライダーをカチカチと鳴らして刃を二センチほど出すと、二の腕までシャツを捲った自分の左腕のヒジのくぼみの近くに当てた。
そして、線を引くように左から右へ引いた。
「何やってんの?」
その声に、咲帆は“心臓が喉から飛び出すかと思った”という状況を初めて体験した。
そして一旦縮み上がった心臓がドクドクと脈打つのを感じながら、声の方を見た。
咲帆の右斜め後ろ、理科室とつながっている理科準備室から、白衣にメガネの若い男性がこちらを見ている。
手には茶色い液体の入ったビーカーを持っている。彼は咲帆に話しかけながら、それを口にした。香ばしい匂いの正体はビーカーに淹れられたコーヒーだった。
「どうした?」
落ち着き払った彼とは対照的に、咲帆は口を小さくパクつかせ、言葉を発せずにいた。
――カランッ
咲帆の手に握られていたカッターが、彼の手から滑り落ちて乾いた音を鳴らした。
「何? もしかしてリスカ?」
自分の足元に転がったそれを拾い上げ、男性が咲帆に話しかける。
捲られた袖とカッターナイフから、咲帆がリストカット――つまり手首や腕を傷つけること――をしようとしたことを察したようだった。
それは、咲帆が息苦しさから逃れたいと願ったときに行う行為だった。
「ふーん」
彼はつかつかと、躊躇なく咲帆の方に歩み寄ってきた。
「腕見せろよ」
教師にしては粗暴さを感じさせる口調だ。
そこでやっと、彼がこの春赴任してきた理科教師の山井賢太郎だということに咲帆の意識が追いついた。
「なんだよこれ」
彼は咲帆の左腕を掴んでまじまじと見ると、不満そうな声を漏らした。
「全然傷になってねえじゃん」
そこにある皮膚には髪の毛ほどの白い線が引かれている。血が出るような傷ではなく、皮膚のほんの表層の部分にうっすら傷がついたような状態。
咲帆のこの行為はいつもこうだ。
「あ、当たり前じゃないですか!」
咲帆は振り払うように腕をバッと上げた。
「何で当たり前なんだよ。リスカしたかったんじゃないのか?」
「…………」
あまりにも淡々と、何でもないことのように聞かれ、咲帆の方が言葉を失ってしまう。
(目の前で生徒が……自殺未遂紛いのことをしたんだぞ? 普通はもっと……)
「何とか言えよ。お前、リスカしようとしたんだよな? あ、わかんねえかリスカって」
「わ、わかります。自分がやろうとしてたことの名称くらい……」
「やっぱそうなんだ」
咲帆は観念して小さく頷いた。
「何で?」
「何でって……何でそんなこと、先生にいわなくちゃいけないんですか」
「バーカ。“先生だから”に決まってんだろ」
とても教師とは思えないような言葉遣いである。
「…………」
「じゃあ今から一緒に職員室行くか。お前のクラスの担任に引き渡すわ」
「え!」
咲帆の声はわかりやすく動揺の色を見せた。その声と彼の顔色を見て、山井はニヤリと企みでもあるかのようにほくそ笑んだ。
「なら話せよ、先生が聞いてやるから」
咲帆は渋々、山井にリストカットの原因である今の自分を取り巻く環境と抱えている気持ちを白状した。
「はーなるほどなぁ。若いなー十代」
静かに話を聞いてくれたかと思っていた山井が最初に放ったのがそんな言葉だったので、咲帆はどこか落胆したような気持ちになった。
「若いとか十代なんてまとめる人に話すんじゃなかった」
まずいところを見られ、事情も聞かれた咲帆は、気にせず悪態をつく。
「あーそうだよな。悪い悪い」
山井は全く悪いと思ってなさそうな軽さで謝罪する。
(こんな人間に秘密を知られるなんて不覚だ)
きっと明日には担任にも話がいって、親との話し合いの場を持たれるか、カウンセラーの紹介なんかをされるのだろうと想像する。
そして見えないため息をつく。
「にしてもダセーな」
山井の口から出たのは咲帆が予想もしない言葉だった。
「そんなんじゃ死なねーじゃん」
「……死ぬ気はないです」
自身の言葉が自分でも情けなくなった。
「その程度じゃストレス解消にもなんねーだろ」
「先生には関係ない」
山井の遠慮のない物言いは、死ぬ気がないどころか痛みを感じる気も、傷跡を残す気も無い弱い自分を突きつけられるようだ。
しかし、続く山井の言葉はさらに意外なものだった。
「なら俺のこと切れよ」
山井は咲帆の目をまっすぐ見て言った。
(この人は何を言っているんだろう)
咲帆はぼーっと、その顔を眺めてしまった。
「何黙ってんの」
そしてハッと意識を戻す。
「切る?」
彼は頷いた。
「……先生を?」
「しつけえな」
今度は呆れたようにため息をつかれてしまう。
今日一日のことを回想してみても、そのあまりにも意外な言葉に納得できる要素はどこにもなかった。
「いや、何で先生を……」
当然の疑問である。
「まあそうだよな」
山井はため息まじりに苦笑いをすると、咲帆に背を向けて白衣を、それからその下のシャツを……と次々と脱いでいった。
「な、何して――」
目の前の教師が急に服を脱ぎ出したことに戸惑った咲帆だったが、露わになった山井の背中を見た瞬間、戸惑いを通り越して言葉を失った。
(なんだこれ……)
山井の広い背中いっぱいに、ナスカの地上絵やどこかの先住民を思わせるような渦や三角形などが使われた幾何学模様のタトゥー、それに、同じような模様のボコっと盛り上がった……まるでミミズのような赤い線が何本も走っている。
(これ、傷……?)
「タトゥーはわかるよな」
「はっはい」
彼の背中の異様な迫力に、咲帆は思わず緊張して背筋を伸ばしてしまった。
「じゃあ、スカリフィケーションは知ってるか?」
咲帆はブンブンと無言で首を振ってから、山井が背中を向けていることを思い出した。
「し、知らないです!」
「何ビビってんだよ」
山井は咲帆の方を振り向いてまた苦笑いを浮かべた。
「簡単に言うと、皮膚に傷をつけて模様を作るんだよ。焼いたりする場合もあるけど、俺は傷の方。タトゥーとスカリフィケーション……まあ平たく言うと“身体改造”ってやつが俺の趣味なわけ」
「へ、へえ」
山井はごく普通の趣味のように言ってのける。
「だからさぁ、自分の身体に刃立てらんないんだったら俺を切れよ。他人の身体でもスカッとすんだろ、きっと」
「な、何で」
「何でが多いな」
山井はまた呆れたように言う。しかし、どう考えても自分の疑問の方が正しいはずだ、と咲帆は思っていた。
「だってそんな、傷なんて」
「言っただろ? 趣味なんだよ。身体に傷つけんのが」
「だからって」
「いいから、まずはやってみろよ。ちょっと待ってろ」
山井は上半身が露わなまま理科準備室に入って行った。
咲帆は逃げることもできず立ち尽くすように、ただその場で山井が戻ってくるのを待っている。
彼はすぐに戻ってきた。
「これ使え。カッターよりよく切れる」
そう言って、山井はペンケースほどの黒い箱を手渡した。
咲帆がパカっとフタを開けると、赤いビロードの真ん中で銀色の細いものが光り輝いている。
「これ……メス……?」
山井が差し出したのは医療用のメスだった。
(この人はこんなものを持ち歩いているのか?)
疑問が浮かんだが、飲み込んでしまった。
咲帆がメスを見つめている間に、山井は背もたれのない理科室の椅子に腰掛けた。
「やれよ。どこでもいいから」
再び咲帆に背中を向けて声をかける。
「い、いや」
「俺がいいって言ってんだから、やれよ」
「いやでも……」
「なら職員室行くか?」
「…………」
咲帆が黙ると、山井は「ふ」っと息を漏らすように笑った。
「お前さあ、そんなんじゃいつまでたっても利用される側だぜ? それでいいのか? 殻を破るチャンスだと思うぞ?」
咲帆のコンプレックスを刺激するような言葉のセットだ。
(殻を破るチャンス……)
咲帆の脳裏に、真香の顔が浮かぶ。
「まずはメスを持って、俺の肌に当ててみるところからだな」
まるで優しくハードルを下げるかのような言葉に、とうとう咲帆はメスを持ち上げた。
それはひんやりとして、彼が想像したよりずっと軽かった。
「そうそう。そしたら背中に当てて、サクッといけばいいんだよ」
背中を向けたままの山井が、見えているかのように言う。派手な背中に似合わない、優しく誘導するような声色に変わっている。
咲帆はゴクリと唾を飲み込むと、小さく一回、深呼吸をした。
そして、右手に持ったメスの先端を山井の背中に向けた。
他人に刃物を向けるという行為が初めてで、どうしたらいいのかがわからない。
まっすぐ向けて行ったが、背中に当たる直前になって刺さるのが怖くて刃を寝かせるようにして、肌にぴたりとくっつけた。
ひんやりとしたメスが当たったからだろう、山井の肌がかすかに動いたように見えた。
その小さな動きに咲帆の背がゾクリと、寒気のようでそれともちがう感じたことのない感覚を覚えた。
(バターナイフみたいだ)
うるさいぐらいに柄の入った背中だが、肌に沿うように寝ている銀色のナイフ状のものを見てそう思った。
「そのまま刃を立ててもいいし、スライドさせてもいい」
山井が唆すように促すが、咲帆の手はその場に貼り付いてしまったかのようにピタリと止まって動かない。
というより動かせなかった。
(本当に切っていいのか?)
異常な状況に、そう簡単に順応できる性格ではない。
(痛いに決まってるよな)
様々な考えがぐるぐると巡る。
(何を考えているかわからない、よく知らない粗暴な教師だ)
山井のことを分析してみる。
(実際にメスを入れたら訴えられるのかもしれない。そうしたら……傷害罪とかになるのか?)
――キーンコーン……
長い沈黙を破るかのように、チャイムが鳴った。
そこで咲帆はハッと我にかえる。
山井の背中にメスを当てたまま三十分以上の時間を過ごしていたことに気づいた。
「す、すみません先生。僕にはやっぱり無理みたいです」
咲帆はメスをケースに戻した。
そんな彼を見て、山井は「はぁ」とため息をついた。
しかし呆れているという雰囲気ではない。
「初日だし、メスを持って背中に当てただけでも上出来だ」
山井はニヤリと笑う。
「え? 初日?」
「明日も来いよ。いや、明日じゃなくてもいいけど。ストレス溜まったら、自分じゃなくて俺に傷つけてよ」
「い、いや、無理です」
山井の笑顔に恐怖を覚える。
「だいたい何で僕が」
「また“何で”。自分じゃ背中に傷つけらんねーからさ」
納得がいくような、いかないような答えである。
「ちなみにスカって俺の秘密なんだわ」
「は、はあ」
「お互いの秘密を知った者同士、仲良くしようぜ」
山井は不敵な笑みを浮かべた。
その顔に、咲帆は言いようのない恐怖を感じた。
「か、帰ります!」
そう言い捨てて、リュックを手に取ると急いで鍵を開けて理科室を後にした。
部屋を出る際、山井がクツクツと愉しそうに笑っているのが目の端に映って、また背筋がゾクリと鳥肌を立てた。
その夜、咲帆はベッドの中でスマホ画面に【スカリフィケーション】と入力した。
WEBの辞書から、目を背けたくなる施術レポートのブログまで、たくさんの肌の写真が目に飛び込んでくる。
山井と同じ民族的な模様もあれば、文字やハートなどのポップな模様を刻んでいる人もいる。
見てはいけないものを見ているかのようで、誰もいない自分の部屋だというのに思わず布団を被ってしまった。
そして、誰にも教えていないSNSのアカウントでも次々と傷の画像を検索しては薄目を開けて見ていく。
(怖いけど……すごい……)
山井と同じ嗜好の人間がいるのだという事実に、新しい世界を知ってしまったような興奮でその夜咲帆はなかなか寝付けなかった。
▶︎▶︎
翌朝。
咲帆は真香と登校している。
この時間も彼を憂鬱な気持ちにする。
学校への道順で言うなら真香の家の方が遠いのに迎えに行くのは咲帆、そして一方的に自分の話ばかりをする真香に付き合うような時間だからだ。当然のように真香のカバンは咲帆が持っている。
けれど、今朝はどこか気分が違った。
というより、自分の周りに広がる世界そのものが違って見える。
昨日、山井と過ごした背徳的とも言える放課後の異様な時間と、スカリフィケーションという新しい世界を知ったせいだ。
そしてそれは、真香の知らない世界でもある。
「なんか今日、咲帆ちょっと変じゃない?」
「え?」
意外な鋭い指摘に心臓がギクリと音を立てる。
「なんか楽しそうっていうか」
「そうかな」
「うん。なんか、らしくないね」
(らしくない?)
楽しそうな自分は、真香の中の咲帆像にマッチしないらしい。そしてどうやらそれはお気に召さないようだ。
「いや全然。いつも通り。あー、でも昨日見た動画がおもしろかったからそのせいかも」
「なーんだ。そんなことで喜んでたんだ」
そしてこれが、真香の中の地味な咲帆像なのだとわかりやすく機嫌を直されてしまう。
▶︎▶︎
放課後。
咲帆は今日も理科室にいる。
そしてなぜか、山井の背中にまたメスを当てている。
今日もメスを持つ手は動かない。
「柳楽だっけ、あれがお前の彼女?」
背中越しに問われる。
「……はい」
つい先ほど、真香と一緒に下校しようとしているところに山井が現れた。
そして『門崎くんに頼みたいことがあるんだ』と言って、ここに連れて来られた。
(誘拐みたいなものだ)
もうここへは来ないつもりだったはずの咲帆は、文句を閉じ込めるように口をギュッと結んだ。
「そんなに好きじゃねーならさっさと別れればいいんじゃないのか?」
(そんなに簡単なことじゃない)
何も知らずに口を挟んでくる山井に腹が立つ。
「幼なじみなんです。生活圏もクラスも一緒で、別れてメリットなんてないですよね」
「まあたしかに、顔は可愛いか」
咲帆の意見にはあまり興味が無いのか、山井は自分の感想だけを述べた。
「でもちょうどよかっただろ? 俺が連れ出して」
「え?」
「お前昨日ここに来た時と同じような死にかけの野良猫みたいな目してたぞ」
(死にかけの野良猫なんて見たことがないけど、まあ確かに生き生きとはしてないだろうな)
今日の真香はどこかピリピリとしていた。
朝の不機嫌さももしかしたらそれと関係があるのかもしれない。
昼ごはんは二人だったが、途中で食べるのをやめて机に突っ伏して寝てしまった。
正直、そんな真香と放課後まで一緒に過ごすのはキツいと思っていた。
(八つ当たりされるのが目に見えてる)
同等であるはずの彼氏彼女、ましてや自分が告白して付き合ってもらったというわけでもない彼女だというのに、八つ当たりに文句を言うことすらできない。
そんな時には真香にも自分にも腹が立つ。
そしてそんな日は、きっと普段なら理科室で昨日と同じことをしていたはずだ。
「で? そろそろいけそう?」
「…………」
昨日あれだけネットで画像を見て慣れたと思っていたが、山井の背中のタトゥーと傷あとの数は群を抜いて多い。一日や二日ではまだ迫力に圧倒されてしまう。
そして、他人を傷つける行為自体もできそうにない。
「無理です」
「まあゆっくりやっていけばいいよな」
「は?」
「嫌か?」
「当たり前じゃないですか。今日で最後です。もう帰ります」
咲帆は語気を強めた。
「お前さあ、生物部入れよ」
また、咲帆の言葉は無視された。
「柳楽と一緒にいる時間、減らしたいんだろ? ならここに来ればいいんだよ」
「なんでそこまでして……」
「結構良くね? お互いの秘密を知ってるってさ」
背中を向けたままの山井の声は軽く弾んでいるように明るい。
「お前が俺の背中にメスを入れられるようになればお互い利害が一致してハッピーだしな」
「教師のセリフとは思えないんですけど」
「教師と生徒じゃなくて、人間同士として喋ってんだよ」
山井は振り向いた。
「人間同士?」
「そ。俺はリスカするやつの人間臭さ、好きだからな」
言われてみれば、山井はリストカットそのものについてはバカにしたようなことも否定するようなことも言ってこなかった。
ますます教師らしくないと思うが、「人間」と言われれば、たしかにそう思える。
「でも僕、やっぱり他人を傷つけるのは無理です」
「いいんだよ、ゆっくりで。メスの冷たさが気持ちいいしな」
(山井先生はヘンタイなんだろうか)
男子生徒にメスを当てられて上機嫌な山井を見ていたら、そんなことを考えてしまった。
▶︎▶︎
二日後の昼休み。
「え? 生物部?」
「うん」
結局咲帆は山井の誘いに乗って生物部に入ることにした。
そして今、誰もいない空き教室で隣り合ってお昼を食べながらそのことを真香に報告している。
「写真部は?」
「掛け持ちすることにした」
「えー! そんなことしたら私と過ごす時間が減っちゃうじゃない! だいたいもう三年ですぐに引退じゃないの」
「大学に行くのに、理系の部活に入っておくと有利なんだ」
もちろんそんなのは大嘘だ。
そもそも山井が顧問を務める生物部は、入部希望者がいなかったせいで活動実態がない。
そして、咲帆が入部したところで、活動は二人が放課後に理科室で行なっている秘密の儀式だけだ。
「なら写真部を――」
「カメラはさ、コンクールで賞も貰ってるから、これも進学に有利だから続けたいんだ」
真香は咲帆の口にする“大学”や“進学”の言葉に弱く、すぐにおとなしく黙ってしまう。
それは咲帆との将来を考えているからだろう。
(僕がいい大学に行くことを期待している)
そして、その先は一流企業に就職してほしいと思っているであろうことが容易に想像できてしまう。
他人頼みの真香の将来設計に、いっそ大学受験でわざと失敗すれば真香のほうから振ってくれるのではないかと考えてしまうこともあるが、そんなことのために自分の人生を棒に振るのもバカらしい。
しかしこれで、真香と一緒に下校する機会が随分と減りそうだ。
「ねえ……」
真香が咲帆を見つめる。
「お休みの日は、会えるよね?」
「う、うん。もちろん」
「さみしい……」
彼女は瞳を潤ませる。
こういう表情を見ると、真香はやはり自分のことが好きなのだと実感させられる。
「ねえ咲帆」
「ん?」
「キスして」
「えっ」
思わず椅子をガタッと引いてしまった。
もう三年も付き合っているのだから、もちろんキスくらいはしている。
それでも昼間の学校で……となると、咲帆には若干ハードルが高い。
「誰もいないよ?」
照れる咲帆に真香はクスッと笑う。
ここで待たせれば、またどんどん真香の機嫌が氷点下に近づいていくのは目に見えている。
誰もいないのはわかりきっているが、咲帆はキョロキョロと周りを確認して真香にキスをした。
「え」
一瞬の口づけで終わるつもりだった咲帆に対して、真香は首に腕を回してせがむようにキスを続けた。
「ねえ咲帆」
吐息を漏らしながら咲帆を見つめる真香は、十七歳の男子高校生が目を逸らすことを許さない。
「私、咲帆のこと大好きだから」
「う、うん。わかってる」
(やっぱり真香って可愛いんだな)
▶︎▶︎
そんなことがあったせいで、翌週月曜日の放課後の咲帆は後悔していた。
(真香と一緒に帰る方が楽しかったんじゃないか?)
山井の背中を眺めながらそう思っていた。
つい先日までの真香は、休みの日は別々に行動したがっていたが、この土日は両日を咲帆とのデートに費やし、その最中ずっと上目遣いで咲帆を眺めてははにかんでいた。
「ふぅ」
思わずため息を漏らして、山井の背中からメスを外した。
「なんだよ、今日はもうギブ?」
(べつに試合でも勝負でもないけどな)
ふと、山井の左手が目に入った。
左手の甲、親指と人差し指の境のあたりに古い傷あとのようなものが見えた。
「それも、スカリフィケーションの一つ?」
「ん? ああ、これ?」
山井は咲帆に見せるように手を肩の近くに一瞬上げ、その後右手で愛おしそうに撫でた。
山井の傷あととタトゥーは、首元を広く残して背中と胸側の胴の部分に限定されている。肩から先には決してはみ出さない。
それは彼が教師だからで、半袖を着ても外からわからないようにしているそうだ。
だから、手に傷あとがあるのはいささか不自然さを感じてしまう。
「先生って、なんで僕に切らせようとするんですか?」
山井の表情から、その傷あとに関係があるような気がした。
山井は咲帆の方に身体を向けた。
「なんだよ。興味湧いちゃったわけ?」
いつものようにどこかふざけたように言われる。
「理由がわからないと、実際切ったら訴えられたりするんじゃないかって気が気じゃないです」
手の傷あとのことが気になっているのが本音だが、これも本心である。山井のようなマトモじゃない人間を、そう簡単には信用できない。
「なんだ、結構鋭いじゃん」
山井は咲帆の考えを見通している様子だ。
「お前が考えてる通り、この傷が原因だよ」
そして山井は、自身の中学時代のことを話し始めた。
◀︎◀︎
十四年前。
山井は中学二年の十四歳。
今のように背が高いわけでもなく、声変わりもしていなかった山井は女の子のような見た目で、一人の男子生徒にパシリ役をさせられていた。
同級生の彼の名は、満島といった。
そして時に彼は、山井に暴力を振るっていた。
『お前、マジでひょろひょろしててムカつく』
理由なんてそんなものだった。
(嫌いだなぁ、満島)
そうは思っていても、反抗すれば殴る蹴るの暴力がエスカレートするだけだ。
ある日の放課後の教室で、満島は山井の指の間にカッターを素早く突き立ていく危険な遊びをしていた。
『怖いだろ?』
そう笑ってみせた満島を、山井は冷めた気持ちで見ていた。
満島が殴ったり蹴ったりはできても、カッターを突き刺したりタバコを押し付けたりはできない小心者だと知っていたから。
つい出来心だった。
山井は満島がカッターを振り下ろす瞬間、スッと少しだけ手をスライドさせた。
『え……』
手から伝わる感触に違和感があったのだろう。満島は不安げな声を漏らした。
視線の先には血を流した山井の手の甲があった。
『え……』
普段は威勢のいい満島が、慌てふためいて声を出せずにいるのを山井は笑いをこらえて見ていた。
『お。俺……』
『ねえ満島くん』
『ご――』
『謝らなくていいよ』
そう言って山井はニコリと微笑んだ。
『その代わり、もっとやってくれないかな。左手がズタズタになってもいいからさ』
『な、何言ってんだよお前……痛くないのか?』
『痛いよ。痛いけど、なんか気持ちがいいんだよね』
山井は心臓が躍るように震えているのを感じていた。興奮しているのが自分でもわかる。
その原因が、手の傷だけでなく満島の泣きそうな表情にもあることもわかっていた。
『ねえ、満島くん。お願いだから』
『な、何言ってんだよ! 気持ち悪い!』
そう吐き捨てると、満島は荷物を持って走って教室から出て行ってしまった。
▶︎▶︎
「それから俺の身長が伸び出したこともあって、満島くんはもう構ってくれなくなって」
虐めに近しいことを“構う”と表現する山井。
若干引いている咲帆の前で、恍惚とも取れる表情を浮かべて昔を懐かしんでいる。
「この傷が案外深くてずっと消えなくてさ」
また、手の傷をゆるりと撫でた。
「見るたびに満島くんのあの泣きそうな表情を思い出させてくれるんだよな」
(そんなものを思い出すのが、そんなに嬉しいことなのか?)
「それで傷あとっていいなって思ってスカとタトゥーに手を出してはみたものの、いまいちあの時の感動が無くてさ」
山井は残念そうにため息をつく。
「俺が思うに、プロに頼むんじゃなくて満島くんみたいな……傷をつけたいと思ってない人間につけてもらうのが良かったんだよな」
「それで僕に……?」
山井はニヤリと笑う。
(絶対にヘンタイ教師だ……)
咲帆の中にまずいことに足を踏み入れてしまったのではないかと後悔の念が芽生える。
「そういえばお前の彼女、どっかで見たなと思ったんだけど」
「え?」
シャツを羽織りながら山井が急に真香の話題を出したのは意外だった。
「どこで?」
「春休みの……んーいや」
「いやって何ですか?」
「やっぱ勘違いだわ。顔よく見てなかった」
ぼんやりとした歯切れの悪さを感じながらも、咲帆はそれ以上詮索しなかった。
▶︎▶︎
便宜上の生物部に入部して半月が経とうとしている。
入部以来、写真部や委員会との兼ね合いで真香との下校はほとんど実現していない。
一緒に過ごす時間が減ったせいか、真香は登校時間も昼休みも、そして休日も咲帆にベッタリとして機嫌を悪くすることもない。
山井のヘンタイっぷりは若干気持ちが悪いが、リストカットの衝動も起こらず平和に過ごしている。
(こんなにすべてが上手く回るなんて)
そう思っていた咲帆に事件が起きたのは次の日曜午後だった。
咲帆の部屋に真香が勉強をしにやって来た。
そう、勉強をするはずだった。
「ちょ! 落ち着いて、真香」
「どうして?」
「どうしてって、勉強しに来たんだろ?」
今、咲帆は真香に床に押し倒され、真香は咲帆を見下ろしている。
「勉強なんてしなくても、咲帆なら大丈夫でしょ? いつもテストで手抜いてるって知ってるんだから」
真香はベタついた声音で笑う。
「いいじゃない。しよ? 私たちもう何年も付き合ってるんだし。私成人したもん」
真香はキス以上の関係に進もうと、咲帆に迫っていた。
「いや、だってまだ全然そんなつもりなかったから避妊とか全然――」
咲帆は真香とそういう関係になるのは高校を卒業してからのつもりでいた。
というより、これ以上真香のわがままに振り回される要素を増やすようなことをしたくなかった。
ここのところの真香との良好な関係をみれば、進展があってもいいのかもしないが――。
真香はなんとか上体だけを起こした彼の右手を取り、自分の左胸にそっと当てた。
五月の気候に合わせた薄手のワンピースの上から、胸のふくらみの感触がはっきりとわかる。
(キモチワルイ)
真香のあまりの積極的な様子に、咲帆は恐怖すら感じていた。
どこか違和感を覚えるほどの積極性。
「ねえ、しようよ」
「いや、真香、なんかおか――」
「おかしい」と指摘しようとした唇を塞がれる。
「もう黙ろうか」
真香は頬を赤らめて笑った。
拒否できそうにない。
そう思った時だった。
「ただいまー!」
玄関の方から咲帆の姉の声が聞こえた。
(助かった)
彼がそう思うと同時に「チッ」という舌打ちのような音が聞こえた気がした。
「真香?」
「ん?」
体勢を直して服と髪を整えている真香は、いつも通りの小動物っぽい笑顔を見せた。
▶︎▶︎
「お前ってマジでダセーな」
金曜、咲帆はその週の間中浮かない顔だったことを山井に指摘され、日曜の出来事を白状させられた。
「女に迫られたら普通ヤるだろ」
山井という人間は、どこまでも教師らしからぬ反応をする。
“真香が怖くて動けなかった”と、つい正直に言ってしまったことを咲帆は激しく後悔する。
(我ながら情けない)
この一週間、咲帆の頭を埋め尽くしていた言葉だ。
山井以外だったとしても同じ反応が返ってくるだろうとも思う。
「と、言いたいところだけど」
「え?」
「お前の彼女、なんか隠してんじゃねえ? 焦ってるってのかな」
「焦る? 何に?」
「さあ」
そうは言っているが、山井は心当たりのありそうな口ぶりだ。
「そういえば先生、春休みに彼女を見たとか言ってましたよね」
「ああ、言ったっけ」
「どこで?」
山井はまたしても、不敵にニヤリと笑った。
▶︎▶︎
次の日曜日も、真香が咲帆の家で勉強したいと言い出した。
咲帆はそれに同意した。
「今日はさすがにその気でしょ?」
咲帆の予想した通り、真香はまた関係を迫ってきた。
その顔には“今日は咲帆も同意してるよね?”と書いてある。
「ね、いいよね?」
そう言ってキスをしようと近づけられた真香の口を手で塞いで押し退ける。
「え?」
「……真香、浮気しただろ」
咲帆がジッと見つめると、真香の目が小さく泳いだのがわかった。
「な、なんの話? そんなわけ――」
「見たって人がいるんだよ」
――『どこで?』
――『隣町のラブホ街』
山井の言葉はそれだけでもにわかには信じられなかったが、続いた言葉はさらに信じられないものだった。
「相手は常田先生なんだろ?」
――『背が高いバスケ部の顧問と一緒にな。それで目立ってた』
「もしかしてさあ……」
真香は顔面蒼白で黙り込んでいる。
「妊娠……でもしてるのか?」
言いながら、咲帆は胸焼けのような気持ち悪さを感じていた。
真香が何を企んでいたのか、その未来を想像してしまったからだ。
「僕を……父親にしようとした……?」
言っていて、えづきそうなほどの吐き気をもよおす。
「……帰る」
真香は俯いたままボソリとつぶやくと、すっくと立ち上がって荷物を手にして部屋を出ていった。
「おい真香!」
咲帆が止めるのも聞かずに出ていってしまった。
その日、咲帆は食欲もなくよく眠ることもできなかった。
その感情が、真香への怒りなのか悲しみなのか、それとも同情も入っているのか判断がつかない。
ここ最近の真香の態度が浮気を誤魔化すためだったのだとわかって、怒りも湧くが妙に納得している自分もいて、それがまた虚しさを誘った。
当然といえば当然だが、真香からはメッセージも電話もなかった。
▶︎▶︎
翌月曜はさすがに真香を迎えに行くこともなく、昼も一緒には食べなかった。
といっても真香が登校してきたのは午後だった。
放課後になって、真香が咲帆に声をかけてきた。
「咲帆、ちょっと話があるんだけど」
もう二人の関係は終わったものだと思っていた咲帆は驚いたが、ケジメの話をするのだと想像して真香についていくことにした。
ついていった空き教室で、彼は信じられない言葉を耳にする。
「は?」
「だからぁ、中絶するから咲帆が父親ってことにしてほしいの」
彼女の発した「中絶」という言葉の扱いの軽さにも、咲帆を父親にするという有り得ない提案にも、あまりのことに言葉が見つからない。
「あ、もちろんお金とかは大丈夫なんだけど」
(言葉が頭に入ってこない……)
「パパとママに言うにも、相手が先生だなんて言えなくて。だけど咲帆だったら二人も公認だったじゃない?」
言葉がうまく入ってこなくても、咲帆の手は無意識に拳を作り、わなわなと震えていた。
「無理に決まってるだろ」
「お願い! 咲帆しか頼れる人がいないの」
真香は目を潤ませるが、その表情が余計に軽蔑心を煽る。
「常田先生に頼るのが筋だろ」
「……無理よ、先生結婚してるもん。奥さんにバレたらお金取られちゃうかも」
(何泣きそうな声出してんだよ。そういうことをしたんだろ?)
責め立ててやりたいが、弱っている相手を責めるのはなんとなく気が引ける。
「無理だよ。もう関わりたくない」
そう言って咲帆はドアの方へと向かった。
「……何よ。悪いのは咲帆じゃない」
耳を疑うような言葉に、咲帆は思わず振り向いた。
「何年も付き合ってるのに全然手だって出してこないし」
「は?」
「成績だってもっと上が目指せるのに手抜いてパッとしないし」
それが今、何の関係があるというのか咲帆にはさっぱりわからない。
「見た目だってもっとカッコよくできたはずでしょ?」
「もしかして、だから浮気したとか言いたいわけ?」
真香は睨むように咲帆を見た。
「私のことが好きなら、浮気されないように努力しなさいよ!」
その言葉に、咲帆の胸に耐えられないくらいの吐き気が込み上げる。
“お前なんか好きじゃない”
言ってやりたい言葉が出てこない。
なんて情けないんだろうかと、自分を責めてしまう。
何も言わず、走って教室を出るので精一杯だった。
吐き気を堪えて理科室へ向かう。
(卵焼きすら真香本人じゃなくての母親の手作りだって知ってたよ)
(僕の身長が伸びてから、成績が良くなってから、急に二人で登下校するようになったのだって気づいてたよ)
(嫌いだよ、お前なんか)
言ってやりたかった言葉が浮かんでは消えていく。
咲帆は理科室に着くと、実験用のテーブルに備え付けられた流し台に向かって、ゲーゲーと嘔吐してしまった。
真香という存在の汚さと、十年以上の時間、そして自分への嫌悪感が一気に押し寄せてきた。
「おーおー。すげーな」
いつもと変わらない山井が準備室から現れた。
すべて察知しているかのような表情だ。
「今日ならいけんじゃね?」
理科室のドアの鍵を閉め、山井がメスを差し出す。そして上半身を露わにして着席する。
「今の絶望感と、憎しみ? なんの感情があるのか知らねーけど、ひと思いにグサっとやっちゃってくださいよ」
この教師はこんな時でも茶化すのか、と呆れるが、咲帆はメスを手にした。
そして、山井の背中に当てた。
瞬間、真香と常田の顔が浮かぶ。
メスを握った手に力が入る。
「――――っ」
山井が声になっていない微かな声を漏らしたのが聞こえて、咲帆はハッと意識を取り戻した。
「うわぁっ」
素っ頓狂な声を出してしまった彼の目の前には、人の肌から流れる赤い血。
「ついに切れたか」
対照的に、山井は嬉しそうな声を出す。
そして壁にかけられた鏡の前で小さな手鏡を使い、背中を確認した。
生まれてはじめて人を傷つけたことに、咲帆の手は罪悪感と恐怖で震えている。
(どうしよう……どうしよう……)
そんな風に思い悩んでいた。
「ぷっ」
吹き出したのは山井だった。
「たったこれだけ?」
咲帆のつけた傷を見て笑っている。
その傷は一センチ程度しかない。
「もっとデカくても全然大丈夫だぜ? もう一回切るか?」
そう言っている間も、山井はずっと笑っている。
真剣に思い悩んだ自分がバカにされているようで、咲帆は急激に恥ずかしくなり、顔がカァッと耳まで熱くなるのを感じた。
「なあ、もう一回――」
――カラーーーンッ
メスを差し出した山井の手を咲帆が払い除けた弾みで、メスが床に落ちて金属の冷たい音を鳴らす。
咲帆は何も言わずに、また走って部屋を後にした。
真香も常田も、そして山井も、全員が寄ってたかって自分をバカにしているような気がした。
▶︎▶︎
「まさか俺まで敵視されちゃうとはな」
三週間後、咲帆は山井に呼び出されて理科室にいた。
「まあなかなか濃密で楽しかったよ、お前との時間」
山井が学校に来るのは今日が最後だ。
「…………」
あの日、家に帰った咲帆はSNSのアカウント名を変えた。
【晴山高校暴露アカウント】
そして、生徒と不倫している英語教師がいること、生徒が妊娠していること、さらにはスカリフィケーションを趣味にして、生徒に強要している理科教師がいることを書き込んだ。
投稿は瞬く間に炎上し、拡散。
翌日には真香の名前まで特定され、三人は学校の聴取を受けることとなった。
私立高校としてのブランドイメージを守りたい学校側は、三人が学校に残ることを許さなかった。
「邪魔者を全員まとめて排除とはな。なかなかやるじゃん」
「山井先生のことは……正直、巻き込んで申し訳なかったと思ってます」
衝動的な行動を後悔した時にはもう、後の祭りだった。
「おいおい謝んなよ。鉄槌の価値が下がるだろ」
山井は冗談めかして笑う。
「お前のつけた背中の傷」
山井はシャツを脱いだ。この異様な背中を見るのも今日が最後だ。
「もう全然残ってねーの」
「そのほうがいいです。他人に傷を残すなんて人生の汚点です」
咲帆の言葉に山井はまた、不敵に口角を上げる。
「残されたけどな、傷」
「え?」
「こんな風に追い出されるなんて、傷以外の何ものでもないだろ」
山井はケラケラと笑う。
「咲帆くんのことは、きっと一生忘れらんねーわ」
そう言った山井の妖艶さを孕んだような笑顔に、咲帆の背筋がゾクリと慄いた。
「じゃーな」
そう言って、山井は理科室を後にしていった。
――『こんな風に追い出されるなんて、傷以外の何ものでもないだろ』
咲帆の頭に山井の言葉が響く。
追い出した側の咲帆にだって、傷が残っている。
真香、常田、山井、それぞれに付けられた見えない傷が、これから一生自分の背中で疼き続けるのだろう。
咲帆の微かなため息が、空中に溶けていった。
END