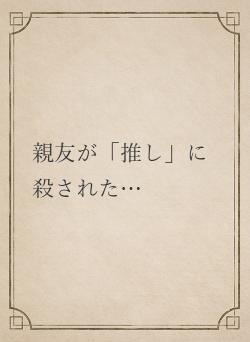「あんた、大丈夫なの?」
心配になって聞いてみた。私は、ただいま涙でぐしょぐしょでございます。
「大丈夫って言ったら、大丈夫っすね」
「は?こんなときにふざけてるの」
「ふざけてないっすよ~」
ヘラヘラ笑い。ムカつく。
「どうして倒れたの。ー私、知ってるけどね。」
「え、それは…」
「ごめんなさい。人には事情があるもんよね。」
「何のことです?」
知らないふりを続けても、無駄だ。どうせ、心の奥底で、私のことを恨んでいるのだろう。
「あの時、『下の名前を教えて』って言っちゃったから。」
「はぁ。さすがっすね。心で考えてること、全部読み取られちゃう」
鈴木は、大きなため息をついた。隠すことを諦めたようだ。
「ー俺、両親が誰だかわからないんです。まぁ、捨てられたんでしょうね。俺、駅前のロッカーで生まれたらしいっす」
笑顔で話すけど、目は全く笑っていない。今でもそのことを引きずっているのか。
「駅前の…ロッカーで」
できるだけ、動揺しているふりをした。「自分も同じようなことがあった」なんて言ったらー
「で、そのあと、施設行き。『名前』がある子がうらやましくて、いつも泣いてました。」
「辛いなら、話さなくていい。」
「ダメです!話したいんです。誰にも言えない自分が大嫌いです、本当に。」
鈴木は、泣いた。大泣きした。
「DNA検査をしたんですけど、結局、よくわからないって言われて。もう、惨めで仕方なくって。」
私も一緒だ。DNA検査をしても、警察に行方を調べてもらっても、正体が出てこなかった。惨めだった。
「中学校を卒業したけど、高校に行く気にもなれなくて。で、たどり着いたのが『ここ』っす。」
私の両親も、鈴木の両親も、クズだ。
普通、子どもというものは、大切で可愛いもんじゃないのか。
「俺、やっぱり、運が悪いっす!」
鈴木は話し終わると、いつものように、ヘラヘラ笑っていた。
「ーで、ずっと気になってたんすけど、この人、誰っすか?」
「え」
突然、視線を向けられた雨歌は、恥ずかしそうに視線を逸らす。
「あ、この子?一流スナイパーの北川雨歌。」
「え~!あの、有名な?え~!」
女子のように騒ぐ鈴木。いつもの光景が戻ってきた。
帰り際、おっさんが話しかけてきた。
「来週から仕事に復帰、だってよ。」
そして、いつものように、「じゃあな、ブルー」と言った。
なんだか、ちょっとだけ気持ち悪かった。
心配になって聞いてみた。私は、ただいま涙でぐしょぐしょでございます。
「大丈夫って言ったら、大丈夫っすね」
「は?こんなときにふざけてるの」
「ふざけてないっすよ~」
ヘラヘラ笑い。ムカつく。
「どうして倒れたの。ー私、知ってるけどね。」
「え、それは…」
「ごめんなさい。人には事情があるもんよね。」
「何のことです?」
知らないふりを続けても、無駄だ。どうせ、心の奥底で、私のことを恨んでいるのだろう。
「あの時、『下の名前を教えて』って言っちゃったから。」
「はぁ。さすがっすね。心で考えてること、全部読み取られちゃう」
鈴木は、大きなため息をついた。隠すことを諦めたようだ。
「ー俺、両親が誰だかわからないんです。まぁ、捨てられたんでしょうね。俺、駅前のロッカーで生まれたらしいっす」
笑顔で話すけど、目は全く笑っていない。今でもそのことを引きずっているのか。
「駅前の…ロッカーで」
できるだけ、動揺しているふりをした。「自分も同じようなことがあった」なんて言ったらー
「で、そのあと、施設行き。『名前』がある子がうらやましくて、いつも泣いてました。」
「辛いなら、話さなくていい。」
「ダメです!話したいんです。誰にも言えない自分が大嫌いです、本当に。」
鈴木は、泣いた。大泣きした。
「DNA検査をしたんですけど、結局、よくわからないって言われて。もう、惨めで仕方なくって。」
私も一緒だ。DNA検査をしても、警察に行方を調べてもらっても、正体が出てこなかった。惨めだった。
「中学校を卒業したけど、高校に行く気にもなれなくて。で、たどり着いたのが『ここ』っす。」
私の両親も、鈴木の両親も、クズだ。
普通、子どもというものは、大切で可愛いもんじゃないのか。
「俺、やっぱり、運が悪いっす!」
鈴木は話し終わると、いつものように、ヘラヘラ笑っていた。
「ーで、ずっと気になってたんすけど、この人、誰っすか?」
「え」
突然、視線を向けられた雨歌は、恥ずかしそうに視線を逸らす。
「あ、この子?一流スナイパーの北川雨歌。」
「え~!あの、有名な?え~!」
女子のように騒ぐ鈴木。いつもの光景が戻ってきた。
帰り際、おっさんが話しかけてきた。
「来週から仕事に復帰、だってよ。」
そして、いつものように、「じゃあな、ブルー」と言った。
なんだか、ちょっとだけ気持ち悪かった。