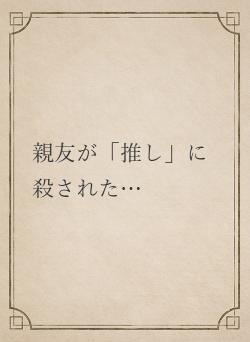本部の密会室に足を踏み入れたのはもう、何回目だろう。
「おっさん、この人って誰?」
耳打ちをしておっさんに聞いた。目の前にいる、この女性は誰なのか。
「ー鈴木の、母親だ。」
「…っ!」
鈴木の母親が、見つかったということか。
「鈴木は来ないの」
「もうじき来るだろう。」
おっさんがそう言った後、本当に鈴木が来たから、笑ってしまった。
でも、今は笑ってはいけない空気ということに気づき、すぐに口を閉じた。
「あなたが私の息子ね」
「あぁ。そうだ」
「なんて呼べばいいの」
「名前が無いから、いつもは『鈴木』って呼ばれてるよ。ロッカーに紙切れが入ってて、そこに『鈴木』って書いてあったからな」
「あなたの名前、教えてあげるわ。あなた、優輝っていうのよ。」
優輝。良い名前だ。鈴木は喜んでくれただろうか。
「俺は、あんたのことを『母親』だと思っていない。血の繋がった他人だと思っている。」
「悲しいわ」
「俺はあんたが喜んだって悲しんだって一切興味がない!」
「あら、一緒ね。私、あなたを捨てたのよ。いらないと思ったから。」
自分の子供のことを「いらない」と言った。只者ではない。精神を病んでいる。
「じゃあ、なんで産んだ。」
「病院に行くのが面倒くさいからよ。家で産んだ後、駅前のロッカーに捨てたの」
私はこの話を聞いてもいいのだろうか。どんな表情で聞けばいいのか。
「それくらい、俺のことが嫌いなんだ」
鈴木がそう言った後、鈴木の母親は去っていった。
居心地が悪そうだったので、私は安心した。
鈴木は、そのまま「帰ります」と行って、帰ってしまった。
沈黙が流れる。
「おっさん、あの女、殺さない?」
先に口を開いたのは私だった。
「あぁ。お願いな。一人で行けるか?」
「当たり前でしょ」
私は、あの女を殺すことにした。鈴木を苦しめた、あの女を。
「おっさん、この人って誰?」
耳打ちをしておっさんに聞いた。目の前にいる、この女性は誰なのか。
「ー鈴木の、母親だ。」
「…っ!」
鈴木の母親が、見つかったということか。
「鈴木は来ないの」
「もうじき来るだろう。」
おっさんがそう言った後、本当に鈴木が来たから、笑ってしまった。
でも、今は笑ってはいけない空気ということに気づき、すぐに口を閉じた。
「あなたが私の息子ね」
「あぁ。そうだ」
「なんて呼べばいいの」
「名前が無いから、いつもは『鈴木』って呼ばれてるよ。ロッカーに紙切れが入ってて、そこに『鈴木』って書いてあったからな」
「あなたの名前、教えてあげるわ。あなた、優輝っていうのよ。」
優輝。良い名前だ。鈴木は喜んでくれただろうか。
「俺は、あんたのことを『母親』だと思っていない。血の繋がった他人だと思っている。」
「悲しいわ」
「俺はあんたが喜んだって悲しんだって一切興味がない!」
「あら、一緒ね。私、あなたを捨てたのよ。いらないと思ったから。」
自分の子供のことを「いらない」と言った。只者ではない。精神を病んでいる。
「じゃあ、なんで産んだ。」
「病院に行くのが面倒くさいからよ。家で産んだ後、駅前のロッカーに捨てたの」
私はこの話を聞いてもいいのだろうか。どんな表情で聞けばいいのか。
「それくらい、俺のことが嫌いなんだ」
鈴木がそう言った後、鈴木の母親は去っていった。
居心地が悪そうだったので、私は安心した。
鈴木は、そのまま「帰ります」と行って、帰ってしまった。
沈黙が流れる。
「おっさん、あの女、殺さない?」
先に口を開いたのは私だった。
「あぁ。お願いな。一人で行けるか?」
「当たり前でしょ」
私は、あの女を殺すことにした。鈴木を苦しめた、あの女を。